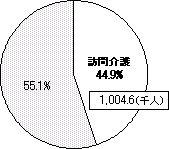
利用者数(2,235.6千人)
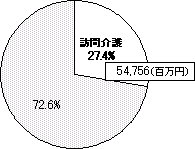
費用額(199,962百万円)
| I.在宅サービス |
|
| ◇ | 居宅サービス全体からみた「訪問介護」の利用者率と費用額のシェア率 |
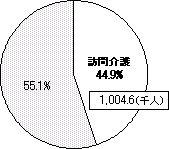 利用者数(2,235.6千人) |
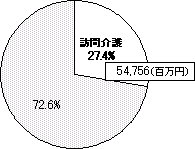 費用額(199,962百万円) | ||
| (平成15年9月サービス提供分) | |||
| ◇ | 「訪問介護」及び「居宅サービス」の利用者と費用額の伸び。(指数) |
利用者数
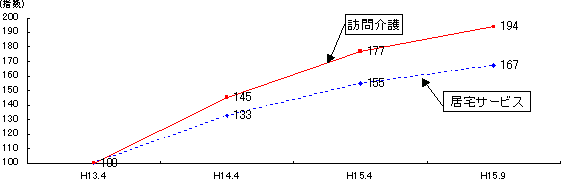
費用額
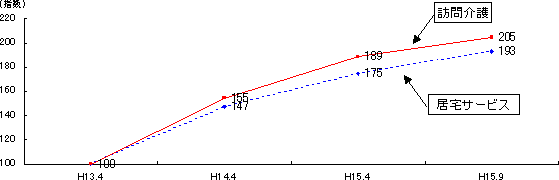
| ◇ | 要介護状態区分別にみた居宅サービス利用者総数に対するサービス別割合(利用者数)と1人あたり費用額 |
(平成15年9月サービス提供分)
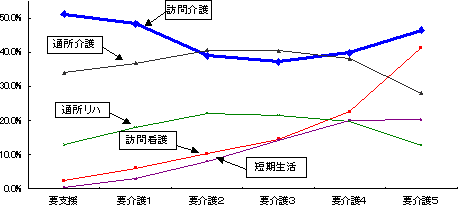 |
| ・ | 「訪問介護」1人あたり費用額 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (単位:円) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◇ | 請求事業所数の状況 |
|
| ・ | 法人種類別の請求事業所数の状況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
出典:介護給付費実態調査
訪問入浴介護
| ◇ | 居宅サービス全体からみた「訪問入浴介護」の利用者率と費用額のシェア率 |
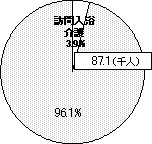 利用者数(2,235.6千人) |
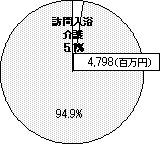 費用額(199,962百万円) | ||
| (平成15年9月サービス提供分) | |||
| ◇ | 「訪問入浴介護」及び「居宅サービス」の利用者と費用額の伸び。(指数) |
利用者数
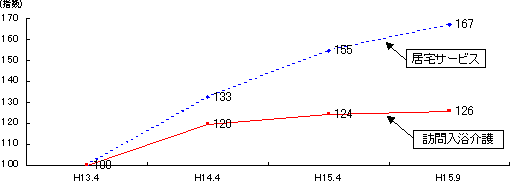
費用額
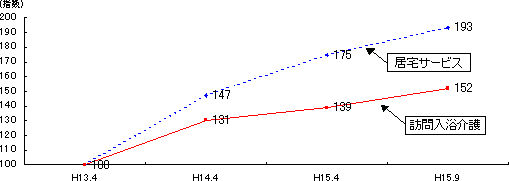
| ◇ | 要介護状態区分別にみた居宅サービス利用者総数に対するサービス別割合(利用者数)と1人あたり費用額 |
(平成15年9月サービス提供分)
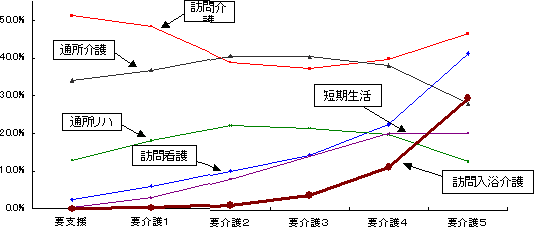 |
| ・ | 「訪問入浴介護」1人あたり費用額 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (単位:円) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◇ | 請求事業所数の状況 |
|
| ・ | 法人種類別の請求事業所数の状況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
出典:介護給付費実態調査
|
| (1) | 訪問介護利用者のうち訪問介護のみを利用している者の割合 |
(介護給付費実態調査10月審査分より) |
| (2) | 訪問介護における請求回数の内訳 |
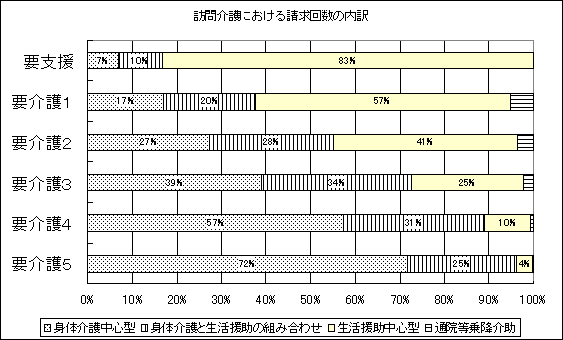 (介護給付費実態調査 H15.9審査分) |
(介護給付費実態調査 H15.10審査分) |
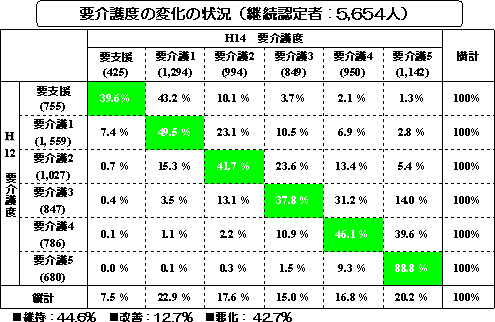 介護サービスの有効性評価に関する調査研究(日本医師会総合政策研究機構・島根県健康福祉部高齢者福祉課) |
|
1.生活援助の滞在時間と内容
| (1) | 訪問1回当たりの平均滞在時間 |
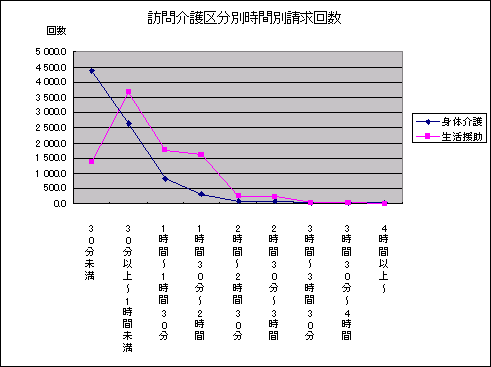
| ※ | 介護給付費実態調査(H15.10審査分)での介護報酬請求上の時間で分類し、集計 |
| ※ | そのうち「身体+生活」での請求は、集計上、その中で請求される「身体介護」の時間と「生活援助」の時間を分離し、それぞれの時間で分類した上で「身体介護中心型」、「生活援助中心型」に加える形とした(そのため、「30分未満の生活援助」が計上されている。)。 |
| (2) | 訪問介護(家事援助)の行為実施割合 |
介護サービス施設・事業所調査(H13.10) |
2.「生活援助」を巡る意見等
| 当部会で出された意見等 |
| ・ | 生活援助は掃除にしても調理にしても、利用者は何もしていない。調理は、生活援助でなく配食サービスで対応できるのではないか。そして空いた時間を身体介護の方に使うべきであり、そのようなことで悪化を防止していくべきではないか。 |
| 「民間事業者の質を高める研究会」(※)要望(平成15年12月) |
| ・ | ヘルパーの調理の廃止と「配食サービス」及び「通所介護施設等での会食サービス」の宅配部分の給付化 |
| ・ | ヘルパーが利用者宅で行う掃除回数の制限(例えば、月2回など) |
| (※)訪問介護、訪問入浴事業を営む民間企業による研究会(会員数419社) |
|
| (※) | 第7回部会資料においてお示ししたものの一部を抜粋し、掲載。 |
| 「在宅高齢者の介護サービス利用状況の変化に関する調査研究」(医療経済研究機構・平成12年度〜14年度) |
| ○ | 入院・入所に至った者の在宅復帰を可能とするために必要な条件として、担当ケアマネジャーは、家族・介護者の協力やサービスの増加・充実、サービス提供のあり方としては、24時間対応・医療的ケア等を挙げている。 | ||||
| ○ | また、在宅での介護を継続できた事例との比較分析を通じ、在宅生活維持の条件として、以下の点を指摘している。
|
| 「在宅要介護高齢者の介護状況実態調査報告」(長寿社会開発センター・平成15年3月) |
| ○ | 訪問介護の利用者及びホームヘルパーに対して、在宅生活継続のための課題について調査したところ、必要なサービスを必要なときに受けられる体制、医療ニーズへの対応、家族の負担の軽減といった事項が挙げられた。
| |||||||||||||||
2.夜間・深夜加算の状況
訪問介護の報酬においては、夜間早朝(夜間:18時〜20時、早朝:6時〜8時)、深夜(20時〜6時)にサービスを提供した場合、それぞれ25%、50%の加算が設けられているが、その請求実績は、以下のとおりとなっている。
| (1) | 「身体介護中心型」の回数全体のうち、加算を請求した回数の割合
|
| (2) | 請求事業所(身体介護)のうち、加算を請求した実績のある事業所の割合
|
1.本事業の目的
2.背景
3.事業内容
|
スウェーデンにおける「夜間専門ヘルパーステーション」
| ○ | スウェーデン ランズクローナ市
| ||||||||||
| ○ | ステーションの体制
|
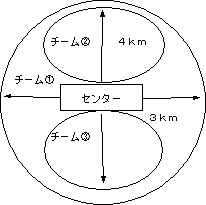
|
| (1) | 訪問介護員の養成研修終了者数(年度別・累計)と実働者数 |
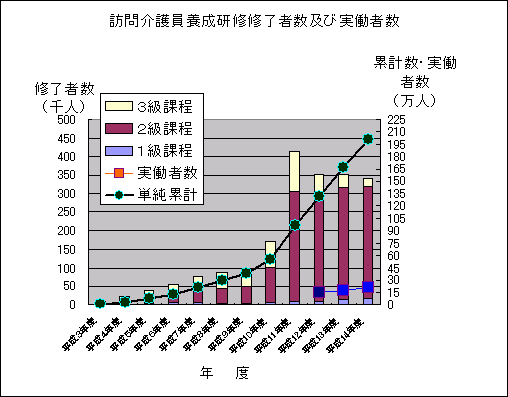
| ※ | 訪問介護員の養成研修終了者数(年度別・累計)は、厚生労働省老健課調べ。なお、各養成課程欄の数値は、1人の者について、年度をおって養成課程昇進(レベルアップ)を行っている場合には重複して計上される。 |
| ※ | 訪問介護員の実働者数は、介護サービス事業所・施設調査による。 |
| (2) | 訪問介護員の養成課程 |
| 課程・総時間数 | 形態 | 目的 |
| 1級 計:230H |
講義:84H 演習:62H 実習:84H |
2級課程において修得した知識及び技術を深めるとともに、主任訪問介護員が行う業務に関する知識及び技能を修得すること。 |
| 2級 計:130H |
講義:58H 演習:42H 実習:30H |
訪問介護員が行う業務に関する知識及び技術を修得すること。 |
| 3級 計:50H |
講義:25H 演習:17H 実習:8H |
訪問介護員が行う業務に関する基礎的な知識及び技術を修得すること。 |
| ※1 | 1級は、2級課程を修了した者を対象とする。 | |
| ※2 | 指定基準上、事業所には、サービス提供責任者として1級課程の研修終了者(経過措置として、2級で3年の実務経験を有する者を含む。)の配置が義務付けられている。また、3級ヘルパーのサービス提供については、報酬上90%算定となっている。 |
(参考)介護福祉士の養成課程
| 総時間数 | 修業年限 | 形態 | 目的 |
| 計:1650H | 2年以上 | 講義:630H 演習:480H 実習:540H |
介護福祉士として必要な知識及び技能の修得 |
| ※ | 上記は、高校卒業者等が介護福祉士となるための課程であり、その他に大学等において厚生労働大臣の指定する科目を修めて卒業した者等を入学要件とする1年以上の課程もある。 |
| ※ | 現在、介護福祉士については、その質の向上に関する検討を行っている。 |
2.従業者数(勤務形態別)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
(平成14年度介護サービス施設・事業所調査) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||