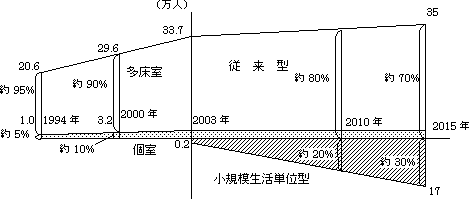
|
| ○ | 本年4月の指定基準省令等の改正により、ユニットケアを行う施設を「小規模生活単位型」として、その運営基準、構造設備基準を設定。 また、これに合わせて「小規模生活単位型」の介護報酬を設定。
| ||||
| ○ | 新設する特別養護老人ホームは、「小規模生活単位型」が基本。
|
|
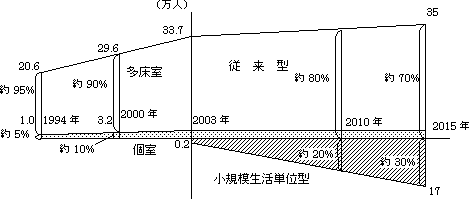
| (注1) | 小規模生活単位型については、平成15年度(2003年度)における新規着工分(約14300人分)が今後2014年度まで継続すると仮定。 |
| (注2) | 従来型については、平成15年度(2003年度)における新規着工分(約800人分)が今後2014年度まで継続すると仮定。 |
| * | 『介護保険施設における個室化とユニットケアに関する研究報告書』(平成13年3月・医療経済研究機構) 『普及期における介護保険施設の個室化とユニットケアに関する研究報告書』(平成14年3月・同) |
| 建て替え前(6床室主体) | → | 建て替え後(ユニット部分) |
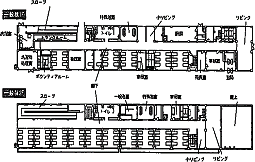 | 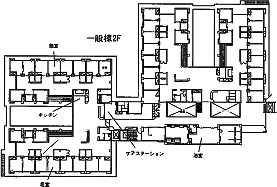 |
| (1) | 居場所の変化
|
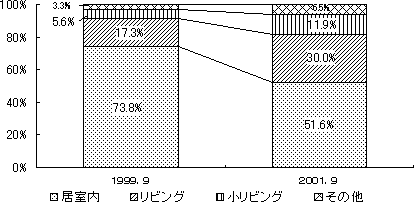 *午前7時から午後7時までの状況を調査。 |
| (2) | 行為の変化
|
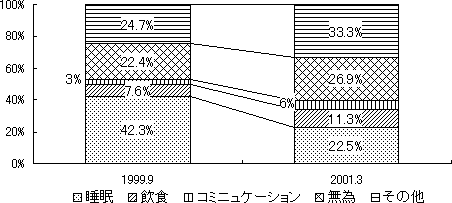 *午前7時から午後7時までの状況を調査。 |
| (3) | 食事場所の変化 ベッド上での食事が約4割→約1割に減少。また、食堂での食事が約4割を占めていたところ、約9割がリビング・サブリビングで食事をとるようになり、生活にメリハリができた。 |
| 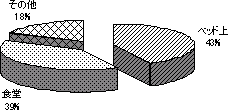 |
|
| 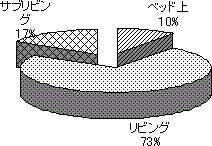 |
| (4) | 残飯の変化 一人当たり残飯量が92g→43gに減少し、食事摂取量が増加。 |
| (5) | 排せつの変化 ポータブルトイレの設置数が29台→14台に減少し、排せつが改善。 |
| ○ | 建て替え前後の面会者数を比較すると、建て替え後は増加。 |
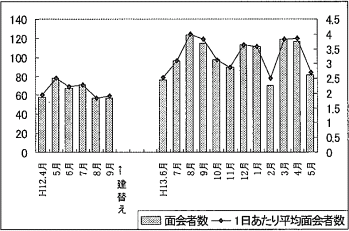
| (1) | 居場所の変化
|
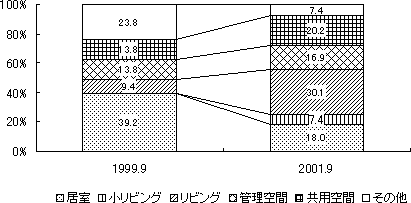 *午前7時から午後7時までの状況を調査。 |
| (2) | 行為内容の変化
|
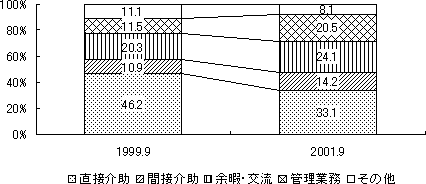 *午前7時から午後7時までの状況を調査。 |
| (3) | 運動量の変化
|
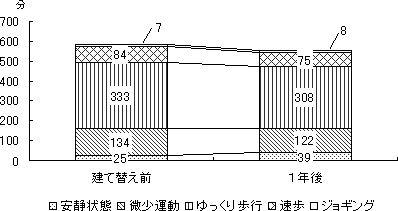 *各職員の勤務時間帯における状況を調査。 |
○従来型
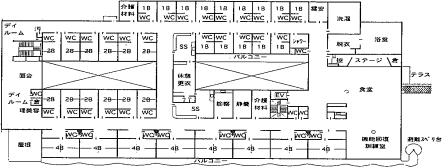
| ・ | 入所定員 | 70名 |
| ・ | 1人当たり延床面積 | 54.67m2 |
| ・ | 東京都(都市部)において従来型特別養護老人ホームを建設する場合、社会福祉法人に対する定員1人当たりの補助金額は650万円。 | |
○小規模生活単位型
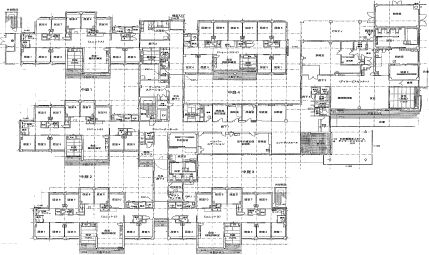
| ・ | 入居定員 | 100名 |
| ・ | 1人当たり延床面積 | 54.95m2 |
| ・ | 東京都(都市部)において小規模生活単位型特別養護老人ホームを建設する場合、社会福祉法人に対する定員1人当たりの補助金額は450万円。 | |
|
| ○ | 小規模生活単位型の特別養護老人ホームでは、在宅に近い居住環境の下で、在宅での暮らしに近い日常生活を通じたケアが行われる。 → 在宅との均衡という観点から、入居者は居住費を自己負担。 |
| ○ | 居住費の額は、個室と共同生活室に係る建築費用、光熱水費等に相当する額。 施設によって異なるが、一定の仮定を置いて試算すれば、1月当たり4〜5万円程度。(低所得者対策あり) |
| ○ | ユニットケアは、在宅に近い居住環境で、入居者一人一人の個性や生活のリズムに沿い、また、他人との人間関係を築きながら日常生活を営めるように介護を行う手法である。その実現のためには、個性や生活のリズムを保つための個室と、他の入居者との人間関係を築くための共同生活室というハードウエアが必要であり、同時に、小グループごとに配置されたスタッフによる一人一人の個性や生活のリズムに沿ったケアの提供(生活単位と介護単位の一致)というソフトウエアが必要となる。 ユニットケアとは、ソフトウエアとハードウエアが相俟って効果を発揮するものであり、そのどちらが欠けても効果的なケアを行うことは難しい。 |
| ○ | 国は、特別養護老人ホームについてはユニットケア型の施設整備を原則としている。 現時点では、既存の特別養護老人ホームのほとんどは従来型のハードウエアであるが、これらの施設においても、ハード面での制約がある中で、ソフト面でのさまざまな工夫によってこれを補い、個別ケアを実現しようとする努力が数多く行われている。このような動きについても積極的な支援が行われるべきである。 |