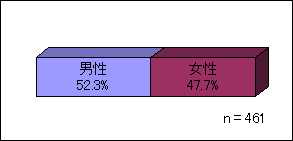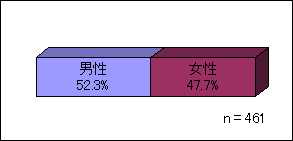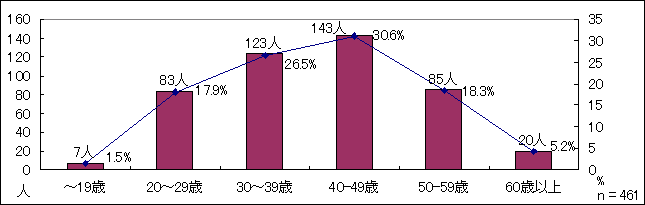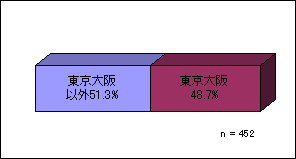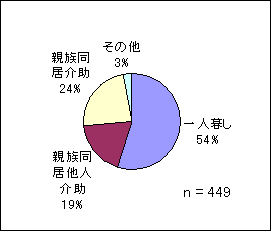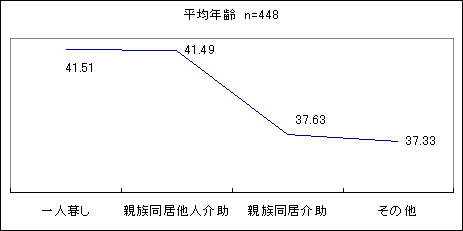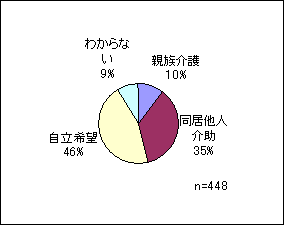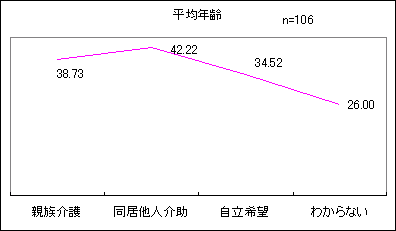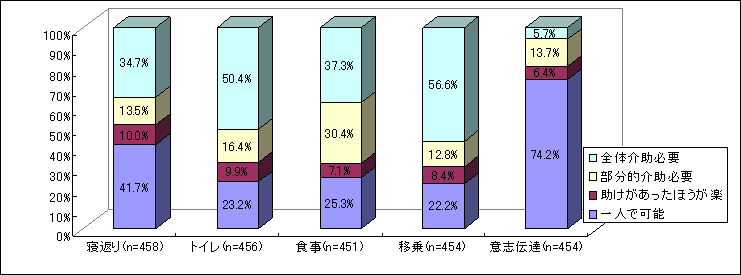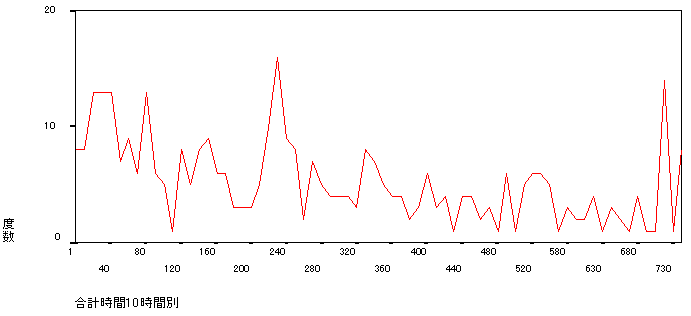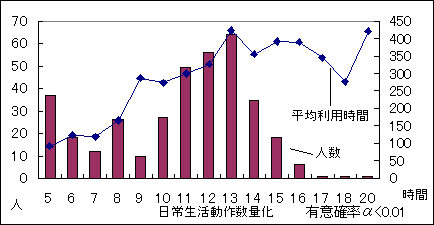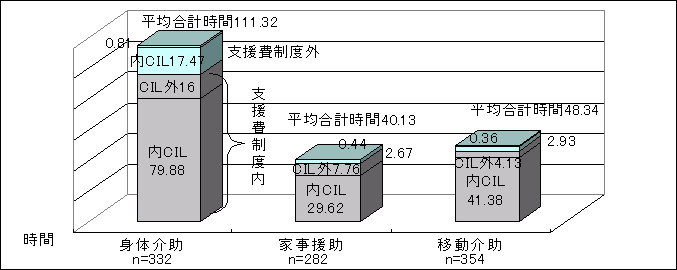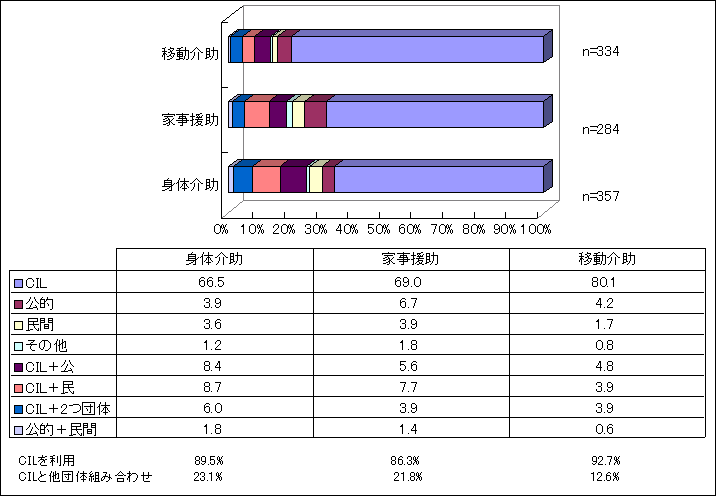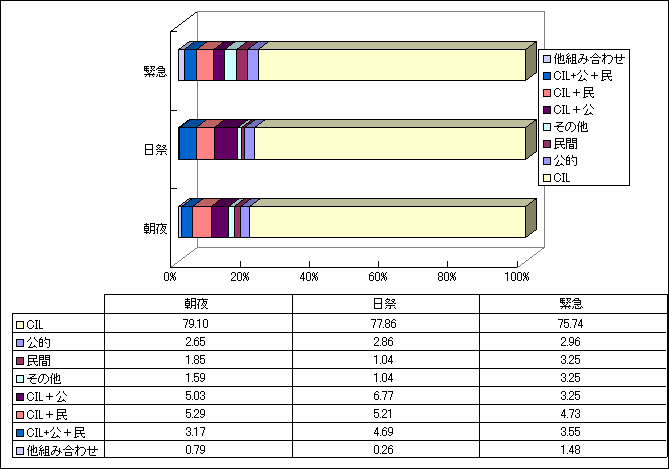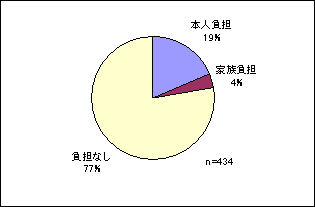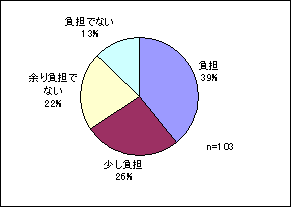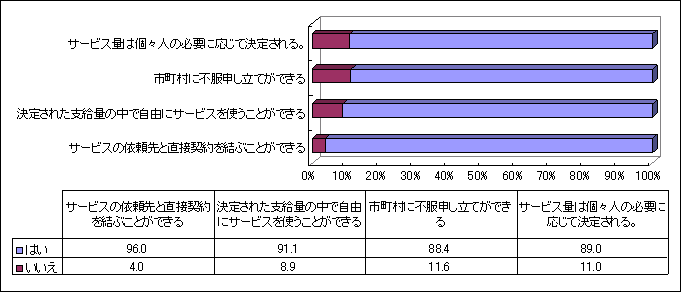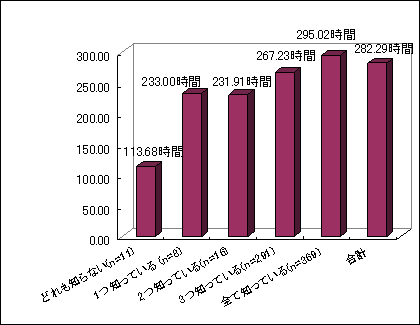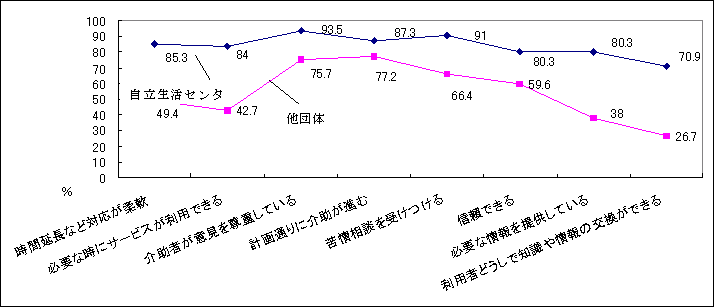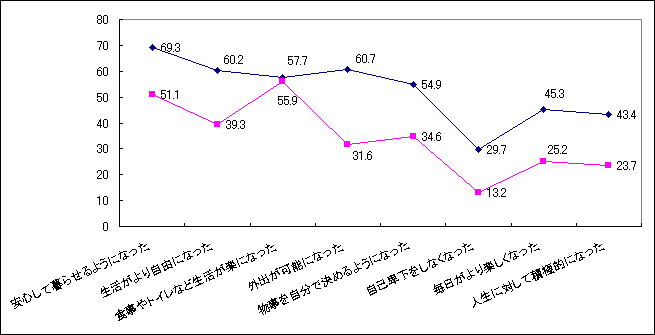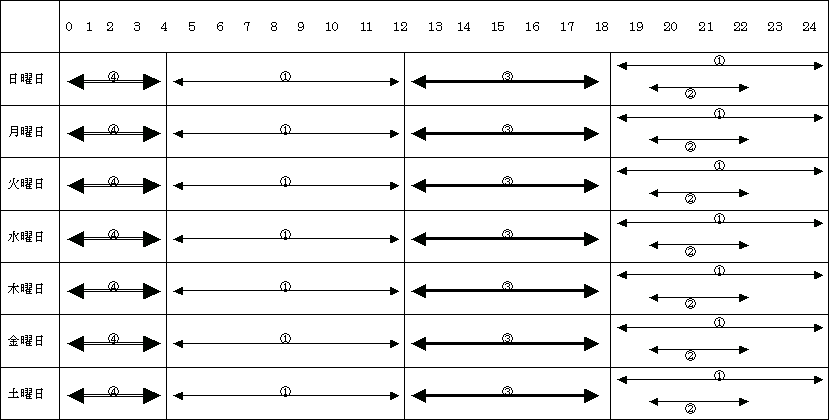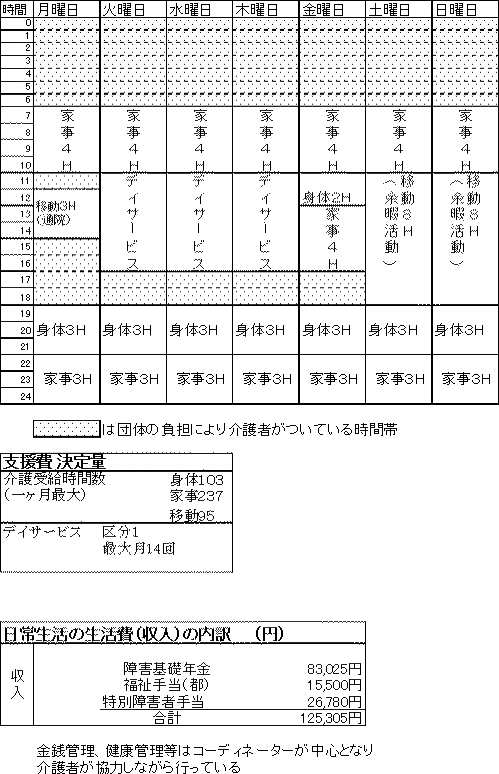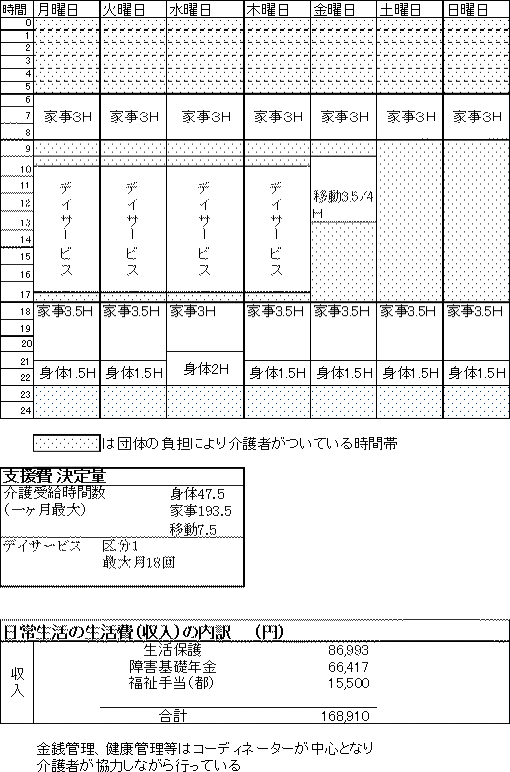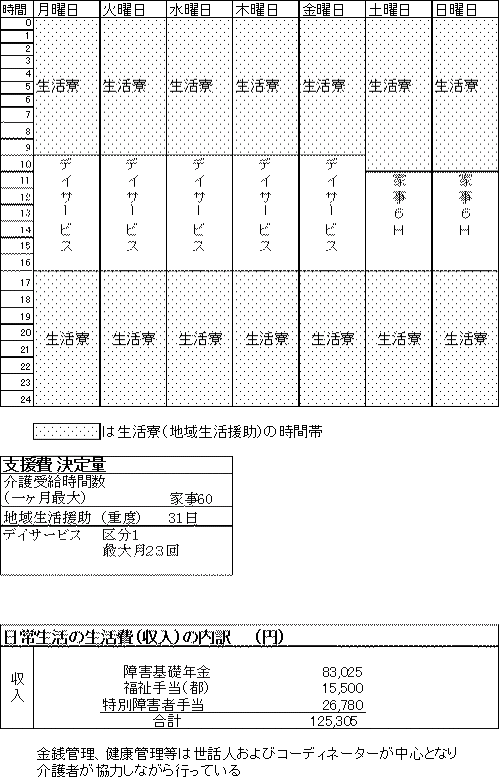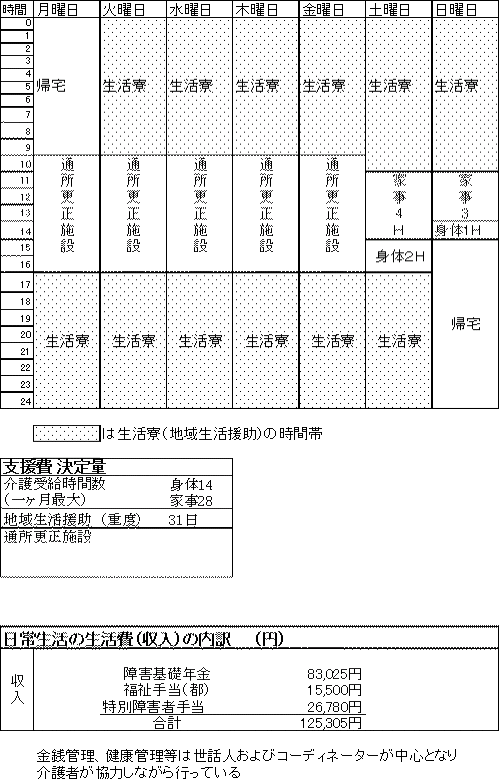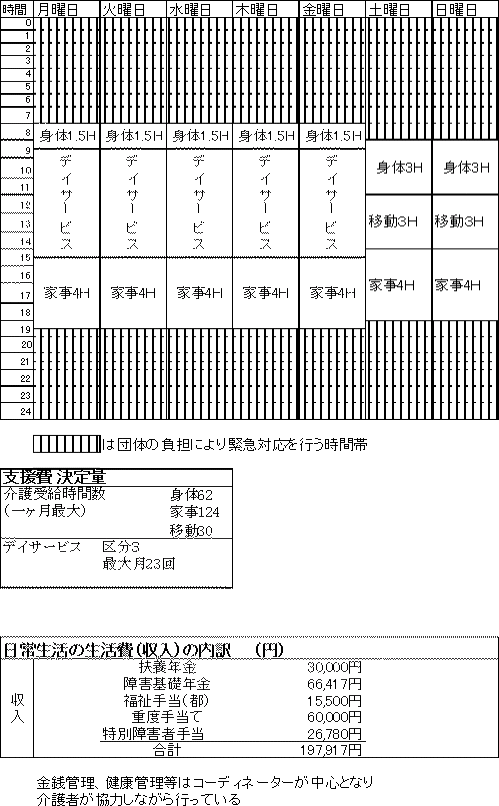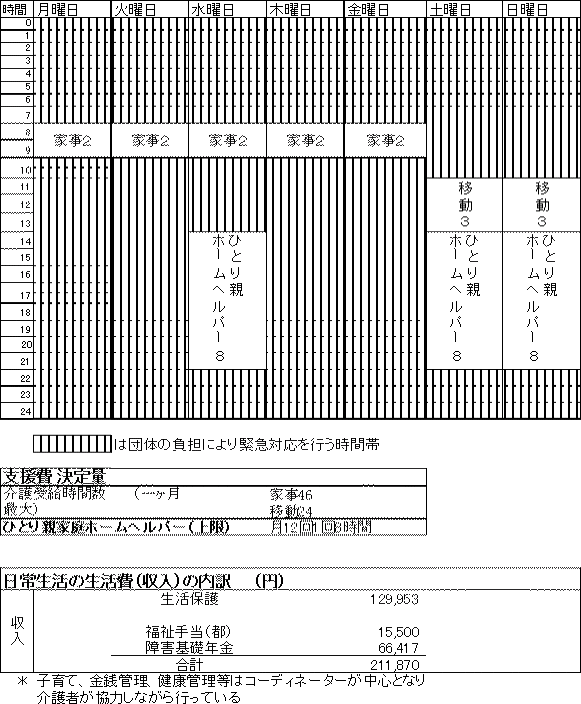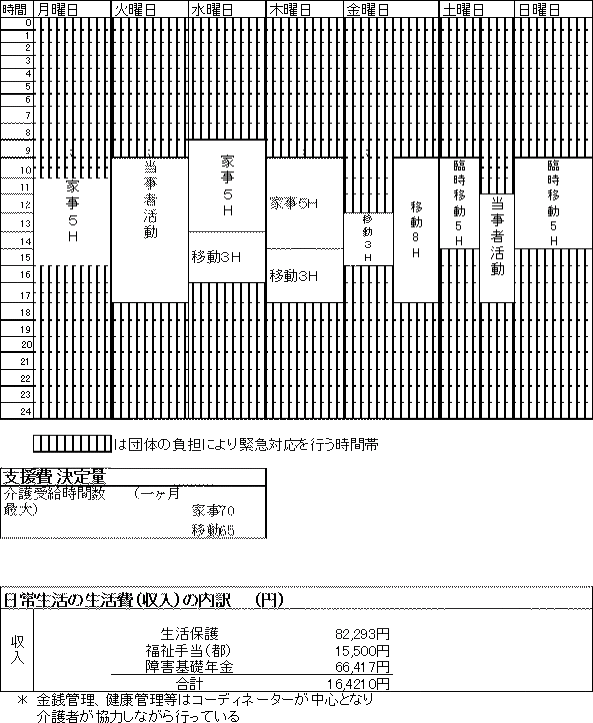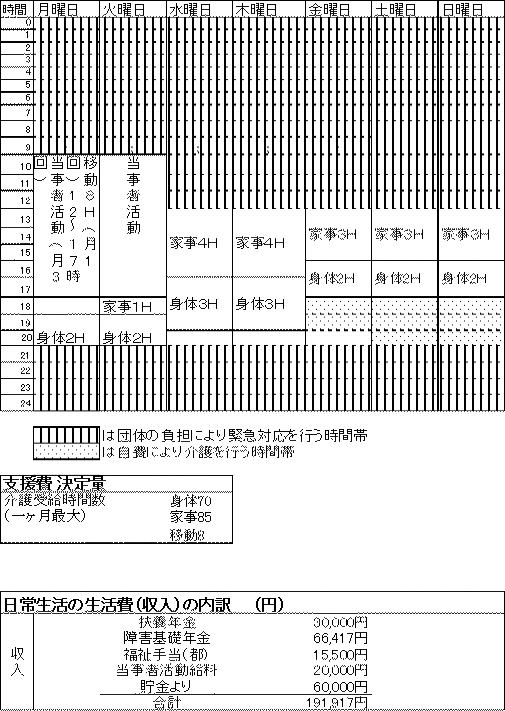戻る
『高齢者エンパワメント調査・研究事業』
アンケート調査報告書(抜粋)
調査概要
| -1 |
対象者
全身性の障害を持つ自立生活センターの利用者(上肢と下肢の両方に障害をもつ障害者1級、またはこれに相当する障害を持つ人)
|
| -2 |
対象地域と回収目標
東京および大阪で活動する自立生活センター利用者 250名
以上の地域以外で活動する自立生活センター利用者 250名
|
| -3 |
調査期間
配布:2003年5月中旬
回収:6月中旬
|
| -4 |
回収方法 郵送法
|
| -5 |
回収率 調査対象者 747人 有効回収率 62.1% 有効回収票 464票
|
【性別】
男性、女性の割合は半々
回答者の男女比は、男性51.7%、女性48.3%で、ほぼ半分づつ。 |
図1 性別
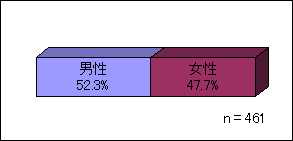 |
【年齢】
平均年齢は約40.58歳、30代、40代が最も多い。最高年齢78歳までと幅広い層の利用者がいる。
女性の平均年齢の方が高い(女性41.81才、男性39.45才)
図2 年齢
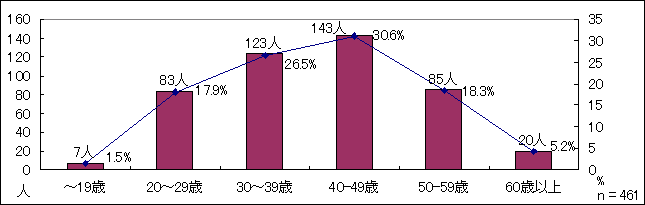
【居住地】
東京、大阪とそれ以外の地域の割合は半数づつ。
東京、大阪に居住の回答者が48.3%、それ以外の地域に居住の回答者は51.7%とほぼ同比。 |
図3 居住地
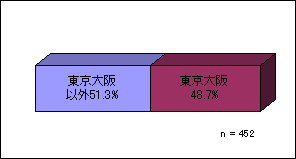 |
【居住形態】
一人暮しをしている人が、半数を上回る。18.5%の人が親族と暮らしながら、他人介助を受けている。年齢が高くなるにつれて、一人暮しの人の割合も増える。
54.5%が一人暮し、23.7%が介助者である親族と同居し、18.5%が親族と暮らしながら主に他人介助を利用している。介助を同居している親族から受けている人の平均年齢が他と比べて低い(資料(1))。
図4 居住形態
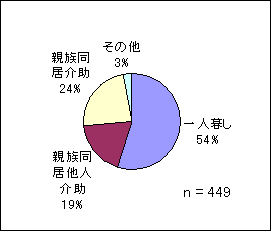 |
図5 居住形態と年齢
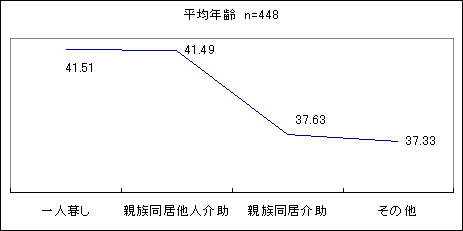 |
【一人暮しへの希望】
同居する親族から介助を受けている人のうち、45%が一人暮しを希望、35%が親族と同居を継続するも、他人介助を望んでいる。
同居する親族から介助を受けている人のうち、「十分な介助サービスを受けることができるなら」という条件のもと、45%が一人暮しを希望。35%が他人介助を中心に利用しながらの親族との同居継続を希望している。年齢をみると、一人暮しを希望する人の平均年齢が低いことから、一人暮しを希望する人は、現在親と同居している割合が高いようだ。一方、他人介助を中心に利用しながら親族との同居継続(「親族同居他人介助」)を選択している人は、配偶者との同居の割合が高いことが予想される。
図6 今後の希望
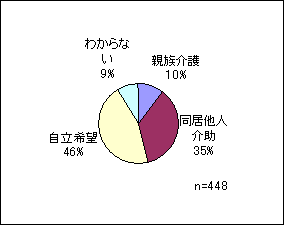 |
図7 今後の希望と年齢
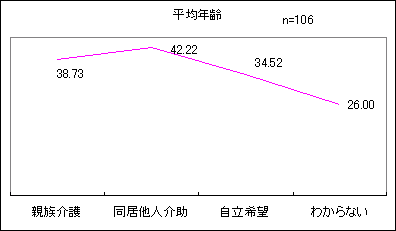 |
【日常生活動作の状況】
意志伝達を除き、平均して約7割の人が、寝返り、トイレ(小便)、食事、移乗に介助が必要。
全身性障害の人を対象としたこ
とから、日常生活動作に平均して7割の人が何らかの介助を必要としている。項目別では、移乗に77.8%、トイレ(小便)の介助に76.8%、食事の介助に64.9%、寝返りに58.6%、意志伝達では25.8%の人が介助を必要としている。
日常生活動作に介助が必要な程度と、年齢、性別、居住地に有意な関連はない。
図8 日常生活動作と介助
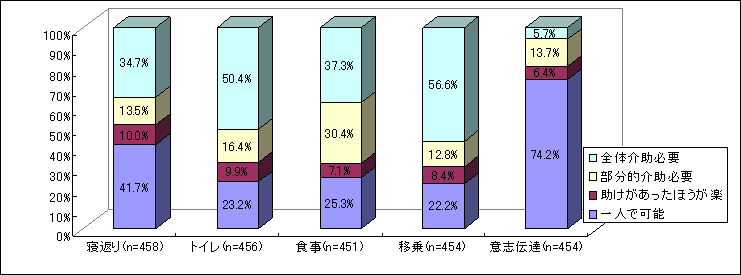
表1 日常生活動作と介助
|
一人で可能 |
助けがあったほうが楽 |
部分的介助必要 |
全体介助必要 |
合計 |
| 度数 |
% |
度数 |
% |
度数 |
% |
度数 |
% |
|
| 寝返り(n=458) |
191 |
42.1% |
46 |
10.1% |
62 |
13.7% |
159 |
35.0% |
454 |
| トイレ(n=456) |
106 |
23.5% |
45 |
10.0% |
75 |
16.6% |
230 |
50.9% |
452 |
| 食事(n=451) |
114 |
25.5% |
32 |
7.2% |
137 |
30.6% |
168 |
37.6% |
447 |
| 移乗(n=454) |
101 |
22.4% |
38 |
8.4% |
58 |
12.9% |
257 |
57.1% |
450 |
| 意志伝達(n=454) |
337 |
74.9% |
29 |
6.4% |
62 |
13.8% |
26 |
5.8% |
450 |
【一人暮し歴】
一人暮しの平均年数は、7.5年。一人暮しを始めてから1年目以内の割合が最も多い。
一方で4人に一人は、10年以上一人暮しをしている。
一人暮らしの平均年数7.5年。一人暮しを始めてから2ヶ月の人から、30年の人まで年数には幅がある。
51.6%が一人暮しをはじめて、5年以内となっている。
【利用時間】
介助サービスの利用合計時間の平均は284時間、中央値は240時間。
最も多いのは720時間(1日24時間×30日)と230時間〜240時間(1日約8時間×30日)の利用者。平均利用時間と、日常生活動作、居住形態、性別、居住地が有意な関連を持つ。日常生活動作では、全体介助の必要な人ほど平均利用時間は長くなる。(図11)居住形態では、一人暮しの人(表2)の平均利用時間が長い。居住地では、東京大阪に居住する人は、それ以外の居住地より60時間ほど平均利用時間が長い(表3)。
図9 利用時間
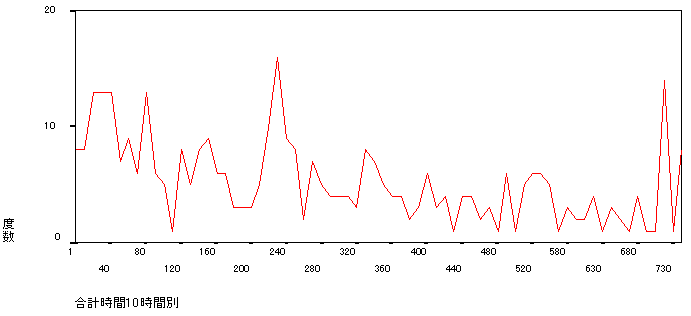
図10 平均利用時間と日常生活動作
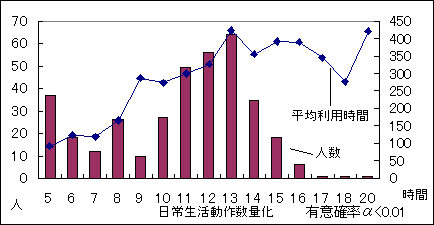 |
【平均利用時間と日常生活動作】
日常生活動作の数量化とは、各動作における介助の必要度を、点数で表したもの(自分一人でできる=1、助けがあった方が楽=2、部分的に介助が必要=3、全体介助が必要=4)。点数が高いほど、介助の必要度が高く、障害も重い。
平均利用時間は、障害の重いほど増えている。 |
【平均利用時間と居住形態】
居住形態をみると、一人暮しをしている人の平均利用時間が圧倒的に多い。親族と同居し親族から介助を受けている人は、一人暮しの人の1/3になっている。 |
表2 平均利用時間と居住形態
|
度数 |
平均時間 |
| 一人暮し |
199 |
341.98時間 |
| 親族同居他人介助 |
78 |
288.88時間 |
| 親族同居介助 |
78 |
112.43時間 |
| その他 |
10 |
351.80時間 |
有意確立α<0.01 |
【平均利用時間と居住地】
東京大阪に居住する人は、それ以外に居住する人より、60時間程度多く利用している。
(東京大阪=平均318.8時間、東京大阪以外=平均253時間) |
表3 平均利用時間と居住地
|
度数 |
平均時間 |
| 東京大阪 |
176 |
318.84時間 |
| 東京大阪以外 |
191 |
253.34時間 |
有意確率α<0.05 |
【内容別利用時間】
利用時間の内訳では、身体介助の平均時間が、111.32時間で最も多い。移動介助では、9割りの時間が自立生活センターの利用になる。全体の利用時間の中で、自立生活センターが、それぞれの利用時間の8割以上を提供しており、自立生活センター抜きでは生活が成り立たない利用が多いことがうかがえる。
身体介助では、最大652時間、平均111.32時間、全体の82.2%の時間は、自立生活センターの介助サービスを利用している。家事援助では、最大485時間、平均40.13時間、全体の80.5%が自立生活センター。移動時間では、最大334時間、平均48.34時間、全体の89.7%の時間が自立生活センターによる。
図11 内容別利用時間
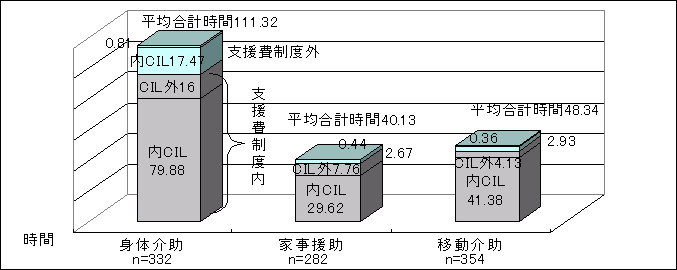
【サービス依頼先】
身体介助で66.5%、家事援助で69%、移動介助で80.1%の人が自立生活センターからのみサービスを利用している。また身体介助、家事援助では2割以上の人が、公的団体、民間団体と自立生活センターを組み合わせてサービスを受けている。
自立生活センターのみからサービスを利用しているのは、移動介助で最も多く80%。
身体介助は公的団体、民間営利団体と併用している人の割合が高い。自立生活センターと公的団体が8.4%、自立生活センターと民間営利団体が、8.7%、自立生活センターと公的、民間団体6%となっている。
家事援助では、公的団体のサービスのみを利用している人の割合が比較的高く、6.4%の人が公的団体のみからサービスを受けている。
※ここでの「公的団体」、「民間団体」とは以下の定義とした。
公的団体=市町村、社会福祉協議会、社会福祉法人
民間団体=営利法人、医療法人・病院
図12 介助内容別サービス依頼先
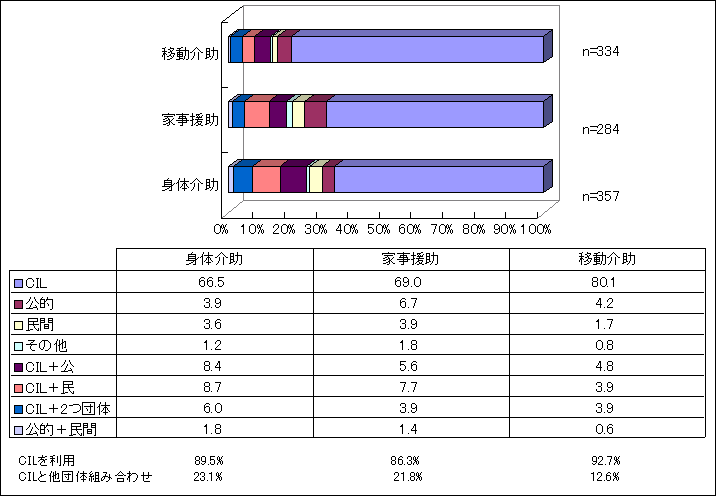
【利用日・時間帯別サービス依頼先】
早朝深夜79%、日曜祭日77%、緊急時75%の人が自立生活センターにサービスを依頼。
日曜祭日は、自立生活センターと公的サービスを併用している人の割合が増える。また緊急時には、ボランティアや個人介助者と思われる「その他」の割合が増えている。
図13 利用日・時間帯別サービス依頼先
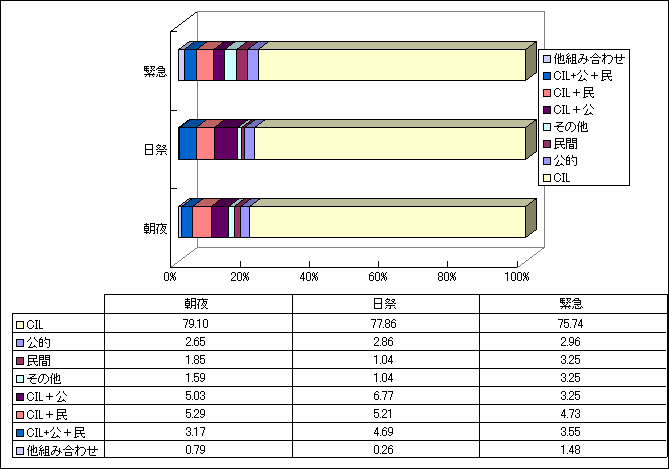
【利用料金負担】
3/4の人が、利用料金を負担していない。利用料金を負担している場合、78%が本人、家族が14.7%。
全体では、負担なし76.4%。本人が負担18.5%、家族が負担3.5% |
図14 利用料金負担
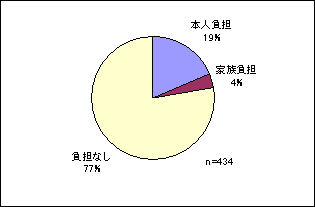 |
【利用料の負担感】
利用料金を負担に感じている人は、66.3%。
利用料金を負担している人の6割以上が負担を感じている。負担に感じる39.6%、少し負担に感じる26.7%、あまり負担に感じない21.8%、負担ではない11.9% |
図15 利用料の負担感
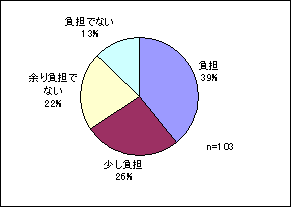 |
【支援費制度の認知度】
77%の人が支援費制度の主な特徴を全て把握している。全く知らない人は、2.4%のみ。
合計利用時間の多い人ほど、支援費制度について把握しており、居住形態では、親族と同居し親族から介助を受けている人の認知度が低い。
支援費制度の主な特徴である―「サービスの依頼先と直接契約を結ぶことができる」「決定された支給量の中で自由にサービスを使う事ができる」「市町村に不服申し立てができる」「サービス量は個々人の必要に応じて決定される」― 4つの点に関して、77%の人が全てを把握している。「市町村に不服申立てができる」が最も低い認知度であったが、それでも88%の人が知っている。
図16 支援費制度の認知度(項目別)
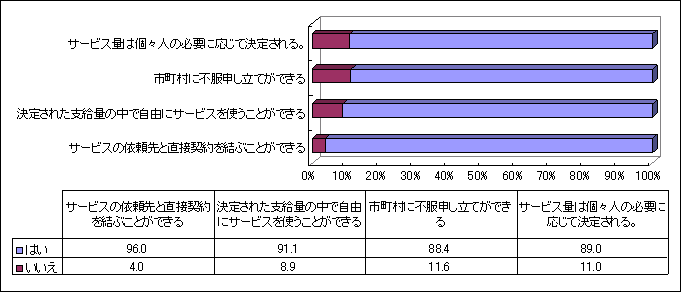
図17 支援費制度認知項目数別、平均利用時間
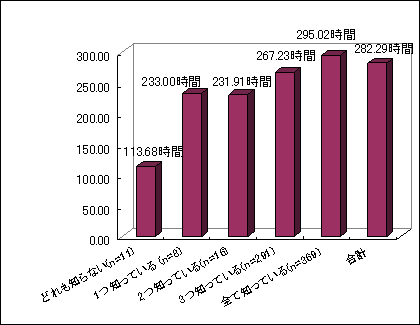 |
表4 居住形態別、支援費制度認知日平均項目数
|
度数 |
支援費制度認知
平均項目数 |
| 一人暮し |
243 |
3.7 |
| 親族同居他人介助 |
83 |
3.7 |
| 親族同居介助 |
105 |
3.4 |
| その他 |
13 |
3.0 |
| 合計 |
444 |
3.6 |
有意確率α<0.001 |
【自立生活センターへの評価】
自立生活センターへの評価は高い。それぞれの項目では、平均して84%の人が満足している。42%の人が全ての点において満足。最も評価が高いのは、「介助者があなたの意見を尊重している」「苦情や相談を受けつける」点にあり、一方他の項目と比較すると「利用者同士で知識や情報の交換ができる」のみが70%と相対的にみて、評価が低い。
【自立生活センター以外の団体への評価】
自立生活センターへの評価に比べ、自立生活センター以外の団体への評価は低い。それぞれの項目に対して、平均して54.5%の人が満足している。全てにおいて満足している人は、8.2%のみ。最も評価されているのは、「計画どおりに介助が進む」点であり、最も低い評価は「利用者同士で知識や情報の交換ができる」点にみられる。
比較すると、全での項目において自立生活センターの方が評価が高い。特に、自立生活センターは、サービス提供だけでなく、利用者同士のつながりや情報提供の点において評価が高い。「利用者同士で知識や情報の交換ができる」(自立生活センター80.3%、その他団体38%)および「必要な情報を提供している」(自立生活センター70.9%、その他団体26.7%)、「必要な時にサービスが利用できる」(自立生活センター84%、その他団体42.7%)点において、自立生活センターは特に高く評価されている。
図18 サービス提供団体への評価
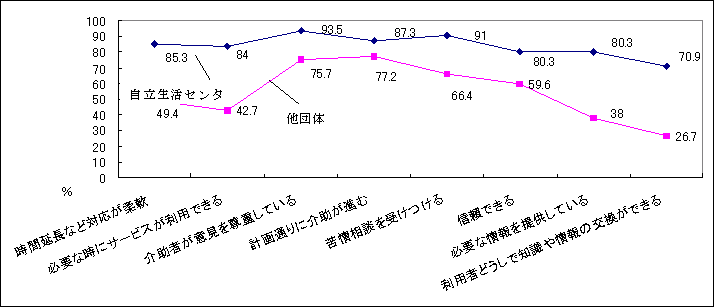
| 評価項目 |
自立生活
センター |
他団体 |
自立生活センター ―他団体評価 |
評価項目 |
自立生活
センター |
他団体 |
自立生活センター ―他団体評価 |
| 時間延長など対応が柔軟 |
85.3% |
49.4% |
35.9% |
苦情相談を受けつける |
91% |
66.4% |
24.6% |
| 必要な時にサービスが利用できる |
84% |
42.7% |
41.3% |
信頼できる |
80.3% |
59.6% |
20.7% |
| 介助者が意見を尊重している |
93.5% |
75.7% |
17.8% |
必要な情報を提供している |
80.3% |
38% |
42.3% |
| 計画通りに介助が進む |
87.3% |
77.2% |
10.1% |
利用者どうしで知識や情報の交換ができる |
70.9% |
26.7% |
44.2% |
【自立生活センターのサービス利用と生活の変化】
自立生活センターのサービスを利用することで、もっとも変化したと評価されているのは、「安心して暮らせるようになった」(69.3%)点である。自立生活センターの利用によって、生活の「安心」と「自由」が得られていることがうかがえる。次に、「外出が可能になった」(60.7%)「生活がより自由になった」(60.2%)の選択が高い割合を示している。また、日常生活動作の程度が重い人ほど、自立生活センターを利用して良かったとする項目が多い。一方、一人暮しの年数が多い人ほど、よかったとする項目の数が減る。
【自立生活センター以外の団体のサービス利用と生活】
自立生活センター以外の団体では、「食事やトイレなど生活が楽になった」(55.9%)「安心して暮らせるようになった」(51.1%)の選択の割合が高い。
比較すると、利用者は、自立生活センターを利用することで、他団体も提供している生活の利便性や安心だけでなく、外出を可能にするなど、生活の自由を得ていることが明らかになった。これは、サービス提供先団体の内訳(8頁、図13)で示したように、移動介助では自立生活センターからのみサービスを利用している人が圧倒的に多いこととも関連している。また、自立生活センターは、利用者の生活を支えるだけでなく、日々の生活により積極的な価値をも見出す助けになっていることがわかる。このことは、「毎日がより楽しくなる」「物事を自分で決めるようになる」「人生に積極的になる」等の選択の割合も、他団体に比べ20%前後高いことから推測できるだろう。
図19 サービスの利用と生活変化
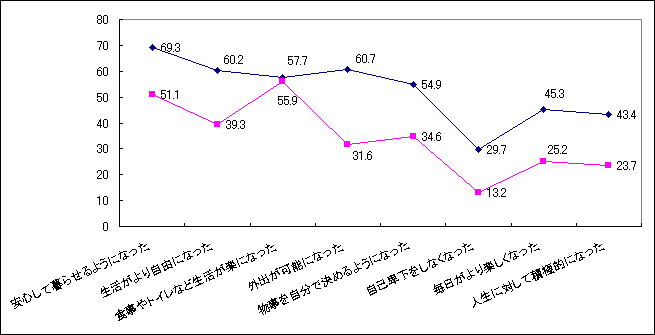
| 項目 |
自立生活
センター |
他団体 |
自立生活センター ―他団体 |
項目 |
自立生活
センター |
他団体 |
自立生活センター ―他団体 |
| 安心して暮らせるようになった |
69.3% |
51.1% |
18.2% |
物事を自分で決めるようになった |
54.9% |
34.6% |
20.3% |
| 生活がより自由になった |
60.2% |
39.3% |
20.9% |
自己卑下をしなくなった |
29.7% |
13.2% |
16.5% |
| 食事やトイレなど生活が楽になった |
57.7% |
55.9% |
1.8% |
毎日がより楽しくなった |
45.3% |
25.2% |
20.1% |
| 外出が可能になった |
60.7% |
31.6% |
29.1% |
人生に対して積極的になった |
43.4% |
23.7% |
19.7% |
自立生活生活センターの事業実績及び財政規模について(2002年度実績)
■A市の自立生活センター(東京の人口50万人都市)
| 収入 |
支出 |
| 会費 |
1,438,000 |
人件費 |
149,199,254 |
| 助成金・補助金 |
155,817,671 |
|
給与 |
138,778,993 |
| |
東京都地域福祉財団(※1) |
18,546,000 |
(うち非常勤ヘルパー 56,339,715) |
| ホームヘルプ事業 |
112,404,570 |
法定福利費等 |
10,420,261 |
| 市町村障害者生活支援事業 |
15,000,000 |
事務所費(※2) |
19,863,657 |
| その他 |
9,867,101 |
旅費交通費 |
1,735,976 |
| 事業収入 |
28,094,003 |
通信費 |
3,245,316 |
| |
有償家事援助事業 |
22,328,750 |
印刷費 |
639,737 |
| 福祉工房 |
435,700 |
研修費 |
2,120,415 |
| 移送サービス |
1,239,760 |
消耗品費 |
887,970 |
| サポートセンター |
569,433 |
修繕費 |
1,466,720 |
| その他 |
3,520,360 |
保険料 |
1,356,223 |
| 雑収入 |
3,398,096 |
その他 |
7,693,500 |
| |
|
当期収支差額 |
539,002 |
| 合計 |
188,747,770 |
合計 |
188,747,770 |
※1 有償家事援助・移送サービス・福祉工房・聴覚視覚サポートセンターの4事業
※2 事務所の賃借料、水光熱費、駐車場等
○職員体制
常勤職員 15名・非常勤職員7名・嘱託5名・ホームヘルパー497名・有料介助473名
○2002年度 介助サービス事業
| 派遣時間数 |
79,592時間 |
|
身体介護・家事援助 |
64,649時間 |
| 知的・視覚移動介護 |
14,943時間 |
| 利用者数 |
411人 |
|
肢体障害者 |
130人 |
| 視覚障害者 |
22人 |
| 知的障害者 |
223人 |
| 精神障害者 |
10人 |
| その他 |
26人 |
※ホームヘルプ・ガイドヘルプ事業及び有料介助派遣事業の合計
○2002年度 市町村障害者生活支援事業 実績
| 公的制度・サービス等の利用援助 |
312件 |
| 社会資源活用の支援 |
706件 |
| 社会生活力向上の支援 |
395件 |
| ピアカウンセリング |
784件 |
| その他 |
7件 |
| 合計 |
2,204件 |
ピア・カウンセリング部門
| 内容 |
実施日数 |
参加人数 |
| ピア・カウンセリング講座 |
91日 |
1211人 |
| ピア・カウンセラー養成講座 |
11日 |
97人 |
| 個別ピア・カウンセリング |
137日 |
137人 |
| 合計 |
239日 |
1445人 |
|
|
自立生活プログラム部門
| 内容 |
実施日数 |
参加人数 |
| 自立生活プログラム講座 |
23日 |
185人 |
| リーダー養成講座 |
3日 |
25人 |
| 個別プログラム |
115日 |
115人 |
| 合計 |
141日 |
325人 |
|
○2002年度 移送サービス実績
| 内容別運行活動実績 |
| 内容 |
平均一日利用件数 |
延利用件数 |
延利用時間数 |
利用実人員 |
| 通院 |
0.20件 |
76件 |
237時間 |
10人 |
| 買い物 |
0件 |
0件 |
0時間 |
0人 |
| 用足し |
0.18件 |
68件 |
303時間 |
15人 |
| 行事参加 |
0.19件 |
71件 |
259時間 |
14人 |
| 旅行 |
0.03件 |
12件 |
65時間 |
7人 |
| 通所 |
0.01件 |
6件 |
15時間 |
3人 |
| その他 |
3.13件 |
1,143件 |
1,666時間 |
43人 |
| 合計 |
3.70件 |
1,376件 |
2,545時間 |
92人 |
■B市の自立生活センター(地方の人口12万人都市)
| 収入 |
支出 |
| 会費 |
665,000 |
人件費 |
17,031,672 |
| 助成金・補助金 |
31,110,000 |
|
常勤職員 |
12,942,442 |
| |
市町村障害者生活支援事業 |
15,000,000 |
非常勤・嘱託 |
2,692,317 |
| ガイドヘルプ事業 |
13,186,075 |
法定福利費等 |
1,396,913 |
| 県雇用対策基金(※1) |
1,818,000 |
事業費 |
15,309,230 |
| 障害者雇用助成金 |
855,925 |
|
有料介助派遣 |
4,664,902 |
| 民間財団 |
250,000 |
ガイドヘルプ |
6,071,340 |
| 事業収入 |
7,232,762 |
生活支援事業 |
3,079,171 |
| |
有料介助事業 |
6,630,610 |
広報活動費 |
690,865 |
| 市町村障害者生活支援事業 |
200,513 |
研修費 |
729,952 |
| 講師派遣事業 |
401,639 |
負担金 |
73,000 |
| 寄付金 |
799,993 |
事務所費(※2) |
2,739,229 |
| 雑収入 |
242,384 |
事務費 |
3,729,375 |
| |
|
車両費 |
934,864 |
| 前期繰越金 |
4,926,825 |
次年度繰越金 |
5,232,594 |
| 合計 |
44,976,964 |
合計 |
44,976,964 |
※1 雇用創出のために新規職員を雇い入れを行った事業所への助成金
※2 事務所の賃借料、水光熱費、駐車場等
○職員体制
常勤職員5名・非常勤職員2名・嘱託7名・ガイドヘルパー30名・有料介助20名
○2002年度 市町村障害者生活支援事業 実績
| 公的制度・サービス等の利用援助 |
164件 |
| 社会資源活用の支援 |
273件 |
| 社会生活力向上の支援 |
163件 |
| ピアカウンセリング |
335件 |
| その他 |
201件 |
| 合計 |
1,136件 |
○2002年度 ガイドヘルプ事業 実績
| 年間派遣件数 |
1,175件 |
| 派遣時間数 |
3,729.6時間 |
|
うち視覚障害者 |
1,424.7時間 |
| うち全身性障害者 |
2,304.9時間 |
| 利用者数 |
290人 |
|
うち視覚障害者 |
150人 |
| うち全身性障害者 |
140人 |
■24時間要介護障害者のサービス利用の事例
| 週間介護ローテーション(ケアプラン)表 |
|
利用者 : 東京都A市在住 Bさん(脳性麻痺・1級)
事業所名: ○△○センター |
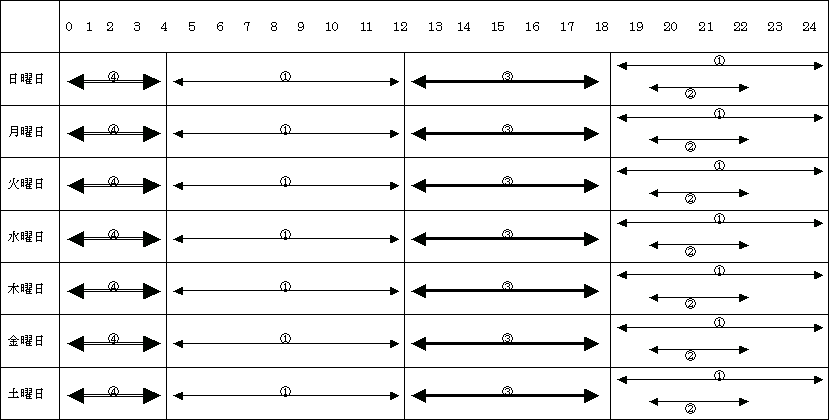
●利用サービス
| (1) 支援費居宅介護 日常生活支援 |
(2)支援費居宅介護 日常生活支援(入浴2人体制) |
| (3) 支援費居宅介護 移動介護 |
(4)生活保護他人介護加算分 |
| 支援費支給決定時間数 日常生活支援=527時間 |
(23h/日×31日分) |
| 移動介護=186時間 |
(6h/日×31日分) |
※ 生活保護他人介護加算分は、市の指導により深夜帯で利用することとなっている。
支援費制度で何がどう変わったか-知的障害児者・障害児について-
自立生活センター・グッドライフ 末永 弘
○自立生活をしている知的障害者
東京都の多摩地域(23区を除く市町村部)では、これまで身体障害者に対して毎日24時間の介護保障を実現してきた市が数多くあり、その基盤の上で自立生活センターやピープルファーストなど団体の支援を得ながら自立生活をする知的障害者が増えてきています。
東京都H市では、毎日24時間の介護が必要な利用者に対して、表1のように1日平均14時間のホームヘルパプサービスと、週3日のデイサービスという支援費の支給決定が出ています。
東京都T市ではやはり毎日24時間介護が必要な利用者に対して、表2のように1日平均8時間のホームヘルプサービスと、週4日のデイサービスという決定になっています。
この2つの市では措置制度の中で認められていた時間数をほぼそのまま支援費の時間数として決定し、新たにデイサービスの支給決定を行いました。支援費制度でNPO法人もデイサービスの指定を受けることができるようになったため、以前から通っていた場所がデイサービスの指定を受ける形で支援費を利用できるようになりました。
24時間介護が必要な知的障害者に対しては、市が認めたホームヘルプサービスやデイサービス以外の時間帯については、その利用者を支援している地元の団体がその支援費の収入を使って独自にヘルパーを派遣しています。
これらの市では数年間に渡って、自立生活をしている当事者と支援団体が協力して市との話し合いを継続しており、その中で下記の内容について一定の合意が得られています。
|
(1)実家での親との同居は、その利用者の障害状況から考えて困難であること。(親も同居は難しいと考えていること)
(2)利用者本人は入所施設や病院での生活を望んでいない、あるいは拒否していること。
(3)市内のアパートを借りて1人暮らしをしていくことは、市の制度を使い団体が支援を行えば可能であること。
(4)自立生活をしている知的障害者の中でも、
|
| ・外で他人(特に子どもや老人)に対して危害を加える行為がある人。
・1人で出かけて行方がわからなくなってしまう人。
・無銭飲食や万引きなど法に触れる行為を頻繁に行う人。
・鍵の付いた車を運転したり、火遊びをするなど危険な行為をする人。 |
このような利用者に対しては、24時間見守りを含めた何らかの形での「介護」が必要であること。(市と話し合いを行う場合には、24時間の制度を市が認めるかどうかではなく、その利用者が地域での生活を継続していくためには24時間何らかの形での介護が必要であることを説明し、そこから話を進めていくことが重要です。)
上記の2つの市でも、これらのことをケースワーカーや係長、課長などと何度も話し合いを重ねることでヘルパーの時間数を徐々に伸ばしてきています。
その他自立生活をしている知的障害者でほぼ毎日家事援助や身体介護、又は移動の介護が必要な利用者には、十分とは言えないながらも必要に応じて毎日2時間〜8時間程度(土日通所が無い日は多くて11時間程度)という形で支給決定がなされています。
表1
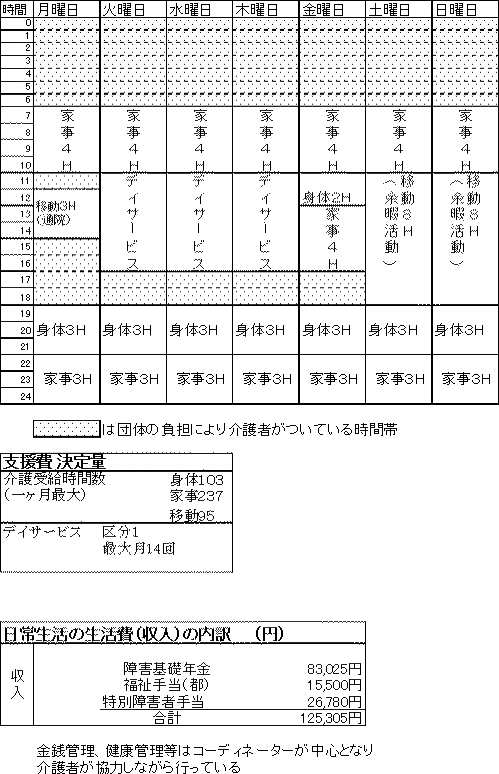
表2
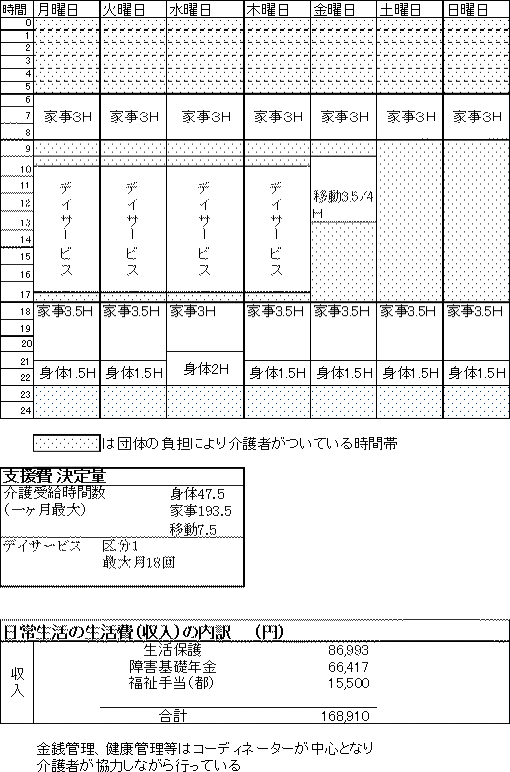
○グループホームで生活している知的障害者
グループホームで生活する知的障害者に対してヘルパー派遣を認める自治体は支援費制度になってかなり増えているようです。制度的には平成12年度に国が行った要綱改正の中で、在宅の範囲にグループホームも含む形で利用が認められていましたが、実際にはほとんど使われていないのが現状でした。
支援費制度では全ての利用者に市のケースワーカーが訪問調査に来て、必要であれば1枚の申請書の中でグループホームとホームヘルプサービス(居宅介護)の申請ができるため、利用者に非常にとっては非常に申請がしやすくなったと言えます。自治体の側も特に土日での外出希望に関しては「移動」での決定を出すところが増えました。
東京都東久留米市の自立生活センターグッドライフが運営を行い、重度知的障害者4人が生活しているグループホームでは、4ヶ所の出身市(4人とも別の市から入居している)との間で、土日に関して実家に帰った日を除いて1日6時間、月最大10日までは家事援助、身体介護、移動の組み合わせでホームヘルプサービスを利用し、マンツーマンでの介護を保障していくことで合意し支援費の決定を得ています。
生活寮に暮らす重度知的障害のDさんの事例
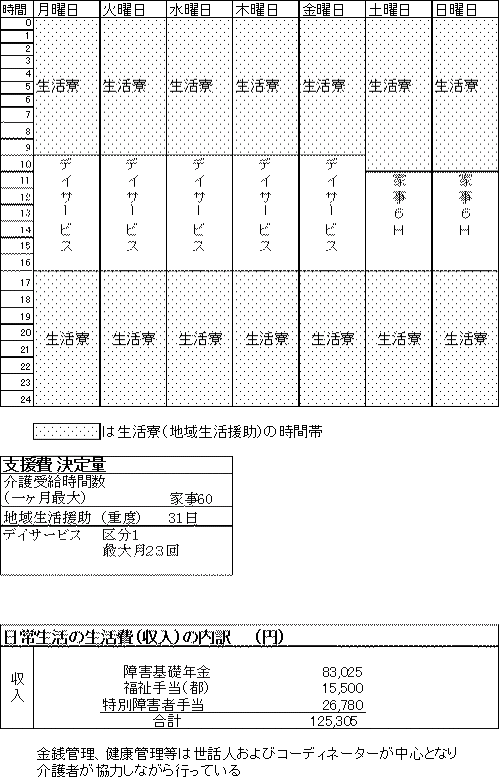
生活寮に暮らす重度知的障害のFさんの事例
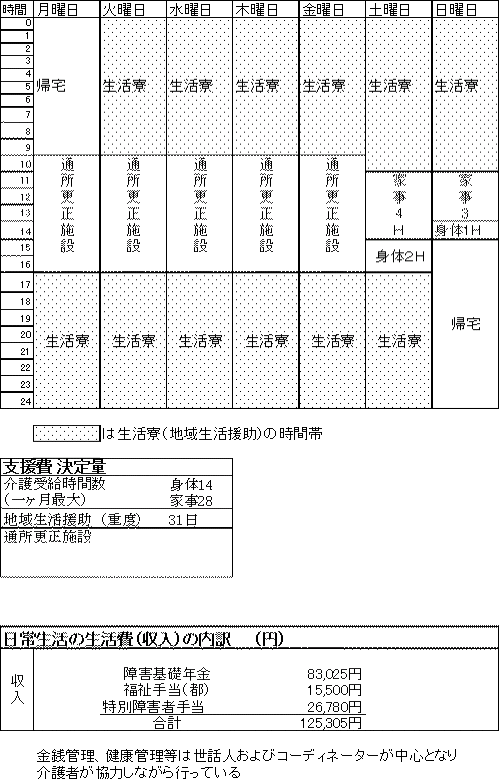
○親元で生活している知的障害者
親元で生活している知的障害者の場合、やはりニーズとしては、通所が休みの土日・祝日の外出介護4時間〜8時間程度と、親の介護負担が大きい知的障害者の場合は、平日通所から帰った後の3時間程度という利用者が多いようです。利用者のニーズに沿って支援費の決定を行っている市では、平日1日3時間(身体介護と家事援助)、土日どちらかで毎週3時間(移動)で月80時間を越える決定が出ている利用者もいます。それに近いところでは平日3時間の週2回(家事援助、身体介護)、土日の移動で月20時間の計約50時間の決定が出ている利用者も少なくありません。
○支援費制度で知的障害者ガイドヘルパーがどこでも利用可能に
知的障害者の場合、旧制度の中では、ホームヘルプサービスとは別に、大阪府、大阪市、東京都、横浜市、名古屋市、札幌市など大都市部を中心にガイドヘルパー制度を実施している自治体があり、それ以外の自治体では知的障害者が外出時にヘルパー制度を活用することはほとんど行われていませんでした。支援費制度では外出時の介護を「移動」という区分で位置づけたため制度的に全国どこの自治体でも外出時のいわゆる「ガイドヘルパー」が使えるようになりました。これは支援費制度の大きな改正点の1つです。
東京都内では14年度中に半数以上の区市で知的障害者のガイドヘルパー制度が実施されていたこともあり、支援費制度の中でも月20時間〜40時間程度までを認めている自治体が多数派となっています。
○ 知的障害者に対する支援費決定の問題点
(1)自立生活をしていて24時間介護の必要な知的障害者に対して、24時間の支給量が認められていないこと。
(2)支援費の調査の際に、例えば入浴や掃除・洗濯などが自分でできるかできないか?という形でケースワーカーに聞かれるため、「できる」と答えた場合に身体介護や家事援助の時間が極端に少なく決定されてしまう。誰かからの声かけがないと週に1回も入浴しない、入っても丁寧に洗えずすぐ出てしまう、掃除・洗濯などもなかなかやれずに日がたってしまったり、逆に1人でやるとものすごく時間がかかってしまう、このような知的障害者にはやはり声かけをしたり、一緒に家事をしたり、見守っていたりというヘルパーが必要ですが、「できる」か「できない」かという2者択一の質問では圧倒的に多いその間にあるニーズが行政から評価されない結果となっています。
(3)身体介護を直接体に触れる介護時間として解釈している市が多く、身体介護と家事援助では圧倒的に家事援助の比率が高い決定になっている。(この問題は身体介護1時間4020円、家事援助1530円という極端な単価差の問題でもあり、来年度介護保険制度にそろえる形で家事援助を「生活援助」として1時間約2000円という改正が行われる予定。)
(4)外出時の「移動」の決定についても、身体介護無しでの決定が圧倒的に多くなっている。外出時のヘルパーの負担はさほど変わらないにもかかわらず、単純に身体障害者には「身体介護有り」、知的障害者には「身体介護無し」という決定が一般化してしまっていること、そこに1時間当たり4020円と1530円という全く不合理な単価差があることは、利用者が事業所を選ぶ際の大きなネックとなっている。
(5)親が本人の意向とは別に数日〜1週間程度施設で預かるショートステイの利用を希望する場合が多く、行政側も比較的安上がりなショートステイの決定を勧める傾向があるため、全国的にショートステイの決定が相当増加したと考えられる。又支援費制度ではNPO法人などのショートステイ事業への新規参入を排除するため、原則として入所施設に併設するという指定要件とされているため、居宅サービスの中のショートステイは事実上施設サービスでしかなく、又施設に入所するための練習や試しのためにショートステイが利用されているという実態も少なくない。
○児童(18歳未満の身体・知的障害児)の支援費利用
児童の部分は支援費制度になり最も在宅サービスが増加した部分だと言えます。措置制度の中では、ホームヘルプサービスはその児童の障害が相当重く、親の介護負担が極端に大きい場合以外にはなかなか認められませんでした。又外出時の介護については国の要綱で18歳未満の障害児は対象外となっていたため、外出時のニーズはあっても実際にヘルパー制度は使えませんでした。支援費制度では児童に対しても外出時の「移動」が認められたため、週に1回土日などに公園やプールなどに外出するという申請が多く出され、時間数の多少はあるにしてもほとんどの利用者に対して支給決定が認められたようです。
又普段はサービスを使っていなくても、いざという時のために受給者証だけは持っておきたいという考えから支援費の申請をした利用者も少なくないようです。
厚生労働省が4月時点での居宅生活支援費(ホームヘルプ、デイサービス、ショートステイ、グループホーム)の支給決定を受けた利用者が約19万人という数字を発表し、多くの福祉関係者が数字の多さに驚いたようですが、増加した部分の相当数はショートステイの利用や、児童の利用者が占めていると考えられます。
児童に関しては月10時間〜20時間という決定が多いようですが、東京都内では知的障害児に対して月に40時間〜50時間という決定が出ている例も少なくありません。例としては、平日の学校後の利用では身体介護と家事援助、土日の外出は「移動」というようなパターンになっています。又自閉症の男性など比較的介護ニーズの高い利用者が多いために、知的障害者と比べて「身体介護」や「移動(身体介護有り)」での決定時間が多くなっているのが特徴です。
○知的障害者や児童に対する事業所の状況
次に支援費制度でホームヘルプサービスを行う事業所の状況ですが、数の上では全国で身体約8100ヶ所、知的6200ヶ所、児童5400ヶ所(基準該当事業所を含む)と大幅に増加しましたが、その約8割が介護保険の指定を併せて受けている事業所であり、指定は受けていても実際には派遣できていない事業所も多いと思われます。
特に知的障害者や児童の中でも最も介護ニーズが高い男性の自閉症の利用者に関しては、女性ヘルパーでの対応が難しいこともあり、実際に派遣を行っている事業所は非常に少ないのが現状です。又事業所としては最大限派遣できるように努力していても、対応できる男性ヘルパーが事業所に1人しかいないというような場合、利用者の希望する日に派遣ができないという事例が多くなっています。
この記事に関するお問い合わせは、以下にどうぞ。
・知的障害者に関する記事部分は 自立生活センター・グットライフ0424-77-8384
毎日昼間の介護が必要な重度知的障害Cさんの事例
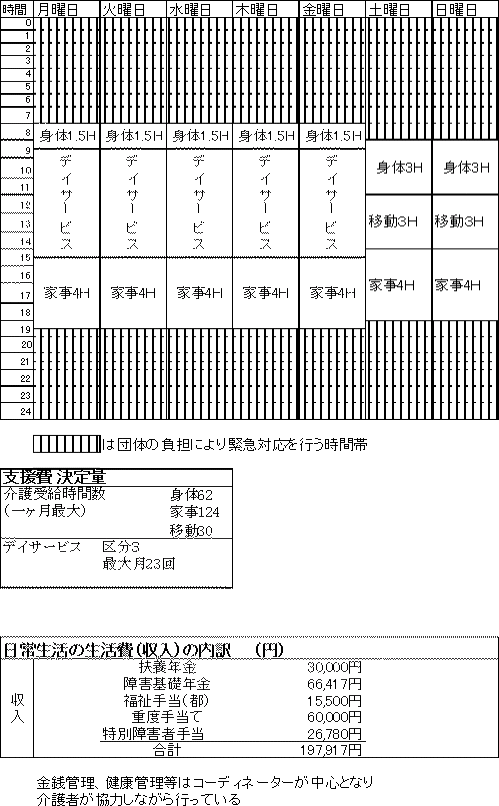
子育て支援の必要な中度知的障害のEさんの事例
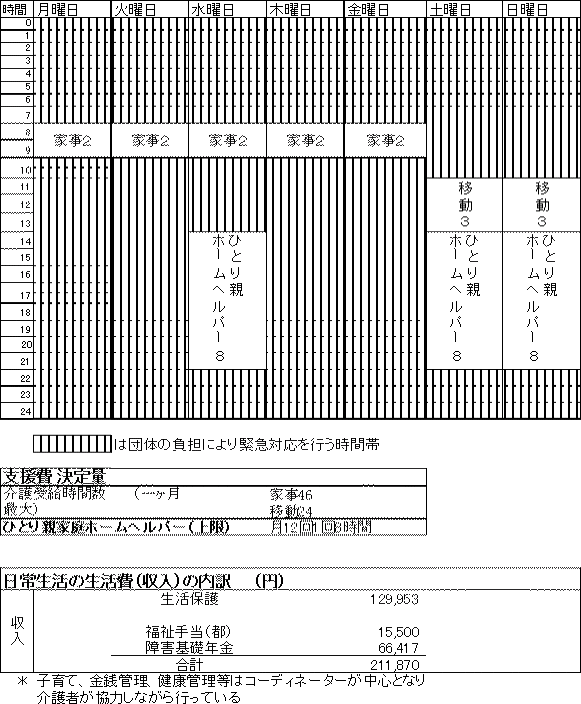
移動と生活支援が必要な中度知的障害のGさんの事例
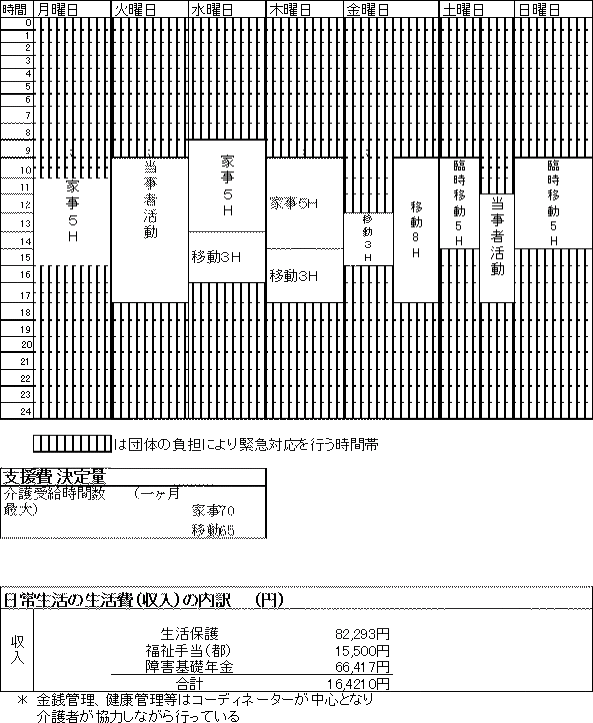
毎日昼間の介護が必要な中度知的障害のHさんの事例
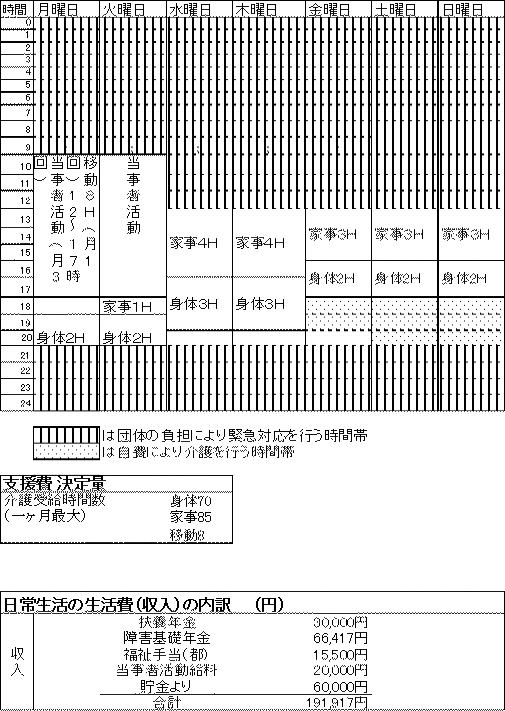
トップへ
戻る