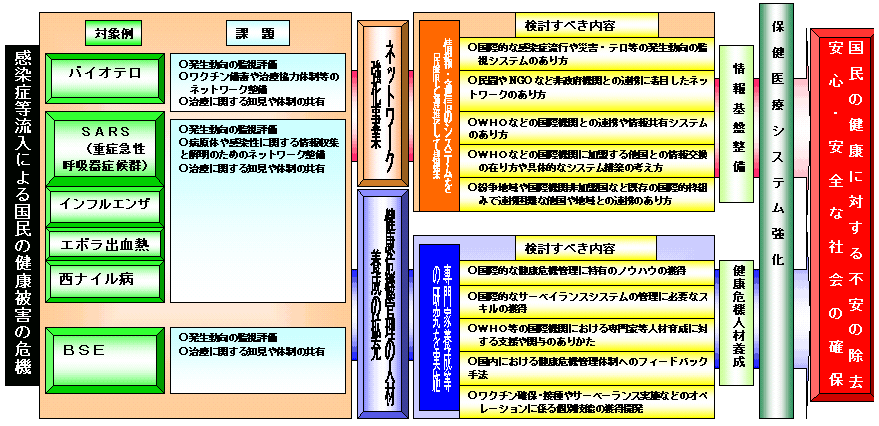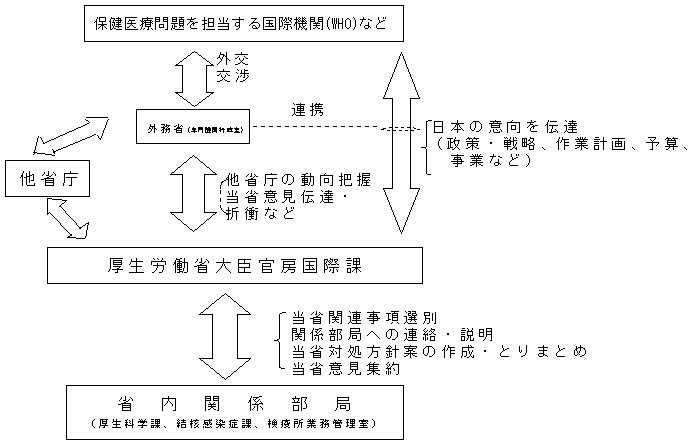| 国際健康危機管理ネットワーク強化研究 |
| ○ | BSE、エボラ出血熱及び最近のSARS(重症急性呼吸器症候群)、更にバイオテロの勃発などに対して、国外からの情報等に基づく健康危機管理体制の強化が国民の健康被害を最小限にするためには必須な状況となってきている。 |
| ○ | これらの国外情報の効率的かつ迅速な入手・活用を強化するため、国際健康危機管理ネットワーク強化について、今後特に重点的に取り組むことが急務。 |
| ○ | ネットワークの構築又は強化のために実施すべき政策課題の解明を主眼に研究を推進。 |
| ○ | このためのネットワーク構築の具体的な柱として、(1)情報基盤整備、(2)国際的な健康危機管理対応人材の養成、の2つに着目して分析する。 |