(参考)日本の残留農薬基準の設定状況(平成15年1月現在)
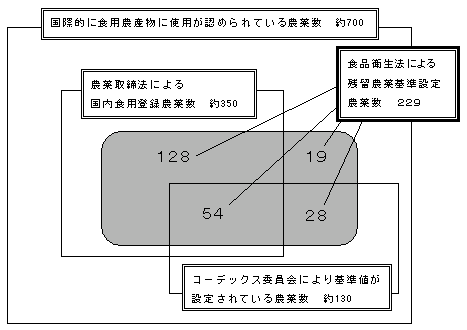
|
| 資料2 |
(参考)日本の残留農薬基準の設定状況(平成15年1月現在)
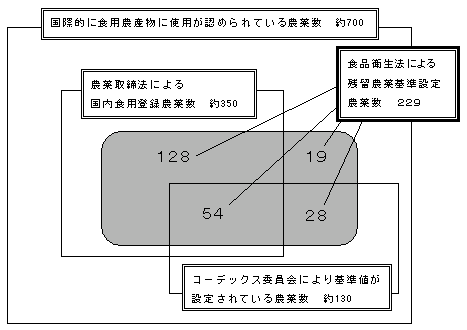
|
| (1) | 参考とする基準 暫定基準を設定するにあたり参考とする基準は、(1)国際基準であるコーデックス基準、(2)国内の農薬取締法における登録保留基準のほか、(3)JMPR (FAO/WHO合同残留農薬専門家会議)で科学的な評価に必要とされている毒性試験結果などのデータに基づき残留基準が設定されている諸外国の基準とする。 |
||||
| (2) | 参考とする諸外国の基準の選定 (1)(3)の諸外国の基準を選定するにあたり、参考とすることができる基準を有していると考えられる国に対して、基準設定の評価資料等(毒性試験、残留試験等)の提供も含め、以下のとおり申出の機会を設けたところである。
その結果、申出があったのは、米国、欧州連合(EU)、オーストラリア、ニュージーランド、カナダの5ヶ国(地域)であった。 |
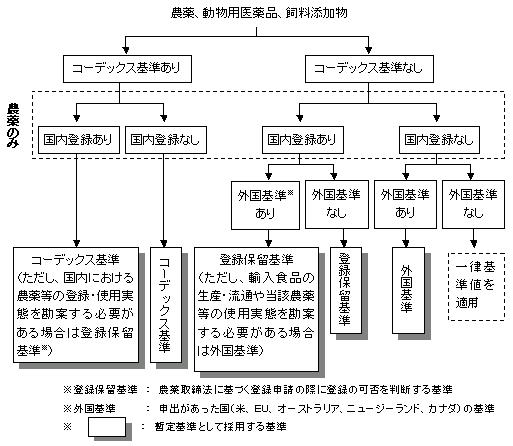
| なお、農薬等に該当するものであって食品に残留する成分が、いわゆる汚染物質等と同じものである場合には、自然に含まれるものが違反とならないように必要な措置を講ずる。 また、農薬等に該当するものであって、かつ、添加物であるものについては、暫定基準策定の対象としない。 |
| (1) | 許容一日摂取量(ADI)の設定 検討すべき農薬における、ラット、マウス等の動物を用いた毒性試験(慢性毒性試験、発がん性試験、繁殖毒性試験、催奇形性試験、遺伝毒性試験等)結果から、各々の試験で毒性影響が認められない量を求め、そのうち最も小さいものを当該農薬の無毒性量とする。この動物実験の結果を人に外挿するために、当該農薬の無毒性量に安全係数(通常は100:10(種差)×10(個人差))を乗じて、許容一日摂取量(Acceptable Dairy Intake:ADI)を求める。 |
| (2) | 最大残留量の原案作成・暴露評価 検討すべき農薬における、動物・植物代謝、環境中の運命、使用方法、作物における残留量等に関するデータから残留及び分析に関する評価を行い、適正な範囲で農薬を使用した場合の最大残留基準値(Maximum Residue Limit:MRL)の原案を作成する。 次に当該農薬の食品中への残留量(MRLや作物残留量データを利用)とその食品の摂取量から、当該農薬の食品由来の摂取量を求め、この摂取量と(1)のADIを比較し、ADIを超えなければ、暴露量が安全な範囲内ということで、当該MRLを基準値案とする。 |
| (1) | 作物残留性に係る登録保留基準 国内で農薬等を販売するためには農薬取締法に基づく農薬の登録が必要であるが、農林水産大臣は、登録申請の際に一定の要件に該当する場合には、当該農薬の登録を保留し、申請者に当該農薬の品質改良すべきことを指示することができるとしている。(農薬取締法第3条) このうち、(1)作物残留性、(2)土壌残留性、(3)水産動植物に対する毒性、(4)水質汚濁性に係るものについては、環境保全と人の健康保護の観点から環境大臣が登録保留基準を定めることができることとしており、当該農薬を適正に使用したときこれらの基準を超えるものについては登録が保留されることになる。 登録保留基準のうち、作物残留性に係る基準については、「登録申請された使用時期・使用方法で使用されたとき、農作物等に残留する農薬濃度が
|
||||
| (2) | 作物残留性に係る登録保留基準の設定方法 上記(b)の設定方法はJMPRにおける評価と同様に、動物を用いた毒性試験の結果からADIを求め、登録申請時に提出された作物残留試験成績を基に設定した基準値原案と国民栄養調査による作物等の摂取量から試算した当該農薬の理論最大摂取量が、ADIの80%以下になるように設定している。 |