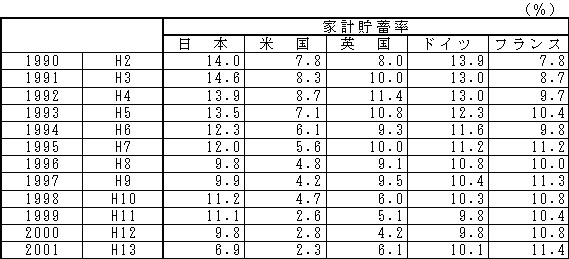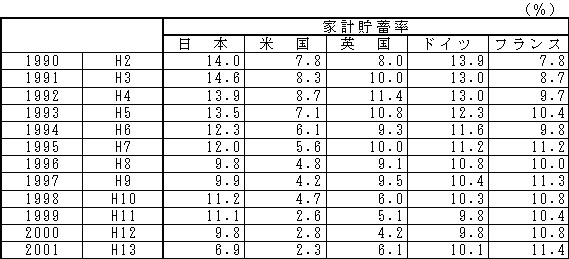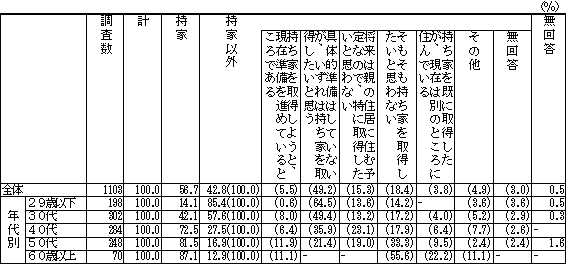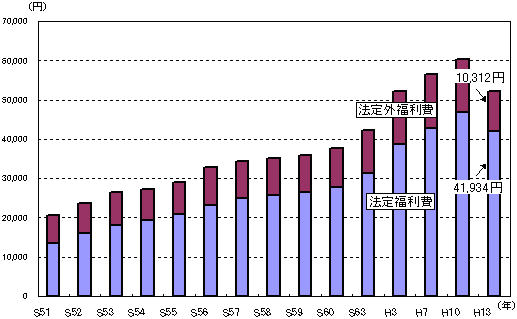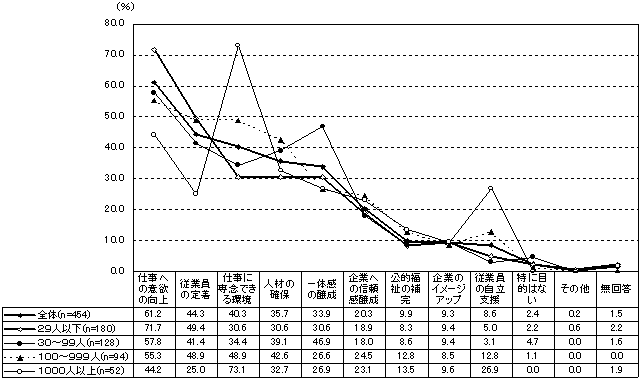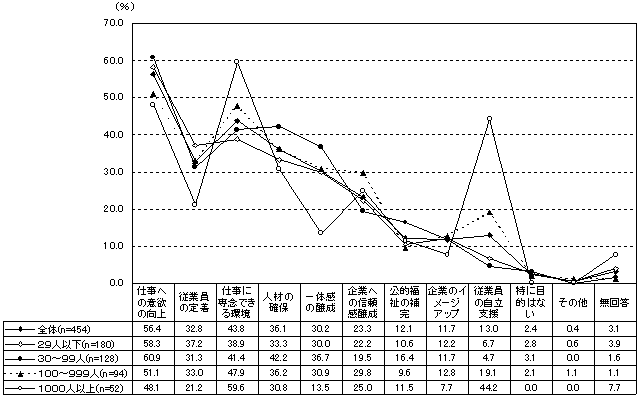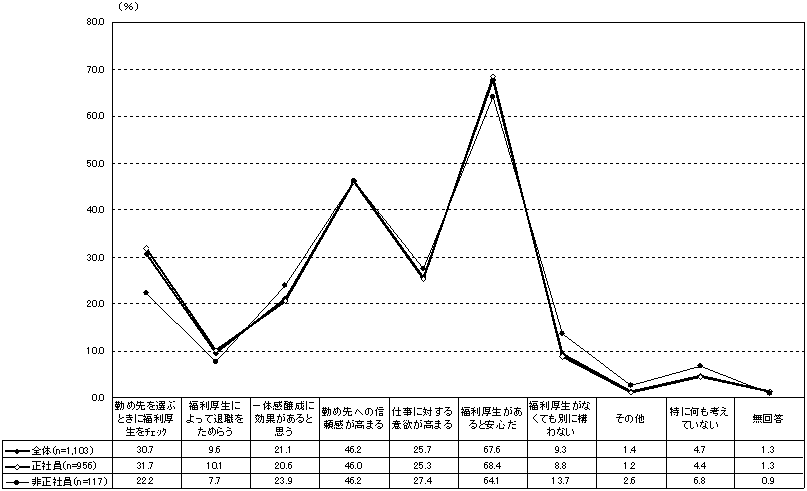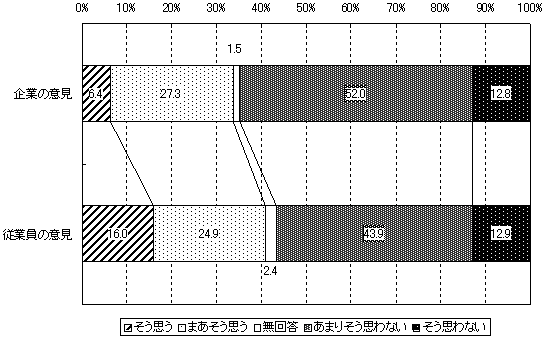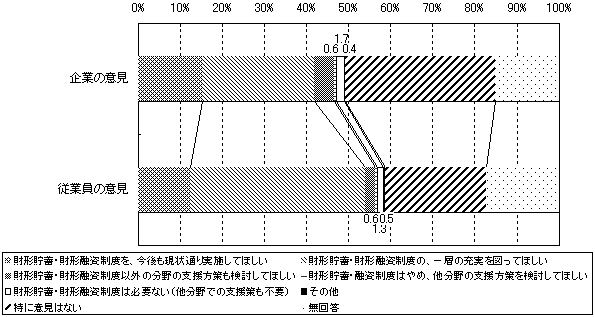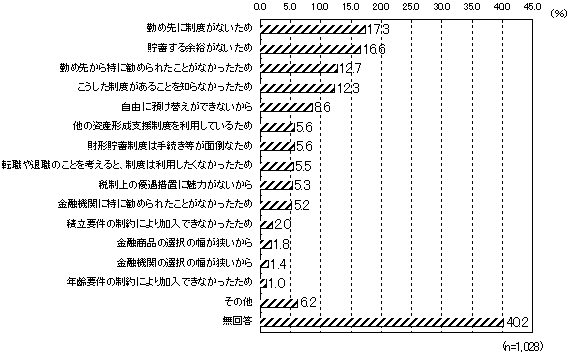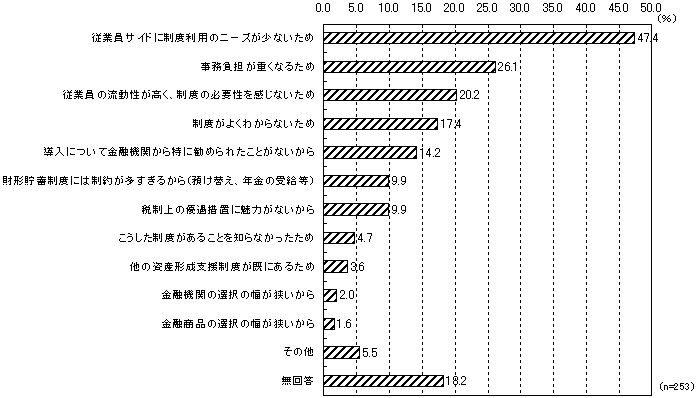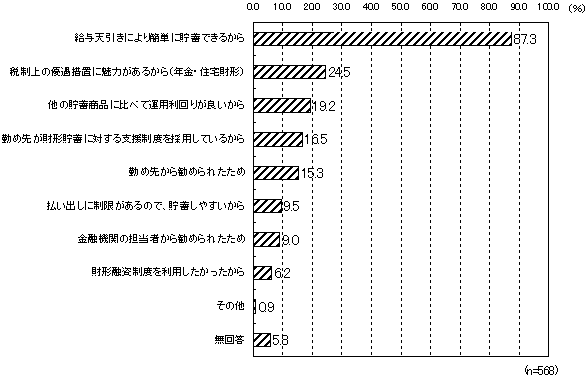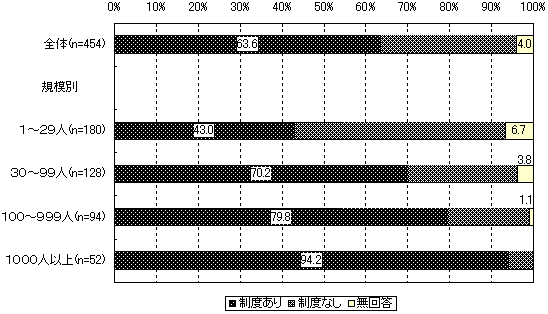戻る
「企業内福利厚生のあり方と今後の勤労者財産形成促進制度の課題について」(概要)
(平成14年度厚生労働省委託研究)
I.研究の概要
経済社会の構造変化の中で、我が国の労働市場や雇用のあり方が大きく変わりつつある。国際化が進んで企業間競争が激化し、定年まで同一企業に勤められる可能性が従前よりも小さくなってきている。また、業績・成果をより重視した賃金制度を導入する企業が増えるなど、従来の日本的雇用慣行に見直しの動きがみられ、勤労者の就業意識も変化している。こういった動きのもとで、企業内福利厚生のあり方も大きく変革しつつある。
このような変革しつつある企業内福利厚生のあり方について検討するとともに、企業内福利厚生の一つでもあり、国が企業内福利厚生を支援する枠組みとして最も大きな施策の一つである勤労者財産形成促進制度(以下、「財形制度」という。)のあり方についても検討することが必要となっている。
このため、(1)企業内福利厚生のあり方についての検討、(2)財形制度のあり方についての検討の2点を大きな目的とした研究を(株)ニッセイ基礎研究所へ委託して、平成14年9月より「雇用の流動化、自己責任時代における企業内福利厚生のあり方に関する研究会(座長:一橋大学 藤田伍一教授)」(参考資料1参照)を7回にわたり開催し、報告書等をとりまとめた。
II.報告書の概要
1.企業内福利厚生と財形制度を取り巻く環境変化
(1) 労働市場・就業構造の変化
(雇用の流動化)
| |
○ |
失業を余儀なくされる者が増加するとともに、勤労者サイドでも転職希望者比率が上昇傾向にあり、雇用の流動化が進んでいくことが予想される。 |
(非正社員の増加)
| |
○ |
パートタイマー、派遣労働者等の非正社員が増加してきている。 |
(2) 企業組織や雇用慣行の変化
| |
○ |
近年、様々な形での企業組織の再編が活発に行われるようになってきているとともに、厳しい経済情勢の下、企業自体の存続についても不透明感も増してきている。 |
| ○ |
大企業正社員に顕著にみられた長期雇用慣行、年功賃金を始めとする日本的雇用慣行に見直しの動きがみられている。 |
(3) 経済環境の変化
(低迷する経済)
| |
○ |
バブル経済が崩壊して以降、日本経済は長期的な低迷から脱しきれず、厳しい経済情勢が続いている。 |
(金融の自由化)
| |
○ |
金融の面においては、特に平成8年以降に自由化が進展し、多様な金融商品やサービスが登場する一方で、競争に生き残れずに破綻する金融機関も出てきた。 |
(4) 社会保障制度の変化
| |
○ |
少子・高齢化の進展の下、社会保障制度の改革が進められる中で、社会保障負担率はここ数年上昇傾向にあり、今後もこの傾向が続くことが予想されている。 |
(5) 勤労者生活の変化
(収入や貯蓄の動向)
| |
○ |
家計貯蓄率がここ数年低下し、家計の貯蓄に係る状況は大きく変化している(図表1)。また、勤労者世帯の家計収入もここ数年減少し、貯蓄残高の伸び率も鈍化してきている。 |
| ○ |
経営環境の変化等により雇用を巡るリスクが高まっていることに加え、賃金の変動要因も大きくなってきたことにより、生活設計の必要性が従前より高まってきている。このような中、特に貯蓄余力の乏しい勤労者(若年層や30〜40歳代等)にとって、早い段階からの貯蓄がより重要になってくると考えられる。 |
(持家比率の推移)
| |
○ |
現在の住居が持家である割合は56.7%で、持家でない人の過半数が今後持家を取得する意向を持っており、持家に対するニーズは依然として根強いといえよう(図表2)。 |
2.企業内福利厚生の動向と課題
(1) 企業内福利厚生の動向
(福利厚生費用の現状)
| |
○ |
少子・高齢化等が進展し、社会保障制度改革が進められる中で、法定福利費は増加傾向が続いてきたが、平成13年には現金給与総額の落ち込み等により法定福利費、法定外福利費ともに平成10年を下回り、これまでの傾向に変化がみられる(図表3)。 |
(企業内福利厚生の格差)
| |
○ |
多くの企業内福利厚生に関する施策において、企業規模による実施率の格差、就業形態による適用率の格差がみられる。 |
(役割・機能の動向)
| |
○ |
企業内福利厚生の以下の役割・機能のうち「従業員の定着」については「現在重視する」とする企業の割合に比べて「今後重視する」割合が低くなっており、特に大企業でこの傾向が顕著である。また、大企業においては、「従業員の自立支援」を「今後重視する」割合が「現在重視する」に比べて著しく高くなっている(図表4、5)。
| ・ |
人材の確保 |
| ・ |
従業員の定着 |
| ・ |
従業員の仕事に対する意欲の向上 |
| ・ |
企業への信頼感やロイヤリティの醸成 |
| ・ |
従業員同士の一体感の醸成 |
| ・ |
従業員が仕事に専念できる環境づくり(生活の安定等) |
| ・ |
従業員の自立支援 |
|
|
| ○ |
勤労者の企業内福利厚生に関する意識をみると、「福利厚生があると安心だ」という回答が7割弱にのぼり、勤労者側では、企業内福利厚生を安心感や信頼感を表すものとして捉えられていると考えられる(図表6)。 |
(運営手法等の動向)
| |
○ |
福利厚生施設・サービス等を提供する民間企業は増えつつあり、近年、大企業を中心に利用が増加している。 |
(2) 企業内福利厚生の課題と方向性
(企業内福利厚生に対する労使のニーズへの対応)
| |
○ |
企業内福利厚生において、企業は良質な労働力を保全する、あるいは労働力の質を高めるための条件整備を重視している一方で、勤労者は不安への備えに対する支援を求めており、企業の方向性と勤労者のニーズとは必ずしも一致しない面もあるが、こうした労使のニーズの違いを踏まえた上で行政としては、企業内福利厚生への支援のあり方を考えていく必要があろう。 |
(企業内福利厚生の運営の効率化への対応)
| |
○ |
企業内福利厚生の運営の効率化への対応として、外部機関への運営委託は有効な手段であると考えられることから、単独では実施が困難な福利厚生施策の実施について、外部機関をより有効に活用できるような、環境整備を図っていくことが望まれる。 |
(企業内福利厚生と賃金)
| |
○ |
「福利厚生費用を可能な限り抑制し、その分を賃金の原資に充てていきたい」という意見については、企業、勤労者の過半数が否定しており(図表7)、福利厚生の賃金化が一般的な流れになるとはあまり考えていないようである。 |
(企業内福利厚生の格差)
| |
○ |
企業規模に関わらず勤労者にとっての必要性やメリットが大きい、あるいは中小企業の勤労者にとって必要性の高いような福利厚生施策については、中小企業への制度普及や支援を図る必要性があるのではないかと考えられる。 |
| ○ |
いわゆる非正社員の比率が高まっていく傾向の中で、非正社員に適用することに意義がある施策については、国としても、非正社員への制度普及や支援を図る必要性があろう。 |
(3) 企業内福利厚生の位置づけ〜公的福祉と自助努力との関係
(企業内福利厚生と公的福祉との関係)
| |
○ |
企業内福利厚生が公的福祉を補完することには一定の限界があるものの、勤労者の生活の安定や、健康・安全の確保、さらには能力開発等、社会的に重要性の高い事項について、企業の役割に対する期待は依然として大きく、企業がこのような企業内福利厚生を実施していく意欲を減少させないような政策が求められる。 |
| ○ |
公的福祉と企業内福利厚生、さらには勤労者自らの自助努力をいかに効率的に組み合わせ、バランスをとっていくかということが、勤労者福祉の実現のためにより重要な課題となっている中、財形制度は自助努力を国及び事業主が支援するという制度であり、企業が勤労者の生活の安定を図るための企業内福利厚生として積極的に利用できるようにその機能を見直していくことも必要であろう。 |
(企業内福利厚生等と自助努力との関係)
| |
○ |
公的福祉の縮減とこれを補完し得る企業内福利厚生の置かれた厳しい環境を考慮すると、勤労者自身の自助努力が、今後、より重要になるものと考えられる。このような中、勤労者自身が自助努力の必要性を認識することが重要であり、そのために様々なリスクを含めて将来の生活設計について考える機会を提供することが求められる。また、自助努力に対する企業内福利厚生の支援、公的支援の内容について情報の共有化があって初めて、公的福祉、企業内福利厚生、勤労者の自助努力の効率的な組み合わせが可能となるであろう。 |
3.財形制度の動向と課題
(1) 財形制度の現状
| |
○ |
財形制度は昭和46年に制定された勤労者財産形成促進法に基づき、預金、有価証券等による貯蓄、住宅の取得等の勤労者の自助努力による財産形成を、国及び事業主が援助する制度である。 |
| ○ |
財形制度の中には、財形貯蓄制度、財形融資制度、財形給付金・基金制度、財形活用助成金制度、事務代行制度等があるが、これらの制度の活用状況についてはここ数年伸び悩んでいる。 |
(2) 財形制度の位置づけ
(企業内福利厚生における位置づけ・意義)
| |
○ |
財形制度については、活用状況の伸び悩みが続いていること、政府の政策が貯蓄から投資へという流れにあること等から、制度の位置づけ、意義を問う声もある。 |
| ○ |
しかしながら、以下の点を踏まえると、現役勤労者世代の貯蓄を下支えし、勤労者の生活の安定を図ること、即ち「計画的な財産形成の促進」という財形制度の目的は今日的にも意義があると考えられ、企業内福利厚生の中で、財形制度を国の政策として引き続き支援する必要性があるといえよう。 |
| (1) |
企業内福利厚生の中では、「老後生活のための資産形成」や「病気・事故など万一のための金銭的準備」等将来への備えに関する項目が勤労者自身にとって必要性の高いものとなっていること。 |
| (2) |
持家比率が一定水準まで上昇してきたにせよ、住宅取得に対する勤労者のニーズは根強いと考えられること。 |
| (3) |
財形制度の仕組みは、企業が自前であるいは個別に金融機関等と提携して実施する社内預金等の施策と比べ、企業倒産のリスク回避やコストの面でも優位性があり、従業員が安心して仕事をしていく上で有益な施策であること。 |
| (4) |
貯蓄政策の転換期となっている一方で、家計貯蓄率は平成13年に6.9%まで低下し、先進諸国の中でももはや貯蓄率が高いとはいえない状況になってきていること。 |
| (5) |
財形制度の長期的方向性に関して、「財形貯蓄・財形融資制度は必要ない(他分野での支援策も不要)」といった財形制度の意義を否定する向きはほとんどみられないこと(図表8)。 |
|
(確定拠出年金制度との関係)
| |
○ |
企業の従業員が加入する個人型の確定拠出年金と財形年金貯蓄は、従業員本人が拠出する点での重複もみられるところである。しかしながら、老後の資産形成に対しては勤労者のニーズが高いことから、老後の資産形成支援制度として、できる限り多くの企業が勤労者の自助努力を支援できるようにすることが重要であり、現状においては企業がその規模や勤労者のニーズを踏まえて選択できる選択肢はできる限り広い方が、実際に恩恵を受けられる勤労者も広がってくる。いいかえれば、財形年金貯蓄制度は、確定拠出年金制度等と異なる特徴を有する選択肢として併存することが望ましい。 |
(財形制度の公共政策的側面)
| |
○ |
財形制度は企業内福利厚生の一つであると同時に、公共政策的側面も持っており、その方向性の検討にあたっては、国が実施する他の貯蓄政策等との整合性についても留意する必要がある。 |
(3) 現行制度が直面する課題
(1) 調査結果からみた課題
| |
○ |
勤労者については、経済環境等の構造的な要因によって財形制度の利用が低迷している面もあるものの、勤め先の制度の有無や勤労者の制度に対する認知不足が利用低迷に少なからず影響を与えていると考えられる(図表9)。一方、企業については、自助努力支援の重要性や勤労者ニーズに対する認識不足、事務への負担感等が制度普及の障害となっていると考えられる(図表10)。 |
| ○ |
勤労者が財形貯蓄制度を利用している理由をみると、「給与天引きにより簡単に貯蓄できるから」が87.3%と最も高く、手軽に貯蓄することによって安心につながるというのが、財形制度の支持につながっているようである(図表11)。 |
(2) 環境変化への対応
a.労働市場・就業構造の変化への対応の遅れ
(失業や転職への対応)
| |
○ |
失業や転職への対応として、転職継続制度等の認知度を上げることが急務となっている。 |
| ○ |
現在の転職継続制度は、退職後1年以内に継続手続きを行う必要があり、再就職までの期間が1年を超えた場合には継続できない仕組みとなっているが、雇用情勢が厳しく、再就職までの期間が長くなってきている中、この期間の限定が、財形制度継続を阻害している恐れもある。 |
(非正社員の増加への対応)
| |
○ |
一般財形貯蓄では3年以上、財形年金貯蓄及び財形住宅貯蓄では5年以上にわたる積立てが加入要件となっていることが、有期契約の非正社員の加入を難しくしている恐れもある。 |
| ○ |
非正社員は正社員に比べて流動性が高いことから、財形制度のポータビリティを強化することも一層重要となってくるものと思われる。 |
b.金融の自由化等への対応の遅れ
| |
○ |
金融の自由化が進展する一方で、財形年金貯蓄及び財形住宅貯蓄は金融機関の経営破綻等の場合にのみ預替えが認められず、金融機関の経営破綻等以外でも預替えが認められている一般財形貯蓄については加入後3年以上経過しないと預替えが認められないという制約がある。 |
| ○ |
金融の自由化に伴い、金融商品の選択肢が拡大する中で、これまで財形貯蓄制度において認められていなかったハイリスク・ハイリターン型の投資商品を選択肢に加えていくことについての検討が必要である。 |
| ○ |
しかしながら、計画的な財産形成という目的を踏まえると、安定的に資産形成をしていくことこそが重要であり、リスクの大きな金融商品まで選択肢として加える必要が果たしてあるのか等の意見もあり、財形制度で金融商品の選択肢を拡大すべきかどうかという点については、意見が大きく分かれている。 |
c.企業の組織再編や人事システムの変化への対応の遅れ
| |
○ |
財形制度の事務について、外部化、共同化を一層推進するための事務代行制度の拡充等により、企業の負担を軽減するとともに、組織再編で継続が困難となった勤労者の制度の受け皿を整備していくことが求められる。 |
d.政策金融の見直し
| |
○ |
財形直接融資を運営している住宅金融公庫の今後の動向について留意する必要がある。 |
(3) 制度に内在する課題
(中小企業への普及の停滞)
| |
○ |
財形貯蓄制度のある企業の割合は、規模が小さくなるほど低くなっている(図表12)。中小企業の勤労者は大企業に比べて、一般に経済的リスクが高く、自助努力支援がより重要であるにもかかわらず、中小企業への普及が引き続き停滞している現状に対しては更なる対策が必要といえる。 |
(その他の課題)
| |
○ |
財形給付金制度については制度のメリットが十分に認知されていないことが、財形基金制度については法人を設立する手法が煩雑であることが、普及の停滞の理由になっていると考えられる。 |
| ○ |
財形活用助成金制度や中小企業財形共同化支援事業助成金制度等については、利用状況を踏まえて見直すべきとの指摘もあった。 |
(4) 諸外国の動向及び我が国における新たな政策課題
(1) 諸外国の動向
| |
○ |
欧米や韓国などでは、従業員の経営参加等の観点から、勤労者の資本参加(自社株の購入等)や勤労者への企業利益分配を盛り込んだ資産形成施策を実施している。 |
(2) 我が国における新たな政策課題
(多様なニーズ等に対応し得る支援の内容の検討)
| |
○ |
雇用の流動化や経済・産業構造の変化といった勤労者の財産形成を巡る状況の変化や、勤労者及び事業主のニーズの多様化・変化等を考慮すれば、例えば「計画的」の要件を緩和し、税制上の優遇等の国の支援を受けて形成した財産を、能力開発・教育や、病気、失業等といった不安への対応等の、勤労者の生活の安定という財形制度の制度目的に合致する範囲内のより広範な目的にも使えるようにすることについても、検討すべきものと思われる。 |
(諸外国の動向を踏まえた制度改善の検討)
| |
○ |
我が国においても、業績・株価連動型の報酬制度への関心が高まっていると考えられることから、財形制度が企業内福利厚生の一環として事業主の協力を得て浸透を図っていくスキームであることに着目すれば、企業にとって様々なメリットを有する自社株等による勤労者の財産形成支援施策の導入を検討してはどうかとの意見があった。 |
| ○ |
しかしながら、財産形成の手段に自社株を組み込むことには危険も伴う。また、そもそも計画的な財産形成という財形制度の目的に、こうした制度がなじむかどうかについても議論を尽くす必要があろう。 |
(5) 時代の要請に適合した制度の構築等に向けて
(基本的な考え方)
| |
○ |
時代の要請に適合した財形制度を構築していくためには、次のような視点を持つことが重要と考えられる。
| (1) |
様々な場面で個人事情に応じた多様な選択をすることが求められるようになってきた現代における福利厚生の有り様として、財形商品の設定その他の場合に、一人一人の勤労者が多様な選択を行うことを可能とするよう留意すべきである。 |
| (2) |
国が運営する制度として維持するからには、常に、より多くの勤労者が財形制度のメリットを享受できるようにする方向で制度を整理すべきであろう。 |
| (3) |
財形制度が企業内福利厚生に係る制度であることから、企業の関与を基本としつつも、企業形態の変化や労働慣行の変化を受けて、できる限り無用な企業の負担を避けたり軽減する方向での検討が必要であろう。 |
| (4) |
企業内福利厚生については効率化や目的重点化の方向で変化してきており、今後も一定の変化をとげていくと考えられる。諸外国でも勤労者の財産形成を支援する制度について、様々な枠組みの変化が見られており、我が国の財形制度に関しても、新たな領域での勤労者施策の拡充をも視野に入れ、中長期的な検討を加える必要があろう。 |
|
(具体的な改善策)
| |
○ |
財形制度について現時点で考えられる様々な改善策について、以下に分類・整理を行った。これらの改善策の中には、必ずしも研究会委員の総意によるものではないものや、実現のためには多くのハードルが存在するものも含まれる。 |
| |
(1) |
一人一人の勤労者が多様な選択を行うことを可能とするための改善策 |
a.預替えの拡充
| |
○ |
金融の自由化等による金融商品の多様化及び勤労者のニーズの多様化への対応、及びペイオフ解禁等を踏まえたリスク分散の観点から、以下のような預替えの拡充等の措置が考えられる。ただし、これらの前提として、金融機関の事務コスト及びシステム開発コストや、非課税限度額管理を担保するための措置等について考慮する必要がある。
| イ. |
一般財形貯蓄の預替期間の短縮 |
| ロ. |
財形年金貯蓄及び財形住宅貯蓄への任意預替えの導入 |
| ハ. |
貯蓄残高の分割預替えの導入 |
| ニ. |
財形年金貯蓄及び財形住宅貯蓄の複数契約 |
| ホ. |
複数契約機関の指定の義務づけ |
|
b.投資商品の拡充等
| |
○ |
預替えの拡充等を行うことを念頭においた上で、財形貯蓄制度において、以下のような投資商品を拡充することが考えられる。ただし、リスクの大きな金融商品まで拡大するかどうかについては、慎重な検討が必要である。
| イ. |
対象となる投資信託の要件緩和 |
| ロ. |
対象となる有価証券の拡大 |
| ハ. |
投資信託の銀行等への拡大 |
|
| |
(2) |
より多くの勤労者が財形制度のメリットを享受できるようにするための改善策 |
| |
○ |
大企業に比べて中小企業への財形制度の普及が進んでいない状況を勘案すると、中小企業の普及促進を図ることが必要である。同時に、増加傾向にある非正規雇用に対する適用割合が低いこと等が課題となっていることから、これらについてもいくつかの対応措置が考えられる。 |
a.事務代行制度の拡充等
| |
イ. |
事務代行制度の普及 |
| ロ. |
事務代行団体の要件緩和 |
| ハ. |
事務代行団体の届出制 |
| ニ. |
事務代行団体の広域化等による活用促進 |
| ホ. |
事務代行の範囲の拡大 |
b.非正社員の増加への対応
| |
○ |
近年、非正社員が増加傾向にあるが、非正社員に対する財形制度の適用割合が低いこと等が課題となっている。この状況に対応するため、以下のような措置が考えられる。
| イ. |
非正社員の財形制度の普及啓発 |
| ロ. |
有期契約労働者や派遣労働者の財形制度の利用可能性の拡大 |
| ハ. |
事務代行団体を通じた直接加入 |
|
| |
(3) |
企業の関与を基本としつつ、企業形態の変化や労働慣行の変化を受けての制度の構築 |
a.雇用の流動化への対応
| |
○ |
現下の厳しい雇用情勢、雇用の流動化等に伴い、財形制度においても転職や長期失業への対応が求められており、転職継続制度について以下のような措置が考えられる。
| イ. |
転職継続制度の普及啓発・情報提供 |
| ロ. |
転職承継可能期間の延長(非課税管理上の問題や金融機関の事務コスト等にも配慮することが必要) |
| ハ. |
適格払出要件の拡充 |
| ニ. |
特例自己積立制度及び事務代行制度の拡充 |
| ホ. |
財形年金貯蓄の据置期間の延長
(非課税管理上の問題を解決することが必要) |
| ヘ. |
財形年金貯蓄及び財形住宅貯蓄の年齢制限の延長等
(非課税管理上の問題を解決することが必要) |
| ト. |
財形教育融資の拡充 |
|
b.事業主の負担の軽減(関与のあり方)
| |
○ |
事業主の負担の軽減のため、以下のような事業主の関与を要件としている制度の見直しが考えられるが、その見直しについて財形制度そのものの根幹に関わるものでもある。以下について今後十分な議論を尽くした上で結論を出す必要がある。
| イ. |
事業主による給与天引きの見直し
(財形制度の意義を損なわない方策があり得るのか検討が必要) |
| ロ. |
財形住宅融資における事業主の負担軽減措置等の要件の撤廃 |
| ハ. |
事業主の非課税管理の負担軽減
| ・ |
預入限度方式への変更 |
| ・ |
財形年金貯蓄と財形住宅貯蓄の統合 |
|
| ニ. |
財形給付金・基金制度の見直し |
| ホ. |
福利厚生会社への出資要件の見直し |
| ヘ. |
企業等のIT化への更なる対応 |
|
(4) 新たな領域での勤労者施策の拡充
| |
○ |
諸外国の動向等を踏まえ、財形制度の中長期的な課題として、例えば以下のようなことが考えられる。
| イ. |
従業員持株制度やストック・オプション等の業績・株価連動型の利益分配制度について、財形給付金・基金制度への導入等の可能性の検討。 |
| ロ. |
在宅就業者等の多様な働き方が増加していることを踏まえ、一定の雇用契約に基づかない勤労者であっても財形制度の対象とすることの検討。 |
| ハ. |
財産形成の範囲を貯蓄・持家取得以外の分野に拡大することにより、勤労者の生活の安定という財形制度の制度目的に合致する範囲内での能力開発・教育や病気、失業等への対応を強化することの検討。 |
|
(5) 現行制度に関するその他の改善策
| |
a. |
現行の財形制度に関して、以下のような点についてもこれまで要望がなされており、アンケートでもニーズがみられた。なお、利子等非課税制度そのものの拡充については、これまで縮小を図ってきた税についての大きな方針に照らし、その可能性等を慎重に見極める必要がある。 |
| |
イ. |
非課税限度額の拡大 |
| ロ. |
非課税限度額超過分の取扱い |
| |
b. |
制度簡素化の観点から以下のことも忘れてはならない。 |
| |
イ. |
財形融資制度の見直し |
| ロ. |
財形活用助成金の見直し |
雇用の流動化、自己責任時代における
企業内福利厚生のあり方に関する研究会委員名簿
【委員】
| |
| 藤田 伍一 |
一橋大学 大学院 社会学研究科 教授 <座長> |
| 奥村 直嗣 |
(株)三菱電機ビジネスシステム 常務取締役経営企画室長 |
| 小澤 敏 |
三井化学(株) 労制部 課長 |
| 斉藤 美彦 |
獨協大学 経済学部 教授 |
| 園田 洋一 |
群馬松嶺福祉短期大学 人間福祉学科 助教授 |
| 中山 良夫 |
全日本電機・電子・情報関連産業労働組合連合会(電機連合) 書記次長 |
| 西久保 浩二 |
(財)生命保険文化センター 生活研究部 主任研究員 |
| 山口 登守 |
日本労働組合総連合会(連合) 総合労働局 労働条件局長 |
(座長以下、五十音順、敬称略)
|
図表1 家計貯蓄率の国際比較
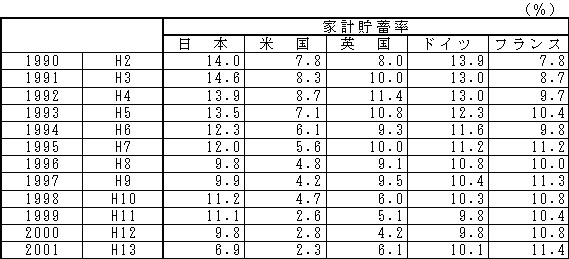
| 資料: |
内閣府「国民経済計算年報」、OECD 「Economic Outlook」(Volume2002/2) |
| 注: |
各国の算出方法は統計上の不統合があるため統一されていない。 |
図表2 現在の住居と今後の持家取得意向<個人調査>
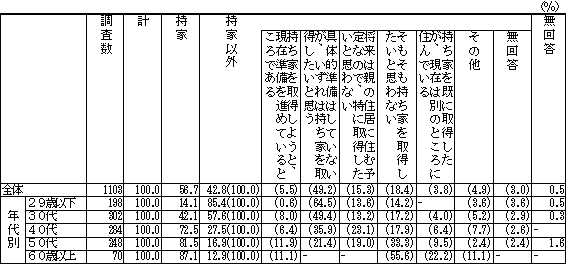
| 資料: |
ニッセイ基礎研究所「企業内福利厚生や勤労者財産形成促進制度に関するアンケート調査」
(厚生労働省委託) |
図表3 従業員1人当たりの福利厚生費(月額)の推移
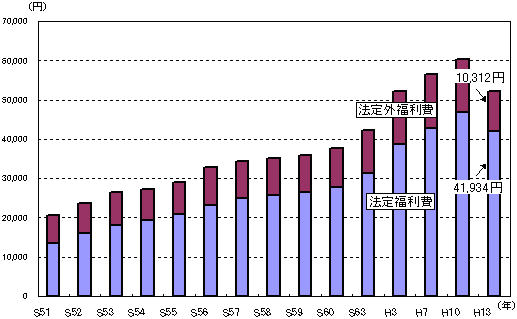
| 資料: |
旧労働省「賃金労働時間制度等総合調査」、厚生労働省「就労条件総合調査」 |
| 注: |
法定福利費は社会保険料の事業主負担分等。法定外福利費は、住居、医療保健、食事、文化・体育・娯楽、私的保健制度への拠出金、労災付加給付、慶弔見舞等、財形貯蓄奨励金、給付金及び基金への拠出金等に係る費用。以下、本調査については同様。 |
図表4 企業内福利厚生で現在重視している目的<企業調査>
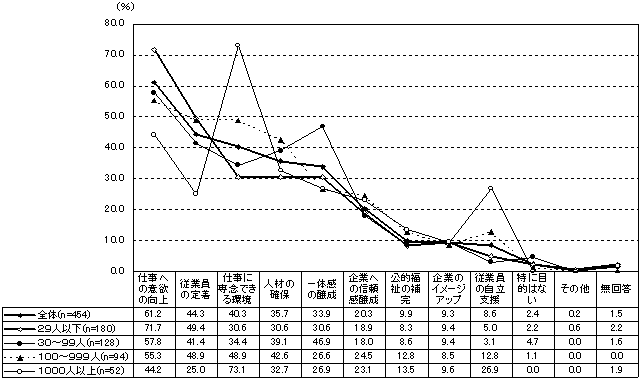
| 資料: |
ニッセイ基礎研究所「企業内福利厚生や勤労者財産形成促進制度に関するアンケート調査」
(厚生労働省委託) |
| 注: |
福利厚生を一つでも実施している企業について。複数回答(三つまで)。 |
図表5 企業内福利厚生で今後重視する目的<企業調査>
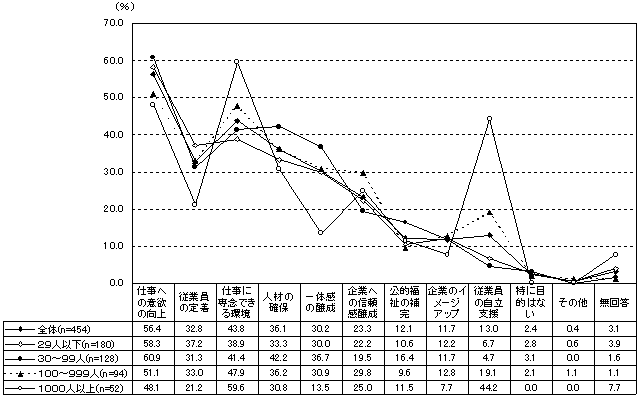
| 資料: |
ニッセイ基礎研究所「企業内福利厚生や勤労者財産形成促進制度に関するアンケート調査」
(厚生労働省委託) |
| 注: |
福利厚生を一つでも実施している企業について。複数回答(三つまで)。 |
図表6 福利厚生に関する意見への考え<個人調査>
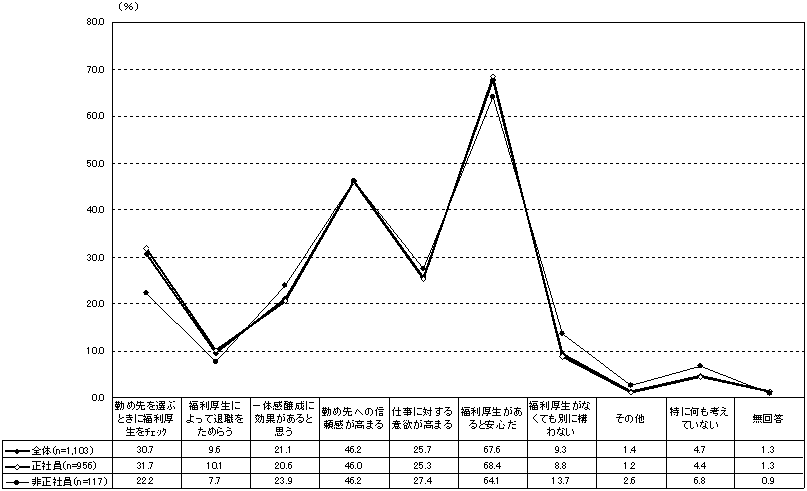
| 資料: |
ニッセイ基礎研究所「企業内福利厚生や勤労者財産形成促進制度に関するアンケート調査」
(厚生労働省委託) |
図表7 「福利厚生を可能な限り抑制し、その分を賃金の原資に充てていきたい/充ててほしい」への意見<企業調査/個人調査>
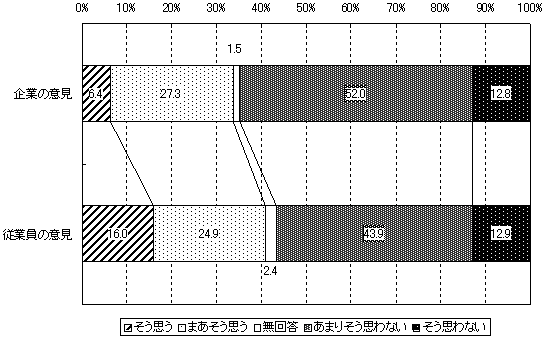
| 資料: |
ニッセイ基礎研究所「企業内福利厚生や勤労者財産形成促進制度に関するアンケート調査」
(厚生労働省委託) |
| 注: |
企業の意見は、一つでも福利厚生を実施している企業について。 |
図表8 財形貯蓄制度の長期的方向性<企業調査/個人調査>
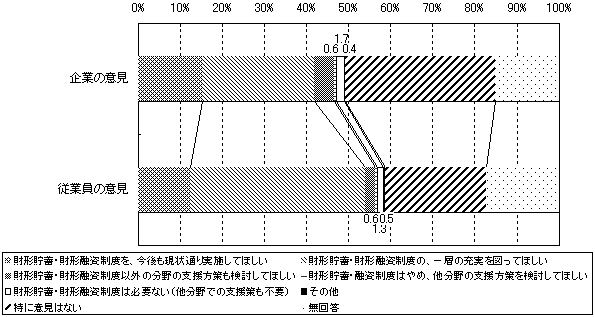
| 資料: |
ニッセイ基礎研究所「企業内福利厚生や勤労者財産形成促進制度に関するアンケート調査」
(厚生労働省委託) |
図表9 財形貯蓄制度を利用したことがない理由<個人調査>
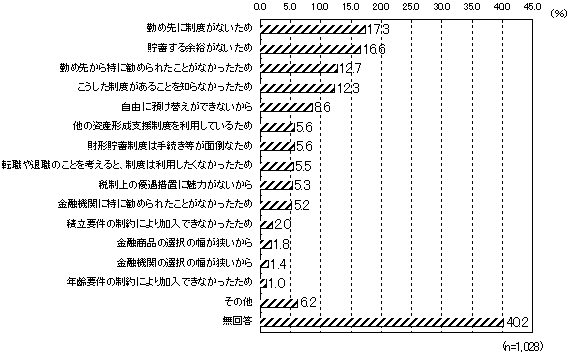
| 資料: |
ニッセイ基礎研究所「企業内福利厚生や勤労者財産形成促進制度に関するアンケート調査」
(厚生労働省委託) |
| 注: |
財形貯蓄制度のうち、いずれかの制度を利用したことがない個人について。複数回答。 |
図表10 財形貯蓄制度を導入していない理由<企業調査>
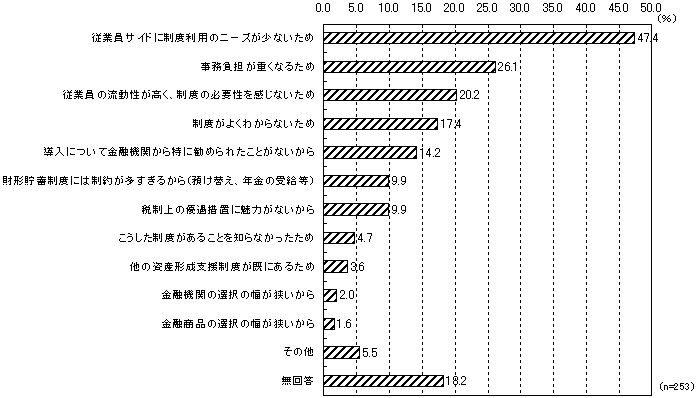
| 資料: |
ニッセイ基礎研究所「企業内福利厚生や勤労者財産形成促進制度に関するアンケート調査」
(厚生労働省委託) |
| 注: |
財形貯蓄制度のうち、いずれかの制度がない企業について。複数回答。 |
図表11 財形貯蓄制度の利用理由<個人調査>
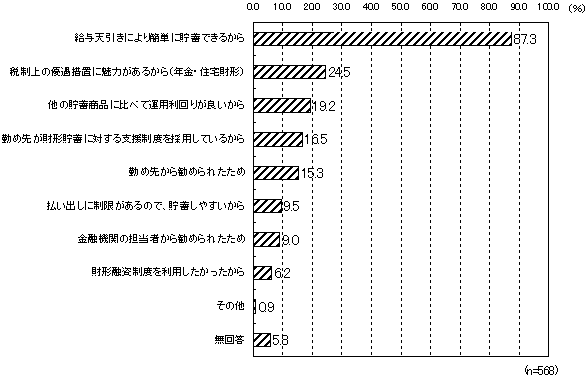
| 資料: |
ニッセイ基礎研究所「企業内福利厚生や勤労者財産形成促進制度に関するアンケート調査」
(厚生労働省委託) |
| 注: |
財形貯蓄制度のうち、いずれかの制度を利用したことがある個人について。複数回答。 |
図表12 財形貯蓄制度の実施状況<企業調査>
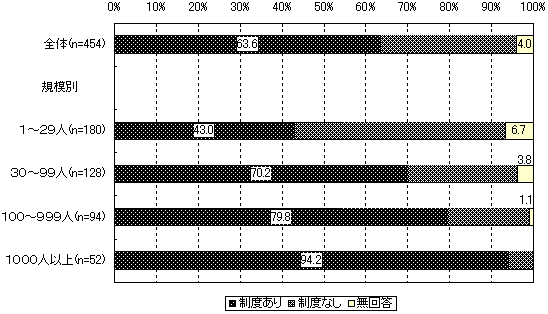
| 資料: |
ニッセイ基礎研究所「企業内福利厚生や勤労者財産形成促進制度に関するアンケート調査」
(厚生労働省委託) |
トップへ
戻る