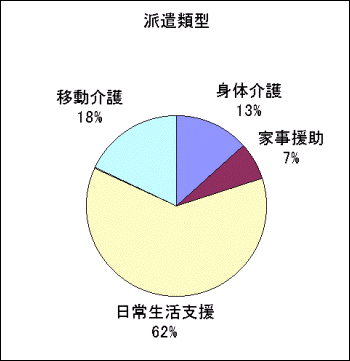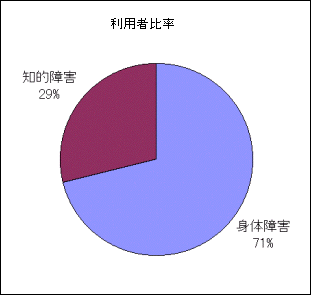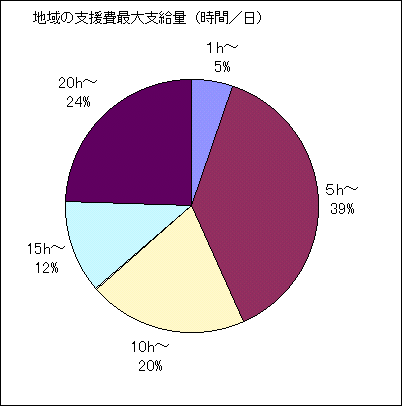| 支援費のサービス提供量の合計 | |||||||||
|
|||||||||
| ※平成15年度の国のホームヘルプ補助金予算:280億 |
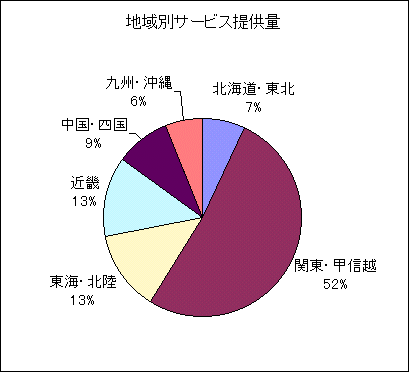
左の図は地域別のサービス提供量(事業収入ベース)をグラフにしたものである。
関東・甲信越地区が最も多く、ついで「東海・北陸」、「近畿」、「中国・四国」、「北海道・東北」、「九州・沖縄」の順になっている。
これは、支援費にさきがけて2000年頃から東京都、埼玉県、愛知県、大阪府、兵庫県などの地域では、ホームヘルプ事業の受託を自立生活センターが受けており、派遣規模の大きいセンターが存在することとがその要因である。また、比較的制度の良かった東京都、大阪府などに障害者が集中して住んでいることもあげられる。
支援費制度が導入され各地域の自立生活センターが事業に参入することができたので、今後は、「中国・四国」、「北海道・東北」、「九州・沖縄」の団体のサービス提供量も伸び、地方の比率が高まっていくと考えられる。