戻る
コーデックスにおける「健康食品」の栄養表示について(目次)
コーデックスとは
コーデックスにおける採択手順
コーデックスの部会
食品表示部会
栄養特殊用途食品部会
食品表示部会と栄養特殊用途食品部会の関係
これまでに策定された健康食品に関系する規格等
食品表示部会(CCFL)における検討状況
強調表示(Claim)とは
健康栄養強調表示の使用に関するガイドライン案
栄養特殊食品部会(CCNFSDU)における検討内容
ビタミンミネラル補助食品ガイドライン案
コーデックスにおける「健康食品」の表示基準について
平成15年5月9日
コーデックスとは
| ・ |
FAO/WHO合同食品規格委員会
(Joint FAO/WHO Codex Alimentarius Commission) |
| ・ |
1962年設立 |
| ・ |
日本は1966年に加盟 |
| ・ |
168か国加盟(2003年1月現在) |
| ・ |
29の下部組織(部会等)を持つ
| − |
世界規模全般課題規格部会として9部会 |
| − |
世界規模食品規格部会として11部会 |
| − |
特別部会として3部会 |
| − |
地域調整委員会として6委員会 |
|
| ・ |
国際的な食品規格を策定することを目的としている。 |
| ・ |
また、策定されたコーデックス規格は、加盟各国の法制定に強制力はないが、食品貿易における紛争解決のための世界貿易機関(WTO)での裁定における判断基準とされている。 |
コーデックスにおける採択手順
| |
コーデックス規格作成の必要性が論議された後、CACの総会で新しいコーデックス規格を作る決議が採択されるとステップ1となり、担当の部会を決めて作業が委嘱される。最初の規格案は通常、提案国と関心国で構成される作業グループで作成される。この過程がステップ2。 |
| |
規格案を加盟各国と関連国際機関に送ってコメントを求め、そのコメントをまとめて加盟各国などに送付するのがステップ3。規格案をコメントに基づいて事務局が一部修正することもある。 |
| |
通常は最初の部会会議が開催される。関係国などが集まり、論議の上修正案についてコンセンサスが得られれば、ステップ5に進める決議が採択される。もし、論議が紛糾し、なお検討が必要と判断されれば、ステップ3に戻し、再びコメントを求めることとなる。 |
| |
ステップ4で採択された規格案が事務局を通じてCAC総会または執行委員会に提出される。CAC総会は2年ごとに開かれるので、毎年開催される執行委員会が代行することもある。論議も行われるが、原則としてステップ5の段階で総会の承認がいる。 |
| |
このステップは基本的にステップ3と同じ。ステップ5までで作成された規格案を加盟国などに送付し、コメントを求める。つまり、コーデックス規格を作るにはステップ5までとステップ8までの2回のサイクルがあり、慎重に論議される。 |
| |
ステップ4と同じく、通常は部会の会議が行われ、規格案を論議する。コンセンサスが得られれば、CAC総会に対してステップ8に採択する勧告を部会として行う決議をする。また、論議が紛糾すればステップ6に差し戻し、再びコメントを求めることとなる。 |
| |
部会の作業はステップ8への勧告を採択した段階で終了し、ステップ8に採択するかどうかはCAC総会で行われる。総会までに事務局から各国などにコメントの提出が要請され、総会でも論議が行われる。コンセンサスまたは投票により規格案が採択されればステップ8となり、コーデックス規格として所定のコードが与えられ、コーデックス・アリメンタリウスといわれる規格集に収録される。 |
コーデックスの部会
食品表示部会
| ・ |
食品全般に適用される表示の基準について検討している部会であり、「健康食品」に関しては、栄養強調表示、健康強調表示等が議題として検討されているところである。 |
| ・ |
毎年開催されており、今年(4月開催)で31回目となる。 |
栄養・特殊用途食品部会
| ・ |
食品の栄養に関する全般的な規格の検討及び特定の栄養上の諸問題を検討している部会であり、「健康食品」に関しては、ビタミン・ミネラル補助食品のガイドライン案等を検討している。 |
| ・ |
近年では毎年開催されるようになり、昨年(11月)までに24回開催されている。 |
健康食品に係る食品表示部会と栄養・
特殊用途食品部会の関係
| ・ |
食品表示部会では、健康強調表示等の「定義」と「適用条件」を決定することを目的としている。 |
| ・ |
栄養・特殊用途食品部会では、表示内容の科学的根拠の確立を目的としている。 |
これまでに策定された健康食品に関係する規格等
| ・ |
包装食品表示一般規格(1985年制定、修正1991年)
| − |
包装食品の表示に関する一般原則(虚偽記載の禁止等)、強制表示事項、任意表示事項を規定 |
|
| ・ |
強調表示に関する一般ガイドライン(1979年制定、修正1991年)
| − |
強調表示する際の条件(「天然」といった用語の使用、栄養表示に関する強調など)、禁止事項(実証しえない強調表示など)等を規定 |
|
| ・ |
栄養表示に関するガイドライン(1985年制定、修正1993年)
| − |
栄養表示の原則(栄養素の明記など)、栄養強調表示の定義、栄養素を明記しなければならない場合(栄養強調表示をする食品には強制)、栄養素基準値(NRV)等を規定 |
|
| ・ |
栄養強調表示の使用に関するガイドライン(1997年制定)
| − |
栄養強調として栄養成分強調、栄養比較強調、栄養機能強調を規定。現在、このガイドラインに健康強調表示を加えた、「健康・栄養強調表示の使用のガイドライン」として修正案を検討中。 |
| (注) |
この他に、特定の健康状態や疾患により要求される特別食として製造された食品に関する「特殊用途食品の表示規格」がある。 |
|
食品表示部会(CCFL)
における検討状況
Codex Committee on Food Labeling
強調表示(Claim)とは
| ・ |
「強調表示(Claim)」とは、食品が、その起源、栄養的特性、性質、生産、加工処理、組成あるいはその他あらゆる品質に関して特別な特徴を持つことを述べたり、示唆あるいは暗示する全ての表示のこと
(包装食品表示一般規格及び強調表示に関する一般ガイドラインに規定されている) |
健康・栄養強調表示の使用に関するガイドライン案
( Proposed Draft Guidelines for Use of Health and Nutrition Claims )
【ステップ8提案】
| 1 |
位置づけ
| |
− |
栄養強調表示の使用に関するガイドラインを改正して、栄養強調表示及び健康強調表示に関して必要な事項を規定するもの。 |
|
| 2 |
前文(健康強調表示関係部分)
| |
− |
健康強調表示は、適用可能な場合、国の栄養政策、健康政策と一致し、その政策を支持するものでなければならない。 |
| − |
健康強調表示は、適切で十分な科学的根拠の裏付けがあり、消費者が健康な食生活を選択するための誤解のない、正しい情報を提供し、また、消費者に対する科学的な教育の支援がなければならない。 |
| − |
健康強調表示が消費者の食行動や食事パターンに与える影響についてモニターしなければならない。 |
| − |
「強調表示に関する一般ガイドライン」で規定されている「(疾病の)予防表示」はできない。 |
|
−3 強調表示の定義−
| ・ |
健康強調表示(Health Claims)とは、食品あるいはその成分と健康の関わりを述べ、示唆し、暗示するすべての表現のことであり、次のものが含まれる。
| |
栄養素機能強調表示(Nutrient Function Claims)
(栄養素以外の)その他の機能強調表示(Other Function Claims)
疾病リスク低減強調表示(Reduction of Disease Risk Claims) |
| (参考) |
「栄養強調表示(Nutrition Claims)」とは、ビタミン及びミネラルの含有量のみならず、熱量、たんぱく質、脂肪及び炭水化物の含有量を含め、食品が特別な栄養上の特性を持っていることを述べ、示唆し、あるいは暗示するすべての表現を意味し、以下の2つがある。
|
|
|
健康・栄養強調表示の使用に関するガイドライン案
が対象とする強調表示
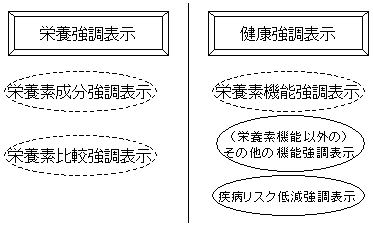
| 注 |
: |
点線部分は、「栄養強調表示の使用に関するガイドライン」に規定があるもの。 |
|
−4 健康強調表示の内容−
| (1) |
栄養素機能強調表示(Nutrient Function Claims)
| |
身体の成長、発達、正常な機能における栄養素の生理学的な役割の表示
| (例: |
「栄養素Aには身体における健康の維持と通常の正常及び発達の促進での、生理学的役割がある。食品Xは、栄養素Aの供給源」 ) |
|
|
| (2) |
(栄養素機能以外の)その他の機能強調表示(Other Function Claims)
| |
食生活において、食品あるいはその成分の摂取が、通常の機能あるいは身体の生物活性に関する、その品もしくはその構成物を摂取することによる特定の有用な効果に関する表示である。このような表示は、健康に対する積極的な貢献、機能の改善、健康の保持に関連している。
| (例: |
「物質Aは、健康に係わる生理学的機能もしくは生物活性を改善、変更における効果がある。食品Yには、○○グラムの物質Aを含む」 ) |
|
|
| (3) |
疾病リスク低減強調表示(Reduction of Disease Risk Claims)
| − |
食生活において、食品あるいはその成分の摂取と、疾病及び健康に関する状態の進行(発症)に関するリスクの低減との関係を示す表示である。 |
| − |
リスクの低減とは、疾病または健康状態に対する主なリスクを有意に改善することを意味する。 |
| − |
疾病には複数のリスク要因があり、それらのうちの一つを改善することでは必ずしも効果があるとは限らないため、リスク低減表示に際しては、適切な言葉を用いるとともに、他のリスク要因にも言及した上で、確実に消費者が予防表示と誤認しないようにしなければならない。
| (例: |
「栄養素A又は物質Aの含有量の低い健康的な食事は疾病のリスクを低減するかもしれない。食品Xは、栄養素A又は物質Aが少ない。」 ) |
|
|
−5 健康強調表示が認められる条件−
| (1) |
健康強調表示は科学的知見に基づくものでなければならない。健康強調表示には以下の2つが必要である。
| 1) |
広く認知されている食事と健康の関わりにおける当該栄養素の生理学的役割に関する情報。 |
| 2) |
上記栄養素の生理学的役割に係わる、当該食品の成分に関する情報。 |
|
| (2) |
食品が販売される国の当局が容認できるものでなければならない。 |
| (3) |
強調表示されている効果は、健康的な食事における合理的な量の食品又は食品成分の摂取により得られるべきである。 |
| (4) |
栄養素機能強調表示については、コーデックスの栄養表示ガイドラインもしくは国で公式に認められたNRV(Nutrient Reference Value)で規定されている必須栄養素を対象とすべきである。 |
−5 健康強調表示を行う際の表示事項−
| (1) |
強調表示された食品の過度の摂取を促進又は容認し、適切な食事習慣をおとしめるような健康強調を行ってはならない。 |
| (2) |
食品成分を強調する場合、強調の根拠となる食品成分の量を表すにはコーデックスに検証された(有効な)方法(重量)で行われなければならない。 |
| (3) |
強調する栄養素又はその食品に含まれる成分の量。 |
| (4) |
(適切であれば)対象とするグループ。 |
| (5) |
強調した有効性を得る為の使用方法、その他の生活要因及びその他の食事源。 |
| (6) |
虚弱な人の場合の使用方法と、強調表示された食品の摂取を忌避する必要がある人へのアドバイス。 |
| (7) |
(必要であれば)食品もしくは成分の最大摂取量。 |
| (8) |
強調表示された食品の食事に対する導入方法。 |
| (9) |
健康的な食事の維持の重要性。 |
栄養・特殊用途食品部会(CCNFSDU)に
おける検討内容
Codex Committee on Nutrition and Foods for
Special Dietary Uses
ビタミン・ミネラル補助食品ガイドライン案
(Proposed Draft Guidelines for Vitamin and Mineral Food Supplements)
【ステップ3】
| − |
前文
| ・ |
バランスのとれた食事を摂取をできる通常の人は、必要なすべての栄養素を普通の食事から摂取することが可能である。食品には健康を促進する多くの成分が含まれているため、ビタミン・ミネラル補助食品の摂取を考える前に、バランスの良い食事が奨励されるべきである。 |
| ・ |
ビタミン・ミネラル補助食品は、通常の食事からの摂取が不十分又は消費者自身が必要と考える場合に、日常の食事の補充として機能するものである。 |
|
| − |
適用
| ・ |
日常の食事の補助に用いるビタミン・ミネラルの補助食品に適用。 |
| ・ |
同補助食品が法的に食品と判断される場合に適用。(同補助食品が医薬品とするか食品とするかは各国の法判断に委ねる。) |
| ・ |
「特殊用途食品の表示規格」が対象とする食品には適用されない。 |
|
| − |
定義
| ・ |
このガイドラインで対象とするビタミン・ミネラル補助食品が含むビタミン・ミネラルとは、栄養学的な意味でのビタミン・ミネラルである。 |
| ・ |
ビタミン・ミネラル補助食品は、通常の食品の形態ではなく、カプセル、錠剤、粉末、液状等、それら単独若しくは複合の濃縮されたものであって、大量のエネルギーを摂取するものでないこと。 |
| ・ |
[ビタミン・ミネラル補助食品は、通常の食事からの摂取が不十分あるいは消費者が自身の食事には補充が必要と考える場合に、日常の食事を補助するものである。※]
| |
注 |
: |
※が附された部分は、当該ステップにおいて合意に至っていない部分である。(以下同じ。) |
|
|
| − |
成分規格
| ・ |
表示基準の対象とするビタミン・ミネラルの選択
| (1) |
ビタミン・ミネラル補助食品は、人に対する栄養価が科学的に証明され、FAO/WHOにより認知された、ビタミン・ビタミン前駆体、ミネラルを含むべきである。 |
| (2) |
適格なビタミン・ミネラル源の選択は、安全性や生物学的利用能の基準を基にすべきである。 |
| (3) |
[補助食品としての個々のビタミン・ミネラル使用は、各国独自の供給状況を考慮し、健康保護、安全性を理由にすべきである。※] |
| (4) |
ビタミン・ミネラル補助食品は、(1)の基準を満たしたすべてのビタミン・ミネラルか、単独のビタミン・ミネラル、適切な組み合わせのビタミン・ミネラルを含むことができる。 |
|
| ・ |
ビタミン及びミネラルの含有量
| − |
各ビタミン・ミネラルの製造者による推奨1日摂取量の最小量は、FAO/WHOによる栄養所要量の[15〜33%※]。 |
| − |
[各ビタミン・ミネラルの製造者による推奨1日摂取量の最大量は、FAO/WHOによる栄養所要量の100%を超えてはならない。 ※] |
| − |
[各ビタミン・ミネラルの製造者による推奨1日摂取量の最大量は、以下の基準を考慮して決定する
| >> |
通常受け入れられている科学的なデータに基づくリスク評価に基づき、必要に応じ、異なる消費者層による感受性の違いを考慮して決定されたビタミン・ミネラルの安全上限値 |
| >> |
食事から摂取するビタミン・ミネラルの1日摂取量 |
推奨1日摂取量の最大値を決めるに際し、当該国民の栄養所要量を考慮される必要がある。※ ] |
| − |
栄養所要量と副作用発現レベルの間の安全域の小さいビタミン・ミネラルについては、国別に異なる最大限度値を定めることができる |
|
|
| − |
表示すべき事項(表示方法は、「包装食品表示一般規格」及び「強調表示に関する一般ガイドライン」に沿ったものである必要がある。)
| ・ |
[製品名は「ビタミン・ミネラル補助食品」もしくは「食事を補充するビタミン・ミネラル補助食品」と表示した上で、栄養素名も表示。※] |
| ・ |
[含有量は、推奨1日製品摂取量に対する割合及び必要に応じ、摂取単位量当たりの重要で表示。※] |
| ・ |
[栄養所要量に関する情報、例えば、「栄養表示に関するガイドライン」における所要量に対する割合を表示※] |
| ・ |
推奨される使用方法(用法、用量、特定の摂取条件等)についての表示 |
| ・ |
警告表示(当該製品にその毒性レベルからみて、相当量の栄養成分が含まれている場合) |
| ・ |
[長期間、食事の代替として使用することはできない旨の表示※] |
| ・ |
[栄養士、栄養管理者あるいは医師の助言の下に摂取すべきとの表示※] |
|
トップへ
戻る