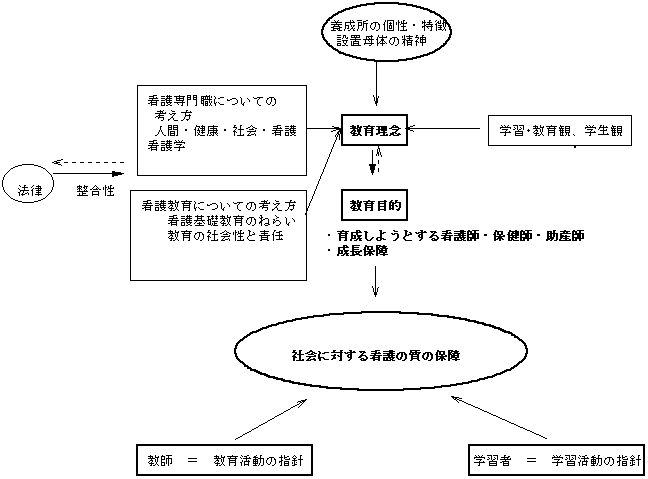
図3.教育理念・教育目的の設定に含むべき条件
| 1. | この指針は、看護師等養成所の自己点検・自己評価のための指針として作成したものである。 保健師養成所、助産師養成所、看護師養成所、准看護師養成所ごとに、個々の状況や背景があり、本指針がその全てを網羅できるものではないので、各養成所においては、自養成所の場合として読み替えて活用する必要がある。 |
| 2. | 本「指針」は、「自己点検・自己評価カテゴリー、下位項目」、「自己点検・自己評価項目の基準」、自己点検・自己評価のために必要とする「資料(データ)」および、「基準」を踏まえて、「点検」する視点をあげ、構成している。 |
| 3. | 「基準」は、各養成所において、自己点検・自己評価についての知識と方法を理解しながら進めていけるように、各自己点検・自己評価のカテゴリー、その下位項目について、どのように見極めていけばよいのか、基本的な説明を含めて記述している。 |
| 4. | 本「指針」の中で示している「資料(データ)」は、「基準」の内容を点検・評価する上での目安として示している。その具体的内容(どのようなもの)や量(どの程度)については、各養成所が、自ら考え、選択していくものである。 |
| 5. | 「点検」は、「基準」と「資料(データ)」から、自己点検・自己評価のカテゴリーがどのような状況になっているのかを明確に捉えられるようにその視点として設定した。 |
| 6. | C.<点検>(評価内容)一覧では、各カテゴリーで設定した「点検」を一覧できるようにした。また、自養成所がどのような現状にあるのかを測定できるように、尺度を設定してある。本「指針」においては、この尺度のみを独立して使用するのではなく、「基準」、「資料(データ)」と連動して活用することに意味がある。 |
| 7. | この指針は各養成所が活用して、自ら改善していくための指針であり、養成所間の相対的レベルを測るものではない。3で述べたように、各養成所が、常に評価結果に基づいて、改善の方向を見出し、その方向に向かって行くための指針である。 |
| 8. | C.<点検>(評価内容)一覧を用いて行った評価が高くなることは、「基準」の内容が示すように、各養成所が自らの設定した教育理念・教育目的達成に向けて、常に自己点検・自己評価の機能を働かせながら、看護師等養成所としての自養成所の水準を維持・発展するように努力していることを示すものである。 |
| 9. | 評価のカテゴリーは9領域あり、「点検」は66項目を設定しているが、一度に全ての領域と項目を改善できるとは限らない。自己点検・自己評価が継続的に、計画的に実施できるようになって行くことに意味があるので、実際に取り組める領域や項目から始めることが望ましい。 また、全てのカテゴリーを自己点検・自己評価しなければならないというものではない。1で述べたように、各養成所の状況に応じて、意図的にカテゴリーを選択して、自己点検・自己評価を行うことである。 |
| * | 本指針において、「教師」は、「学術・技芸を教授する人」(広辞苑1998)として、教育を行う個人を表している場合に用いている。 一方、「教員」は、「学校に勤務して教育を行う人」(同上)として、組織員としての意味や、勤務等に関連する内容を表す場合に用いている。 |
自己点検・自己評価カテゴリーおよび下位項目一覧
I
|
|
III
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
II
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IV
|
|
V
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VI
|
|
VIII
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VII
|
|
IX
|
|
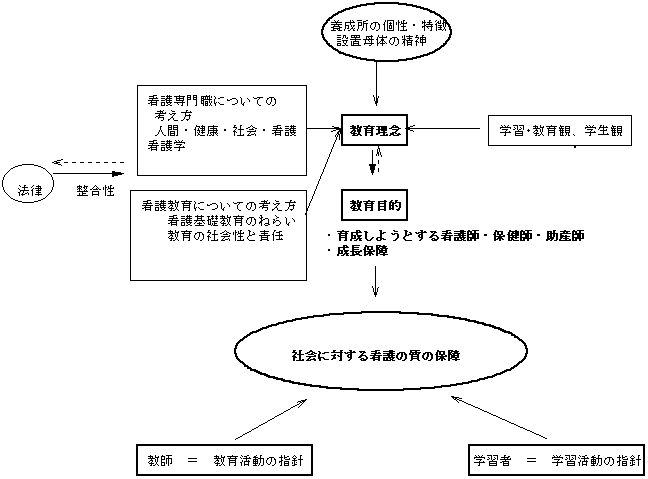
図3.教育理念・教育目的の設定に含むべき条件
<点検>
|
||||||||||||||
|
教育理念・教育目的との一貫性 教育目標は、教育理念・目的を達成するために必要な教育内容について、目標として表現し、設定したものである。教育内容は、教育的に意図した学習経験のまとまりごとに区分され、それが科目−単元−一回ごとの授業の内容として組織化されるため、教育目標もそれに対応し、(分野別目標−領域別目標−)科目目標−単元目標−授業単位の目標へと展開していく階層的な構造を成している。 したがって、教育目標は、設定した教育内容を網羅し、目標階層の最上位に位置する。すなわち、すべての科目の授業を通して最終的に修得してほしい能力を、具体的に示しているものであり、教育活動の最終的なゴールを表すものとして明示される必要がある。以上より教育目標についてはまず、教育理念・教育目的との一貫性があることが必要である。 |
|
||||||||||||
|
目標内容の側面と到達レベルの側面 教育目標の設定にあたっては、教育理念・目的の実現のために、どのような内容をどのレベルまで到達させるのか、目標内容の側面と、達成レベルの側面からの検討が必要である。目標内容については、看護実践者としての能力の育成と専門職としての生涯学習の視点から自立した学習者としての能力の育成、つまり成長保障に関する検討を意味する。具体的には、獲得しなければならない専門的な看護の知識・技術、看護専門職として多種の職種の人々とチームを組み、自ら意思決定し行動するために必要な倫理性、自律性、責任性、協調性、柔軟性、生涯教育の原動力となる探求性、グローバル化が進む社会に対応するための国際性などの側面から検討する必要がある。これらの教育内容は看護専門職に求められるものであり、看護師等養成所においてもこれらの内容が教育できるような体制を整えることや、継続教育との関連からも検討する必要がある。 到達レベルについては、達成目標、向上目標、体験目標の区別を明確にして目標内容と対応して表示する必要がある。 |
|||||||||||||
|
設定意図とその明確性 教育目標は、学生にとっては、学習活動の明確な方向とその達成を評価する基準として欠くことができないものであり、教師にとっては、教育活動の指針となる。そのため、目標の羅列に終わらず、教育目標について理解が得やすいように設定意図を明確に示し、各養成所の独自性を明らかにすることが重要である。教育目標の表示に当たっては、社会の人々や学生が理解できるように表現し、期待する具体的行動や思考の特徴がわかりやすく、かつ、実現可能なものとして示されている必要がある。 |
|||||||||||||
|
教育目標の評価 教育理念・教育目的は不変のものではなく、社会の変化や看護・教育に関する捉え方の変化、あるいは、不断の評価活動によって検討され、修正されるものである。さらに 教育目標は、具体的な教育内容の抽出・精選、教育の方法論に直接関連し、教授・学習活動へと結びついていくため、常に点検・評価することが必要である。教育目標は、看護実践者としての能力、自立した学習者としての能力の育成を示していることから、それらの能力の到達度を把握し、フィードバックすることが必要である。 |
|
||||||||||||
|
継続教育との関連 社会が期待する看護専門職の育成は、看護基礎教育と卒業後の継続教育との一貫性によって初めて可能となる。大学、大学院への進学、看護職としての専門性をより追求するための職場における現任教育、これらの継続教育は体系化され、看護基礎教育から発展したものとして位置づけることが出来る。継続教育との一貫性を保障するためには、看護基礎教育において、看護師として必要な知識、技術、態度の何がどこまで獲得出来ている必要があるのかを判断し、教育目標に反映させる必要がある。 卒業時に獲得している能力が明確であれば、卒業生を受け入れた施設にとって有効な教育プログラムを作成することができる。また逆に、臨床側から看護師として何を求められているのかの情報の提供を受けることによって、より具体的な教育目標の設定が可能となる。さらに、大学への編入学等を視野に入れることにより、養成所のあり方を発展的に思考した教育目標の検討が可能になる。 そして、社会にとって必要な一専門職業人としてあり続けるためには、社会の変化に対応し、看護のあり方を自ら思考し、生涯において学習を続ける能力を、看護基礎教育の段階で育成していくことも必要である。自ら学び続けることが看護の対象に対し看護の質を保障することにつながっていく。 以上より、教育目標の設定に当たっては、看護の専門職教育全般を視野に入れ、継続教育、生涯教育の視点から、専門職の基礎教育としての到達レベルをどこにおくのかについて明確にしておく必要がある。 |
|
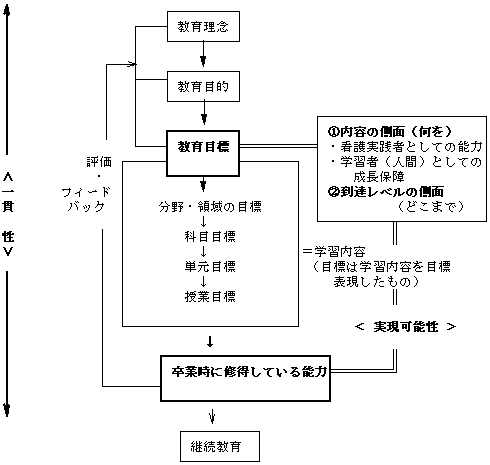
図4.教育課程における教育目標の位置づけと設定に含むべき条件
<点検>
|
||||||||||||||
|
教育課程経営者の活動 教育課程経営とは、教育課程を編成し、運営する活動を意味している。教育課程編成は、教育課程編成委員会等によって、組織的に行われる。そのためには、組織の目的、機能・役割が明確に規定されている必要がある。また、教育課程の運営は、養成所の教務主任等の職位にある者によって遂行されるが、その活動は、教授・学習・評価過程(授業)と経営・管理過程をつなぐ活動である(図2参照)。それは、編成した教育課程が授業としてどのように実践され、その評価をどのように行うか、その評価結果をどのように教育課程の改善につなげるかを明確に意図した活動でなければならない。この活動は、その任に在る者が単独できることではなく、教育課程編成委員会や授業を実践する教員と連携し、教育目的、教育目標達成に向けて、養成所全体として、一貫性がなければならない。 <点検>
|
|
||||||||||||
|
教育課程編成の考え方と具体的な構成 教育課程の編成にあたっては、どのような教育課程編成の考え方に基づいているかについて、明確でなければならない。指定規則に示された教育内容を単に遵守するだけではなく、また、伝統的な学問の体系に固執することなく、各養成所が主体的に教育課程を編成することが重要である。そのためには、看護師等養成所として、看護の専門職育成のためにどのような教育課程が適切であるか、その考え方が自覚されている必要がある。 たとえば、理解の深さが学習によって向上していく「看護の考え方」や「看護の対象者である人間の理解に関する内容」と、ある一定レベルの達成を設定できる「看護の技術」では、それぞれに異なる考え方によって編成してよいと考える。前者では、多様な考え方を育成できるようなカリキュラムの類型を選択する必要がある。後者では、技術という特徴に適したカリキュラム類型が選択される必要がある。 また、学生の成長発達だけではなく、学習への動機付け、学問への興味関心・追究などを意図して、何を必修とするか、どのような内容を基本として設定するか、何を選択とするか、等についてもその考え方が明確になっている必要がある。 <点検>
|
|
||||||||||||
|
教育内容の階層的関連性、配分の考え方 基礎分野、専門基礎分野、専門分野についての考え方と各分野の具体的な内容をどのようなものとするかその考え方が明示されている必要がある。つまり、基礎分野として設定した内容がなぜ「基礎」と位置づけられるのか、何に対する基礎なのか、が明確になっている必要がある。専門基礎分野についても同様に、設定した内容が、専門分野のどの内容とどのように関連しているのかを明確になっている必要がある。専門分野は、看護学の内容で構成されるが、看護の実践者を育成するために妥当な内容が選択されていなければならない。そして、それが基礎分野、専門基礎分野とどのように関連しているかが明確になっている必要がある。 指定規則には各分野の単位が明確に定められているが、各養成所においては、具体的に設定した各分野の教育内容にどれだけの単位と時間数を配当するのかについて、根拠を明確にもっている必要がある。単位数と授業にかける時間数は、設定した教育内容がどのように授業され、学生によって、どのように学ばれるのかということと関連していることを理解して設定する必要がある。 |
|
||||||||||||
|
科目・単元構成 設定された各分野の教育内容は、さらに、科目として区分・構成される。つまり、科目は、「既存」しているのではなく、教育理念・目的、教育目標との一貫性の基に、意図的に「まとまり」をつけ、区分して構成するものである。したがって、カリキュラム編成にあたっては、この科目構成の考え方が明確でなければならない。どのような科目として構成するか、設定された各分野の科目(群)が直接的に各養成所の教育理念を反映し、養成所の特色を示すものとなる。このような考え方は、養成所独自のものと、医療の現状や将来性を見据えた上で、文献検討等を踏まえ、看護専門職育成のための科目として、妥当であることが十分に検討されていなければならない。 科目が構成されたならば、その科目の内容をさらに授業実践に向けて、より下位のまとまり(通常、単元と言われる)をつける。ここにおいても、単元間の重複や関連性が明確に意識され、科目目標との整合性がなければならない。 <点検>
|
|
||||||||||||
|
単位履修の考え方 養成所は、指定規則に定められた就業年限を遵守した上で、学生が効果的に学修できるために、科目の履修方法を考慮していなければならない。単位制の基本的な考え方を十分に理解し、単位修得の期限、それに基づいた教育計画が立案されていることである。 現代の生涯学習の理念を踏まえ、従来の、通年で単位を修得する考え方のみではなく、学生が単位を履修できる方法を可能な限り柔軟に取り入れ、学修支援の方法を提示しておく必要がある。つまり、どのような内容を、いつ、どのような頻度で履修させるかの考え方が明確でなければならない。 |
|
||||||||||||
|
科目の配列 一方、育成する看護実践者の質を維持するためには、学生は科目間の有機的関連を十分に理解し、各科目で修得した知識・技術が統合されて理解に至っていることが重要である。この意味において、科目の配列(履修の順序性)は意図的に計画されなければならない。 単位履修の方法とそれに伴う制約は、教師、学生の双方が明確に理解している必要があり、明示されていなければならない。 <点検>
|
|||||||||||||
|
単位認定の考え方 単位認定は、養成所が設定した教育内容を修得したことを学生に対て認めるものであり、社会的には、卒業時に、看護実践者としての必要な能力を学修したことを保証するものである。したがって、単位認定にあたっての考え方は、教育理念、目的、教育目標との一貫性がなければならない。この意味において、養成所が設定している全科目の評価の時期、評価基準(認定基準)は明確に設定され、全ての授業担当者に理解されていなけれならない。また、単位認定の方法は学生に明示され、それが学修の支援につながっている必要がある。学修の支援につながるという意味においては、大学等、他の高等教育機関において修得した単位が相互に認められる体制を整えて置くことも必要である。 また、授業担当者の裁量と学校としての基準との関連を明確にしておく必要がある。 |
|
||||||||||||
|
評価の体系 教育課程の評価は、直接的には、教育目的、教育目標の達成を見極め、改善して行く活動である。したがって、個々の授業の結果としての学生の到達状況や、単位認定結果だけではなく、教師を対象とした評価 、学習環境を対象とした評価、経営管理過程を対象とした評価など、多角的に資料を収集し、分析する必要がある。つまり、どのようなものを評価対象とし、どのようにその資料を収集するのか、時期、具体的な手段などが明確になっている必要がある。 評価資料を多角的かつより客観的に得るためには、たとえば、教師を対象とした評価では、学生による授業評価の取り入れ、経営管理過程の評価では、第三者から評価を受けることなど、意図的に取り入れる必要がある。 そして、分析方法や評価結果をどのように活用するのか、データの蓄積をどのようにするのかなどについても、明確になっている必要がある。 また、評価結果の活用にあたっては、評価対象者にとって不利にならないようような配慮についても、明確になっている必要がある。 <点検>
|
|
||||||||||||
|
教員の専門性を高める体制 学生が専門分野において、教育目標を達成するためには、看護学の各専門領域を担当する教員が確実に指導できるような体制を整えることが必要である。各領域毎にどのような資格や専門領域を持った教員を何人配置するか、他の領域の教員とどのような協力体制をとっていくのか、各教員がどの内容を担当するのか、領域の特徴、学生数、履修形態などと考え合わせて体制を整えていく必要がある。教員によって担当する授業科目数、時間数に偏りがなく、授業に対する準備時間を保障し、適切な配分が必要である。 |
|
||||||||||||
|
教員の相互研鑽を保障するシステム 日々の教育実践の積み重ねが卒業時の学生像を創り上げる。教育目標の達成のために、教員には日々の授業を充実させ、常に評価していく能力、つまり自らの教育力を高めるための取り組みが求められる。教育課程の運用という視点から考えると、これはひとりの教員の問題ではなく、教師集団として教育力を高めていくという捉え方をする必要がある。教師集団として教育力を高めていくためには、具体的には、日々の教育活動について、授業案の検討、教育方法のあり方、情報交換、研究会などという内容や名称で互いに検討し合う機会を定期的に開催することが考えられる。これらの検討会は、教員自身が問題意識を持って自主的に運営していくことが望ましい。特に新任教員や経験のすくない教員にとっては学びの場として有意義である。 教育課程運用にあったっては、このような検討システムを背景に、教員それぞれが刺激しあい、学び合う文化を創りあげることが重要である。 |
|
||||||||||||
|
教員の自己研鑽を保障するシステム 教員は、それぞれ専門領域をもち、その領域の教育課程の運用の責任を担っている。教員自ら専門領域について学問的に追究していく姿勢をもつことはもちろんであるが、経営の点から、各教員の専門性の質の維持・向上を保障するシステムをつくることも必要である。具体的には、研修や研究活動への取り組み、学会への参加などに対して、時間的、予算的な対応を明確にしておく必要がある。 <点検>
|
|
||||||||||||
|
実習施設の選択と開拓 看護師等養成所の特徴として、臨地実習がある。実習施設は、看護学の教育施設として、養成所の教育理念・目的、教育目標を達成するために適した施設がまず第一に考慮されなければならない。医療施設として、どのような理念の基に運営されているのか、どのような看護の考え方を持ち、どのような看護の体制を整えているのか、学生の看護の学修の場として適しているかどうか十分に検討されている必要がある。また、実習施設の事情や他校との実習の重なりなどから実習施設の変更の可能性も往々にして起こるため、学生の学習の保障のためには、実習施設の開拓も視野に入れておくことが必要である。 |
|
||||||||||||
|
実習目標達成のための実習施設との協力体制 臨地実習の場は学生にとって、看護の実践を学ぶ場であり、専門職業人としてのモデルを見出す場でもある。したがって、実習の場を学生にとって看護への関心が高まり、充実感を味わえる様に調整するために、看護に必要な物品や実習中にも必要な図書、カンファレンスルームなどの整備が必要である。さらに、実習施設の責任者をはじめ、病棟師長、臨地実習指導者に実習目標について理解を得るような働きかけが不断に必要である。連絡会、学習会を設けたり、情報交換を行うことによって養成所と実習施設が同じ目標に向かって協力体制を整える必要がある。臨地実習施設の協力を得ることによって、臨地実習場における指導体制を意図的計画的に整えることが可能になる。 実習施設を以上のように整備する一方で、養成所は、実習施設内で、学生が確実に看護実践が学修できるように、患者数、患者の健康段階や疾病構造、提供される看護の内容等を考慮して、適正な学生数の配置をする必要がある。 |
|||||||||||||
|
臨地実習指導者と教員の協働 臨地実習において、学生に対する指導は、臨地実習指導者と教員が協力しあいながら行なわれている。臨地実習指導者は看護の実践について豊富な経験をもっていることから、学生が実施するケアに対し、日々変化していく看護の対象者の状況に応じ適切な指導が期待されている。一方教員には、学生のレディネスに配慮し、臨地実習における学生の体験の意味づけを教育的視点に立って指導することが期待されている。両者の指導によって学生の学習が成り立っていることから、それぞれの能力が発揮できるように役割を明確にし、日々の学生、患者の状況に合わせて学習内容、指導方法の選択について連携を図っていくことが必要である。さらに、2者がに互いに刺激し、学び合っていく関係をつくることが、学生にとっての学習の動機づけや施設全体の協力体制への強化へとつながる。 学生の看護実践を指導する臨地実習指導者は、以上のように学生の学習に大きく影響することから、質的、量的に充実を図ることは非常に重要である。実習を受け入れる学生数や、学生の学習段階に応じて的確に指導できるように、質的には、実習指導者講習会の受講者を整備するなど、また、量的にも整えていく必要がある。 |
|||||||||||||
|
学生からケアを受ける対象者の権利の尊重 学生が実践する看護の対象となる患者等に対して、患者の権利およびプライバシーが侵害されることがないように、学生の受け持ちとなることへの依頼・承諾、実習記録の取り扱い等について、養成所の基本的な考え方、姿勢を明確にしておく必要がある。 |
|
||||||||||||
|
臨地実習における安全対策 臨地実習においては、学生自身が事故を起こしたり、巻き込まれたりすることがないとは言い切れない。この事故の中には看護・医療事故のみではなく感染に関する内容も含む。また、学生が被害者になる場合も加害者になる場合も考える必要がある。このような事態において、学生への影響を可能な限り最小限に止め、学習の継続が可能になるような手だてを整えて置く必要がある。事故の対策に先だって事故の考え方、実習に関連する事故の現状や対策について実習の進度にあわせて系統的に安全教育を実施していく必要がある。また学生の事故発生の実態を把握し、分析し、安全対策に活かしていくようなシステムをつくることも重要である。 <点検>
|
|
||||||||||||
|
授業内容と教育課程との一貫性 教授・学習・評価過程の自己点検にあたっては、教授・学習・評価過程は「授業」と同義であり、教師が教授し、学生が学習する過程は、教師と学生の双方向コミュニケーションにおいて成立することを前提にしている。学生、教育内容、教師の3要件によって、教授・学習・評価過程は成り立つ。 ここにおける学生は、学生一般ではなく、当該の授業をうける当該の学生(特定の学生:集団、個人)であることを理解していなければならない。 教授・学習・評価過程における授業内容は、学生に対する授業において教授・学習される教育内容であり、各科目の教育課程上の位置づけ・目標のみならず、養成所の教育理念・教育目標との一貫性を常に意識して授業内容を設定する必要がある。 |
|
||||||||||||
|
看護学としての妥当性 教育内容が看護学の内容として妥当性があるためには、看護教師としての学習・教育観、看護観、学生観を明確にした上で、教育内容をどのような意図の基にどのような内容として設定しているのか(授業内容のとらえ方)を明確にする必要がある。その意味においても各授業における教育内容は、担当教師の専門性や得意分野を強調するのではなく、看護学を構成する科目や単元、当該授業の意図にそった教育内容となっている必要がある。 |
|||||||||||||
|
授業内容間の関連と発展 教師は授業を構成する際、その授業が他の授業とどのような関係にあるのかを明確にしておく必要がある。例えば、専門分野の内容が基礎分野あるいは専門基礎分野の内容とどのように関係しているのか、専門分野の内容間ではどのように関係しているのか明確にするということである。つまり、学生の理解を効果的にするためには、この授業の内容がどのように発展していくかを考えたり、既習の内容であっても教育内容としておくことによりさらに理解を促すなど、教育内容の有機的なつながりを明確にしておくことである。教師がこのような考えを持つことは、授業において学生の学習意欲を刺激するうえで重要である。 |
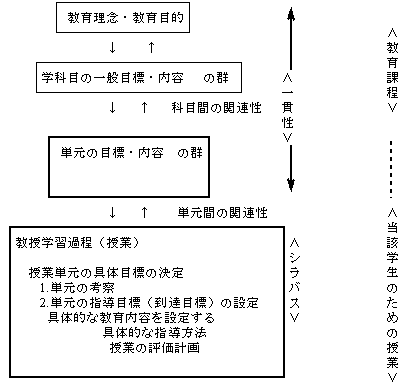
図5.教育課程における教授学習過程(授業)の位置づけと構成因子
<点検>
|
||||||||||||
|
履修形態の選択 授業を展開するにあたっては、まず第一に履修形態が選択されなければならない。履修形態としては、講義、演習、実験、実習がある。教師は、各履修形態の特徴を十分に理解した上で、設定した授業内容に適した形態を選択しワンパターンの履修形態とならないよう工夫する必要がある。 看護学基礎教育において実習という履修形態は、各看護学の講義・演習により得た知識・技術を看護の対象者に実践し、既習の理論・知識・技術を統合することが可能である。したがって看護実践力を備えた学生を育成するために重要な履修形態であると言える。しかし、単に実習という形態を選択したからといって理論・知識・技術が統合されるものではない。つまり、履修形態は学習の段階や授業内容の関連性を十分考慮した上で授業内容との関係性において選択されていなければならない。 |
|
||||||||||
|
授業の対象学生の構成と指導方法 授業を受ける学生の構成から指導方法を選択するには、一斉授業(クラスや学年をひとまとまりとして)、小集団(グループ)指導、個別指導がある。教師は当該授業において、学生をどのように構成して指導を行うのか、それぞれの特徴を十分に理解した上で選択する必要がある。 |
|||||||||||
|
指導技術の工夫 実際の授業を展開する中では、教師は教育内容の説明のみならず、それを効果的に行うために、また、学生の理解や、学習意欲、課題の追究を支援するために、多くの指導方法(指導技術)を持ち、工夫して授業を展開する必要がある。具体的な指導技術としては、「説明」「発問」「指示」「演示」などがあり、教師は高等教育として学生が自ら学習意欲を高められるようにこれらの指導技術を駆使し、授業展開を工夫する必要がある。その際、レポート課題の設定等は、学生の負担のみにならないよう教師は支援ができることも教育方法の1つとして重要である。 また、設定した当該授業の内容は、常に一人の教師で行う必要はなく、各教師が持っている専門領域や経験を効果的に活用して、複数の教師で授業を行う方法なども行われてよい。当該授業において複数の教師によって授業を行う方法や、科目や単元を複数の教師で授業する方法もある。例えば、看護技術教育においては、学生の技術の習得を確実なものにするため複数の教師で演習形態の授業を行い効果的な授業展開を計画する必要がある。いずれの場合においても、授業内容についての考え方、教育方法について一貫性や統一性が必要なため、検討され、教師間での充分な協力体制が不可欠である。 |
|
||||||||||
|
教材・教具の活用と開発 教材・教具は先に述べた教師の指導技術の一環として、また、学生の理解を深め、支援するために欠くことができない。したがって、教師は、看護学教育に必要な教材に関する情報の収集や看護の各領域に適した教材を意図的に選択し、効果的に活用できる能力や既製の物の活用にとどまらず、教師自ら教材を作成するなどの工夫ができる能力も必要である。また、学生がシミュレーションモデルなどを活用し、自己学習するように指導できることも必要である。 <点検>
|
|||||||||||
|
評価の計画性 授業における評価の計画性は、単元の教授・学習過程を計画的に評価し、必要に応じて授業展開を修正・改善することや、当該授業を進める過程において、学生の理解の状況をどのように把握し、どのように授業の目標を達成するのか、そのための形成的評価を授業の流れの中でどのように行うのかなど、授業の進め方の判断を意図的に行うために必要である。 |
|
||||||||||
|
また、看護学教育は、高等教育であり、学生は専門教育を受ける者として、自らの学習の経過や成果を自ら認識し、主体的に学習し続けることが期待される。したがって、教師からの評価結果を活用し、自らの学習をより深めて行けるようになる必要がある。 評価結果が公正で明確であれば、自己の学習課題が理解しやすく学生の学習意欲につながると考えられる。そのためには、提出されたレポートや試験成績、実習記録などは、適切な時期に返却され学生が自己の学習活動に活用できるようにしていることが重要である。 |
|
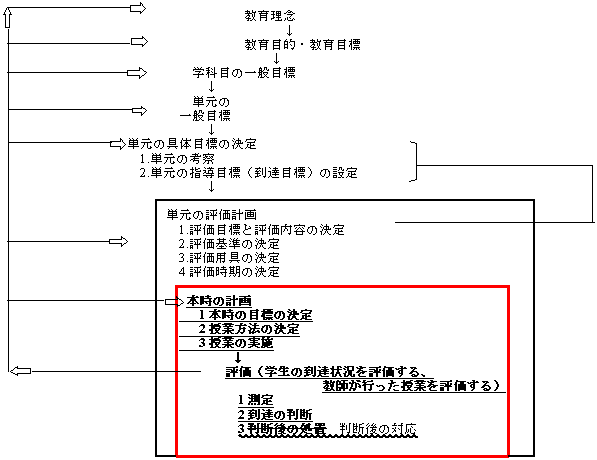
図6.教育課程における単元評価のフィードバックシステム
<点検>
|
||||||||||||||||||
|
シラバスの作成 学生が授業を受けるにあたって、授業のねらい、進め方、参考文献などを予め知ることは、その授業へ主体的に参加し、興味関心を持ち、理解を深める上でシラバスの提示は重要である。シラバスは、授業内容がどのような意図で、どのような内容として設定されているかなど、学生が理解しやすいように、また、興味関心を持てるように、具体的に記述されている必要がある。 また、教師にとっては、授業内容を設定するにあたって、その授業目標の明確性や授業の展開過程の明確性の点で重要である。 また、それを教師間で共有できるように整えておくことにより、学習への支援が、養成所全体としての一貫性を持つうえで必要なことである。 |
|
||||||||||||||||
|
学習の支援の体制 学習への動機づけをより確かなものにするためには、学生は、授業を受ける前にも、授業後にも、当該授業に対する興味関心や理解をより深めるような支援を必要とする。そのためには、必要時、教師の助言・指導を受けられるような体制を整えておく必要がある。 いつでも学生が教員に対して自由に疑問をなげかけ学び合う学校文化を形成していくことは重要である。また、特に学習の支援体制として実習期間中は実習終了後に自己学習することが必須であり、学生が抱えている問題も多様であるためことから教師が指導する時間を保障することも必要になる。図書館や情報科学室の解放など自己学習できる環境を提供することも求められる。 <点検>
|
|
||||||||||||||||
|
設置者の意思の明示と経営・管理過程の一貫性 設置者の意思は、教育理念と合わせて、養成所の教育・研究活動の指針となるものである。看護の専門職育成機関として、また、資格試験受験資格を付与する機関として、設立の意図を踏まえ、養成所指定時の水準を維持するだけはなく、より発展して行くための主体的な指針として明示されている必要がある。 この意思は、直接的には、設置者の命を受けた管理職にある者の考え方と、その経営・管理過程を通して実現される。したがって、管理職にある者は、養成所の「組織体制」、「財政基盤」「施設設備の整備」「学生生活の支援」「養成所に関する情報提供」「養成所の将来構想」「自己点検・自己評価体制」について、どのような考え方に基づいて、どのように経営・管理にあたるのかが明確になっている必要がある。それは、養成所の教育理念、教育目的達成にむけて、設置者が示す指針との一貫性がなければならない。 さらに、設置者の意思・指針と経営・管理にあたる管理者の考え方は、養成所の教職員に理解・浸透していることが重要である。 <点検>
|
|
||||||||||||||||
|
意思決定機関・意思決定システムの明確性 養成所の経営・管理にあたって、意思決定機関・意思決定のシステムは明確な規定に基づいて組織されている必要がある。この規定の中には、養成所の経営・管理にあたる者の権限や意思決定システムを構成する各組織の相互の役割機能が明示されている必要がある。 さらに、意思決定システムは、各組織やその構成員の意思や考え方が十分に反映されるように整えられていること、および、決定事項等が周知されるように整えられている必要がある。 また、この組織体制は、養成所の拡大、発展に伴って、柔軟に再構築されていくものとして考えられていることが重要である。 |
|
||||||||||||||||
|
組織の構成と教職員の任用の考え方 養成所の組織体制は、教育理念・目的を達成するために、最も適切と思われる教職員の組織を設け、その役割機能を明確にし、これに必要かつ十分な教職員を配置することによって、教育・研究活動の成果を収めることに努力する必要がある。 教員の任用にあたっては、看護学の各専門領域を確実に指導できるようにするために、質的には、看護教員養成課程等を修了していること、量的には、各領域毎に指導体制が整うように、教員の選考、資格審査、任免、昇格等について明確になっている必要がある。これは、授業科目を担当する非常勤講師の選定にもあてはまる。 さらに、養成所においては、教員は、授業を行うだけではなく、図書に関することや、後述する「学生生活への支援」において、多大な時間を割かなければならない現状がある。したがって、教員の任用・配置においては、この点からも十分に検討する必要がある。 また、養成所は、教育機関として、教員のみではなく、管理、事務組織によって支えられ、成り立っていることから、管理職、事務職員の任用についても、養成所の教育理念、目的を達成する観点から、明確になっている必要がある。 |
|
||||||||||||||||
|
教職員の資質の向上についての考え方と対策 任用後には、各教員の専門性や教育的資質、管理・事務職員の資質をどのように維持・向上しようとしているか、その考え方が明確になっている必要がある。 このなかには、教職員の倫理や福利厚生に関する規定も含めて明確になっている必要がある。 <点検>
|
|
||||||||||||||||
|
財政基盤 養成所の運営にとって、財政基盤は重要課題である。学生の教育の費用のみならず、教員の教育的資質の向上、研究に必要な経費、学習・教育環境の整備など、常に十分な財源が確保されているとは限らないであろう。収入の基盤、支出の根拠、その両者において学習・教育が効果的に実施されるようにすることが重要である。つまり、管理者は、どのようにして財政基盤を整えるのかその基本的な考え方を明確にしておかなければならない。 また、教職員は、自らの所属する養成所がどのような財政基盤に基づいてなりたっているかを十分に理解していることも重要である。これは、教員は教育的観点から、事務職員は事務的な観点から、その意見を養成所の経営・管理過程に反映させる意味において必要である。 <点検>
|
|
||||||||||||||||
|
整備の考え方と計画性 効果的に教育目的を達成するために学習・教育環境を整えておくことは当然のことである。指定規則の遵守にとどまらず、より良い環境の中で教育・学習が行われるようにする必要がある。そのためには、管理者がどのような考え方のもとに学習・教育環境を捉え、整えようとしているのかが問われる。看護師等養成所として、規模の大小があっても、学習・教育環境において質的な格差がないように常に意識し、意図的、計画的に整備していくことが重要である。 整備の考え方の中には、学生および教職員の活動が安全かつ快適であるかどうかも含まれている必要がある。 |
|
||||||||||||||||
|
看護学の発展や医療・看護へのニーズ、学生層の変化に対応する整備 看護師等養成教育は、看護の専門職を育成するのであるから、学習・教育環境として、特に図書・文献資料の整備、看護の技術を習得するための器具機材は、単に指定基準が示した数量を養成所認可時の状態を維持するだけでは、実質的には維持にはならない。これらは、看護学の発展や医療・看護へのニーズの変化に対応して、教育内容、教育方法も変化・発展していくので、可能なかぎり最新のものに更新、充実させていく必要がある。さらに、看護技術を学習・教育するための器具機材および実習室は学生が自己学習時にも活用できるように整備しておく必要がある。 また、通常の授業においても、学生層が多様化してきている傾向に対応し、指導方法の多様性も求められている。学生が小グループで自由に討議できるような演習室の整備、自己学習ができる部屋や情報機器の整備など、多様な学習・指導方法がとれるように施設設備を整備することも重要である。 |
|
||||||||||||||||
|
学生および教職員にとっての福利厚生のための整備 学習・教育活動には、学生にとっても、教職員にとっも、必然的に生活活動が伴っている。こうした生活活動や友人との交流、課外活動等が円滑に行えるように施設設備が整備されていることは、教育課程を通しての学生の人間性や社会性の涵養を支え、より豊にする意味において重要である。教職員にとっても職務が円滑に遂行できるような施設設備の整備は欠くことができない。 このような福利厚生のための施設設備は、養成所が設置されている地域環境との関連から検討し、整備されることが望ましい。 <点検>
|
|||||||||||||||||
|
学修継続への支援体制 看護師養成所に入学後、規定の教育課程を修了できず途中で学修を断念せざるを得ない者も少なからずいる。この理由や背景には、経済的理由、心身の健康上の理由、家族・家庭生活に関連する時間的制約などが挙げられる。このような困難や制約を克服して、学修を継続できるように、養成所は、教育的観点から、奨学金等の経済的支援の体制、カウンセラーの配置等健康相談を受ける体制、教育課程経営において述べたように、単位履修の方法を可能な限り多様に整えておく必要がある。 |
|
||||||||||||||||
|
学習困難への支援体制 看護学を学ぶうえで、基礎学力の問題や、多くの科目が「必修科目」であることによる過重や、臨地実習では、人間関係の形成に困難を示す学生も少なくない。これは、文字通り、学習支援を要する学生である。養成所は、正規の授業のみではなく、このような学生が、より確かに看護を学べるような体制を整える必要がある。 |
|||||||||||||||||
|
社会的活動への支援体制 養成所に入学後、看護学のみを学ぶことに専念するだけではなく、より広い観点から自らの資質を高める活動や、広く社会に目を向け、社会的活動を通して、社会の一員としての視野や認識を持てるようになることも重要であり、このような点においても、教職員の支援・指導をうけることができるようになっていることである。 |
|||||||||||||||||
|
卒業後の進路選択への支援体制 卒業、就業にあたっての進路についての相談・指導体制も充実したものにしておく必要がある。 以上の、学生生活を支援する体制は、単に体制を整えるだけではなく、実際に学生がそれを活用して、学修を継続する結果をもたらしていることが重要である。 <点検>
|
|
||||||||||||||||
|
教育活動に関する関係者への情報提供 教育・学習活動は養成所内における教職員と学生の学習活動を支援する関係者との協力によって推進される。したがって、このような関係者に対して、養成所の運営への協力や、学生が学習に専念するための支援が得られるように、養成所の経営・管理方針や学生の学習状況に関する情報を積極的に提供する必要がある。 |
|
||||||||||||||||
|
広報活動 養成所がさらに発展するためには、その存在と活動内容を広く社会に知らせる必要がある。それは、入学希望者の開拓や地域社会との連携の点からのみではなく、看護専門職を育成する機関として、社会的責任の点からも欠くことができない。したがって、この広報活動の中には、養成所の一般的な案内だけではなく、自養成所の自己点検・自己評価の結果なども含められていることが望ましい。 <点検>
|
|
||||||||||||||||
|
年間の運営計画と評価 養成所の運営は、設立の理念、教育目的、教育目標を達成するために、年間の運営計画に基づいて実施されている必要がある。この中には、養成所として毎年の定例のもの、その年に特有の内容などがあるが、長期的展望、短期計画との整合性をもって計画・運営・評価する必要がある。 |
|
||||||||||||||||
|
短期計画 長期的展望を実現するためには、年間の運営計画を積み上げて行くだけではなく、より短期の目標を設定し、その計画を確実にする手だてが明確になっている必要がある。この短期計画は、年間の運営計画の実施結果や、社会的背景の状況により、適宜修正されていく必要がある。 |
|||||||||||||||||
|
中・長期的計画 各養成所は、現在置かれて状況や時代の変化にともなって、養成所に対する社会の要請が変化することを常に意識している必要がある。そして、その存在を維持し、さらに発展して行くためには、長期的展望を持ち、その将来構想を明確にしておく必要がある。 <点検>
|
|||||||||||||||||
|
自己点検・評価の組織 自己点検・自己評価は、管理者のみが行うものではなく、またできるものではないので、組織的、体系的に取り組む体制を整える必要がある。これは、養成所の全教職員が常に自らが所属する養成所の「教育の水準を維持・発展するために活動しているという認識の形成にもつながるものである。 自己点検・自己評価は、資料(データ)収集、分析・解釈、課題の改善、教育理念、目的へのフィードバックという段階があるので、組織編成にあたっては、これらを効果的に行えるように、編成する必要がある。その上で、どのような活動を実際に行うのか、組織としての活動、メンバー個々の活動が明確になっている必要がある。 |
|
||||||||||||||||
|
資料・データの収集、蓄積 資料・データは、養成所として、明確に収集、蓄積が可能であるものと、教職員が個人の活動の中で蓄積しているもの、資料として必要であっても、あらたに作成からはじめなければならないものなどがある。自己点検・自己評価のカテゴリー、下位項目との関連で、資料・データをどのように収集していくのか、意図的、計画的に行われる必要がある。 |
|||||||||||||||||
|
資料、データの分析、解釈 資料・データは、収集し蓄積してあるだけでは意味がない。それを分析し、課題や改善点を見出していくことがその本来の意味である。したがって、自己点検・自己評価の過程で、資料が整っていることは望ましいが、それをもってよしとするものではない。 資料・データの分析・解釈には、専門的な知識を必要とする。管理・事務的な観点や、教育的観点、研究的観点など、多角的に分析できるようになっている必要がある。この段階において、課題、改善点が明確に抽出され、明示される必要がある。 |
|||||||||||||||||
|
課題や改善点への取り組み 資料、データの分析によって明確にされた課題や改善点は、それをどのように解決していくのかについての検討が加えられ、意図的計画的にとりくまれなければならない。課題や改善点の解決のための計画には、いつ、どのように取り組むのか、取り組みのための手段、達成の時期などが明確になっている必要がある。これは、同時に教育理念、教育目的、教育目標へフィードバックされ、これらの修正、維持、改正等の検討がされることになる。 以上の過程と結果を踏まえ、養成所の質の向上に向けて、あらたな自己点検・自己評価の過程が継続・循環されていくことが重要である 。 |
|
||||||||||||||||
|
第三者評価、結果の公表 自己点検・自己評価は文字通り、養成所の自らの意思で行うものである。しかし、その結果について、客観的な視点を加えるならば、分析・解釈においても、課題の抽出においても、広い視野から検討が可能になり、看護専門職者を育成する機関として、より確かな教育目的の達成につながるものと考える。 第三者評価は、「第三者評価機関」としてはないので、どのような「第三者」にどのような内容を依頼するのか等、養成所が自ら企画して行うものである。 公表は、看護専門職を育成する機関としての社会的説明責任を果たすものとしてあるが、第三者評価と同様に、いつ、どのような対象に、どのような方法で行うのかなど、各養成所が自ら企画するものである。この公表によって、養成所がより発展していくような社会的反応だけではなく、負の反応もあることが推測される。しかし、養成所が教育機関として、社会的存在であることを考えるならば、それを受け止め、自ら改善してく力をもつことが重要である。 <点検>
|
|
||||||||||||||||
|
入学者の選抜の考え方と教育理念、教育目的との一貫性 教育理念・教育目的を実現するためには、教育理念、教育目的つまり教育方針を適切に反映した入学者選抜の方法を採択し、入学者を確保する必要がある。入学時にどのような能力を重要視するか、それはどのような選抜方法(筆記試験−科目の設定、論文、面接−個人、集団、その他)によって可能なのかが検討され、入学者選抜方針が決定され示される。 この方針の決定にあたっては、社会人入学生の増加など、受験生の動向を把握し対応することも重要である。また、入学者選抜は、準備、実施、採点、発表まで正確性、公平性が求められ守秘義務を伴うことから、組織を編成し一貫した対応が必要である。 |
|
||||||||||||||||
|
選抜の公平性 入学者選抜は、準備、実施、採点、発表の過程において公平性を保つことが受験生や社会に対する責任である。組織された委員会が守秘義務を徹底して果たし、入学試験問題の漏洩や採点における不平等が起こらないよう管理上の工夫、徹底が必要である。 |
|
||||||||||||||||
|
選抜方法の妥当性 入学者選抜方法とその後の成績の推移などからこの選抜方針が適切であったかについての評価を計画的に行う必要がある。教育理念・教育目的の実現にむけ、教育活動を有効に行うため、特に看護基礎教育において特徴的な演習や臨地実習における教育効果を高めるためには、学生定員と在学生数の比率が適性な範囲であることが重要である。また、在学生数に対する社会人入学生、編入学生の比率について不断に検証していくことが必要である。 |
|
||||||||||||||||
|
入学希望者開拓への取り組み 18歳人口の減少や看護系大学の増加の中、教育方針にかなった入学者を獲得するためには、まず、受験生の動向や背景を把握、分析する必要がある。その上で、従来の募集範囲や方法を維持するだけではなく、入学希望者本人、保護者、地域の高等学校、さらに全国に向けてそれぞれのニーズにあった方法で教育理念・教育目標・特徴をピーアールし、募集活動を積極的に行い、入学希望者の確保に取り組む必要がある。具体的には、募集要項の作成、ホームページの作成、受験生への説明会への参加など、受験生募集の方針・内容・方法について、養成所として、組織的、計画的に検討し取り組む必要がある。 <点検>
|
|
||||||||||||||||
|
進路選択状況と教育理念・教育目的との整合性 看護職の活躍の場が多様化する中で、看護師等養成所は教育理念・教育目標に応じた卒業生を養成しているか把握している必要がある。 卒業の状況は、入学時の状況との比較において評価する必要がある。学生数の変動(編入学、休学、復学、留年、退学等)を把握することは、入学試験において養成所の求める学生を選抜できているかという評価につながる。 就業状況は、卒業生をどのような看護のフィールドに送り出したかを把握することで、養成所の理念や目的にあげている人材を育成しているかを把握するために必要である。また、就業にあたっては、免許が必要であり、国家試験の合格状況を把握し、教育目的の到達状況の評価として分析している必要がある。 進学状況は、卒業生がどのような看護職をめざしているかを把握することは養成所の理念や目的にあげている人材を育成しているかを評価するために必要である。 |
|
||||||||||||||||
|
進路選択状況と卒業後の活動状況の評価 卒業時の学生の看護実践能力を把握することは、看護実践者を育成する教育目的が達成できているかを評価することであり、カリキュラム全体の評価にもつながるため評価結果を分析し、カリキュラムの改善に活用する必要がある。 就職先での評価は、在学中の教育内容が看護の現場で必要とされる実践能力の基盤となりえているのかを判断する情報として把握している必要がある。期待する卒業生像についても、実際との比較に置いて、妥当であるのか検討していなければならない。そのため、卒業後に、看護の実践能力をどのように発揮しているのか、卒業時の習得状況との関連で把握しておく必要がある。そのため、卒業生の就職先との情報交換や調査の実施などが計画的になされている必要がある。 看護職は専門職業人として社会への貢献が期待されている。そのためには、卒業生の活動状況を長期的に追跡し、把握した結果を統計的に整理しておくことは、養成所が社会のニーズに応じた人材の養成を行っているかを評価するための根拠となる。情報の入手方法として、同窓会との連携なども考える必要がある。 <点検>
|
|
||||||||||||||||
|
健康や看護についての啓蒙・普及活動 養成所の個別性を発揮する一つの方法として、地域との密接な関係を通して、地域の諸資源を含んだ教育課程を開発することも可能になるため、看護学教育研究活動を通してどのように地域社会に貢献するかの考え方を明確にしておく必要がある。 地域住民に対し、健康や看護について啓蒙・普及活動につながるような公開講座などの実施を通して、地域に貢献していることが重要である。看護学教育研究活動を通した地域への貢献としては、ボランティア活動など地域のニーズを反映した取り組みを通して貢献している必要があり、そのためには、地域ニーズの把握の方法についても計画性があることが望ましい。これは、養成所が地域から活用される側面である。 |
|
||||||||||||||||
|
地域社会と交流するための体制 地域社会との交流は、養成所と地域社会との双方にとって、意味があるようにする必要がある。そのためには、委員会や専任の教職員を配置する等組織的に取り組む必要がある。 |
|
||||||||||||||||
|
地域社会における資源の活用 看護師等養成所にとって、地域とは、ただ単に「そこに在るもの」としてではなく、意図的に関わり、「形成するもの」としてとらえる考え方がある。言い換えれば、地域は、静態的概念としてではなく、動態的概念として考えられる必要がある。そのために、看護師等養成所は、養成所が設置されている地域の住民や団体、保健・医療・福祉施設等のニーズを把握すると同時に地域の人的・物的資源を活用する考え方を明確にもっている必要がある。 養成所が設置されている地域は学生にとっては、重要な学習環境である。地域の特徴を把握し、それが看護学実習やフィールド研究において活用されるならば、養成所と地域との関係はより密接になると考えられる。すなわち地域社会における資源の活用をどのように考えているのか明確にし、積極的に諸資源を活用できるようになっている必要がある。 <点検>
|
|
||||||||||||||||
|
学生・教員の国際的視野を広げるためのシステム 看護師等養成所においても、国際的視野を広げるための教育は必要であり、例えば、外国の文献が蔵書されているか、インターネットの活用は容易であるかなどの授業科目の設定や自己学習できるシステムを整える必要がある。 また、卒業後に、海外での学習(勉学)や、技術協力、就労を希望する者に対して、適切な情報を提供できる体制を整えることも必要である。 |
|
||||||||||||||||
|
留学生の受け入れ等に関する対応 また、海外からの帰国学生の受け入れや留学生の受け入れについても地域のニーズに応じて体制を整える必要がある。さらに、海外留学を希望する学生に対しては、英文での卒業関係書類や単位認定書類の準備ができる必要がある。 <点検>
|
|
||||||||||||||||
|
研究的姿勢の涵養 大学は、学術研究の中心的機関であり、研究活動は備えるべき基本的なものとして明確に位置づけられている。看護師等養成所における教員の研究活動は、大学のようには位置づけられていない。しかし、看護師等養成所の教員にも、下記の意味において、研究活動は不可欠である。 看護師等養成所は看護の専門職業人を育成する看護基礎教育を担い、高等教育機関として位置づけることができる。また、看護基礎教育の学問的背景である看護学は、現在発展過程にある新しい学問領域であり、体系化が進められている段階である。このような背景の中で、社会の期待・ニーズに対応しうる看護専門職業人の育成をめざさなければならない。流動性のある環境の中で、教育活動をおこなうためには、学校の教育活動全般に対して批判的、創造的に取り組み、自らの専門性を探求し、常に新しい情報を取り込み 、創意工夫した教授・学習活動を展開することによって、養成所の教育水準の維持・向上を図ることができなければならない。 批判的、創造的な姿勢をもち、創意工夫のある教育活動を行うためには、教員に文献のクリティークを踏まえ、研究成果を活用できる力、および看護の事象、教育の事象について分析的に捉え、そこに問題や課題を見出す力がなければならない。このような能力は、研究活動を通して培われるものである。特に、看護実践者を育成することに重点が置かれる養成所の教員には、看護実践について、常に研究的関心と、それを追究をしていく研究的姿勢が重要である。 |
|
||||||||||||||||
|
研究活動の保障 これらの教員の研究活動は、養成所自体による研究活動の支援体制が整っていることによって保障される。まず、教員1人1人が研究に価値をおき、研究活動の意義を認め、教員相互で支援し合う学校の文化を創り上げるとともに、学校自体が研究活動を奨励し、時間的(研究時間の確保)、財政的(研究費の支給)、環境的(研究室・情報検索システムなど物的環境)支援の具体的内容を提示する必要がある。 |
|
||||||||||||||||
|
研究活動の評価 研究活動は教員個人の興味・関心ではなく、必ず教育に還元できるのであり、この視点から研究活動の計画・成果について評価を受けるシステムを養成所内部に持つことも必要である。 看護学及び看護教育の研究そのものが学際的傾向があるため、自施設のみではなく、他の施設及び他の領域の研究者とのネットワークを積極的につくること、あるいは、学会・誌上発表を通して研究成果についての評価と他の研究者との交流・連携をもつこと、研究協力に関する依頼に対してコミットメントし積極的にかかわること、これらの日常の活動を通して教員自らが研究的姿勢を育成していくことが、視野の広がりと専門性を高め、教育活動に還元される。 <点検>
|
|