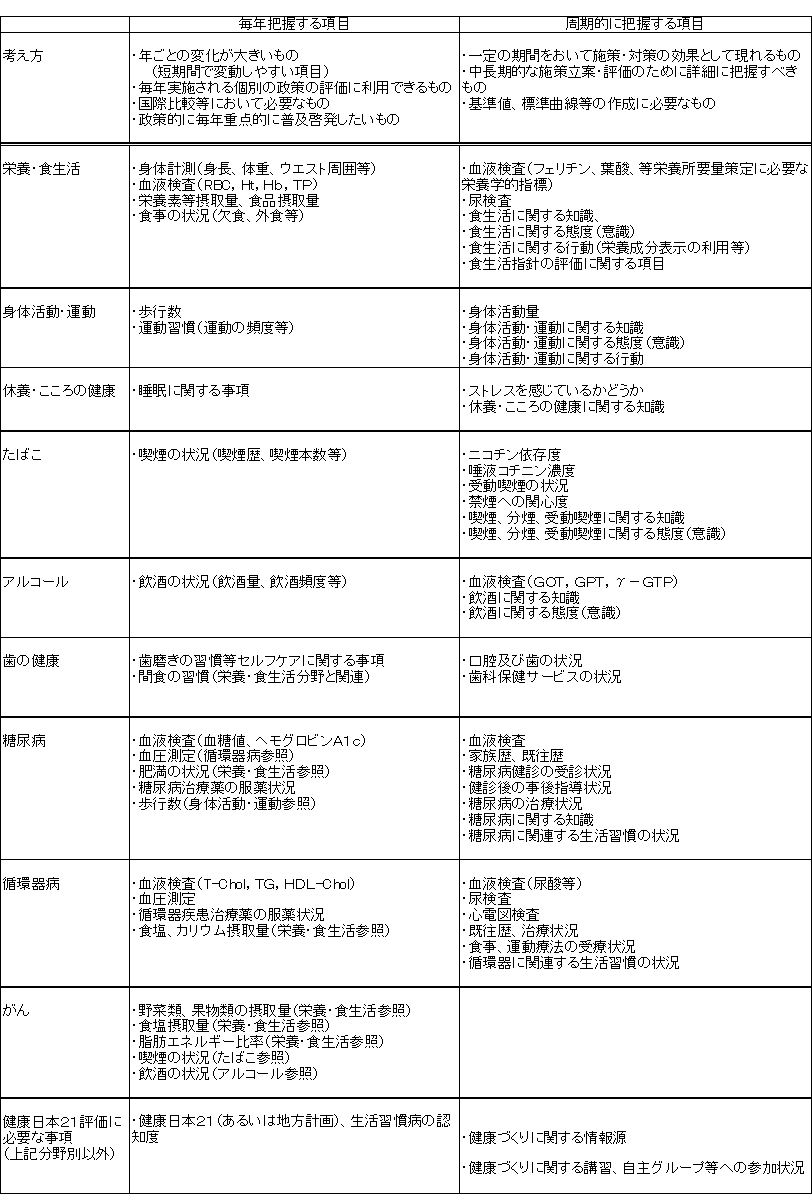
|
(照会先)厚生労働省健康局総務課 生活習慣病対策室 TEL:03−5253−1111(代表) 正林(内線2348) 清野(内線2344) |
2.国民健康・栄養調査のあり方
(1)調査の枠組みについて
(1)調査内容の周期について
(2)調査内容の構成について
a.身体状況の把握
b.栄養素等摂取状況の把握
c.生活習慣等の把握
(3)調査対象等について
(2)行政施策との関連について
(1)健康増進施策(健康日本21)との関連
(2)栄養施策との関連
(3)他の行政施策との関連
(3)調査体制について
(1)国・研究所における体制
(2)都道府県、政令市、特別区における体制
3.調査実施にあたって留意すべき事項について
(1)検査の精度管理
(2)調査票の再現性・妥当性
(3)調査員の質の確保
(4)被調査者の協力の確保
(5)調査票の取り扱い等について
4.調査結果の解析、公表及び活用について
(1)調査結果の解析、公表について
(2)研究等への調査データの活用について
| 1. | 基本的考え方
我が国における急速な高齢化の進展及び疾病構造の変化に伴い、国民の健康の増進の重要性が著しく増大しており、国民の健康の増進の総合的な推進に関し基本的な事項を定めるとともに、国民の栄養の改善その他の国民の健康の増進を図るために、医療制度改革の一環として、平成14年8月に健康増進法が公布され、本年5月1日に施行されるところである。 |
| (1) | 調査の枠組みについて
|
| (2) | 行政施策との関連について
|
| (3) | 調査体制について
|
| (1) | 検査の精度管理 各種検査については、横断的なデータの解析とともに経年変化の解析を行うためにも、必要な精度管理を行うこととする。 |
| (2) | 調査票の再現性・妥当性 また、生活習慣の状況及び栄養素等摂取状況の調査票については、質問票の再現性や妥当性についても研究において検討する必要がある。 |
| (3) | 調査員の質の確保 調査に従事する国民健康・栄養調査員の質を確保するために、調査必携において、調査方法を構造化、図式化して示すなど調査の標準化を行う必要がある。 また、栄養素等摂取状況の調査については、特に専門性を要することから管理栄養士・栄養士の研修を充実する必要がある。身体計測、血圧測定方法等も、調査必携を充実させるとともに、研修等により調査員の質の確保に努める。 |
| (4) | 被調査者の協力の確保 調査世帯に属する者は、法に基づき調査の実施に協力しなければならないことと規定されているが、近年、被調査者の協力率の低下が見られることから、協力率の低下を防ぎ、調査に対する理解と協力を得るため、調査実施のPRを工夫する。 |
| (5) | 調査票の取り扱い等について 調査票の取り扱い等については、従来より国民栄養調査において個人情報の漏洩のないように十分に配慮してきたが、健康増進法において新たに調査に従事する者に対する守秘義務が課せられたことから、国及び独立行政法人国立健康・栄養研究所において、調査票管理責任者、調査票の保管場所及び管理方法等について、管理規程を整備する必要がある。 また、都道府県、政令市、特別区職員及び国民健康・栄養調査員が調査の実施及び調査後の調査票の取り扱いにあたって留意すべき事項として、調査会場設営に当たって調査票の記入内容が他の世帯の人の目にふれないように配慮すること、調査票に記入された調査票を適切に管理保管することなどが考えられる。このような基本的な事項については、調査必携において示し、調査実施に当たって国民健康・栄養調査員等に対し、周知徹底を図ることが必要である。 |
| (1) | 調査結果の解析、公表について 調査結果の解析、公表は、その結果が広く普及啓発に用いられ、健康増進施策や栄養施策の推進に反映できるよう十分に検討を行うこと。また、調査結果の公表にあたっては、速報による発表と十分な解析を加えた報告書の作成の2段階で発表を行う。 公表結果については、従来からホームページ等にも掲載してきているが、今後も各種媒体により国民への情報提供の充実を図る。 国民健康・栄養調査結果は、国レベルの健康・栄養状態を示す世界的にも唯一の貴重なデータであるため、従来実施してきた国民栄養調査結果も併せ、海外への情報発信ができるように工夫する。 |
| (2) | 研究等への調査データの活用について 従来国民栄養調査結果については、統計法第15条2に基づき、厚生労働省の使用許可承認の後、個人情報の保護に配慮しながら厚生労働科学研究等における解析に活用してきたことろであり、今後も健康増進等に資する研究に活用できるよう体制を整備する。 |
| 5. | おわりに 本調査は、これまでの栄養改善法に基づき50年以上も続けて行われてきた歴史ある国民栄養調査を引き継ぐものであり、今後とも国民の栄養の改善その他健康の増進の総合的な推進に役立てられるよう継続、発展していくことが望まれる。 |
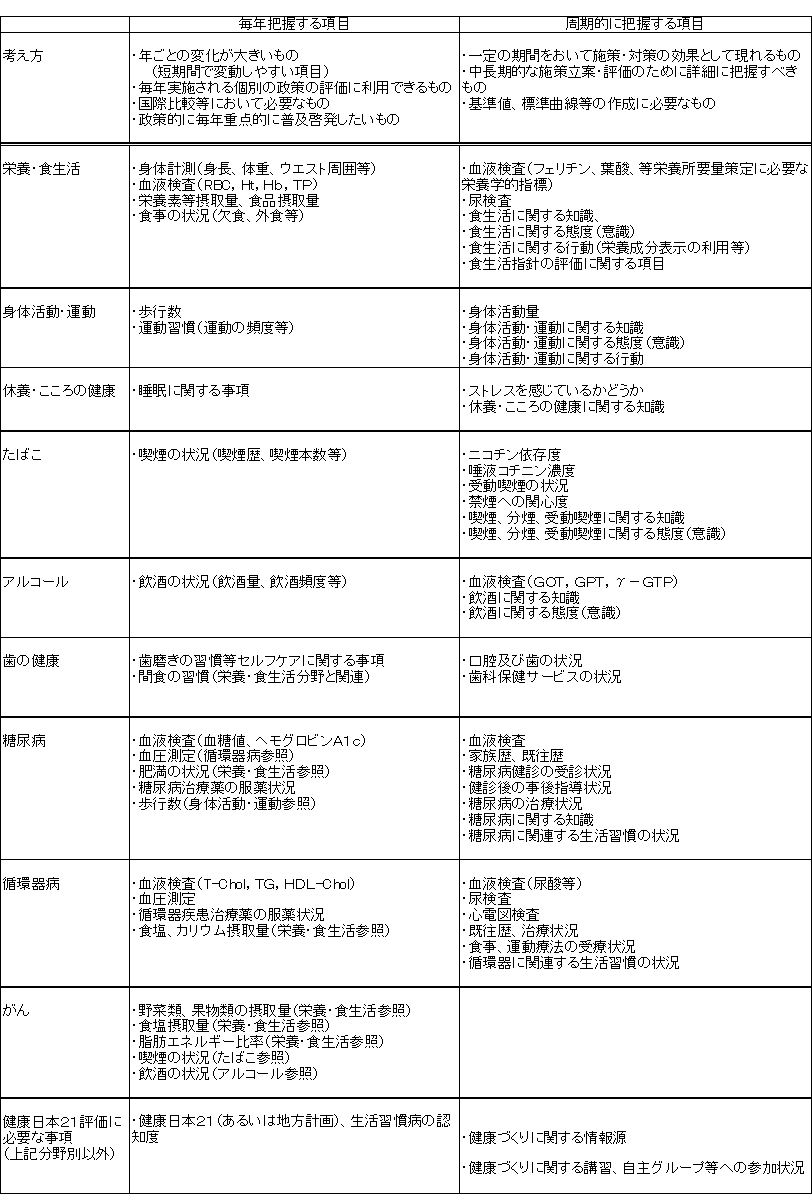
| 重点事項 | |
| 平成15年(2003) | たばこ、健康日本21中間評価関係項目 |
| 平成16年(2004) | 歯の健康、健康日本21中間評価関係項目 |
| 平成17年(2005) | 食生活、飲酒 |
| 平成18年(2006) | 休養・睡眠 |
| 平成19年(2007) | 身体活動・運動 |
| 平成20年(2008) | 糖尿病、健康日本21最終評価関係項目 |
| 平成21年(2009) | 歯の健康、健康日本21最終評価関係項目 |
| 平成22年(2010) | 食生活、循環器疾患 |
(参考資料)
○健康増進法(平成14年法律第103号) (該当条文抜粋)
(国民健康・栄養調査の実施)
| 第十条 | 厚生労働大臣は、国民の健康の増進の総合的な推進を図るための基礎資料として、国民の身体の状況、栄養摂取量及び生活習慣の状況を明らかにするため、国民健康・栄養調査を行うものとする。 |
| 2 | 厚生労働大臣は、独立行政法人国立健康・栄養研究所(以下「研究所」という。)に、国民健康・栄養調査の実施に関する事務のうち集計その他の政令で定める事務の全部又は一部を行わせることができる。 |
| 3 | 都道府県知事(保健所を設置する市又は特別区にあっては、市長又は区長。以下同じ。)は、その管轄区域内の国民健康・栄養調査の執行に関する事務を行う。 |
| 第十一条 | 国民健康・栄養調査の対象の選定は、厚生労働省令で定めるところにより、毎年、厚生労働大臣が調査地区を定め、その地区内において都道府県知事が調査世帯を指定することによって行う。 |
| 2 | 前項の規定により指定された調査世帯に属する者は、国民健康・栄養調査の実施に協力しなければならない。 |
| 第十二条 | 都道府県知事は、その行う国民健康・栄養調査の実施のために必要があるときは、国民健康・栄養調査員を置くことができる。 |
| 2 | 前項に定めるもののほか、国民健康・栄養調査員に関し必要な事項は、厚生労働省令でこれを定める。 |
| 第十三条 | 国は、国民健康・栄養調査に要する費用を負担する。 |
| 第十四条 | 国民健康・栄養調査のために集められた調査票は、第十条第一項に定める調査の目的以外の目的のために使用してはならない。 |
| 第十五条 | 第十条から前条までに定めるもののほか、国民健康・栄養調査の方法及び調査項目その他国民健康・栄養調査の実施に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。 |
| 第三十六条 | 国民健康・栄養調査に関する事務に従事した公務員、研究所の職員若しくは国民健康・栄養調査員又はこれらの職にあった者が、その職務の執行に関して知り得た人の秘密を正当な理由がなく漏らしたときは、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 |
| 2 | 職務上前項の秘密を知り得た他の公務員又は公務員であった者が、正当な理由がなくその秘密を漏らしたときも、同項と同様とする。 |
(参考1)
| 回次 | 開催日 | 検討内容 |
| 第1回 | 平成14年7月31日 | 国民健康・栄養調査のあり方について |
| 第2回 | 平成14年9月 4日 | 国民健康・栄養調査のあり方について |
| 第3回 | 平成15年2月14日 | 報告書骨子(案)について |
| 第4回 | 平成15年3月10日 | 報告書(案)について |
(参考2)
1 目的
厚生労働省においては、平成12年より、21世紀における国民健康づくり運動(健康日本21)を推進している。健康日本21では、目標の設定と目標に達成するための具体的な諸活動の成果を適切に評価して、その後の健康づくり運動に反映させることを基本方針の一つとして掲げている。そこで、評価に用いる手法について検討することとしているが、評価に活用する国民栄養調査等の調査の内容、今後の調査の在り方について、この分科会において検討することとする。
2 組織
(1)健康日本21評価手法検討会の分科会として設置する。
(2)構成員は別紙のとおりとする。
(3)構成員の任期は、平成15年3月までの期間とする。
3 検討課題
健康日本21評価に活用する国民栄養調査等の調査について
4 事務局
会議の事務は、健康局総務課生活習慣病対策室が行う。
5 その他
この要綱に定めるものの他、分科会の運営に関し必要な事項は、分科会座長が健康局長と協議の上定める。
| (五十音順) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||