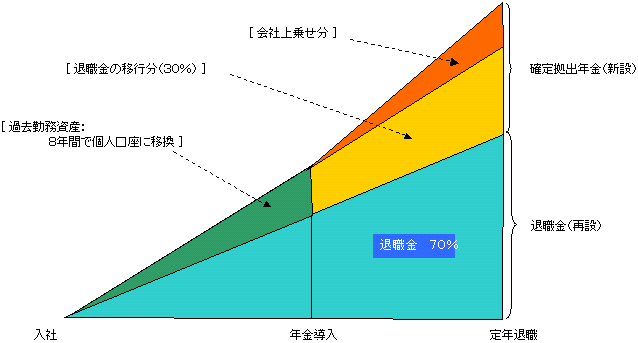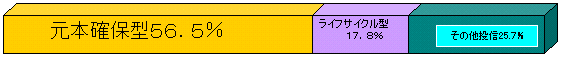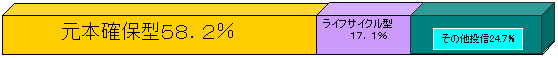| (1) |
制度導入の目的
| ■ |
当社には企業年金制度がなく、予想される公的年金縮小に対応する補完的年金として老齢時所得の確保 |
| ■ |
社員が自主性を発揮し、自己責任・自助努力により資産形成を成し得ることへの支援 |
|
| (2) |
制度導入の時期
|
| (3) |
制度のイメージ
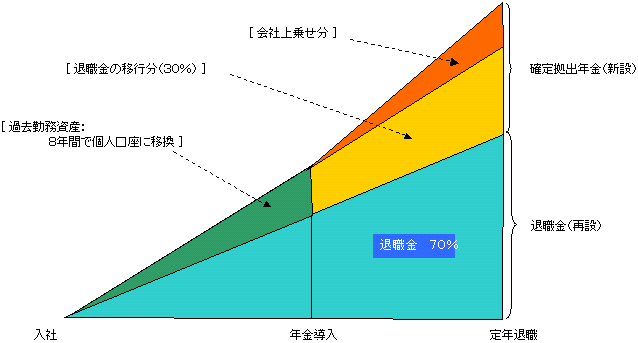
|
| (4) |
加入対象者
| ■ |
対象者は、プロパー社員のみの758名
(他社を定年退職し企業年金を保持している社員及び出向社員は対象とせず) |
| ■ |
加入者は、50歳以上のプロパー社員30名中、退職一時金の継続を選択した21名を除く737名が加入(加入率97.2%) |
|
| (5) |
掛金の原資
| ■ |
移行割合: |
退職一時金からの30% |
| ■ |
制度移行: |
過去勤務分の移換金として、制度導入時退職金要支給額の30%を8年間で移行 |
|
| (6) |
掛金額
| ■ |
掛金の設定: |
資格等級に応じた等差額
8,000〜36,000円 |
| ■ |
掛金の条件: |
掛金が資格等級別の退職金要支給額の平均額
(×30%)を下回らない |
|
| (7) |
給付の方法
| ■ |
5、10,15,20年又は一時金
(利率保証型積立生命保険の場合のみ終身あり) |
|
| (8) |
受給権
| ■ |
勤続3年以上で退職した場合には、掛金総額等の全額を付与 |
| ■ |
勤続3年未満で退職した場合には、掛金総額と退職時の年金資産のいずれか少ない額に、加入者の勤続期間に応じた会社への返還率を乗じた額を除いた額の付与 |
|
| (9) |
制度の特徴
| ■ |
掛金の設定において、初任資格等級から最上位等級までの掛金を等差とし、各等級別の退職一時金要支給額30%の平均額と比較して、掛金が低くならず既得権を確保 |
| ■ |
資格等級を基準とすることによって、社員の意欲と業績成果に期待 |
|