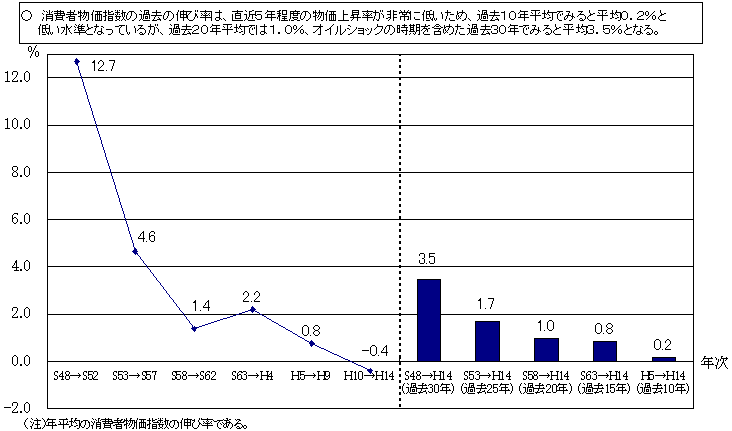
| 第16回社会保障審議会年金部会 | 資料1 |
| 平成15年3月18日 |
財政再計算における経済前提等について
目次
| 1 | 経済前提
|
||||||||||
| 2 | 被保険者推計に係る前提
|
||||||||||
| 3 | その他の前提 |
1.経済前提
(1)経済前提の設定における基本的考え方と平成11年財政再計算における設定方法
《賃金上昇率及び運用利回りにおける名目と実質の違い》
| ○ | 公的年金は、既裁定年金については物価の上昇に伴い、新規裁定年金については名目賃金の上昇に伴い、年金額が改定される仕組みであるため、年金財政は、物価を上回る実質賃金上昇率や名目賃金を上回る積立金の実質運用利回りの水準に大きく影響を受ける。実質賃金上昇率や実質運用利回りの水準が同じであれば、名目の賃金上昇率や運用利回りの水準にはほとんど影響を受けない。 |
| ○ | つまり、年金財政の観点からは、名目でなく実質の水準がどの程度になっているかが重要であり、経済前提の水準を考えるにあたっては、名目ではなく実質の水準について考えることが必要である。 |
| ※ | なお、保険料固定方式を採用し、名目年金額下限型のように名目年金額の下限を設けて給付水準の調整を行う場合は、名目の水準が給付水準調整度合に影響を与えることがあり得る。例えば、マクロ経済スライド(名目年金額下限型)で給付水準調整を行う場合、実質賃金上昇や実質運用利回りが計画どおり確保されていても、物価上昇率がゼロとなれば、既裁定年金の調整ができなくなる。 |
《長期の前提と短期の前提》
| ○ | 年金制度は数十年という人の一生に及ぶ長期の制度であるため、足下での賃金や利回りの水準の低下の影響は小さく、数十年におよぶ長期の賃金や利回りの水準に大きく影響を受ける。 |
| ○ | したがって、経済前提を定めるにあたっては、現下の厳しい経済情勢について、一時的なものであって10年程度以内で回復するものであるとみるのか、あるいは、今後、数十年に渡って続く長期的なものであるとみるのかを考える必要がある。一時的なものと考えるの場合、足下の前提と長期の前提を分けて考えることが適切である。 |
《平成11年財政再計算における経済前提の設定方法》
| ○ | 平成11年財政再計算では、足下の前提と長期の前提を区別せず、好景気の期間を含めた過去の実績を基準として経済前提を定めた。物価上昇率、賃金上昇率、運用利回り、それぞれの決定の考え方は次のとおりである。 |
|||||||
| ○ | 物価上昇率 物価上昇率は、前回再計算の検討を行っていた平成10年当時の過去10年間の実績より1.5%と設定した。 |
|||||||
| ○ | 賃金上昇率 物価を上回る実質賃金上昇率の過去10年間(平成10年当時)の実績が1.0%であったことと、各種の長期の経済成長率の見通しが概ね1.0%程度であったことを踏まえ、長期の実質賃金上昇率を1.0%と定めた。名目賃金上昇率については、これに物価上昇率を加え、2.5%とした。
|
|||||||
| ○ | 運用利回り 今後、自主運用されることを念頭におきつつ、国内債券が運用の中心的な役割を果たすであろうと想定し、名目賃金上昇を上回る実質運用利回りを
|
(2)足下での経済前提(物価上昇率、実質賃金上昇率、実質運用利回り)
《直近の経済指標の推移》
| (単位:%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注1: | (2)(4)(5)(6)は、名目値である。 |
| 注2: | (2)(5)(6)は、1人当たりの上昇率である。 |
| 注4: | 毎月きまって支給する給与、現金給与総額の上昇率は、事業所規模5人以上の調査産業計の上昇率である。 |
| 注5: | 平成14年のGDP成長率は速報値である。 |
| ※ | 標準報酬月額は、5,6,7月の給与の平均により10月から定時改定する仕組みとなっており、給与上昇の反映が遅れることとなるため、年平均の上昇率でなく、12月の前年同月に対する給与の上昇率を使用した。 |
| 《「年金改革の骨格に関する方向性と論点」の足下の経済前提(平成15(2003)〜19(2007)年度まで)》 |
| 実質賃金上昇率 | 実質運用利回り | 備考 | |
| ケースA | 1.0% | 1.5% | 名目賃金1.0%、物価上昇率0.0%、名目利回り2.5% |
| ケースB | 0.5% | 1.25% | 名目賃金0.5%、物価上昇率0.0%、名目利回り1.75% |
| ケースC | 0.0% | 1.0% | 名目賃金0.0%、物価上昇率0.0%、名目利回り1.0% |
| 注1: | 実質賃金上昇率とは、物価上昇率に対する実質的な賃金上昇率のことである。(実質賃金上昇率=名目賃金上昇率−物価上昇率) |
| 注2: | 実質運用利回りとは、名目賃金上昇率に対する実質的な運用利回りのことである。(実質運用利回り=名目運用利回り−名目賃金上昇率) |
| 注3: | 上表の運用利回りは自主運用分の前提である。試算に用いている運用利回りはこれに財投預託分の運用利回り(平成13年度末の預託実績より算出)を勘案した数値を使用。 |
| 《「改革と展望−2002年度改定」の審議ための参考資料(内閣府作成、平成15年1月経済財政諮問会議提出)》 |
| 単位:%程度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ○ | 「改革と展望の参考資料」における経済見通しでは、物価上昇率は、2004年度までマイナスが続き、2005年度にプラスの物価上昇率が実現される見通しとなっており、実質成長率は、2003年より0.6%以上の見通しとなっている。 |
|||||
| ○ | 足下での経済前提を「改革と展望の参考資料」と「年金改革の骨格に関する方向性と論点」を比べると、
|
|||||
| ○ | 実質運用利回りについては、平成20(2008)年度までは、財務省財政融資資金(旧大蔵省資金運用部)への預託金が存続し、この資金については利回りが確定していることについて考慮する必要がある。 |
《足下での経済前提を定める上での論点》
| ○ | 足下での経済状況を設定するうえで、現下の厳しい経済状況をどのように評価するか。 |
| ○ | 足下の前提と長期の前提を区別して経済前提を定める場合、足下の期間をどの程度とするか。 |
| ○ | 物価上昇率、実質賃金上昇率の2007年度までの前提を定めるにあたって「改革と展望の参考資料」をどのように評価するか。 |
(3)長期の物価上昇率の前提
図表1 物価上昇率(単年当たり)の推移
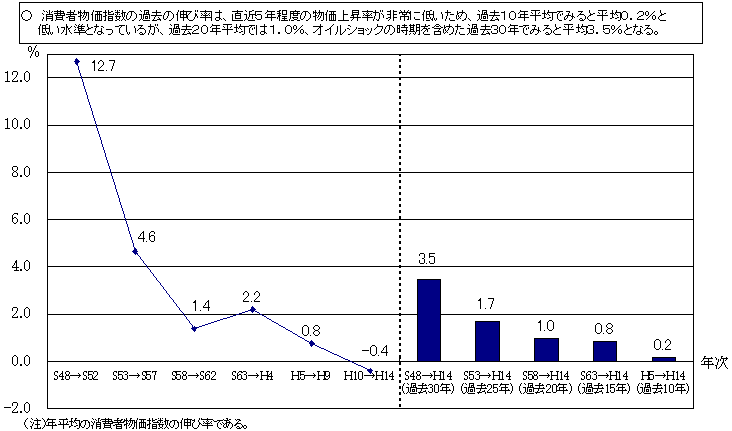
| ○ | 平成11年財政再計算では、前回再計算の検討を行っていた平成10年当時の過去10年間の実績より1.5%と設定した。 |
| ○ | 過去の実績を見ると、直近5年程度の物価上昇率が非常に低く、逆にオイルショック期の物価上昇率が非常に高いため、過去10年平均でみると平均0.2%と低い水準となっているが、過去20年平均では1.0%、オイルショックの時期を含めた過去30年でみると平均3.5%となる。 |
《長期の物価上昇率の前提を定める上での論点》
| ○ | 過去の実績より長期の前提を定める場合、どの程度の過去期間を見るのが適切か。 |
| ○ | 過去の実績以外で参考となるものがあるか。 |
(4)長期の実質賃金上昇率の前提
図表2 実質賃金上昇率(単年当たり)の推移
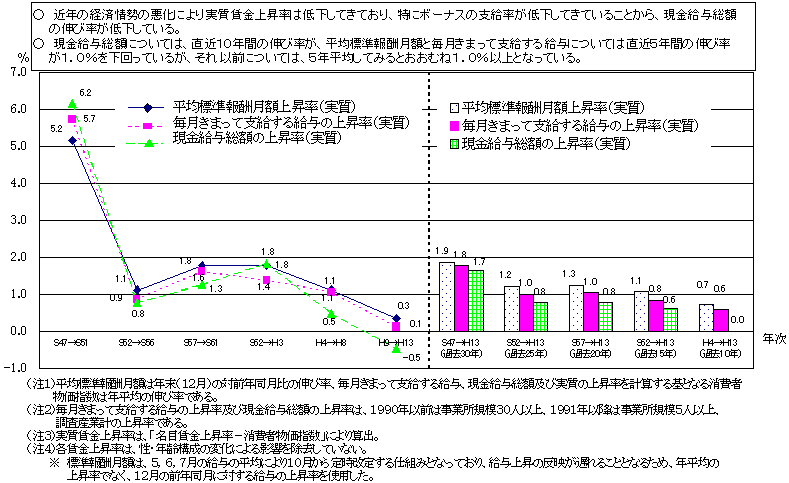
図表3 各機関の実質経済成長率の見通し
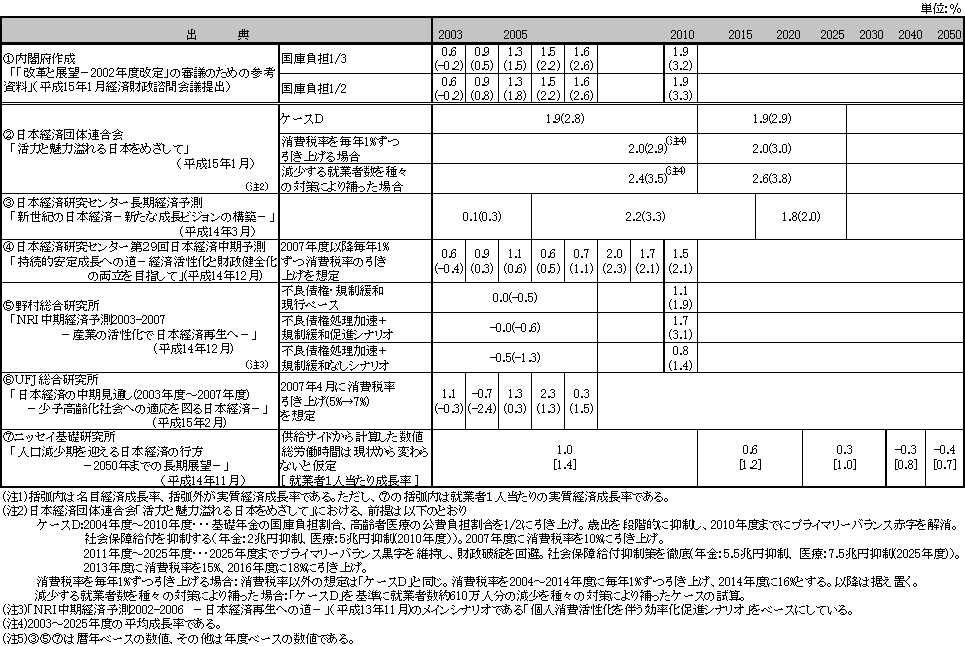
図表4 「年金改革の骨格に関する方向性と論点」の試算における総賃金の増加率(実質)の見通し
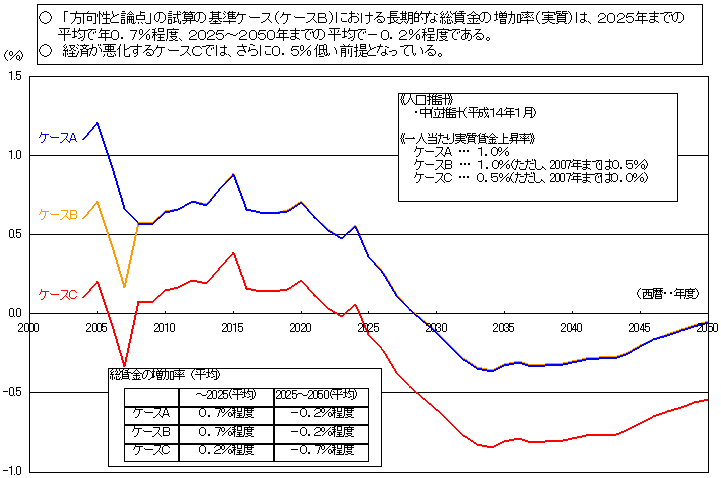
| ○ | 平成11年財政再計算では、当時の過去10年間の実質賃金上昇率の実績が1.0%であったことと、各種の長期の経済成長率の見通しが概ね1.0%程度であったことを踏まえ、長期の実質賃金上昇率を1.0%と定めた。 |
| ○ | 過去の実質賃金上昇率の実績をみると、近年の経済情勢の悪化により実質賃金上昇率は低下してきており、特にボーナスの支給率が低下してきていることから、現金給与総額(実質)の伸び率が低下している。これを反映し、現金給与総額(実質)については、直近10年間(H4→H13)の伸び率が、平均標準報酬月額(実質)と毎月きまって支給する給与(実質)については直近5年間(H9→H13)の伸び率が1.0%を下回っているが、それ以前については、5年平均してみるとおおむね1.0%以上となっている。 |
| ○ | 「改革と展望の参考資料」では、2010年のマクロの実質経済成長率を1.9%と見込んでおり、民間シンクタンクにおいても、2010〜2025年ごろのマクロの実質経済成長率をおおむね1.0〜2.0%と見込んでいる。 |
| ○ | 長期の実質賃金上昇率の前提を考える上では、将来、労働力人口が減少していく中で、マクロの指標と一人当たりの指標の間に労働力人口減少分の乖離が生じることを考慮しなければならない。 |
| ○ | 年金改革の骨格に関する方向性と論点」の試算における一人当たり実質賃金上昇率の前提から、総賃金の増加率(実質)を考えると、2025年までの平均でみて、ケースA及びケースBで年0.7%程度、ケースCで年0.2%程度となり、各種の長期経済見通しにおける実質経済成長率と比べると、ケースA、ケースBでも最も低い実質経済成長率と同程度の水準となっており、ケースCにおける0.2%のような低い水準の実質経済成長率の見通しは見あたらない。 なお、試算における2025年以降の一人当たり実質賃金上昇率の前提から、総賃金の増加率(実質)を考えると、2025〜2050年までの平均でケースA及びケースBで年−0.2%程度、ケースCで年−0.7%程度に相当することとなる。 |
《長期の実質賃金上昇率の前提を定める上での論点》
| ○ | 過去の実績から長期の前提を定める場合に、直近5〜10年間の実質賃金上昇率が低いことをどのように評価するか。 |
| ○ | 「改革と展望の参考資料」等の各種経済見通しでは、おおむね1.0%以上の実質経済成長率を見込んでいることをどのように評価するか。 |
(5)長期の実質運用利回りの前提
図表5 運用利回り(実質)の推移(昭和61年度〜平成12年度)
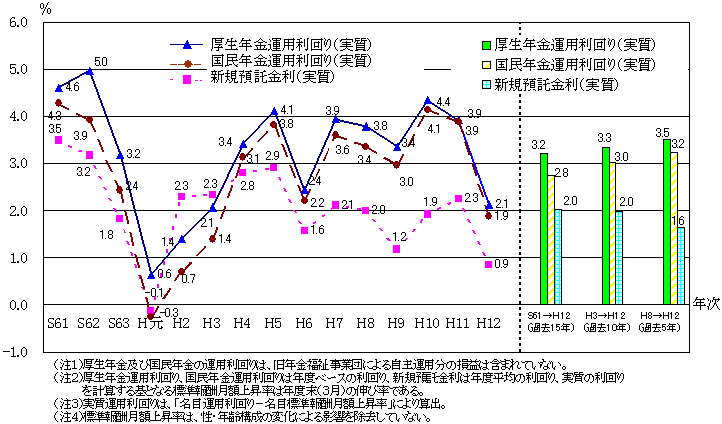
(参考1)厚生年金及び国民年金の運用利回り(名目)の実績(昭和61年度〜平成12年度)
| 過去15年(平均) (S61→H12) |
過去10年(平均) (H3→H12) |
過去5年(平均) (H8→H12) |
|
| 厚生年金 | 5.4% | 4.8% | 4.1% |
| 国民年金 | 4.9% | 4.5% | 3.9% |
| 注1: | 旧年金福祉事業団による自主運用分の損益は含まれていない。 |
| 注2: | 年度ベースの名目運用利回りである。 |
(参考2) 旧年金福祉事業団及び年金資金運用基金の運用利回り(名目)の実績
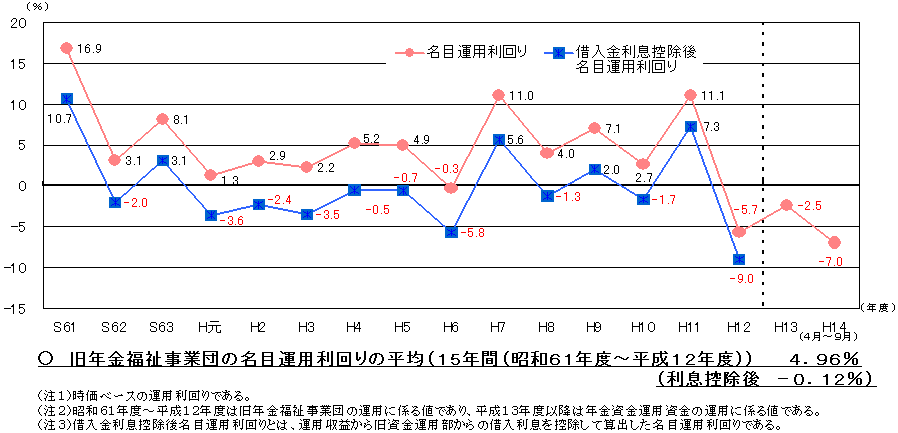
《平成13年度(全額自主運用への移行期)の運用利回り》
| 名目運用利回り | 実質運用利回り | ||||
| 積立金全体 | 積立金全体 | ||||
| 市場運用分 | 財投債引受け分 | 財政融資資金預託分 | |||
| 厚生年金 | 1.99% | −2.59% | 1.13% | 3.02% | 2.27% |
| 国民年金 | 1.29% | −2.59% | 1.13% | 2.57% | 1.56% |
| (出所) | 平成13年度厚生年金保険及び国民年金における年金積立金運用報告書 |
| (注1) | 市場運用分は運用手数料等控除後の数字である。 | |
| (注2) | 実質運用利回りは、(1+名目運用利回り÷100)÷(1+名目賃金上昇率÷100)×100−100により求めている。 ここで、名目賃金上昇率は、年齢構成の変動による影響を控除した名目標準報酬月額上昇率である。 |
| ○ | 公的年金は債務である年金の給付額が賃金上昇率に連動して上昇する仕組みであるため、公的年金の積立金の運用においては、名目の運用利回りでなく、賃金上昇を上回る実質的な運用利回りをどれだけ確保できるかが重要である。 |
| ○ | 預託金利が市場金利に変動して定められることとなった昭和62年度以降の厚生年金及び国民年金の実質運用利回りの推移を見ると、年度により変動はあるが、前回財政再計算の前提とした1.5%をおおむね上回っている。特に近年、名目の預託金利や名目賃金上昇率が下降局面となった状況で、過去の預託分の金利が比較的高いことから厚生年金及び国民年金の実質運用利回りは高い水準にあるが、今後、過去の高い金利で預託した資金が償還されるに伴い近年の低金利状況が反映されるため、預託分の名目運用利回りは低下していくこととなる。 |
| ○ | 年金積立金は、平成12年度までは全額を旧資金運用部へ預託することが義務づけられていたが、財投改革に伴い、平成13年度から義務預託が廃止され、厚生労働大臣が年金積立金に最もふさわしい方法で自主運用する仕組みへと大きく変わった。 |
2 被保険者推計に係る前提
(1)将来推計人口
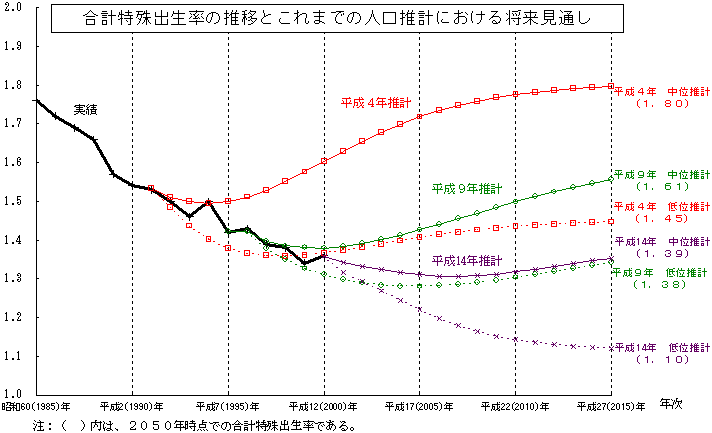
| ○ | 少子化傾向が顕著になった平成に入ってからの人口推計をみると、新しい人口推計における中位推計値が、直近の人口推計の低位推計値に近い値で見直されてきている。これまでの財政再計算では、将来推計人口の中位推計を基本としてきており、5年ごとの財政再計算において、年金の収支見通しが前回の予想以上に悪化する原因となってきた。 |
| ○ | 過去の人口推計では、足下での出生率の低下は晩婚化に伴う一時的な現象と捉え、中位推計における出生率が一定程度回復する見込みとなっていたが、今回の人口推計(平成14年1月推計)では、結婚した夫婦の子供の数にも低下の傾向がみられることから、その影響を織り込み、中位推計において出生率が現在の水準程度で推移するものとなっている。 |
| ○ | 将来推計人口は、出生率については一定の幅を持ってみる必要があるため、中位推計だけでなく、高位推計や低位推計についても参考とする必要がある。 |
| ○ | 平成9年の将来推計人口における国際人口移動は、過去の実績をみると日本人は一貫して出国超過であるのに対し、外国人は概ね入国超過となっているが、日本人、外国人ともに時系列的に一定しておらず特定の傾向が見られないことから、日本人、外国人を区別せず、直近5年間(平成2年10月〜平成7年9月)の男女年齢別入国超過率の平均値により一定と仮定した。 |
| ○ | 一方、平成14年の将来推計人口における国際人口移動は、過去の実績をみると日本人は一貫して出国超過であり1995年以降4万人台と比較的安定しているのに対し、外国人についてはほぼ入国超過であり、近年増加傾向にあることから、日本人と外国人を分けて仮定し、外国人については増加傾向にあることを織り込み、入国超過数の仮定は、2001年の男子2.9万人、女子3.3万人から2025年に男子4.4万人、女子5.0万人に増加し、その後一定と仮定している。 |
(2)労働力率の見通し
《労働力率の見通し(平成14年7月、厚生労働省職業安定局推計)》
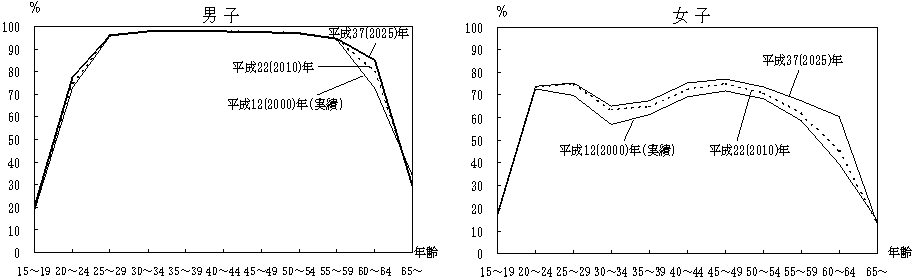
《労働力率の見通し(平成10年10月、労働省職業安定局推計)》
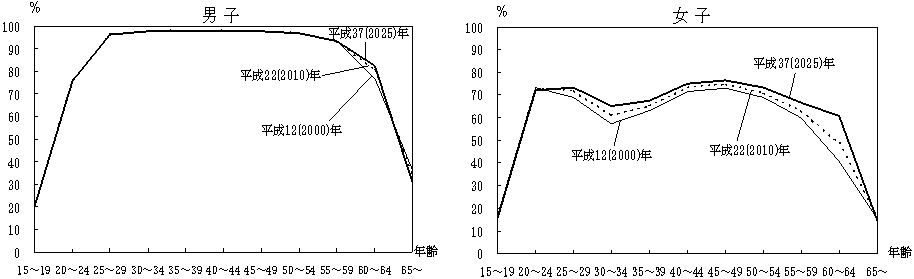
労働力率の推移と見通し
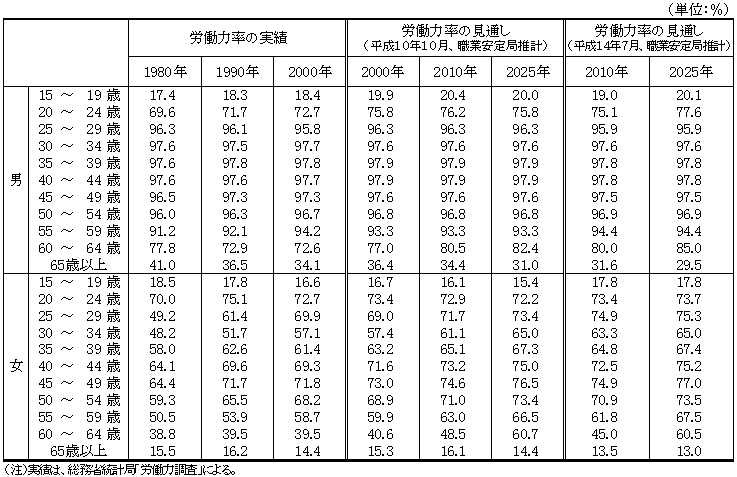
| 《「方向性と論点」の試算上の生産年齢人口(20〜65歳)の減少率と厚生年金の被保険者数の減少率》 |
| 〜2025年(平均) | 2025〜2050年(平均) | |
| 生産年齢人口の減少率 (20〜65歳) |
−0.7%程度 | −1.2%程度 |
| 厚生年金の被保険者数 | −0.3%程度 | −1.2%程度 |
| 注: | 労働力率は、2025年までは職業安定局推計(平成10年10月)、2025年以降は一定と仮定して厚生年金の被保険者数を推計している。 |
| ○ | 平成11年財政再計算では、労働力率の見通し(平成10年10月、当時の労働省職業安定局推計)を使用した。 |
| ○ | 前回の財政再計算で使用した労働力率の見通し(職業安定局推計)は、進学率(上昇傾向)、短時間労働者比率(上昇傾向)、年金支給額と現金給与総額の比率(60〜64歳については支給開始年齢の引上げに伴い年金額の比率が低下)等と労働力率の関係を表す回帰式を求め、その前提の下に労働力の見通しを試算したものであり、その結果、女性や高齢者について引き続き労働市場への参入があるものと見込んだ。 |
| ○ | 平成14年7月に新しい労働力率の見通し(職業安定局推計)が出されているが、手法、結果ともに平成11年財政再計算に使用した平成10年10月推計と大きな変化はない。 |
| ○ | 職業安定局推計の労働力率の見通しは、2025年までの推計である。このため、2025年以降は、労働力率は一定と仮定し、平成11年財政再計算や「方向性と論点」の試算は行っている。この結果、「方向性と論点」の試算では、2025年までは生産年齢人口の減少率より被保険者数の減少率は0.4%程度小さいが、2025年以降は生産年齢人口と同じように被保険者数が減少する見込みとなっている。 |
| ○ | 2025年以降も引き続き女性や高齢者の労働市場への参入が進めば、2025年以降も労働力率が上昇することとなるが、2025年以降も労働力率が上昇するような仮定をおくことについてどのように考えるか。 |
3.その他の前提
| ○ | 財政再計算においては、経済前提や被保険者推計に係る前提のほか、脱退率、失権率等の様々な前提おいて将来の被保険者及び年金受給者等の状態を年次別に推計し、財政見通しを作成している。 |
|
| ○ | 平成11年財政再計算においては、これらの前提については、直近3年の実績を基に作成した。なお、死亡による年金失権率及び脱退力については、将来推計人口(平成9年推計)の死亡率の改善に伴い、将来、失権率及び脱退力が低下する前提としている。 |
|