| 資料2 |
1.はじめに
人に対して健康被害を与える可能性のある病原微生物は多様であるが、水道水を介して伝播するものは主に腸管系の病原微生物あり、糞便による水の汚染が原因している。このため、現行の水質基準では、糞便性汚染指標及び現存量指標(ひいては塩素消毒が適正に行われているか否かの判定指標)として、それぞれ「大腸菌群」及び「一般細菌」が定められている。
これらの指標については、最新の知見に照らして見直しが行われるべきであり、本専門委員会においては、この機会に再評価を行うこととした。具体的には、
| 1) | 「大腸菌群」に代えて直接的に糞便由来である「大腸菌」を水質基準とすること |
| 2) | 一般細菌」の妥当性と従属栄養細菌(Heterotrophic Plate Count, HPC)の追加、あるいはHPCへの転換の可能性 |
について検討を行うこととした。
また、クリプトスポリジウム(Cryptosporidium Parvum)等の塩素耐性を持つ病原微生物による汚染、あるいは配管系や受水槽等でのレジオネラ(Legionella)を含む微生物の増殖(regrowth)の問題への対応が新たな課題となっており、これらへの対応が必要となっている。
このうち、クリプトスポリジウム等の塩素耐性を有する病原微生物については、現在、厚生労働省において暫定対策指針を策定し、水道事業者等の指導に当たっているが、ここでは次の点について検討を行うこととした。
| 1) | クリプトスポリジウム等に関し、暫定対策指針から一歩進めて水質基準を設定することの是非 |
| 2) | 病原微生物対策として消毒等の措置を規定している水道法第22条に基づく措置として、塩素消毒に加え、塩素耐性微生物に係る措置(具体的には、これらの微生物の存在が疑われる場合における適正なろ過操作を行うべきこと)を加えることの是非 |
2.現行水質基準項目の再評価
現行水質基準項目である「一般細菌」と「大腸菌群」に関し検討を行ったところ、水質基準項目としては、以下の2項目とすることが適当であると考えられる。
| 一般細菌 | : | 1mlの検水で形成される集落数が100以下であること |
| 大腸菌 | : | 検出されないこと (ただし、検水量は100ml) |
本来、水道水に係る基準値の設定の意義は、基準値の遵守により高品質な水道水の供給若しくは、水道水を介した健康被害の回避に寄与することにある。しかしながら、全ての危害物質が基準項目になじむものではなく、長期曝露による健康被害を生じさせる物質でその濃度の変動がないか若しくは、変化の時間軸が長い物質が対象となる。
一方、短期曝露により健康被害が予見される危害物質、濃度変動が大きいか若しくは、変化の時間軸が短い物質に対しては連続監視あるいは相当の頻度でのモニタリングにより汚染を把握し、一連の浄水処理で汚染防止、除去若しくは、消毒による不活化が原則となる。病原微生物は短期曝露により健康被害が予見されることなど、その特性から連続監視の対象となる危害物質に分類される。水道法第4条には「病原生物に汚染され、又は病原生物に汚染されたことを疑わせるような生物若しくは物質を含むものでないこと」と規定されており、その理念には上述の原則が強く反映されている。
ところで、現行の水質基準では微生物に係る項目として一般細菌および大腸菌群が定められており、定期検査(年に12回)においてそれらが検出若しくは、存在しないことを確認している。いうまでもなく本措置は日々の工程管理に資すべき情報の蒐集を目的としたものではなく、もっぱら最終産物である水道水の品質保証にある。保証すべき品質とは病原微生物による汚染のないことであるが、一般細菌および大腸菌群はいずれもそれ自体が病原微生物ではなく、汚染の有無を表現する包括的な代替指標と位置付けられている。
ところで、これらの基準項目が制定(導入)された当初は「一般細菌は緩速ろ過施設におけるろ過効率評価の指標」として、また、「大腸菌群は糞便汚染の指標」と位置付けられていたものと承知する。基準項目の導入からほぼ一世紀が過ぎた今日では、水道を取り巻く環境あるいは検出技術などあらゆる面で当時とは大きく様変わりしている。この間、これら項目に係る検査方法は繰り返し見直され改良が重ねられ、あわせて指標の意味論も討議されてきた。
病原微生物対策の原則は連続監視により汚染を検知し、浄水への混入を未然に防ぐことである。
現行の浄水システムにおいては、そもそも近代水道は、飲料水を介した感染症の発生防止を目的として始まった経緯があり、微生物対策については、ことのほか注意が払われている。具体的には、糞便性の汚染が排除できない表流水を原水とする浄水場では、必ず微生物の付着が疑われる異物を除去するためのろ過施設を設置しているほか、浄水の最終工程では塩素による消毒が行われている。また、水道法においても、第5条で消毒設備の設置を義務付けているほか、第22条で消毒の実施を義務付けている。さらに、第23条において、人の健康を害するおそれがあるときは給水を停止すべきことを義務付けている。併せて、水質基準に示される微生物項目の定期検査により、基準が遵守せられていることの確認がなされている。
一連の浄水処理は、各々の工程につきpH、濁度(粒子数)、凝集剤添量、水温、塩素注入量、残留塩素濃度、その他適宜物理・化学的パラメータを定めてその連続監視を通して運転状況の把握・管理がなされている。すなわち、本システムは基本的に食品製造分野で開発・導入された衛生管理計画(Hazard Analysis and Critical Control Point: HACCP)、あるいはWHOの水安全計画(Water Safety Plan)と概念を共有するものである。今後とも、その維持・強化に努める必要がある。
かつて、水道水を介する主要な感染症はコレラやチフスあるいは赤痢といった腸管系細菌による感染症であった。基本的には、今日もこの構図に変りはない。その一方で、わが国においても水道を介したクリプトスポリジウム症の集団発生を経験したように、クリプトスポリジウム等の耐塩素性病原微生物による汚染問題は深刻である。また、レジオネラ属菌など配管系で増殖する可能性のある病原体が新たな脅威として関心をよんでいる。今般の水質基準改定に際してはこのような状況の変化を基準項目等に反映させる必要がある。
水道の分野における微生物汚染への対応はRobert Kochの業績に始まり、緩速砂ろ過により細菌聚落数(現在の一般細菌に相当)が 100個/ml 以下に制御(ろ過除去)された水道水を介してコレラやチフスが発生していないことを根拠として、細菌数の測定をろ過工程評価に採用したことである。わが国においてもこの目的で一般細菌が導入された。
ところで、わが国ではこれまで一貫して水質基準に一般細菌を採用してきた経緯があり、浄水の現場ではこの指標を有効活用すべく創意工夫がなされてきた。その結果、検出対象の細菌類が限定されるものの、検出に要する時間が24時間程度と短く検査方法も簡便であることから、工程管理的要素を加味した指標細菌として活用している浄水場も少なくない。
上水試験方法(日本水道協会)等の記載によれば、一般細菌の指標性に関して、幾つかの異なった機能が解説されている。一義的には、細菌の現存量指標として意味付けされているが、一方では塩素消毒が確実に行われているか否かをチェックするためにも用いられる、とされている。さらに、糞便や下水等に見られる従属栄養細菌は比較的高い栄養(現行の標準寒天培地)の培地に成育し、36℃付近で速やかに生育するのに対して、多くの環境由来の従属栄養細菌は生育し難く、増殖速度も遅いことが知られている。そのため、糞便等の汚染がある場所では一般細菌数の増加が認められるとし、糞便汚染の指標となり得るとも説明されている。また、場合によっては、本来的な指標、すなわち水処理工程における細菌学的な水質改善効果の判定等に有効であるとの解説もある。
今日の水道にあっては、細菌の現存量の把握は一般細菌に代わって従属栄養細菌を用いるのが適当と考えられる。その理由は、従属栄養細菌は本来的な水中細菌数を表現すること、培養方法が確立していること、配水系等での生物膜やスライムの形成など水道施設の清浄度の劣化を端的に表現する指標として優れていること、等々である。また、今般問題となっているレジオネラ属菌は水中に形成された生物膜中の原生動物(アメーバ等)を宿主として増殖する菌で、従属栄養細菌との量的相関は認められないものの、従属栄養細菌の測定を通してその水系がレジオネラの増殖を許す環境であるか否かの判定が可能である(Guidelines for drinking-water quality)。従属栄養細菌の培養方法が確立された今日では、多くの国が従属栄養細菌測定を行っている。
しかしながら、わが国では従属栄養細菌は限られた水道施設において試験的に計測されているに過ぎず、十分な基礎資料の蓄積がない。一方、一般細菌は現行の培養条件から、従属栄養細菌の一部の細菌を検知するに留まり、感度が劣るものの、従属栄養細菌との量的相関が認められること、培養技術が確立していること、培養時間が短いことから、当面は水質基準項目として据え置くことが妥当と考える。
水系感染の主な原因菌が人を含む温血動物の糞便を由来とすることから、水道の微生物学的安全性確保に向けては糞便汚染を検知することがきわめて重要と考えられる。すなわち、水道水の品質保証という観点から糞便汚染の検知には高い精度が求められる。大腸菌は糞便汚染の指標として適当と判断される。
今日まで、大腸菌群を代替指標として用いてきたが、糞便汚染の指標性は低い(別紙1)。大腸菌群が基準項目に設定されるに至った経緯をみても明らかなように、指標細菌として大腸菌を用いるべきであった。然るに、大腸菌群が採用された理由は、単に当時の培養技術が制約となっていたに過ぎない。今日では、迅速・簡便な大腸菌の培養技術が確立されており、技術的問題は解決されている。(別紙1)
上述のとおり、細菌の現存量の指標としては有効と考えられるものの、我が国の水道における情報等の不足から、従属栄養細菌を水質基準とすることは見送らざるを得なかった。
このため、よりよい基準の設定に向け、今後、従属栄養細菌に関する調査研究が一層促進されることが望まれる。具体的には、
| 1) | 従属栄養細菌に関する資料の収集・解析を進め、現存量指標としての有効性を確認すること |
2) |
これに併せ、培養方法の普及に努め、水道事業体を始めとする関係者の協力を得て、我が国における従属栄養細菌の存在量に関するデータを収集すること。 |
3.クリプトスポリジウム等の耐塩素性病原微生物対策
病原微生物を対象とした即時監視は技術的制約から現実的とは考えられない。本件に関する現実対応の要点は、あらかじめ水源域における汚染源の特定、汚染の機会やその程度、および変動量等々を把握し、その汚染の程度に見合った処理技術を設備し、管理・運転させることである。注意すべきことは、クリプトスポリジウム等の耐塩素性病原微生物には塩素消毒が無効なことで、これに代わる措置が必要となることである。
1994年以降わが国でも顕在化したクリプトスポリジウム等の耐塩素性病原微生物による汚染問題は水道水の衛生行政上重要課題となっている。このため、厚生労働省においては、平成8年10月、「水道におけるクリプトスポリジウム暫定対策指針」(以下「暫定対策指針」という。)を策定し、クリプトスポリジウム等による汚染のおそれの検討及び汚染のおそれがある場合における適切なろ過処理を指導してきた。また、平成12年4月に施行された「水道施設の技術的基準を定める省令」においては、原水に耐塩素性病原微生物が混入するおそれがある場合にはろ過等の設備すべき旨規定された。
この結果、我が国では原水中におけるクリプトスポリジウムなどの検出事例や浄水中での検出による給水停止事例は毎年報告されているものの、対策指針策定の契機となった埼玉県越生町の水系集団感染(平成8年6月)以降に大規模な感染事故の発生はない。このこと及び各国の状況及び今般のWHOガイドライン等に照らし、暫定対策指針の基本姿勢及び水道事業体に求めた措置は正しいものと判断されるが、万全を期すためには、今回の水質基準の改正を機に一層の対策の充実・強化を行っていくことが肝要である。
暫定対策指針策定から6年が経過した現在、クリプトスポリジウム等に関する対策が必要とされる浄水施設数は平成14年4月現在3,404施設あるが、このうち、対策済みの施設数は1,916施設に止まっている(厚生労働省集計)。水道水の安全に万全を期するためには、これら耐塩素性病原微生物に対する対策を一層推進していく必要がある。
わが国では塩素耐性を有する病原微生物のうちクリプトスポリジウムおよびジアルジアが水道水系から検出されており、また、水道水を介したクリプトスポリジウムによる集団感染事例を経験している。したがって、これらの2種類の原虫類には引き続き注意が必要であるが、将来的に起こり得るCyclosporaなど新たな病原微生物への対策も積極的に検討する必要がある。
上述のとおり、病原微生物対策は、原則として汚染を未然に防ぐことにあり、そのためにはあらかじめ水源域における汚染源の特定、原水汚染の機会、程度、その変動量等々を把握することが重要である。その上で、対策上で必要な処理能力を有する設備の導入・充実、あるいは改善をはかることで安全が確保されるものである。
暫定対策指針においては、検査の実行性の観点から、通常、試料水10Lを用いてクリプトスポリジウムの存在の有無を検査することとしている。仮に、原水中に1個/10Lのクリプトスポリジウム・オーシストが検出された場合におけるリスクをWHOが提唱する参考許容値(Reference Level of Acceptable Risk、単位はDALYs)の考え方を用いて試算すると、ろ過等の措置を行わない場合には、WHOの参考許容値(1.4×10-6DALYs)を大幅に上回る(100倍)。一方、浄水操作により2log除去(99% 除去)が保証された場合には、リスクは概ねWHOの参考許容値と同程度の水準にあるといえる。換言すれば、原水中に1個/10L程度の汚染であってもオーシストが検出された場合には適切な浄水操作が必要であることを示すものでもある。(別紙2)
ところで、通常の日感染リスクが十分に低いものとすると、年間感染リスクは日感染リスクの和に近似することが想定できる。その結果、感染リスクに係る様々な変動要因がある中で、年間感染リスクは特異的に高い値を示す日感染リスク値に強く影響される。ひるがえって、その特異的に高い値を発生させない措置を講じることで年間感染リスクは低く抑えられることが、原水中のオーシスト調査の結果を基にしたモンテカルロ・シミュレーションにより示されている。(別紙3)
上記のシミュレーションでは、相当量の浄水に存在するオーシストを常時監視し、その結果を日々の給・配水の可否判断に反映させるという想定となっており、実際上の浄水管理には適応し得ないものである。しかしながら上記の研究では、年間感染リスクに影響する変動要因が種々ある中で、年間感染リスクは特異日の感染リスクに大きく影響されていること、その特異日を排除する(発生させない)ことが安全につながるという方向性が明確に示されている。実際上の浄水場の運営にあって、「特異日を発生させない」措置とは、対策指針に示されるところの「ろ過施設の整備と浄水工程の管理強化」措置である。
したがって、本専門委員会としては、対策指針に示された方針の一層の維持・強化を目指し、水道法第22条に基づく措置として、消毒に加え、塩素耐性微生物に係る措置(原水がクリプトスポリジウム等により汚染され、又は汚染されているおそれがある場合には、適切なろ過操作を行うべきこと)を加えることが必要であり、これによって、耐塩素性病原微生物対策が促進されるものと考えるものである。
なお、水質基準とすることについては、仮に米国環境保護庁(USEPA)で用いている微生物許容感染リスクの考え方(10-4/年以下)を採用したとしても、極めて多量(15トン)の試料水を用いて検出されないことを確認することが求められるところとなり、現実的ではないと考えられる。
クリプトスポリジウム等による汚染のおそれについては、暫定対策指針において、「水道の原水から大腸菌群が検出されたことがある場合」又は「水道の水源となる表流水、伏流水若しくは湧水の取水施設の上流域又は浅井戸の周辺に、人間又は哺乳動物の糞便を処理する施設等の排出源がある場合」に、指標菌(大腸菌及び嫌気性芽胞菌)の検査を行い、これが検出された場合に「汚染のおそれ」があると判断することとされている。しかしながら、排水処理として塩素消毒がなされている場合があることを想定すれば、大腸菌を指標とすることに蓋然性を欠く事態も生じ得る。
クリプトスポリジウム等による汚染は、水源域における人間又は哺乳動物の糞便処理施設及びその排出源等の人口汚染源、降雨や融雪などに伴った農業用地からの流入汚染、または野生動物の活動などが直結する原因であり、レクリエーション等で水源への人の出入りや、地層の亀裂など地質学的な特性も汚染につながる要素となる。
このようなことを考えるとき、暫定対策指針に示されている判断基準については、さらに検討が加えられ、よりよいものとしていくことが望まれる。
原水がクリプトスポリジウム等により汚染され、又は汚染のおそれがあると判断される場合には、適切なろ過措置を義務付けるべく、法令による措置を提言してきたところである。
これらの提言は、暫定対策指針の根幹部をなすものであり、その性格は変わらざるを得ない。しかしながら、水道水中の耐塩素性微生物対策は、今回の提言に限られるものではなく、汚染のおそれの判断→適切なろ過施設の整備→適切なろ過管理と循環する総合的な対応が求められる。
このような観点からすれば、今後とも、暫定対策指針は、法令上の措置の解説として、また、水道における耐塩素性病原微生物対策の総合的対策書として機能させることが有益である。
なお、上記3)を踏まえて対策指針の改訂が必要と考えられる。また、その際には、これらの微生物については、常時監視が不可能であることから、水質管理の万全を期すためには、地域性などに応じ、原水汚染のおそれを事前に把握し、その上で、それに対応した管理を行うことが必要であり、食品衛生分野における危害分析・重要管理点(HACCP)やWHOの水安全計画(Water Safety Plan)などの考え方に十分配慮がなされるべきである。この意味で、暫定対策指針が指導的な役割を担うような形で位置付けられることが望まれる。
これまでのクリプトスポリジウムの集団感染事例から学ぶところは、高濃度汚染が一過性、あるいは間欠的に発生する点である。このような異常事態への対処方法は事前と事後に分けられる。望むべくは、事前に汚染を察知して事故を未然に防ぐことである。しかしながら、原虫そのものを対象として常時連続監視することは非現実的で、取水地点における原水濁度の急激な変化(上昇)などの意味付けを適正に行い、浄水管理に反映させることが望まれる。このことは現行の暫定対策指針においても述べられているところである。
一方、異常事態が発生した場合には、当該事態への速やかな対応が求められる。その際、集団感染の汚染源の特定は被害を最小限にとどめるために、事後の措置として採るべき最重要課題の一つである。そのため、各浄水場においては配水の一部あるいはその沈渣を一定期間保存する制度の導入を検討すべきものと考える。その詳細は、暫定対策指針において示すことが必要である。
今回の報告では、クリプトスポリジウム等の除去対策としてろ過による対策を提言したところであるが、紫外線(UV)照射による不活化等の研究も進められており、クリプトスポリジウムのオーシストやジアルジアのシストに対し顕著な不活化効果が示されている。
しかしながら、その一方で強いUV耐性を有する原虫類(トキソプラズマ)のオーシストの存在も知られるところとなっている(Sobsey 私信、 2002)。したがって、その使用は特定の病原体を対象とした消毒措置として限定的に扱われることが妥当と考えられる。今後とも、これらの研究の発展に努めるとともに、有効と認められる場合には、対策指針を逐次改訂し、除去対策として採用していくことが望まれる。
クリプトスポリジウムやジアルジアは、ヒトや家畜などの哺乳類から排泄され、それによって汚染された飲食物や飲料水を経由して人間が摂取することで感染するものである。
従って、水道における感染防止対策としては、浄水処理工程での除去・不活化は不可欠であるが、基本は原水の保全であり、その対策が推進されるべきである。なお、この場合において、クリプトスポリジウムなどの耐塩素性の病原微生物に注意して対策を実施することが必要である。
病原微生物については、常時監視が不可能であることから、水質管理の万全を期すためには、地域性などに応じ、原水汚染のおそれを事前に把握し、その上で、それに対応した管理を行うことが必要である。
しかしながら、小規模水道、特に零細規模の水道においては、財政的及び人的資源の不足からこれらの対策が適切に講ずることができないことが懸念される。このため、WHOが提言しているとおり、例えば、一定規模以下であり、かつ、これら微生物による汚染に関する一定の条件を満たす場合には、無条件にろ過施設の導入を義務付ける、といった制度の導入についても検討する必要がある。
別紙1 一般細菌、従属栄養細菌、大腸菌群
1. 一般細菌
水道における微生物学的な管理は、19世紀末のRobert Kochの業績によるところが大きい。コレラやチフスの集団感染は砂ろ過により細菌聚落数(現在の一般細菌に相当)が <100個/1ml に制御された水道水を介して発生しない、という観察事実に依拠したものであった。ドイツでは、その後この値が緩速ろ過の基準に採用された。わが国においても1904年に導入され、緩速ろ過池の運転管理に用いられてきたことは周知のことである。
当初の培養技術は現在のそれと比べるべくもないが、培地成分にゼラチン(25℃付近でゾル化)が用いられており、培養温度は20℃付近に設定されていた。その後の培養方法の変遷を見ると、必ずしも指標細菌としての一般細菌の位置付け(理解)が一様ではなかったとの印象がある。
まず、大きな変化として、培地成分として寒天の利用があげられるが、これにより培養温度を高温域まで広げることが可能となり1929年から37℃(24時間)が採用された。培養温度を温血動物の体温に近づけた真の理由は明らかではないが、病原微生物あるいは糞便汚染の把握を企図したものと推測される。ここで注意すべきは、後述するようにこの時点ですでに糞便汚染の指標として別途大腸菌群の導入が図られていた点で、糞便汚染あるいは病原微生物汚染の代替指標が重複化する傾向を見せている点である。1950年に、水道協会協定の上水判定標準と日本薬局方による常水判定標準が厚生省の飲料水検査指針に統一され、「一般細菌数は1ml中100を超えてはならない」ことが定められた。1978年の「第4条に基づく水質基準に関する省令」(厚生省令第56号)により、それまでの普通寒天培地から標準寒天培地に変更されて現在に至っている。この改訂では培地の組成が統一されただけではなく、それまでの糞便性細菌の検出に適した高栄養で食塩含量の多い培地から低塩濃度のものに改められ、従属栄養細菌の検出に向けた修正がはかられた。しかしながら、この培養条件では従属栄養細菌のうち、中温(37℃付近)で短時間に集落を形成し、比較的高濃度の栄養条件で増殖する細菌類が検出対象となっている。従属栄養細菌分離用の培地(PGY培地、R2a 培地等)が考案されてより以降は、基準項目として従属栄養細菌を採用する国が多くなっている。
ところで、わが国では一般細菌を一貫して水質基準として採用してきたという経緯があり、浄水の現場ではこの指標を有効活用すべく創意工夫がなされてきた。その結果、検出に要する時間が24時間程度と短く、検査方法も簡便であることから、工程管理的要素を加味した指標として活用している浄水場も少なくない。上水試験方法(日本水道協会)等の記載によれば、一般細菌の指標性に関して、幾つかの異なった機能が解説されている。一義的には、細菌の現存量指標として意味付けされているが、一方では塩素消毒が確実に行われているか否かをチェックするために用いられるとされている。さらに、糞便や下水等に見られる従属栄養細菌は比較的高栄養(現行の標準寒天培地)の培地に成育し、36℃付近で比較的速やかに生育するのに対して、多くの環境由来の従属栄養細菌は生育し難く、増殖速度も遅いことが知られている。そのため、糞便等の汚染がある場所では一般細菌数の増加が認められるとし、糞便汚染の指標となり得るとも説明されている。また、場合によっては、本来的な指標、すなわち水処理工程における細菌学的な水質改善効果の判定等に有効であるとの解説もある。
上述のように、現在のところ一般細菌の位置付けは一義的には細菌の現存量指標とされる現存量とは浄水の保有する生物(細菌)量を指すもので、この概念の中にはろ過等の処理で除去できなかった残存細菌数のみならず、配管系を含む上水システム全体での微生物の再増殖(regrowth)した菌量も含まれる。
この様に一般細菌検査の目的は不明瞭となっているが、いずれの説明も正当性があるものと考えられる。導入当時と今日とでは上水施設における処理技術は大きく変容を遂げ、また、「一般細菌」という項目名こそ変わっていないが培養方法そのものも大きく様変わりしている。それにもかかわらず、一般細菌の指標性について正面から再評価してこなかったことが今日の状況を招いているものと考えられる。
2. 従属栄養細菌
従属栄養細菌とは生育に有機物を必要とする多様な細菌のことで、浄水処理過程や消毒過程での細菌の挙動を評価するのに適している。また配水系における塩素の消失や滞留に伴い増加することから、配水系の微生物学的状態を把握するには有用である。
3. 大腸菌群
な水系感染の原因菌は人を含む温血動物の糞便を由来とすることから、糞便汚染を検知することで病原体混入の危険性を探知する、といういわゆる代替指標菌を用いた検査手段が導入された。糞便汚染の指標として、温血動物の腸管内に常在する菌の内で最も数の多い(108〜9個/g)大腸菌、Escherichia coli、が選択された。しかしながら、当時の培養技術では大腸菌を直に検出する技術はなく、菌の同定には高度な細菌学的知識と複雑な培養技術が要求されていた。そこで、大腸菌が有する生化学性状のうちの5つに着目し、その性状をすべて備える細菌群をもって大腸菌を代弁させた。この細菌群が大腸菌群で、それ以降、今日まで代替指標菌として用いられている。
時経列的に見ると、大腸菌群の検査が検討された時期は1911年頃にまでさかのぼることができる。1926年に協定上水試験法の附則として採用され、1932年に判定基準(常水判定基準及試験方法)が設けられた。
その後、1966年の水質基準に関する省令(厚生省令第11号)で「大腸菌群は検出してはならない」と規定された(検水量は50ml)。周知のごとく、大腸菌群にはEscherichia属、Citrobacter属、Enterobacter属、およびKlebsiella属などが含まれており、その中には外界でも増殖可能な細菌類が含まれる。また、これら細菌類の構成比率は常に流動的である。したがって、大腸菌群には糞便汚染の指標性は低いという認識が今日の国際的な理解である。
別紙2 WHOの提起するReference Level of Acceptable Risk(参考許容値)
WHOはクリプトスポリジウムを含む微生物による汚染に対しては、原水の汚染状況の把握と汚染量を許容できる範囲(Reference Level of Acceptable Risk:参考許容値)にまで低減できる浄水処理工程の導入により対応するよう提言している。WHOの水質基準にクリプトスポリジウム等に関する項目は含まれない。
疾病ごとの健康影響は多様で、比較に際しては共通の尺度が必要となる。WHOでは感染症に限らず全ての疾病における健康影響度を『Disable Adjusted Life Years(DALYs:障害調整生存年数)』という指標を用いて表現し、それぞれの疾病毎に健康影響度を算出することで比較を行っている。その際用いる疾病毎の健康への影響度は0から1の間の値をとり、影響が全くないものを0、死を1と規定している。
DALYs値は疾病によって失われた余命(Years of Life Lost:YLL)と障害を持って過ごす時間(Years of Life Lived with a Disability:YLD)の和で、以下の式で表される。
クリプトスポリジウム症に関するDALYs値の計算は、以下の手順で算出されている。クリプトスポリジウム症の主な症状は下痢(水様便)で、疾病による負荷量の研究(Murray、1996)によると水様便の平均加重は0.066とされている。本症では下痢症状が平均7.2日(0.020年)続く。米国ミルウォーキーにおけるクリプトスポリジウム集団感染事例より、健常者での死亡は10万人当り1名(40万人のうち4名死亡)と推定される。オランダの1993〜1995の統計資料によると、下痢症が原因の死亡は75歳以上に認められ、その余命は13.2年となる。本症の発症者は感染者の71%とされる。損失生存余命(YLL)および障害をもって過ごす時間(YLD)は以下の通りとなる。
上記の結果より、健康影響度は以下の通りとなる。
1回のクリプトスポリジウム感染による健康影響度は感染者1000人あたり、1.03 DALYsと計算される。
わが国における現行の「水道におけるクリプトスポリジウム暫定対策指針」では、原水の汚染濃度把握のために、概ね10Lの試料水よりオーシスト数を測定している。仮に、原水10L中に1個のオーシストが存在するものとして、無処理あるいは上水処理後の水道水に潜むクリプトスポリジウム症のリスクを試算した(表)。クリプトスポリジウムによる感染確率は後述のHaasらの式(別紙3 Equ (1))より求められ、オーシスト1個の摂取による感染率は4.0×10-3となる。
ところでWHOは水道水中の臭素酸の摂取による腎細胞癌(Renal cell cancer)の許容発生率を10-5(1/100,000人)としている。腎細胞癌は平均65歳で発生し、その平均余命は19年である。このときの死亡確率を60% とし、症状の重さは致死であることから1とする。損失生存余命(YLL)は以下の通りとなる。
本症より派生する障害をもって過ごす時間(YLD)はYLLに比べて十分に小さく、YLDは無視できる。人の寿命を80年と仮定した腎細胞癌の年間のDALYは、以下の通りである。
すなわち、WHOの発癌物質(臭素酸)による癌の年間許容発生率は、障害調整生存年数1.4×10-6 DALYsに相当する。
表に示した試算によると、無処理(1.5×10-4)ではWHOの参考許容値を大幅に上回る。一方、2log除去が保障された上水処理(1.5×10-6)であれば、概ねWHOの参考許容値と同程度のリスク水準にあるといえる。
なお、旧建設省土木研究所資料第3533号(1998年1月)によれば全国67ヶ所の下水処施設におけるオーシストの調査では処理水中のオーシスト数は0.05〜1.6個/Lであったとされている。この数値に、河川における希釈率(10倍)を加味すれば概ね1個/10L以下と推測される。また、同調査における河川水でのオーシスト数は0.05〜3.2個/Lで(最大値の3.2個/Lは越生町におけるクリプトスポリジウム集団感染直後の越辺川の値で、これを除くと最大値は0.1個/L)、両者のデータはよく符合する。
表1 クリプトスポリジウムの年間リスク
| 原水中のオーシスト濃度 | 1個/10L | |||
| 上水処理における除去率 | 3 log | 2.5 log | 2 log | 無処理 |
| 水道水中の濃度 | 10-4個/L | 3×10-4個/L | 10-3個/L | 10-1個/L |
| 飲用日量 | 1L/日 | |||
| 曝露量/日 | 10-4個/日 | 3×10-4個/日 | 10-3個/日 | 10-1個/日 |
| 1オーシスト摂取による 感染確率 |
4×10-3 | |||
| DALYs/case 1感染あたりの健康 影響度 |
1.03×10-3 DALYs (発症率71%を採用) |
|||
| 1日あたりの感染率 ( 年間 ) |
4×10-7/日 (1.5×10-4/年) |
1.3×10-6/日 (4.7×10-4/年) |
4×10-6/日 (1.5×10-3/年) |
4×10-4/日 (1.5×10-1/年) |
| 1人あたりの年間 健康影響度 |
1.5×10-7DALYs | 4.8×10-7DALYs | 1.5×10-6DALYs | 1.5×10-4DALYs |
別紙3 微生物許容感染リスクに基づく評価
Haasらによれば、クリプトスポリジウムの用量-作用(infection probability/particle)に関する計算式は、次のとおり与えられる。
| P(N) = 1 - exp ( - N / k ) N: 摂取オーシスト個数 k: パラメータ(= 238.6) |
Equ(1) |
| Pn = 1 - ( 1 - P1 ) n Pn: 反復暴露による感染確率 n: 反復回数 P1: 単回暴露による感染確率 |
Equ (2) |
Haas CN et al., Accessing the risk posed by oocysts in drinking water. Journal of American Water Works Association 88(9):131-136,1996.
米国EPAによれば、微生物許容感染リスク10-4/年以下を満足することを目標にしている。この目標を満たすための条件を一日の水道水の飲用量を1Lとして試算すると(摂取日量の分布の97.5パーセンタイルがおよそ1000ml、矢野一好等、2000年)、Equ (2) より、
を満たすことが求められる。Equ (1) からNを求めると、N≦6.51×10-5となり、6.51×10-5個/L以下,すなわち15.4t当り1個 (6.5個/100t)と計算される(飲用量を2L/dayとすれば1個/30t)。
ところで、クリプトスポリジウムの感染リスクを考える場合、高度に汚染された原水の流入や浄水処理における障害など様々な要因で平常時の年間感染リスクを超えるような日感染確率(特異日の感染確率)が生じることを想定する必要がある。たとえば10−4を年間感染リスクとした場合、浄水中のクリプトスポリジウム濃度2.5個/100Lで日感染リスクが10-4となるが(1日飲水量1L、1個摂取した場合の感染確率0.4%として計算)、このような測定値は実際に観測され得る汚染である。
ちなみに、年間感染リスクは、感染しない確率を算出してその値を1から減じることで得られることから、次式で計算される。
| |
Equ (3) |
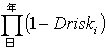 の値はほぼ 1 に近似される。ここで、特異日の感染リスクを p とすると
の値はほぼ 1 に近似される。ここで、特異日の感染リスクを p とすると 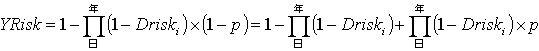 |
Equ (4) |
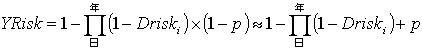 |
Equ (4') |
上記のことを念頭に入れて、仮の目標値として米国EPAの微生物許容感染リスク10-4/年以下を達成するための特異日感染リスクの排除条件を検討した研究報告がある(Masago et al., 2002)。そこでは、相模川水系におけるクリプトスポリジウムの調査結果(Hashimoto et al., 1999)をもとにモンテカルロ・シミュレーションを用い、浄水中に、ある限度以上のオーシストが含まれている日には飲用が中止されるものとして年間感染リスクの計算を行っている。詳細は原著に譲るが、シミュレーションでは水系におけるオーシストの分布様式が概ね適合すること、非加熱の水道水の飲水量はTeunis等(1997)の報告を採用(0.153L/日を中央値とした対数正規分布)、その他の変動要因として降雨による原水中のオーシスト量の変化、浄水処理効率等々が組み込まれている。その結果、対策指針に定められた条件、すなわち20Lの検水からオーシストが検出された日には給水が停止される(その日の感染リスクが0である)ものとすると、年間感染リスクの95%値はおよそ1 log程度低下することが示された。さらに、オーシスト測定の際の検水量を変化させて検討した結果、検水量をおよそ80 L以上にすることで年間感染リスクの95%値を許容リスク以下にすることができたとしている。
矢野一好、保坂三継、大瀧雅寛、田中愛、伊予亨、土佐光司、市川久浩 (2000)日本水環境学会シンポジウム講演集(摂南大学 9月13−14日)
Y. Masago, H. Katayama, A. Hashimoto, T. Hirata and S. Ohgaki (2002). Assessment of Risk of Infection Due to Cryptosporidium parvum in Drinking Water, Water Science and Technology. Water Science & Technology 46(11-12): 319-324.
Hashimoto A. and Hirata T. (1999). Occurrence of Cryptosporidium oocysts and Giardia cysts in Sagami river, Japan. Proceedings of Asian Waterqual '99: 7 th IAWQ regional conference, 2: 956-961.
Teunis P.F.M., Medema G.J., L. Kruidenier and A. H. Havelaar (1997). Assessment of the risk of infection by Cryptosporidium or Giardia in drinking water from a surface water source.
Water Research, 31(6):1333-1346.