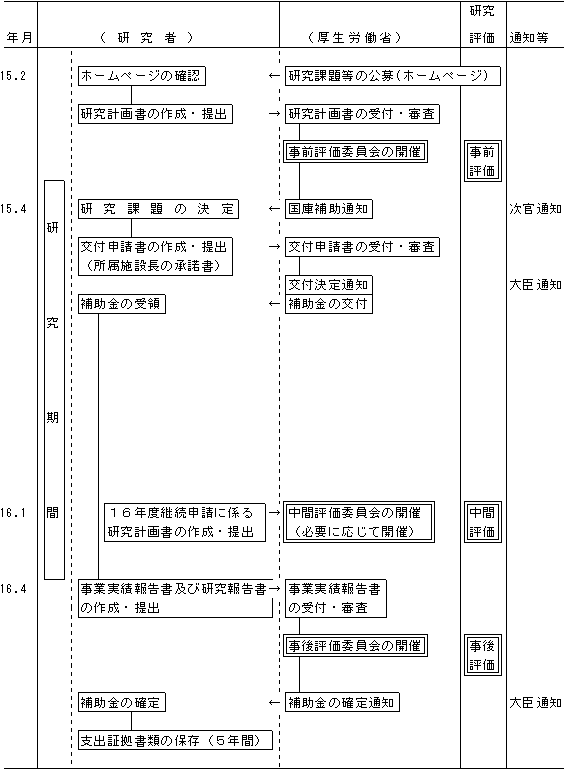| ア. | 申請できる研究経費 研究計画の遂行に必要な経費及び研究成果の取りまとめに必要な経費。 なお、経費の算出に当たっては、別添「厚生労働科学研究費補助金における補助対象経費の単価基準額一覧表(平成15年度)」により算出して下さい。 |
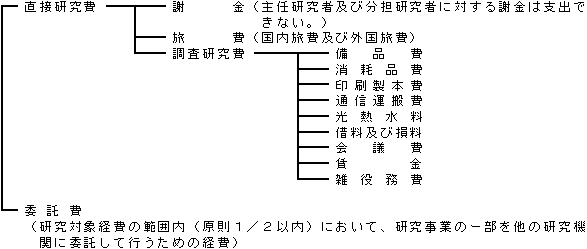
| イ. | 申請できない研究経費 本補助金は、当該研究計画を遂行する上で必要な一定の研究組織、研究用施設及び設備等の基盤的研究条件が最低限確保されている研究機関の研究者又は公益法人を対象としているので、研究計画の遂行に必要な経費であっても、次のような経費は申請することはできませんので留意して下さい。 |
| (ア) | 建設等施設に関する経費。 |
| (イ) | 研究補助者に対する月極めの給与、退職金、ボーナスその他各種手当。(若手研究者育成活用事業などの推進事業を利用してください。) |
| (ウ) | 机、いす、複写機等研究機関で通常備えるべき設備備品を購入するための経費。 |
| (エ) | 研究実施中に発生した事故又は災害の処理のための経費。(被験者に健康被害が生じ補償を要する場合に当該補償を行うために必要な保険(当該研究計画に位置づけられたものに限る。)の保険料を除く。)。 |
| (オ) | その他本補助金による研究に関連性のない経費。 |
| ウ. | 外国旅費等について 主任研究者又は分担研究者(公益法人にあっては、当該研究に従事する者であって主任研究者又は分担研究者に準ずる者)で1行程につき最長2週間の期間に限り、海外渡航に必要な外国旅費及び海外で必要となる経費(直接研究費の各費目に限る)が補助対象となっています。(ただし、当該研究上必要な専門家会議、情報交換及び現地調査又は国際学会等において当該研究の研究成果の発表を行う場合に限ります。)外国旅費等を申請する場合には、当該年度申請額の20%(ただし、最高5,000千円を限度とする。)を上限額としています。 |
| エ. | 備品について 価格が50万円以上の機械器具であって、賃借が可能なものを購入するための経費の申請は認められません。研究の遂行上、調達が必要な機械器具等については、原則的にリース等の賃借により研究を実施していただくことになります。 |
| オ. | 賃金について 賃金は主任研究者(分担研究者含む)の研究計画の遂行に必要な資料整理等(経理事務等を行う者を含む)を行う者を日々雇用する経費ですが、これらの者を補助金により研究機関においても雇用することができます。 この場合、研究機関が雇用するために必要となる経費は、補助金から所属機関に対して納入してください。(間接経費が支給される場合は除く) 国立試験研究機関(注)の研究者に公募による研究経費が交付された場合、経理事務及び研究補助に要する賃金職員は別途の予算手当によって各機関一括して雇用するため、研究経費からこれらに係る賃金は支出できません。 |
| (注) | 国立試験研究機関とは、国立医薬品食品衛生研究所、国立社会保障・人口問題研究所、国立感染症研究所及び国立保健医療科学院をいう。 |