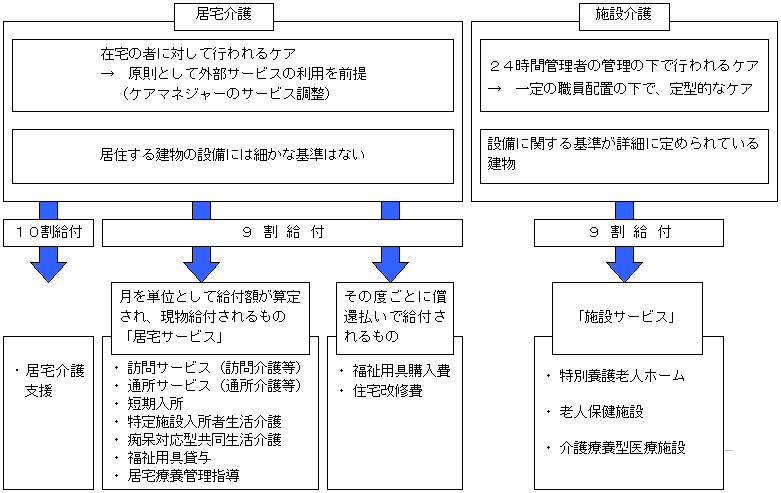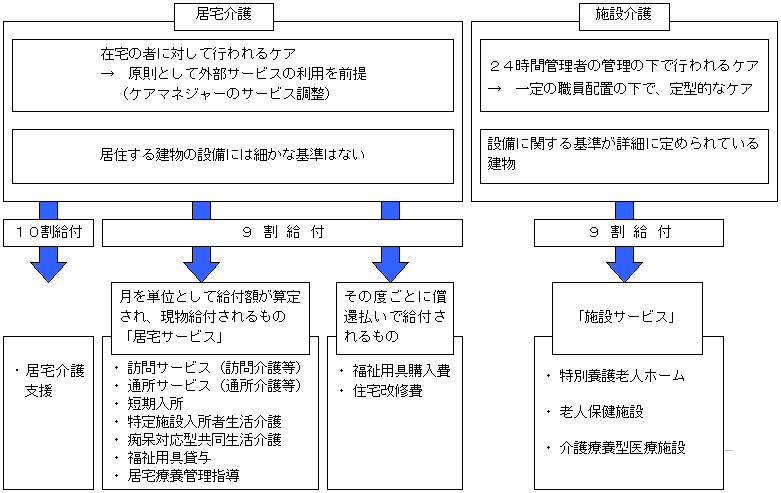戻る
<概要>
|
個別的な指導に基づくADL指導を中心とした外来リハビリテーションは、一般的な機能訓練中心の外来リハビリテーションと比較し、退院1年後、5年後のADL自立度の維持に極めて有効であることを示す研究結果は次のとおり。
-
○ 退院1週後と1年後を比較しADLが低下した者の割合
-
| ・ADL指導中心群 |
→ |
1.0% |
| ・機能訓練中心群 |
→ |
18.3% |
○ 退院1年後と5年後を比較しADLが低下した者の割合
-
| ・ADL指導中心群 |
→ |
2.9% |
| ・機能訓練中心群 |
→ |
47.1% |
|
<研究概要I(抄)>
1 対象と方法
脳卒中片麻痺患者で、病棟ADL訓練中心の入院リハビリテーションをうけて退院後、外来リハビリテーションをADL指導中心にうけた患者と機能訓練中心でうけた患者について、退院1週後と1年後のADLの変化について比較検討。
2 結果
|
退院1週後と1年後のADL自立度の変化
| |
ADL指導中心
外来リハビリ |
機能訓練中心
外来リハビリ |
有意差 |
| ADL自立度 |
維持者 |
200/202名
(99.0%) |
165/202名
(81.7%) |
P<0.001 |
| 低下者 |
2/202名
(1.0%) |
37/202名
(18.3%) |
P<0.001 |
|
<研究概要II(抄)>
1 対象と方法
脳卒中片麻痺患者で入院リハビリテーション(病棟ADL訓練中心)をうけて退院後、退院時点の自宅でのADLが最低限入浴以外の身辺 ADLは自立している患者について、外来リハビリテーションをADL指導中心にうけた患者と機能訓練中心でうけた患者について、退院1年後、5年後でADLの変化について比較検討。
2 結果
|
表1 退院1年後と5年後の間のADL自立度変化
| |
ADL指導中心
外来リハビリ |
機能訓練中心
外来リハビリ |
有意差 |
| ADL自立度 |
維持者 |
99/102名
(97.1%) |
54/102名
(52.9%) |
P<0.001 |
| 低下者 |
3/102名
(2.9%) |
48/102名
(47.1%) |
P<0.001 |
年齢
(5年後時点) |
73.4± 13.2 |
72.1± 14.2 |
N.S. |
|
|
表2 退院後1〜5年間のADL低下(一時的を含む)
| |
ADL指導中心
外来リハビリ |
機能訓練中心
外来リハビリ |
有意差 |
| ADL低下者 |
30名(29.4%)
[100%] |
51名(50.0%)
[100%] |
P<0.001 |
ADL低下後
改善者 |
27名(26.5%)
[90.0%] |
3名(2.9%)
[5.9%] |
P<0.001 |
ADL低下後
非改善者 |
3名(2.9%)
[10.0%] |
48名(47.1%)
[94.1%] |
P<0.001 |
|
出典)
| 1 |
地域リハビリテーション懇談会報告書(平成12年3月)、日本公衆衛生協会、2000
(寝たきり予防総合戦略に関する研究事業(平成11年度厚生省老人保健推進費等補助金)) |
| 2 |
地域リハビリテーション懇談会報告書(平成13年3月)、日本公衆衛生協会、2001
(寝たきり予防と地域リハビリテーションの推進に関する研究(平成12年度厚生省老人保健推進費等補助金)) |
介護保険3施設の機能分担について
| |
|
<今後、充実すべき機能> |
|
<介護報酬上の評価等> |
|
|
→ |
自立した生活への支援
(日常生活を通じたケアの実現) |
|
→ |
小規模生活対応型特別養護老人ホーム
(仮称)の普及(ユニットケアの導入) |
|
| |
|
|
→ |
|
→ |
| 在宅復帰につながる施設内のリハビリテーションの評価 |
| 自立支援につながる通所リハビリテーション、訪問リハビリテーションの評価 |
|
| |
介護療養型医療施設
| [ |
療養上の管理、看護、医学的管理の下での介護 |
] |
|
|
→ |
| 長期にわたる療養の必要性が高く、要介護度の高い者へのケア |
|
→ |
介護療養型医療施設の対象者の重点化
(医学的管理下における重度介護者に重点化した施設) |
|
* 括弧内は、それぞれに特徴的なサービス
小規模生活対応型特別養護老人ホーム(仮称)について
これまでの特別養護老人ホームのケア
○ 食事、排泄、入浴など、施設が定めた日課に沿ったケア
○ 集団対応によるケア
○ 4人部屋や大きな食堂など、非日常的な空間 |
} |
入所者にとって在宅での暮らしと落差が大きく、
自立した生活を営む観点からは問題
(徘徊等の行動障害も)
|
|
|
| ↓ |
| 入所者ができる限り自立した生活を営むことができるよう、ケアの在り方を改めることが必要 |
|
| ↓ |
小規模生活対応型特別養護老人ホームのケア(ユニットケア)
○ 在宅の暮らしに近い日常の生活を通じたケア
○ 一人ずつの生活を尊重した個別ケア
○ こうしたケアを行うためには、在宅に近い居住環境が不可欠
| |
* |
入所者の自立的な生活を保障する個室(使い慣れた家具等を持ち込むことができる自分の空間) |
| * |
少人数の家庭的な雰囲気の中で生活できる部屋(在宅での居間に相当する空間) |
|
|
| |
整備方針(14年度〜)
| ○新設 |
… |
小規模生活対応型での整備を推進(設置準備の状況を勘案して、当面、小規模生活対応型又は従来型のいずれかを選択可とする取扱い) |
| ○既存施設 |
… |
改築等を行う場合は、上記の新設に準じた取扱い |
| * |
小規模生活対応型については、食堂、静養室、面接室を設けなくてよいこととするとともに、廊下幅も規制緩和 |
|
|
居住費(15年度〜)
| ○ |
小規模生活対応型特別養護老人ホームでは、在宅に近い居住環境の下で、在宅での暮らしに近い日常生活を通じたケアが行われる。 |
| |
→ |
在宅との均衡という観点から、入所者は居住費を自己負担 |
|
|
図 先行事例における居室等の配置
(PDF:250KB)
介護サービスの体系
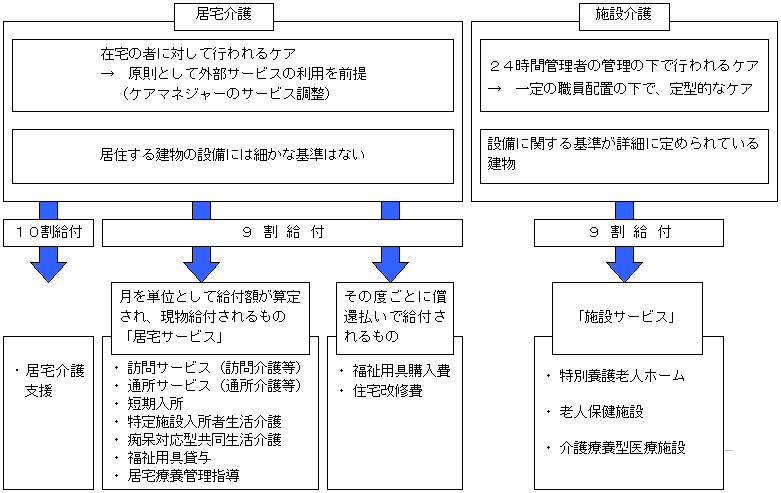
トップへ
戻る