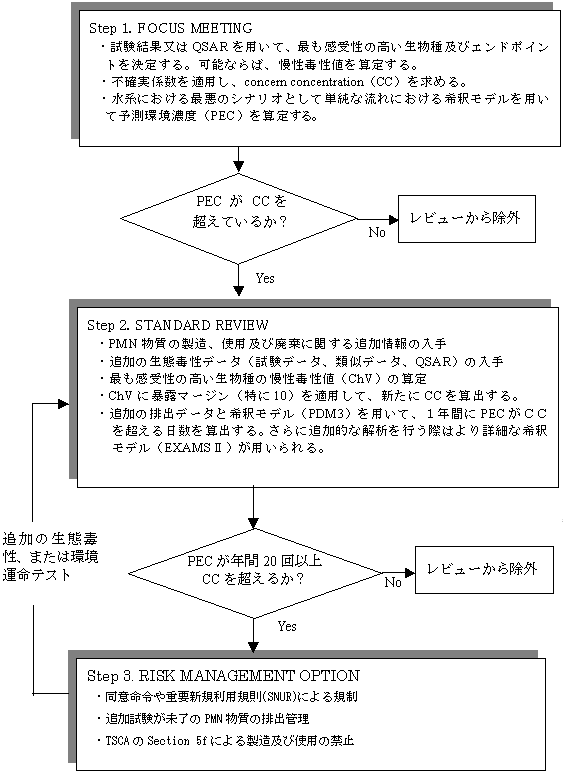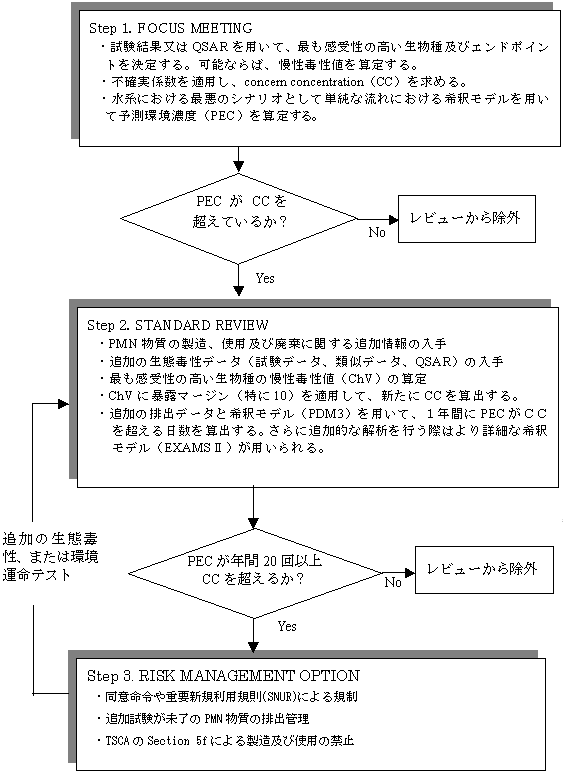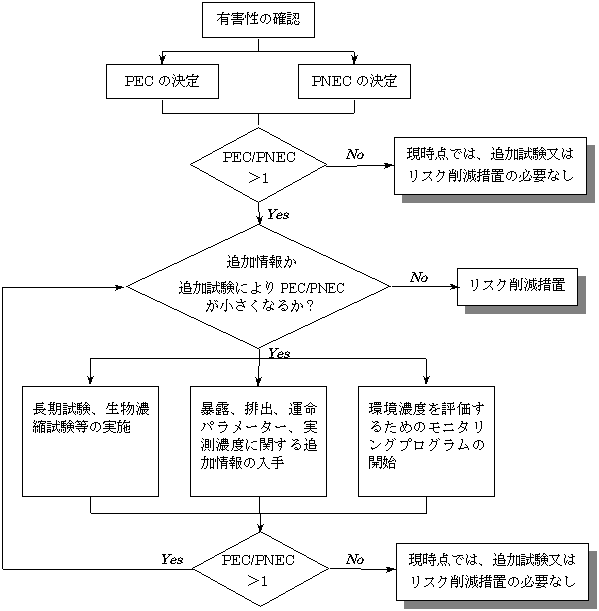戻る
化学物質による環境中の生物への影響に関する評価方法
1.米国
米国では、有害物質規制法(TSCA)に基づき、新規化学物質の製造前届出(PMN)がなされた場合、EPAがリスク評価を行い、その結果も踏まえて規制が行われている。
TSCAでは届出の際には新たな試験の実施を求めておらず、届出者が有しているデータのみを提出すればよいこととなっている。このため、EPAでは主にQSAR(定量的構造活性相関)を用いて届出物質の生態毒性値を予測し、その結果に基づきリスク評価を行っている。
(1)生態リスクの評価方法
TSCAにおける新規化学物質のリスク評価は、試験生物の生死、成長、発生、生殖への影響を把握して生物の個体群(population)レベルで影響を及ぼす可能性のある濃度を算出し、これと暴露される可能性のある環境中濃度とを比較することにより行われている。
最初の段階では、試験データやQSARにより藻類、ミジンコ類、魚類の中で最も感受性の高い種とそのエンドポイントについて影響を及ぼす可能性のある濃度を求め、その値を表1のアセスメント係数で除することにより、CC(Concern Concentration:影響の懸念がある濃度)を算出する。暴露される可能性のある濃度は、最悪のケースを想定した水中の流れによる希釈によるモデルから予測環境濃度(PEC)を算出する。予測環境濃度がCCを超える場合には、リスクの可能性があると判断され、生態毒性試験の追加や、さらに詳しい暴露に関する情報を求め、それらに基づきさらに詳細なリスク評価が行われる。
図1に、リスク評価のフローを示す。
| 表1 アセスメント係数 |
| データ |
アセスメント係数 |
データが限られている場合
(SAR/QSARによる急性LC50値が1つなど) |
1000 |
急性毒性基本セット
(魚類及びミジンコのLC50と藻類のEC50) |
100 |
| 慢性毒性値(最大許容毒性濃度:MATC) |
10 |
| 野外試験データ |
1 |
|
(2)評価に基づく規制
リスク評価の結果、リスク管理の必要があると判断された化学物質については、一般的にはその製造、輸入、使用を制限又は禁止する同意命令や重要新規利用規則(SNUR)に基づく規制が行われる。
同意命令は届出者のみを規制の対象とするものであり、EPAと届出者とで話し合いを行い、追加情報の提出、規制の遵守、届出の取下げ等のうちのいずれかを届出者に選択させるものである。SNURはすべての者を対象とする規制であり、届出以外の用途での使用に係る届出義務、事業所ごとの取扱量制限、排水基準設定などいくつか用意されている措置のメニューから必要なものを選択して規制を実施している。この中には水への排出に関する規定など水生生物への影響を考慮した内容も含まれる。SNURの対象物質を製造、輸入又は使用する場合には、その化学物質に関するSNURの要件を遵守する必要があり、その範囲を超えて当該化学物質を利用したい場合は事前に届出が必要である。
(3)PBT(難分解・高濃縮・毒性)化学物質への対応
米国ではPBT化学物質によるリスクの削減のための「PBTプログラム」が進められている。TSCAにおいても1999年にPBTカテゴリーが定められ、難分解・高蓄積の物質は人の健康影響に関する試験及び生態毒性試験(一般的には哺乳類及び鳥類等の慢性毒性試験)の結果に基づいて分類され、その結果が出るまでは製造が禁止される。人や環境へのリスクがある可能性がある場合はリスクがないことが確認されるまで製造が禁止され、最終的にリスクが低いと判断される場合もSNURにより環境排出は禁止される。なお、POPsについては製造・使用を原則禁止することが提案されている。
2.EU
EUでは、域内における届出者の予定上市量が年間1トン以上の場合、ベースセットとして魚類急性毒性、ミジンコ急性毒性及び藻類生長阻害の各試験結果の添付が義務づけられており、予定上市量が増加していくにつれて段階的にさらに詳細な生態毒性試験の実施が要求される。
新規化学物質については、有害性のレベルが理事会指令に従った分類・表示をするに至った場合に、リスク評価が行われる。
(1)生態リスクの評価方法
a) 環境リスク評価(生態リスク評価)の基本的考え方
環境リスク評価は、基本的には、予測環境濃度(PEC)と予測無影響濃度(PNEC)との比較により行われる。保全すべき対象は(1)水生生態系、(2)陸生生態系、(3)高次捕食者(食物連鎖に伴うもの)、(4)排水処理施設中の微生物、(5)大気環境の5媒体となっている。生態系の感受性は最も感受性の高い生物種に依存すること及び生態系の構造を保護することにより生態系の機能も保護されるという考え方を踏まえ、リスク評価により環境の保全を図ろうとしている。
b) 環境暴露評価
環境暴露評価手法のポイントは以下のとおりである。
| ○ |
化学物質の全てのライフサイクルを考慮し、「排出シナリオ」を仮定して排出量を推計する。 |
| ○ |
実測値とモデル計算との両方を考慮し、相互補完的に利用する。 |
| ○ |
発生源近傍の地方レベルの予測濃度(PEC local)と、バックグラウンドとして考慮すべき広域レベルの予測濃度(PEC regional)を求める。この場合、PEC localは C local(発生源からの排出をもとに算出される濃度)とPEC regionalの和となる。実測値についてはどちらに該当するかを検討して割り振る。 |
c) 生態リスク評価
生態リスク評価のポイントは以下のとおりである。
| ○ |
保全すべき対象はa)に示した5つであるが、水生生物への影響データが最も多く提出されることから、水生生物への影響の評価のみが詳細に行われることが多い。底質や土壌への影響評価は限定的になる。大気への影響は、酸性雨やオゾン層への影響などの非生物影響も考慮するが、手法は確立されていない。生体内への蓄積性が高い物質については、魚や虫などにおける化学物質濃度予測値(PEC oral, fish, PEC oral, worm)を計算して、これと魚や虫の捕食動物のPNECと比較してリスク評価を行う。 |
| ○ |
実測値とモデル計算との両方を考慮し、相互補完的に利用する。 |
| ○ |
水生生物に係るPNECは、最も高い感受性を示した生物種の急性又は慢性毒性の試験結果を表2のアセスメント係数で除することによって算出する。ただし、データの状況によって変更もありうる。新規化学物質について言うと、通常はベースセットデータが提出されるので、アセスメント係数は1000を用いる。定量的構造活性相関(QSAR)については、補完的に用いる。 |
| 表2 アセスメント係数 |
| |
アセスメント係数 |
| ベースセット(魚、ミジンコ、藻類)の3つの栄養段階からそれぞれ少なくとも1種以上の短期L(E)C50値 |
1000 |
| 魚かミジンコのいずれかの長期NOEC |
100 |
| 魚・ミジンコ・藻類のうちいずれか2つの栄養段階からの2つの長期NOEC |
50 |
| 3つの栄養段階からの3つ以上の種(通常は魚・ミジンコ・藻類)についての長期毒性 |
10 |
| フィールドデータ又はモデル生態系 |
ケースバイケース |
|
d) リスクの判定
最終的なリスクの判定は、環境媒体ごとに算出した様々なPECとPNECとを比較して、
| ・ |
追加情報や試験によりPEC/PNEC比が変わるかを判断し、 |
| ・ |
適当なら追加情報や試験を求め、 |
| ・ |
PEC/PNEC比を精査して再度判断する。 |
追加データが得られた場合、これを繰り返して、最終的に
| ・ |
追加試験やリスク削減措置が必要ない |
| ・ |
リスク削減措置が必要 |
のいずれかの結論を得ることになる。
図2に、リスク評価のフローを示す。
リスク評価の結果については、以下のとおり扱われる。
○新規化学物質については、PEC/PNEC比が1以下であれば、
| ・ |
当該物質は直ちに問題になることはなく、追加情報が提出されるまでは再度検討する必要なし。 |
という結論になる。もし1を超えれば、当局は以下の3つのどれにするかを決定する。
| ・ |
当該物質は問題があり、当局は評価の改善のためにどんな情報が必要かを決定するが、次の量的裾切りレベルに達するまでその要求を延期する。 |
| ・ |
当該物質は問題があり、追加情報を直ちに要求すべきである。 |
| ・ |
当該物質は問題があり、当局は直ちにリスク削減の勧告をすべきである。 |
○既存化学物質については、PEC/PNEC比が1以下であれば、
| ・ |
現在のところ追加情報や追加試験の必要はなく、既に適用されているリスク削減措置を超える措置の必要はない。 |
という結論になる。もし1を超えれば、
| ・ |
追加情報や追加試験が必要である。 |
| ・ |
リスクを削減する必要がある。ただし既に適用されているリスク削減措置を考慮に入れなければならない。 |
という結論のいずれかとなる。この場合、PEC/PNECの値の大きさや、濃縮可能性、生態毒性試験における経時変化、その他の毒性、構造類似物のデータを考慮に入れて検討することとされている。
図2 リスク評価のフロー
(2)評価に基づく規制
新規化学物質については、生態毒性試験結果に基づき、必要に応じ危険有害性の分類及び表示(リスク警句及び安全警句)が行われる。また、リスク評価の結果に基づき、必要に応じてリスク削減措置が求められる。
既存化学物質についても同様に分類及び表示と、リスク評価に基づくリスク削減措置が講じられる。
(3)PBT化学物質への対応
EUでは、現在White Paperにおいて新たな化学物質対策が提案され、その具体化が検討されているが、その中でPOPsについては認可(やむをえない場合に特定の用途のみ暫定的に認める)の対象とすることとされ、その他のPBT(生態毒性も含む。)化学物質も認可の対象とするかどうか検討されている。
3.GESAMP
船舶による有害物質輸送に伴う海洋汚染防止という観点から、国際海事機関(IMO)が中心となり設立した各分野の科学者による助言組織であるGESAMP(海洋汚染について科学的観点から助言する専門家グループ)の作業グループにより、船舶で運搬される種々の化学物質の有害性評価が行われている。
(1)生態毒性等の判断方法
評価は、生物蓄積性、生分解性、水生生物に対する毒性等について行われ、ランク付けがなされる。水生生物に対する毒性のうち、船舶で有害化学物質を運搬する場合に必ず要求される急性毒性試験の評価については、OECDテストガイドライン等に準拠した信頼性の高い試験データを用いて、最も感受性の高い生物種に対する最も強い毒性値に基づき毒性の程度に応じて7段階に分類される。また、必要に応じて要求される(亜)慢性毒性試験のデータについては、毒性の程度に応じて5段階に分類され評価される。
これらのうち、生物蓄積性と生分解性(サブカラムA1、A2)及び水生生物への毒性(サブカラムB1、B2)については、表3.1〜表3.4にしたがってランク付けがなされている。
| 表3.1 生物蓄積性(サブカラムA1)の評価※ |
| 記号 |
蓄積性の程度 |
Log Pow |
BCF |
| 0 |
蓄積性がない |
<1または
>約7 |
- |
| |
|
(分子量700以上) |
|
| 1 |
蓄積性が非常に低い |
1〜<2 |
1〜<10 |
| 2 |
蓄積性が低い |
2〜<3 |
10〜<100 |
| 3 |
中程度の蓄積性 |
3〜<4 |
100〜<500 |
| 4 |
蓄積性が高い |
4〜<5 |
500〜<4000 |
| 5 |
蓄積性が非常に高い |
>5 |
>4000 |
| ※ |
log PowとBCFの両方のデータが入手できるときは、後者の実測値を優先させる。(logPow:化学物質の1-オクタノールと水との間の分配係数。被験物質を1-オクタノールと水の2つの溶媒層中に加えて十分に混和した後、2層に分離し、各層中の濃度を測定することにより求める。BCF:生物濃縮係数ともいう。被験物質を溶解した水中で魚を飼育し、被験物質の魚体中の濃度と試験水中の濃度より濃縮倍率を求める。) |
|
| 表3.2 生分解性(サブカラムA2)の評価 |
| 記号 |
生分解性の程度 |
| R |
易分解性 |
| NR |
易分解性ではない |
| NI |
データがない |
|
| 表3.3 水生生物に対する急性毒性(サブカラムB1)の評価※ |
記
号 |
急性毒性の程度 |
96時間LC50(mg/L) |
| 0 |
毒性がない |
>1000 |
| 1 |
事実上毒性がない |
100〜1000 |
| 2 |
わずかに毒性がある |
10〜100 |
| 3 |
中程度の毒性がある |
1〜10 |
| 4 |
毒性が高い |
0.1〜1 |
| 5 |
毒性が非常に高い |
0.01〜0.1 |
| 6 |
とくに毒性が高い |
<0.01 |
| ※ |
96時間魚類毒性試験でのLC50、48〜96時間甲殻類毒性試験でのLC50又はEC50及び72〜96時間藻類生長阻害試験でのEC50を用い、信頼できるデータの中で最も強い毒性のものを用いて評価される。 |
|
| 表3.4 水生生物に対する慢性毒性(サブカラムB2)の評価※ |
| 記号 |
慢性毒性の程度 |
NOEC(mg/L) |
| 0 |
毒性が低い |
>1 |
| 1 |
中程度の毒性がある |
0.1〜1 |
| 2 |
毒性が高い |
0.01〜0.1 |
| 3 |
毒性が非常に高い |
0.001〜0.01 |
| 4 |
とくに毒性が高い |
<0.001 |
| ※ |
OECD TG215(28日間の幼魚生長試験)、OECD TG210(魚類初期生活段階毒性試験)、OECD TG202(21日間ミジンコ類繁殖試験)や、この他海産あるいは淡水生物について国際的に認知されている標準的な毒性試験の結果に基づき、信頼できるデータの中で最も強い毒性のものを用いて評価される。 |
|
(2)評価に基づく規制
この評価結果は、海洋汚染防止のための国際条約であるマルポール条約に基づく規制(我が国の海洋汚染防止法を含む)に反映されている。
4.GHS
(1) 検討の経緯
化学物質の有害性による分類や表示方法は、国や地域、化学物質のタイプ等により各国ごとに異なっており、人の健康保護や環境保全の観点から不適当なことから、GHS (Globally Harmonized System)、すなわち地球的規模で調和のとれた有害性の分類と互換性のあるラベリングシステムの確立が、1992年の地球サミットにおいて採択されたアジェンダ21において国際的な目標として決定された。これを受け、現在、有害性項目ごとにOECD等において分類・表示システムの検討が行われ、2002年12月に当面のシステムについて合意し、2003年7月に国連勧告が行われる見込みとなっている。
(2)水生環境における有害性分類
水生環境における有害性分類についてはOECDにおいて検討され、最終的に図4.1〜図4.2に示すように、急性毒性について3区分に、慢性毒性について4区分に分類する方法が提案されている。
| 図4.1 水生環境 急性毒性 |
有害性
カテゴリー |
クライテリア |
表示項目 |
| 1 |
96hr LC50 (魚) < 1 mg/l 及び/又は
48hr EC50 (甲殻類) < 1 mg/l 及び/又は
72又は96hr ErC50 (藻類又は他の水生植物)
< 1 mg/l |
| ※ |
規制システムによってはLC50< 0.1 mg/lというレベルでカテゴリー内に区分を設ける場合もある |
|
シンボル |
 |
| 注意喚起語 |
警告 |
| 有害性の説明 |
水生生物への強い毒性を有する |
| 2 |
96hr LC50 (魚) >1-< 10 mg/l 及び/又は
48hr EC50 (甲殻類) >1-< 10 mg/l 及び/又は
72又は96hr ErC50 (藻類又は他の水生植物)
>1-< 10mg/l |
|
シンボル |
無し |
| 注意喚起語 |
無し |
| 有害性の説明 |
水生生物への毒性を有する |
| 3 |
96hr LC50 (魚) >10-< 100 mg/l 及び/又は
48hr EC50 (甲殻類) >10-< 100mg/l 及び/又は
72又は96hr ErC50 (藻類又は他の水生植物)
>10-< 100 mg/l |
| ※ |
規制システムによってはさらにL(E)C50>100mg/lというカテゴリーを設ける場合もある |
|
シンボル |
無し |
| 注意喚起語 |
無し |
| 有害性の説明 |
水生生物に有害 |
|
| 図4.2 水生環境 慢性毒性 |
有害性
カテゴリー |
クライテリア |
表示項目 |
| 1 |
96hr LC50 (魚) < 1 mg/l 及び/又は
48hr EC50 (甲殻類) < 1 mg/l 及び/又は
72又は96hr ErC50 (藻類又は他の水生植物)
< 1 mg/l |
上記に加え、
低分解性 及び/又は
log Kow >4
(実験的に求められたBCFが500未満でない場合に限る) |
|
シンボル |
 |
| 注意喚起語 |
警告 |
| 有害性の説明 |
長期にわたり影響し、水生生物への強い毒性を有する |
| 2 |
96hr LC50 (魚) >1-< 10 mg/l 及び/又は
48hr EC50 (甲殻類) >1-< 10 mg/l 及び/又は
72又は96hr ErC50 (藻類又は他の水生植物)
>1-< 10mg/l |
上記に加え、
低分解性 及び/又は
log Kow >4
(実験的に求められたBCFが500未満でない場合に限る)
ただし慢性NOEC>1mg/Lである場合はこの限りではない |
|
シンボル |
 |
| 注意喚起語 |
無し |
| 有害性の説明 |
長期にわたり影響し、水生生物への毒性を有する |
| 3 |
96hr LC50 (魚) >10-< 100 mg/l 及び/又は
48hr EC50(甲殻類) >10-< 100mg/l 及び/又は
72又は96hr ErC50 (藻類又は他の水生植物)
>10-< 100 mg/l |
上記に加え、
低分解性 及び/又は
log Kow >4
(実験的に求められたBCFが500未満でない場合に限る)
ただし慢性NOEC>1mg/Lである場合はこの限りではない |
|
シンボル |
無し |
| 注意喚起語 |
無し |
| 有害性の説明 |
長期にわたり影響し、水生生物に有害 |
| 4 |
低溶存性であって水への溶解するレベルでは急性毒性が報告されていないこと
|
低分解性であって、log Kow >4、潜在的に生物蓄積性があることを示すこと
|
| ただし分類が不要であることを示す他の科学的証拠がある場合はこの限りでない。そのような科学的な証拠は実験的に求められたBCFが500未満であること、又は慢性NOEC>1mg/Lであること、又は環境中での易分解性を示す証拠を含む。 |
|
シンボル |
無し |
| 注意喚起語 |
無し |
| 有害性の説明 |
水生生物に長期の有害影響を有する可能性がある |
|
(3)評価に基づく対応
GHSは自主的な仕組みではあるが、化学物質の安全性に関する政府間フォーラム(IFCS)では2008年までの完全実施を目標として各国が早期に取り組むよう奨励されている。また、APEC諸国においても2006年までの実施を目標としている。
トップへ
戻る