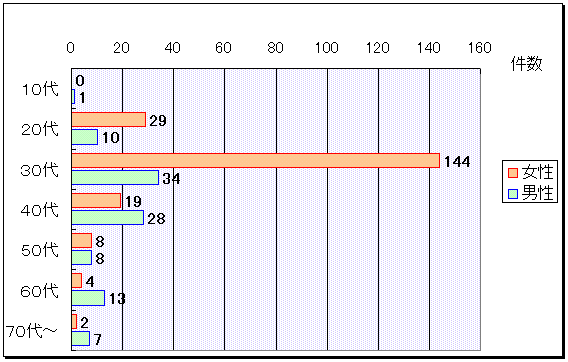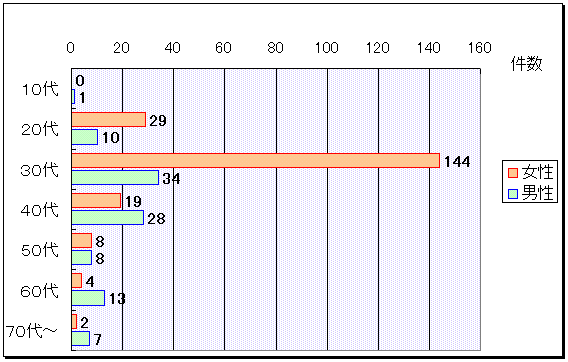戻る
「少子化社会に対する御意見の募集」の結果について(概要)
○ 募集開始以降、これまでにいただいた御意見は377件。
-
| ・ |
募集開始 |
: |
平成14年6月4日(火) |
| |
締め切り |
: |
平成14年8月31日(土) |
| ・ |
電子メールによるもの |
: |
277件 |
| |
FAX、郵送によるもの |
: |
100件 |
| ・ |
男性 |
: |
119件 |
| |
女性 |
: |
243件(全体の65%) |
|
<参考>
御意見募集のホームページへのアクセス件数:約13,000件
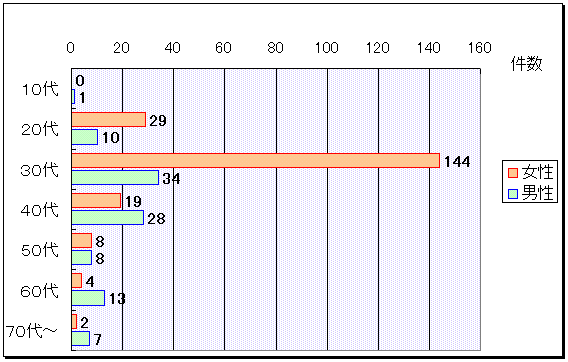
○ 少子化対策に必要と思われる施策の例として寄せられた御意見の主な内容は以下のとおり。(重複回答あり)
-
| 項目 |
件数 |
保育所や学童保育のさらなる整備
(延長保育や一時保育の実施等も含む) |
110 |
職場の環境改善
(有給休暇や育児休暇の確実な取得、残業の削減、出産・休暇時の職場の理解など) |
100 |
不妊治療に対する支援
(医療保険の適用や治療費の低廉化など) |
94 |
| 教育費負担の軽減 |
71 |
育児手当や優遇税制の創設・拡充
(育児期間中の社会保険料の免除なども含む) |
68 |
| 保育料の軽減 |
63 |
地域社会との関わりの見直し
(高齢者の育児参加、保育ママや育児サークルの利用促進、コミュニティーセンター等の有効活用など) |
52 |
○ そのほか、少子化が進行している要因として以下のような御意見があった。
経済の先行き不透明感が子どもを産もうという気持ちを阻害している。
価値観の多様化や子供に対する意識の変化、パラサイトシングルの増加などが少子化を進めている
政府や自治体の実施している施策が身近でなく、わかりにくい。
|
御意見の抜粋
保育園の利用条件が非常に厳しい。働いていても、家に祖父母がいるだけで断られてしまう。しかし、現実には高齢の祖父母が一日中子どもの面倒を見るのは無理。
勤め先や交通機関に託児所があれば、共働きでも時間を気にせずともよい。商業施設に託児スペースがあると集客数の増加にもなるのでは。
サービス業に勤務している人が多いのに、保育園は土日休みが多い。公務員に対して基準をあわせてもらっては困る。パートなら別だが、いまどき6時にお迎えに行ける仕事なんてそんなにないと思う。
保育施設を増設してほしい。整備コスト等の問題があるのなら、公立学校の余っている教室を保育施設として利用できないか。
保育園には入れたが、上の子と下の子が全く違う保育園に通い、通勤に支障がある。兄弟は同じ保育園に入れることを原則とすべき。
延長保育もされているが、ほとんどが19時まで、残業があったときなどは対処できない。20〜21時まで延長保育してほしい。
学童保育は保育所と並んで、なくてはならない施設と認識されようになってきたが、まだまだ保育所に比べて量的、質的に大きく立ち後れている。
|
企業の人事評価体系を変えて欲しい。今は長時間労働や永続勤務が評価システムに組み込まれてしまっている。これらは夫の長時間労働や勤務の継続を支援し、私たち妻の勤務を中断させ、同期の男性との差を決定的なものにしてしまう。
企業から父親を返してもらう。我が家の夫は囚われの身だ。経済中心の考え方を変えるべき。
奴隷のような長時間労働を何とかして欲しい。強制力ある罰則規定を。
子どもを産み、育てることが企業内でマイナスに作用しないような時代の到来を強く望む。
男女間、正社員とパートの待遇の差をなくし、ワークシェアリングを進めるべき。
出産のための休暇による人員補充への資金援助を。
一度仕事を辞めると、第一線に戻るのが非常に難しいという状況がある。
|
これまでの対策は、「産む気がない人」への配慮が目立つ。「産みたいのに産めない人へ」の対策を行えば、より直接的な効果が見込めるのでは。
地方では、大学病院でも高度な不妊治療の技術・知識を保有しておらず、わざわざ都会まで治療に出かけている。不妊治療の技術・知識の全国への普及を。
私たち夫婦には、立派な病名までついている。不妊は病気でないという考えは理解できない。
不妊治療には時間がかかる。経済的な援助に加え、もっと勤務先の理解がほしい…。
|
介護保険だけなく育児保険も。そのために消費税の引き上げはやむを得ない。
子どもが幼いうちは夜泣きなどで体力的に厳しく、就業は困難。児童手当を拡充することで経済的な支援を。
子どもの数に応じて年金を割増(もしくは減額)するのはいかがでしょうか。
産休の間は年金も健康保険も全く免除されていない。「出産」も「育児」と同じ補助を。
|
近所に気軽に子どもを任せられる施設がほしい。人とのつきあい方が分からないまま大人にならないための場としても必要なのではないか。
働きながら2人、3人の子どもを育てるには父親はもちろん周囲の多くのサポートが不可欠。
孤独の中で初めて赤ちゃんを育てる親にとって、マニュアルのない育児はとても不安。そんなときに保育園が開放されていたり、子育て支援のサークル等があればとても気が楽になるだろう。子どもはたくさんの愛情に支えられて大きくなるものだと思う。
保健師、保育士等の専門家がもっと地域に密着したサービスを。そうすれば密室虐待も減ると思います。
幼稚園、保育園を中心に児童相談所と連携してサポート体制を作り、電子メールなどでも相談できる窓口を設ける。
育児サークルでは子ども達同士を遊ばせることができると同時に、母親達の情報交換の場としても役立つ。
|
トップへ
戻る