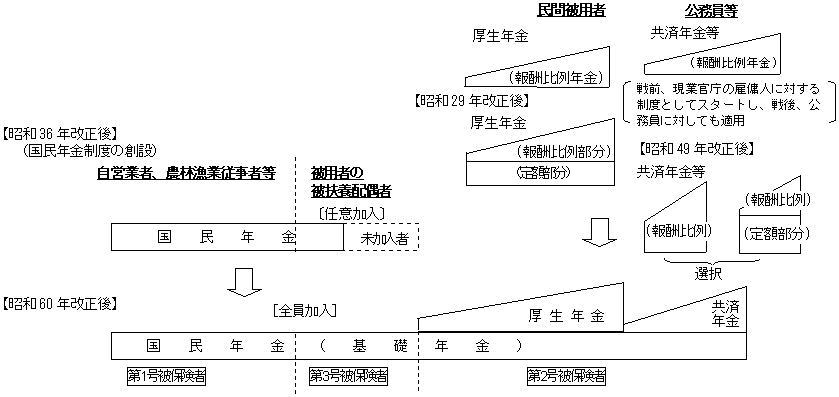
I 年金制度の体系について
| 今後の議論を進める上で必要と考えられる論点(例)や参考資料をとりまとめたものである。 |
我が国の年金制度の体系
|
○我が国の社会保険方式の年金制度は、被用者を対象とする被用者年金(厚生年金等)制度からスタート。 ○発足時、1階建ての所得比例年金の体系でスタートしたが、昭和29(1954)年改正において、厚生年金について、定額部分(1階)+所得比例部分(2階)の2階建ての体系に再編成。 ○昭和36(1961)年に自営業者や農林漁業従事者等を対象とする国民年金制度を創設。 ○昭和60(1985)年改正において、全国民共通の横断的な仕組みとして基礎年金制度を創設。 |
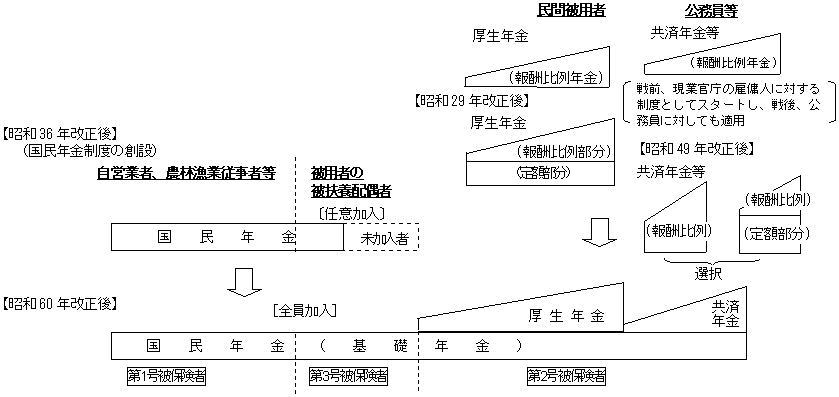
諸外国の年金制度の構造比較
| 国名 | アメリカ | ドイツ | スウェーデン | イギリス | ||||||||||||||||||||||||
|
公的年金の体系
|
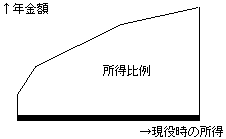 |
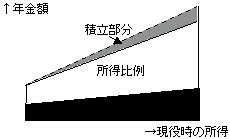 |
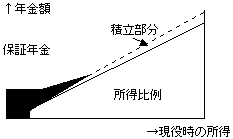 |
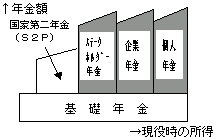 |
||||||||||||||||||||||||
| 被保険者 (◎強制△任意×非加入) |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
| 公的年金の財政方式 (積立金の積立度合) 保険料及び給付の構造 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
| 所得再分配 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
| 将来の負担と給付 保険料水準(対年収) (2001年) |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
| 国庫負担 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
| 無・低所得者への対応 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
| 年金制度における最低保障 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
| 公的年金と私的年金 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
| 国民に対する個人年金情報の提供 |
|
|
|
− |
| (※) | スウェーデンの保険料率18.5%は、粗収入から被用者本人分の保険料を控除した残りの額に対する保険料率。粗収入に対する割合でみると、16.94%(労使折半)。 |
諸外国の年金制度の構造と日本の仕組み
| 我が国の公的年金制度の体系は、諸外国の年金制度の体系の特色が混合された形をとる一方、独自の面も有していると考えられる。 |
| 国名 | アメリカ | ドイツ | イギリス | |||
|
公的年金の体系
|
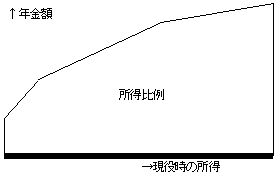 |
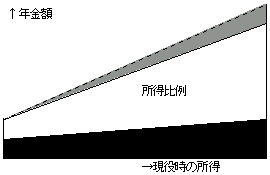 |
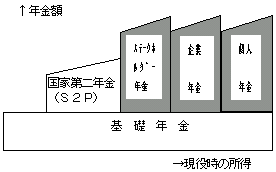 |
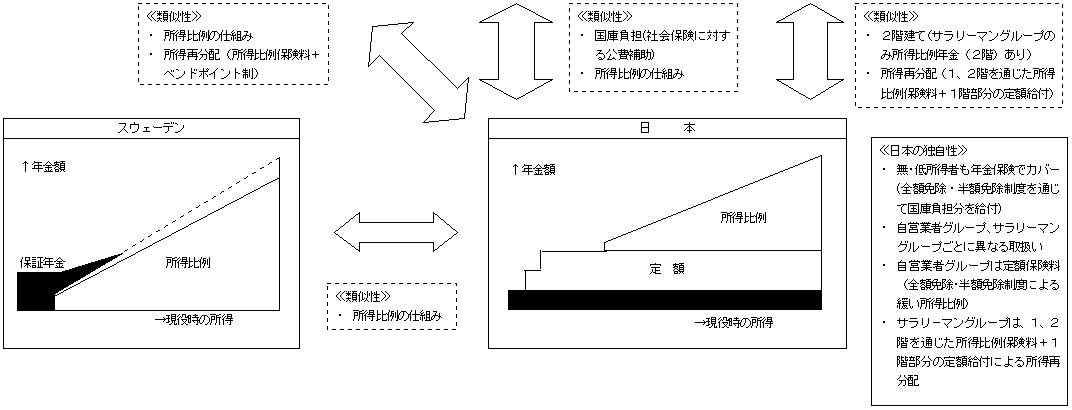
我が国の現行社会保険制度の体系
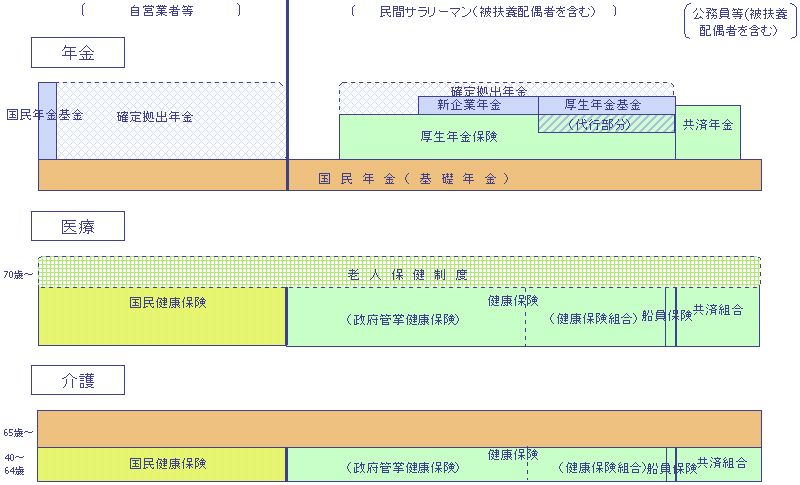
論点(例)
1 サラリーマングループと自営業者グループの間で異なる取扱いとされていることについて、どう考えるか
○ 欧米主要国では、一定以上の所得のある者のみを対象として強制適用することが基本であるが、我が国では、無・低所得者も含めて年金保険でカバーしている。(国民皆年金)
○ 我が国では、就業や稼得の態様に違いがあること等から、1階に全国民共通の基礎年金を設けつつも、2階の所得比例給付はサラリーマングループのみとするとともに、基礎年金に係る個々人の保険料負担については、サラリーマングループと自営業者グループの間で異なる取扱いとしている。
○ 厚生年金、共済年金に分立しているサラリーマングループについては、将来の一元化を目指すこととされている。(財政単位の一元化も含め、更なる財政単位の拡大と費用負担の平準化を図るための方策について、21世紀初頭の間に結論を得る。(平成13年3月16日閣議決定))
○ サラリーマングループと自営業者グループの間の異なる取扱いをどのように評価し、将来に向けてどのように見直すのか。
サラリーマングループと自営業者グループの間での、就業や稼得の態様、所得把握の違いをどう考えるか。
サラリーマングループと自営業者グループの間での、高齢期の所得保障の必要性の違いをどう考えるか。(資料2−2「給付と負担について(参考資料)」の1−6参照。)
2 給付の構造(所得比例、所得再分配)について、どう考えるか
○ ドイツ、スウェーデンは、給付、保険料負担ともに稼得に応じた所得比例方式。
○ アメリカは、保険料負担は所得比例、給付は低所得者に相対的に手厚い給付を支給する方式をとることにより、所得再分配を実施。
○ イギリスは、サラリーマングループについて、保険料負担は所得比例、給付は定額年金(1階)+所得比例年金(2階)の2階建ての構造により、所得再分配を実施。自営業者グループについては、保険料負担は定額、給付は定額年金(1階)のみ。(但し、高所得の自営業者は、一定額以上の所得部分について、別途定率保険料を負担(給付に反映されず)。)
○ 我が国の現行給付構造はイギリス型。
ドイツ、スウェーデンのような完全所得比例方式を目指すのかどうか。この場合、サラリーマングループと自営業者グループの間の所得把握の相違をどうするのか。
あるいは、アメリカ、イギリスのような所得再分配機能を一層強めるのかどうか。
3 所得のない、或いは低い者に対する年金による保障について、どう考えるか
○ 公的年金制度は、そもそも、従前所得(=現役時代の所得)の喪失補填による高齢期の所得保障を目的とする制度。
○ したがって、アメリカ、ドイツ、イギリスでは、無・低所得者は公的年金制度の対象としておらず、これらの者の老後の所得保障は、生活保護の体系で対応することが基本。
○ 一方、スウェーデンでは、無・低所得者は所得比例年金の対象とはしていないが、無・低年金者に対しては、税を財源とする保証年金により対応。
○ 我が国では、高齢期における従前所得(=現役時代の所得)の喪失補填を基本としつつ、無・低所得の期間もできるだけ年金保険でカバーすることとしている。具体的には、保険料を納めることが困難な期間について国民年金の保険料の免除制度の対象とし、免除を受けた期間についても1/3(基礎年金の国庫負担相当分)の年金額を支給。(平成14年度から保険料の半額免除制度もスタート。)
○ 公的年金制度の体系において、従前所得(=現役時代の所得)の喪失補填による高齢期の所得保障という目的に加えて、無・低年金者に対する最低保障という考え方を入れることが適切かどうか。
4 公的年金の一部を確定拠出型(積立型)とすることについて、どう考えるか
○ 欧米主要国では、所得比例年金をすべて民営化している国は見られない。なお、イギリスでは、一定の適格要件をみたす企業年金、個人年金等の加入者に限り、2階部分の所得比例年金の適用除外(コントラクト・アウト)を認めている。
○ ドイツでは、将来の保険料負担の過度の上昇を抑制するため公的年金の給付水準を適正化する一方、公的年金の給付の補完として、任意加入の確定拠出型の企業年金、個人年金(一定の要件を満たすものに対して政府の補助あり)を拡充。
○ スウェーデンでは、従前の賦課方式の公的年金の保険料の一部を強制的に積立方式(個人勘定の確定拠出型)で運営。
○ アメリカでは、賦課方式の公的年金を補完する任意加入の確定拠出型の個人勘定を設けることについて検討中。(新設追加する案と賦課方式保険料の一部を切り替える案あり。)また、公的年金とは別に、確定給付型・確定拠出型の企業年金・個人年金が普及している。
○ 我が国で、仮に賦課方式の公的年金の給付を補完する確定拠出型(積立型)の年金を導入する場合、
現在の賦課方式部分に付加する形で、任意加入の制度を設けるのか。この場合、我が国では、昨年度から確定拠出年金制度がスタートしたところであるが、こうした制度の普及との関係について、どう考えるか。
あるいは、賦課方式の公的年金の保険料の一部を切り替える形で、強制加入の制度を設けるのか。この場合、現在の年金受給者の年金水準を落とすことなく賦課方式の保険料の一部を切り替えるためには、年金給付を賄うための別の財源を用意することが必要となるが、これについてどう考えるか。