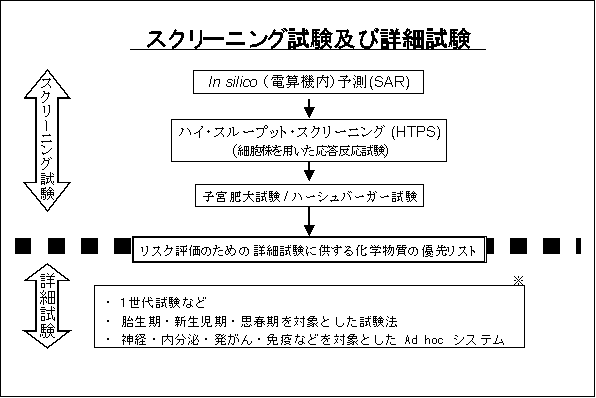
※ 低用量問題(P.35〜参照)を含む、内分泌かく乱作用の発現メカニズムの解明には、遺伝子発現解析を駆使した研究が考慮される。
3 重点課題と検討成果
昨年12月の検討会において、これまでに得られた科学的な知見や国際的な動向を踏まえると、「中間報告で示された調査・研究の内容は適切であり、今後ともこれらを継続する必要があるが、短期的には、下記の事項について、詳細にわたる専門的な検討を加える必要がある」とされた。
中間報告は、「逆U字効果の存否の確認とともに、仮にその効果が存在する場合はそれに関する作用メカニズムの解明を急ぐ必要がある」としている。平成12年10月に米国において開催された低用量における作用に関する文献査読会議(ノースカロライナ会議)の結果等を踏まえつつ、我が国においても科学的な見地から早期に検討する必要がある。
イ.HTPS(超高速自動分析装置)を用いた対象物質の選定
中間報告は、事前スクリーニングとして、超高速自動分析装置(HTPS)による受容体結合レポータージーン実験を行うこととしており、厚生科学研究等により、試験法の開発はほぼ終了している。今後、順次、化学物質をHTPSにより分析することとなり、試験を行う物質の選定及びHTPSによる試験結果の解析・評価の方法等について検討を行う。
ウ.ほ乳動物を用いたスクリーニング試験法の検討
経済協力開発機構(OECD)は、スクリーニング試験法(子宮肥大試験、去勢雄ラット反応試験及び改訂28日間反復投与試験法)について、平成14年3月までに各国の検討結果の解析等を行うこととしている。OECDにおける検討状況を踏まえ、我が国においてもスクリーニング試験法の妥当性、適用限界、試験結果の解析・評価の方法等について検討を行う。
エ.内分泌かく乱作用の同定・確認のための詳細試験方法
スクリーニング試験後の内分泌かく乱化学物質同定・確認のための詳細試験について、最新の知見を踏まえ、適切な詳細試験方法について検討を行うことが必要。特に内分泌かく乱作用のエンドポイント(観察項目)の考え方を早急にとりまとめるべきである。
オ.試料の採取・分析方法の確立
内分泌かく乱化学物質は、低用量においてその作用を発現することが指摘されていることから、適切な試料採取法及び高感度の分析法の開発が必要である。例えば、フタル酸エステル類のように広範に利用されている物質については、被験試料の十分な管理が行われていない場合、周辺環境から汚染(コンタミネーション)が起こることが常識とされている。汚染を防ぐための試料採取法及び高感度の分析法等の確立及びその標準操作書を整備する必要がある。
カ.暴露・疫学的情報等の収集及び解析
暴露の経路や量などの情報を収集し、リスク評価に活用する。経年的な情報も過去のリスクと比較する上で有用である。
中間報告は、「現在のところ、内分泌系への薬理作用を期待して使用されたDESのような例を除き、内分泌かく乱化学物質が与える人への健康影響について確たる因果関係を示す報告は見られない。」とする一方、いわゆる内分泌かく乱化学物質による人への影響が懸念されている具体的な疾病として、「子宮がん、子宮内膜症、乳がん、精子数の低下、前立腺がん、精巣がん、尿道下裂等」をあげている。また、甲状腺や神経系への影響について懸念する意見もある。
これらの疾病と化学物質の因果関係を検証するためには疫学的手法を用いた調査研究が有効である。疫学的手法を用いた調査研究は、一般に長期の調査期間が必要であることから、短期的には調査体制の整備等を図る。
キ.リスクコミュニケーションの充実
内分泌かく乱化学物質問題は、多くの人々が関心を抱いていること、多様な調査研究結果、科学技術の進歩等を背景に多くの認識の不一致が生じていると考えられる。リスクコミュニケーションの充実を図ることにより、できるだけ多くの人々が情報を共有し、問題の解決に必要な対応策を冷静かつ合理的にすすめる必要がある。
本検討会では、上記ア〜キの事項を解決するために、次の5つの作業班を設置して、各事項について専門的な検討を行った。
事前スクリーニング試験、スクリーニング試験、詳細試験の個々の課題を並行して整理する。また、これらの試験方法に他の要因(暴露情報等)を組み合わせた内分泌かく乱化学物質同定のための試験スキームを構築する。必要があれば、本検討会が中心となり試験計画書の作成を行ったうえで、試験を実施する。
(2) 採取・分析法検討(検討事項オ)
被検試料の採取から分析までの測定ガイドラインを策定する。必要があれば、本検討会が中心となり試験計画書の作成を行ったうえで、試験を実施する。
(3) 低用量問題対策(検討事項ア)
低用量問題に係る現在までの科学的知見をとりまとめ、現時点で明確になっている事項と不明確な事項を整理する。これを踏まえ、問題解決のために必要な試験方法等を提案する。必要があれば、本検討会が中心となり試験計画書の作成を行ったうえで、試験を実施する。また、低用量における相加・相乗作用についても検討を行う。
(4) 暴露疫学等調査(検討事項カ)
化学物質による暴露経路、暴露量等の経年変化等を把握するため、これらに対する現在までの知見をとりまとめるとともに、今後、これらを効率的に把握するための手法を検討する。
内分泌系を中心に化学物質の因果関係が指摘されている疾病、内分泌かく乱作用によって起こりうる疾病等を現在までの知見をもとに整理する。取り上げられた疾病について疫学的手法を用いた調査の必要性や優先順位、実施の可能性等を検討する。必要があれば、本検討会が中心となり優先順位の高い疾病に対し、試験計画書の提案、調査体制の整備を行う。また、各化学物質に着目して、関連する可能性のある疾病についての検討も行う。
(5) リスクコミュニケーション対策(検討事項キ)
複雑で理解の難しい内分泌かく乱化学物質問題の本質を多くの関係者に正しく理解してもらうための方途を検討する。基本的なリスクコミュニケーションのあり方について検討するとともに、本問題の理解の難しい点、認識の相違の多い点等を整理しとりまとめる。これらを踏まえ、具体的なコミュニケーションの方途として本問題に係る平易なパンフレットの作成等を行う。
本年7月の検討会では、これら重点課題についての検討成果が報告された。次項から、その内容について示す。
本作業班では、内分泌かく乱作用に関する事前スクリーニング試験、スクリーニング試験、及び詳細試験の課題を整理し、今後の試験実施の方針を提示する。また、必要な場合は、試験計画書の作成も行う。なお、詳細試験に関しては、低用量問題対策における検討と連携して進める必要がある。
基本的戦略
本作業班では、図のように、段階的スクリーニング試験及び詳細試験の関係を規定し、その各々の要素となる試験法について検討を加える。
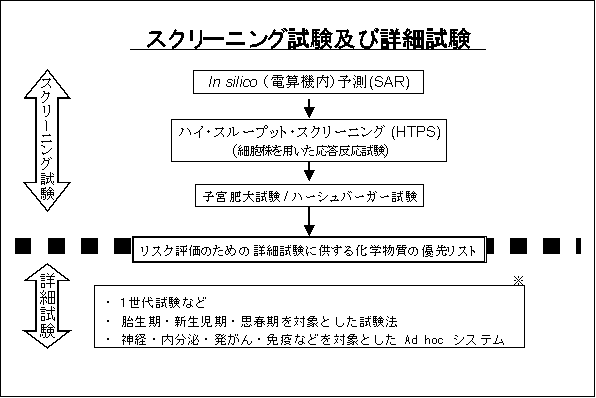
In silico(電算機内)予測(SAR)は、現時点ではHTPS等のデータも踏まえつつ、その有効性を評価している段階ではあるが、手法として確立されれば、その処理スピードと経費の安さから、スクリーニングの第1段階として位置づけられる。
次に、ヒト培養細胞においてエストロゲン応答を測定する試験をロボット技術によりハイ・スループット化した超高速測定法(HTPS)を置く。
そしてその下に、人工的に作成した高感度バイオアッセイとして、子宮肥大試験及びハーシュバーガー試験を配する。
これらスクリーニング試験を通じて、ホルモン様作用(低用量域の作用を含む)を有することが生物学的に説明可能な物質としての順位付けがされる。これらの物質は、ヒト健康への悪影響があるのかどうかリスク評価のための詳細試験に供される優先物質となる。
スクリーニング試験
ヒト培養細胞を用いた応答反応系(ハイ・スループット・スクリーニング:HTPS)
厚生労働省及び経済産業省の共同研究によって、Hela細胞を基礎とするヒトエストロゲン受容体α応答反応を測定する試験を、ロボット技術によりハイ・スループット化した超高速測定方法(HTPS)を開発することに成功し、既にエストロゲン・アゴニスト(agonist)及びアンタゴニスト(antagonist)について、再現性及び有用性に関するデータの蓄積が進んでいるところである。一方、反応系の特性に起因すると思われる、受容体結合性からみた予想外の結果(例えば、アンタゴニストとしてレチノイン酸が選択される、など)が若干得られており、その細部に対する検証がさらに必要である。しかし、目的とするスクリーニング手法として適用するための基本的性能には問題がないことが示されつつある。現在、エストロゲン受容体αに対応する試験系が確立されたところであり、他の試験系(アンドロゲン受容体など)についても開発を続行中である。
子宮肥大試験及びハーシュバーガー試験
卵巣摘出雌ラット等を用いた子宮肥大試験(エストロゲン・アゴニスト及びアンタゴニストを検出)及び去勢雄ラットを用いたハーシュバーガー試験(アンドロゲン・アゴニスト及びアンタゴニストを検出)については、OECDが試験法ガイドライン作成のための検討を進めてきた。特に子宮肥大試験については、国立医薬品食品衛生研究所の主導により試験プロトコールの開発と有効性の確認を実施し、現在ガイドライン化の作業を進めているところである。また、ハーシュバーガー試験については、米国の主導により、開発した試験プロトコールの有効性確認を実施中であり、その作業が終了次第ガイドライン化を進めることとしている。
これらの試験によりスクリーニングは完了し、詳細試験を行うに当たっての優先物質のリストが作成されることになる。
詳細試験
詳細試験については、一部の機関では、従来の毒性評価方法にのっとった「二世代生殖毒性試験」を中心とする比較的大規模なバイオアッセイにより実施に移っているところもある。しかし、本作業班では、「従来型の生殖毒性試験」における指標(エンドポイント)では、多くの陽性候補物質が陰性の結果に終始することが予測されるとの立場にたっている。実際予測どおり、エストラジオールのような一部の陽性候補物質について陰性所見が得られている。したがって、これら従前の試験では、提起される低用量問題への対応が実質的に困難であると考えられる。
現時点では、低用量問題を含む内分泌かく乱による生体反応を簡便かつ詳細に掌握するためには、1世代試験などを中心に据えたmRNAの発現解析によるメカニズム解析が考慮される。また、胎生期・新生児期・思春期を対象とした試験法及び、特定臓器に焦点を絞ったad hoc な試験法(神経、内分泌、発がん、免疫など)の開発も考慮される。
〔その他の関連する試験〕
改良28日間連続投与試験(TG407e)
この試験は、現行の28日間反復経口投与毒性試験(OECD試験法ガイドラインNo.407)を基礎とし、新たに内分泌関連の検索項目(血清中ホルモンの定量、精子検査、雌の性周期、等)を追加して改良すべく、現在、OECDの場で、スクリーニング試験法の一つとして開発中であり、日本もこれに参加している。検出感度の問題も指摘されているが、今後の開発状況によっては、試験スキームの中に組み入れられる可能性がある。
結語
図に示す階層的スキームを規定し、各試験法を逐次整備してきた。
今後の焦点として、スクリーニング試験については、国内及び国際の要望に応えられるように、開発したプロトコールの細部調整と有効性確認をどのように行うか(評価基準)、また詳細試験については、従来の毒性試験のエンドポイントに加え、遺伝子発現解析手法を駆使した研究をどのように利用するかが挙げられる。また、生体の成長過程(胎生期・新生児期・思春期)や生体反応の局面(神経系、内分泌系、発がん、免疫、等)を切り出した特異的実験系による方法も並行して行われる必要があると考えられる。
概要
いわゆる内分泌かく乱化学物質の分析結果については、社会の関心の高さから、数値だけが一人歩きする傾向にある。特に信頼性の高くない分析法によるデータや、安易なデータの解釈及び取扱によって、社会を混乱させている場合があるのも事実である。
本作業班では、検体の採取から分析までを包括した、精度管理等ガイドラインの策定を目標として作業を進めた。
当初、生体試料(血液、母乳、尿等)の分析法について調査したが、公表されている学術論文をレビューしてみたところ、
| ・ | 複数の機関で同一試料を分析して、分析値の信頼性を評価した分析法がほとんどないこと |
| ・ | 分析室内外における汚染を防ぐためには、試料の採取、運搬、保存及び測定、並びに器具、装置及び試薬類の取扱等において留意すべき点があり、これを怠ると分析結果の信頼性が損なわれること |
| ・ | 代謝物に関する検討がなされていないこと |
そこで、本作業班では、まず、食品中に混入する、(1)ビスフェノールA、(2)フタル酸エステル類、(3)ノニルフェノールの3物質を調査対象物質として検討した。
本作業では、これらの物質の分析法として、食品衛生上問題とすべき食品を対象とした信頼性の高い分析法を提示し、さらにその分析法に対する注解等を、分析担当者あるいはデータの解析・評価をする方の参考になる指針として提供することを念頭において編集を行い、「食品中の内分泌かく乱化学物質分析ガイドライン」として暫定的にとりまとめた。
この暫定ガイドラインは2部から構成されており、第1部は一般試験法ガイドライン、第2部は(1)ビスフェノールA、(2)フタル酸エステル類、及び(3)ノニルフェノールの3物質について個別の分析法となっている。
第2部の個別分析法は、客観的な論文審査のなされている学術誌に掲載されている論文を参考論文とした。
なお、食品容器包装材料に関連する材質試験、溶出試験については除外した。
上記の分析法に関しては、今後も様々な手法を用いた新規分析法が報告される可能性もあり、引き続いて情報の収集・評価を行う必要がある。さらに、精度管理を視野に入れた、同一試料のクロスチェックを実施してその妥当性を検討する等の研究が必要である。
また、生体試料を対象とした採取・分析法については、今後、信頼性の高い分析法を基軸としたガイドラインを策定する必要がある。
さらに、実験動物について、飼育環境及び実験環境からの暴露調査を実施して、動物実験の信頼性を検証し、試験法の改善に役立てることが必要である。
第1部
はじめに
いわゆる内分泌かく乱化学物質の食品中に存在する濃度は一般的に低濃度であり、現在の分析測定技術レベルで信頼性の高い数値を得るためには、分析装置や測定室の設備に加えて、測定・分析操作等にかかわる一定水準以上の技術が要求される。
そこで、内分泌かく乱化学物質等の食品試料中の濃度を測定する際の一般的留意点をまとめた。なお、ここで示した以外の方法であっても測定結果の信頼性を確保できることが認められるならばその方法を採用しても良い。
1.試料の採取、運搬及び保存
2)手袋等の選択に当たっては、ブランク試験を実施して、分析対象物質の汚染がないことを確認する。
3)採取器具等は、ステンレス、ガラス製等のものを、分析対象物質の汚染がないことを確認した後使用する。
4)採取容器等は、ガラス製ないしはフッ素樹脂製等のものを用いる。採取容器等の選択に当たっては、ブランク試験を行い、分析対象物質の汚染がないことを確認する。
5)試料は少なくとも最低2回分析できる量(試料の均一性を確保する観点から1kg以上が望ましい。)を採取し、二等分する(一方は再試験用)。
6)試料は冷凍し、暗所に保存する。
7)運搬・保存容器等は、ガラス製ないしはフッ素樹脂製等のものを用いる。運搬・保存容器等の選択に当たっては、ブランク試験を行い、分析対象物質の汚染がないことを確認する。
2.器具・装置及び試薬類
2−1器具・装置
2)試料の汚染を防ぐ観点から、使用するすべての器具及び装置はクリーンな状態に保つこととし、当該分析対象物質専用とすることが望ましい。
<例>
2−2試薬類
2−2−1標準品
2)ロット番号等を5.に従って記録する。
2−2−2試薬
2)必要に応じて蒸留、加熱処理、洗浄等により精製する。
3)第2部の分析法に従って使用する量が、定量に悪影響を及ぼさないことを確認する。
<例>
3.分析法
3−1試料調製法(クリーンアップ、濃縮)
2)溶媒の濃縮に際しては、ロータリーエバポレーター、クデルナダニッシュ(KD)濃縮器及び窒素吹きつけ濃縮操作等での汚染を排除する。
3−2測定(分析装置の保守管理、校正、洗浄)
GC/MSを分析対象物質が測定できる条件に設定し、GC/MSの再現性、感度等が適切な状態であることを確認する。
2)HPLC等の分析装置の状態確認及び測定条件の設定
分析対象物質が測定できる条件に設定し、HPLC等分析装置の再現性、感度等が適切な状態であることを確認する。
3)GC/MS、LC/MSで測定するときは、同位体希釈質量分析(IDMS)によることが望ましい。
4.検出下限値
4−1装置の検出下限値
標準物質を測定したときのクロマトグラムピーク高が S/N=3 に相当する標準物質の絶対量を装置(HPLC、GC、GC/MS、LC/MS等)の検出下限値とするが、分析機器で検出できる低濃度標準溶液を5回以上繰り返し測定し、その標準偏差の3倍を検出下限値としても良い。
2)実測定の検出下限値
実試料を測定し、そのときの分析対象物質のクロマトグラムピーク高を標準物質のピーク高と比較し、試料中のピーク高がS/N=3に相当する標準物質濃度と、採取試料量等から計算した値を実測定における検出下限値とする。実試料でピークが出現しない化合物に関しては、S/N=3に相当するピーク高を、標準物質を測定したときのピーク高から推定し、それに等しいピーク高に相当する標準物質濃度と採取試料量等から計算した値を実測定の検出下限値とする。なお、試料の検出下限値は目標定量下限値を満足していなければならない。
5.精度管理及び精度保証
概略を図1に示した。
測定値の精度保証のため以下のとおり、作業し、記録を取る。記録すべき事項を欠いている場合は、その原因を明らかにするとともに、可能な場合は原因を取り除いた後、再分析等を行う。
2)試料採取の記録:試料の採取日時・場所、採取者、採取器具・容器、採取方法、運搬・保存容器、保存方法等を記録する。
3)試験機関における試料の受付・確認の記録:試料確認の日時・場所、確認した者、運搬方法、試料の状態、保管場所、保管方法、管理番号等を記録する。運送業者を利用した場合、その配送伝票の複製を保管する。
4)試薬類の記録:用いた標準品・試薬のメーカー名、製品名、ロット番号、純度、使用期限、購入日、購入先等を記録する。調製した場合その状況(調製日時・場所、調製者、試薬類の使用履歴等)を記録する。
5)機器の記録:使用記録(使用状況、測定条件)、日常点検記録、感度の記録(測定時に必要な感度が得られていることを確認できる記録(クロマトグラム等))、保守点検・修理の状況等を記録する。
6)分析の記録:分析の各段階における操作日時、分析場所及びその環境、分析者、分析した試料、分析に供した試料の量、試料の測定順序、用いた試薬類及び使用量、を記録する。
7)最終溶媒ブランク、全操作ブランク、2重測定(同一試料バイアルからの2回測定、試料採取からの2重測定)等の記録を残す。
8)同位体測定を行う場合、標準物質の同位体比を確認:測定した標準物質中の各化合物に関して、2つのモニターイオンのレスポンス比が理論値とずれていないことを確認できる記録を残す。理論同位体存在比と実測同位体比の採用範囲は30%以内とする。
9)クロマトグラムの保管:標準溶液、最終溶媒ブランク、全操作ブランク、試料に係るクロマトグラムを保管する。
10)計算
11)ブランク試験
12)2重測定
分析検体数10に対して1以上の頻度で行うことが望ましい。この2重測定の結果は各実測値の差が30%以内であることが望ましい(実測値が目標定量下限値の10倍以下の化合物に関しては規定しない)。
13)外部機関とのインターキャリブレーションを行うことが望ましい。
7.その他
食品衛生法「食品衛生検査施設における検査等の業務管理要綱」参照。
図1
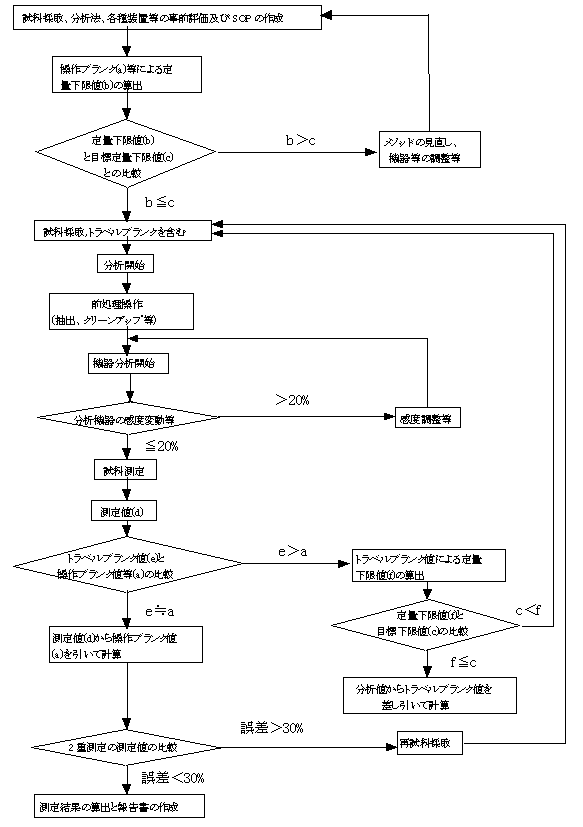
第2部
食品中のビスフェノールAの分析法
【試験法の概要】食品からアセトンによりビスフェノールA(BPA)を抽出し、抽出液をC18及びPSA (primary secondary amine)カートリッジにより精製後、ヘプタフルオロブチル(HFB)誘導体1)とした後にガスクロマトグラフ/質量分析計(GC/MS)で定性・定量する。
【試薬】
すべての試薬類は、クロマトグラム上でBPAの分析に支障がないことを確認した後用いる。
(2) アセトン、ジエチルエーテル、アセトニトリル、メタノール、トルエン、n-ヘキサン:残留農薬試験用又はHPLC用を用い、使用直前に開封する。
(3) 水酸化ナトリウム、塩酸、リン酸:試薬特級品を用いる。
(4) 塩化ナトリウム、無水硫酸ナトリウム:試薬特級品を450から500℃で5時間加熱処理して用いる。
(5) 精製水:BPAフリーのミリQ水等2)を用いる。
(6) ヘプタフルオロ酪酸無水物:ガスクロマトグラフ用を用いる。
(7) C18及びPSA (primary secondary amine)カートリッジ:充填量 500mgのものを用いる。C18カートリッジはアセトニトリル及び蒸留水各10mLで、PSAカートリッジはアセトン及びn-ヘキサン各10mLでコンディショニングした後使用する。
(8) 食塩水:精製水1Lに塩化ナトリウム 200gを溶解して使用する。
(9) 0.5 mol/Lリン酸緩衝液:リン酸二ナトリウム12水和物53.72gを精製水300mLに溶解したものと、リン酸二水素ナトリウム46.80gを精製水600mLに溶解したものを混合してpHを6.0に調整した後使用する。
(10) 標準溶液、内標準溶液:BPA及びBPA−d16各50mgを50mLのメスフラスコにとり、メタノールで50mLとして標準原液、内標準原液を調製し、適宜希釈して標準溶液及び内標準溶液とする。
【器具】
器具の洗浄は常に一定の条件で行う。特にガラス器具は洗浄後、200℃で2時間以上加熱し、BPAの汚染を受けないところで放冷する。使用直前にアセトンで洗浄して使用する。
【装置】
ガスクロマトグラフ/質量分析計(GC/MS):電子イオン化(EI)イオン源及びキャピラリーカラムを装着し、選択イオン検出法(SIM)による分析が可能な装置を用いる。
【試験溶液の調製】2)
試料は必要に応じて蒸留水を加えてホモジナイズして均一とし、その20g3)を遠心分離管に量り採る。BPA−d16 0.2 μg及びアセトン100 mLを加えてホモジナイズ抽出4)後、遠心分離(3000rpm,10分間)し、上清をとる。さらに、残さにアセトン50mLを加え,同様に操作する。
(2)抽出溶液の精製
上清を合わせ、減圧濃縮後5)0.2 mol/L NaOH 20mLを加えて溶解して分液ロートに移し、n-ヘキサン50mLで3回洗浄6)する。0.1 mol/L 塩酸 50 mL を加えた後、50% ジエチルエーテル/n-ヘキサン 50 mL で2回振とう抽出する。抽出液を合わせ、無水硫酸ナトリウム30gで脱水後減圧乾固する。残さを30%アセトン/n-ヘキサン 3mLで溶解し、PSAカートリッジに負荷する。カートリッジを30%アセトン/n-ヘキサン10mLで洗浄後、70%アセトン/n-ヘキサン10mLで溶出する。溶出液を減圧乾固後、50%アセトニトリル2mLに溶解し、C18カートリッジ7)に負荷する。カートリッジから50%アセトニトリル3mLで溶出し、流出液と溶出液を合わせ、20%食塩水を10mL加えた後、50%ジエチルエーテル/n-ヘキサン5mLで2回抽出する。抽出液を減圧乾固後トルエン1mLに溶解する。ピリジン8)20μL、ヘプタフルオロ酪酸無水物100μLを加え、室温で30分間放置する。反応液に0.5mol/Lリン酸緩衝液6mL及びトルエン3mLを加え、振とう抽出後トルエン層を無水硫酸ナトリウムで脱水して試験溶液とし、GC/MSに供する9)。
【試験操作】
| カラム: | ヒューズドシリカ・キャピラリーカラム(内径 0.25mm、長さ 30m、膜厚 0.25 μm)、液層は5%フェニルメチルシリコンを使用する10)。 |
| カラム温度: | 80℃(1min)→25℃/min→150℃→10℃/min→300℃(7min) |
| 注入口温度: | 250℃ |
| 注入方式: | スプリットレス |
| 注入量: | 2μL |
| イオン化エネルギー: | 70eV |
| SIM条件: | 定量用、m/z 605、331 (BPA)1)、616 (BPA-d16) 定性用、m/z 315、 331、 169 (BPA) m/z 321、 169 (BPA-d16) |
(2) 定性、定量:試験溶液の一定量をGC/MSに注入し、SIM法を用いて上記に示したBPAの確認用イオン及び定量用イオン、内標準物質の定量用イオンをモニターし、SIMクロマトグラムを得る。定量用イオン及び確認用イオンが同時に検出されたピークについて、その保持時間がBPAのそれに一致することを確かめ、保持時間に相当する位置の定量用イオンのピーク面積(あるいは高さ)を求める。あらかじめ作成した検量線よりBPAの濃度を求める。
(3) 検量線の作成: BPA標準溶液1.25〜250ng/mLの範囲で段階的に調製し、試験溶液調製法に従ってヘプタフルオロ酪酸無水物と反応後、GC/MSに供する。得られたクロマトグラムよりピーク面積を求め、内標準(BPA-d16 )とのピーク面積比から検量線を作成する11)。
【検出下限・定量下限】
全操作を通したブランク値の標準偏差(SD)の3倍を検出下限値(LOD)、10倍を定量下限値(LOQ)とする12)。
【注解】
BPAは、ポリカーボネート樹脂、エポキシ樹脂の原料やポリ塩化ビニルの安定剤として多用されている.その国内生産量は平成11年度で約35万トンである。BPA は2分子のフェノールとアセトン1分子の縮合反応物で、その性状は白色の粉末状でアセトン、メタノールには易溶であるが水には溶けにくい性質を有している。
2) BPAは、プラスチック製実験器具、精製水、駒込ピペットのゴムキャップなどにも含まれており、高感度分析を達成するためには次の点等に留意し、操作ブランク値の低減化を図る必要がある。
3) 脂質の多いチョコレート(10g)やバター(5g)等の食品は、サンプリング量を少なくする。
4) ばれいしょ、ぶどうなどでは、食品成分によりBPAの吸着・分解が疑われる。吸着・分解を抑制する目的でリン酸(1mL/20g)の添加は有効である。
5) 数mL程度まで濃縮する(アセトンが留去されるまで)。
6) n-ヘキサン洗浄操作は、主として脂肪の除去のため行う。したがって、野菜・果実などの場合、本操作は省略できる。
7) C18カートリッジは、高級脂肪酸の除去を目的に使用する。したがって、野菜・果実などの場合、本操作は省略可能である。なお、PSAカートリッジのみで色素成分の除去が不十分な場合、C18カートリッジによる操作は色素成分の除去に有効である。
8) 反応触媒として用いる。トリエチルアミンも採用できるが、反応再現性の点ではピリジンが優れている。
9) 本操作によるBPA-d16 の添加回収率は、0.2μg/20gの添加レベルで70〜90%である。なお、本添加濃度レベルでの回収率は70〜120%の範囲であることが望ましい。
10) J&W Scientific社製のDB-5MS等がある。
11) サロゲートによる内標準法を採用することにより、より正確な測定が可能となる。
12) 本法の目標検出下限値 (LOD)は食品中濃度として1ng/g、定量下限値(LOQ)は3ng/gである。
食品中のフタル酸エステル類の分析法1、2)
【試験法の概要】
食品からアセトンによりフタル酸エステル類(PAE)を抽出し、抽出液をフロリジルカラムクロマトグラフィーによって精製し、ガスクロマトグラフ/質量分析計(GC/MS)で定性、定量を行う。
分析の対象となるPAEは、フタル酸ジエチル(DEP)、フタル酸ジプロピル(DPP)、フタル酸ジ-n-ブチル(DBP)、フタル酸ジ-n-ペンチル(DPeP)、フタル酸ジ-2-エチルヘキシル(DEHP)、フタル酸ジシクロヘキシル(DCHP)、フタル酸ブチルベンジル(BBP)である。
なお、本法は農水産物、加工食品全般に適用できる。
【試薬】
すべての試薬類は、クロマトグラム上でPAEの分析に支障のないことを確認した後用いる。
(2) 無水硫酸ナトリウム:PCB・フタル酸エステル試験用を用いる。
(3) 塩化ナトリウム:試薬特級品を 450 から 500℃ で 5 時間加熱後、汚染のないところで放冷したものを用いる。
(4) 精製水:逆浸透、ミリQ及び紫外線処理した精製水、あるいは市販のフタル酸エステル分析用精製水を用いる4)。
(5) フロリジル:残留農薬試験用を500℃で5時間加熱し、デシケーター内で放冷する。これに精製水を加え、6%含水フロリジルとして使用する。
(6) フタル酸エステル及びフタル酸エステル-d4標準品:純度98%以上のものを使用する。
(7) PAE標準溶液:各標準品 50 mg を 50 mL のメスフラスコに量り取り、n-ヘキサンにて 50 mL とし、1000 μg/mL 溶液を調製する。適宜希釈し、PAE標準溶液とする。
(8) 内標準溶液:各フタル酸エステル-d4標準品 10 mg を 100 mL のメスフラスコにとり 、n-ヘキサンで 100 mL とし、100 μg/mL 溶液を調製する。適宜希釈し、内標準溶液とする。
【器具】
器具の洗浄は常に一定の条件で行う。特にガラス器具は洗浄乾燥後、200℃ で 2 時間以上加熱し、環境中のフタル酸エステルによる汚染を受けないところで放冷する。使用直前にアセトン又はn-ヘキサンで洗浄して使用する。
【装置】
(2) フロリジルカラム:ガラス製クロマトカラム(内径10mm、長さ300mm)に6%含水フロリジル1g をn-ヘキサンを用いて湿式で充填し、その上に無水硫酸ナトリウム1gを積層する。
【試験溶液の調製】5、6)
ii) 液体試料
試料 50 g を分液ロートにとり、一定量の内標準溶液を添加し、酢酸エチル:n-ヘキサン(1:2)50 mL で2回抽出を行い、以下、固体試料と同様に操作する。
(2) 抽出溶液の精製
残さを溶解したn-ヘキサン溶液をフロリジルカラム9)に負荷する。その後、n-ヘキサン50 mL で洗浄し、0.5%アセトニトリル/n-ヘキサン 50 mL でPAEを溶出する。溶出液を減圧濃縮後、10 mL に定容し、試験溶液とする。
【試験操作】定性、定量分析10)
| カラム: | ヒューズドシリカ・キャピラリーカラム(内径 0.25 mm、長さ 30m、膜厚 0.25 μm)液層は5%フェニルメチルシリコンを使用する11)。 |
| カラム温度: | 50℃(1分)→20℃/分→280℃(分) |
| 注入口温度: | 220℃ |
| 注入方式: | スプリットレス |
| イオン化エネルギー: | 70eV |
| キャリヤーガス: | ヘリウム、流量:1.2mL/min |
| モニターイオン: | 表1に示した。(別冊参照) |
(2) 定性、定量:試験溶液の一定量をGC/MSに注入し、SIM法を用いて表1に示した各PAEの確認用イオン及び定量用イオン、内標準物質の定量用イオンをモニターし、SIMクロマトグラムを得る。定量用イオン及び確認用イオンが同時に検出されたピークについて、その保持時間が各PAEのそれに一致することを確かめ、保持時間に相当する位置の定量用イオンのピーク高又は面積を求める。あらかじめ作成した検量線より各PAEの濃度を求める。
(3) 検量線の作成:各PAEの濃度を段階的にとり、これに試験溶液と同濃度の内標準物質を加え、試験溶液と同様にGC/MS分析を行い、内標準法により検量線を作成する。
【注解】
2) 本法ではサロゲートによる内標準法を採用し、回収率を補正している。また、本法の目標検出下限値は食品中の濃度としてDEHPで 50 ng/g、その他のPAEで 10 ng/g とする。
3) 開封後長期間経たものは、環境中からフタル酸エステルが混入している可能性が高いので、使用しない。
4) 使用する精製水に妨害ピークが認められた場合には、n-ヘキサンによる洗浄を繰り返し実施するとよい。
5) フタル酸エステルの分析では試薬器具等に起因する汚染に十分注意する必要があり、試料を用いずに、試料と同様に操作を行うブランク試験を必ず実施し、分析操作中に混入するPAEを把握する必要がある。また、操作を重ねる毎にブランク値が高くなるため、できるだけ簡潔な方法を採用することが望ましい。
6) 試料を開封し、直ちに検査を実施しない場合には、ガラス瓶に入れ、密閉して−20℃以下で保存する。
7) 脂質の多い試料は分析に供する量を少なくしたほうが良い。
8) アセトニトリルが残っていると、フロリジルカラム処理において、n-ヘキサンによる洗浄段階でフタル酸エステルが溶出することがある。
9) 脂質の多い場合は、フロリジル量を多くするか、カラムに負荷する量を少なくする。
10) 溶媒等に混入しているフタル酸エステルがスプリットベントラインに溜まってしまうことが予想される。注入後スプリットベントラインを大量のガスパージすることにより、汚染を少なくすることができる。分析を始めるに当たって、n-ヘキサンのみを数回注入し、GC/MSの状態をチェックすると良い。また、GCにオートサンプラーで試験溶液を注入すれば、ブランク値が低くなり、その値も安定する。
11) J&W Scientific社製の DB-5MS 等がある。
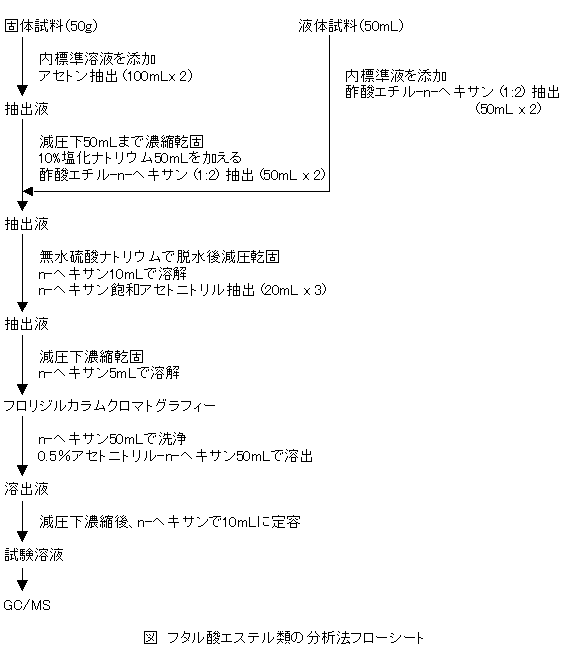
食品中の4-ノニルフェノールの分析法1,2)
【試験法の概要】
各種食品(精白米、畜産物、水産物、乳製品、野菜、果物)からアルカリ性エタノールで加熱還流して抽出し、精製後ガスクロマトグラフ/質量分析計(GC/MS)により定性、定量を行う。
なお、本試験の主な対象化学物質は、4-ノニルフェノール(NP)であるが、その他のアルキルフェノール(4-ブチルフェノール、4-ペンチルフェノール、4-ヘキシルフェノール、4-ヘプチルフェノール、4-オクチルフェノール)及び2,4-ジクロロフェノールにも適用できる。
【試薬】
すべての試薬類は、クロマトグラム上でNPの分析に支障のないことを確認した後用いる。
(2) 標準溶液の調製:NP標準品1) 50.0 mgを50 mLのメスフラスコに量りとり、アセトンを加えて50mLとして標準原液を調製し,適宜希釈して標準溶液とする。
(3) 有機溶媒:残留農薬試験用、環境分析用又はHPLC用を用いる。
(4) 精製水:NPの汚染が少ないミリQ水又は市販のフタル酸エステル類分析用精製水を用いる。
(5) 内標準物質:NPの直鎖重水素化体を使用して、内標準補正を行う。回収率や再現性等測定に支障のない場合は、絶対検量線法による測定も可能である。
(6) 前処理用カートリッジ:クリーンアップに使用するカラムとして、その回収率及び精製効果より、10%含水酸性アルミナとSAX(Varian製)を用いる。
【器具】
器具の洗浄は常に一定の条件で行う。特にガラス器具は洗浄後、200℃で2時間以上加熱し、環境中のNPの汚染を受けないところで放冷する。使用直前にアセトンで洗浄して使用する。
【装置】
ガスクロマトグラフ/質量分析計(GC/MS):電子イオン化(EI)イオン源及びキャピラリーカラム(スプリットレス)を装着し、選択イオン検出法(SIM)による分析が可能な装置を用いる2)。
【試験溶液の調製】
図1及び図2に示した分析法フローシートに従って試験溶液を調製する1,3)。
【試験操作】
| カラム: | ヒューズドシリカ・キャピラリーカラム(内径 0.25 mm、長さ30 m、膜厚 0.25μm)、液層は5%フェニルメチルシリコンを使用し4)、ガードカラムとして不活性化キャピラリーカラム(内径0.25 mm、長さ1 m)を接続する。 |
| カラム温度: | 50℃(1min)→10℃/min→300℃(4min) |
| 注入口温度: | 250℃ |
| トランスファーライン温度: | 310℃ |
| キャリヤーガス: | ヘリウム(1mL/min) |
| 注入圧力: | 7.7psi→99psi/min→40psi(0.1min)→99psi/min→7.7psi |
| イオン化エネルギー: | 70eV |
| 測定モード: | SIM(誘導体化する場合は、引用文献2)を参考にする。また、誘導体化しない場合は m/z 135) |
| 注入量: | 2 μL(スプリットレス) |
(2) 定性:標準溶液及び試験溶液をGC/MSに注入し、SIM法を用いて得られたクロマトグラム上のピークの保持時間及びピークパターンを比較して定性を行う。場合によっては、SCANモードでマススペクトルを測定し、比較する。
(3) 定量:ヘプタフルオロ酪酸(HFB)無水物による誘導体化後測定を実施する。定量は、GC/MS−SIMにより、主なピーク12本の総面積を用いて行う。また、誘導体化を行わない場合は、SIM (m/z 135)測定で検出される5本ピーク中、妨害を受けない2本のピーク面積を用いて定量を行う2)。測定において、操作ブランクを生じる場合があるため、注意が必要である。そのため、操作ブランクモニタリングを数回行い、NPの操作ブランク値を求め、試料濃度より差し引いて測定値を算出する。また、ブランク値の標準偏差の3倍以上を測定試料に対する検出下限値とする。
【参考測定法】
本法は、食品を分析対象とした方法である。食品以外の試料を分析対象とした方法(GC/MS,LC,LC/MS等)も報告されており、参考測定法として参考文献を示す3-8)。
【注解】
2) 例)HP5890(Series II)-HP5972 MSD(Hewlett Packard 社製)
3) 食品用器具及び容器・包装からの汚染が予想されるため、以下の注意が必要である。
4) J&W Scientific社製のDB-5MS等がある。
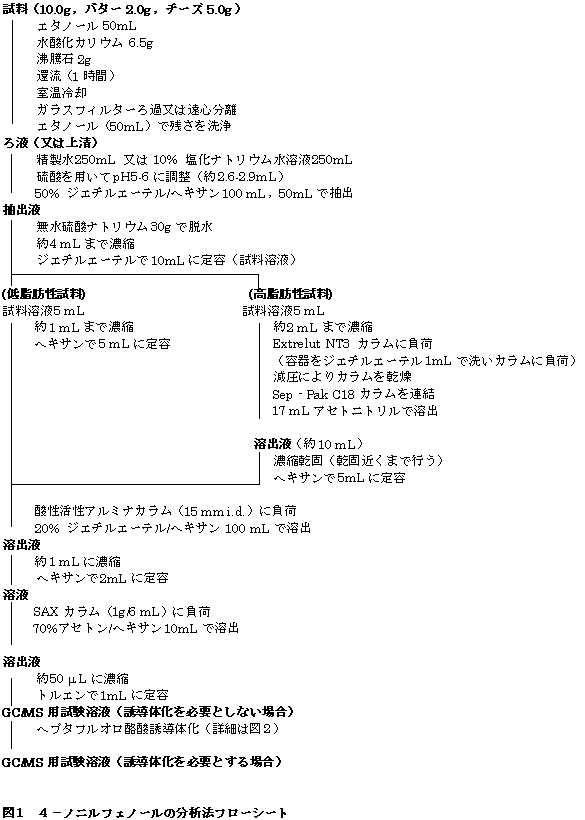
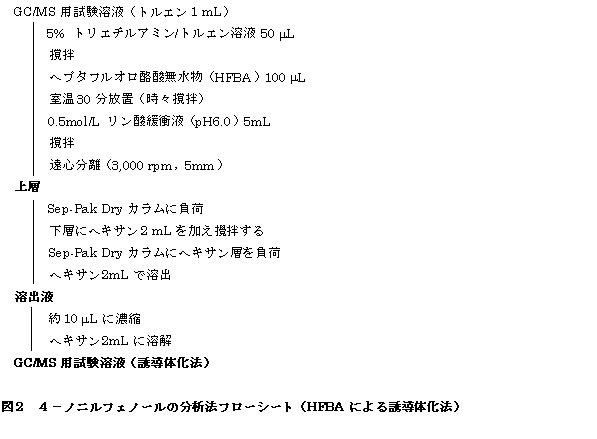
1.はじめに
化学物質の用量(濃度)と生体に与える影響については、一般的に毒性発現の閾値があり用量を増加させることにより毒性発現が増大しシグモイド(あるいはS字)形で表されるような関係を示すと考えられている。しかし、vom Saalらは、妊娠雌ネズミに、これまで影響を表すと考えられていたよりもはるかに少ない量の化学物質を投与したときに、生まれてきた雄ネズミの前立腺重量が増加したということから用量反応パターンは逆U字形を示すと報告し、ホルモン様作用を持つ物質の場合には従来考えられていたよりも低い用量による影響が観察されると主張した。
このような低用量作用の意義をどう理解するかにより、閾値を前提としたこれまでのリスク評価の考え方(動物での無毒性量を不確実係数で除して人での安全量を求める考え方)に基づく化学物質の安全性評価試験方法の見直しが必要となる。
そうしたことから、EPAは、米国国立保健研究所の傘下の米国国立環境衛生科学研究所に属する米国国家毒性計画に対して、この問題を内分泌学、毒性学、生物学などの専門家で精査することを依頼し、平成12年10月10−12日、ノースカロライナ州で、低用量問題に関する文献査読会議(ノースカロライナ会議)が開催された。しかしここでは、低用量作用が存在するとする見解と低用量作用が認められないとする見解双方に信頼性(credibility)を確認するという結果に終わり、今後に解明すべき課題を残すとともに、低用量作用の毒性学的な意義を明確にできないという現段階の認識を浮き彫りにした。
しかしながら、低用量問題は、内分泌かく乱化学物質の関わりの可能性が問われている精子の質的・量的機能低下、免疫系に対する影響、子宮内膜症などの諸問題のそれぞれに確かに関わっていると考えられる。例えば、マウスの前立腺重量増加に影響を与えるビスフェノールA(BPA)の用量は 2 μg/kgと低く、子宮内膜症で検討対象となったアカゲザルの実験におけるダイオキシン(2,3,7,8-TCDD)の毒性反応を起こす最小毒性量(LOAEL)は、100 pg/kg/dayとさらに低い値であったという報告がある。これら個々の問題の解決は、低用量問題をめぐる諸問題の解決次第という面もあり、他方、個々の問題の解決こそが低用量問題をめぐる諸問題の解決に寄与するものとも言え、ここではその双方の可能性から検討をすすめる。
昨年12月の本検討会での合意事項に従って、この問題について重点的な調査を開始した本作業班では、ノースカロライナ会議の成果を踏まえつつ、独自に文献調査を行い、今後の解決への道筋を明らかにすべく検討を行った。
低用量問題は、種々のホルモン様作用をもつ化学物質の、(1)受容体を介した作用様式、(2)その受容体側の多様な反応特性、及び(3)ホルモン様物質の形態形成期にかかわる不可逆性変化に関連した要因など、いくつかの異なった要因が関係しており、各要因の作用メカニズムにかかわる解明が待たれている。この問題は現状では可能性の問題ではあるが、そうした諸々のメカニズムにかかわることが明らかになりつつあるのは、国際的な研究の進展に基づく重要な成果である。しかし、これまでのいずれの化学物質の毒性解明にあたってもしばしばそうであったように、毒性発現メカニズムを明らかにすることは容易なことではない。
2)低用量作用の語義
ノースカロライナ会議では、低用量作用を「ヒトの通常の暴露の範囲又はEPAで採用している生殖・発生毒性評価のための標準試験法において一般に使用されている用量より低い用量で起こる生物学的変化」とした。本作業班では、それを踏襲して、低用量作用を、「標準的な毒性試験において観察されてきた無作用量(NOEL)や無毒性量(NOAEL)よりも低い用量で観察されるホルモン様の影響」として考える。この場合、対象となる濃度は、生体内の17β-エストラジオールを例とすると10-10M程度の血中濃度(この濃度は、動物に数μg/kg/day投与したときに得られる)である。
2.ホルモン様作用と内分泌かく乱の区別
内分泌かく乱化学物質問題では、ホルモン様作用を及ぼす化学物質の存在と、それらによる生体障害性の両者について仮説が提示され、検討がなされてきた。試験法の開発((1)試験スキーム)では、ホルモン様作用の有無を同定・検出する試験法の開発と、その生体障害性作用を検出する方法がそれぞれ検討されているが、前者と後者の作用メカニズムは、今後の対応策も念頭に置き、相互の関連を考慮しつつも、概念的には区別しながら検討する必要がある。
ホルモン様作用を持つ化学物質は、(1)何らかの形で種々のホルモン受容体との直接相互作用を有するものと、(2)これらへの間接作用を有するもの、特に、(3)内分泌ホルモン代謝に対して作用するものなどに区別される。
ここで、(1)〜(3)の諸作用について、受容体との相互作用、作用における閾値の有無の問題、用量作用反応の性質、作用のきっかけとなるシグナルの特徴、さらに胎児及び新生児に対する特異的な影響に関心が集まっている。
本作業班には、低用量問題に対する重点的な作業が求められているので、ここではホルモン受容体と化学物質の相互作用の問題を中心に検討を行い、その他の事項については、必要に応じて記述した。
3.ホルモン様作用を有する化学物質
ホルモン様作用を有する物質には、(1)生理的ホルモン、(2)ホルモン療法に用いられるホルモン様作用を有する種々の医薬品、(3)植物ホルモン及び(4)種々の化学物質の中で、ホルモン受容体との相互作用又は内分泌器官へ影響を与えることが知られている物質群などがあげられる。この他、受容体との相互作用を介さずにステロイド代謝を修飾する物質、性腺へ作用する物質等が、広義のホルモン様作用物質として加えられる。
ホルモン様作用を有する化学物質の受容体を介する作用の特徴としては、(1)種を越えた受容体構造の近似性、(2)各種性ステロイドホルモンの活性部位の構造の近似性及び(3)受容体反応特有の未知の事柄(受容体結合とシグナルの関係、受容体結合と解離、各種シグナルの交叉性、未知の核内受容体の関与、など)をあげることができる。外因性のホルモン様作用を有する化学物質の多くは生体内において、生理的ホルモンの存在下で作用することになるという点も特徴の一つといえよう。
これら化学物質の"ホルモン様作用の強さ"は、評価法によって異なる。例えば受容体結合反応でみる場合、及び受容体と作用物質(リガンド)との解離の速度係数を指標にみた場合で、双方の指標は必ずしも平行しないが、両者ともに生体と化学物質との反応の局面を表現していると考えられる。これらについては解明の途上にあり、現状ではホルモン様作用の強さを一般化した表現で説明できる段階にないが、生体障害性の有無についての議論においては投与条件にかかわることが多い。極端な条件下での生体障害性の如何については、摂取・摂食量に応じて説明ができると考えられる。また、例えば、大豆の成分であるゲニスタインでは、日本人の摂取量の範囲での抗乳がん作用及び閉経後のホルモン代替療法としての有効性が信じられている。
既に、ホルモン様作用を有する農薬の安全性評価が行われてきたが、ここでは、従来評価が行われてきた用量よりも低用量における影響を取り上げるという点で区別される。
4.低用量作用をめぐる諸問題
多くの化学物質の高用量における生体影響・生体障害性に対する安全管理についての考え方は、それなりに整備されているので、前項にみたようなホルモン様作用と生体障害性の境界にまたがった形での低用量作用が問題の焦点となる。
生物学的恒常性(ホメオスタシス)が機能している成熟個体においては可逆的な変化を惹起するにとどまる用量の化学物質であっても、生体の発生期、形態・機能形成期においては非可逆的な変化を惹起する可能性が指摘されている。したがって、実験的にも、疫学的にも、発生期、胎生期・形態形成期の暴露には特に注意を払うことが求められている。ヒトにおけるこのような作用の可能性について見解は様々であるが、実験報告を基礎として生物学的に説明可能である点については、現状で明確に否定する根拠はない。これとあわせて、受容体の状態により、ホルモン様作用物質の効果が異なることも知られている。成長期の小児・思春期と成人、あるいは成人と更年期後の女性とでは、ホルモンに対する受容体の応答性が大きく異なる可能性が指摘されており、これに呼応して、ホルモン様作用物質の作用も異なったものになると信じられている。
2)生物学的蓋然性*について
低用量作用についての現時点の科学的解明は、まだ不完全である。我が国の諸研究だけでなく、EPA及び食品医薬品庁、欧州共同体の環境化学担当部門などの機関が今日までに集約した結果でも、「低用量作用に関する十分なデータを持ちあわせていないという点に充分注目する必要がある」と結論するにとどまっていることに象徴される。具体的には、低用量影響が認められるとする見解と認められないとする見解とが両立するために、実験系の手探り状態となっているのが現状である。先のノースカロライナ会議における個々の論文の重点的な検討結果(別冊1-3、文献査読会議報告和訳参照)でも、また、同一の関係論文について当作業班が独自に検討(本作業班では、特に用量―作用曲線パターン、閾値の有無、反応オシレーションの有無、相加・相乗性の有無といった点に着目して検討を行った。)した結果(別冊1-3参照)でも、低用量影響が認められるとする見解と認められないとする見解の双方に信頼性を確認するという結果になっている。
このように両者に信頼性を確認することになった背景には、それらが生物学的には説明可能であるという根拠が控えている。すなわち、(1)報告された多くの物質で、リン脂質細胞膜の易透過性及び受容体結合の可能性があることの指摘、(2)用量増加に伴い受容体遺伝子の発現が抑制を受け、結果として反応が低下することによる非直線性の用量−反応関係、(3)核内受容体相互の交叉反応性などの指摘、更にデータを公表する動き、があることである。これらにより、低用量作用が生物学的には説明可能であることは示せても、現時点において、これをヒト健康影響の可能性の問題とするには、データが不足している。
3)試験系とデータ解釈
低用量作用の有無とその用量−反応相関については、試験系に依存して、異なった結果が得られている。標準的な試験系が確立していないために、いくつかの影響の有無についての論争が継続しており、試験を行った研究者により、陽性あるいは陰性の両方の結果が得られている。この背景には、(1)試験条件(動物を含む)の違い、(2)観察条件と観察内容の違い、(3)未解明のメカニズムによる影響の関与、などが考えられる。
そこで低用量作用について報告していると考えられる文献(ノースカロライナ会議での検討のために提供された未公表のものを含む会議時点までに入手した関連文献、及び我々の調査過程で目についた重要な最新の関連文献の計64文献)についてノースカロライナ会議で指摘された問題点を踏まえつつ、次の項目について精査し、データベース(添付省略)に整理した。さらに用量―作用曲線パターン、閾値の有無、反応における逆U字現象の有無、反応における相加・相乗性の有無について問題点を抽出し、検討を加えた。
その結果、各報告を(ア)低用量作用があると報告されている文献、(イ)著者の主張にもかかわらず実験上の不備などにより低用量作用があることを示すといえない文献、(ウ)低用量作用が見られないと考えられる文献、(エ)いずれとも判断できない文献に分類し、その判断根拠を付した。調査結果から要点を以下に記す。
Ashbyら(1999)は、vom Saal(1998)らによる低用量のBPA暴露により精子生産効率及び前立腺重量への影響が見られたという報告の再現性について検討した中で、動物の系統だけでなく、実験動物供給源の違いによる動物の感受性や生理状態(遺伝的な背景を含む)の違いの可能性があることを指摘している。
(2) 飼料の問題
市販の飼料中には植物エストロゲンなどのホルモン活性を有する物質が混入しており、その混入レベルは十分管理できていない。Odumら(2001)は、低用量での影響が見られた又は見られなかったというこれまでの報告中で用いられた飼料(特別仕様のものを含む)及び毒性試験でよく用いられている市販の飼料について、比較分析と生殖・発生毒性試験を行い、いくつかの指標に対する影響について調べた。その結果、飼料中の植物エストロゲンの含量は、発生におけるいくつかの指標に影響を及ぼすが、植物エストロゲン以外にも未知の因子がこれらの指標に影響を与えているらしいことがわかった。
吉田ら(2001)は、市販の固形飼料が40 ppm 程度のBPAを含んでいたと報告し、混入経路については不明であるが製造過程であろうと推定している。
他方、Emaら(2001)は、試験に用いた市販飼料を分析したところ、BPA含量は検出限界(3ppb)以下であったと報告しており、用いる飼料間における差の存在をうかがわせる。
(3) 飼育条件の問題
Ashbyら(1999)はvom Saal(1998)らの報告を再現する試みの中で、仔動物を個別又は群で飼育することによる影響を検討し、個別に飼育した方がやや体重が重くなると報告している。
(4) 用量設定の問題
Nagelら(1997), vom Saalら(1998)は、対照群以外に10倍の公差で2群が設定されているのみで用量段階の不足が見られる。
(5) データの解釈の問題
臓器重量の違いを体重で補正することが適切かどうかについては、双方の変化について相関性の検討が必要であるが、共分散分析では、すべての投与量において相関性が同様に成立することを前提としている。また実際に子宮重量が体重と逆相関するという試験例も見られている。統計処理において同腹仔を適切に扱う(母獣の影響を検討しておく)ことは言うまでもないが、一定数の仔動物を検査する際に、一腹から複数の仔動物を用いて偽陰性率を下げることはできても偽陽性率を減らすことにはならない点に留意すべきである(NTP/NIEHS, 2001)。
4)問題解決のために必要な検討
低用量問題をめぐっては、多くの実験的な工夫が求められている。本項では、この点に関連する主な事項を掲げる。
生体は、生体内の環境を一定範囲に保とうとするホメオスタシス機能によって制御されており、低用量作用は、これに打ち消されて観察されない所見が多いのではないかと考えられる(卵巣摘出動物又は幼若動物を用いる子宮肥大試験は、そうしたホメオスタシスを遮断することによってホルモン作用やホルモン様影響を観察するものである。)。しかし、このことをもって、低用量問題は問題ではないとはいえず、ここではそうした環境下における作用による生体障害の可能性の如何を論じることの難しさがある。さらに内因性と外因性作用物質との間でホメオスタシスへの作用における違いがあるかについても未解明である。
この問題の克服に、今日国内外で検討されている遺伝子発現解析の手法が寄与するかもしれない。
(2)受容体の発現低下
低用量における受容体を介する作用は、高用量ではホメオスタシス機能による受容体の発現低下などの理由によって観察されないこともある。個体レベルでもこうした現象があり得るとすれば、非直線性反応を考察する手がかりになるかも知れない。そのことを一般化するためには、適切な分界点を与える実験系が開発される必要性があるが、現状では、その試験系と評価法は不充分である。
(3)女性ホルモン作用に関する未解明の問題
女児における初経の低齢化や早期の性成熟、あるいは閉経後の女性ホルモン療法と乳がん発生リスクとの関連で、ホルモン様作用物質のリスクが論じられている。しかしエストロゲンの有する弱い変異原性は既知の問題である。成熟女性の生体内にはホルモンが大量に存在しており、ここでは、むしろ成熟女性における 400 pM/L に達するエストロゲンの影響の生理的"安定性"のメカニズムこそ、ある意味では未知の問題と考えられる。そしてこのことは、次の実験的事実とも関連する。
(4)多世代試験と胎児影響
実験的に二世代試験又は多世代試験が行われているが、多くの場合、いわゆる内分泌かく乱化学物質による影響は認められない。例えば、本作業班員のEmaら(2001)による、ラットにBPAの低用量(0.2, 2, 20, 200 μg/kg体重)を投与した二世代試験において、様々な生殖・発生指標(性周期、妊娠率、臓器重量、肛門生殖器間距離、精巣上体精子数及び精子の質的特性、種々の血清性ホルモンレベル、反射反応の発達、など)を検査した結果でも、BPA投与に起因すると考えられる生殖・発生への障害は見いだされなかった。 これまでの報告で影響が認められるのは、胎生期影響及び新生児期影響に限られている。 これに対して、そうした条件下での低用量影響を検出する方法、特にその妊娠中や授乳時における生物の発生過程への影響に注目した方法の開発が種々の面から試みられ始めている。
(5)試験結果の再現性
前記文献調査の結果、次のような研究課題が一つの可能性として浮かび上がってきた。すなわち低用量影響を認めないとする結果では、ジエチルスチルベストロール(DES)のような物質でも反応性が認められなかった事が注目された。この結果からは、追試によって解決することのできない未知の問題が含まれていることが示唆される。本作業班では、DESを陽性対照として用いた試験について、実際に陽性結果が得られた場合及び得られなかった場合の試験条件及び結果について比較検討し、何が結果の違いに寄与していると考えられるのかを解析している。この結果を基にして、陽性対照であるDESについて再現性をもって陽性結果を得られる試験系を確立し、同一条件で他の試験物質がどのような結果を示すか検討できるようにする事が肝要である。
DESを陽性対照に用いた20件の報告を収集し、これらについて低用量での試験結果に違いが見られた場合、試験条件(試験動物、飼育条件、食餌、投与条件)、試験結果(エンドポイントと用量ごとの影響の有無、データの解析)及び反応に影響を及ぼす生物学的要因について比較検討した。その結果、陽性試験結果の再現性を確保するためには次のような調査研究の検討が必要と考えられた(大竹、関沢、印刷中)。
5.ヒトへの生体障害性
低用量作用は、認められるとする研究報告と認められないとする研究報告の双方に信頼性が確認されており、低用量作用による実験的な障害性については生物学的に説明可能であるとの指摘を否定する根拠は乏しい。胎生期・新生児期影響への可能性については、特に注意が傾けられるべきであることが指摘されている。他方、ヒトへの影響の可能性については、疫学研究の必要性が指摘されている(National Research Council, 1999)。実質的にヒトへの影響を取り扱かった報告は、次で述べるダイオキシン類やPCB類を除き見出されず、またそれらの結果についての評価は定まっていない。以下は、現時点における生体影響のケーススタディーである。
ダイオキシン類の障害性については、ラットの2年間投与試験における体重抑制や肝障害、またラットの三世代生殖試験での子宮内死亡、同腹児数の減少などが認められており、さらにアカゲザルの子宮内膜症に関する報告がみられる。
ヒトにおける低用量暴露での影響のうち、内分泌かく乱との関係が指摘されている事実としては、オランダのディメルゼィディク地区(Diemerzeedijk)におけるステロイド代謝に起因するとされる口蓋裂があるが、EPAはその因果関係を採用せず、注視するにとどめている。また、ミシガン湖におけるポリ臭化ビフェニル類汚染魚を食べたことに起因するとされる甲状腺機能低下に関する報告については、議論の決着が得られていない。
(2)乳がん等女性に与える影響
(3)子宮内膜症も同様であるが、乳がんを含むヒト成熟女性に与える影響を肯定する報告は見出されない。ちなみに未知の事柄が少なくない中で、そうした影響の生物学的説明可能性についても成熟個体を用いた実験に関する限り認められない。初経年齢の低齢化と乳がん発生の相関についての考察が散見されているが、この相関については、同時に身長の増加も相関することが知られている。欧州各国では、過去30年間で年平均 3.5 mm の身長の増加と約1年の初経年齢の低齢化が記録されている。これらの相関に外因性内分泌作用物質の影響を加味することは困難であり、少なくとも現状ではそうした調査報告は見られない。受胎調節に用いられるピルや閉経期のホルモン補充療法を含む女性ホルモン剤の影響を見た研究が多数あるが、誘発される反応が内分泌かく乱化学物質の影響として確立した報告は見られない。
(3)子宮内膜症
子宮内膜症は、性周期を有する哺乳綱霊長目の動物に認められる病因不明の疾患で、ダイオキシン類(TCDD/PCBs)による病態の重篤化傾向が指摘されている。その根拠には、アカゲザルの実験データがあるので生物学的説明可能性は否定できない。しかし、これについてヒトでの関連性を肯定する報告は見られていない。
(4)その他のヒト影響の可能性について
ヒトへの影響の可能性の一つとして、BPA重合樹脂成型血液透析器からのBPA溶出による腎障害患者へのリスクが検討された(関沢ら、2001)。これまで報告されたBPAの低用量作用が陽性であったという報告は妊娠マウスにおける前立腺重量増加、精巣上体重量の低下(Gupta , 2000; vom Saalら,1998)及び成熟雄ラットにおける精巣精子生産量の低下(Sakaueら、2001)のみである。後者は妊娠期間中の投与による影響ではないという特徴があり、低用量で見られた影響はさらに用量を10-100倍に増やし高用量にしても一定レベル(精巣精子一日生産量の低下は25%まで)にとどまり用量―反応関係のオシレーションは観察されず、また精巣における病理変化などもなく、この影響が有害な障害であるといえるか否か必ずしも明確ではなかった。これらの報告で影響が観察された濃度は2-50μg/kg体重レベルであるが、実験的に調査した血液透析器からの溶出量を標準的な使用形態にあてはめた場合に8 ng/kg体重に相当 (Haishimaら, 2001) し、動物で低用量影響が観察されたとする濃度に比べてほぼ1000分の1のレベルであった。
免疫影響については油症 (Yu-sho) の報告が知られているが、これはむしろ高濃度暴露による影響の一つと考えられる。
6.試験法の充実と確定試験法の確立
スクリーニング試験によって優先順位付けされる物質の中のどれだけの物質を内分泌かく乱化学物質と考えるべきかについては、見解が分かれている。スクリーニング試験系は、ホルモン作用の検出法から成立しており、内分泌かく乱作用との異同は、作業として区別されるからである。
できるだけ早く、関連物質の事前スクリーニング及びスクリーニングを進めてゆくことの必要性もさることながら、リストアップされるであろう物質の内分泌かく乱性の可能性が定まらないため、試験法のエンドポイントは定まらない状態となる。このような状態でスクリーニング試験によってリストアップされる不確定物質が滞貨する状態は避ける必要がある。このためEPAでも欧州共同体でもスクリーニング後の試験法の充実に乗り出している。EPAにおける甲状腺影響を念頭に置いたげっ歯類思春期雄アッセイ、アロマターゼ試験、げっ歯類胎生期-授乳期試験などは、その例であり、これまでのスクリーニング試験法における不確実性の補強をねらっている。また米国食品医薬品局では、国際生命科学研究所(ILSI)との共同により、遺伝子発現の網羅的検出をリスクアセスメントに用いる検討に力を入れ始めた。他方、世界保健機関/国際化学物質安全性計画(WHO/IPCS)は、地球規模のアセスメントの際に、内分泌かく乱化学物質の「検出法」について言及することを避ける方針をとっている。
我が国では、胎生期ウインドウ効果に注目した1世代試験(子宮内位置効果、肛門・生殖突起間距離、性的二型核などの検討を含む)及び、同じく胎生期ウインドウを考慮した発がん性試験に対して、発現遺伝子の網羅的検索を組み合わせた系を対象に、補助スクリーニング+確定試験としての方向性を検討している。ただし、スクリーニングで選別される物質の中で、真に生体障害性を持つ物質を最終的に選別する確定試験法が、作用メカニズムの解明の現状に照らして適切に開発されるのかどうかについては、課題が残されている。
7.まとめ
現時点では、ヒトに対する内分泌かく乱作用が確認された事例はない。低用量域のホルモン様作用の問題は、内分泌かく乱性を考察する上での中心的課題であるが、現時点で入手できる科学的知見からは、低用量域における内分泌かく乱作用を直ちに断定することには疑問がある。EPAでは、内分泌かく乱性のスクリーニングに関してさしあたり500物質程度、2005年を目途として終了する計画を出している。本作業班では、Emaら(2001)によるBPA低用量試験結果と、前記の独自の文献調査結果を踏まえて考察されたBPAの低用量反応によるリスクの評価(関沢ら、印刷中)などを進めてきた。今後、DES陽性対照が再現性をもって陽性反応を示す試験系の確立とそのための背景データベースの構築や統計解析手法の検討、及びホメオスタシス反応の寄与を確認する遺伝子発現解析などを含む対応するメカニズムの研究を進め、前記の時期に照準を合わせて試験法の開発とそれに基づく試験目標を達成すべく、一刻も早くその実態を明らかにしたい。
総括
外的要因のヒトへの健康影響については、例えば放射線について、広島・長崎・チェルノブイリの事例などが明らかにされ、放射線暴露量と甲状腺をはじめとする諸臓器の発がんについて確かめられた。暴露量の正確な決定が健康影響の検討に不可欠であることを示す事例である。
現在、問題となっているいわゆる内分泌かく乱化学物質についても、事故や不注意による大量暴露により健康影響が問題となった事例がある。1958年に日本で、また1968年に台湾で起きた食用油の製造過程でのPCB汚染では臨床的疾患としての「油症」が出現し、暴露量と臨床症状との関連が討議された。1975年にイタリアで起きた工場事故によるダイオキシンの地域暴露では、成人男性の暴露量とその後のパートナーから生まれた子供の性との関係が最近明らかにされた。最近になって実情が明らかにされたスロバキアのPCB高濃度汚染等については、暴露量と甲状腺自己免疫異常の頻度が関係することが明らかにされている。これらは暴露の初期にたまたま生体試料を採取・保存し、その後測定技術が進歩してからの測定により、暴露量と健康影響との関係について報告がなされ、さらに長期のフォローアップから新しい知見が追加され続けているコホートである。
事故や高濃度汚染以外に、より一般人の生活に近い場面でも、いわゆる内分泌かく乱化学物質の影響が懸念される場面がいくつもある。これらについては人間の側での何らかの異常を感出する手段と生体試料採取など暴露量を評価する体制を確立した上で、厳密な疫学的手法により、暴露と異常との関係が確立されなければならない。
本項では、人間の側の異常を「発がん」、「器官形成」、「神経発達」、「生殖機能」等としたとき、いわゆる内分泌かく乱化学物質との因果関係についてこれまでに報告されている疫学研究の結果をまとめ報告する。また、我が国でも厳密な疫学研究が実施される必要があり、その際に必要ないわゆる内分泌かく乱化学物質の濃度測定法の抜本的改良並びに因果関係の傍証となる実験的研究の成果について報告する。
前者の結果として言えることは、(1)乳がんのリスクはDESにより20〜30%上昇する可能性が示唆されるが、その他のいわゆる内分泌かく乱化学物質による明らかな上昇は認められていないこと、また、その他のがんとそれら化学物質との関係については信頼できる疫学研究が少なく、関連性について言及できないこと、(2)PCBは高濃度暴露により甲状腺異常を来す可能性が示唆されること、(3)尿道下裂、停留精巣など器官形成にかかわる問題については疫学研究が少なくいわゆる内分泌かく乱化学物質との関連性について言及できないこと、(4)PCBは日常摂取されるレベルで、小児の神経系の発達に影響する可能性が示唆されること、(5)精子数低下及び子宮内膜症については疫学研究が少なく、いわゆる内分泌かく乱化学物質との関連性について言及できないこと、等である。今後我が国で質の高い疫学研究が行われる必要性が具体的研究プロジェクトと共に提言されている。
また経口避妊薬のようなホルモン作用を期待して作られた医薬品については、エストロゲンなどの併用方法、使用量、使用期間、使用者の特性などによって異なる影響を与える可能性があるので、今回の考察では触れていない。しかし一方で、女児が胎内でDESに暴露されると子宮の先天奇形や成人前に膣がんを発生するリスクが高まることが知られている。DESは強力な合成エストロゲン剤であり、過去には流産防止や乳がんの治療の目的で使用されていたが、現在では使用が制限されており、DESが使用される以前と使用が制限された後では、そのような例がない。DESは強力なエストロゲン製剤であることから、上記の異常は胎児期に不適当なエストロゲン作用を受けたことに起因すると考えられる。一方、乳がんとの因果関係については、乳がんの多くが成人発症であることから、DESが間接的にホルモン作用に影響を与えた結果である可能性が示唆される。
後者では、BPA、クロロベンゼン類、パラベン類、フタル酸エステル、ベンゾピレン、PCB、クロルデン、トリブチルスズ化合物等について、抽出・測定法を改良して、さい帯血、母体血、母乳、尿、毛髪、腹水、臓器等の濃度を測定したところ、クロルデン及びナフタレンを除いた上記物質は、いずれかの生体試料中に含まれており、環境中暴露の点から問題となりうることが示された。また、いわゆる内分泌かく乱化学物質の一部はヒト由来細胞を用いた受容体に結合すること、作用機序として乳腺細胞・子宮内膜細胞を増殖させ、栄養膜幹細胞分化に影響すること、代謝過程でのグルクロン酸抱合の役割などが明らかにされた。
これらの成果は、今後疫学研究の成果と相まって、いわゆる内分泌かく乱化学物質と人の健康影響との因果関係についての重要な示唆を与えるものと思われる。
(4−1)生体暴露量等(別冊1-4-1参照)
内分泌かく乱化学物質問題が社会の関心を集めて久しいが、環境中暴露や生物発生への影響に関する報告が散発的に行われる中で、ようやく本領域への研究の取り組むべき方向が明確になりつつある。本問題に係る当初の社会的混乱は、水、土壌、魚類などの自然環境からのいわゆる内分泌かく乱化学物質の一時的な検出結果や生物発生異常についての報道が、それら物質を「なんとなく怖い物質」に祭り上げたことに始まる。その後、厚生科学研究による総合的かつ基本的な調査研究等の取組等により、内分泌かく乱化学物質問題の今後の研究・作業の進め方が示唆されるようになりつつある。
内分泌かく乱化学物質の測定法の確立
いわゆる内分泌かく乱化学物質のヒト健康への影響を研究する際に第一に重要な点は、感度と特異性に優れた測定法の確立である。測定法に関連した事項として、試料の取扱は看過出来ない。特に試料の採取から始まり、分離・保存の過程を経て、いかに背景因子の干渉及び夾雑物の混入を防ぎ、信頼しうる測定値を得るに至るかまでの各種操作法の確立は重要である。これついては、既に厚生科学研究「高分子素材からなる生活関連製品由来の内分泌かく乱化学物質の分析及び動態解析(主任研究者:中澤裕之 星薬科大学教授)」において、協力して検討を進めてきたところである。
いわゆる内分泌かく乱化学物質の生体暴露量
第二に重要な点は、真の生体暴露量、すなわちこれら物質の生体中の存在量(体内負荷量)の解析である。厚生科学研究「内分泌かく乱化学物質に関する生体試料(さい帯血等)分析法の開発とその実試料分析結果に基づくヒト健康影響についての研究(主任研究者:牧野恒久 東海大学医学部教授)」では、前出の研究と連携を取りながら、測定法が確立していて安定した測定結果が常に得られ、過去及び現在の我が国における工業生産量等からして黙視できない化学物質として、(1)BPA、(2)クロロベンゼン類、(3)パラベン類、(4)フタル酸エステル、(5)ベンゾピレン、(6)PCB、(7)クロルデン、(8)トリブチルスズ化合物などを測定候補とした。
測定対象としたヒト生体試料は、主として(a)さい帯血、(b)母体血、(c)母乳、(d)腹水などで、可及的に一個体から(a)〜(d)を同時採取し、同一個体内での臓器間の濃度勾配も検討した。
その結果、樹脂原料として未だ年間約30万トン生産されるBPAは、(a)〜(d)いずれの試料においても検出され、その濃度範囲は0.21〜0.79ppbであった。
クロロベンゼン類としてはヘキサクロロベンゼンを分析したが、一般末梢血及び母体末梢血で100%、さい帯血で88%に検出され、その濃度範囲は0.03〜0.10ppbであった。また、同一個体から採取した試料中のヘキサクロロベンゼン濃度について、末梢血と腹水との間に有意な正の相関関係(順位相関関係数=0.722、n=12、p=0.017)が認められた。
一方パラベン類は、メチルパラベンとして、さい帯血や母乳から検出され、妊婦が暴露を受けたパラベン類が、血液を介して母乳やさい帯血に移行したことが推定された。
プラスチックなどの可塑剤として使用されるフタル酸エステルについては末梢血中、腹水中に、フタル酸モノブチル(MBP)、フタル酸モノベンジル(MBzP)、フタル酸モノ-2-エチルヘキシル(MEHP)が、平均で1〜5ng/mLの濃度で検出された。
化石燃料の不完全燃焼などにより大気中に放出されるベンゾ(a)ピレンは、モノヒドロキシベンゾ(a)ピレン(OH-BaP)として男子尿中から検出された。引き続き、母乳、さい帯血、母体末梢血、腹水などにおける暴露状況を検討する予定である。
不燃・絶縁剤として用いられたPCBは、1972年以降生産は中止されているが、母乳、母体末梢血、さい帯血中で35種の同族体及び異性体として検出され、その濃度範囲は脂肪あたり60−99 ng/gであった。
シロアリの駆除などに使用されたクロルデンは、1986年以降生産中止になっているが、trans-ノナクロルが63%(0.06〜0.17ppb)に、cis-ノナクロルが17%(0.03〜0.05ppb)に検出されたが、ヘプタクロロエポキシド、オキシクロルデン、trans-クロルデン及びcis-クロルデンは、いずれの試料からも全く検出されなかった。
船底塗料や漁網防汚剤として用いられ、現在これら開放系の使用が一部中止されているトリブチルスズは、測定法によって差があるものの、毛髪試料の33〜77%に検出(5〜45ppb)され、同一家族から高濃度に検出(41〜45ppb)された例を平成11年に報告している。
また、その他の環境汚染化学物質の暴露状況と比較する意味で、トルエン、ベンゼン、キシレン、スチレン、パラジクロロベンゼンなどの揮発性有機化合物についても測定を行ったところ、末梢血、腹水中に0.6〜4.0 ppbの濃度で検出され、陽性率はトルエンが80%に、パラジクロロベンゼンが49%に、o-キシレンが29%に、スチレンが26%に検出された。なおナフタレンは全く検出されなかった。
生体内での作用発現
第三に重要な点は、ヒト生体内での作用機序の検討である。具体的には、(a)ヒト体内におけるこれら物質の受容体の有無、(b)ホルモン様作用発現の有無、(c)ヒト生体内での代謝・解毒のメカニズム などの検討である。
いわゆる内分泌かく乱化学物質のヒト生体内受容体については、ヒト副腎皮質由来(H295R細胞)、ヒト乳腺細胞(T47D)などに、生体内エストロジェンと同様の受容体が存在することを見出した。さらにヒト子宮内膜細胞(HHUA)、ヒト乳腺由来細胞(MCF-7)を用いて、受容体についてさらに詳細に検討すると、これらの物質はエストロジェンのαとβの受容体と結合することが確かめられた。受容体については、さらに、既知の受容体のほかに、未知のいわゆるオーファン受容体の存在の有無についても検討することとした。
生体内での作用発現については、ヒト副腎皮質細胞に対して、そのコルチゾール産生を抑制することが判明した。また乳腺細胞、子宮内膜細胞の増殖を刺激することも確認された。さらにマウスでは、トリブチルスズが免疫系に作用して経口免疫寛容の誘導に影響を及ぼすことが示唆されること、及びベンゾ(a)ピレンはラットの栄養膜幹細胞株(TS細胞)の分化過程に影響を及ぼすことを見出した。作用発現についての今後の課題としては、生体内に実際に存在するこれら化学物質の量(体内負荷量)の範囲でどのような作用が発現するか否かの検討が残されている。
代謝・解毒の検討は、まだ今後の研究に多くの余地が残されている。BPAを例にとると、ラットではその大部分は消化管と肝臓でグルクロン酸抱合されることが判明した。一方、腎臓では代謝は行われず、ろ過・排泄されるのみであると推察された。グルクロン酸抱合体を分解してもとの化学物質にもどす酵素(β-グルクロニダーゼ)の存在も見出し、今後ヒト生体内での検討を行うこととしている。
結語
以上、本作業班は、生体試料の測定法の確立に基づき、いわゆる内分泌かく乱化学物質の真の生体暴露量を測定すると共に、これら物質の生体内受容体、作用発現、さらに代謝・解毒などの検討を通して、ヒト健康への影響についての結論を導くことをその主たる研究目標とした。
今後は、内分泌かく乱作用が疑われるその他の環境汚染化学物質についても、同一母体の複数部位からの生体試料の採取及び濃度分析データの蓄積を行い、また当該母体の胎児からも同様に生体試料の採取及び濃度分析データの蓄積を行うことにより、母体からの暴露の実態を解明することが目標となる。さらに、これらの物質が生体内に実際に存在する量(体内負荷量)の範囲で、生体にどのような作用を発現するのか否か、代謝・解毒の全容も含めて明らかにすることが求められる。
(4−2)疫学研究(別冊1-4-2参照)
1.はじめに
いわゆる内分泌かく乱化学物質の人への健康影響を評価する場合、動物やヒト細胞などを用いた実験室での研究に基づき、人への健康影響を推察する方法が主として用いられている。しかし、実際に人間社会に存在している量の化学物質が、人に対して何らかの健康影響を及ぼしているか否かを知るためには、人間集団を対象として、化学物質暴露と健康影響との関連を検討する疫学研究から得られる証拠が重要である。
本作業班では、いわゆる内分泌かく乱化学物質暴露による健康影響の可能性が懸念されている、発がん、甲状腺機能、器官形成、小児神経発達、生殖機能などについて、疫学研究に基づいた刊行論文についてレビューすることにより、現状での人への健康影響に関する問題の整理を行うとともに、今後の研究の方向性についての提言を試みた。
2.因果関係の評価の方法論の現状
疫学研究をいわゆる内分泌かく乱化学物質の人への健康影響という問題解決に適用することは、「それら化学物質の暴露量の多い人達が、少ない人達に比べて、ある病気になる確率が高いか否か」について検証を行うことになる。そのためには、疾病頻度の指標、暴露の指標、暴露要因と疾病の関連性の指標及び研究デザインが、それぞれ適切に選択されて、研究が実施されなければならない。
また、実施された疫学研究の成果の質に基づいて、暴露要因と疾病との因果関係を評価する際には、一定の判定基準が求められる。この基準になるものとしては、英国の疫学者Hillによる判定基準(1965)、ダイオキシンの健康影響に関する全米科学アカデミーの判定基準、化学物質等の発がん性評価に関する米国保健省と国際がん研究機関の判定基準が挙げられる。後二者には次のような共通点がある。
2) 因果関係が「ある」又は「ない」という二分法ではなく、「十分な知見がある」、「限定的な知見がある」、「不適切な知見がある」などの段階的な判定を採用していること。
3) 疫学研究及び動物実験の双方を利用するが、最終的な判定にあたっては、疫学研究の知見をより重視していること。例えば、三者いずれの判定においても、ヒト集団を対象とする疫学研究で「十分な知見」が存在しない限り、動物実験の知見のみに基づいて、因果関係の存在を肯定する最高位の判定(国際がん研究機関におけるグループ1など)を適用することは、原則的にないこと。
4) 疫学研究の評価にあたり、因果推論の典型とみなされているHill流の判定基準は用いず、偶然・バイアス・交絡という競合的解釈を排除することができている程度によって、研究の質を判断していること。すなわち、Hill流の判定基準を満たすデータがどれだけ蓄積されているかという帰納主義的な立場ではなく、因果性以外の競合的解釈(偶然・バイアス・交絡)という「誤り」が研究からどれだけ排除されているかという反証主義的な立場から、疫学研究の妥当性を判断していること。
5) 研究の進展に合わせて、判定の見直しと更新が行われていること。
暴露要因と健康障害との因果関係の有無を、議論の余地なく完全に証明することは、疫学研究と動物実験のいずれでも、原理的に不可能である。それを前提とした上で、不完全な実証研究のデータに基づいて、できるだけ誤りの少ない形で因果関係を評価し、具体的な対策に結びつけるために考案された方法論として、上記の共通点を理解することができる。したがって、我が国において、いわゆる内分泌かく乱化学物質の健康影響を評価し、その対策を検討する場合も、因果推論の方法に関する国際的な現状を十分に踏まえて議論することが重要である。
3.各論
3−1 乳がん
有機塩素系化合物などの化学物質にはエストロゲン様作用があるため、これらの物質の暴露と内分泌関連がんである乳がん発生との関連が注目されてきた。動物実験ではDESやエチニルエストラジオールがマウスに乳腺腫瘍を発生させることが報告されている。
そこで、いわゆる内分泌かく乱化学物質(ダイオキシンを除く)と乳がんに関する疫学研究の現状について文献的考察を行った。米国立医学図書館の医学文献データベース(PubMed)を利用して選択した文献は48件で、コホート研究6件、症例対照研究34件(うち、コホート内症例対照研究10件)、断面研究4件、エコロジカル研究3件であった。日本人を対象とした研究は1件もなかった。文献的考察の結果、有機塩素系化合物に関しては明確なリスク上昇についての一貫した証拠は見いだせなかった。DESについては乳がんのリスクを上昇させるという結果が複数の前向き研究で報告されており、経口暴露の場合にはリスクの上昇が起こると考えられた。DESと有機塩素系化合物以外の化学物質と乳がんとの関連に関する研究はきわめて乏しく、疫学研究の必要がある。
3−2 子宮体がん
いわゆる内分泌かく乱化学物質と女性のがんについてのこれまでの疫学研究は、前述の乳がんに関する報告が大半を占める。一方、エストロゲンに対する感受性は乳房よりも子宮内膜の方が高く、それら化学物質によるヒト発がんリスクを評価するためには、乳がんではなく子宮体がんに関する研究を行うことが重要である、という指摘もある(Adamiら(1995))。
そこで、いわゆる内分泌かく乱化学物質(ダイオキシンを除く)と子宮体がんに関する疫学研究の現状について文献調査を行った。PubMedを利用した結果、人口ベースの症例対照研究が2件報告されていた。その結果、いずれも、DDTやPCB等の血清レベルの上昇による明らかなリスク上昇は認められなかった。現状では、疫学的知見は極めて乏しく、それら化学物質と子宮体がんとの因果関係を適切に判断することは困難と思われ、子宮体がんに関するコホート内症例対照研究の必要性が示唆された。
3−3 卵巣がん
いわゆる内分泌かく乱化学物質(ダイオキシンを除く)と卵巣がんに関する疫学研究の文献的考察を行った。PubMedを利用して選択した文献は7件で、コホート研究3件、症例対照研究2件、エコロジカル研究2件であった。日本人を対象とした研究は1件もなかった。文献的に検討した結果、DESについては卵巣がんのリスクとなる可能性は低いと考えられた。DES以外の内分泌かく乱化学物質と卵巣がんとの関連に関する研究は極めて乏しく、疫学研究の必要がある。
3−4 前立腺がん
有機塩素系化合物などのいわゆる内分泌かく乱化学物質にはエストロゲン受容体、アンドロゲン受容体に親和性が認められるため、これら物質の暴露と内分泌関連がんとの関連が注目されてきた。動物実験では、ラットでテストステロンによる前立腺がんの発生が報告されている。
そこで、いわゆる内分泌かく乱化学物質(ダイオキシンを除く)と前立腺がんに関する疫学研究の現状について文献的考察を行った。PubMedを利用して選択した文献は13件で、コホート研究7件、症例対照研究3件、エコロジカル研究3件であった。日本人を対象とした研究は1件もなかった。文献的考察の結果、農薬暴露による前立腺がんリスクの増加が示唆されたが、有機塩素系農薬など特定の物質に関しての評価は不可能であった。有機塩素系化合物以外のそれら化学物質と前立腺がんとの関連に関する研究も極めて乏しく、疫学研究の必要がある。
3−5 精巣がん
いわゆる内分泌かく乱化学物質(ダイオキシンを除く)と精巣がんに関する疫学研究について文献的考察を行った。PubMedを利用して選択した文献は16件で、コホート研究7件、症例対照研究7件、エコロジカル研究2件であった。日本人を対象とした研究は1件もなかった。文献的考察の結果、有機塩素系化合物に関する研究は極めて少なかった。DESについては精巣がんリスクが統計的に有意に上昇するという一致した結果はみられなかった。その他の化学物質についての研究はなかった。有機塩素系化合物などの化学物質と精巣がんの関連に関する研究は極めて乏しく、疫学研究の必要がある。
3−6 甲状腺がん
有機塩素系化合物などの化学物質には、ホルモン受容体とのアゴニスト作用又はアンタゴニスト作用があるため、これらの物質の暴露と内分泌関連がんとの関連が注目されてきた。ダイオキシンやヘキサクロロベンゼンのように、動物実験において甲状腺に腫瘍が発生することが報告されている物質もある。
そこで、いわゆる内分泌かく乱化学物質(ダイオキシンを除く)と甲状腺がんに関する疫学研究の現状について文献的考察を行った。PubMedを利用して選択した文献は6件で、コホート研究3件、症例対照研究0件、エコロジカル研究3件であった。日本人を対象とした研究は1件もなかった。文献的考察の結果、有機塩素系化合物に関する研究はほとんどなく、クロロフェノキシ除草剤でリスクの上昇がみられた研究1件のみであった。DESについては複数の前向き研究の結果で有意なリスクの上昇がみられていなかった。その他の化学物質についての疫学研究はなかった。有機塩素系化合物などの化学物質と甲状腺がんの関連に関する研究は極めて乏しく、疫学研究の必要がある。
3−7 甲状腺機能への影響
ダイオキシンに暴露された人に甲状腺機能の異常が起こることを示唆する報告があり、PCBなどダイオキシン以外の化学物質暴露と甲状腺機能との関連が注目されてきた。
そこで、いわゆる内分泌かく乱化学物質(ダイオキシンを除く)と甲状腺機能への影響に関する疫学研究の現状について文献的考察を行った。PubMedを利用して選択した文献は4件で、コホート研究1件、症例対照研究1件、断面研究12件であった。日本人を対象とした研究はPCBについての2件であった。文献的考察の結果、PCBについては甲状腺機能への影響が複数の高濃度暴露集団での研究で報告されており、一般人口での疫学研究が必要である。その他の化学物質と甲状腺機能の関連に関する研究は極めて乏しく、疫学研究の必要がある。
3−8 尿道下裂
尿道下裂は、精巣がん、停留精巣、精子数減少、男女比の低下などとの共通の背景としていわゆる内分泌かく乱化学物質が考えられ、最近ではこれによる影響で説明しようという試みが多い。
そこで、いわゆる内分泌かく乱化学物質(ダイオキシンを除く)と尿道下裂に関する疫学研究の現状について文献的考察を行った。PubMedを利用して選択した文献は5件で、コホート研究1件、症例対照研究4件であった。日本人を対象とした研究は一件もなかった。文献的考察の結果、有機塩素系化合物などの化学物質についての報告はなかった。農業従事、ホルモン製剤、廃棄物処分場周辺居住などをあげて、いわゆる内分泌かく乱化学物質による暴露を間接的に想定した研究からは、リスクの上昇を示唆するものもあるが、種々の交絡も無視できないので、それら化学物質による影響と判断することは難しい。内分泌かく乱化学物質を特定できる疫学研究はきわめて乏しく、今後、よくデザインされた疫学研究を実施する必要がある。
3−9 停留精巣
男児の泌尿器先天異常の主たるものである停留精巣のリスク要因として、これまでの研究では胎児期の内外のエストロゲン暴露が指摘されている。
そこで、いわゆる内分泌かく乱化学物質(ダイオキシンを除く)と停留精巣に関する疫学研究の現状について、文献的考察を行った。PubMedを利用して選択した文献は10件で、介入研究1件、症例対照研究9件であった。日本人を対象にした研究は一件もなかった。これまで報告されている研究では、有機塩素系化合物などの化学物質についての報告が1件あり、ヘプタクロロエポキシド、ヘキサクロロベンゼンとの関連を認めた。その他、農薬、ホルモン製剤との関連が報告されている。有機塩素系化合物などの化学物質と停留精巣との関連に関する研究はきわめて乏しく、今後、疫学研究の必要がある。
3−10 小児神経発達への影響
PCB、ダイオキシン等の有機塩素系化合物は、脳神経分化発達に重要な作用を有する甲状腺ホルモンと類似する構造的特異性がある。甲状腺ホルモンの受容体あるいは結合蛋白との親和性が高く、その作用を阻害すると考えられている。脳血管関門の未成熟な胎児期から乳児期の脳神経の発達に影響を及ぼすことが示唆されている。一方、視床下部−下垂体系の神経内分泌系は様々なホルモン受容体が存在する。化学物質が胎児・新生児期の視床下部・下垂体・甲状腺へ直接又は間接的に働き脳の機能や知能、学習などに関与する神経発達の異常をもたらす可能性も示唆されている。
そこで、いわゆる内分泌かく乱化学物質(ダイオキシンを除く)と小児神経発達に関する疫学的研究について文献的考察を行った。PubMedを利用して選択した文献は29件で、6つの地域のコホートで行われている研究が、6地域で合計25件、その他が4件であった。日本人を対象とした研究は油症に関する1件であった。文献的考察の結果、PCBが小児の神経発達に影響を与えている可能性が示唆されたが、PCB暴露や神経系発達に対する評価の方法や時期が多様であり、個々の関連に対する再現性は十分とは言えない。有機塩素系化合物としてはDDEについて報告があったが因果関係を適切に評価することは困難であった。その他の化学物質についての報告はなかった。アジアにおける研究はきわめて乏しく、今後、日本においてよくデザインされた疫学研究を実施する必要がある。
3−11 精子数
いわゆる内分泌かく乱化学物質による男性生殖器系への影響の一つとして、近年における人の精子数減少など、精液の質的低下の傾向が危惧されている。それら化学物質の精子への影響は野生動物での事例や動物実験では確認されているが、人での影響についてはまだ確実な証拠が示されていない。
そこで、いわゆる内分泌かく乱化学物質(ダイオキシンを除く)の精子数への影響等を扱った疫学研究について文献的考察を行った。PubMedを利用して選択した文献は、断面研究が6件、コホート研究が1件、コホート内症例対照研究が1件であった。精子に関する研究のうち、いわゆる内分泌かく乱化学物質との関連を扱った文献は極めて少なく、その少数例は農薬等の化学物質の生産・加工・使用に携わる人集団における職業性暴露及び胎児期のDES暴露による成人後の影響等を非暴露群と比較したものであった。化学物質としては有機リン系農薬、除草剤等で4件あり、うち3件が精子への何らかの影響を示していた。有機溶剤関連の研究が2件含まれていたが、2件とも影響を認めないという報告であった。大気汚染との関連を異なる2地域で調査した研究では、精子数の変化はないが、長期にわたる汚染地域での居住が精子の質を劣化させるという報告であった。DESの胎内暴露例の成人後の生殖機能を調査した1例では、DESは生殖異常に対するリスクを増大させないとしている。しかしながら、単なる精巣毒性と内分泌かく乱作用との違いをこれらの文献から区別することは困難であり、いわゆる内分泌かく乱化学物質の影響評価のための方法論の整備と目的の明確な研究デザインによる疫学調査の必要性が示唆される。
3−12 子宮内膜症
PCB等の有機塩素系化合物の一部には、エストロゲン様作用があると考えられている。そのため、これらの物質が、女性の内分泌関連がん(乳がん・子宮体がん)や子宮内膜症の発生に関与する可能性が指摘されてきた。なかでも、ダイオキシンを混入させた食事をアカゲザルに与えたところ、用量依存的に子宮内膜症の発生率が上昇したことを、1993年にRierらが報告して以来、ダイオキシン等の化学物質とヒト子宮内膜症との関連が疑われてきた。
そこで、いわゆる内分泌かく乱化学物質(ダイオキシンを除く)と、子宮内膜症に関する疫学研究について、文献調査を行った。胎児期のDES暴露に関する断面研究が2件報告されており、暴露群は非暴露群よりも子宮内膜症の有病率が高い傾向にあった。DESの胎内暴露は不妊や子宮頸管狭窄を起こすことが知られており、このため二次的に子宮内膜症の発生リスクが高まる可能性もある。DES以外の化合物に関して、病院ベースの小規模な症例対照研究が4件報告されていた。内膜症症例で、血清中PCBレベルの上昇を認めるものと認めないものがあり、結果は不一致だった。現状では、疫学的知見はきわめて乏しく、いわゆる内分泌かく乱化学物質と子宮内膜症との因果関係を適切に判断することは困難と思われた。より大規模な症例対照研究の必要性が示唆された。
4.各論の総括
4−1 発がん影響
| ・ | 複数のコホート内症例対照研究の成績から、有機塩素系化合物(PCBや主な有機塩素系農薬)による乳がんリスクの上昇はなさそうである。しかし、層別解析(閉経前/閉経後、遺伝子多型など)で関連が強く現れる可能性を示唆する報告があり、影響を受けやすいサブグループの存在が今後の検討課題となる。 |
| ・ | 複数のコホート研究の成績から、DESの経口投与によって20〜30%程度の乳がん発生リスクの上昇がありそうである。 |
| ・ | その他のいわゆる内分泌かく乱化学物質とその他の内分泌関連がんとの関係については、疫学研究の成績はほとんど存在せず、関連性について言及できない。 |
4−2 甲状腺機能への影響
| ・ | 複数の断面研究の成績から、PCBの高濃度暴露者において、甲状腺機能の低下をもたらす可能性が示唆されるが、さらに、より質の高い疫学研究が必要である。 |
4−3 器官形成への影響
| ・ | 尿道下裂、停留精巣との関連については、疫学研究の成績はほとんど存在せず、関連性について言及できない。 |
4−4 小児神経発達への影響
| ・ | 複数のコホート研究の成績から、PCBが小児の神経発達に影響を与えている可能性が示唆されたが、PCB暴露や神経系発達に対する評価の方法や時期が多様であり、個々の関連に対する再現性は十分とは言えない。今後、日本人を対象としたコホート研究が必要である。 |
4−5 生殖機能への影響
| ・ | 精子数低下、子宮内膜症との関連については、疫学研究の成績はほとんど存在せず、関連性について言及できない。 |
5.必要な研究の提言
いわゆる内分泌かく乱化学物質によるヒトへの健康影響を知る上で、疫学研究からの知見は極めて乏しいのが現状であったのに加え、日本人を対象とした研究はほとんど存在しなかった。しかし、欧米においては、PCBや残留有機塩素系農薬の健康影響に対する強い関心から、特に、乳がんを対象として、コホート研究内で保存されている血清を用いた症例対照研究や生体試料測定を含めた大規模な症例対照研究などが複数行われており、重要な科学的根拠を提供している。
いわゆる内分泌かく乱化学物質の暴露状況、健康影響が懸念されている疾病の罹患状況、あるいはエストロゲンなどの内因性ホルモンのレベル、経口避妊薬などの合成ホルモンの使用状況、大豆など植物由来エストロゲンの摂取量など、交絡要因が大きく異なり、さらに遺伝的素因も異なる可能性のある日本人において、いわゆる内分泌かく乱化学物質の暴露による健康影響が存在するか否かを検証することは、極めて重要と考えられる。現在、厚生科学研究費補助金(生活安全総合研究事業)における調査研究では、乳がん・尿道下裂・停留精巣・子宮内膜症などの症例対照研究や精子数に関する断面研究などが進行中であり、今後その成果が発表されるものと期待されるが、研究デザインや研究数を考えると、それらの結果のみでは、十分な証拠を得ることはできない。
このような状況に鑑み、本作業班からは、我々人間社会に現実に存在し得るレベルでのいわゆる内分泌かく乱化学物質による人への健康影響に関して、より質の高い科学的根拠を得るために、以下の様な疫学研究を推進することを提言する。
いわゆる内分泌かく乱化学物質の人への暴露状況について現状を把握するために、日本国民を代表し得る対象者を設定し、生体試料中のそれら化学物質濃度を測定する。また、その測定を定期的に実施し、それら化学物質の暴露状況を継続的に監視することが望まれる。例えば、国民栄養調査の調査項目を拡大し、いわゆる内分泌かく乱化学物質などの国民の健康を脅かす可能性のある化学物質の血中濃度などの測定を、調査項目に含めていくことが考えられる。
また同時に、いわゆる内分泌かく乱化学物質暴露の影響として懸念されている疾病のモニタリングも必要になる。国レベルの統計としては、人口動態死亡統計が最も信頼性の高いものであるが、いわゆる内分泌かく乱化学物質との関連で注目されている乳房、子宮、前立腺、精巣、甲状腺などの部位のがんについては、5年生存率が高く、死亡統計では不十分である。幸いにも、現在、有志地域によるがん登録が行われているために、罹患の現状と動向については考察が可能であるが、人口動態統計と同様、国レベルでの実態把握と継続監視が必要である。また、子宮内膜症や精子数、あるいは器官形成の異常などについても、国レベルでの監視システム確立が望まれる。
2) 症例対照研究やコホート研究などの、疫学を方法論の基盤とする、ヒトを対象とした研究の推進
ある疾病の発生にいわゆる内分泌かく乱化学物質の暴露が関係しているか否かを実証するためには、疾病を保有している者についてのみ暴露量を測定しても解決しない。また職業的にいわゆる内分泌かく乱化学物質に高度に暴露した人から、それら化学物質との関連が懸念されている疾病が発生したからといって、それが暴露に関係しているとは言えない。疫学研究の方法論を用いて、可能な限り偶然・バイアス・交絡による誤りを最小限にする努力をした上で、両者の関連を客観的かつ定量的に表現して初めて科学的根拠となりうる。 今回の検討では、疫学研究の科学論文を系統的にレビューすることにより、いわゆる内分泌かく乱化学物質といくつかの疾病との因果関係について結論を導くことを試みた。残留農薬の乳がん罹患に及ぼす影響については、欧米からは数多くの証拠が提示されているが、生活習慣や遺伝的素因などが異なる日本人に関するデータは皆無であるため、日本人に対する影響については未知である。また他の疾病や他のいわゆる内分泌かく乱化学物質については、研究数が限られていた。
今後、疫学研究の方法論に基づいた大規模かつ質の高い次のような研究の推進が望まれる。
| ・ | 各種生体試料を保存しているコホート研究における症例対照研究 |
| ・ | 妊婦や乳幼児を対象としたコホート研究及び先天異常に対する症例対照研究 |
| ・ | 男性生殖機能への影響に関する疫学研究 |
| ・ | 職域集団を対象とした疫学研究 など |
3) いわゆる内分泌かく乱化学物質の人への健康影響に関する研究の継続的な総括とその情報公開
いわゆる内分泌かく乱化学物質の人への健康影響に関する疫学研究は、国際的な関心を反映して急速に発展し、論文報告数も増加している。国際的な研究の進展に迅速に対応するために、今回の検討で試みた、刊行論文のレビューと更新を継続的に実施することが重要である。そして、このような最新の研究状況に関する総括の成果については、インターネット等を用いて国民に公表する必要がある。このような措置を通じて、十分な科学的根拠に基づく情報を国民と行政が共有するようになれば、内分泌かく乱化学物質問題の理解と対策はさらに促進されるはずである。
1.はじめに
本作業班では、内分泌かく乱化学物質の問題を例としたリスクコミュニケーションの実行基盤の整備に向けて、前提となる概念に対する理解を促進し、具体的な検討課題を提言としてまとめることを目的とする。その提言のなかには、具体的な行動とその行動主体が誰なのか、またさらに、そのために必要な組織や予算はどのようなものか、行動を如何に実行に移すか、行動の効果をいかに計量するか、が含まれる。
2.前提となる概念と理解について
考察の対象
一般にコミュニケーションは、「誰(情報作成者・発信者)が、誰(情報の受け手・利用者)に、どのような目的で、何(どのような情報)を、どのような手段(情報経路と伝達媒体)と表現で、いつ(あるいはどのくらいの頻度で)伝えるのか」によって規定される。この中でも、「誰が、誰に、何を」がもっとも基本的であるが、本作業においては、「調査研究の成果を国民の健康的な生活のために調整・活用する(行政科学)立場にいる者(行政)が、一般消費者に、内分泌かく乱化学物質のリスクについての予測を伝える」場合と、「一般消費者が、行政に、内分泌かく乱化学物質のリスクについて尋ねる」場合を考察の対象とする。ここでいう行政とは主として厚生労働省であり、厚生労働省から一般消費者への情報伝達に最も重点を置き、次にその逆方向の情報伝達を考慮する。なお、それ以外の情報伝達、例えば調査研究に携わる者(研究者)からの情報発信や異なる政府機関同士における情報伝達などは、必要な場合に考察の対象にする。
リスクの概念
ここで言うリスクとは、本来化学物質の安全性の研究や毒性学で使用される用語である。
一般に化学物質がヒトや野生生物に接触すれば、何らかの影響を及ぼす可能性がある。その中には、薬のように好ましい作用を及ぼすものもあれば、発がん物質のように悪い作用を及ぼすものもあり、無害あるいは何ら影響を及ぼさないものもある。より正確に言うならば、薬に関してもいわゆる副作用が伴うことがあり、良い作用、好ましい作用、好ましくない作用、悪い作用、警戒すべき影響などは、並存している可能性がある。いずれにしても、その内の好ましくない作用や悪い作用がどういうものであるかを見極める(判別する)ことが必要である。この判別の作業を有害性の同定(Hazard Identification)と言う。
有害性が同定された化学物質に接触する(暴露される)可能性があるヒトや野生生物は、実際に有害作用(被害)を受ける可能性がある。それは接触が濃厚であれば受へやすく、希薄であれば受にくいと考えられる。すなわち、有害作用が実際に起きるか否かは確率的な事象である。
有害作用を実際に受ける可能性をリスクという。したがってリスクは確率的な概念である。ただし、どれほど有害性の強い物質であっても、ヒトなどへの暴露が起こりえなければ、実際の被害は考えられない。したがって、このような場合のリスクはゼロであると言える。日本語では、リスクは高い、又は低いと表現される。また、ヒトが同じ有害な化学物質を体内に取り込んだとしても、被害は性、年齢、遺伝的要因、体調、食事などで異なる。すなわち、ヒトによってリスクは異なると言える。
コミュニケーションにおいて、何を伝えるかの「何」に当たるのがここではリスクである。
確率は数学でいう測度の一種であり、0から1の間の連続値で表される。したがって、リスクの概念(数学で言う確率事象)が正確に定義され、それが情報作成者・発信者と情報の受け手・利用者との間で共通に理解されていれば、伝えるのは推定された数値であり、誤解の生ずる余地はない。例えば、我が国の交通事故による死者は年間およそ1万人であるから、ある人が1年間で交通事故死する確率は、人口を約1億人とすれば、1万分の1である。これが最も簡単に算出した交通事故死のリスクである。交通事故にはけがもあるが、けがのリスクは死亡のそれより大きい。
しかし、化学物質の有害性にはより複雑な性格があり、けがと死亡のような単純な尺度で測ることはできない。化学物質の生体影響は、様々な指標(エンドポイント)で観察され、現実には有害性の同定は科学的に難しいことが多い。また化学物質の地球上の分布も一様ではなく、その暴露の推定も前提条件に大きく左右される。こうした一意的な同定が難しい事象は不確定であると言われるが、不確定さは様々な因子に随伴して現れる。すなわち不確定さも多様である。そのため、確率の概念を適用する前提となる科学的な表現、すなわち数学的な定式化は極めて困難なことが多い。したがって、こうした問題を一般消費者に理解してもらうことは極めて困難である。
リスクマネジメント
化学物質によるリスクがあれば、対策が必要になる。リスクの算定は科学の問題である。すなわち科学技術が進歩し、また十分費用が使えるならば、リスクの算定は原理的には可能である。一方、対策の問題になるとそこに価値観が絡んでくる。両者の違いは、医学における診断と治療の違いに例えられる。医学が進歩すれば診断は正しいものに収斂していく。しかし、どのような治療を行うべきか(受けるか)は、人によって意見は必ずしも一致しない。何らかの対策をとるか、あるいは何もしないかは、対策をとる立場ととられる立場にいる人間の双方の価値観に左右される。リスクに対する対策はリスクマネジメントと呼ばれる。リスクマネジメントは、主として対策をとる立場の責任者(責任者)の価値観に左右されるが、責任者の行動もその他の多くの意見(価値観)に左右される可能性がある。もし責任者が、一般消費者の価値観を理解するように努めた上で、自らの取る対策が一般消費者にとって最善と考えるなら、彼らは自分の行動の根底にある価値観を明らかにする必要がある。行動の根底にある価値観を明らかにすることは、いわゆる説明責任(accountability)に関係している。
内分泌かく乱化学物質の特色
ヒトの精子形成能の低下や野生生物に見られるメス化の現象が、環境中に存在する内分泌系の働きに影響を及ぼす化学物質の影響であるという仮説がC.コルボーンらによって立てられ、その検証が全世界的な関心事となった。これが内分泌かく乱化学物質問題である。
この問題が大きな論争を巻き起こした背景には、
| ・ | 提出された仮説が概念として専門家の意表を突くものであったこと |
| ・ | 事実ならば大変な問題であるが、その検証が容易ではない仮説であったこと |
| ・ | 実際に仮説検証作業が始まってからも、研究者の間で意見が分かれるほど相反する結果が報告されていること |
| ・ | 従来の科学的(毒性学的)手法では予測できない結果(逆U字現象など)が報告されていること |
リスクコミュニケーションとその必要性
前述のように、対策をとる立場の責任者が、自らの取る対策が一般消費者にとって最善と考えるなら、彼らは自分の行動の根底にある価値観を明らかにする必要があるが、一方で、確率的な概念であるリスクを一般消費者に理解してもらうことは極めて困難である。しかしこの点がある程度理解されなければ、その行動は、一般消費者が持つ不安の解消のために何ら具体的(社会的)貢献もすることができないであろう。したがって、専門家あるいは責任者の義務としてのリスクへの対応の最終段階として、リスクにかかわるコミュニケーション(リスクコミュニケーション)の必要性が生じる。言い換えれば、十分な、あるいは効果的なリスクコミュニケーション無しでは、それまでに積み上げられた膨大な量の専門的調査研究や検討結果が、学問としては記録に残るとしても、人間の生存あるいは健康保護には全く生かされないこととなる。そのため、リスクコミュニケーションの中では、「誰が」と「誰に」と「何を」という重要三項目に加えて、「どうやって」と「いつ」の二つの重要性も認識されなければならない。
以上を前提として、これから具体的に検討しなければならない課題は、次のとおりとする。
3.検討すべき課題と範囲
(1)考察の対象
考察の対象とするのは、行政と一般消費者との双方向のリスクコミュニケーションである。具体的には、情報作成者・発信者が厚生労働省であり、情報の受け手・利用者が一般国民・消費者である場合と、その逆方向の情報伝達を主たる対象とする。
なお、必要な場合、情報の受け手・利用者の立場に、
| ・ | 政府内部 |
| ・ | NGO/NPO |
| ・ | 企業 |
| ・ | その他の関係者(Stakeholders) |
| ・ | 特別な関係者(Specific Audience) |
| ・ | 海外の専門家及び市民 |
(2)リスクコミュニケーションの目的
何のために情報を伝達するかは、情報作成者・発信者が誰かで異なる。それが行政であれば、
| ・ | 政策への理解(Accountability) |
| ・ | 合意の形成 (Public Acceptance) |
| ・ | リスクの低減 |
| ・ | 問題解決の加速 |
| ・ | 緊急の警告 |
| ・ | 意見の表明 |
| ・ | 政策の提言 |
| ・ | 問題解決への参画 |
(3)情報の内容(コンテンツ)
どのような情報を発信するかは、根拠となるデータが得られるのか、またそれを誰が作成するかにもかかわるが、発信者と目的によって違ってくる。
情報の内容には、
| ・ | 問題全体にかかわる科学的知見と行動の説明(Conceptual Framework) |
| ・ | 行政の行動の結果伝達(調査研究などの報告) |
| ・ | 誤解解消のための説明 |
| ・ | 対象化合物の範囲(リスト作成有無) |
| ・ | 対象集団 (population) の範囲(小児や妊婦などの高感受性弱者等) |
| ・ | 危険性の同定 (Hazard Identification) |
| ・ | 暴露の推定・評価 |
| ・ | リスクの予測(危険の性質と程度) |
| ・ | リスクマネジメントのための行動 |
| ・ | リスクとコストベネフィット(費用効果) |
(4)メディア
メディアとは情報を伝達する手段のことであり、以下が含まれる。
| ・ | 厚生労働省の広報(ニュースレター、パンフレット、小冊子など) |
| ・ | インターネットホームページ(報告書、海外の信頼のおける文書の翻訳、データベースなど) |
| ・ | マスメディア(テレビ、ラジオ、新聞など) |
| ・ | 雑誌(解説記事) |
| ・ | 単行本(解説書) |
| ・ | 講演会、説明会、対話集会 |
| ・ | 電話、Fax、CD-ROM、 |
| ・ | その他 |
(5)ユーザーの視点:情報の利用法
発信された情報が、受け手にどのように利用されるかを予想、分析しておく必要がある。その際には、
| ・ | 概念的理解 |
| ・ | 科学的知見の理解 |
| ・ | 規制状況とその背景の理解 |
| ・ | 化合物より情報が追えること |
| ・ | 規制などの変化に応じて適時に説明があること |
(6)継続対応
リスクコミュニケーションは相互の理解を最重視するのであるから、情報を伝達すれば、その受け手の応答に的確に対応することが重要となる。具体的には、
| ・ | 問い合わせへの対応 |
| ・ | 情報の更新と発信の継続 |
| ・ | 消費者ニーズの把握 |
(7)リスクコミュニケーションの実行と組織
上記の(1)〜(6)の検討・実行のための基盤として求められるのは、厚生労働省としての「リスクコミュニケーションガイドライン」の策定と実施体制の整備である。
具体的には、次の順に進めることになろう。
| ・ | 上記の各事項に関する詳細な調査検討 |
| ・ | 検討会等の開催による指針の策定 |
| ・ | 情報提供の方法と組織と予算の手当て |
| ・ | 実行 |
| ・ | 評価:効果判定の基準と継続的な評価の実施 |
なお、内分泌かく乱化学物質問題は既に全世界的な関心事になっている訳であるから、実際には、これらの基盤整備と並行して、本項に掲げられた事項をたたき台として、できるところから即実行に移していくことになる。例えば、次のような事項は、即実行に移すことができよう。
| ・ | 情報発信の中核となるWeb-siteは、国立医薬品食品衛生研究所化学物質情報部が作成しているものを利用することとし、新たに情報源を追跡できる機能をつける。 |
| ・ | 対話集会ないし啓蒙のための講演会をできるだけ早い機会に開催する。 |
| ・ | どのような誤解があるのか、その原因は何か、それはどのようにしたら解消できるのかについて作業班が中心となって分析する。 |
| ・ | 情報源である関係者(Stakeholder)に係る目録を整備する。 |
| ・ | 本問題についての理解を促進するため、この「中間報告書追補」の解説書を作成する。 |
(8)リスクコミュニケーションからみた内分泌かく乱化学物質問題と行政科学(レギュラトリーサイエンス)の判断基準
リスクコミュニケーションからみた内分泌かく乱化学物質問題には、これまでにはない、以下のような問題点がある。
| ・ | 内分泌かく乱作用という新しい概念と新しい危険物質であるかもしれないという仮説 | ||||||||||
| ・ | 環境ホルモンという化合物群があるという誤解。例えば、「ダイオキシンは猛毒、ダイオキシンは環境ホルモン、ゆえに環境ホルモンは猛毒」というような解釈 | ||||||||||
| ・ | 科学的に決着のつきにくい知見 例えば、
| ||||||||||
| ・ | 対応上の難しさ
|
これらは、調査研究の成果を国民の健康的な生活のために調整・活用する行政科学的な立場にいる者(行政)にとって、従来のやり方では施策に移すことが極めて困難な問題である。従来、人の健康影響への有無を考慮して何らかの施策を実行に移す際には、蓄積した科学的な証拠に基づいて、人の健康影響に悪影響を及ぼす可能性があるかどうかを判断することを鉄則としている。ここでいう科学的な証拠とは、適切なプロトコールに沿って実施される実験や調査から得られる結果、すなわち、動物実験から人への影響を予測した結果や、人を対象とした複数の疫学研究からの成績である。しかし、内分泌かく乱作用はこれまでの毒性とは異なる新たな概念であり、現時点で入手できる実験成績は内分泌かく乱作用が生物学的には説明可能であることは示すが、実際ヒトに有害な影響を及ぼすかどうかを判断するには、外挿データが余りにも不足していて十分な予測ができない状態であることから、この「生物学的説明可能性(Plausibility)」という判断基準を如何に国民の健康的な生活のために調整・活用していくかが問われることになる。
行政科学の判断基準を明文化したものはないことから、これを整備して、従来の手法では予測できない内分泌かく乱作用のような、化学物質の安全性に関する問題に対して、限られた知見を国民の健康的な生活のために最大限調整・活用できるようにすることが重要と考えられる。その基本骨子としては、
| ・ | 行政科学 |
| ・ | 判断基準 |
| ・ | リスクコミュニケーション |
| ・ | 合意形成 |
| ・ | 高感受性弱者(小児、妊婦など)への対応 |
(9)その他の検討事項
その他の検討事項として、
| ・ | 研究班の報告書などを読みやすくする注文 |
| ・ | 海外の著名人を招いた対話集会の企画 |
| ・ | 外国語(英語など)での情報提供の必要性 |