|
厚生労働省発表 平成19年7月18日 |
| 担 当 |
厚生労働省労働基準局 勤労者生活部企画課 課長坂本 耕一 課長補佐宮本 悦子 係長前村 充 電話 03-5253-1111(内5353) 夜間 03-3502-1599 |
テレワーク試行・体験プロジェクト参加者募集
テレワークのメリットを体感してみませんか
|
総務省及び厚生労働省では、多くの企業や地方公共団体にテレワーク(在宅勤務、モバイルワーク等)を試行・体験してもらい、テレワークの効果・効用を体感いただくプロジェクトを実施します。本プロジェクトで用意するテレワークシステムを活用し、自社等でテレワークを試行・体験する希望者を募集しますので、別添募集要項をご参照の上、積極的にご応募ください。 |
テレワークは情報通信技術を活用した場所と時間にとらわれない柔軟な働き方を実現するものです。我が国の世界最高水準のブロードバンド環境の進展に伴い、いつでもどこでもテレワークが可能な環境が整ってきております。
人口減少・少子高齢化時代における労働力確保、国際競争激化による生産性向上等は企業等にとっても喫緊の課題となっているところですが、テレワークはこれらの解決に寄与するものであるとともに、その他社会全体にとっての様々な効果・効用を発揮するものと考えられています。
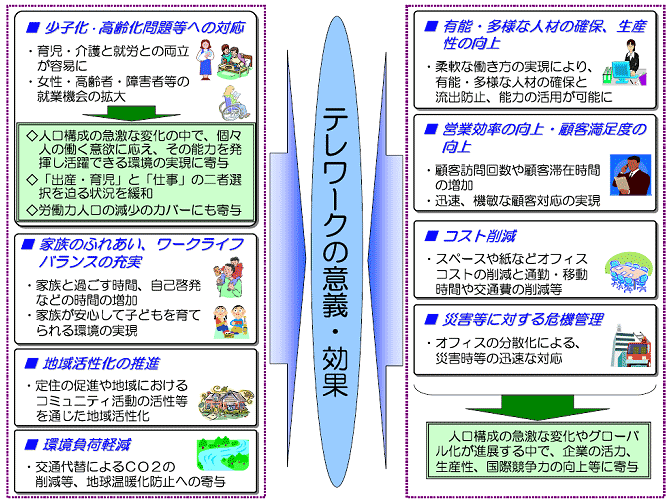
〈事例1〉中小企業において、人材が少ない中、経理の仕事を一身に担っていた女性が親の介護のため、遠隔地へ引っ越せざるを得なくなり、会社側がテレワークを導入 → 経験がある優秀な社員の流出防止に寄与。
〈事例2〉企業において、フリーアドレスとともにテレワーク制度を導入し、オフィスコストを削減するとともに、顧客先等でも仕事ができるようにした → 顧客訪問回数や顧客対応時間が増加し、営業効率の向上に寄与。
※フリーアドレス…個人専用のデスクを割り当てず、どの席にでも座って仕事ができるようなレイアウトのこと。
政府全体としても、「テレワーク人口倍増アクションプラン」(平成19年5月29日テレワーク推進に関する関係省庁連絡会議決定、IT戦略本部了承)を策定するなど、より一層のテレワーク推進に向けて取り組んでいるところです。
その一環として、総務省、厚生労働省において、安心・安全で簡易にテレワークが導入できるシステムを用意し、そのシステムを活用して自社等でテレワークを試行・体験するプロジェクトを実施します。
〜是非ご参加いただき、テレワークのメリットを体感してみませんか〜
(応募方法等)
(1) 募集期間は、平成19年7月23日(月)〜8月31日(金)までです。
(2) 本プロジェクトの概要及び応募方法の詳細については、別紙「テレワーク試行・体験プロジェクトの概要」(1〜4ページ(PDF:457KB)、 5〜8ページ(PDF:369KB)、 全体版(PDF:819KB))、別添「参加者募集要項」(1〜4ページ(PDF:457KB)、 5〜8ページ(PDF:369KB)、 全体版(PDF:819KB))をご覧ください。
なお、参加費用はかかりません。参加者には、テレワークに用いるシステム(認証USBメモリキー等)を無償提供します。また、参加者には、アンケートにご協力いただきます。
※ 今年度、国土交通省においてはテレワークセンターの実証実験を予定しており、当該テレワークセンター(神奈川、埼玉を予定)においてもご利用いただけるよう検討中です。
(参考1)※「テレワーク人口倍増アクションプラン」http://www.kantei.go.jp/jp/singi/it2/others/telework.html ※総務省におけるテレワーク推進施策http://www.soumu.go.jp/joho_tsusin/telework/index.htm ※厚生労働省におけるテレワーク推進施策テレワーク相談センター http://www.japan-telework.or.jp/center/index.html 「企業のためのテレワーク導入・運用ガイドブック」概要 |
(参考2:総務省の担当部局)総務省情報通信政策局情報流通振興課 情報流通高度化推進室 担当:野中専門職、内海主査 電話:03-5253-5751 FAX:03-5253-5752 |
(参考3:国土交通省のテレワークセンター実証実験に関する担当部局)国土交通省都市・地域整備局大都市圏整備課 担当:荒川課長補佐、西村係長、松井 電話:03-5253-8400 FAX:03-5253-1587 |
PDFファイルを見るためには、Adobe Readerというソフトが必要です。
Adobe Readerは無料で配布されています。(次のアイコンをクリックしてください。) Get Adobe Reader