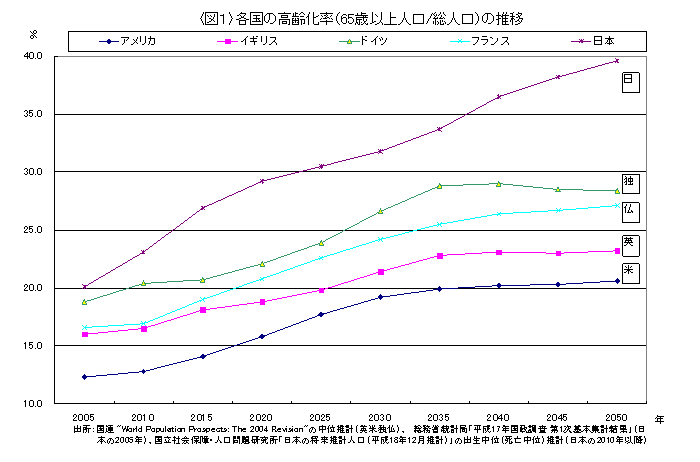|
|
| 担当 |
厚生労働省大臣官房国際課
海外情報室
電話 5253-1111 内線7315
夜間直通 3595-3083 |
|
「2005〜2006年 海外情勢報告」について
〜特集「諸外国における高齢者雇用対策」〜
本年の報告は、「諸外国における高齢者雇用対策」を特集し、EU、アメリカ、イギリス、ドイツ、フランス等主要先進諸国を中心に調査を行った。
また、定例報告として、主要諸国の2005年から2006年にかけての労働及び社会保障情勢全般の情報を取りまとめた。
諸外国における高齢者雇用対策
−「2005〜2006年海外情勢報告」のポイント−
| ○ | 我が国同様、人口の高齢化に直面し高齢者雇用対策を実施している主要先進諸国等(EU、アメリカ、イギリス、ドイツ及びフランス)の調査を行った。 |
| ○ | 各国とも公式引退年齢((満額)年金支給開始年齢)以前に引退する傾向が強い。また、実引退年齢はアメリカ及びイギリスに比べドイツ及びフランスが低い。 |
| ○ | 高齢者(55〜64歳)の就業率は、各国とも年齢計(15〜64歳)より低い。また、高齢者の就業率はアメリカ及びイギリスに比べドイツ及びフランスが低い。 |
| ○ | EUは2010年までに高齢者(55〜64歳)の就業率を50%とし、平均引退年齢を約64.9歳に引き上げる目標を打ち出し、「活力ある高齢化(アクティブエージング)」施策の実施を加盟国に求めている。 |
| ○ |
手厚い社会保障制度(年金、失業保険など)は、高齢者の就労意欲を削ぎ、引退を促進する恐れがある。そのため、各国とも年金の支給開始年齢の引上げ、失業保険の受給要件の厳格化などの改革を実施(又は予定)。 |
| ○ | 各国とも高齢者の就労促進のため、雇用における年齢差別禁止法令を整備。ただし、イギリス、ドイツ及びフランスでは65歳以上の定年制は例外として認めている。 |
| ○ | 段階的な引退支援策は、引退を遅らせるため就労時間を減らして働く選択肢を提供する制度であるが、調査対象国ではうまく機能している事例はみられない。 |
| ○ | 各国とも高齢者や事業主に対し、様々な積極的な就業促進策を実施している。 |
|
| 1 | 趣旨
高齢者の就業促進を進める上で、我が国同様、高齢化が進展する先進諸国における各国の取り組みは参考になると思われる。
そこで、主要先進諸国(EU、アメリカ、イギリス、ドイツ及びフランス)における、[1]高齢者の雇用失業情勢、[2]社会保障制度、[3]年齢に関する法規則、[4]段階的な引退の支援制度及び[5]高齢者に対する積極的な就業促進策(狭義の高齢者雇用対策)について調査を行った。
|
2 高齢者の雇用失業情勢
| (1 | )人口の動向
各国とも65歳以上の高齢者が増加する見込みである。また、高齢化率(65歳以上人口/総人口)はドイツ、フランス、イギリス、アメリカの順に高い。
|
| (2 | )労働市場の動向
| ア 高齢者の引退年齢 |
| |
実引退年齢1が公式引退年齢((満額)年金支給開始年齢2)を下回っている国が多い。実引退年齢はアメリカ、イギリスに比べドイツ及びフランスが低い。 |
| <表1>実引退年齢及び公式引退年齢 |
(歳) |
| |
実引退年齢(1999〜2004年) |
公式引退年齢(2004年) |
| 男性 |
女性 |
男性 |
女性 |
| アメリカ |
64.2 |
63.1 |
65.3 |
| イギリス |
63.0 |
61.6 |
65.0 |
60.0 |
| ドイツ |
61.3 |
60.6 |
65.0 |
| フランス |
59.3 |
59.5 |
60.0 |
| 日本 |
69.3 |
66.1 |
60.0 |
| OECD諸国平均 |
63.2 |
61.8 |
64.0 |
62.9 |
|
| 出所:OECD事務局(雇用労働社会問題局)資料 |
| イ 高齢者の就業率 |
| |
高齢者(55〜64歳)の就業率は、各国とも年齢計(15〜64歳)より低い。また、アメリカ及びイギリスに比べドイツ及びフランスが低い。 |
|
| <表2>各国の就業率(2005年) |
| |
アメリカ |
イギリス |
ドイツ |
フランス |
日本 |
| 15〜64歳 |
71.5% |
72.6% |
65.5% |
62.3% |
69.3% |
| 55〜64歳 |
60.8% |
56.8% |
45.5% |
40.7% |
63.9% |
|
| 出所:OECD”Labour Market Statistics-INDICATOR”,”Employment Outlook 2006” |
3 諸外国における高齢者雇用対策
| (1 |
)EUにおける取組み
| ア 目標 |
| |
2010年までにEU域内の高齢者(55〜64歳)の就業率を50%とし、平均引退年齢を64.9歳まで引き上げる。 |
| イ 活力ある高齢化(アクティブエージング) |
| |
EUは、高齢労働者の就労能力及び就労意欲を高める「活力ある高齢化(アクティブエージング)」施策の推進を加盟国に求めている。
|
「活力ある高齢化」の内容
[1]継続的な訓練機会の提供、[2]職場の安全衛生条件の改善、[3]弾力的な作業編成による多様な働き方の実現、[4]早期引退促進制度の廃止、[5]積極的労働市場施策の活用など
|
|
|
| (2 | )各国における取組み
| ア 高齢者の引退と社会保障制度 |
| |
| (ア)老齢年金制度 |
| |
年金受給可能となる年齢が低く給付水準が高い場合、早期引退を促進する恐れがある。各国は[1](満額)支給開始年齢の引き上げ(英・米・独)、[2]繰上げ(早期)支給制度の縮小(独)、[3]繰下げ支給時の給付増額率の引上げ(米・仏)などの改革を実施(又は予定)している。 |
年金制度の国際比較
| [1] |
年金の(満額)支給開始年齢は、米>独>英>仏の順に高い。 |
| [2] |
年金の繰上げ(早期)支給可能な年齢は仏>独・米の順で低い(英では繰上げ支給制度自体がない)。 |
| [3] |
年金の受給時期を繰下げ(遅らせ)支給時の給付増額率は、英>米>独>仏の順に高い。 |
| [4] |
年金の支給水準は、独>仏>米>英の順に高い。 |
|
|
| (イ)失業保険制度 |
| |
失業保険についても容易に受給でき給付内容が充実している場合、早期引退を促進する恐れがある。各国は[1]受給要件の厳格化(独)、[2]最長給付期間の短縮(独・仏)を実施(又は予定)している。 |
失業保険制度の国際比較
| [1] |
高齢者の失業保険受給が容易な国(高齢者に対する求職活動義務の免除措置実施国(独・仏) |
| [2] |
失業保険の給付水準は、独≒仏>米>英の順に高い。 |
| [3] |
失業保険の最長給付期間は、仏>独>米≧英の順に長い。 |
|
|
| (ウ)失業扶助制度 |
| |
一部の国では、主に失業保険受給終了後の求職者の生活を支える制度である失業扶助制度がある。同制度は、受給要件を満たせば年金支給開始まで受給できるため、高齢者の就労意欲を削ぐ恐れがある(米該当制度なし、英所得調査制求職者給付、独失業給付II、仏連帯失業手当)。 |
| (エ)その他の社会保障制度 |
| |
上記以外の社会保障制度も、本来の趣旨と異なり、実態上年金の支給開始まで所得保障に活用された場合、高齢者の就労意欲を削ぐ恐れがある(英就労不能給付、独障害年金、仏年金相当給付)。 |
|
| イ 年齢に関する法制度 |
| |
| (ア)年齢差別禁止法制 |
| |
各国とも雇用における高齢者に対する年齢差別を法令により禁止し、高齢者の就労促進をはかっている(米雇用における年齢差別禁止法、英2006年雇用均等(年齢)規則、独一般雇用機会均等法、仏労働法典L.122-45条など)。 |
| (イ)定年制 |
| |
アメリカでは定年制を原則禁止している。一方、イギリス、ドイツ及びフランスでは65歳以上の定年制は認めている。 |
| (ウ)高齢者の解雇に対する特別な保護 |
| |
高齢者の解雇に対する特別な保護制度は、高齢労働者の雇用維持に効果がある反面、事業主が高齢失業者の採用を躊躇する可能性もある(米先任権制度、英高齢者に対する雇用保護制度の付与、独解雇制限法による高齢者の解雇保護、仏ドラランド拠出金(廃止予定)など)。 |
|
| ウ 段階的な引退の支援策 |
| |
段階的な引退支援策は、高齢者の就労能力や就労意欲にあわせ、就労時間を減らす選択肢を提供することにより引退を遅らせるための制度であるが、調査対象国では十分に機能していない(独高齢者パート就労促進制度、仏段階的引退制度)。 |
| エ 積極的な就業促進政策(狭義の高齢者雇用対策) |
| |
| (ア)供給側(求職者及び労働者)に対する施策 |
| |
高齢求職者に対し、職場の提供(米高齢者地域社会サービス雇用事業)、職業相談及び各種支援策の組み合わせ(英ニューディール50プラス)を実施している国がある。また、在職中の高齢労働者に対する職業訓練参加支援を実施している国もある(独高齢者向けの職業継続訓練の促進、仏「被用者の職業人生にわたる訓練機会」に関する全国業種横断的協約)。 |
| (イ)需要側(事業主)に対する施策 |
| |
アメリカ以外の国は、年齢差別是正のためのキャンペーン(英エイジ・ポジティブ)や高齢失業者雇入れ時の賃金助成措置(独統合助成金、仏雇用主導契約など)などにより高齢者の労働需要を喚起する施策を展開している。 |
|
|
| 1 | 40歳以上の者が労働力を離れた(継続就労の意思なく退職した)年齢の平均値 |
| 2 | 公的老齢年金を減額されずに満額受給できる年齢。 |