(別紙)
次世代育成支援対策推進法に基づく企業等の認定表示の愛称募集要領
| 1. | 趣旨・目的 |
この中で、企業は、次世代育成支援対策のための一般事業主行動計画(以下「行動計画」という。)を策定し、その旨を都道府県労働局に届け出た上で、その行動計画に基づく取組を進めていくこととなっています。
また、事業主は、雇用環境の整備について適切な行動計画を策定したこと、その行動計画に定めた目標を達成したことなどの一定の要件を満たす場合は、申請を行うことにより厚生労働大臣の認定を受けることができ、認定を受けた事業主は、その旨を示す表示(以下「認定マーク」という。)を広告、商品などにつけることができるようになり、認定を受けた企業であることを対外的に示すことができます。
認定マークについては、平成16年7月に公募を行い、別添のとおり決定しているところですが、平成19年4月から、企業の認定申請が始まることに伴い、認定マークをより多くの方々に知っていただくためにも、わかりやすく、親しみやすい愛称を募集します。
| 2. | 応募資格 |
| 3. | 応募方法 |
応募に当たりましては、作品のほか、作品に関するコメント、郵便番号、住所、氏名(ふりがな)、年齢、職業、性別、電話番号を必ず記入してください。
1人何点でも応募できますが、はがき1枚又は応募用紙(任意様式)1枚につき、1作品を記入してください。(複数応募する場合には、必要な枚数をお送りください。)
| 4. | 応募締切 |
| 5. | 応募先 |
| 郵送 | : | 郵便番号 100−8916 東京都千代田区霞が関1−2−2 厚生労働省雇用均等・児童家庭局 職業家庭両立課育児・介護休業推進室 |
| ファクシミリ | : | 03−3502−6763 |
| 電子メール | : | jisedainintei@mhlw.go.jp |
| 6. | 作品の取扱い |
| (1) | 応募作品の著作権・使用権等一切の権利は厚生労働省に帰属するものとします。 |
| (2) | 応募作品は、未発表かつ自作の作品に限ります。 |
| (3) | 応募作品は返却いたしません。 |
| 7. | 発表等 |
| 8. | 問い合わせ先 厚生労働省雇用均等・児童家庭局職業家庭両立課 育児・介護休業推進室 育児・介護休業係 03−5253−1111(内線7863) |
(別添)
次世代育成支援対策推進法第14条第1項の
厚生労働大臣の定める表示(認定マーク)
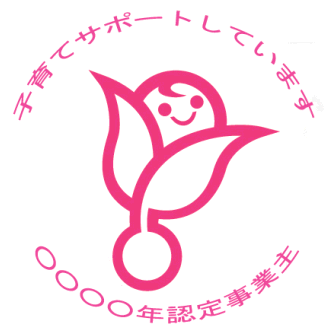
厚生労働大臣の定める表示(認定マーク)
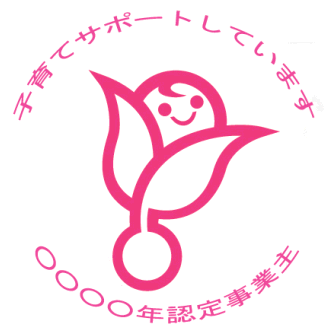
(解説)
働きながら子育てできるようにするため、企業等による仕事と子育ての両立支援に対する取組の推進が期待されています。
この表示(マーク)では、このような企業等による取組に支えられ、子どもが優しく包み育てられているイメージを表現しました。
カラーはピンクとし、明るさ、優しさ、暖かさを表現しています。
次世代育成支援対策の推進により、子どもが健やかに生み育てられる明るく、優しく、そして暖かい未来を目指します。
(参考)
次世代育成支援対策推進法に基づく「認定を受けた旨の表示」について
| 1 | 認定を受けた旨の表示とは |
次世代育成支援対策推進法(以下「次世代法」という。)第12条に基づき、常時雇用する労働者が300人を超える一般事業主は一般事業主行動計画を策定し、その旨を届け出ることが平成17年4月1日から義務づけられています(労働者が300人以下の一般事業主は努力義務)。
この計画に基づき次世代育成支援対策を推進した一般事業主は、一定の要件を満たす場合は次世代法第13条に基づき厚生労働大臣(具体的には権限委任された都道府県労働局長)から「認定」を受けることができます。
そして、この「認定」を受けた一般事業主であることを明らかにするものが、次世代法第14条に基づく「認定を受けた旨の表示(以下「認定表示」という。)」です。
| 2 | 認定表示のイメージ |
認定を受けた一般事業主は、認定表示を、商品又はサービス、広告、求人広告等様々なものに付することができます(参考1)。
この認定表示により、当該一般事業主が、次世代法に基づく適切な行動計画を策定し、その行動計画に定めた目標を達成する等の認定基準(参考2)を満たした結果認定を受け、次世代育成支援対策へ取り組んでいるということが対外的に明らかになるものです。
(参考1)認定表示を付することができるもの(次世代育成支援対策推進法施行規則(平成15年厚生労働省令第122号)第5条)
| (1) | 商品又は役務 |
| (2) | 商品、役務又は一般事業主の広告 |
| (3) | 商品又は役務の取引に用いる書類又は通信 |
| (4) | 一般事業主の営業所、事務所その他事業場 |
| (5) | インターネットを利用した方法により公衆の閲覧に供する情報 |
| (6) | 労働者の募集の用に供する広告又は文書 |
(参考2)次世代法第13条に基づく一般事業主の認定基準(次世代育成支援対策推進法施行規則第4条)
| (1) | 雇用環境の整備に関し、次世代法第7条第1項の行動計画策定指針に照らし適切な一般事業主行動計画(次世代法第12条第1項に規定する一般事業主行動計画をいう。以下同じ。)を策定したこと。 |
| (2) | 策定した一般事業主行動計画の計画期間(以下この条において「計画期間」という。)が、2年以上5年以下であること。 |
| (3) | 策定した一般事業主行動計画を実施し、当該一般事業主行動計画に定めた目標を達成したこと。 |
| (4) | 計画期間において、その雇用する男性労働者のうち育児休業等(育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号。以下「育児・介護休業法」という。)第2条第1号に規定する育児休業及び第23条第1項又は第24条第1項の規定に基づく措置として育児休業の制度に準ずる措置が講じられた場合の当該措置によりする休業をいう。以下同じ。)をしたものの数が1人以上であること。ただし、当該計画期間において、その雇用する男性労働者のうち育児休業等をしたものがいない中小事業主にあっては、当該計画期間の開始前3年以内の期間において、その雇用する男性労働者のうち育児休業等をしたものがいれば足りること。 |
| (5) | その雇用する女性労働者であって計画期間において出産したものの数に対するその雇用する女性労働者であって当該計画期間において育児休業等をしたものの数の割合(以下この号において「育児休業等をしたものの割合」という。)が10分の7以上であること。ただし、計画期間において育児休業等をしたものの割合が10分の7未満である中小事業主にあっては、当該計画期間の開始前3年以内の日であって当該中小事業主が定める日から当該計画期間の末日までの期間を計画期間とみなした場合における育児休業等をしたものの割合が10分の7以上であれば足りること。 |
| (6) | その雇用する3歳から小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者について、育児・介護休業法第24条第1項の規定により、労働者の申出に基づき適用される育児休業の制度又は勤務時間の短縮等の措置に準じて講ずるよう努めなければならないものとされている必要な措置を講じていること。 |
| (7) | 所定外労働の削減、労働基準法(昭和22年法律第49号)第39条の規定による年次有給休暇の取得の促進その他の働き方の見直しに資する多様な労働条件の整備のための措置を講じていること。 |
| (8) | 次世代法及び次世代法に基づく命令その他関係法令に違反する重大な事実がな いこと。 |
次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号)(抄)
(一般事業主行動計画の策定等)
| 第 | 12条 国及び地方公共団体以外の事業主(以下「一般事業主」という。)であって、常時雇用する労働者の数が300人を超えるものは、行動計画策定指針に即して、一般事業主行動計画(一般事業主が実施する次世代育成支援対策に関する計画をいう。以下同じ。)を策定し、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣にその旨を届け出なければならない。これを変更したときも同様とする。 | ||||||
| 2 | 一般事業主行動計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
| ||||||
| 3 | 一般事業主であって、常時雇用する労働者の数が300人以下のもの(第16条第1項及び第2項において「中小事業主」という。)は、行動計画策定指針に即して、一般事業主行動計画を策定し、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣にその旨を届け出るよう努めなければならない。これを変更したときも同様とする。 | ||||||
| 4 | 第1項に規定する一般事業主が同項の規定による届出をしない場合には、厚生労働大臣は、当該一般事業主に対し、相当の期間を定めて当該届出をすべきことを勧告することができる。 |
(基準に適合する一般事業主の認定)
| 第 | 13条 厚生労働大臣は、前条第1項又は第3項の規定による届出をした一般事業主からの申請に基づき、厚生労働省令で定めるところにより、当該事業主について、雇用環境の整備に関し、行動計画策定指針に照らし適切な一般事業主行動計画を策定したこと、当該一般事業主行動計画を実施し、当該一般事業主行動計画に定めた目標を達成したことその他の厚生労働省令で定める基準に適合するものである旨の認定を行うことができる。 |
(表示等)
| 第 | 14条 前条の規定による認定を受けた一般事業主(以下「認定一般事業主」という。)は、商品又は役務、その広告又は取引に用いる書類若しくは通信その他の厚生労働省令で定めるもの(次項において「広告等」という。)に厚生労働大臣の定める表示を付することができる。 |
| 2 | 何人も、前項の規定による場合を除くほか、広告等に同項の表示又はこれと紛らわしい表示を付してはならない。 |