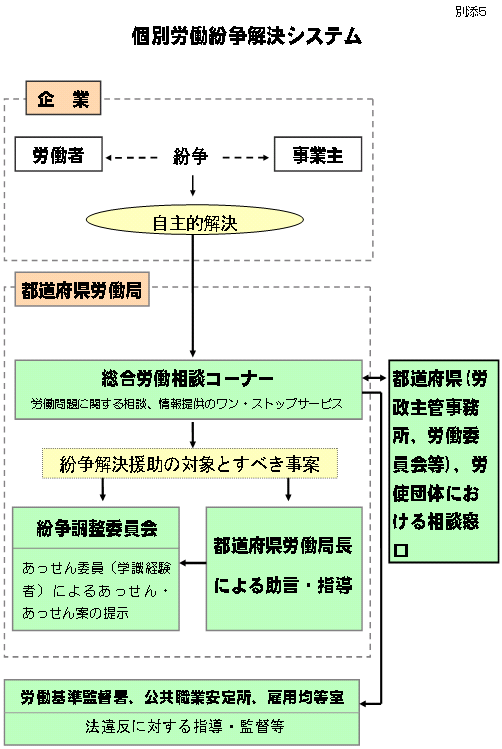| 厚生労働省発表 平成18年5月25日 |
|
《平成17年度個別労働紛争解決制度施行状況》
個別労働紛争解決制度の利用が引き続き拡大| ・ | 民事上の個別労働紛争相談件数 | 約17万6千件 |
| ・ | あっせん申請受理件数 | 約7千件 |
《概要》
|
「個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律」施行状況〜平成17年度〜
個別労働紛争解決制度は、平成13年10月の施行から今年で5年目を迎えるが、企業組織の再編や人事労務管理の個別化等の雇用形態の変化等を反映し、全国約300ヵ所の総合労働相談コーナーに寄せられた民事上の個別労働紛争に係る相談件数は17万件を超え、制度発足以降依然として増加を続けている(総合労働相談件数は90万件超)。 また、助言・指導申出受付件数は6千件を超え、あっせん申請受理件数は約7千件といずれも昨年度実績を上回っており、引き続き、制度の利用が進んでいることが窺える。
|
||||||||||||||||||||||
『個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律(別添4、5)』に基づく、個別労働紛争解決制度の平成17年度の施行状況は以下のとおりである(概要は別添2、都道府県労働局別一覧は別添3)。
| 1. | 相談受付状況 |
| 各都道府県労働局、主要労働基準監督署内、駅近隣の建物などにおいて、労働問題に関するあらゆる相談にワンストップで対応するための総合労働相談コーナー(約300ヵ所)を設置しているところであるが、平成17年度1年間に寄せられた相談は90万7,869件であった。 このうち、労働関係法上の違反を伴わない解雇、労働条件の引下げ等のいわゆる民事上の個別労働紛争に関するものが17万6,429件である。 年度ごとの推移をみると、確実に件数が増えている。(第1図) |
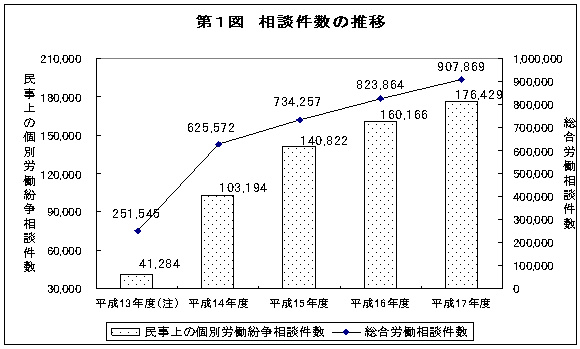
| (注) | 平成13年度の件数は、6ヶ月分(H13.10.1〜H14.3.31)である。 |
| また、民事上の個別労働紛争に係る相談内容の内訳は、解雇に関するものが最も多く26.1%、労働条件の引下げに関するものが14.0%、いじめ・嫌がらせに関するものが8.9%と続いている(第2図)。 |
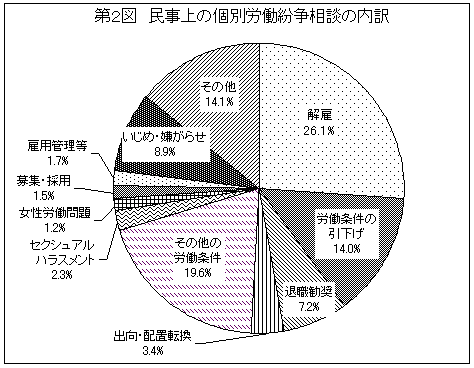
| 2. | 都道府県労働局長による助言・指導及び紛争調整委員会によるあっせんの受付状況 |
| 平成17年度の当該制度に係る助言・指導申出件数は6,369件で、平成16年度比20.5%の増加となっている。 あっせん申請受理件数は6,888件、同じく14.5%の増加となっている。(第3図) |
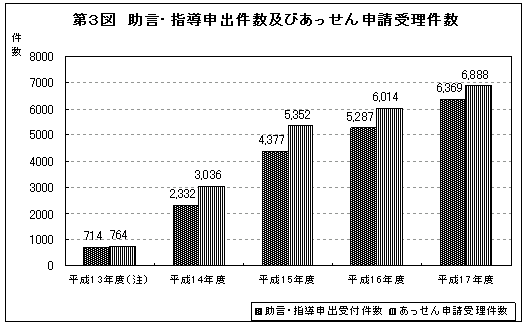
| (注) | 平成13年度の件数は、6ヶ月分(H13.10.1〜H14.3.31)である。 |
| 3. | 都道府県労働局長による助言・指導の主な内容 |
| 助言・指導の申出の主な内容は、解雇に関するものが30.9%と最も多く、次いで、労働条件の引下げに関するものが12.0%、いじめ・嫌がらせに関するものが7.8%と続いている(第4図)。 |
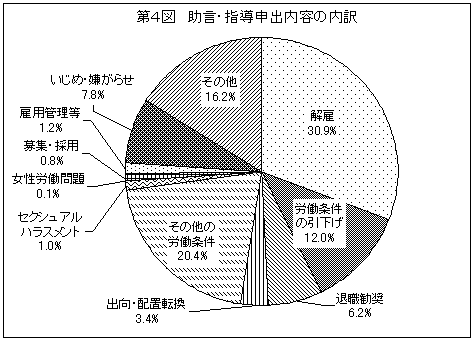
| 申出を受け付けた事案の都道府県労働局における処理状況をみると、平成17年度1年間に手続きを終了したものは6,345件である。このうち、助言・指導を実施したものは6,011件で94.3%、申出が取り下げられたものは206件で3.2%、処理を打ち切ったものは92件で1.4%となっている。 処理に要した期間は、1ヶ月以内が95.6%となっている。 申出人は、労働者が97.0%と大半を占めるが、事業主からの申出も194件と3.0%あった。 労働者の就労状況は、正社員が57.7%と最も多いが、パート・アルバイトが20.6%、派遣労働者・期間契約社員も15.0%を占めている。 事業所の規模は、10〜49人が32.5%と最も多く、次いで10人未満23.9%、100〜299人が10.4%となっている。 また、労働組合のない事業所の労働者が70.4%である。 なお、助言・指導の実施事例は、別添1のとおりである。 |
| 4. | 紛争調整委員会によるあっせんの主な内容 |
| あっせん申請の主な内容は、解雇に関するものが39.5%と最も多く、次いで、いじめ・嫌がらせに関するものが10.5%、労働条件の引下げに関するものが9.9%と続いている(第5図)。 |
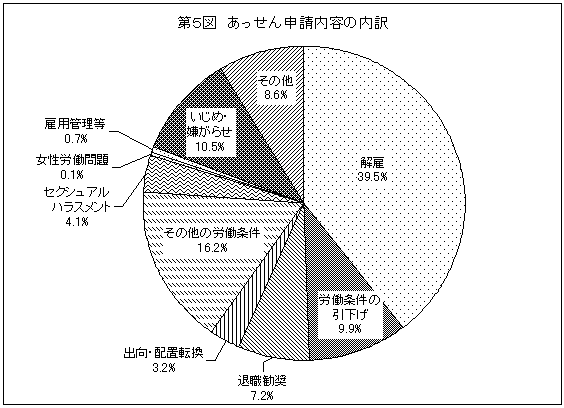
| 申請を受理した事案の都道府県労働局における処理状況をみると、平成17年度1年間に手続きを終了したものは6,856件である。このうち、合意が成立したものは2,961件で43.2%、申請者の都合により申請が取り下げられたものは450件で6.6%、紛争当時者の一方が手続きに参加しない等の理由により、あっせんを打ち切ったものは3,406件で49.7%となっている。 処理に要した期間は、1ヶ月以内が63.5%、1ヶ月を超え2ヶ月以内が27.9%となっている。 申請人は、労働者が6,775件で98.4%と大半を占めるが、事業主からの申請も106件で1.5%となっており、労使双方からの申請も7件で0.1%あった。 労働者の就労状況は、正社員が60.0%と最も多いが、パート・アルバイトが16.8%、派遣労働者・期間契約社員も15.9%を占めている。 事業所の規模は、10〜49人が32.4%と最も多く、次いで10人未満が21.7%、100〜299人が10.9%となっている。 また、労働組合のない事業所の労働者が74.4%である。 なお、あっせんの実施事例は、別添1のとおりである。 |
| 【紛争調整委員会とは】 弁護士、大学教授等の労働問題の専門家である学識経験者により組織された委員会であり、都道府県労働局ごとに設置されている。この紛争調整委員会の委員のうちから指名されるあっせん委員が、紛争解決に向けてあっせんを実施するものである。 |
別添1
【助言・指導の例】
| 事例1:懲戒解雇に係る助言・指導 | |
| 事案の概要 | 申出人は、社長から突然懲戒解雇を言い渡されたが、解雇理由は全く身に覚えがないことであり、それについての弁明の機会も与えてもらえないことから、解雇の撤回を求め、労働局長の助言・指導を求めたもの。 労働局長の助言・指導を踏まえ、申出人と会社側とで話し合った結果、解雇理由が誤解であったとして、解雇が撤回された。 |
| 助言・指導 の内容 |
申出人が、懲戒解雇事由について身に覚えがなく話を聞いてほしいと主張していることから、事実関係について、当事者間でよく話し合うこと。 |
| 事例2:配置転換に係る助言・指導 | |
| 事案の概要 | 申出人は、X店で働くパート労働者であるが、突然Y店への配置転換を指示され、これを断ったところ退職勧奨を受けたことから、配置転換命令の撤回を求め、労働局長の助言・指導を求めたもの。 労働局長の助言・指導を踏まえ、申出人と会社とで話し合った結果、これまでどおりX店で働くことができることとなった。 |
| 助言・指導 の内容 |
労働契約上勤務場所が特定されている場合には使用者がそれを一方的な命令により変更することはできないことから、当事者間でよく話し合うこと。 |
【あっせんの例】
| 事例1:採用内定取消に係るあっせん | |
| 事案の概要 | 申請人は、採用内定を受けた後就職に向けた準備を進めている段階で突然内定取り消しの連絡を受け、その理由についても納得できないことから、損害賠償を求め、あっせん申請を行ったもの。 あっせんの結果、○○万円の和解金を支払うことで合意が成立した。 |
| あっせんの ポイント |
事業主が内定の取消しについて非を認め、それを踏まえて和解金を支払うことで双方の合意が成立した。 |
| 事例2:いじめ・嫌がらせに係るあっせん | |
| 事案の概要 | 申請人は、担当業務について上司から必要以上に叱責され、人格を否定するような発言を受け続けた結果休養を余儀なくされたとして、職場環境の改善を求め、あっせん申請を行ったもの。 |
| あっせんの ポイント |
あっせん委員の指摘を踏まえ、会社側が業務指導について配慮を欠いた行為があったことを認めて謝罪するとともに、職場環境の改善に取り組むことで双方の合意が成立した。 |
別添2
個別労働紛争解決制度の運用状況(概要)
(平成17年4月1日〜平成18年3月31日)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
別添3
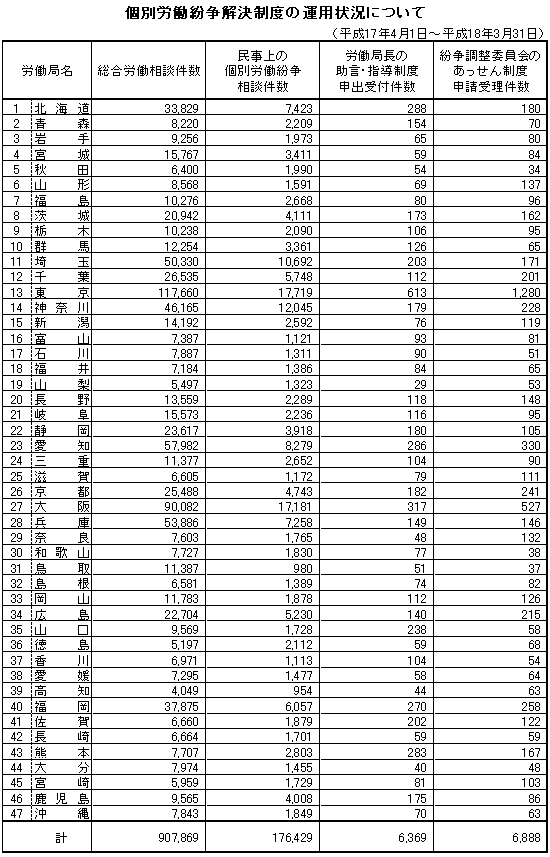
別添4
個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律の概要
| 1 | 趣旨 企業組織の再編や人事労務管理の個別化等に伴い、労働関係に関する事項についての個々の労働者と事業主との間の紛争(以下「個別労働関係紛争」という。)が増加していることにかんがみ、これらの紛争の実情に即した迅速かつ適正な解決を図るため、都道府県労働局長の助言・指導制度、紛争調整委員会のあっせん制度の創設等により総合的な個別労働紛争解決システムの整備を図る。 |
||||||||||||||||||
| 2 | 概要
|