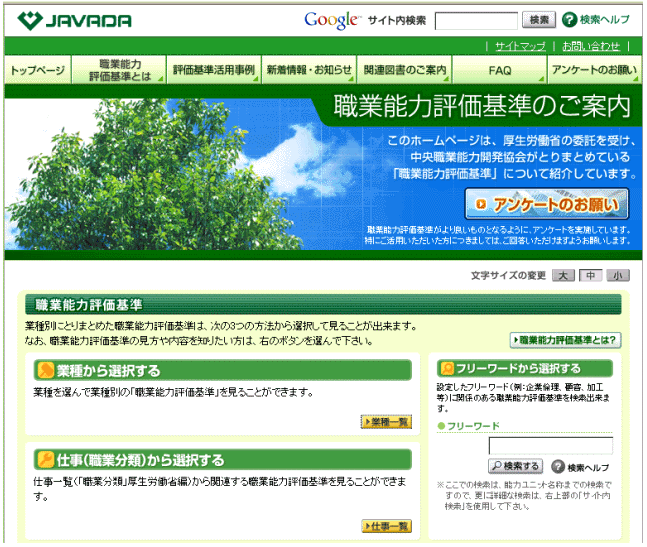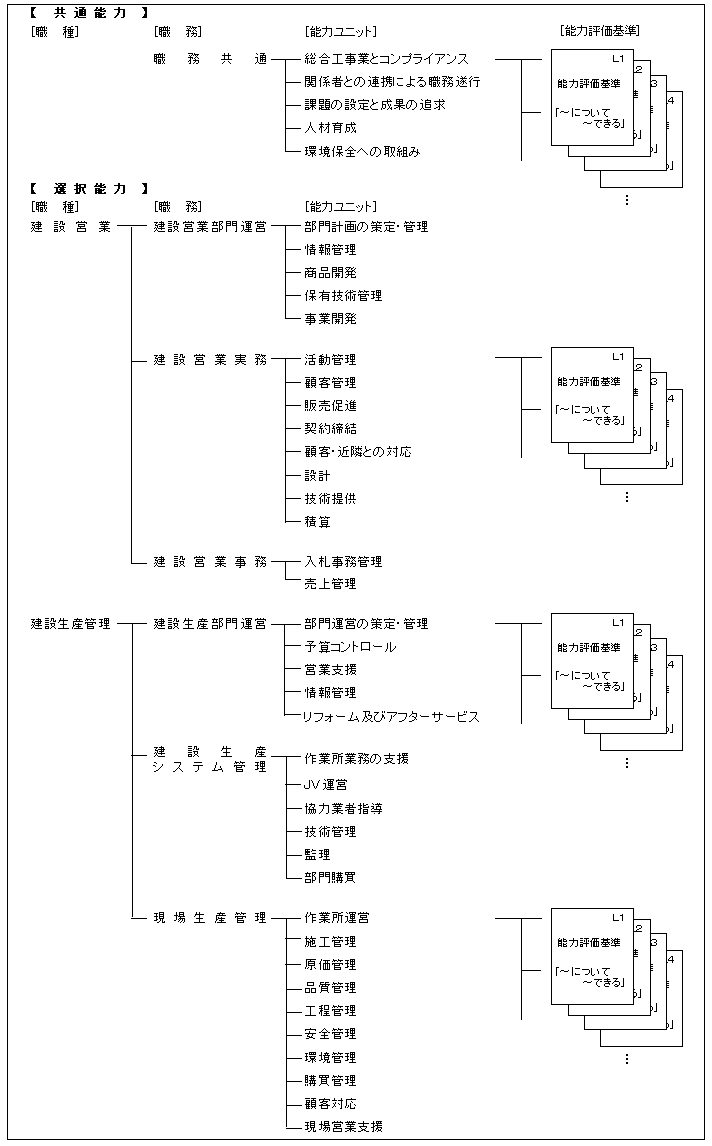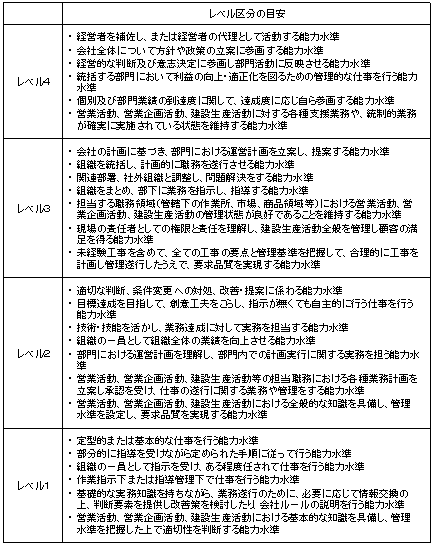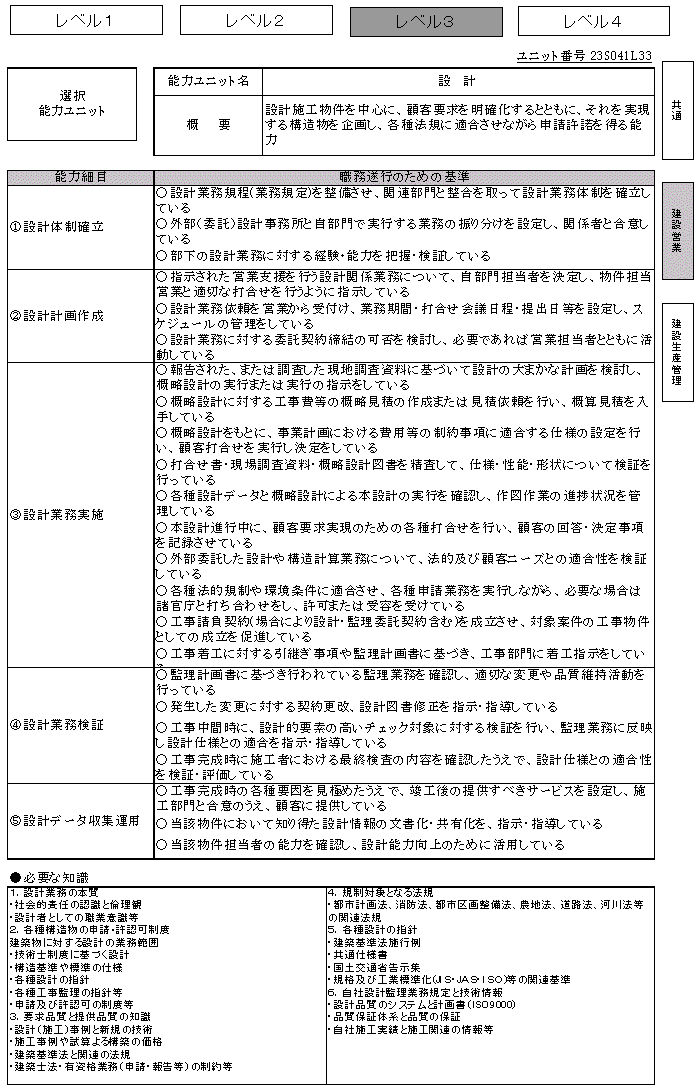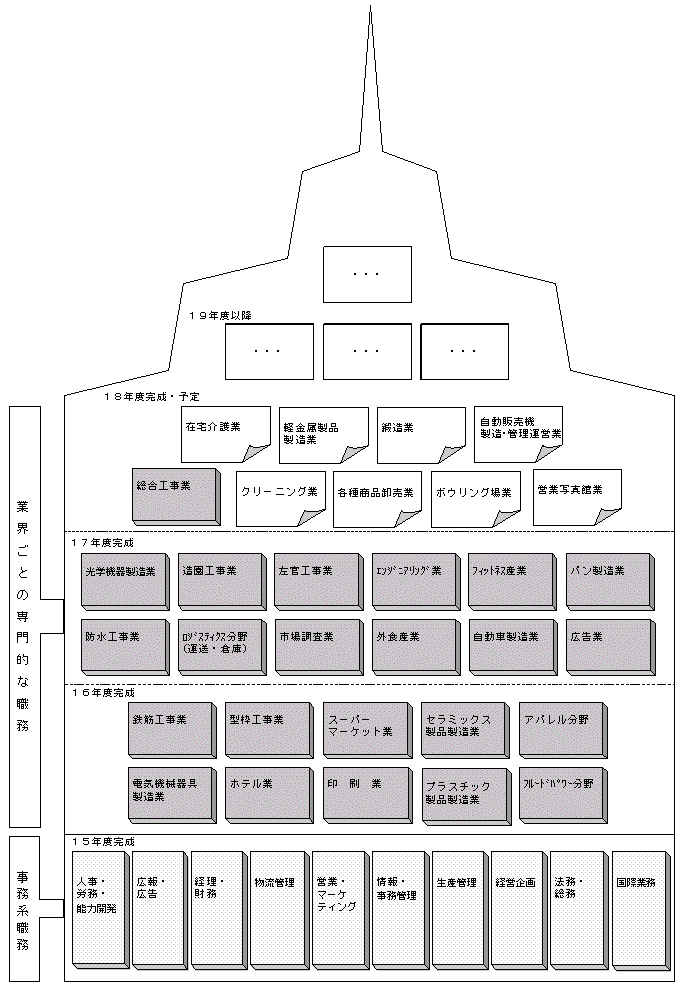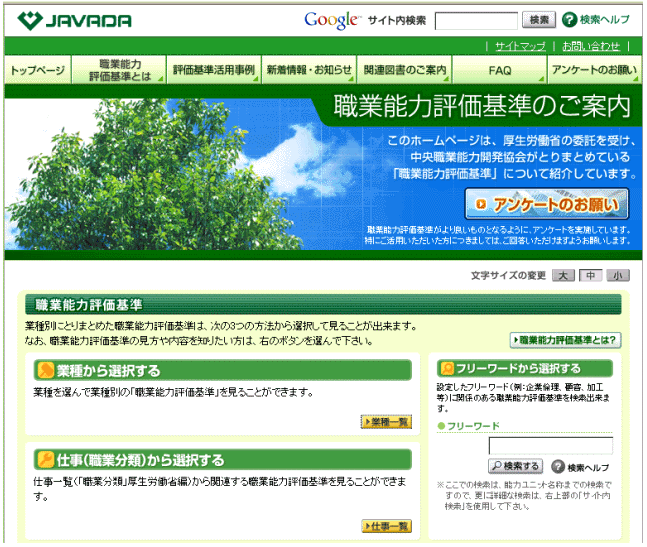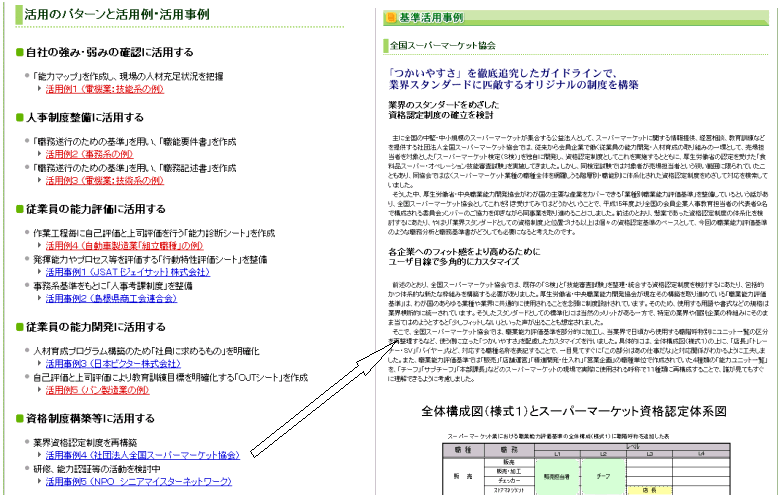|
|
職業能力開発局能力評価課
| | 課長 | 小林 洋司 |
| 課長補佐 | 桃井 竜介 |
| 電話 | 03(5253)1111(内線5969) |
| 夜間直通 | 03(3502)6958 |
中央職業能力開発協会
| | 能力評価部次長 | 内藤 眞紀子 |
| 評価制度開発課長 | 山浦 晃 |
| 電話 03(5800)3689(直通) |
|
|
「総合工事業」の能力評価基準が完成
ホームページを活用しやすくリニューアル
(ポイント)
【総合工事業の能力評価基準】
| ○ | 現在、厚生労働省では職業能力が適正に評価される社会基盤づくりを進めており、能力評価のいわば“ものさし”、“共通言語”となる能力評価基準の策定に取り組んでいる。これまで、経理・人事等の「事務系職種」に関する横断的な能力評価基準のほか、電気機械器具製造業、ホテル業、自動車製造業等22業種の能力評価基準が策定されたところである。
|
| ○ | 「総合工事業」の能力評価基準は、(社)全国建設業協会(会長・前田 靖治)との連携のもと、企業実務家や学識者からなる職業能力評価制度整備委員会において策定作業が進められ、今般報告書が取りまとめられた。
同報告書においては、業界の職業能力や人材育成に関する状況が分析され、その結果を踏まえて能力評価基準が定められた。
|
| ○ | 能力評価基準は職務遂行に必要な職業能力や知識に関し、担当者に必要とされる能力水準から組織・部門の責任者に必要とされる能力水準まで4つのレベルを設定している。また、単に知識があるということにとどまらず、職務を確実に遂行できるか否かの判断基準となるよう、典型的なビジネスシーンにおける行動例を記述している。このため、職業能力を評価する基準であると同時に、労働者にとってキャリア形成上の指針としての活用も期待される。 |
【ホームページのリニューアル】
| ○ | 職業能力評価制度整備委員会報告書及び能力評価基準は、中央職業能力開発協会のホームページから入手可能である。本日、検索機能の強化や活用事例の掲載など、より使いやすいホームページとなるようリニューアルしたところである。 |
|
【総合工事業の能力評価基準】
| 1 | 総合工事業については、(社)全国建設業協会(会長・前田 靖治)との連携のもと、職業能力評価制度整備委員会(座長・蟹澤 宏剛:芝浦工業大学 工学部建築工学科 助教授)を設置し、検討を行った。
|
| 2 | 同委員会は、営業に関する「建設営業職種」と建設現場に関する「建設生産管理職種」の2職種について能力評価基準の策定を行った(図1参照)。
| (1) | 建設営業職種
建設営業職種には顧客に対する営業活動と部門の管理が含まれる。
営業活動は、顧客の要望への対応、販売促進、自社技術の紹介と顧客ニーズの結びつけを行い、自社の技術と市場を結びつけ、工事の受注を行う仕事である。
部門の管理は、営業活動に対する統制や支援を行い、営業目的の達成を図る仕事である。
職務としては、「建設営業部門運営職務」、「建設営業実務職務」、「建設営業事務職務」の3つに区分している。 |
| (2) | 建設生産管理職種
建設生産管理職種には作業所(建設現場の組織)と部門の管理が含まれる。
作業所は、品質、原価、工程、安全、環境などを計画・管理し、近隣や協力業者との関係も含めた施工環境を良好に保ち、構築物を完成させる仕事である。
部門の管理は、作業所に対する統制や支援を行い、部門や作業所の目標達成を図る仕事である。
職務としては、「建設生産部門運営職務」「建設生産システム管理職務」「現場生産管理職務」の3つに区分している。 |
なお、幅広い企業で活用されるよう、いわゆるスーパーゼネコンではなく地方の地場建設業に多い完工高30億〜50億程度の建設会社を想定して策定した。
また、総合工事業が扱う工事のうち、基本的には建築工事を主体としつつ、土木工事も考慮した記載となっている。
|
| 3 | 総合工事業では、従来の生産現場を管理する能力に加え、関連企業の指導・育成、顧客要求を理解したうえでの適切な工法の提案・対応を行う能力や自社の総合工事業としてのノウハウと顧客のニーズを結びつける能力等の多様な能力が求められており、こうした現状も踏まえつつ能力評価基準が策定され、報告書が取りまとめられた。 |
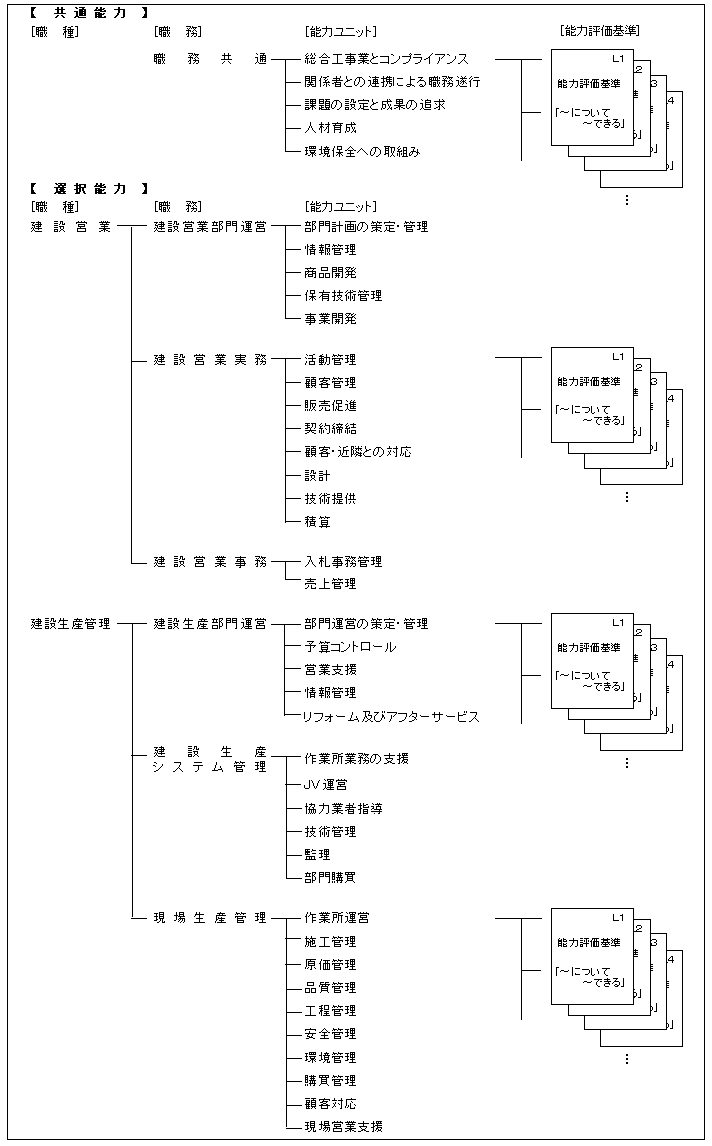
| | 能力評価基準の策定に当たっては、これが職業能力を評価する基準であると同時に、労働者にとってキャリア形成上の指針となるように、役職等とそれに必要とされる職業能力の関係の実態に照らし、担当者に必要とされる能力水準(レベル1)から組織・部門の責任者に必要とされる能力水準(レベル4)まで4つのレベルを設定している。
能力評価基準全体に共通するレベル区分の考え方に沿いながら、より具体的にイメージできるよう、企業において期待される役割に着目してレベル区分の目安を設定した(図2参照)。 |
| | 能力評価基準の具体的な記述に当たっては、単に知識があるということにとどまらず、当該職務を確実に遂行できるか否かの判断基準となるように典型的なビジネスシーンにおける行動例を記述している(図3参照)。 |
| | 能力評価基準が明らかになることによって、的確なキャリア形成を図ることができる環境が整備され、また、職業能力に関するミスマッチが縮小することが期待される。 |
| 1 | 求職者・労働者にとっては、職業選択やキャリア形成の目標を立てる際に、(1)自らの能力の客観的な把握、(2)企業が必要とする能力の把握が可能となり、職業能力の向上に向けた取組みにつなげることができる。 |
| 2 | 企業にとっては、人材に関する企業戦略を立てる際に、採用すべき人材の明確化、人材育成への効果的な投資、能力に基づいた人事評価・処遇等の導入・定着に関する新しいスタンダードとして活用できる。 |
| 3 | ハローワーク等の労働力需給調整機関にとっては、労働者、企業の双方が職業能力を明確に示すことにより、雇用のミスマッチ解消につなげることができる。 |
| 4 | 教育訓練実施機関にとっては、職業訓練の対象者の能力レベル表示や修了時の能力評価を適切に行うことができる。 |
| | 現在、在宅介護業等について、能力評価基準の策定作業を進めているところである。今後も引き続き、幅広い分野について能力評価基準の整備を行うこととしている(図4参照)。
また、今までに策定されてきた能力評価基準がどのように使われてきたのか、活用手法の具体的な好事例を活用事例集としてとりまとめ、更なる活用・普及促進を図ることとしている。 |
【ホームページのリニューアル】
| | 広く活用を図るため能力評価基準データを自由に閲覧・ダウンロードできるよう中央職業能力開発協会のHPで公開を行っている。
本日、より使いやすいHPとするための改修を行った。
| (1) | 業種を選んで業種別の「職業能力評価基準」を見ることができる「業種から選択する」 |
| (2) | 仕事一覧(職業分類(厚生労働省編))から関連する職業能力評価基準を見ることができる「仕事(職業分類)から選択する」 |
| (3) | 設定したフリーワード(例:企業倫理、顧客、加工等)に関係のある職業能力評価基準を検索する「フリーワードから選択する」 |
等、利用者の立場に応じて3つの方法から選択できるようにされ、より活用しやすいつくりとなっている(図5参照)。
また、新たに基準活用事例が追加されており、活用の例として5つのパターンについて、企業や団体の活用事例や評価手法の例示などが紹介されている(図6参照)。
なお、HP上において、今後の策定の参考となるようアンケート調査を実施している。 |
| (図5) | リニューアル後の職業能力評価基準ホームページ |