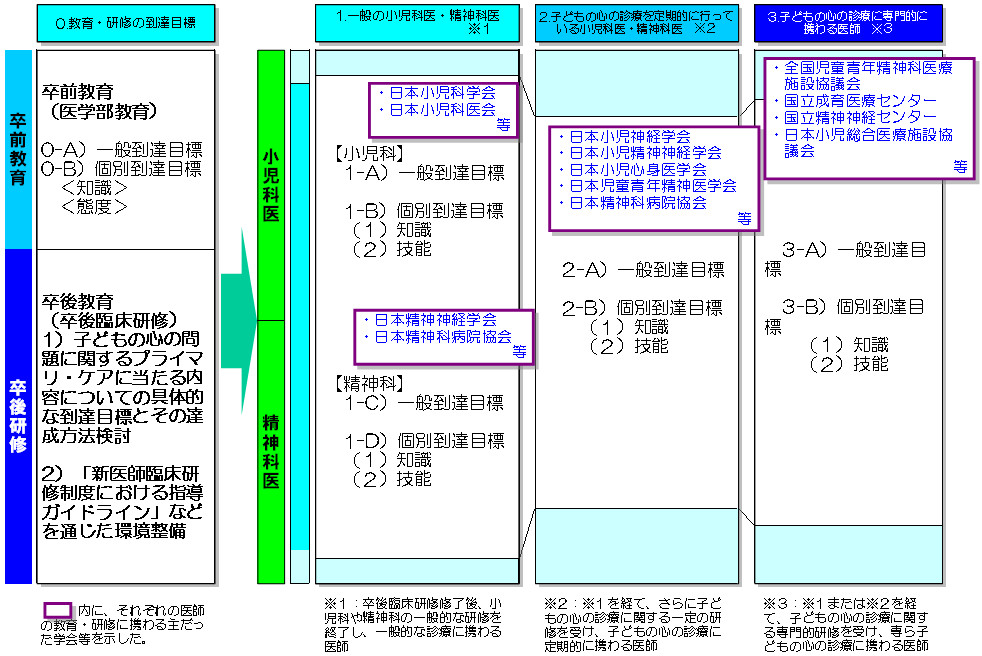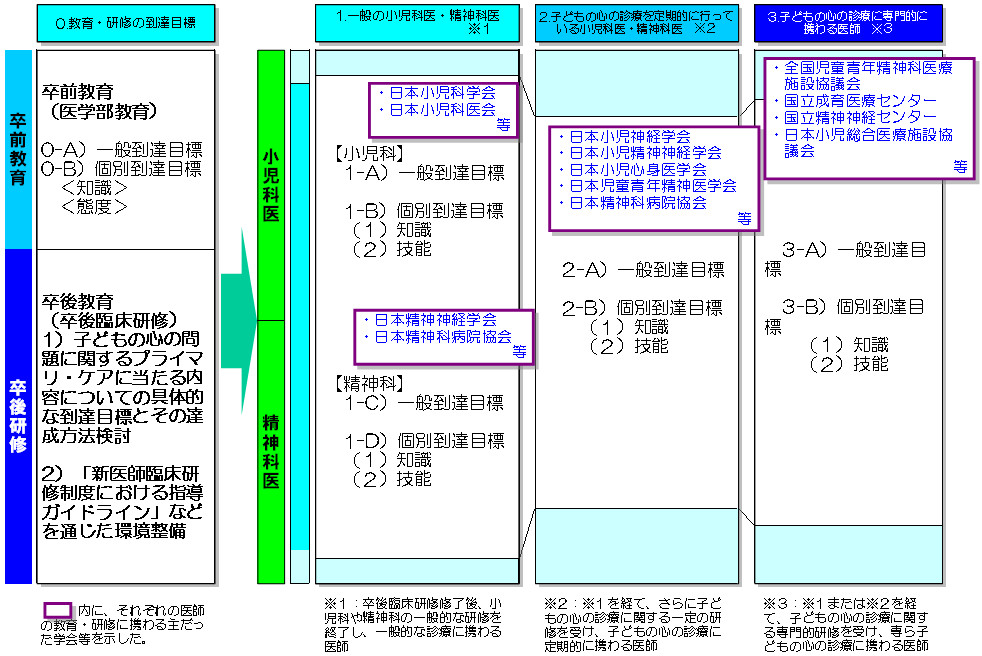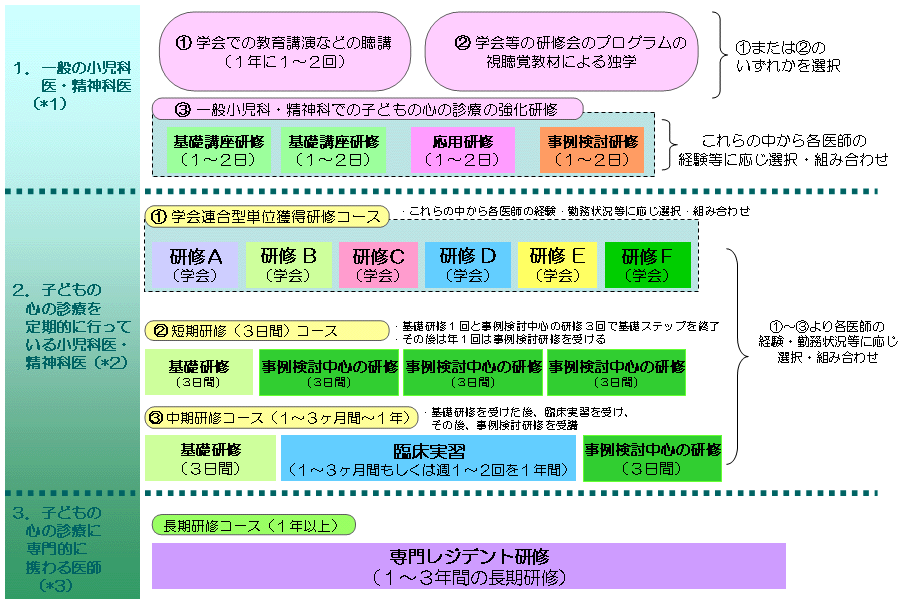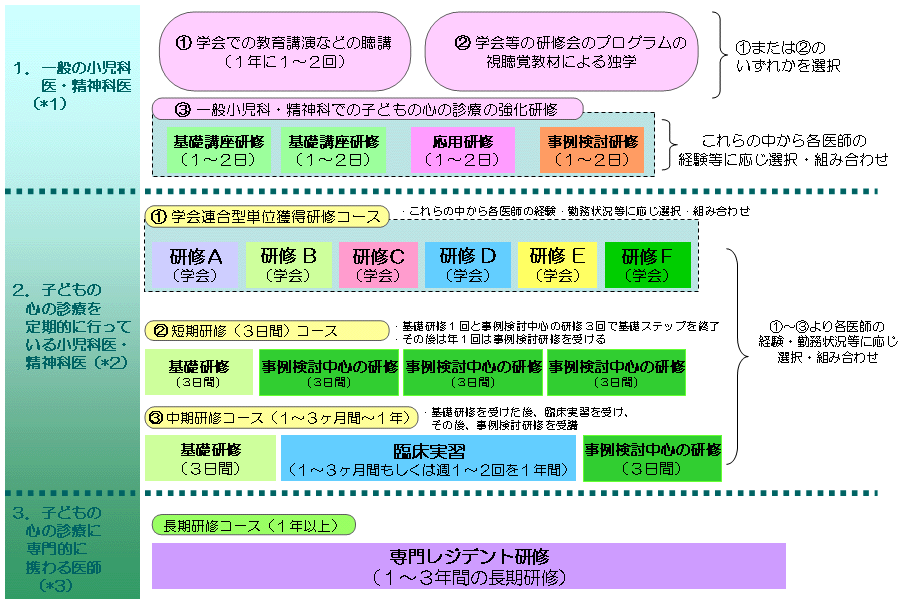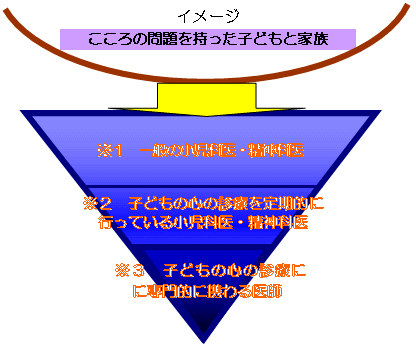〈照会先〉
厚生労働省雇用均等・児童家庭局
母子保健課
| 担当 |
: |
斎藤,木阪,飯野 |
| 電話 |
: |
03-5253-1111(内線7933、7939) |
|
子どもの心の診療医の養成に関する検討会
平成17年度報告書について
PDFファイルを見るためには、Adobe Readerというソフトが必要です。
Adobe Readerは無料で配布されています。
(次のアイコンをクリックしてください。) 
|
近年、発達障害児や虐待による心の問題をもつ子どもへの対応の充実が求められているが、こうした分野の専門的な診療を行うことができる医師や医療機関は限られており、いわゆる「子どもの心の診療医」の養成・確保が急務である。
そこで、「子どもの心の診療医の養成に関する検討会」を設置し、一般の小児科医や子どもの診療を行う精神科医が子どもの心の診療に関する基礎知識や技能を身につけるための方策を検討し、
平成17年度の検討会の報告書を取りまとめた。
| |
「子どもの心の診療医」を、その専門性のレベルから、三種類に分類(図1)し、それぞれについて、 |
| 1 |
現行の医学教育・研修や医師の生涯教育における子どもの心の診療に関する教育・研修の現状を把握した上で、学会等関係者の今後の活動計画を調査した。 |
| 2 |
子どもの心の診療医が身につけるべき基本的知識や技能について、専門性のレベルごとに「到達目標」として取りまとめた(図2)。 |
| 3 |
子どもの心の診療に関する「研修モデル」の骨格を示した(図3)。 |
| 4 |
「研修モデル」を実施するために、今後、関係者が行うべき活動を示した。 |
|
図1
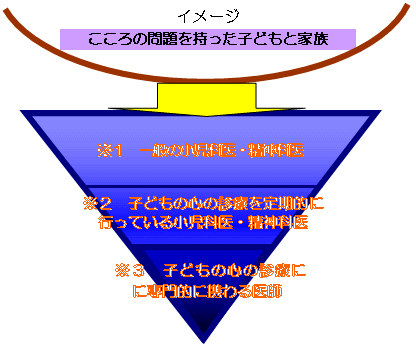 |
| ※1 |
卒後臨床研修修了後、小児科や精神科の一般的な研修を修了し、一般的な診療に携わる医師
|
| ※2 |
上記1を経て、さらに子どもの心の診療に関する一定の研修を受け、子どもの心の診療に定期的に携わる医師
|
| ※3 |
上記1又は2を経て、子どもの心の診療に関する専門的研修を受け、専ら子どもの心の診療に携わる医師
|
|
報告書のポイント(抜粋)
| |
子どもの心の診療について教えることのできる教官・教員が非常に少ないことや学生の実習ができないことが指摘された。 |
| |
日本小児科学会では、小児科認定医(現在の専門医)の到達目標に、子どもの心の診療に関する項目を含めているが、指導医の不足や症例をみる機会が少ないことが指摘された。
一方、精神科でも日本精神神経学会が認定医制度の中に児童・小児精神科医等の履修を義務づけているが、子どもの心の診療に関する教育の占める割合は、大きくはなかった。 |
| |
学会や医師会等の関係団体が子どもの心の診療に関する生涯教育を行っている例を取りまとめた。 |
| 2. |
子どもの心の診療を定期的に行っている小児科医・精神科医のための研修・生涯教育の現状 |
| |
学会や医師会等の関係団体が子どもの心の診療に関する各種専門的研修や生涯教育を行っている例を取りまとめた。 |
| 3. |
子どもの心の診療に専門的に携わる医師のための研修の現状 |
| |
平成18年1月現在で、専門研修を行うことが可能と考えられる専門診療施設は全国で約20か所であったが、このうち実際に専門的な研修を行っているのは、国立精神・神経センター国府台病院、国立成育医療センター及び全国児童青年精神科医療施設協議会に加盟している8病院であった。 |
| II. |
子どもの心の診療のための教育・研修の到達目標について |
それぞれの段階の「子どもの心の診療医」が修得すべきと考えられる一定水準の知識と技能について、求められる知識や技能を「一般到達目標」として包括的に述べ、修得すべき具体的な知識や技能を「個別到達目標」としてとりまとめた(
図2)。
| III. |
「子どもの心の診療医」養成の方法について |
それぞれの段階の「子どもの心の診療医」が教育・研修到達目標を達成するための方法を検討し、前述の養成のための「研修モデル」の骨格を提示した(
図3)。
| |
専門的指導を行うことのできる教員の確保と実習場所の確保が必要である。 |
| |
小児科・精神科の研修指導医が、子どもの心の問題についても、適切な指導を行えるよう、「卒後臨床研修制度における指導ガイドライン」などを通じて環境整備を行う必要がある。 |
| 2) |
小児科及び精神科の専門研修(卒後臨床研修修了後の研修)と生涯教育 |
| |
卒後臨床研修修了後の子どもの心の診療に関する研修の場の具体的な施設要件
について、関係学会などが検討する必要がある。
また、学会・医師会・協議会等の関係団体が実施する既存の研修を有効に活用し、充実させる必要がある。ここでは、年1〜2回の学会の教育講演の聴講と、子どもの心の診療の強化研修のモデル等を示した。 |
| 2. |
子どもの心の診療を定期的に行っている小児科医・精神科医の養成について |
| |
学会・医師会・協議会、ナショナルセンター、大学、その他民間非営利団体等が実施する既存の講習会等の研修プログラムを有効に活用し、さらに充実・発展させる必要がある。求められる研修のモデルとして、学会連合型単位獲得モデル等を示した。 |
| 3. |
子どもの心の診療に専門的に携わる医師の養成について |
| |
子どもの心の診療を専門的に実施している医療機関において、1〜3年間の長期研修が必要であるが、これについては平成18年度に引き続き検討を行う。 |
| 本検討会報告書に基づき、関係者は、子どもの心の診療医の養成・確保に向けた取り組みを積極的に進めることが期待される。 |
図2
子どもの心の診療のための教育・研修の到達目標(イメージ)
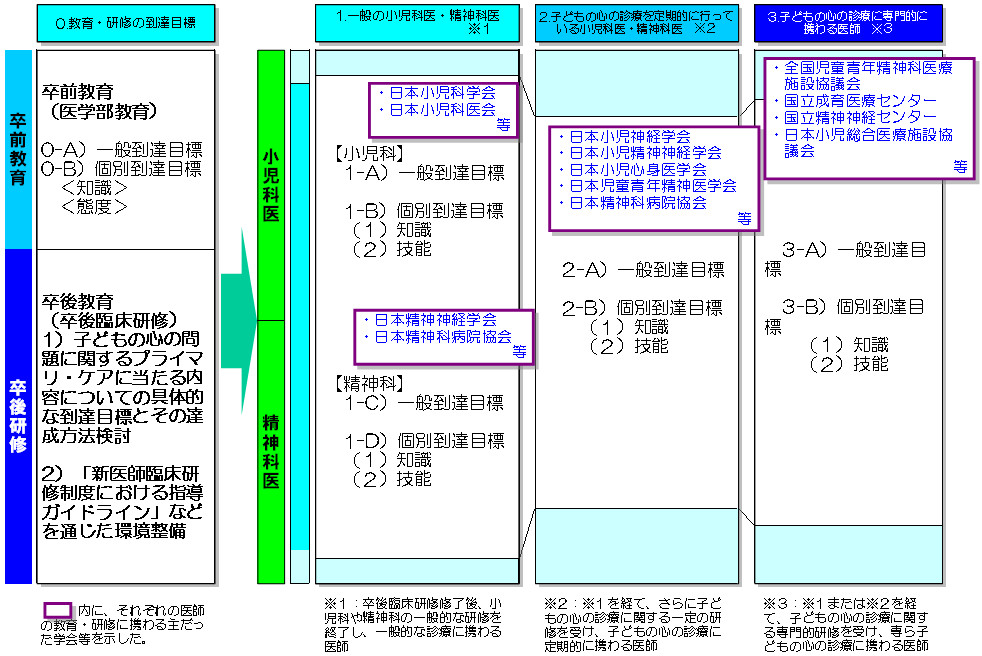
図3
「子どもの心の診療医」の養成研修モデル
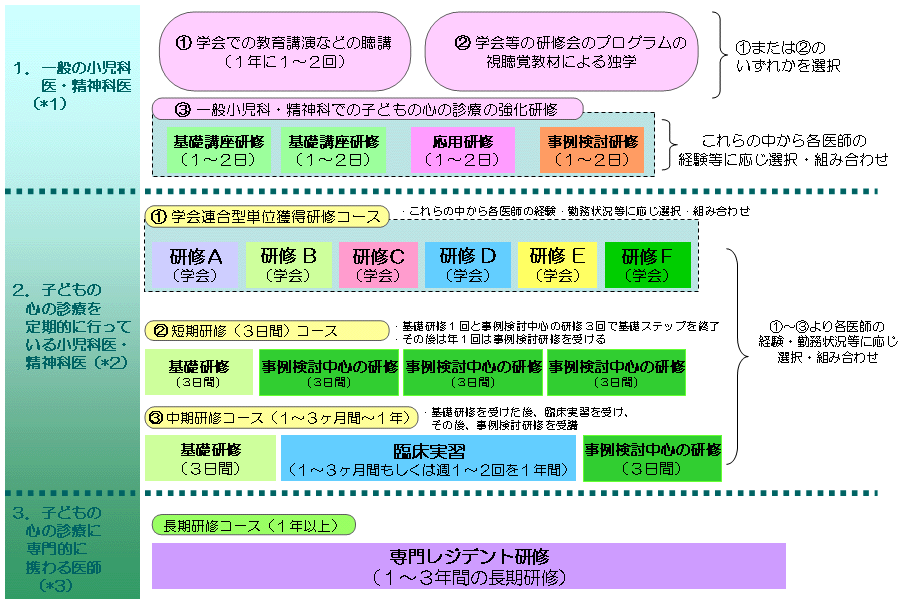
| *1 |
卒後臨床研修修了後、小児科や精神科の一般的な研修を修了し、一般的な診療に携わる医師。 |
| *2 |
上記*1を経て、さらに子どもの心の診療に関する一定の研修を受け、子どもの心の診療に定期的に携わる医師。 |
| *3 |
上記*1又は上記*2を経て、子どもの心の診療に関する専門的研修を受け、専ら子どもの心の診療に携わる医師。 |