平成17年8月4日
|
大臣官房国際課国際協力室 補佐 今井(内7302) 主査 稲川(内7306) (直通)03-3595-2404 |
第3回ASEAN・日本社会保障ハイレベル会合
社会福祉・保健におけるパートナーシップと人づくり
−母子保健福祉と障害者保健福祉を中心として−
(8月29日〜9月1日、東京)の開催について
| 1. 経緯 |
第3回会合では、特に、ASEAN諸国において対応の強化の必要性が認識され、二国間・多国間協力が今後最も成果をあげ得る分野である、母子保健福祉と障害者保健福祉を中心に、社会福祉・保健におけるパートナーシップと人づくりをテーマに、ASEAN各国間の情報・経験の共有を図り、中長期的な協力関係の構築につながる議論を展開する。
また、本会合は、ASEAN+3保健担当及び社会福祉担当大臣会合を支える事業として関係国間で位置づけられており、第1回及び第2回会合の結果は、2004年4月にマレーシアで開催されたASEAN+3保健大臣会合及び2004年12月にタイで開催されたASEAN+3社会福祉会合に報告され、高い評価を得ると同時に、今後の会合への期待が表明された。
| 2. 主催 |
| 3. 協力 |
| 4. 開催日時・場所 |
| (1) | 日時 平成17年8月29日(月)〜9月1日(木) | ||
| (2) | 場所
|
| 5. 参加者(予定) |
| 6. プログラム(予定) |
9:00〜17:00
| ・ | 施設見学(身体障害者授産施設、身体・知的障害児通園施設、母子保健センター等) |
8月30日(火) 於:厚生労働省専用第15会議室(7階)
9:00〜15:30 全体会合
| ・ | 開会挨拶(厚生労働大臣又は厚生労働審議官(予定)) |
| ・ | 「日・ASEAN保健福祉人材育成連携協力と本会合の意義」 講師:皆川尚史 厚生労働省大臣官房審議官 |
| ・ | 「ASEAN地域のコミュニティー構築における保健・福祉人材育成」 講師:Ms. Moe Thuzar ASEAN事務局人材開発課長補佐 |
| ・ | 「障害者保健福祉活動の動向」 講師:多々良紀夫 淑徳大学総合福祉学部教授 |
| ・ | 「SEARO(南東アジア)地域のコミュニティーにおける保健・福祉活動」 講師:Dr. U Than Sein WHO/SEARO非感染症・精神保健局長 |
| ・ | 「母子保健福祉分野における国際協力」 講師:仲佐保 国立国際医療センター国際医療協力局派遣協力第二課長 |
| ・ | 「ODAケースレポート:(1)タイにおける障害者の就労機会開発と山岳民族の自立支援、(2)国際基準に合った理学療法士と作業療法士の育成に向けて」 講師:渡辺肇 JICA人間開発部社会保障チーム長 他 |
8月31日(水) 於:厚生労働省専用第18、20会議室(17階)
9:00〜12:00 分科会
| ・ | グループ1「母子保健とコミュニティーサポート」 |
| ・ | グループ2「障害者・児のための福祉・保健サービス」 |
9月1日(木) 於:厚生労働省専用第18、19、20会議室(17階)
9:00〜12:00
| ・ | 全体会合・総括 |
| 7. 使用言語 |
| 8. 傍聴・取材 |
傍聴又は取材を希望される方は下記募集要領によりお申し込み下さい。
(募集要領)
| (1) | 会場設営の関係上、予めご連絡いただきますようお願いいたします。 |
| (2) | 葉書、ファクシミリ又は電子メールにてお申し込み下さい。 (別紙1を参照下さい。また、電話でのお申し込みはご遠慮下さい。) |
| (3) | 申し込み締め切り日は8月23日(火)(当日必着) |
| (4) | 傍聴が可能な人数は20名です。傍聴希望者がこれを上回った場合、傍聴希望者の中から抽選により、傍聴できる方を選定することと致します。抽選の結果、傍聴できない方に対しましては後日ご連絡差し上げます。(傍聴可能な方には特段通知等いたしません。) |
| (5) | 当日は、会場への入場の際、身分を証明するものをご提示下さい。 |
| (6) | 傍聴者は別紙2に掲げる留意事項を遵守してください。遵守されない場合は、ご退場いただく場合があります。 |
別紙1
| (1) | 葉書でお申し込みの場合
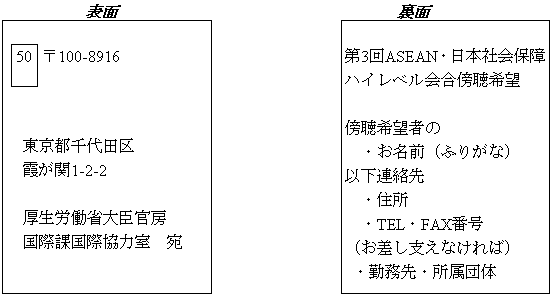
|
| (2) | ファクシミリ又はE-Mailでお申し込みの場合
ファクシミリ番号:03(3502)6678 E-Mailアドレス:cooperation@mhlw.go.jp
|
別紙2
傍聴される皆様への留意事項
第3回ASEAN・日本社会保障ハイレベル会合の傍聴にあたり、次の留意事項を遵守してください。これらを守れない場合は退場していただくことがあります。
| 1 | 事務局の指定した場所以外の場所に立ち入ることはできません。 |
| 2 | 携帯電話・ポケットベル等の電源は必ず切って傍聴してください。 |
| 3 | 写真撮影やビデオカメラ・テープレコーダー等の使用はご遠慮下さい。(報道関係者の写真撮影等は、傍聴・取材が可能な日の冒頭の頭撮りに限り可。) |
| 4 | 静粛を旨とし、意見聴取の妨害となるような行為は慎んでください。 |
| 5 | 意見聴取における言論に対し賛否を表明し、又は拍手することはできません。 |
| 6 | 傍聴中、新聞又は書籍の類を閲覧することはご遠慮下さい。 |
| 7 | 傍聴中、飲食及び喫煙はご遠慮下さい。 |
| 8 | 傍聴中の入退席はやむをえない場合を除き謹んで下さい。 |
| 9 | 銃器その他危険なものを持っている方、酒気を帯びている方、その他秩序を乱す恐れがあると認められる方の傍聴はお断りいたします。 |
| 10 | その他、事務局職員の指示に従うようお願いします。 |