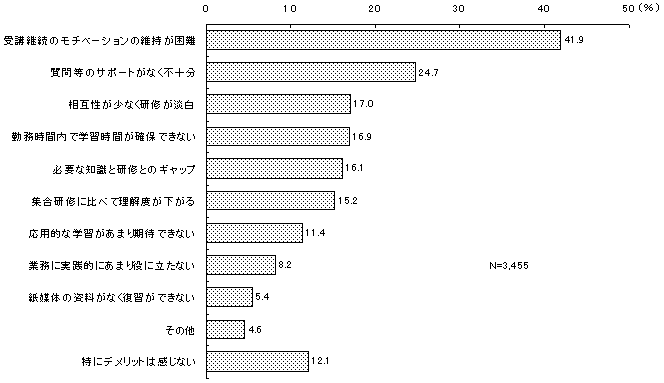|
|
「平成16年度能力開発基本調査結果概要」
| ○ | 計画的・組織的に能力開発を行う企業は経常利益が増加しているとする割合も比較的高い。 |
| ○ | 企業のOff-JT又は計画的OJT実施率は、昨年度より増えたが長期的には減少傾向 |
| ○ | 団塊の世代の定年に伴う技能継承の問題(2007年問題)への対応として、意欲ある若年・中堅層を確保し、円滑に技能が伝承できるようにすることが重要 |
[職業能力開発促進法に基づく取組]
|
| I | 調査の概要 |
| 1. | 「能力開発基本調査」は、我が国の企業、労働者の能力開発の実態を明らかにすることを目的として、平成13年度より実施しており、平成16年度は職業能力開発促進法に定める法定事項、教育訓練の実施状況、「2007年問題」等を時事的な主題として、平成17年1月に調査を実施した。 |
| 2. | 調査は「企業調査」「従業員調査」からなり、前者は「教育訓練の実施」、「2007年問題に対する意識」等、後者は「自己啓発の実施状況と外部教育訓練機関の活用」、「eラーニングの利用」等について質問した。 |
| 3. | 調査の対象は、全国・全業種(農林漁業、鉱業、公務を除く)の従業員(正社員)規模30人以上の企業から無作為に抽出した企業1万社とその従業員3万人であり、回答を得たのは企業1,405社(有効回収率14.1%)及び従業員3,455人(有効回収率11.5%)であった。 |
| II | 調査結果の概要 |
| 1 | 企業調査 |
| (1) | 教育訓練の実施 |
| ⅰ) | 特定の能力のある者が必要な場合の対応 特定の能力のある者を必要としている場合、「従業員を訓練して能力アップを図り、必要な人材の確保を図る」(1)(44.8%)とした企業が「外部からその能力のある者を雇い入れる」(2)(15.8%)とする企業よりも多くなっている。なお、「求める職種、役職によって異なる」(31.6%)は3割を占めている。 |
||||
|
|||||
| こうした対応をとる理由として、「従業員の能力アップを図る」場合は、「自社内の訓練の方が効率的(費用対効果)」(70.9%)が多い。一方、「外部からその能力のある者を雇い入れる」場合は、「内部育成では、間に合わない」(53.7%)が多かった。 | |||||
| 図1 | 特定の能力の者が必要な場合の対応(業種別) |
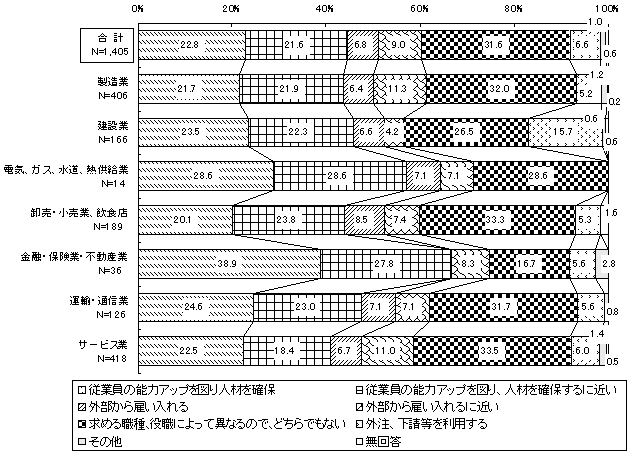
| 図2 | 対応をとる理由(特定の能力が必要な時の対応別) |
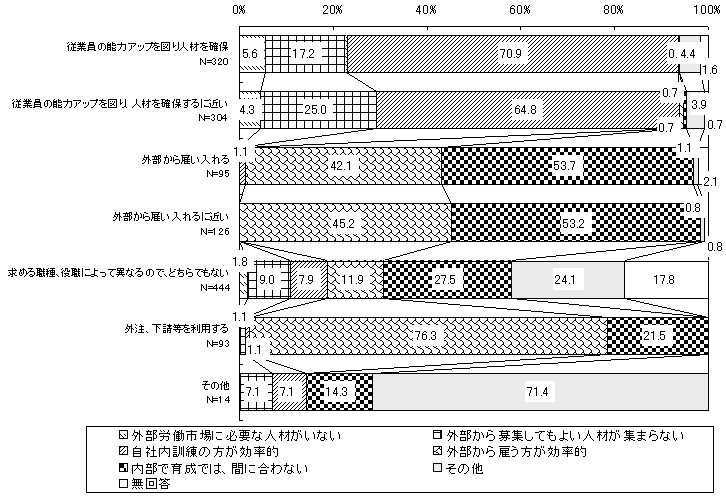
| ⅱ) | 能力開発の積極度 従業員に対する能力開発の積極度は、「積極的である」(3)(53.4%)企業が、「積極的ではない」(4)(45.8%)企業よりも多かった。 |
||||
|
|||||
| 経常利益別に見ると、5年前と比べ経常利益率が増加した企業では従業員に対する能力開発の積極度が高くなっている。 | |||||
| 図3 | 従業員の能力開発(業種別) |
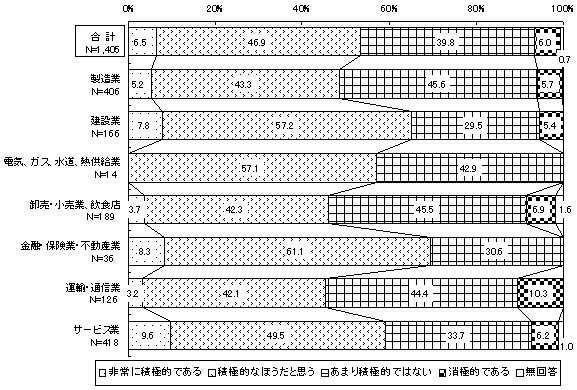
| 図4 | 従業員の能力開発(経常利益の増減別(5年前=100)) |
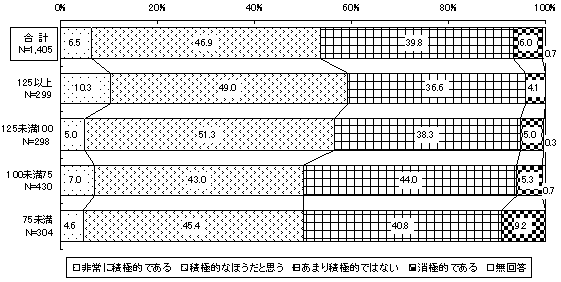
| ⅲ) | 職業能力開発促進法に基づく取組 |
| ア) | 職業能力開発計画の作成 事業所における職業能力開発計画について、「作成していない」(63.3%)企業が「作成している」(5)(31.4%)企業よりも多かった。 |
| (5) | 「事業所ごとに単独で作成している」「本社で一括して作成し、事業所に適用している」「いくつかの事業所は作成している」の回答計 |
| 図5 | 職業能力開発計画の作成(業種別) |
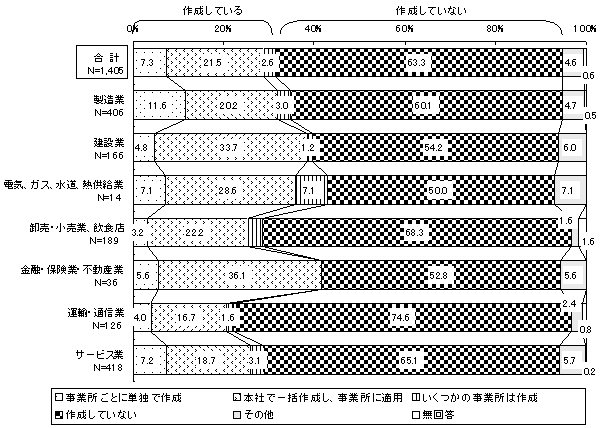
| イ) | 職業能力開発推進者の選任 事業所における職業能力開発推進者の選任状況は、「選任している」(6)(37.9%)企業よりも「選任していない」(59.5%)企業が多かった。 |
| (6) | 「事業所ごと単独で選任している」「本社で一括して選任している」「本社一括以外のかたちで他の事業所等と共同選任している」の回答計 |
| 図6 | 能力開発推進者の選任(業種別) |
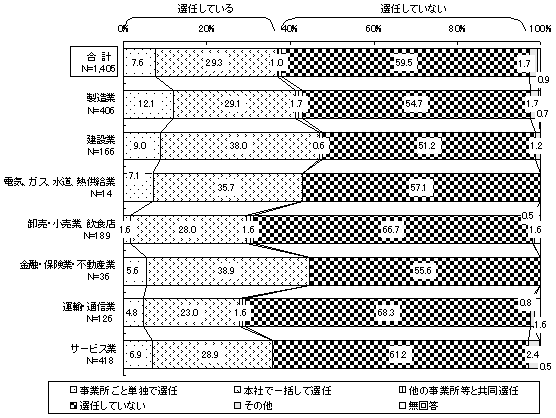
| ウ) | 計画の策定・推進者の選任と企業の経常利益の増減 事業所における職業能力開発計画を作成している企業及び職業能力開発推進者を選任している企業は、それぞれ作成していない企業及び選任をしていない企業と比べて5年前より経常利益が増加しているとする割合が高い傾向が見られた。 |
| 図7 | 5年前を100とした経常利益の構成比(職業能力開発計画作成の有無別) |
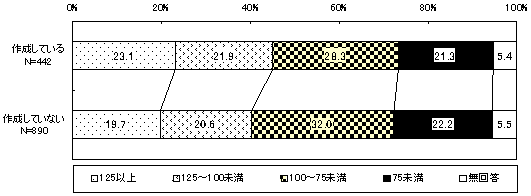
| 図8 | 5年前を100とする経常利益の構成比(職業能力開発推進者の選任の有無別) |
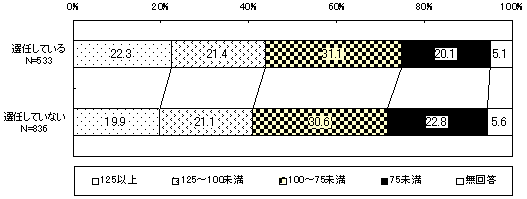
| ⅳ) | Off-JTの実施状況 |
| ア) | 実施率 平成15年度に従業員(正社員)に対して、Off-JT(7)を「実施した」企業(58.3%)は、「実施していない」企業(40.4%)よりも多く、約6割ではOff-JTを実施している。平成12年度(64.9%)と比較すると、6.6ポイント減少した。 |
||
|
|||
| 業種別に見ると、「金融・保険業・不動産業」(77.8%)がOff-JTの実施率が最も高い。 | |||
| 図9 | Off-JTの実施状況 |
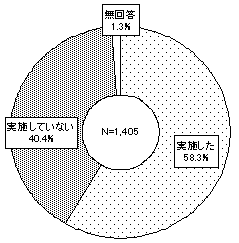
| 図10 | Off-JTの実施率(業種別) |
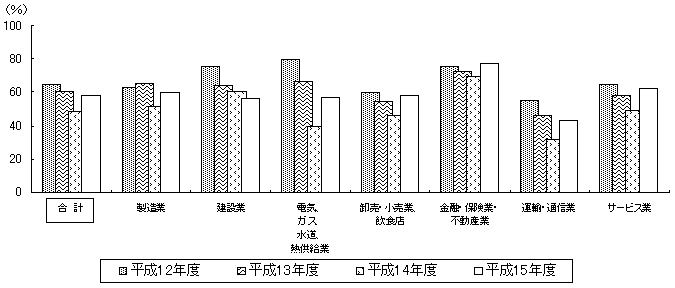
| イ) | 実施施設・手段 Off-JTで利用した教育訓練(教育訓練機関)は、「自社内の施設」(46.0%)が最も多く、以下「民間教育訓練機関」(43.8%)、「商工会・商工会議所・業界団体・協同組合」(39.7%)などであった。 |
| 図11 | Off-JTで利用した教育訓練(教育訓練機関) |
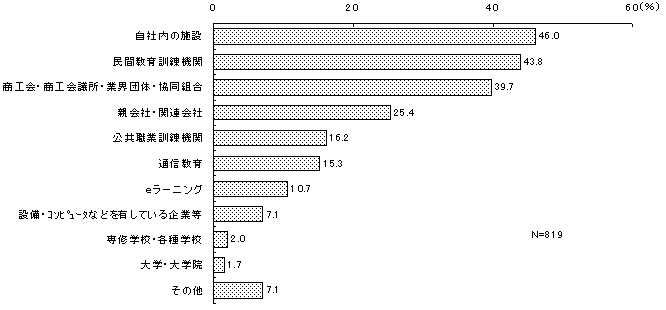
| ウ) | Off-JT費用 Off-JTを実施したと回答した企業における従業員1人当たりのOff-JTの平均費用総額は34,095円となり、平成12年度(24,600円)より9,495円高くなっている。 |
| 図12 | 従業員1人当たりのOff-JT平均額(過去3年間との比較) |
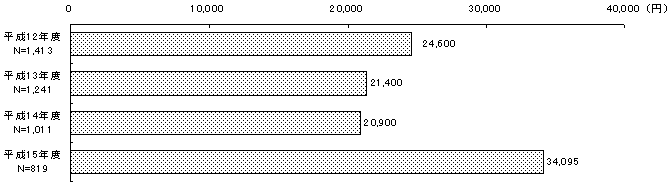
| ⅴ) | 計画的なOJTの実施状況 平成15年度に従業員(正社員)に対して計画的なOJT(8)を「実施した」企業(46.7%)は、「実施していない」企業(52.0%)より少ないが、平成12年度から横ばいである。 |
||
|
|||
| 業種別に見ると、「金融・保険業・不動産業」(55.6%)、「製造業」(52.5%)、「建設業」(50.0%)では計画的なOJTの実施率が半数以上となっている。 | |||
| 図13 | 計画的なOJTの実施 |
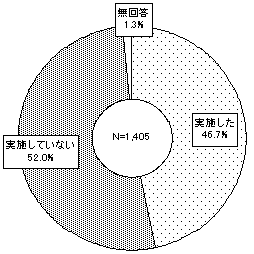
| 図14 | 計画的なOJTの実施率(業種別) |
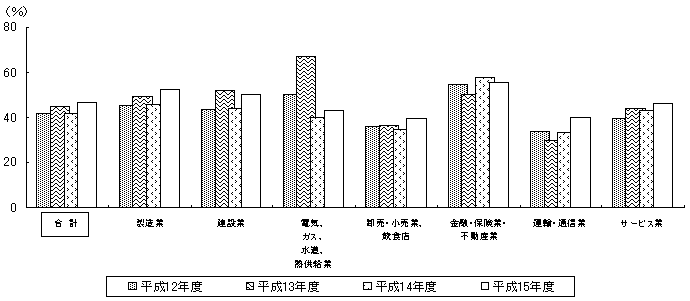
| ⅵ) | Off-JT又は計画的OJTの実施状況 平成15年度に従業員(正社員)に対して、Off-JT又は計画的OJTを実施した企業は68.2%であり、昨年度調査(59.5%)より増加したが、平成12年度(70.4%)と比較すると2.2ポイント減少し、長期的には減少傾向にある。 |
| 図15 | Off-JT又は計画的OJTの実施率の推移 |
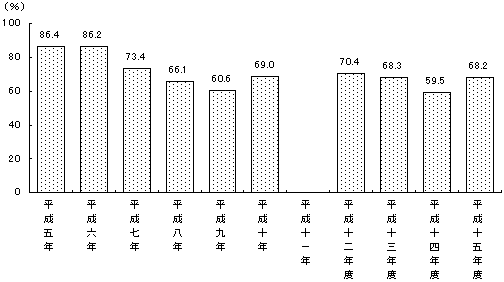
| 注) | 平成10年までは民間教育訓練実態調査の結果である |
| ⅶ) | 教育訓練の方針 能力開発の責任の主体について、「これまで」は、「従業員個人の責任」(11)(29.3%)よりも「企業責任」(12)と回答した企業が6割強(64.9%)を占めている。 |
||||
|
|||||
| しかし、「今後」についての回答では「企業責任」(62.1%)が若干低くなり、「従業員個人の責任」(32.5%)が若干高くなっている。 なお、3年前の調査結果と比べると、「これまで」を「従業員個人の責任」と考える企業は20.1%から29.3%へと増加している。 |
|||||
| 図16 | 能力開発責任主体の現状と今後(平成15年度) |
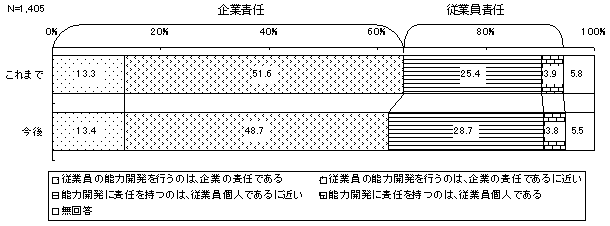
| 図17 | 能力開発責任主体の現状と今後(平成12年度) |
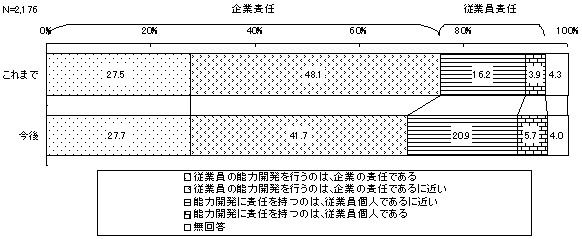
| ⅷ) | 能力開発や人材育成における問題点 能力開発や人材育成における問題点は、「指導する人材が不足している」(47.4%)、「人材育成を行う時間がない」(46.6%)等の人材不足・時間不足が問題点となっている割合が高くなっている。 |
| 図18 | 能力開発や人材育成における問題点 |
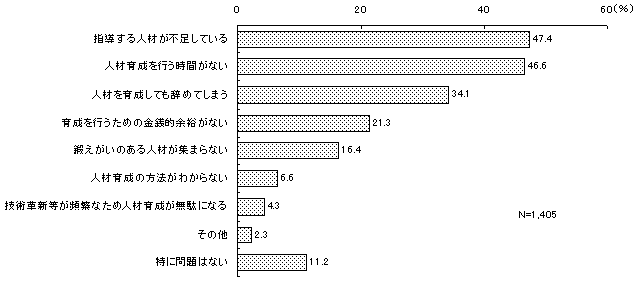
| (2) | 能力開発に係る支援 |
| ⅰ) | 自己啓発支援 |
| ア) | 支援方法 従業員の自己啓発支援として、「受講料等の金銭的援助」(59.6%)とする企業が多く、次いで「社外の研修コース、通信教育コース、図書等に関する情報提供」(47.0%)などであった。 |
| 図19 | 自己啓発支援(平成12年度との比較) |
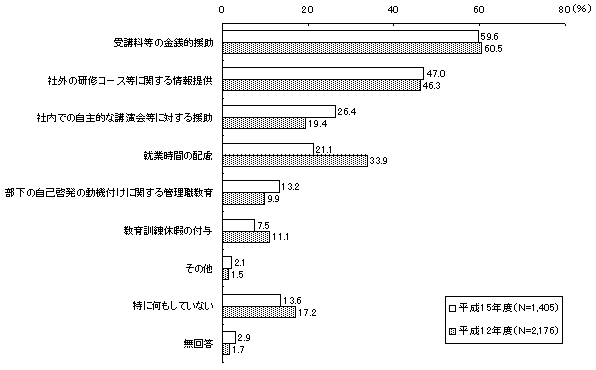
| ⅱ) | 日本国内の従業員に対する海外教育訓練 日本国内の従業員に対して海外教育訓練を「実施している」(5.8%)企業及び「実施を予定している」(2.2%)企業は合わせて1割弱で、「実施しておらず、予定していない」(90.1%)が9割以上を占めている。 |
| 図20 | 日本国内の従業員に対する海外教育訓練(業種別) |
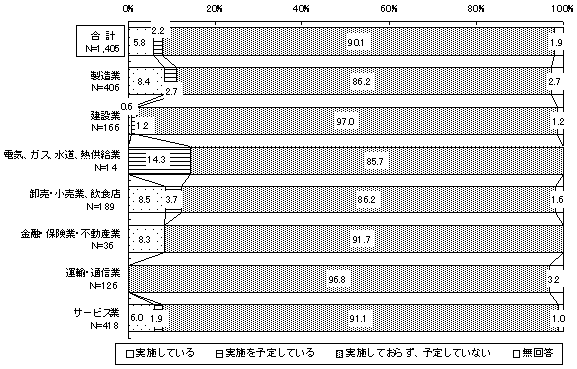
| ⅲ) | デュアルシステムの導入・認知状況 デュアルシステム(13)の導入・認知状況は、「知らないが、興味がある」(45.7%)が最も多く、次いで「知らないし、興味もない」(29.4%)が多く、「知っており、導入している」(2.2%)、「知っており、導入を検討している」(1.1%)は1割弱で、一方「知っているが、導入は検討していない」(19.7%)が2割以下となっている。 |
| (13) | 企業における実習訓練とこれに密接に関連した教育訓練機関における座学を並行的に実施し、修了時には能力評価を行うことにより、若年者を一人前の職業人に育てることを目的とする人材育成システム |
| 図21 | デュアルシステムの認知・導入状況(業種別) |
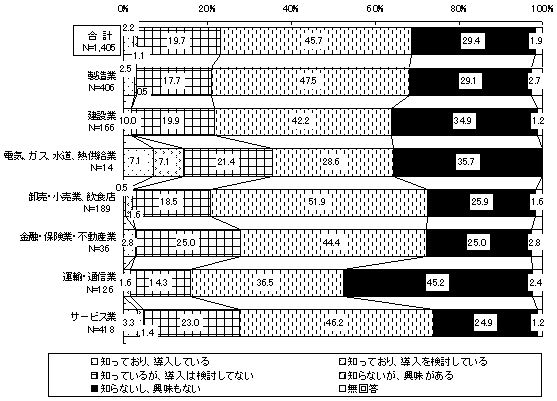
| ⅳ) | キャリア・コンサルティング |
| ア) | 実施状況 キャリア・コンサルティングを社内の制度・体制として「実施している」(3.3%)、「実施を予定している」(5.0%)は合わせて1割弱で、「実施しておらず、予定していない」(89.5%)企業が9割以上を占めている。 |
| 図22 | キャリア・コンサルティングの実施(業種別) |
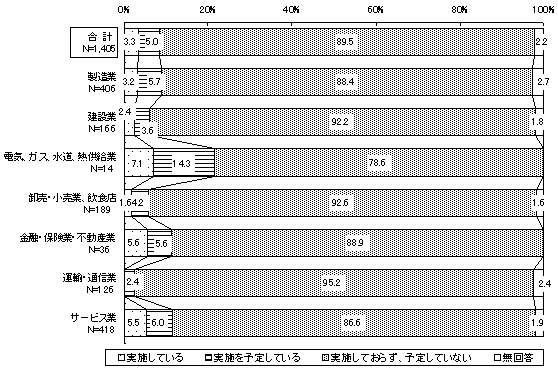
| イ) | 実施組織・機関 キャリア・コンサルティングを「実施している」「実施を予定している」と回答した企業(全体の8.3%)に実施する組織・機関について尋ねたところ、実施機関は「企業内部」(14)(62.9%)が多く6割以上を占めており、「企業外の機関等(アウトプレースメント会社、キャリア・コンサルティングサービス機関等)」(24.1%)が全体の1/4となっている。 |
| (14) | 「企業内の人事部(人事部付属のキャリア相談室等を含む)」「企業内の人事部以外の組織(人事部から独立したキャリア相談室等)」の回答計 |
| 図23 | キャリア・コンサルティングを実施する主な組織・機関(業種別) |
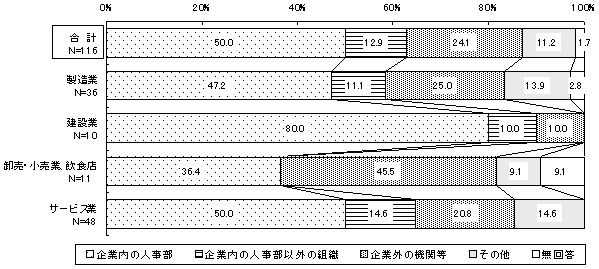
| ウ) | 実施目的 キャリア・コンサルティングの実施目的は、「従業員の能力開発のため」(75.0%)が最も多く、次いで「従業員の適正配置のため」(54.3%)となっている。 |
| 図24 | キャリア・コンサルティング実施の目的 |
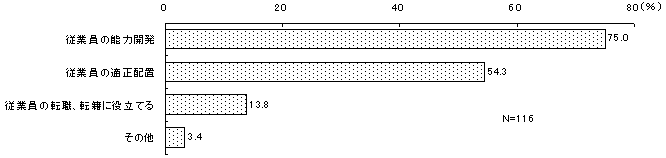
| (3) | eラーニング |
| ⅰ) | eラーニング予定 Off-JTで利用した教育訓練(教育訓練機関)のうち、eラーニングの利用は10.7%(図11参照)で、これ以外の企業の今後の利用予定は、「検討もしていない」(64.0%)、「利用を検討している」(21.3%)となっている。 |
| 図25 | eラーニング利用予定 |
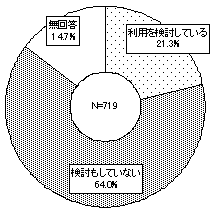
| ⅱ) | eラーニングの利用目的 eラーニングを利用している、利用予定の企業(全体の17.2%)に、eラーニングの利用目的について尋ねたところ、「都合の良い時間に合わせて、教育訓練が実施できる」(72.2%)が最も多く、以下「通所させる必要がない」(37.8%)、「社内において、多様な教育機関の教育内容を学習させることができる」(34.9%)などであった。 |
| 図26 | eラーニングを利用・利用予定の理由 |
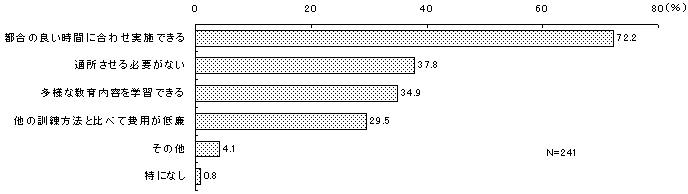
| ⅲ) | 活用分野 eラーニングの活用分野は、「IT・コンピュータ」(47.3%)が最も多く、以下「その他の専門知識」(32.8%)、「経営・管理(プロジェクト管理・企画・経営学、ISO取得等)」(31.1%)などであった。 |
| 図27 | eラーニングの活用分野 |
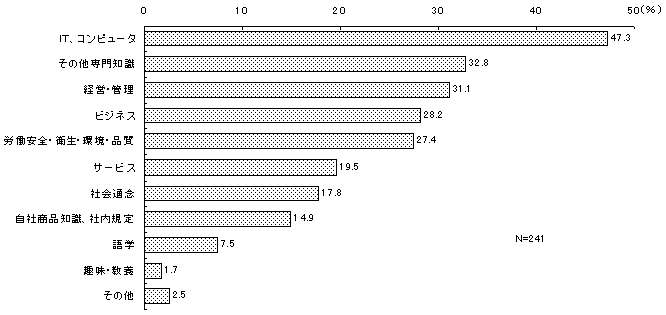
| ⅳ) | eラーニングを利用しない理由 eラーニングの利用を検討していない企業(全体の32.7%)にその理由について尋ねたところ、「eラーニングをよく知らない」(35.4%)が最も多く、以下「教育訓練の内容がeラーニングになじまない」(27.6%)、「他の教育訓練の方が効果的である」(26.7%)などであった。 |
| 図28 | eラーニングを利用しない理由 |
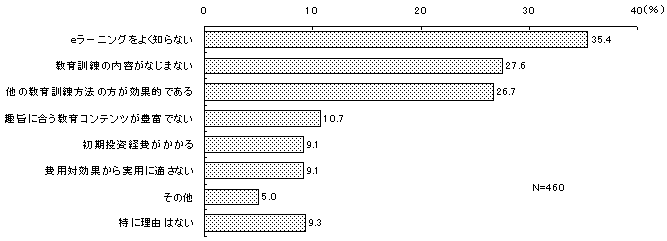
| (4) | 「2007年問題」 |
| ⅰ) | 団塊世代の労働者の占める割合 全従業員に対する団塊世代(1947年~1949年生まれ)の労働者の占める割合は平均で、9.2%となっており、「運輸・通信業」(12.6%)、「電気、ガス、水道、熱供給業」(10.9%)、「建設業」(10.5%)で1割以上となっている。製造業のうち、「出版・印刷・同関連産業」(11.6%)で高くなっている。 |
| 図29 | 団塊世代(1947年~1949年生まれ)の労働者の占める割合(業種別) |
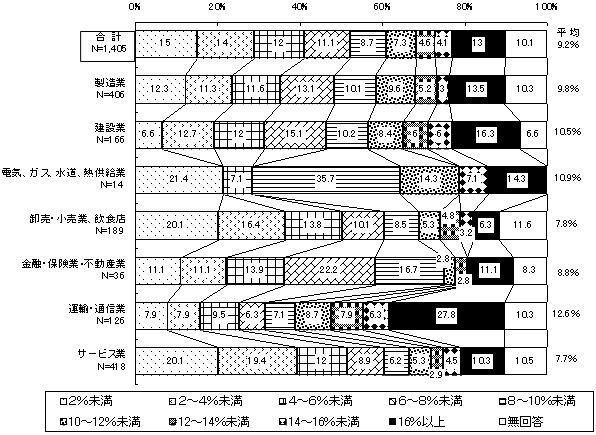
| ⅱ) | 「2007年問題」に対する危機意識 「2007年問題」に対する危機意識を「持っている」企業は22.4%、「持っていない」企業は61.6%、「分からない」企業は13.2%となっている。製造業では危機意識を「持っている」企業が30.5%と高くなっている。製造業のうち、「化学工業」(47.8%)、「一般機械器具製造業」(40.5%)、「金属製品製造業」(35.1%)で危機意識が高くなっている。 正社員規模別に見ると、300人以上の企業では危機意識が高い傾向にある。製造業の正社員規模別に見ると、どの正社員規模でも全業種よりも危機意識が高くなっている。 経常利益の増減別に見ると、5年前と比較して増加している企業では危機意識が高くなっている。 |
| 図30 | 「2007年問題」に対する危機意識(業種別) |
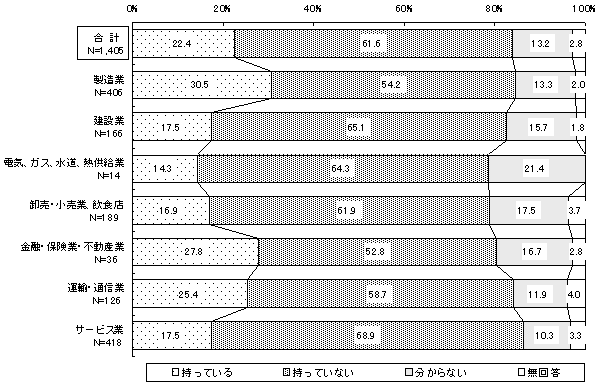
| 図31 | 「2007年問題」に対する危機意識(製造業内訳別) |
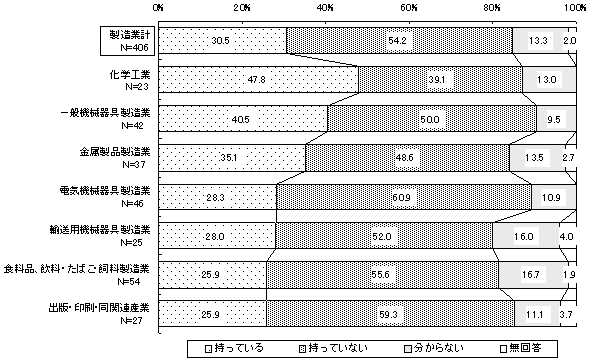
| 図32 | 「2007年問題」に対する危機意識(全産業:正社員規模別) |
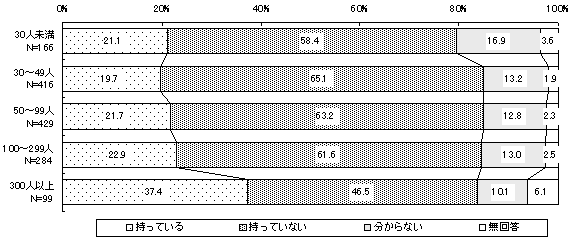
| 図33 | 「2007年問題」に対する危機意識(製造業:正社員規模別) |
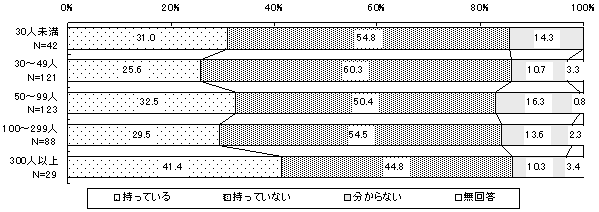
| 図34 | 「2007年問題」に対する危機意識(売上高の増減別(5年前=100)) |
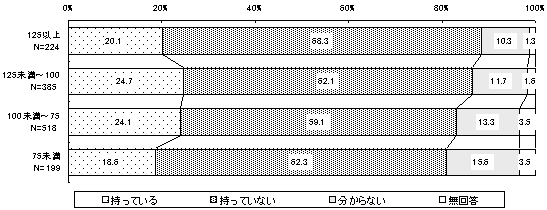
| 図35 | 「2007年問題」に対する危機意識(経常利益の増減別(5年前=100)) |
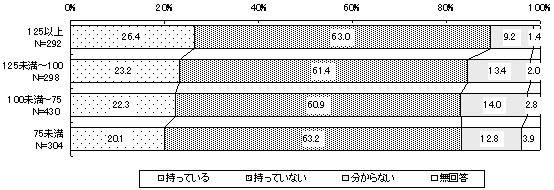
| 図36 | 「2007年問題」に対する危機意識(能力開発の積極性別) |
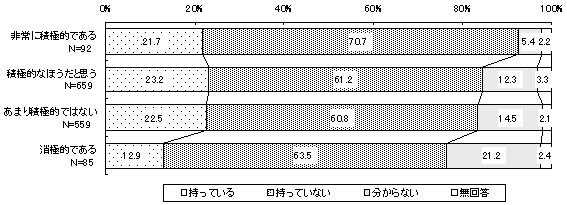
| ⅲ) | 危機意識を持つ要因 「2007年問題」に対する危機意識を持つ要因は、「意欲のある若年・中堅層の確保が難しい」(63.2%)が最も多く、以下「技能・ノウハウ等伝承に時間がかかり、円滑に進まない」(51.1%)、「教える方と教わる方の年代/レベルの差が開きすぎていて、コミュニケーションが厳しい」(35.9%)などであった。製造業では「技能・ノウハウ等伝承に時間がかかり、円滑に進まない」(68.5%)が最も多くなっている。 |
| 図37 | 危機意識を持つ要因(全業種と製造業の比較) |
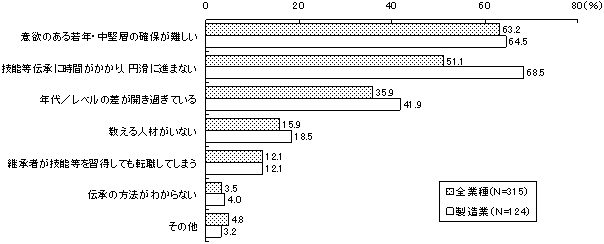
| ⅳ) | 取組 「2007年問題」に対する取組状況は、「必要な者を選抜して雇用延長、嘱託による再雇用を行い、指導者として活用予定」(40.7%)が最も多く、以下「中途採用を増やす」(21.2%)、「新規若年者の採用を増やす」(19.3%)などであった。「製造業」「建設業」ではこれに続いて「外注の活用」(15.0%,18.1%)を挙げている企業が多くなっている。 全業種と「製造業」を比較すると、「2007年問題」に対する取組は全て「製造業」の方が高くなっている。 危機意識の有無別に見ると、危機意識の有無に関わらず「必要な者を選抜して雇用延長、嘱託による再雇用を行い、指導者として活用予定」(60.6%,35.8%)とする企業が最も多くなっている。また、危機意識を「持っている」企業が「持っていない」企業よりいずれの取組も高い割合で取組んでいる。 製造業のうち、危機意識の高い「一般機械器具製造業」「金属製品製造業」は「新規若年者の採用を増やす」(35.7%,32.4%)「中途採用を増やす」(33.3%,29.7%)が製造業全体より高くなっている。 |
| 図38 | 「2007年問題」に対する取組 |
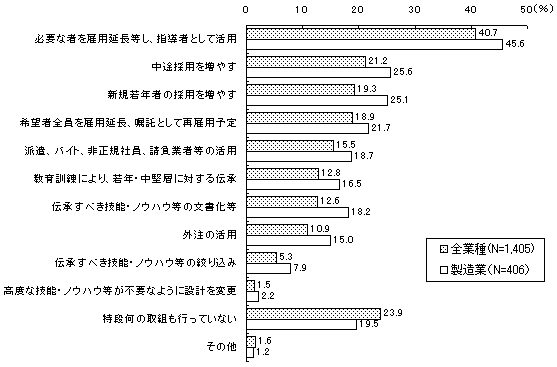
| 図39 | 「2007年問題」に対する取組(危機意識の有無別) |
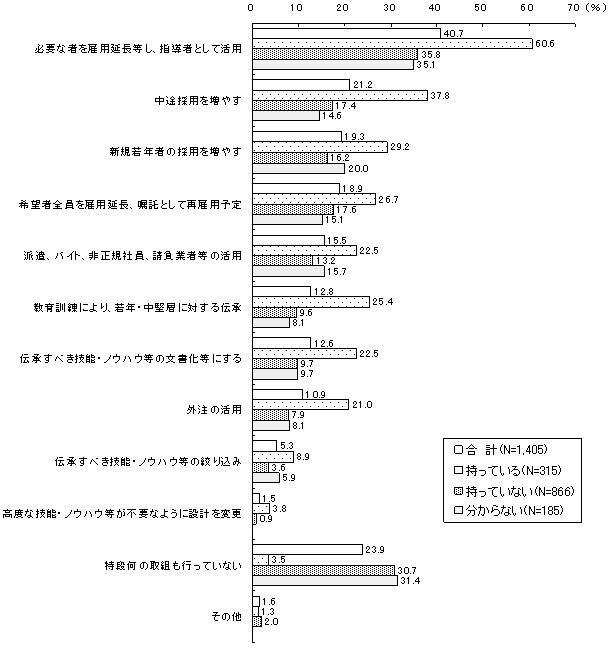
| 2 | 従業員調査 |
| (1) | 教育訓練の受講 |
| (ⅰ) | Off-JTの受講状況 平成16年にOff-JTを「受講した」従業員は29.0%であった。3年前の調査と比べると、6.4ポイント減少している。 Off-JTの受講した内容は、「階層別教育研修(管理職向け、中堅社員向け、新入社員研修など)」が39.7%で最も多く、「営業・販売職」においては51.5%と受講率が高くなっている。 受講した教育訓練の平均受講時間も「階層別教育研修(管理職向け、中堅社員向け、新入社員研修など)」が26.6時間で最も多く、「24歳以下」の従業員においては平均受講時間が107.2時間と長くなっている。 |
| 図40 | Off-JTの受講率(過去3年間との比較) |
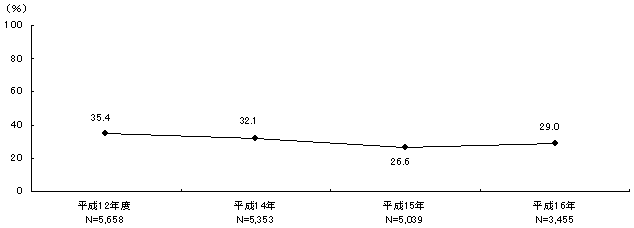
| 図41 | 平均受講時間 |
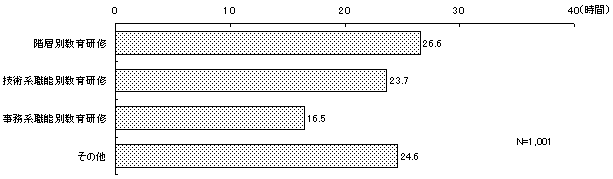
| (ⅱ) | 自己啓発の実施状況 |
| ア) | 実施状況 平成16年の自己啓発の実施率は36.5%で、3年前の調査結果から横ばいである。 |
| 図42 | 自己啓発の実施率(過去3年の比較) |
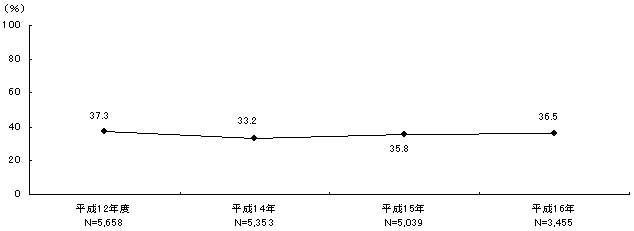
| イ) | 実施目的 自己啓発の実施目的は、「現在の仕事に必要な知識・能力を身につけるため」(77.4%)が最も多く、以下「将来の仕事やキャリアアップに備えて」(37.3%)、「資格取得のため」(36.7%)などであった。 |
| 図43 | 自己啓発の目的(3年前の調査結果と比較) |
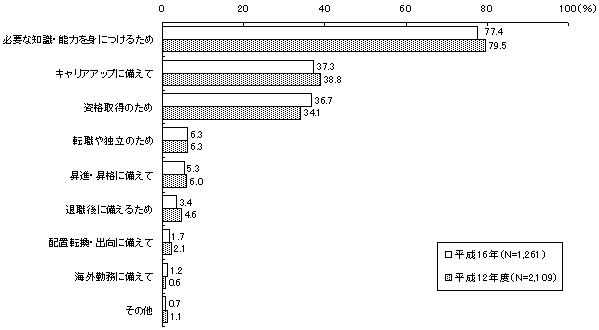
| ウ) | 自己啓発内容 実施した自己啓発の内容は、「ラジオ・テレビ・専門書・パソコン通信などによる自学・自習」が36.5%で最も多く、以下「民間教育訓練機関の講習会・セミナーへの参加」(28.7%)、「社外の勉強会・研究会への参加」(28.0%)などであった。3年前の調査結果と比較すると、「社内の自主的な勉強会・研修会への参加」「社外の勉強会・研究会への参加」などでは今年度の参加率が高くなっている。 |
| 図44 | 自己啓発の参加率(3年前の調査結果と比較) |
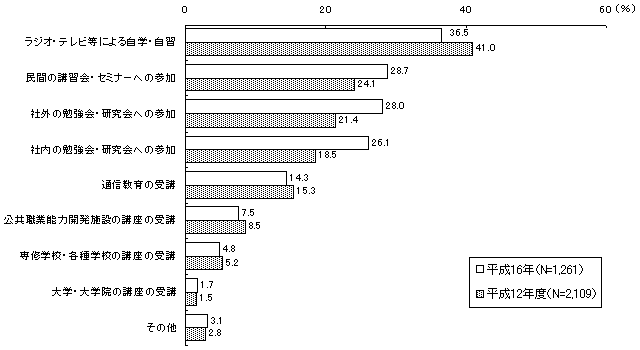
| エ) | 時間・費用 実施した自己啓発の平均受講時間は、「専修学校・各種学校の講座の受講」(91.4時間)、「ラジオ・テレビ・専門書・パソコン通信などによる自学・自習」(87.0時間)が長くなっている。 自己啓発にかかった費用(自己負担額)の平均総額は82,500.2円となった。3年前の調査結果(76,541円)と比較すると、5,959.2円高くなっている。 |
| 図45 | 平均受講時間 |
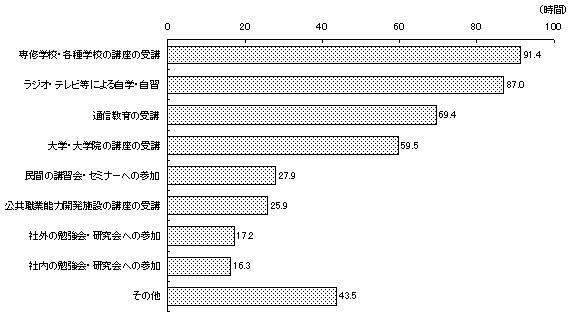 |
||
|
| (ⅲ) | 自己啓発・職業生活設計の際に不足している情報 自己啓発等をする際に不足している情報は、「能力を習得したあとの処遇についての情報」(30.8%)が最も多く、以下「企業外の教育訓練、自己啓発に関する情報」(24.1%)、「各職業に必要な能力・技術・資格、キャリアルートについての情報」(21.7%)などであった。 |
| 図46 | 自己啓発・職業生活設計の際に不足している情報 |
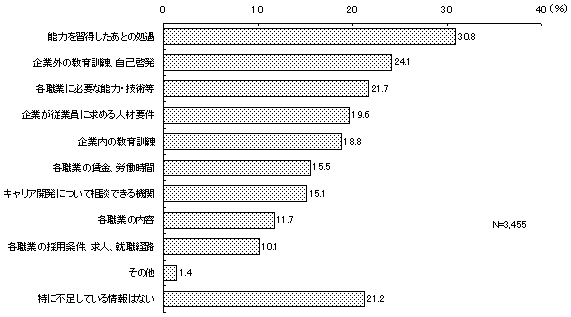
| (ⅳ) | 自己啓発にあたっての問題点 自己啓発の問題点は、「忙しくて自己啓発の余裕がない」(42.1%)が最も多く、以下「費用がかかりすぎる」(31.7%)、「休暇取得・早退等が会社の都合でできない」(19.7%)となっており、問題点としては金額・時間の問題が多くなっている。3年前の調査結果と比較すると、「コースの受講や資格取得の効果が定かでない」「費用がかかりすぎる」は6.2ポイント、5.8ポイント増加している。 |
| 図47 | 自己啓発にあたっての問題点 |
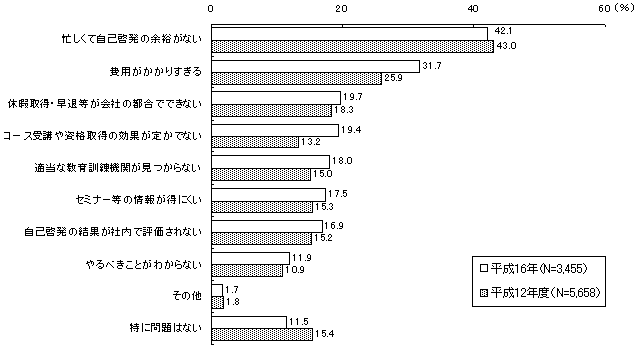
| (2) | eラーニング |
| (ⅰ) | 認知状況 eラーニングの認知状況は、「全く知らない」が51.9%、「知っている」(1)は47.6%であった。 |
| (1) | 「よく知っている」「何となく知っている」の回答計 |
| 図48 | eラーニングの認知状況 |
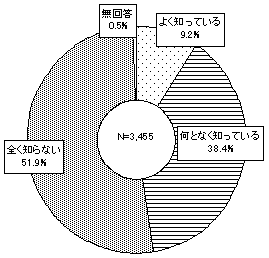
| (ⅱ) | 利用経験 eラーニングの利用経験は、「利用しておらず、予定もない」が79.0%、「今後利用する予定」は11.6%、「利用したことがある」は8.6%となっている。 |
| 図49 | eラーニングの利用経験 |
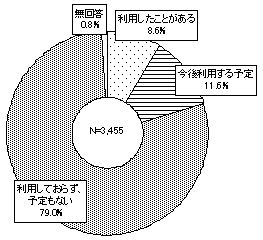
| (ⅲ) | 活用分野 eラーニングの活用分野は、「IT・コンピュータ」(49.2%)が最も多く、以下「趣味・教養」(34.2%)、「ビジネス(経理・法律・金融・不動産等)」(29.2%)などであった。 |
| 図50 | eラーニングの利用分野 |
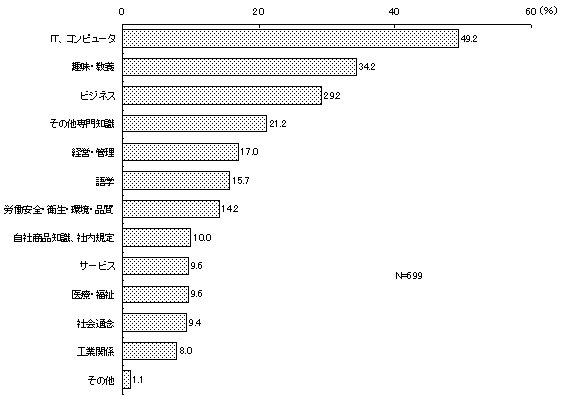
| (ⅳ) | メリット eラーニングのメリットは、「時間が自由(好きなときに学習でき、自分の速さで進められる)」(67.5%)が最も多く、以下「場所が自由」(43.7%)、「1人でできる(他の人を気にしなくて良い、知られない)」(34.2%)、「繰り返し学習できる」(31.5%)などであった。 |
| 図51 | eラーニングのメリット |
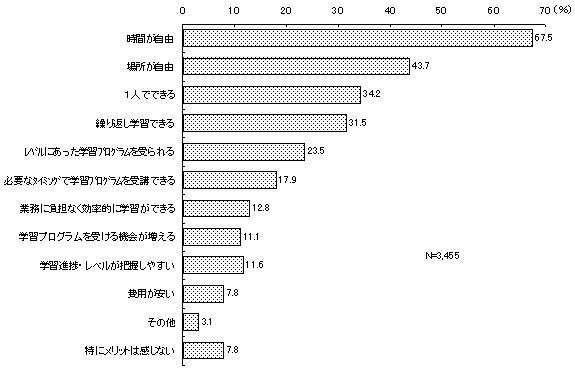
| (ⅴ) | デメリット eラーニングのデメリットは、「受講継続のモチベーションの維持が困難」(41.9%)が最も多く、以下「質問等のサポートがない、不十分」(24.7%)、「インタラクティブ性(相互性)が少ないため、研修自体淡白に感じる」(17.0%)、「勤務時間内で学習時間が確保できない」(16.9%)などであった。 |
| 図52 | eラーニングのデメリット |