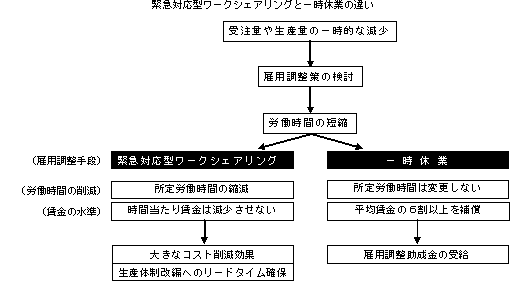
|
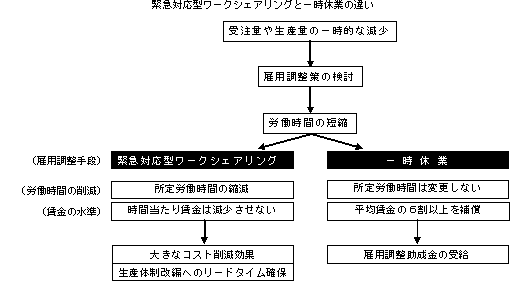
| (1)一時的なコスト削減 |
| (2)熟練従業員の確保による生産回復への対応力の維持 |
| (3)手待ち時間減少によるモラール維持 |
| (4)雇用不安感の解消、会社への忠誠心の維持 |
| (5)生産体制改編へのリードタイムの確保 |
| (6)良好な労使関係の維持 |
| 参考: | A社における段階別の雇用調整策
|
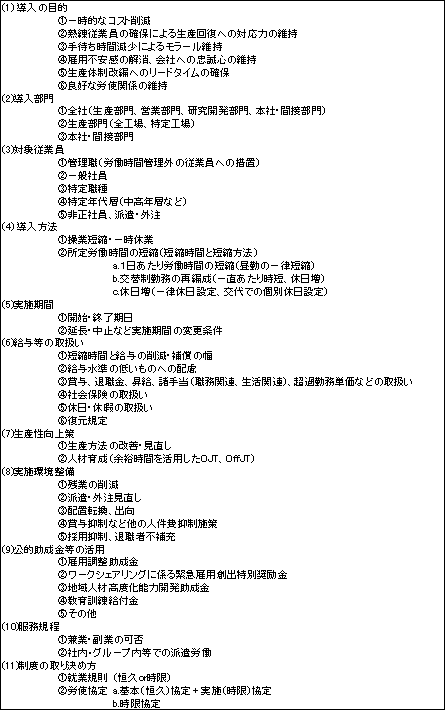
| (1)全社(生産部門、営業部門、研究開発部門、本社・間接部門) |
| (2)生産部門(全工場、特定工場) |
| (3)本社・間接部門 |
| (1)管理職(労働時間管理外の従業員への措置) |
| (2)一般社員 |
| (3)特定職種 |
| (4)特定年代層(中高年層など) |
| (5)非正社員、派遣・外注 |
| (1)操業短縮・一時休業 | ||||||
(2)所定労働時間の短縮(短縮時間と短縮方法)
|
| (1)開始・終了期日 |
| (2)延長・中止など実施期間の変更条件 |
| (1)短縮時間と給与の削減・補償の幅 |
| (2)給与水準の低いものへの配慮 |
| (3)賞与、退職金、昇給、諸手当(職務関連、生活関連)、超過勤務単価などの取扱い |
| (4)社会保険の取扱い |
| (5)休日・休暇の取扱い |
| (6)復元規定 |
| (1)生産方法の改善・見直し |
| (2)人材育成(余裕時間を活用したOJT、OffJT) |
| (1)残業の削減 |
| (2)派遣・外注見直し |
| (3)配置転換、出向 |
| (4)賞与抑制など他の人件費抑制施策 |
| (5)採用抑制、退職者不補充 |
| (1)雇用調整助成金 |
| (2)ワークシェアリングに係る緊急雇用創出特別奨励金 |
| (3)キャリア形成促進助成金 |
| (4)教育訓練給付金 |
| (5)その他 |
| (1)兼業・副業の可否 |
| (2)社内・グループ内等での派遣労働 |
| (1)就業規則(恒久or時限) | ||||
(2)労使協定
|
| (1)経験・技術技能・知識をもった社員の活用 |
| (2)60歳前半層の雇用機会の確保 |
| (3)技術技能の伝承と次代の人材育成 |
| (4)総額人件費の抑制・削減 |
| (5)稼働率の向上、需要への柔軟な対応力の維持・向上 |
| (6)労働力の確保 |
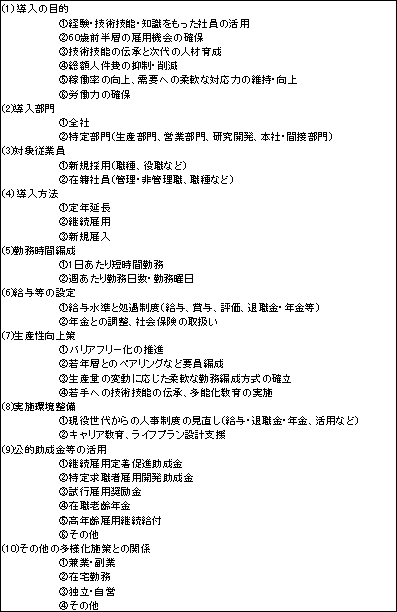
| (1)全社 |
| (2)特定部門(生産部門、営業部門、研究開発、本社・間接部門) |
| (1)新規採用(職種、役職など) |
| (2)在籍社員(管理・非管理職、職種など) |
| (1)定年延長 |
| (2)継続雇用 |
| (3)新規雇入 |
| (1)1日あたり短時間勤務 |
| (2)週あたり勤務日数・勤務曜日 |
| (1)給与水準と処遇制度(給与、賞与、評価、退職金・年金等) |
| (2)年金との調整、社会保険の取扱い |
| (1)バリアフリー化の推進 |
| (2)若年層とのペアリングなど要員編成 |
| (3)生産量の変動に応じた柔軟な勤務編成方式の確立 |
| (4)若手への技術技能の伝承、多能化教育の実施 |
| (1)現役世代からの人事制度の見直し(給与・退職金・年金、活用など) |
| (2)キャリア教育、ライフプラン設計支援 |
| (1)継続雇用定着促進助成金 |
| (2)特定求職者雇用開発助成金 |
| (3)試行雇用奨励金 |
| (4)在職老齢年金 |
| (5)高年齢雇用継続給付 |
| (6)その他 |
| (1)兼業・副業 |
| (2)在宅勤務 |
| (3)独立・自営 |
| (4)その他 |
| (1)育児・介護などの家庭責任への対応 |
| (2)ボランティアなど個人生活志向への対応 |
| (3)教育訓練・自己啓発など人材投資への対応 |
| (4)人材の確保・リテンション(引き止め) |
| (5)戦略・専門人材の確保 |
| (6)従業員の活性化 |
| (7)独立・自営の準備支援 |
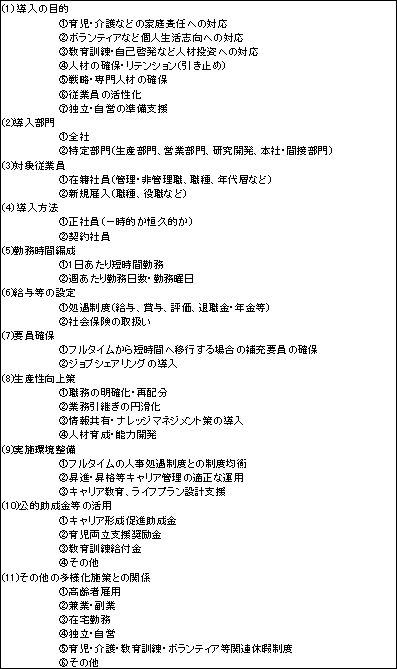
| (*) | 日本版デュアルシステム・・・企業における実習訓練と教育訓練機関における座学とを一体的に組み合わせた教育訓練を行うことにより、若年者を一人前の職業人に育てることを目的とする新たな人材育成システム |
| (1)全社 |
| (2)特定部門(生産部門、営業部門、研究開発、本社・間接部門) |
| (1)在籍社員(管理・非管理職、職種、年代層など) |
| (2)新規雇入(職種、役職など) |
| (1)正社員(一時的か恒久的か) |
| (2)契約社員 |
| (1)1日あたり短時間勤務 |
| (2)週あたり勤務日数・勤務曜日 |
| (1)処遇制度(給与、賞与、評価、退職金・年金等) |
| (2)社会保険の取扱い |
| (1)フルタイムから短時間へ移行する場合の補充要員の確保 |
| (2)ジョブシェアリングの導入 |
| (1)職務の明確化・再配分 |
| (2)業務引継ぎの円滑化 |
| (3)情報共有・ナレッジマネジメント策の導入 |
| (4)人材育成・能力開発 |
| (1)フルタイムの人事処遇制度との制度均衡 |
| (2)昇進・昇格等キャリア管理の適正な運用 |
| (3)キャリア教育、ライフプラン設計支援 |
| (1)キャリア形成促進助成金 |
| (2)育児両立支援奨励金 |
| (3)教育訓練給付金 |
| (4)その他 |
| (1)高齢者雇用 |
| (2)兼業・副業 |
| (3)在宅勤務 |
| (4)独立・自営 |
| (5)育児・介護・教育訓練・ボランティア等関連休暇制度 |
| (6)その他 |
| (1)良質な若年人材・後継者の確保 |
| (2)若年者を訓練する負担の軽減 |
| (3)若年者の職場定着 |
| (*) | 「7・5・3」離職・・・中卒者の7割、高卒者の5割、大卒者の3割が3年以内に離職していること |
| (1)全社 |
| (2)特定部門(生産部門、営業部門、研究開発、本社・間接部門) |
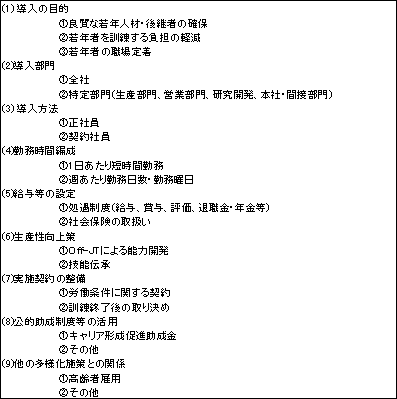
| (1)正社員 |
| (2)契約社員 |
| (1)1日あたり短時間勤務 |
| (2)週あたり勤務日数・勤務曜日 |
| (1)処遇制度(給与、賞与、評価、退職金・年金等) |
| (2)社会保険の取扱い |
| (1)Off-JTによる能力開発 |
| (2)技能伝承 |
| (1)労働条件に関する契約 |
| (2)訓練終了後の取り決め |
| (1)キャリア形成促進助成金 |
| (2)その他 |
| (1)高齢者雇用 |
| (2)その他 |
| (1)短時間就業ニーズへの対応 |
| (2)ローコスト・オペレーションの実現 |
| (3)パートタイムの量・質両面の基幹化、人材活用 |
| (4)業務量の変動・繁閑に応じた人材活用の効率化 |
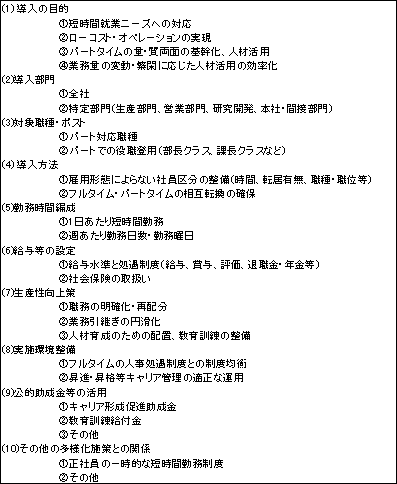
| (1)全社 |
| (2)特定部門(生産部門、営業部門、研究開発、本社・間接部門) |
| (1)パート対応職種 |
| (2)パートでの役職登用(部長クラス、課長クラスなど) |
| (1)雇用形態によらない社員区分の整備(時間、転居有無、職種・職位等) |
| (2)フルタイム・パートタイムの相互転換の確保 |
| (1)1日あたり短時間勤務 |
| (2)週あたり勤務日数・勤務曜日 |
| (1)給与水準と処遇制度(給与、賞与、評価、退職金・年金等) |
| (2)社会保険の取扱い |
| (1)職務の明確化・再配分 |
| (2)業務引継ぎの円滑化 |
| (3)人材育成のための配置、教育訓練の整備 |
| (1)フルタイムの人事処遇制度との制度均衡 |
| (2)昇進・昇格等キャリア管理の適正な運用 |
| (1)キャリア形成促進助成金 |
| (2)教育訓練給付金 |
| (3)その他 |
| (1)正社員の一時的な短時間勤務制度 |
| (2)その他 |
| (1)育児・介護などの家庭責任への対応 |
| (2)ボランティアなど個人生活志向への対応 |
| (3)教育訓練・自己啓発など人材投資への対応 |
| (4)人材の確保・リテンション(引き止め) |
| (5)戦略・専門人材の確保 |
| (6)従業員の活性化 |
| (7)独立・自営の準備支援 |
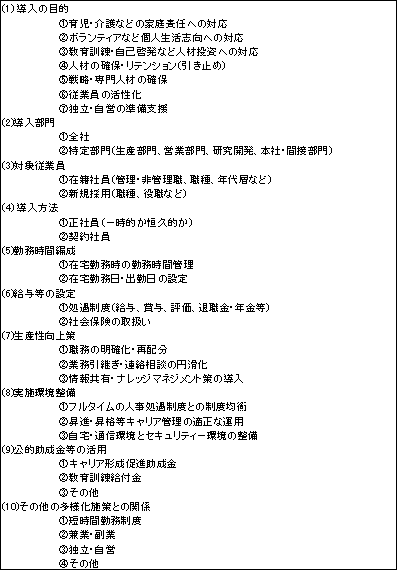
テレワークには、雇用形態で行われるものと非雇用の形態で行われるものがある。このうち雇用形態で行われるものには、(1)自宅で勤務する「在宅勤務」、(2)郊外等の小規模なオフィスで勤務する「サテライトオフィス勤務」、(3)臨機応変に選択した場所をオフィスとする「モバイルワーク」がある。 |
||||||
| (1)全社 |
| (2)特定部門(生産部門、営業部門、研究開発、本社・間接部門) |
| (1)在籍社員(管理・非管理職、職種、年代層など) |
| (2)新規採用(職種、役職など) |
| (1)正社員(一時的か恒久的か) |
| (2)契約社員 |
| (1)在宅勤務時の勤務時間管理 |
| (2)在宅勤務日・出勤日の設定 |
| (1)処遇制度(給与、賞与、評価、退職金・年金等) |
| (2)社会保険の取扱い |
| (1)職務の明確化・再配分 |
| (2)業務引継ぎ・連絡相談の円滑化 |
| (3)情報共有・ナレッジマネジメント策の導入 |
| (1)フルタイムの人事処遇制度との制度均衡 |
| (2)昇進・昇格等キャリア管理の適正な運用 |
| (3)自宅・通信環境とセキュリティー環境の整備 |
| (4)人材育成・能力開発 |
| (1)キャリア形成促進助成金 |
| (2)教育訓練給付金 |
| (3)その他 |
| (1)短時間勤務制度 |
| (2)兼業・副業 |
| (3)独立・自営 |
| (4)その他 |
| (1)多様なキャリア形成支援 |
| (2)独立・自営の準備支援 |
| (3)転職の準備支援 |
| (4)能力開発支援 |
| (1)在籍社員(管理・非管理職、職種、年代など) |
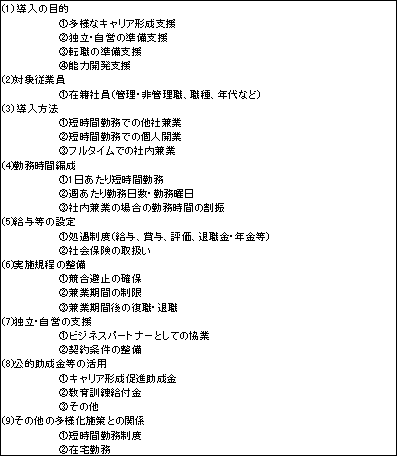
| (1)短時間勤務での他社兼業 |
| (2)短時間勤務での個人開業 |
| (3)フルタイムでの社内兼業 |
| (1)1日あたり短時間勤務 |
| (2)週あたり勤務日数・勤務曜日 |
| (3)社内兼業の場合の勤務時間の割振 |
| (1)処遇制度(給与、賞与、評価、退職金・年金等) |
| (2)社会保険の取扱い |
| (1)競合避止の確保 |
| (2)兼業期間の制限 |
| (3)兼業期間後の復職・退職 |
| (1)ビジネスパートナーとしての協業 |
| (2)契約条件の整備 |
| (1)キャリア形成促進助成金 |
| (2)教育訓練給付金 |
| (3)その他 |
| (1)短時間勤務制度 |
| (2)在宅勤務 |