図表1 性別(N=2166)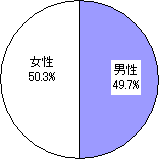 |
図表2 年齢構成(N=2166)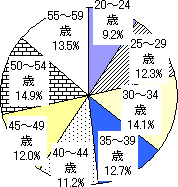 |
図表3 家族構成(1)(N=2166)
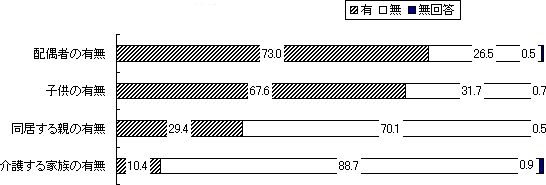
図表4 家族構成(2)(N=2070)
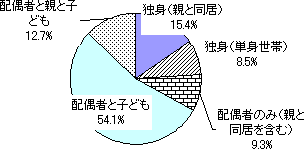
図表5 就業状況(N=2166)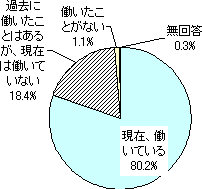 |
図表6 就業形態(N=1737)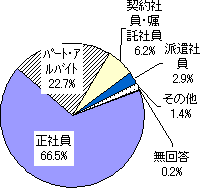 |
図表7 職種(N=1737)
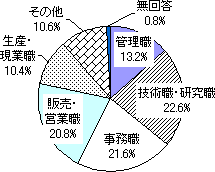
| (注) | 就業形態及び職種は、「現在、働いている」と回答した者の状況である。 |
| (1)個人調査 | 平成15年10月2日〜10月16日まで | |
| (2)企業調査 | 平成15年10月2日〜11月7日まで |
| (1)個人調査 | 20〜50歳代の男女各1,250人を地域・年齢・性別等による一定の分布基準(国勢調査の構成比)から抽出。 | |
| (2)企業調査 | 全業種の従業員数300名以上の全上場・店頭公開及び非上場企業5,630社 |
| (1)個人調査 | 有効回答数 | 2,166件(86.6%) | ||
| (2)企業調査 | 有効回答数 | 646件(11.5%) |
| 回答者の性別、年齢、家族構成、就業状況・形態、職種は、以下のとおりである。 |
図表1 性別(N=2166)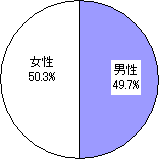 |
図表2 年齢構成(N=2166)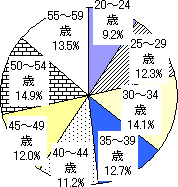 |
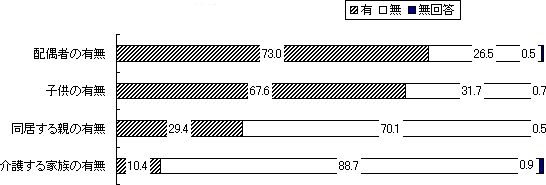
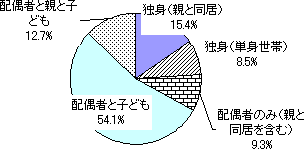
図表5 就業状況(N=2166)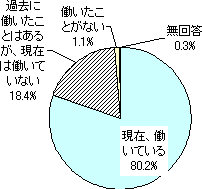 |
図表6 就業形態(N=1737)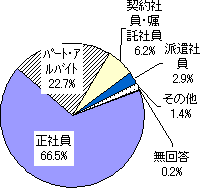 |
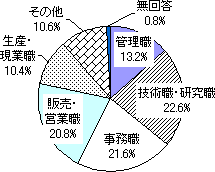
| (注) | 就業形態及び職種は、「現在、働いている」と回答した者の状況である。 |
| 回答者のうち配偶者ありと回答した者の配偶者の就業状況・形態は、以下のとおりである。 |
図表8 配偶者の就業状況(N=1582)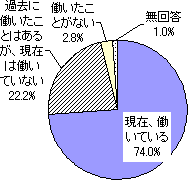 |
図表9 配偶者の就業形態(N=1171)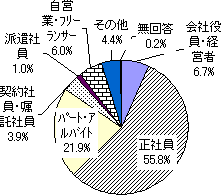 |
| ライフステージ別にみた回答者自身及び回答者の配偶者に対する多様な働き方への希望と、現時点での回答者の多様な働き方に対する希望は以下のとおりである。 |
| (1)短時間正社員 ライフステージ別にみた「短時間正社員」(働く時間が短い正社員)に対する希望(「希望する」及び「どちらかと言えば希望する」の合計)をみると、「学習活動に取り組みたい時期」(71.6%)、「高齢期」(71.0%)、「介護を必要とする家族がいる時期」(70.3%)のニーズが大きい。性別にみると、男性は「学習活動に取り組みたい時期」、「高齢期」、「介護を必要とする家族がいる時期」が7割以上を占め、女性は「子どもが小・中学生の時期」が78.9%で最も高く、「介護を必要とする家族がいる時期」、「高齢期」、「学習活動に取り組みたい時期」、「子どもが未就学の時期」が約7割となっている。また、男女とも低年齢層ほど「子どもが未就学の時期」、「子どもが小・中学生の時期」のニーズが高い。 |
| (単位:%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
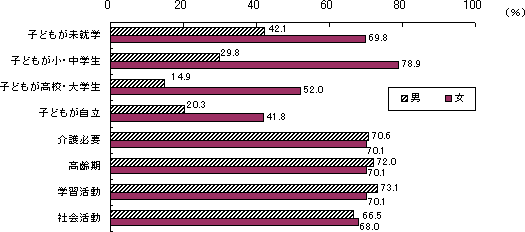
| (2)在宅勤務 ライフステージ別にみた「在宅勤務」に対する希望をみると、「介護を必要とする家族がいる時期」が75.1%で最も高く、次いで「高齢期」(68.5%)、「子どもが未就学の時期」(66.7%)、「学習活動に取り組みたい時期」(65.0%)となっている。性別にみると、男性は「介護を必要とする家族がいる時期」が74.9%で最も高く、次いで「高齢期」「学習活動に取り組みたい時期」が7割近くになっているのに対し、女性は「子どもが未就学の時期」が79.2%で最も高く、「介護を必要とする家族がいる時期」とともに「子どもが小・中学生の時期」も7割を超えている。また、男女とも低年齢層ほど「子どもが未就学の時期」のニーズが高い。 |
(単位:%)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
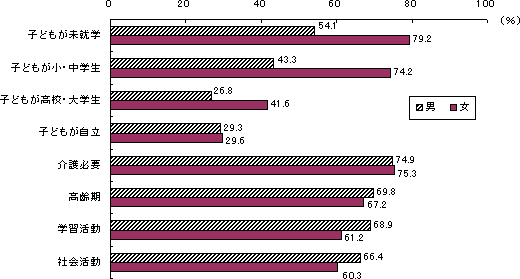
| (1)短時間正社員 ライフステージ別にみた配偶者に対する「短時間正社員」の希望をみると、「介護を必要とする家族がいる時期」が61.5%で最も高く、次いで「高齢期」(57.7%)、「子どもが未就学の時期」(48.4%)となっている。性別にみると、男性は、全てのライフステージにおいて女性よりも配偶者(妻)に対して短時間正社員を希望する傾向が強く、特に「子どもが未就学の時期」「子どもが小・中学生の時期」で男女の差が顕著である。年齢別では、20歳代の女性は他の世代よりも「子どもが未就学の時期」「子どもが小・中学生の時期」で配偶者(夫)に対する短時間正社員の希望が強い。 |
(単位:%)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
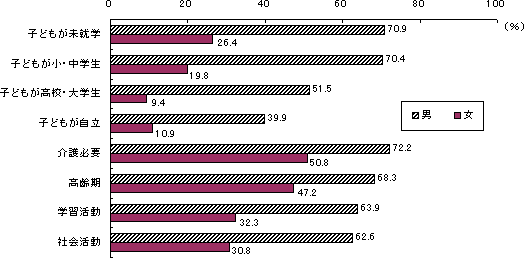
| (2)在宅勤務 ライフステージ別にみた配偶者に対する「在宅勤務」の希望をみると、「介護を必要とする家族がいる時期」が61.6%で最も高く、次いで「高齢期」、「子どもが未就学の時期」が約5割となっている。性別にみると、男性は、全てのライフステージにおいて配偶者(妻)に対して在宅勤務を希望する傾向が強い。 |
(単位:%)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
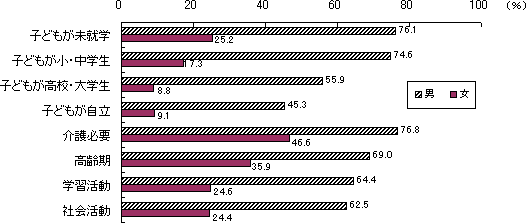
| 現時点での回答者の多様な働き方に対する希望は以下のとおりである。 (1)短時間正社員 現時点での短時間正社員の希望派(「希望する」と「どちらかと言えば希望する」の合計)は、37.3%となっている。性別にみると、女性は希望派が52.4%と半数を超える一方、男性は「希望しない」が54.3%となっている。また、年齢別にみると、30歳代の女性は希望派が62.4%と最も高くなっている。なお、20歳代の男性では25.3%と4分の1以上が希望している。 |
(単位:%)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (注) | 「希望指数」は、「希望する」×4点+「どちらかと言えば希望する」×3点+「どちらかと言えば希望しない」×2点+「希望しない」×1点を、「無回答」を除く全体で除した値。(図表20も同じ。) |
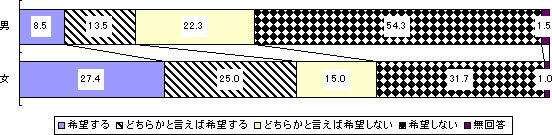
| (2)在宅勤務 現時点での在宅勤務の希望派(「希望する」と「どちらかと言えば希望する」の合計)は、38.9%となっている。性別にみると、希望派は男性が37.2%、女性は40.6%で、女性の方がやや希望が強い。また、年齢別にみると、女性の30歳代で希望派が51.9%と半数を超え、最も高い。 |
(単位:%)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
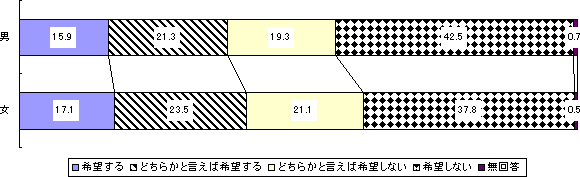
| 短時間正社員として働く場合に希望する期間について、育児等の理由で一定期間のみ短時間正社員で働きたいとする者は49.4% 、期間を特に定めず短時間正社員で働きたいとする者が49.5%で、ほぼ同数となっている。 希望する勤務時間については、「フルタイム正社員の1/2程度」が53.7%で最も多く、次いで「同3/4程度」が39.8%となっている。 また、希望する時間当たり賃金水準は、「フルタイム正社員の8割程度」が37.2%で最も多く、これに「同9割程度」(25.7%)、「フルタイム正社員と同じ」(21.2%)が続いている。 |
図表22 「短時間正社員」として働く場合に希望する期間(N=1210)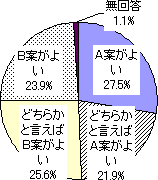
|
図表23 「短時間正社員」としての希望勤務時間(N=1210)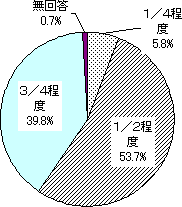
|
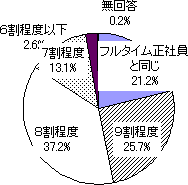
| 多様な働き方をする場合の仕事の進め方に関する問題点については、短時間正社員では、「顧客等会社外部への対応で支障」(48.1%)、「仕事の配分」(47.1%)、「フルタイム正社員への仕事のしわ寄せ」(44.0%)、「責任の所在」(43.4%)が挙げられている。 また、在宅勤務では、「他の社員とのコミュニケーション」が64.7%で最も高く、次いで「社内での打ち合わせや会議で支障」が53.8%と、社内でのコミュニケーションに関する点が問題として挙げられている。 |
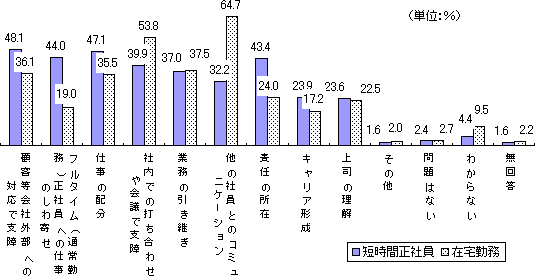
| 多様な働き方をする場合の処遇上の心配点としては、短時間正社員では、「賃金の減少」が75.3%で最も多く、次いで「希望した時にフルタイム正社員になれるかどうか」(52.1%)、「退職金の取り扱い」(50.0%)、「公的年金の取り扱い」(44.9%)が挙げられている。 また、在宅勤務では、「賃金の減少」(55.6%)、「希望した時に通常勤務の正社員になれるか」(41.1%)が挙げられているが、全般的に短時間正社員に比べて心配している点は少なくなっている。 |
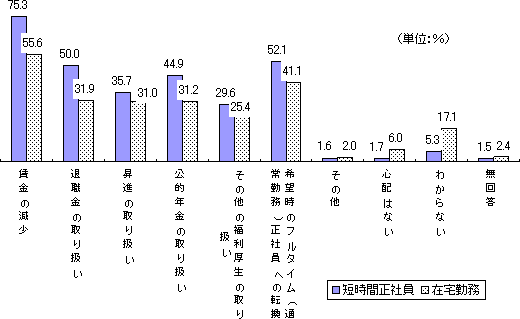
| 回答企業の業種及び企業規模は以下のとおりである。 |
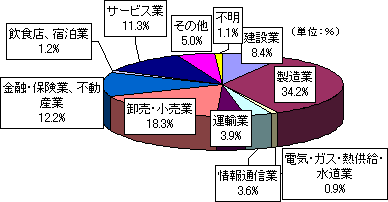
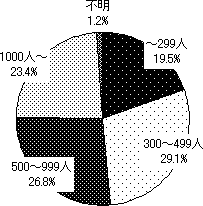
| 多様な働き方の主要な制度の導入状況についてみると、正社員の所定労働時間を一時的に短くする短時間正社員制度(以下「短時間正社員制度(タイプI)」という。)を導入している企業は28.0%、導入を検討中の企業を合わせると約3割となっている。また、所定労働時間をフルタイムの正社員より短く設定する短時間正社員制度(以下「短時間正社員制度(タイプII)」という。)を導入している企業は6.5%であり、導入を検討中の企業を合わせても1割に満たない。 在宅勤務制度は導入企業が2.8%、ジョブシェアリング(一つの仕事を2人で労働時間を分担しつつ行い、評価・処遇も2人がセットで受ける働き方)は、導入企業が1.2%にとどまっている。 |
(単位:%)
|
| (注) 「短時間正社員制度I」:正社員の所定労働時間を一時的に短くする短時間正社員制度。 「短時間正社員制度II」:所定労働時間をフルタイムの正社員より短く設定する短時間正社員制度。 「ジョブシェアリング」:ある仕事を他の誰かと2人で労働時間を分担しつつ行い、評価・処遇も2人セットで受ける働き方。 |
| 短時間正社員制度(タイプI)を導入または導入検討中とする企業における同制度の対象者は、「家庭内に要介護者を持つ正社員」が78.5%、「未就学の子どもを持つ正社員」が77.9%となっており、その他の対象者は1割に満たない。
また、短時間正社員制度(タイプII)を導入または導入検討中とする企業における同制度の対象者は、「未就学の子どもを持つ正社員」(54.4%)、「家庭内に要介護者を持つ正社員」(43.9%)が多いが、「理由を問わず短時間勤務を希望する正社員全員」(17.5%)、「短時間正社員として勤務することを希望する新規採用者」(12.2%)、「短時間正社員への転換を希望するパート等の非正社員」(10.5%)も1割を超えている。 |
(単位:%)
|
| 注) | 「転換を希望する非正社員」「新規採用者」は、短時間正社員制度Iでは選択肢がない。 |
| 制度の導入の有無に関わらず、企業に対し、制度の対象にできる社員群を社員区分と職種の面から聞いたところ、どの社員群においても導入は困難とされているが、短時間正社員制度(タイプII)では、「再雇用等の定年後の高齢者」が最も導入が容易な社員群であり、次いで「定年前の中高年正社員」、「事務職」、「勤務地に限定のある社員」となっている。また最も導入が困難とされているのは、「管理職」であり、次いで「勤務地に限定のない社員」、「販売・営業職」となっている。 在宅勤務制度では、短時間正社員と同様の傾向にあるものの、短時間正社員制度よりも全般に導入が困難とされている。 |
| 短時間正社員制度II | 在宅勤務制度 | |
| 勤務地に限定のない社員 | 1.65 | 1.57 |
| 勤務地に限定のある社員 | 2.08 | 1.89 |
| 管理職 | 1.33 | 1.21 |
| 技術職・研究職 | 1.74 | 1.74 |
| 事務職 | 2.18 | 1.61 |
| 販売・営業職 | 1.67 | 1.49 |
| 生産・現業職 | 1.88 | 1.15 |
| 定年前の中高年正社員 | 2.24 | 1.66 |
| 再雇用等の定年後の高齢者 | 2.98 | 1.84 |
| 注) | 「導入容易度指数」は、「容易」の件数×4点+「やや容易」の件数×3点+「やや困難」の件数×2点+「困難」の件数×1点を(646件−「該当者なし」の件数−「不明」の件数)で除した値。同指数が高いほど、導入が容易であることを示している。 |
| 社員の生活面のニーズからみて多様な働き方を導入することがどの程度必要であるかを聞いたところ、短時間正社員制度(タイプII)、在宅勤務制度ともに、「家庭内に要介護者を持つ社員」、「未就学の子どもを持つ社員」については、必要と考える企業が多くなっている。また、どのような社員群に対しても、短時間正社員制度(タイプII)の方が在宅勤務制度よりも導入が必要と考える企業が多くなっている。 |
(単位:%)
|
| (注) | 導入必要性指数は、「そう思う」の件数×4点+「ややそう思う」の件数×3点+「あまりそう思わない」の件数×2点+「そう思わない」の件数×1点を、(646件−不明の回答件数)で除した値。同指数が高いほど、導入が必要と考えていることを示している。 |
| (1)短時間正社員制度(タイプII) 短時間正社員制度(タイプII)を導入した場合の効果について、「雇用の維持」が54.5%で最も多く、次いで「人件費の削減」(46.9%)、「人材の有効活用」(44.9%) となっている。制度の導入の有無別にみると、導入または導入検討中の企業は、導入予定なしとする企業に比べ、「雇用の維持」、「人材の有効活用」、「社員の定着」、「社員の勤労意欲の向上」を挙げる割合が高く、「人件費の削減」、「仕事の能率の向上」は低くなっている。 |
(MA)(単位:%)
|
| (2)在宅勤務制度 在宅勤務制度を導入した場合の効果について、「人材の有効活用」が44.6%で最も多く、次いで「事務所スペースの節約」(36.1%)、「仕事の能率の向上」(30.7%)となっている。これを制度の導入の有無別にみると、導入または導入検討中の企業は、導入予定なしとする企業に比べ、「人件費の削減」を除く点について、効果を挙げる割合が高く、特に「人材の有効活用」、「仕事の能率の向上」、「社員の勤労意欲の向上」で顕著になっている。 |
(MA)(単位:%)
|
| (1)短時間正社員制度(タイプII) 短時間正社員制度(タイプII)の導入に当たって、仕事の進め方の留意点としては、「フルタイム正社員に仕事のしわ寄せがいかないようにする」(70.0%)、と「顧客等会社外部への対応で支障が生じないようにする」(69.7%)が約7割となっており、「仕事の配分方法をきちんと決めておく」(56.0%)、「業務の引継ぎ」(51.5%)も半数以上の企業が挙げている。制度の導入の有無別にみると、導入または導入検討中の企業は、導入予定なしとする企業に比べ、「配置の柔軟性低下」、「労働時間編成の弾力性低下」、「上司への教育」を挙げる割合が高くなっている。 |
(MA)(単位:%)
|
| (2)在宅勤務制度 在宅勤務制度の導入に当たって、仕事の進め方の留意点としては、「顧客等会社外部への対応で支障が生じないようにする」(65.2%)、「社内での打合せや会議に支障が生じないようにする」(60.1%)が6割を超え、「通常勤務の正社員に仕事のしわ寄せがいかないようにする」(59.8%)がそれに次いでいる。制度の導入の有無別にみると、導入または導入検討中の企業は、導入予定なしとする企業に比べ、「目標の与え方」、「仕事の配分方法」、「配置の柔軟性低下」、「上司への教育」を挙げる割合が高くなっている。 |
(MA)(単位:%)
|
| (1)短時間正社員制度(タイプII) 短時間正社員制度(タイプII)を導入するに当たっての処遇面の留意点としては、「賃金制度」が90.1%で最も多く、次いで「評価制度」(72.1%)、「退職金制度」(52.0%)となっている。制度の導入の有無別にみると、導入または導入検討中の企業は、導入予定なしとする企業に比べ、「人材育成策」、「キャリア管理」を挙げる割合が高くなっている。 |
(MA)(単位:%)
|
| (2)在宅勤務制度 在宅勤務制度導入に当たっての処遇面の留意点としては、「評価制度」が77.6%で最も多く、次いで「賃金制度」が71.8%となっている。制度の導入の有無別にみると、導入または導入検討中の企業は、導入予定なしとする企業に比べ、「評価制度」、「人材育成策」、「キャリア管理」を挙げる割合が高くなっている。 |
(MA)(単位:%)
|
| (1)短時間正社員の時間当たり賃金水準 短時間正社員(タイプII)のフルタイム正社員と比較した時間当たり賃金水準を聞いたところ、「7割程度」が40.2%で最も多く、次いで「8割程度」が27.1%となっている。 |
(単位:%)
|
| (注) | 近接度指数は、「フルタイム正社員と同じ」×5+「9割程度」×4+「8割程度」×3+「7割程度」×2+「6割程度以下」×1を、(100−不明の回答比率)で除した値。指数が高いほど、フルタイム正社員に近い扱いを考えていることを示している。 |
| (2)その他の人事管理上の取扱い a 短時間正社員制度(タイプII) 短時間正社員(タイプII)の人事管理上の取扱いについては、「教育訓練」、「担当する仕事」は、フルタイム正社員と同様に扱い、「転勤」、「昇進」は別に扱うとする傾向がある。制度の導入の有無別にみると、導入または導入検討中の企業は、導入予定なしとする企業に比べ、全般的にフルタイム正社員と同様に扱うとしているが、「残業・休日勤務」は導入予定なしの企業の方が同様に扱うとする傾向がある。 |
| 残業・休日勤務 | 転勤 | 配置転換 | 担当する仕事 | 昇進 | 評価 | 教育訓練 | 合計 (件) |
|
| 全体 | 2.20 | 1.75 | 2.05 | 2.50 | 1.78 | 2.19 | 2.76 | 646 |
| 【該当制度】 | ||||||||
| 導入あるいは検討中 | 2.04 | 1.80 | 2.15 | 2.56 | 1.92 | 2.35 | 2.87 | 215 |
| 導入予定なし | 2.28 | 1.72 | 2.00 | 2.45 | 1.70 | 2.10 | 2.71 | 424 |
| (注) | 近接度指数は、「【A案】フルタイム正社員と同様に扱う」×4+「ややAの案に近い」×3+「ややBの案に近い」×2+「【B案】フルタイム正社員とは別に扱う」×1を、(100−不明の回答比率)で除した値。指数が高いほど、フルタイム正社員に近い扱いを考えていることを示している。 |
| b 在宅勤務制度 在宅勤務制度の人事管理上の取扱いについては、「教育訓練」は通常勤務の正社員と同様に扱い、「転勤」、「残業・休日勤務」、「配置転換」は別に扱うという傾向がみられる。制度の導入の有無別にみると、導入または導入検討中の企業は、導入予定なしとする企業に比べ、いずれの項目についても通常勤務の正社員と同様に扱うとする傾向がみられる。 |
| 残業・休日勤務 | 転勤 | 配置転換 | 担当する仕事 | 昇進 | 賃金 | 評価 | 教育訓練 | 合計 (件) |
|
| 全体 | 1.64 | 1.60 | 1.71 | 2.01 | 1.96 | 2.01 | 2.08 | 2.33 | 646 |
| 【該当制度】 | |||||||||
| 導入あるいは検討中 | 2.27 | 2.00 | 2.17 | 2.44 | 2.46 | 2.56 | 2.54 | 2.65 | 48 |
| 導入予定なし | 1.59 | 1.57 | 1.68 | 1.98 | 1.91 | 1.96 | 2.03 | 2.30 | 592 |
| (注) | 近接度指数は、「【A案】通常勤務の正社員と同様に扱う」×4+「ややAの案に近い」×3+「ややBの案に近い」×2+「【B案】通常勤務の正社員とは別に扱う」×1を、(100−不明の回答比率)で除した値。指数が高いほど、通常勤務正社員に近い扱いを考えていることを示している。 |
| 短時間正社員(タイプII)からフルタイム正社員への転換については、「一定の条件を満たせばできるようにする」が83.9%と最も多く、「自由に転換」や「転換を認めるべきではない」は1割以下となっている。 また、在宅勤務から通常勤務の正社員への転換についても「一定の条件を満たせばできるようにする」が75.7%と最も多いが、「自由に転換」が10.1%と、短時間正社員よりも自由に転換を認めるとする企業の割合が高くなっている。 |
(単位:%)
|
| 個人調査と企業調査では、質問の仕方が異なるので、直接比較することは難しいところであるが、あえて単純に比較してみると、以下のような相違が読みとれる。 |
| ・ | 短時間正社員制度、在宅勤務制度ともに約4割の個人が希望。 |
| ・ | 短時間正社員制度Iを「導入」あるいは「導入検討中」の企業は約3割あるが、他の短時間正社員制度IIや在宅勤務制度では1割にも満たない。 |
| (注) | 短時間正社員I及びIIについては、次のとおり(以下、同様)。 「短時間正社員制度I」:正社員の所定労働時間を一時的に短くする 「短時間正社員制度II」:所定労働時間をフルタイムの正社員より短く設定する |
| 企業のニーズ | 個人のニーズ | |
| 「導入」+「検討中」の比率(%) | 「希望する」+「どちらかと言えば希望する」の比率(%) | |
| 短時間正社員制度I | 30.2 | 37.3 |
| 短時間正社員制度II | 8.8 | |
| 在宅勤務制度 | 7.4 | 38.9 |
| ・ | 「家庭内に要介護者を持つ社員(個人)」、「未就学の子どもを持つ社員(個人)」については、短時間正社員制度と在宅勤務制度が必要であると企業、個人の多くが考えている。 |
| ・ | ボランティア等の社会活動と学習活動のために「多様な働き方」を活用する必要性についての企業と個人間のニーズの違いは大きい。 |
| ・ | 短時間正社員制度と在宅勤務制度を比較すると、全般的にみて、企業と個人間のニーズの違いは短時間正社員制度に比べて在宅勤務制度で大きい。 |
(単位:%)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (注) | (1)の「導入必要性」とは、「そう思う」と「ややそう思う」の合計。 (2)の「希望派」とは、「希望する」と「どちらかと言えば希望する」の合計。 |
| 個人の意識も多様化しているが、特に個人間の意識の違いは性別に強く現れており、以下のような特徴がみられる。 |
| ・ | 男性より女性でニーズが高い。 |
| ・ | 女性の中でも、夫と妻の就業形態の組合せによってニーズの強さが異なり、正社員の夫を持ち現在非正社員として働いている女性が短時間正社員型働き方を強く希望している。 |
| ・ | 男性の中では、夫婦ともに正社員の場合にニーズが強くなっている。 |
| ・ | 「子どもが未就学」、「子どもが小・中学生」、「子どもが高校・大学生」の時期を中心にして、男性より女性のニーズが強い。 |
| ・ | 男性が「子どもが未就学」、「子どもが小・中学生」、「子どもが高校・大学生」の時期に、配偶者(妻)に短時間正社員型働き方を求めるニーズが強い。 |
| 性別 | 年齢 | 世帯所得 | 就業形態 | 職種 | |||||||
| 男 | 女 | 男 | 女 | 正社員(夫)&正社員(妻) | 正社員(夫)&非正社員(妻) | 正社員(夫)&無職(妻) | 男性 | 女性 | |||
| 現在の本人のニーズ | ○ | 30歳代 | 男 | 女 | 販売 | 販売 | |||||
| 本人の 潜在的ニーズ |
子どもが未就学 | ○ | 低 | 低 | 低 | 男 女 | 技術研究 | ||||
| 子どもが小・中学生 | ◎ | 低 | 低 | 低 | 男 | 女 | 技術研究 | ||||
| 子どもが高校・大学生 | ◎ | 低 | 男 | 女 | 事務 | ||||||
| 子どもが自立 | ○ | 高 | 高 | 女 | |||||||
| 介護必要 | 高 | 男 女 | 技術研究 | ||||||||
| 高齢期 | 高 | 女 | |||||||||
| 学習活動 | 女 | ||||||||||
| 社会活動 | 高 | 女 | |||||||||
| 配偶者に対する 潜在的ニーズ |
子どもが未就学 | ◎ | 低 | 女 | 男 | 販売 | 技術研究 | ||||
| 子どもが小・中学生 | ◎ | (男)低 | 女 | 男 | 生産 | ||||||
| 子どもが高校・大学生 | ◎ | (男)低 | 女 | 男 | 販売+事務 | ||||||
| 子どもが自立 | ○ | (男)低 | 男 | 販売+事務 | 事務 | ||||||
| 介護必要 | ○ | 男 | 販売 | 技術研究 | |||||||
| 高齢期 | ○ | (男)低 | 男 | 販売 | 技術研究 | ||||||
| 学習活動 | ○ | 男 | 販売 | ||||||||
| 社会活動 | ○ | 男 | 販売 | ||||||||
| (注)(1) | 「性別」について〜○印は男女を比較したときに、他に比べてニーズが強いことを示している。◎印はその傾向がとくに強い場合である。 |
| (2) | 「年齢」について〜「低(高)」は若年(高年)層ほどニーズが大きいことを示している。 |
| (3) | 「世帯所得」について〜とくにニーズの大きい層を記入してある。「(男)低」は所得の低い世帯の男性でニーズの大きいことを示している。 |
| (4) | 「就業形態」について〜男(女)のなかで、図表中の三つの就業形態のうち特にニーズの強い就業形態に「男」(「女」)と記入してある。 |
| (5) | 「職種」について〜男(女)のなかで、他職種に比べてニーズの強い職種が記入されている。 |
| ・ | 未経験企業(「導入予定なし」とした企業)が経験企業(「導入」または「導入検討中」とした企業)以上に期待している点は、「人件費の削減」であり、それ以外は、おおむね経験企業が肯定的な評価をしている。 |
| ・ | 短時間正社員制度では、経験企業の方が「社員の定着」、「雇用の維持」、「社員の勤労意欲の向上」を挙げる割合が高い。 |
| ・ | 在宅勤務制度では、経験企業の方が「人材の有効活用」、「仕事の能率の向上」、「社員の勤労意欲の向上」を挙げる割合が高い。 |
(1)仕事の進め方の留意点
|
(単位:%)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注) | ○印は経験企業と未経験企業を比較したときに、他に比べて「制度導入の効果」が大きい、あるいは「制度導入の留意点」として重視していることを示している。◎印はその傾向がとくに強い場合である。 |