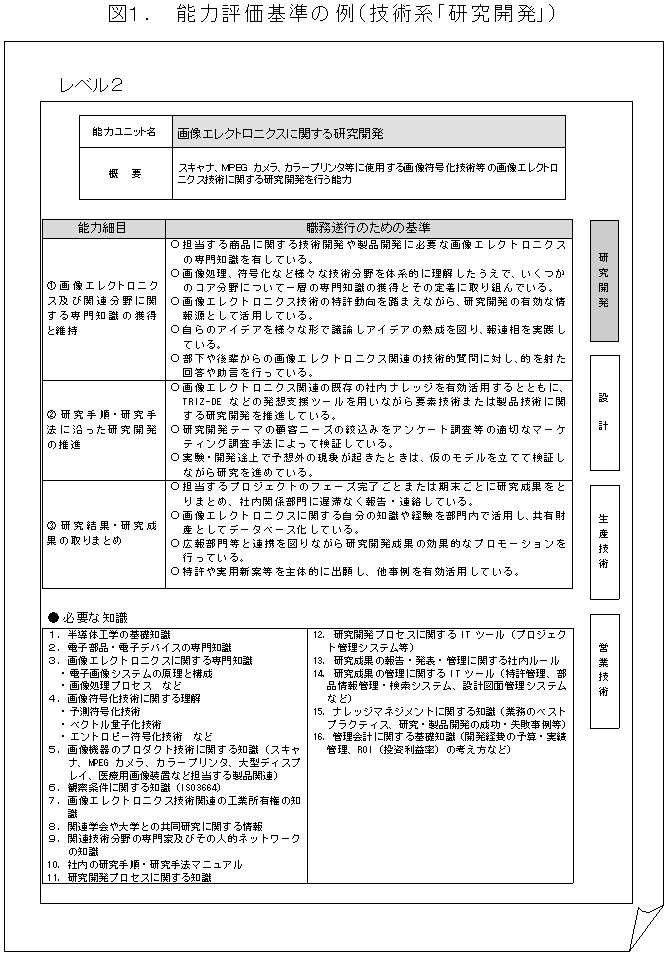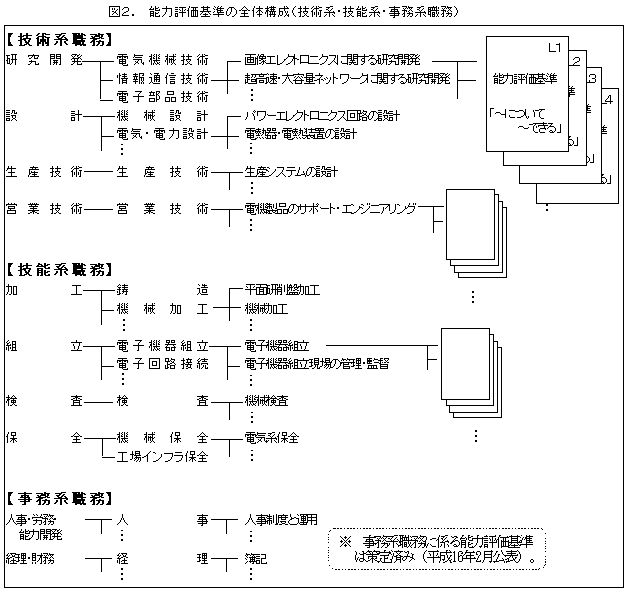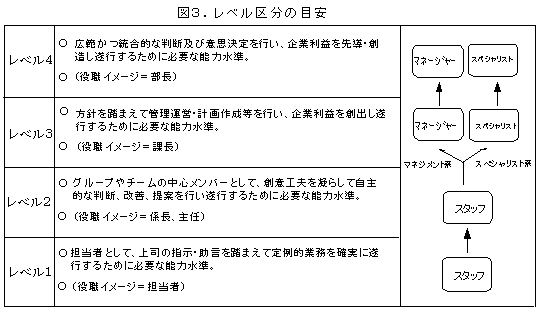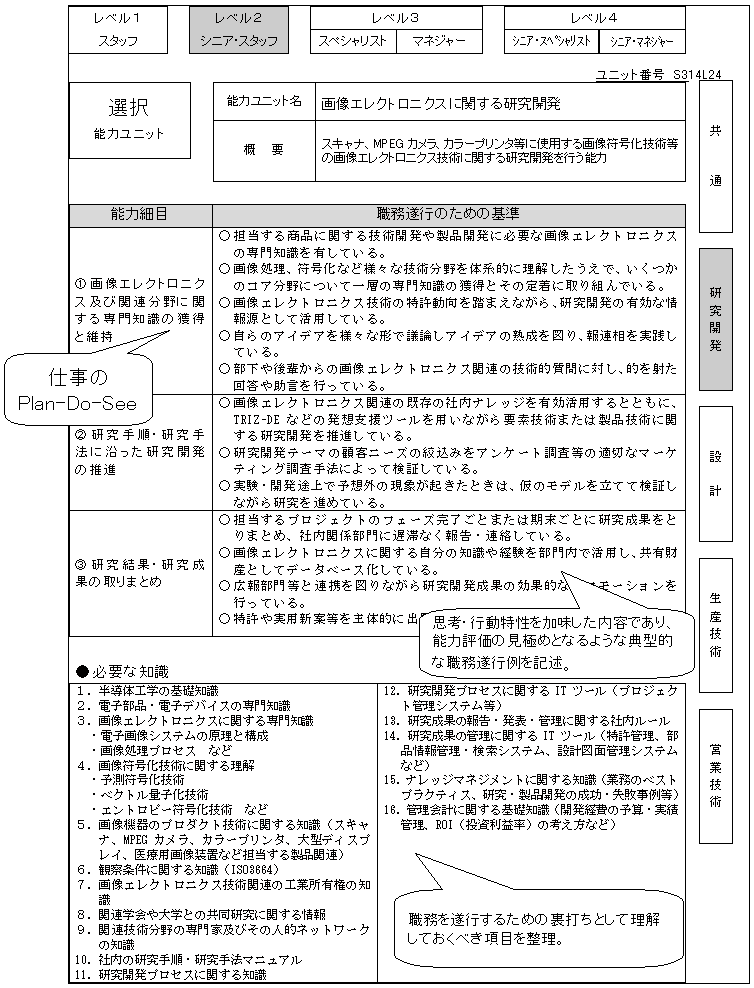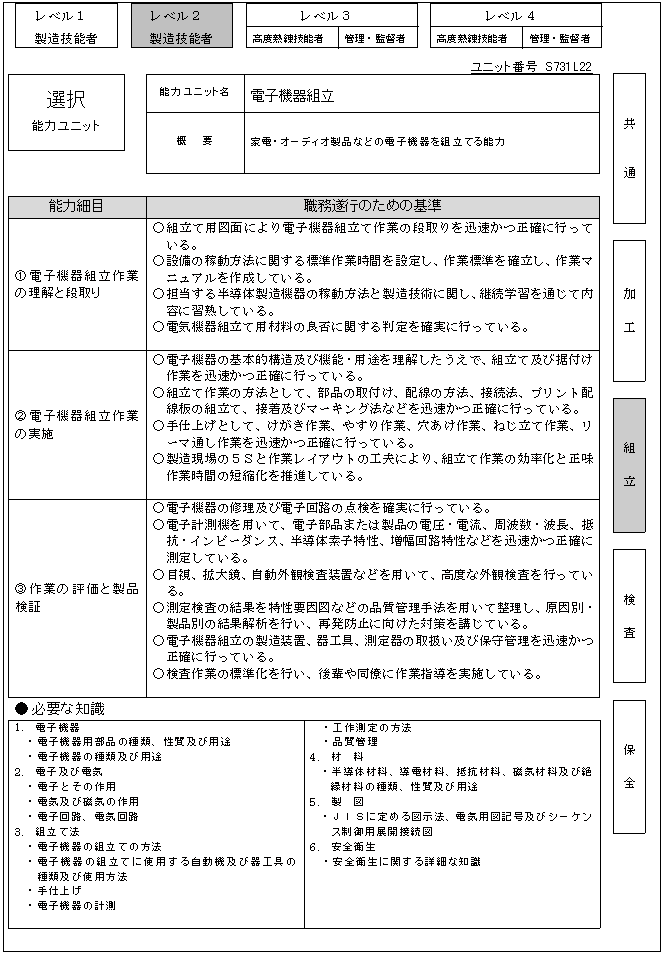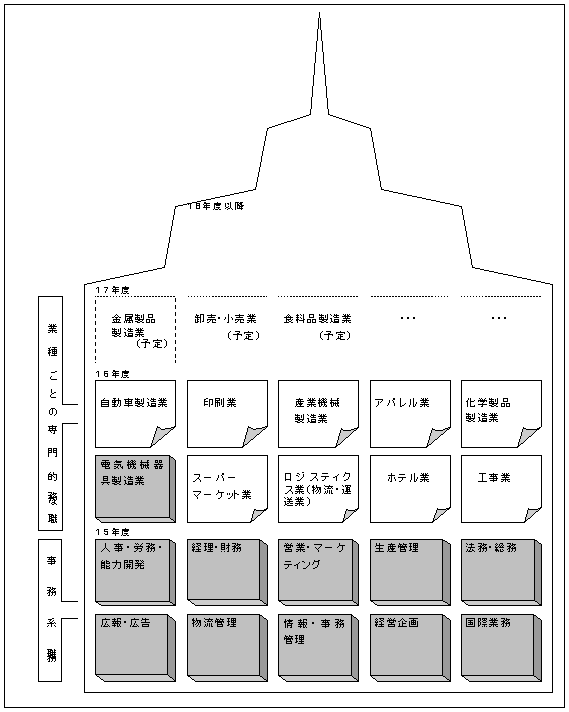| ○ | 現在、厚生労働省では職業能力が適正に評価される社会基盤づくりを進めており、労働者の能力を客観的に評価する仕組みとして、経理・人事等の事務系職務(本年2月26日発表済み)や、製造業にみられる技術・技能系の職務において、仕事をこなすために必要な職業能力や知識を整理・体系化することを目的として、業界団体等との連携のもと能力評価基準の策定に取り組んでいる。 |
| ○ | 今般、業種別の職務として初めて電気機械器具製造業の能力評価基準が完成した。これは当該業種において、技術系は「研究開発」「設計」「生産技術」「営業技術」、技能系は「加工」「組立」「検査」「保全」を取り上げ、それぞれについてスタッフレベル、スペシャリストレベル等4段階にレベル分けを行い、仕事をこなすために必要な職業能力や知識を整理・体系化したものである[図1参照]。 |
| ○ | また、現在、自動車製造業、ホテル業、スーパーマーケット業等幅広い業種において能力評価基準の策定を進めているところである。 |