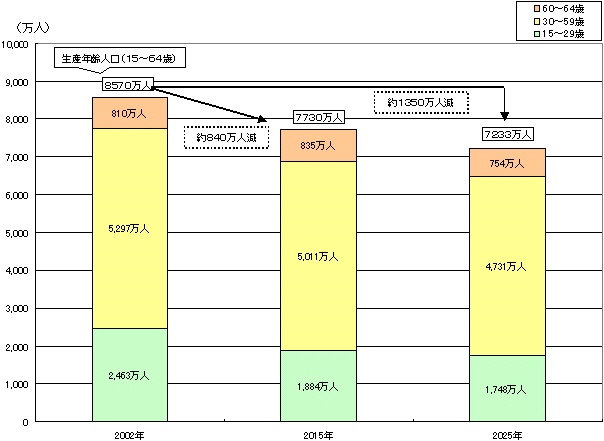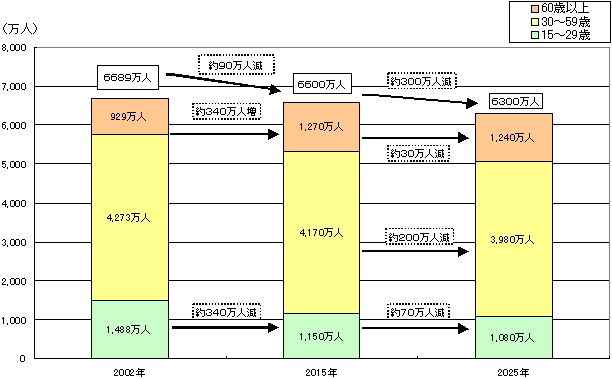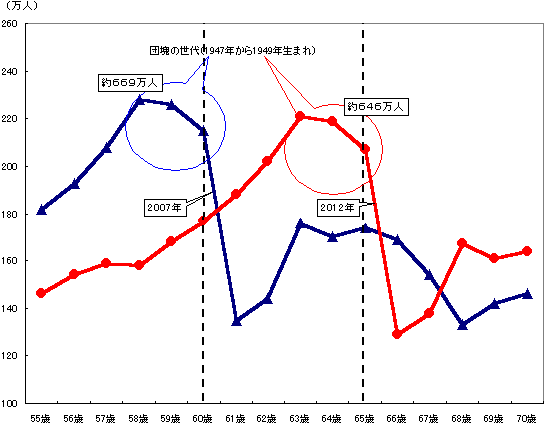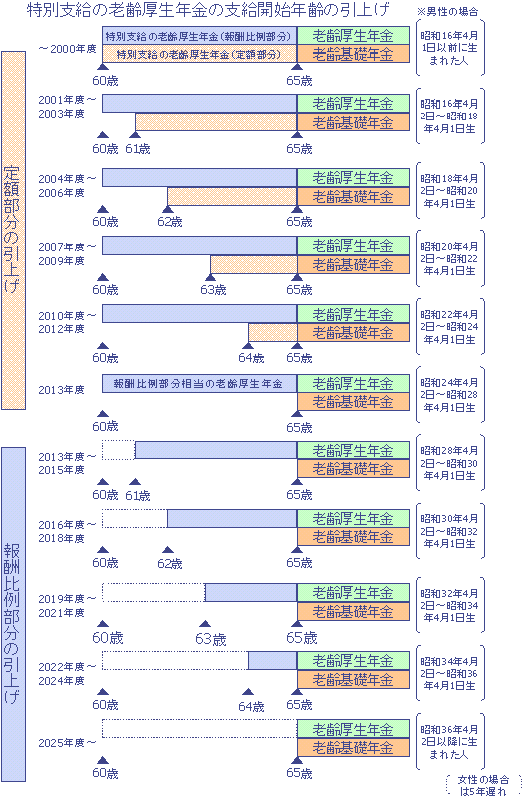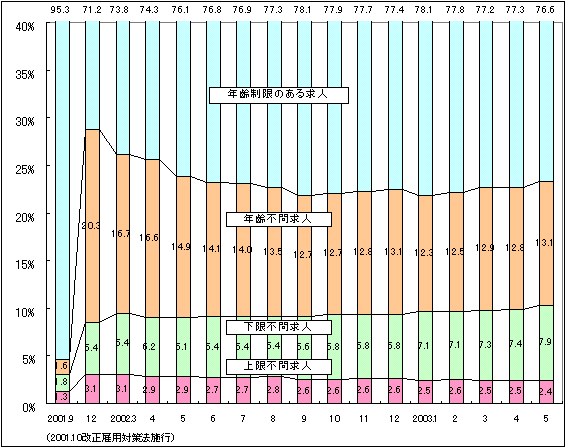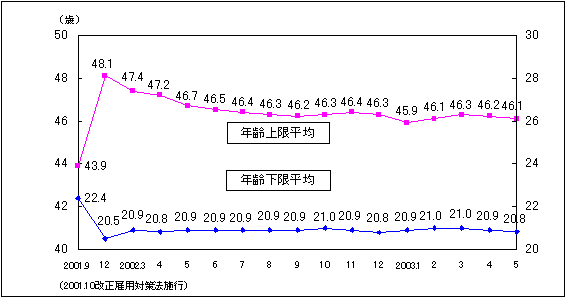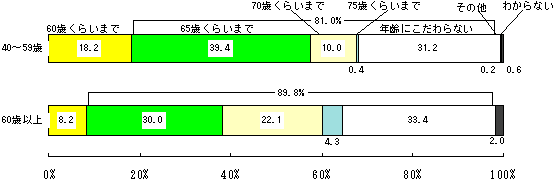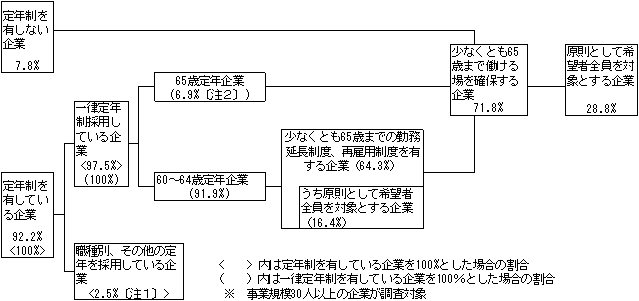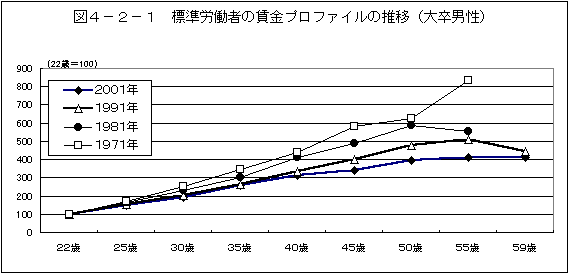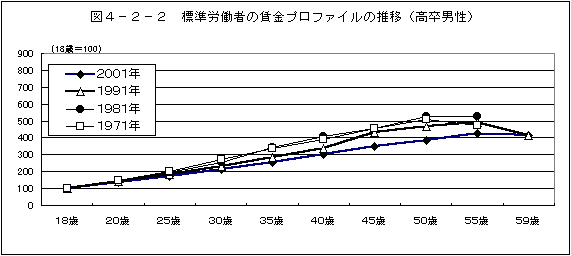| (1) |
再就職援助の必要性と取組の方向
これまで述べたように、まずは各企業において働き続けることのできる制度設計が求められるところであるが、経済社会の構造的な変化等が進む中にあっては、すべての企業が安定した経営を続けることも容易ではなく、その雇用する労働者の雇用維持が困難な局面に遭遇し、年金支給開始年齢前にやむを得ず離職させざるをえないことも十分に想定される。このため、このような場合には、雇用を守れなくなった企業から雇用を増やそうとする企業に、労働者をできる限り失業を経ることなく移動させること、すなわち、労働市場を通じた雇用機会の確保が求められることとなる。
特に中高年齢者の場合は、一旦離職するとその再就職は困難であり、失業期間も長期化するおそれが高いこと、非自発的失業者のうち45から59歳の中高年齢者が54万人とその三分の一以上を占めていることなどを踏まえると、離職を余儀なくされる中高年齢者について、その再就職の促進策を強化する必要があると考えられる。
また、中高年齢者の再就職の際の問題点としては、企業側は年齢を理由に中高年齢者を募集・採用の対象から外してしまう傾向にあること、労働者側は自らの能力を客観的に把握していない傾向にあることなどに、十分留意する必要がある。
このため具体的には、
| (1) |
募集・採用時の年齢制限の是正 |
| (2) |
求職者及び求人者の相互理解の促進 |
| (3) |
事業主都合離職の場合の事業主による再就職援助 |
| (4) |
労働者の能力開発等の支援 |
という点についての取組を行うことが求められる。
|
| (2) |
募集・採用時の年齢制限の是正
募集・採用時の年齢制限は、年齢という個人の意思や能力によっては動かし得ない所与の事実を理由として就職の機会を奪うものであり、求職者と求人者が賃金や労働条件を巡って交渉する労働市場の調整機能を失わせ、市場の効率性を阻害するという問題を生じさせている。また、実態としても45歳以上では失業者が仕事に就けない理由として「求人の年齢と自分の年齢が合わない」が約半数を占めている。このような状況に対応すべく、雇用対策法において年齢制限是正の努力義務が定められ、政府においても3年間で年齢不問求人30%を目指す、との目標を立てて公共職業安定所での指導に取り組んでいるところであるが、年齢不問求人の割合は2003年5月時点で13%程度、年齢制限の上限は平均して45歳程度となっている。したがって、中高年齢者の再就職促進のために、募集・採用時の年齢制限是正への取組をさらに強化することが必要である。
募集・採用時の年齢制限是正の実効性を上げるための方策の一つとしては、現在、雇用対策法において「事業主は、労働者の募集及び採用について、その年齢にかかわりなく均等な機会を与えるよう努めなければならない」旨の努力義務が定められているが、これをさらに進めて事業主の義務とすることにより、募集・採用時の年齢制限を禁止することが考えられる。これについては、法律上禁止したとしても、事業主が真に納得した上でないと実質的に中高年齢者が排除されてしまう可能性があり、形骸化の可能性が大きいこと、年齢に代わる基準がない中で年齢制限を禁止すると、募集・採用の場面で労使ともに混乱を招くおそれがあること等の指摘もある。
もう一つの方策としては、募集・採用時の年齢制限を行おうとしている事業主に対して、その年齢制限が真に必要なものか否か、ひいては、高齢者をその職務に活用できないのか、ということを改めて考えてもらうために、現在よりも踏み込んだ説明義務を課すことが考えられる。これについては、このような義務を課すだけではなく、適切な実効性確保のための措置も併せて講じることによって、不合理な理由による年齢制限や年齢制限自体が減少することが期待される。
募集・採用時の年齢制限是正の強化に直ちに取り組むためにも、これらの方策について議論を深めた上で、早急にいずれかの方策を選択し、実施に移すことが必要である。
なお、いずれの方策をとる場合であっても、募集・採用時の年齢制限是正の実効性を上げるためには、求人者が求める職業能力や職務内容の明確化、採用後の適正な労務管理への理解促進が必要であり、年齢制限を行う企業に対する指導・援助をはじめとするコンサルティング体制の強化などの施策を一体的に講じる必要がある。
|
| (3) |
求職者及び求人者の相互理解の促進
中高年齢者の再就職の際の主な問題点として、企業側としては「応募者にどのような能力や適性があるのか、雇ってみるまでわからなかった」、「本人が言うほど能力がなかった」といった点が、労働者側としては「自分が外部(他企業)でどれくらい価値があるのかわからなかった」、「年齢制限があった」といった点が挙げられている。新卒採用の場合とは違って、中途採用の場合は特定の能力を有していることを前提として採用することが一般的であるため、求人企業にとっては、如何にして求職者の的確な能力評価を行うかが重要となる。また、労働者にとっても、再就職に当たって、その企業にうまくなじむことができるかどうかを判断することは大きな問題である。
したがって、中高年齢者の再就職促進のためには、企業が試行的に労働者を雇用して、その間に労働者の能力、適性を見極め、労働者もその企業の特質を判断するというトライアル雇用制度や、紹介予定派遣制度を積極的に活用し、求職者と求人者が互いに相手を理解し、判断できる時間的猶予を与えることが有効であると考えられる。
また、労働者がどのような能力を有しているのかを明確にするためには、それまで経験した職種、職務内容等について、いわゆるキャリアの棚卸しを的確に行うことが有効であるが、その際、企業、労働者間において、相互に理解可能な形で表現できるように共通言語化を推進すべきである。これは、労働者自身の客観的な自己評価にも資することになると考えられる。
さらに、再就職を望む労働者が自らの能力を客観的に認識したり、自らの適性を把握するために、キャリア・コンサルタントなどによるキャリア・コンサルティング体制の充実等が必要である。トライアル雇用制度や紹介予定派遣制度の活用に当たっても、常用雇用に結び付かなかった場合の原因分析や解決策を指南し、再挑戦を後押しするようなカウンセリングを併せて実施することが効果的であると考えられる。
|
| (4) |
事業主都合離職の場合の事業主による再就職援助
現在事業主には、定年、事業主都合解雇等を理由として離職することとなっている中高年齢者のために、求人の開拓などの再就職援助措置を講じる努力義務を課した上で、必要な場合には公共職業安定所から、個々の離職予定者の再就職援助計画を作成し、当該離職予定者に交付するよう要請することとされている。
この制度は、中高年齢者の早期再就職のためには、労働者の能力や適性を十分に把握している事業主による在職中からの再就職援助が有効であるとの考え方に基づくものであるが、依然として厳しい中高年齢者の雇用失業情勢に鑑み、特に事業主の都合により年金支給開始年齢前に離職を余儀なくされる労働者については、その事業主の取組の実効性を高めることが必要である。このため、(3)で述べたような求職者及び求人者の相互理解の促進に資するようこの計画の内容を充実させることが考えられる。具体的には、特に労働者のキャリアの棚卸しに当たり、単にその労働者の職位や部門だけを記入させるのではなく、例えば、その労働者がこれまでどのような仕事をしてきたのか、どのような成果を上げてきたのかなどを盛り込むようにした上で、事業主による計画の作成・交付の実施をより強力に求めるべきである。
これらの制度の充実強化により、この計画は、
| (1) |
労働者がこれによって自らのキャリアを整理しやすくする機能、 |
| (2) |
事業主がどのような再就職援助措置を行うかを明らかにする機能、 |
| (3) |
労働者や国が、事業主の行う再就職援助措置を踏まえた求職活動、職業紹介等を行うことを可能にする機能、 |
を併せ有するものと位置付けることができ、中高年齢者の早期再就職に有効なものになると考えられる。また、このような制度の充実を図った上での再就職援助の取組を事業主に求めることは、企業内の人材を再評価し、その労働者を真に離職させる必要があるか否かを改めて事業主に考えてもらうことにつながるため、事業主の雇用維持努力の促進にもなると考えられる。
さらに、事業主が労働者に対して行う再就職援助の取組、例えば、労働者が行うキャリアの棚卸しに対する支援、能力開発、求職活動のための休暇付与、再就職支援会社の活用などについての実効性を高めるため、行政としても、事業主に対する必要な相談・援助体制の充実や助成措置の活用促進を図っていくべきである。
|
| (5) |
労働者の能力開発等の支援
離職を余儀なくされた中高年齢者が失業を経ることなく再就職するためには、再就職先の企業において活かすことができる能力を身に付けていることが求められるが、そのための能力開発を中高年になってから始めては遅いと考えられる。労働者がその意欲と能力に応じて年齢にかかわりなく働き続けるためには、労働者自らがその職業生活の早い段階から、その能力を客観的に認識するとともに、自らのキャリア設計を含めた職業生活の設計を行い、それに沿った能力開発を進めることが求められる。
このため、労働者のキャリアや適性に関する理解の促進や行うべき能力開発の選別のためのキャリア・コンサルティング体制の強化、能力開発や長期リフレッシュのための休暇付与等の取組を、特に中高年齢者はこれまで企業による能力開発に依存していたことにも配慮しつつ、労働者自身の自助努力に加え、企業、国もそれぞれの立場から支援していくことが必要である。また、職業生活設計を考慮した人事配置を行い、OJTを活用した能力開発を実施することや、将来の再就職や独立自営準備に資するような当該企業における業務経験以外の幅広いキャリアを身に付けるため、他の企業における仕事を同時に行うことが許容されるようなシステムの整備を行うことも有効であろう。
さらに、とりわけ中高年齢者の求職活動においては、その有する能力や資格をどのように採用された企業の中で活かしていくことができるかということについての提案能力や現実化能力が求められる。そのため、適切なキャリア・コンサルティングを受けられるサポート体制を整備するとともに、職業訓練後の職業紹介により就職に至らなかったケースにおいて、職業紹介機関と職業訓練機関の間でのケース会議等によりその原因を探求し、今後の就職活動に効果的な再訓練を実施する等の取組を行うことも有効であると考える。 |
| ■ |
年功賃金
我が国においては、単に年功的な要素で基本給を決定する方式は高度成長期においても少なく、職務内容や職務遂行能力などを総合的に勘案して決定する方式がとられていたが、実際の運用は年功的になされることも多く、結果として賃金プロファイルが年齢や勤続年数とともに上昇する形状となった。このような結果として右肩上がりとなっている賃金プロファイルを年功賃金という。
|
| ■ |
紹介予定派遣
紹介予定派遣とは、派遣就業終了後に派遣先に職業紹介することを予定してする労働者派遣をいう。
|
| ■ |
キャリアの棚卸し
キャリアの棚卸しとは、労働者自らがどのような職業経歴を有しており、それぞれの経歴においてどのような成果を上げてきたのか、また、どのような自己啓発等を行ってきたのか等を明確にすることをいう。
|
| ■ |
キャリア・コンサルティング、キャリア・コンサルタント
キャリア・コンサルティングとは、労働者が、その適性、職業能力、職業経験等に応じて自ら職業生活設計を行い、これに即した職業選択やキャリア形成を図るために必要となる職業訓練の受講等の職業能力開発を効果的に行うことができるよう、労働者の希望に応じて行う相談をいう。キャリア・コンサルタントとは、以上のような相談を行う者をいう。
|
| ■ |
OJT
OJTとは、On the Job Trainingの略で、従業員を職務につかせたままで行う訓練の形態をいう。
|
| ■ |
短時間正社員
短時間正社員とは、パートタイム労働研究会最終報告によれば、常用フルタイム社員より一週間の所定労働時間は短いが、常用フルタイム社員と同様の役割・責任を担い、同様の能力評価や賃金決定方式の適用を受ける社員のことをいう。
|
| ■ |
多様就業型ワークシェアリング
ワークシェアリングとは、雇用の維持・創出を図ることを目的として労働時間の短縮を行うことをいい、ワークシェアリングを活用して多様な働き方を適切に選択できるようにすることを多様就業型ワークシェアリングという。
|
| ■ |
創業サポートセンター
創業サポートセンターとは、新事業による起業を希望する者をはじめ、新分野への事業進出を考えている事業主などに対して、能力開発や人材養成を中心とした支援を実施し、起業や新分野展開による良好な雇用創出の実現を図ることを目的として設立されたものをいう。「起業・新分野展開支援センター」の愛称。 |