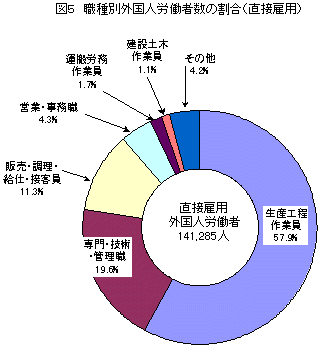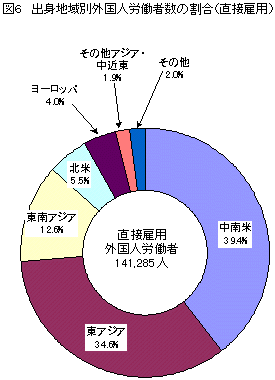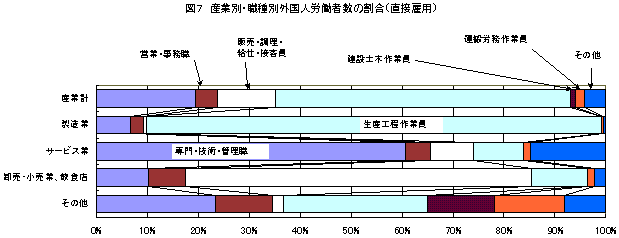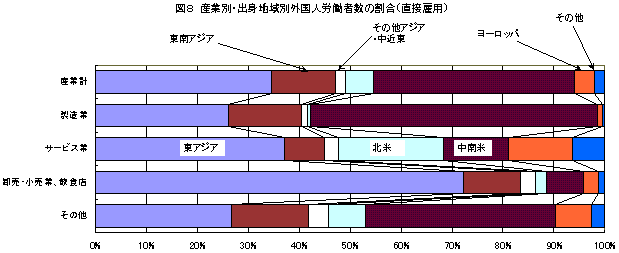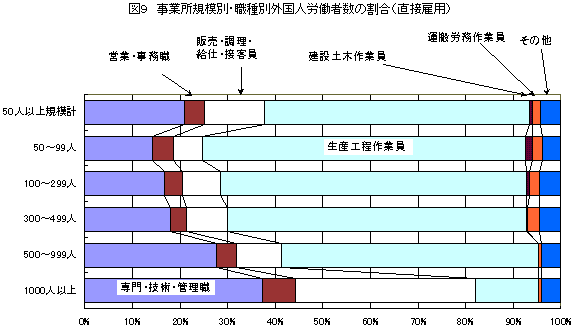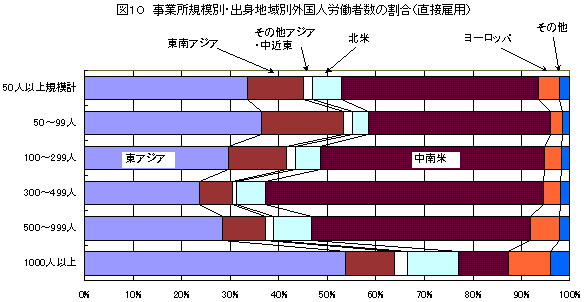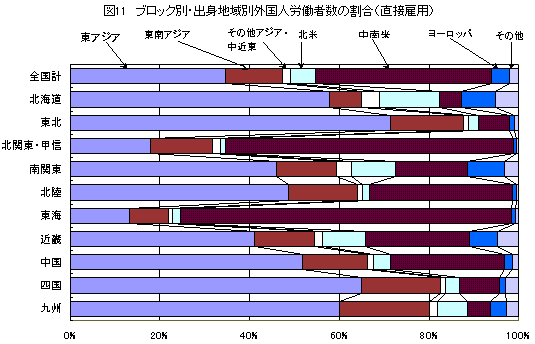外国人労働者を直接雇用しているとして報告を行った事業所は19,197所であり、141,285人の外国人労働者数について報告を受けた。前年の報告結果と比べると事業所数は713所(対前年比 3.9%増)、外国人労働者数は10,845人(同 8.3%増)増加した。
| (イ) | 産業別 産業別では、事業所数、外国人労働者数ともに「製造業」が最も多く9,893所(構成比 51.5%)、82,933人(同 58.7%)、次いで「サービス業」が4,784所(同24.9%)、29,201人(同20.7%)、「卸売・小売業、飲食店」が2,601所(同13.5%)、18,495人(同13.1%)であり、これら上位3分類で全体の約9割を占めた(図1)。
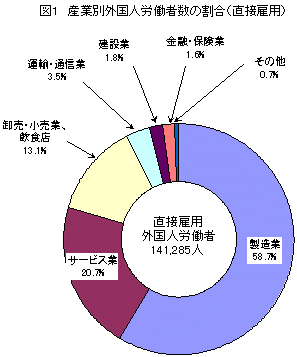
このうち「製造業」についてみると、「輸送用機械器具製造業」〔事業所数1,103所(製造業に占める構成比11.1%)、外国人労働者数20,910人(同25.2%)〕、「食料品、飲料等製造業」〔1,389所(同14.0%)、13,883人(同16.7%)〕、「電気機械器具製造業」〔1,354所(同13.7%)、12,394人(同14.9%)〕などに従事する外国人労働者が多い。
また、「サービス業」についてみると、「教育」 〔事業所数857所 (サービス業に占める構成比17.9%)、外国人労働者数11,059人(同37.9%)〕に従事する外国人労働者が最も多く報告された。 |
| (ロ) | 事業所規模別 事業所規模別では、「100〜299人」規模が事業所数5,406所(構成比 28.2%) 、外国人労働者数43,182人(同 30.6%)、「50〜99人」規模が 4,946所(同 25.8%)、25,202人(同 17.8%) で、これら2分類で事業所数、外国人労働者数ともに約5割を占めた(図2)。
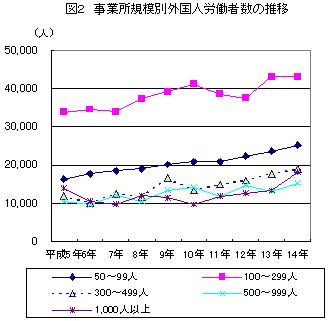 |
| (ハ) | 1事業所当たり外国人労働者数 外国人労働者数を事業所数で除した1事業所当たりの外国人労働者数は7.4人(前年7.1人)であった。 |
間接雇用については、3,972事業所(これには「直接雇用と間接雇用のいずれの形態も有する事業所」と「間接雇用の形態のみを有する事業所」が含まれる。)から間接雇用の形態で外国人労働者が就労しているとの報告を受け、間接雇用の外国人労働者数は86,699人であった。これは前年の報告結果と比べると事業所数は37所(対前年比 0.9%増)とやや増加したが、外国人労働者数では4,668人(同5.1%減)減少した。
延べ外国人労働者数に占める間接雇用の外国人労働者数の割合は、今年は38.0%であり、前年(41.2%)に比べ低下した(図3)。
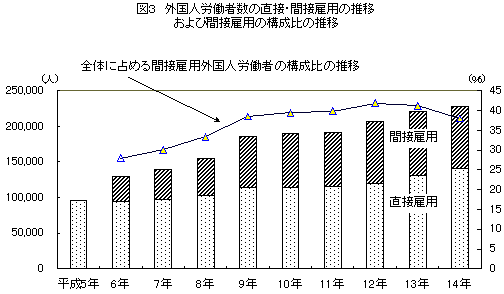
| (イ) | 産業別 産業別では、事業所数、外国人労働者数ともに「製造業」が最も多く(それぞれ3,175所(構成比 79.9%)、80,169人(同92.5%))、大部分を占めている(図4)。
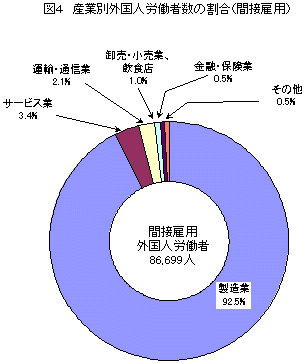
前年の報告結果と比べると、「製造業」において、事業所数は 50所(対前年比 1.6%増)増加したが、外国人労働者数は 4,036人(同 4.8%減)減少した。 |
| (ロ) | 事業所規模別 事業所規模別にみると、「100〜299人」規模が、事業所数1,381所(構成比 34.8%)、外国人労働者数30,733人(同 35.4%)で最も多かった。 |
| (ハ) | 1事業所当たりの外国人労働者数 1事業所当たりの外国人労働者数は、21.8人(前年23.2人)であった。また、50人以上規模の事業所では、25.5人(同27.7人)であった。 |