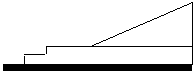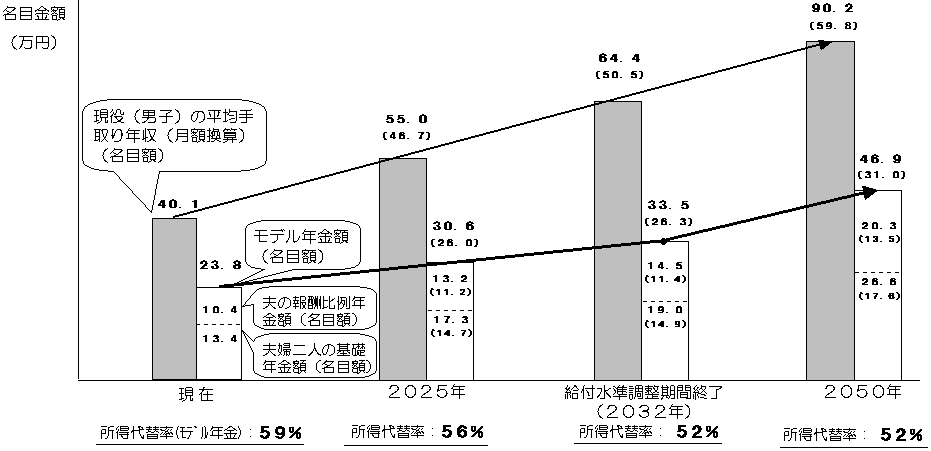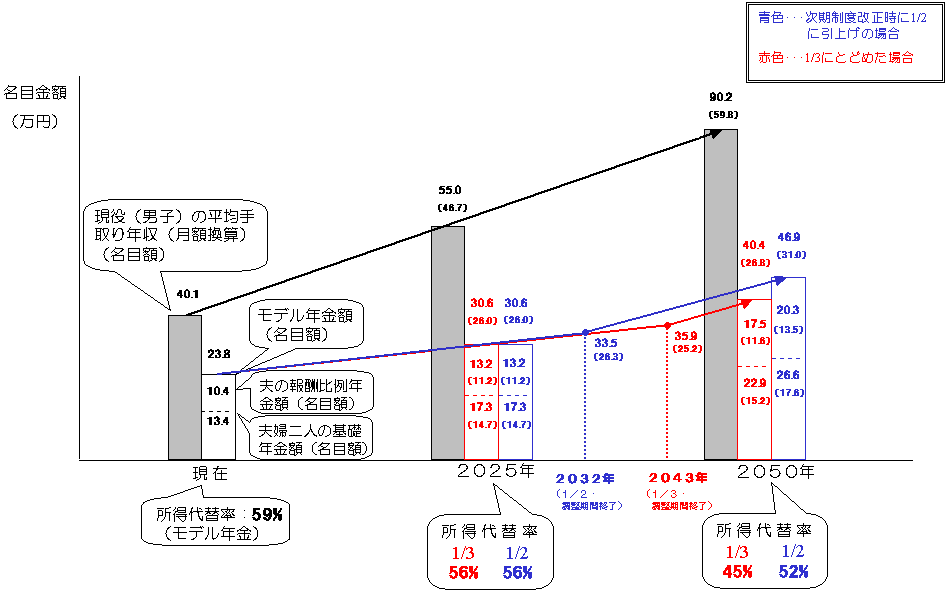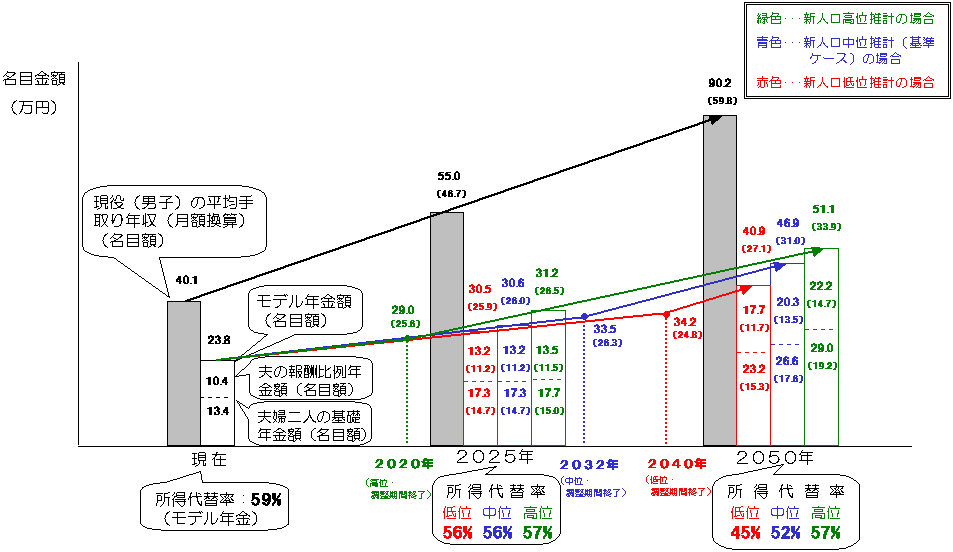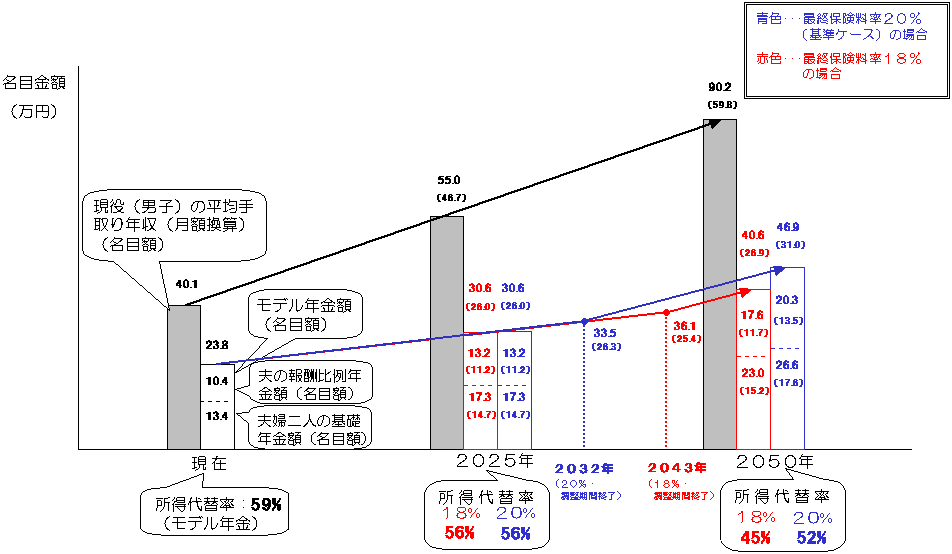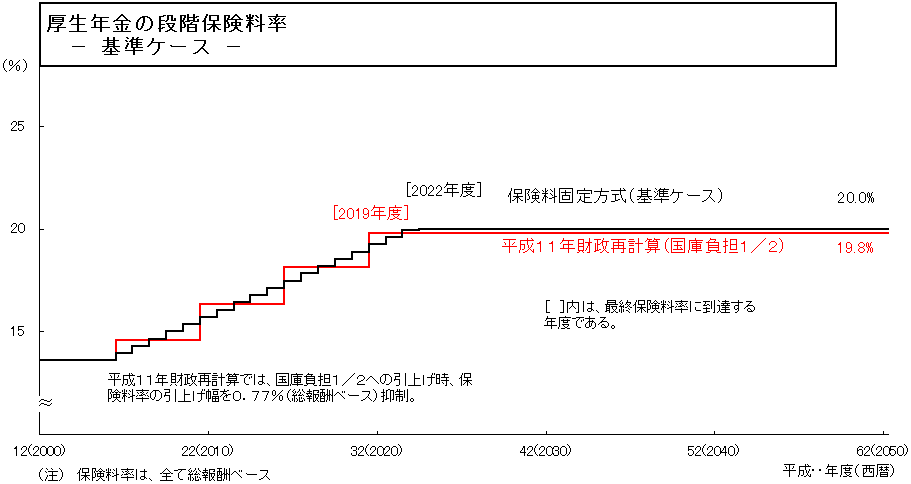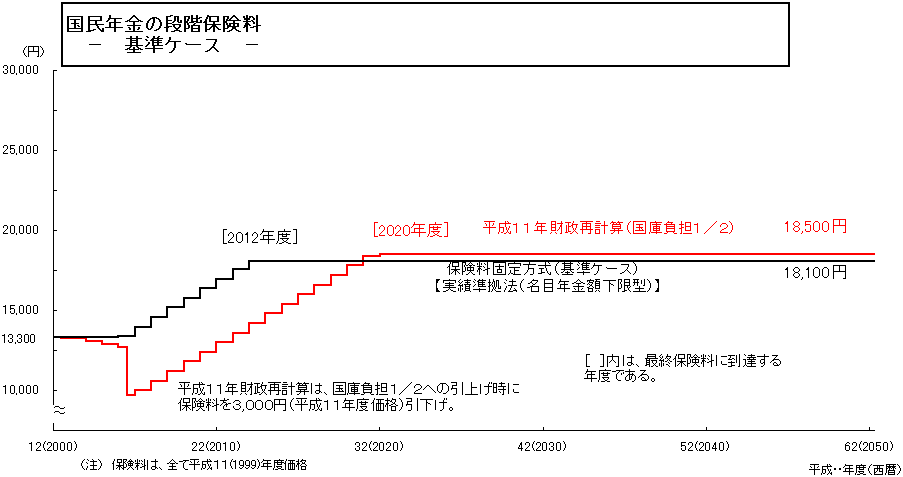戻る
年金改革の骨格に関する方向性と論点(要約)
平成14年12月
厚生労働省
| ○ |
この「年金改革の骨格に関する方向性と論点」は、平成16(2004)年の年金改革に向けて、これまでの各方面の議論を参考にし、厚生労働省において、改革の骨格に関して今後の議論のたたき台としてとりまとめたものである。論点ごとに必要に応じ選択肢を示しながら、今後の幅広い議論の参考として作成したものである。
今後、広く国民的議論が行われることを期待するとともに、そのような議論に基づいた国民的な合意の下で改革を進めていくことを目指すものである。 |
|
1. 平成16年の年金改革の基本的視点
| (1) |
若い世代を中心とした現役世代の年金制度に対する不安感、不信感を解消すること
|
| (2) |
少子化の進行等の社会経済情勢の変動に対し、柔軟に対応でき、かつ恒久的に安定した制度とすること
|
| (3) |
現役世代の保険料負担が過大にならないよう配慮することに重点を置きつつ、給付水準と現役世代の保険料負担をバランスのとれたものとすること
|
| (4) |
現役世代が将来の自らの給付を実感できる分かりやすい制度とすること
|
| (5) |
少子化、女性の社会進出、就業形態の多様化等の社会経済の変化に的確に対応できるものとすること |
|
《特に平成16年の年金改革において取り組むべき課題》
○
前回改正法で規定された、安定した財源を確保して基礎年金国庫負担割合を2分の1に引き上げることは、最終保険料水準を過大にせず、給付も適切な水準を保つため、不可欠。
|
|
| ○ |
少子・高齢化が急速に進行する中で、将来の保険料水準を過度に上昇させないため、保険料引上げ凍結の解除が必要。 |
2.改革の基本的な方向性と論点
(1)年金制度の体系
国民皆年金と社会保険方式を基本とした現行の制度体系
| ○ |
国民皆年金の下、保険料納付が年金給付に結びつく社会保険方式。
|
| ○ |
統一的な定額基礎年金に所得比例年金を上乗せした体系で、所得再分配機能が働く仕組み。
|
| ○ |
制度運営への国の責任の表明として基礎年金に一定の国庫負担。
|
| ○ |
賦課方式を基本に積立金を保有し、運用収入で将来の保険料水準を抑制していく財政方式。 |
|
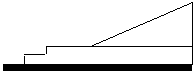 |
|
年金制度の体系に関する各方面での議論
|
《基礎年金を税方式とする体系》
| ○ |
基礎年金について税財源による無拠出制の給付を行う税方式については、未加入・未納問題が存在しなくなる等の利点があるが、現役時代の拠出の有無に関わりない保障が、自律と自助の精神に立脚する我が国の経済社会の在り方に反しないか。
|
| ○ |
その他、巨額の税財源の確保の必要性、所得制限が不可避となること、これまでの保険料納付実績の評価をどうするか等、困難な問題があり、これら論点についての総合的な議論が十分行われる必要がある。 |
|
|
《定額の公的年金とその上乗せの私的年金を組み合わせた体系》
| ○ |
公的年金としては基礎的生活費を賄う水準の定額年金のみとし、上回るニーズには私的年金という考え方もある。
|
| ○ |
定額保障は、公的年金として、現役時代と比べて老後の所得保障の機能が十分でなくなる等の問題があり、十分な議論が必要。 |
|
|
《一本の所得比例年金と補足的給付を組み合わせた体系・・・スウェーデンの例を参考》
| ○ |
近年の就業形態の多様化等を踏まえ、一本の所得比例年金を創設し、低・無所得者については税財源の無拠出制の補足的給付を設ける考え方。
|
| ○ |
所得把握の問題、稼得の態様の違い等により、現時点でこれを直ちに実現することには困難がある。 |
| ○ |
無拠出制補足的給付の導入方法、完全な所得比例年金の評価、生活保護制度との整合性等も十分な議論を進める必要がある。 |
|
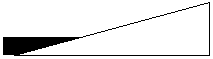 |
|
平成16年の年金改革の方向
| ○ |
社会保険方式に基づく現行の制度体系を基本として改革を進めていく。
|
| ○ |
安定した財源を確保して国庫負担割合の1/2への引上げ、国民年金保険料の多段階免除導入の検討、徹底した保険料収納対策等により長期にわたる安定的な運営の確保を図っていく。
|
| ○ |
制度改革により、長期的に安定した制度とする措置を講じた上で、今後さらに、所得比例構造に基づく一本の社会保険方式による年金制度の導入等を含め、長期的な制度体系の在り方について議論を進めていく。 |
|
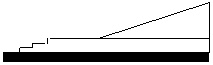 |
|
(2)少子化の進行等の社会経済情勢の変動を踏まえた給付と負担の見直し
|
給付と負担の見直しの基本的な考え方
| ○ |
これまでの方式
(方式I) |
− |
5年ごとの財政再計算の際に、人口推計や将来の経済の見通しの変化等を踏まえて、給付水準や将来の保険料水準を見直す |
|
| |
| ○ |
新しい方式
(方式II) |
− |
最終的な保険料水準を法定し、その範囲内で給付を行うことを基本に、少子化等の社会経済情勢の変動に応じて、給付水準が自動的に調整される仕組みを制度に組み込む(保険料固定方式) |
|
|
| 最終的な保険料水準を固定する考え方を含め、複数の方式による給付と負担の見通しを試算 |
| 方式I |
5年ごとの財政再計算の際に、人口推計や将来の経済の見通しの変化等を踏まえて、給付水準や将来の保険料水準を見直す |
|
|
方式I−1 給付水準維持方式
現行の給付水準を維持し、5年ごとの財政再計算の際に、少子化等の社会経済情勢の変動に対応して、 保険料水準の見直しを行う
|
《試算結果について》
基準ケースでは、現行の給付水準を維持するためには、最終保険料(率)は、厚生年金について23.1%、国民年金について20,500円(平成11年度価格)とすることが必要。
| |
厚生年金の最終保険料率
(総報酬ベース) |
国民年金の最終保険料
(平成11年度価格) |
平成11年財政再計算
(参考)国庫負担割合を1/3にとどめた場合 |
19.8%(100) |
18,500円(100) |
| 21.6%<100> |
25,200円<100> |
| 新人口対応試算(H14.5)(中位推計) |
22.4%(113) |
21,600円(117) |
今回の試算の基準ケース
(参考)国庫負担割合を1/3にとどめた場合 |
23.1%(117) |
20,500円(111) |
| 26.2%<121> |
29,300円<116> |
| 注1 : |
( )及び〈 〉内は、平成11年財政再計算を100とした指数である。 |
| 注2 : |
基準ケースと新人口対応試算が異なるのは、経済前提、国庫負担引上げ時の保険料(率)の取扱い、保険料(率)の引上げ計画が異なるためである。 |
| 注3 : |
現在の保険料(率)は、厚生年金が13.58%(総報酬ベース)、国民年金が月額13,300円。 |
| 注4 : |
国庫負担割合を1/2に引き上げる場合には、基礎年金全体で引上げ分として、平成16年度2.7兆円(平成11年度価格。その後所要財源は増加。)の税財源の確保が必要となる。 |
|
方式I−2 給付と負担の双方見直し方式
将来の保険料水準が過重なものとならないように、5年ごとの財政再計算の際に、少子化等の社会経済 情勢の変動に対応して、保険料水準とともに、現行の給付の内容や水準の見直しを行う
|
この方式の場合には、給付と負担の双方について総合的に検討して設定することとなるが、給付内容の見直しについては、支給開始年齢の見直し、基礎年金水準の見直しや厚生年金の給付乗率の見直し、年金改定率(スライド率)の変更等の方法を組み合わせることが考えられる。
| ○ |
最終的な保険料水準を法定し、その負担の範囲内で給付を行うことを基本に、少子化等の社会経済情勢の変動に応じて、給付が自動的に調整される仕組みを制度に組み込む。年金制度を支える力である社会全体の所得や賃金の変動に応じて、給付水準を自動調整。
|
| ○ |
給付水準の自動調整は、少子化等の社会経済全体(マクロ)の変動の実績(または将来見通し)を、一人当たり賃金や物価の上昇による現行の年金給付の改定方法に反映させることにより、時間をかけて緩やかに実施(マクロ経済スライド)。少子化等の社会経済情勢が好転すれば、給付水準は改善される。
|
| ○ |
マクロ経済スライドは、固定した最終的な保険料水準による負担の範囲内で年金財政が安定する見通しが立つまでの期間中(特例期間中)適用。その後は、現行の年金給付の改定方法に復帰。 |
|
|
現行の年金改定率(スライド率)
≪新規裁定年金の年金改定率≫
| ○ |
厚生年金 |
:賃金再評価
|
| ○ |
基礎年金: |
政策改定 |
≪既裁定年金の年金改定率≫
|
|
→
特例
期間中 |
|
マクロ経済スライド
(実績準拠法(名目年金額下限型))
| ○ |
新規裁定年金(厚生年金・基礎年金)の年金改定率
| = |
被用者の総賃金(手取りベース)の伸び率(実績値) |
| ※ |
厚生年金では、1人当たり賃金上昇率(手取りベース)と総賃金の伸び率(手取りベース)に差がある場合、この差(=スライド調整率。労働力人口の変動率に相当)の分だけ、給付水準が調整される。 |
|
| ○ |
既裁定年金の年金改定率=物価−スライド調整率
|
| ※ |
単年度当たりの年金改定率に下限を設定。 |
┌
|
|
|
|
└ |
新裁、既裁それぞれについて、スライド調整を行うと前年度の名目年金額を下回るときは、年金改定率をゼロとすることとして試算。一人当たり賃金や物価が下落する場合を除き、名目年金額は下げないという考え方。(名目年金額下限型) |
┐
|
|
|
|
┘ |
|
|
|
|
| (参考) |
試算における1人当たり賃金上昇率(手取りベース)と総賃金の伸び率(手取りベース)の差の見通し |
| (平均) |
高位推計 |
中位推計 |
低位推計 |
| 〜2025年度 |
−0.30% |
−0.30% |
−0.31% |
| 2025〜2050年度 |
−0.92% |
−1.18% |
−1.50% |
基準ケース(保険料固定方式)(厚生年金の最終保険料率20%)
−マクロ経済スライド(実績準拠法(名目年金額下限型))でスライド調整する場合 |
| ○ |
実績準拠法では、労働力人口等の減少が本格化する2025年頃から、給付水準の調整度合いが大きくなる。 |
| ○ |
マクロ経済スライドによる給付水準の調整は2032年まで続き、その後は一人当たり賃金や物価の上昇による現行の年金給付の改定方法に復帰する。 |
| ○ |
最終的な給付水準は、モデル年金の所得代替率(現在59%)でみて52%となる。 |
| ○ |
国民年金の最終保険料(平成11年度価格)は、18,100円となる。 |
|
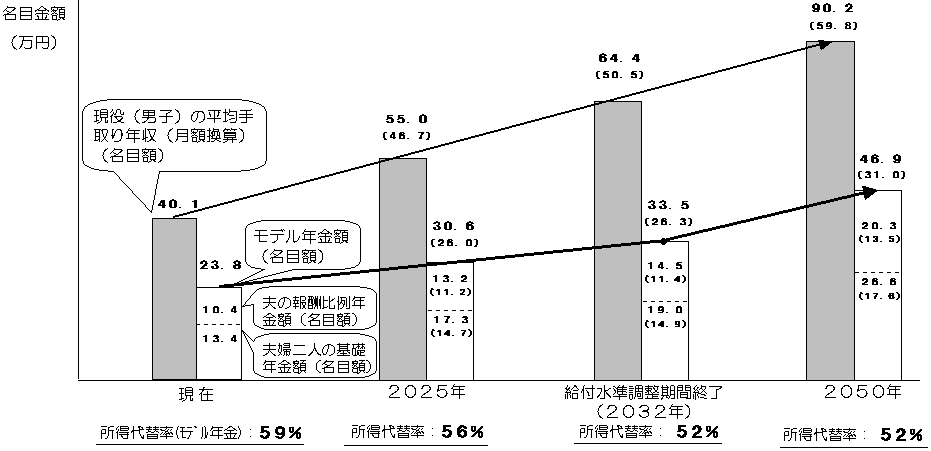
| ※ |
賃金額及び年金額のカッコ内の数値は、物価で現在価値に割り戻したもの。 |
| ※ |
基礎年金国庫負担割合は、次期制度改正時に、安定した財源(平成16年度 2.7兆円(平成11年度価格)その後所要財源は増加。)を確保し、1/2に引き上げて計算している。 |
基礎年金国庫負担割合を1/2に引き上げなかった場合(保険料固定方式)
−マクロ経済スライド(実績準拠法(名目年金額下限型))でスライド調整する場合 |
| ○ |
基礎年金国庫負担割合を1/3にとどめると、基準ケース(1/2)と比べ、給付水準調整期間が長くなる(2032年→2043年)とともに、最終的な給付水準が相当低下する。(モデル年金でみた所得代替率52%→45%)
| ※ |
なお、基礎年金国庫負担割合1/2の場合、1/3にとどめた場合と比べ、最終的な給付水準が高くなることから、給付に要する費用が多くなり、これを賄うために必要となる社会保険料と税を合わせた全体的な負担の水準も高くなることに留意が必要である。 |
|
| ○ |
また、このときの国民年金の最終保険料(平成11年度価格)は、国庫負担割合1/2の場合(18,100円)と比べ5,000円上昇し、23,100円となる。 |
|
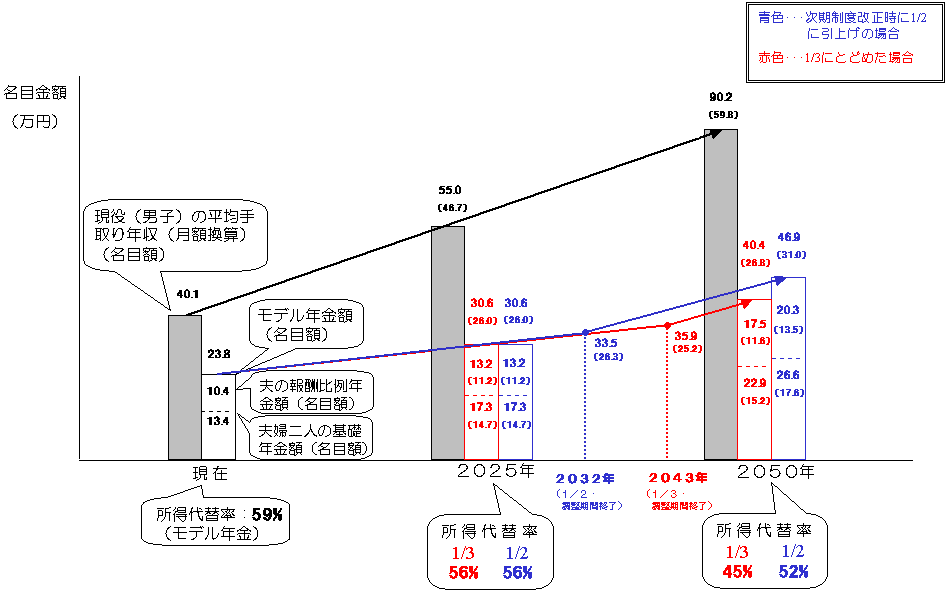
| ※ |
賃金額及び年金額のカッコ内の数値は、物価で現在価値に割り戻したもの。 |
諸前提について異なる仮定を置いた場合 (1)
人口が変動した場合(保険料固定方式) (厚生年金の最終保険料率20%)
−マクロ経済スライド(実績準拠法(名目年金額下限型))でスライド調整する場合 |
| ○ |
少子化の状況が改善する高位推計では、基準ケース(中位推計)と比べ、給付水準調整期間が短くなる(2032年→2020年)とともに、最終的な給付水準が高くなる。(モデル年金でみた所得代替率52%→57%)
|
| ○ |
少子化が一層進行する低位推計では、基準ケース(中位推計)と比べ、給付水準調整期間が長くなる(2032年→2040年)とともに、最終的な給付水準が低くなる。(モデル年金でみた所得代替率52%→45%) |
|
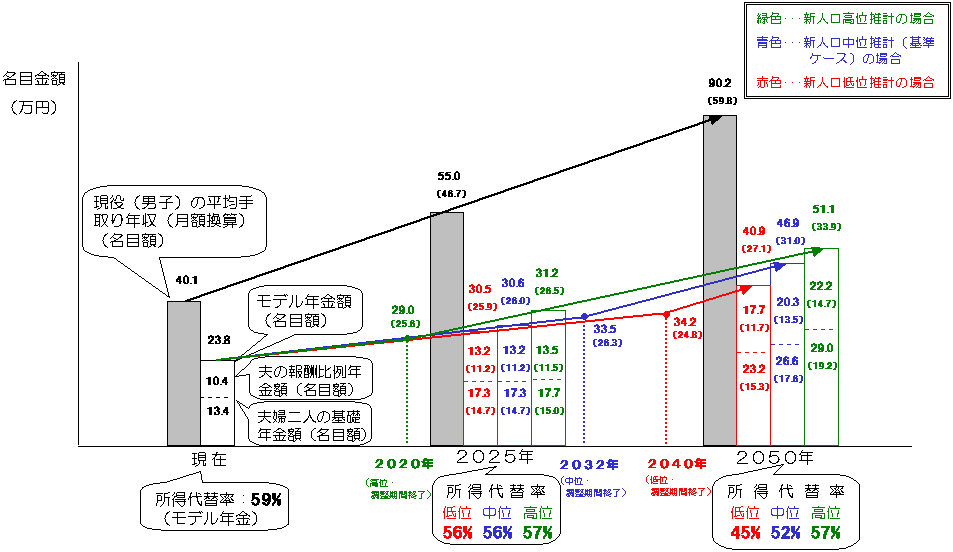
| ※ |
賃金額及び年金額のカッコ内の数値は、物価で現在価値に割り戻したもの。 |
| ※ |
基礎年金国庫負担割合は、次期制度改正時に、安定した財源(平成16年度2.7兆円(平成11年度価格)その後所要財源は増加。)を確保し、1/2に引き上げて計算している。 |
諸前提について異なる仮定を置いた場合 (2)
厚生年金の最終保険料率を18%とした場合(保険料固定方式)
−マクロ経済スライド(実績準拠法(名目年金額下限型))でスライド調整する場合 |
| ○ |
厚生年金の最終保険料率を18%とすると、基準ケース(最終保険料率20%)と比べ、給付水準調整期間が長くなる(2032年→2043年)とともに、最終的な給付水準が低くなる。
(モデル年金でみた所得代替率52%→45%)
|
| ○ |
なお、このときの国民年金の最終保険料(平成11年度価格)は、厚生年金の最終保険料率20%の場合(18,100円)と比べ、基礎年金の給付水準が低くなるため、1,700円低下し、16,400円となる。 |
|
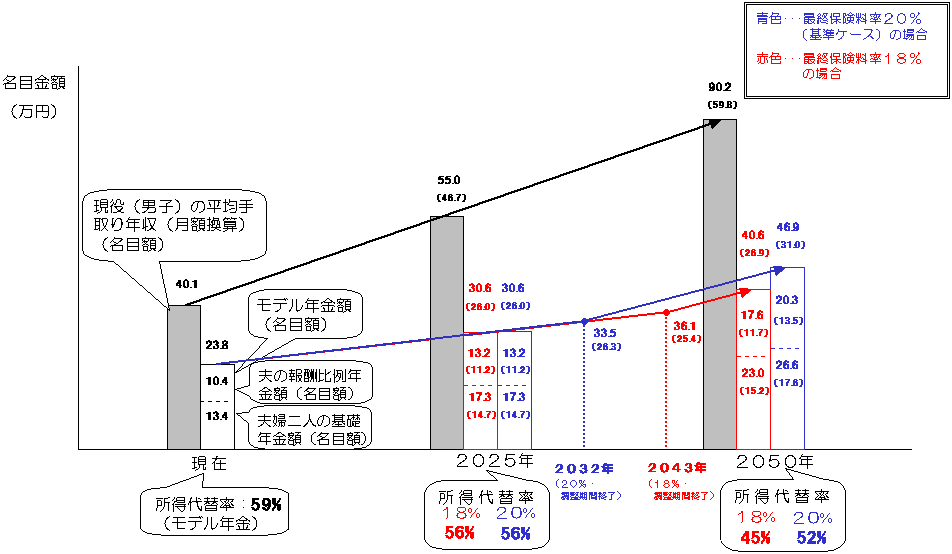
| ※ |
賃金額及び年金額のカッコ内の数値は、物価で現在価値に割り戻したもの。 |
| ※ |
基礎年金国庫負担割合は、次期制度改正時に、安定した財源(平成16年度 2.7兆円(平成11年度価格)その後所要財源は増加。)を確保し、1/2に引き上げて計算している。 |
| 諸前提 |
基準ケース |
| 経済前提 |
平成20(2008)年度以降
| |
実質賃金上昇率1.0%、実質運用利回り1.25%
(名目賃金2.0%、物価1.0%、名目利回り3.25%) |
平成15(2003)〜19(2007)年度
| |
実質賃金上昇率0.5%、実質運用利回り1.25%
(名目賃金0.5%、物価0.0%、名目利回り1.75%) |
|
| 将来推計人口 |
新人口中位推計(平成14年1月)
| |
合計特殊出生率(2050年) 1.39
2050年における平均寿命 男80.95歳、女89.22歳 |
|
| 国庫負担割合の引上げ |
次期制度改正時に、安定した財源を確保し、基礎年金国庫負担を1/2に引上げ |
| 国庫負担割合引上げ時の保険料(率) |
保険料(率)の引上げ幅の抑制や引下げを行わない。 |
| 保険料(率)の引上げ計画 |
毎年度引上げ(最終保険料(率)に到達するまで)
- 厚生年金 毎年0.354%(総報酬ベース)引上げ
| |
(国庫負担割合1/3の場合、総報酬ベースで0.384%) |
平成11年財政再計算と5年間での引上げ幅を同じとする
┌
|
|
|
└ |
平均的な被用者(月収36.7万円(ボーナスは年2回合計で月収3.6ヶ月分)の場合、毎年、保険料率の引上げにより、月650円程度(ボーナス1回分につき1,150円程度)保険料負担(被保険者分)が増加する |
┐
|
|
|
┘ |
国民年金 毎年600円(平成11年度価格)引上げ
| |
(国庫負担割合1/3の場合、平成11年度価格で800円) |
《下図参照》
|
| 厚生年金の最終保険料率 |
20%(保険料固定方式の場合)
《下図参照》
|
| (参考) |
保険料固定方式における基準ケースの保険料(率)の引上げ計画(基礎年金国庫負担割合1/2の場合) |
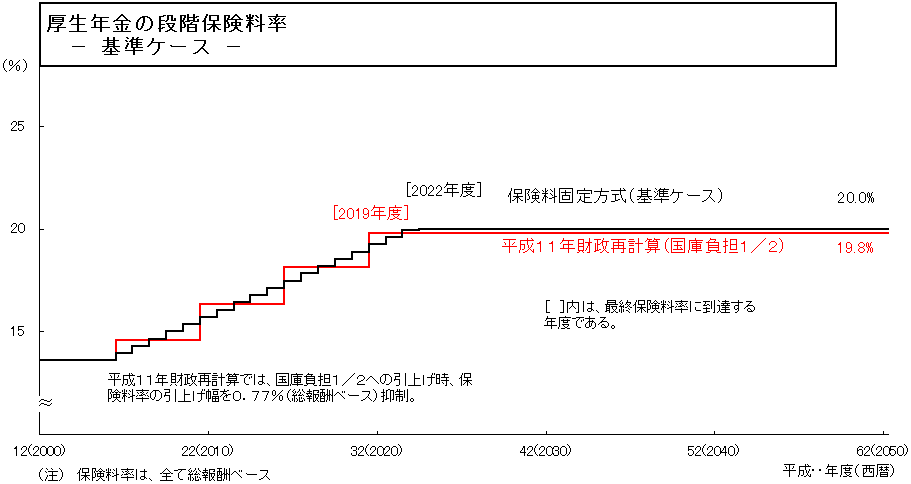
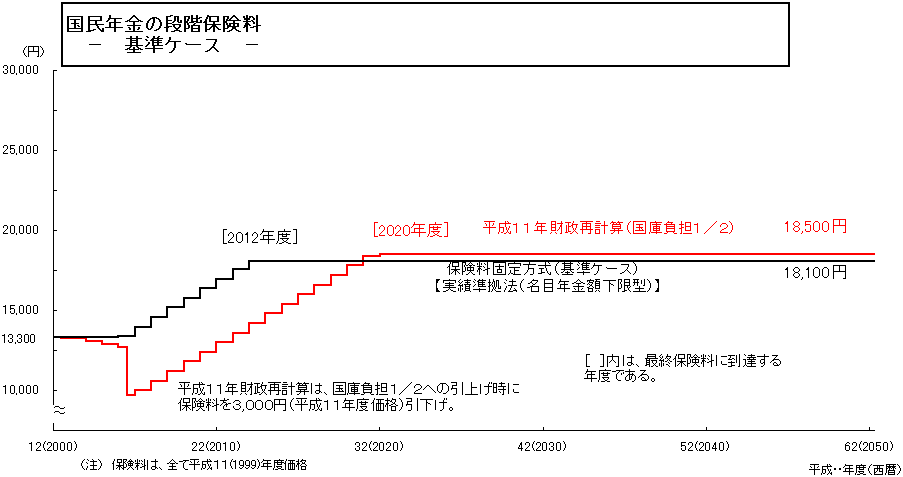
(3)現在受給している年金の取扱い
| ○ |
平成16年の年金改革において、将来世代に対して保険料負担の引上げや給付水準の調整を求めることとする場合、世代間の公平の観点から、現在の年金受給者に対しても、一定の給付水準の調整を求めていくことが必要との意見が多い。
|
| ○ |
この場合、年金受給者の生活の安定を考慮すれば、一人当たり賃金や物価が下落する場合を除き、年金の名目水準を維持しつつ、時間をかけて給付水準の調整を行うことが考えられる。
|
| ○ |
世代間の公平や高齢世代内の公平の視点に立って、公的年金に対する課税(公的年金等控除)を見直すべきではないかという意見が多い。
|
| ○ |
年金課税を見直した場合には、給付水準を調整するのと同様の効果が結果として生じ、現在の既裁定年金受給者を含めて、高額年金受給者や他の所得を有する者にとってより大きな効果が生じ得る。
|
| ○ |
また、これにより得られる財源を、世代間扶養を基本として運営されている年金制度の趣旨にかんがみ、年金制度に還元することが考えられる。 |
(4)企業年金、確定拠出年金等の拡充、育成
| ○ |
高齢期の生活の基本部分を支えるものは公的年金であるが、高齢期の生活は個人によって様々であり、私的年金は、公的年金を補完して多様化した老後生活のニーズに対応する役割を持つ。このような公私それぞれの役割を踏まえ、公的年金を土台として、両者を組み合わせて老後の収入を確保することが適当。
|
| ○ |
また、公的年金の給付の調整が今後図られる場合には、企業年金、確定拠出年金等の一層の拡充、育成が必要。 |
(5)給付と負担の関係が分かりやすい年金制度
| ○ |
現役世代、特に若い世代の年金制度に対する理解と信頼を高めるため、ポイント制を導入する。
|
| ○ |
また、年金ポイント数や将来支給する年金見込額等を、定期的に被保険者に対して情報提供(通知)していく仕組みを導入する。 |
|
| |
| 年金額 |
= 報酬比例年金ポイント
| 毎年のその人の賃金をその年の被用者全体の平均賃金で割って点数化 |
┌
|
|
|
|
└ |
例えば、平均的な給与で1年間保険料を納めた場合を1ポイントとすると、標準的な労働者は、40年間の勤務で累積40ポイントとなる。 |
┐
|
|
|
|
┘ |
|
× 単価(年金現在価値)
| ○ |
40ポイント獲得した場合に標準的な年金額を受給できるように設定 |
| ○ |
単価(年金現在価値)は、賃金等の上昇に応じて改定 |
|
|
|
|
ポイント制の意義
| ○ |
保険料の納付に伴い年金ポイントが増加していくので、自らの拠出実績が確認できるとともに、将来受給する年金権が着実に増加することが実感できる。
|
| ○ |
標準的な年金水準に必要となる年金ポイント数から見て、自らの年金権が現在どの程度の位置にあるかが分かるので、老後の生活設計がしやすい。
|
| ○ |
加入者からみて、年金額の算定式が分かりやすい。 |
|
(6)少子化、女性の社会進出、就業形態の変化に対する対応
○ 公的年金制度における次世代育成支援策
| |
| (1) |
育児期間に対する配慮措置の拡充 |
| (2) |
年金資金を活用した次世代育成支援策の検討 |
|
○ 支え手を増やす取組
| |
| (1) |
多様な働き方への対応−短時間労働者等に対する厚生年金の適用 |
| (2) |
高齢者の就労促進−在職老齢年金制度の見直しなど |
|
○ 女性と年金
| |
第3号被保険者制度については、女性と年金検討会における検討等を踏まえ、以下の4つの案に整理。 |
| |
(1) |
夫婦間の年金権分割案
保険料負担については、従来どおり、第2号被保険者がその報酬額に応じた保険料を納付することとする一方、給付については、世帯賃金が分割されたものとして評価する考え方。
|
|
| (2) |
負担調整案
| 第3号被保険者に関して、何らかの保険料負担を求める考え方。
|
|
| (3) |
給付調整案
第3号被保険者に関して、保険料負担を求めないが、基礎年金給付を減額する考え方。
|
|
| (4) |
第3号被保険者縮小案
短時間労働者等に対する厚生年金の適用等により第3号被保険者の対象者を縮小していく考え方。
|
|
(7)国民年金の徴収強化
国民年金の未加入・未納の問題に対応し、その長期にわたる安定的な運営を確保するため、制度の意義・役割に関する国民一人一人の理解を深める一方、保険料を納付しやすい環境整備、適確な保険料収納のための制度整備を図っていくとともに、その徴収が法令の規定により担保されているという観点から、徹底した保険料収納対策を講じていくことが必要。
(8)公的年金制度の一元化の推進
公的年金制度の一元化については、「被用者年金制度の統一的な枠組みの形成を図るために、厚生年金保険等との財政単位の一元化も含め、更なる財政単位の拡大と費用負担の平準化を図るための方策について、被用者年金制度が成熟化していく21世紀初頭の間に結論が得られるよう検討を急ぐ(平成13年3月16日閣議決定)。」とされているが、給付と負担の見直しに関する新たな議論も踏まえて、さらに検討を進める。
(9)総合的な社会保障の在り方と年金改革
社会保障全体を考えると、年金だけでなく、医療、介護等他の社会保険料負担や税負担があり、これらを含めて全体的な負担の在り方を考えることが必要である。したがって、総合的な社会保障の展望の下で、整合性ある年金改革を進めていくことが必要。
3.今後の議論
今回、「年金改革の骨格に関する方向性と論点」に示した事項を含め、専門的技術的検討が必要な重要事項(年金の財政見通しや資産運用の在り方等)や制度設計上の詳細な事項については、今後、社会保障審議会資金運用分科会や年金部会の議論等も踏まえ、順次議論を進め、適切な結論を得る。
トップへ
戻る