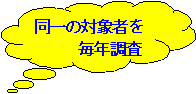 |
| 第1回「国民の生活に関する継続調査」11月20日実施! |
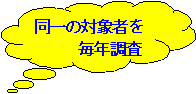 |
| 第1回「国民の生活に関する継続調査」11月20日実施! |
厚生労働省では、20〜34歳の男女及びその配偶者を対象に「第1回21世紀成年者縦断調査―国民の生活に関する継続調査―」を以下の概要のとおり実施します。
調査の概要
| 1 | 調査の目的 この調査は、男女の結婚、出産、就業等の実態及び意識の経年変化の状況を継続的に調査することにより、少子化対策等厚生労働行政施策の企画立案、実施等のための基礎資料を得ることを目的として実施 |
| 2 | 調査の対象及び客体 全国の20〜34歳(平成14年10月末現在)である男女及びその配偶者を対象とし、平成13年国民生活基礎調査の調査地区から無作為抽出した1,700地区内の男女約43,000人 |
| 3 | 調査の実施日 平成14年11月20日(水) |
| 4 | 主な調査事項 家族構成、家計の状況、就業の状況、健康の状況などの基礎的な事実関係と、家庭観、子育て負担感などの意識等 |
| 5 | 調査の方法 あらかじめ調査員が配布した調査票に被調査者が自ら記入・密封し、後日調査員が回収 |
| 6 | 結果の公表 平成15年10月ごろを予定 |
| 照会先 厚生労働省大臣官房統計情報部社会統計課 国民生活基礎調査室調査第4係 03−5253−1111(内線7592) |
| ○ | 縦断調査は、同一調査対象を継続的に調査し、その実態や意識の変化を捉えることにより、同じ集団の行動変化のタイミングや因果関係が明らかになることから、施策効果や行政ニーズの分析が出来るという特質を持っています。 |
| ○ | 当省では、昨年度において、21世紀初年に生まれた赤ちゃんを調査対象に、 児童の健全育成の観点から子どもの育て方等の実態を継続的に調査する「21世紀出生児縦断調査」を実施し、第1回調査結果を10月21日に公表したところです。 |
| ○ | このたび実施する「21世紀成年者縦断調査−国民の生活に関する継続調査−」は、20歳から34歳の男女及びその配偶者の人達を調査対象に、仕事と子育ての両立支援や若者の雇用対策の観点から、主として、就職、結婚、出産、転職などに関する実態や意識及び行動の変化を継続的に調査します。 |
本統計調査の利活用例
(少子化)
| ○ | 少子化の主な要因は未婚・晩婚化といわれているが、未婚・晩婚化は何故起きているのでしょうか。
この調査は、毎年同一対象者に対し継続的に実施するので、例えば、調査初年に「絶対結婚したい」という意識をもった人達が、その後「結婚していない」状態であった場合、その集団について、健康状況、就業状況、家計の状況又は家庭観など意識等が変化する中で、どの要因がどのくらい影響を与えているのかを明らかにすることができます。 |
| ○ | 「日本の将来推計人口」(平成14年1月推計)の中では、「夫婦の出生力の低下」という新しい現象もみられているが、この現象は何故生じてきたのでしょうか。 継続的に調査をしていく中で、例えば、「子どもを持ちたい」という意識を持っていた人達が、結婚し、「子どもがいない」状態であった場合、その集団について就業状況、家計の状況の他、親との同別居や勤務先の雰囲気、更には子育て負担感など意識等が変化する中で、どの要因がどのくらい影響を与えているのかを明らかにすることができます。 |
| ○ | このように、要因やその程度が分かることから、子育て支援等の具体的ニーズの分析が可能となり、また、男性を含めた働き方の見直しの資料としても利活用できます。 |
(若年者の雇用)
| ○ | いわゆるフリーター的な働き方をする若者や働かない若者が増加しているが、その要因に雇用環境だけではなく、就業意識の変化や親との同居なども挙げられています。このような不安定な就労の増加は、経済・社会全般に及ぼす影響が懸念され、少子化を加速させる一因になると考えられています。 |
| ○ | フリーターが200万人を超えたといわれる中(日本労働研究機構推計)で若年層の就業形態はどのような要因によってどの様に変化していくのでしょうか。 この調査では、職業、労働時間、賃金、収入、能力開発の機会、親との同別居及び就業意欲などの意識等を継続的に調査していくので、その動向が分析できることから若年者の雇用対策にも利活用できます。 |
以上に挙げたように、「国民の生活に関する継続調査」は、少子化対策及び雇用対策等厚生労働行政基礎資料として広く利活用されます。