7 検証事項
(1)評価基準
- 福祉サービスの質を評価するための基準として妥当か。
- 他に重要な項目がないか。
- どの施設にも適用できる汎用性のある基準となっているか。
(2)判断基準
- 判断基準の段階(2段階、3段階、複数回答方式等)は妥当か。
- マニュアル等で説明を要する事項はないか。
- 判断基準の内容が妥当か。
- 利用者質問票の項目は妥当か。
(3)評価の方法
- 事前評価(自己評価)を行うことは必要か。
- 訪問調査の進め方に問題はないか。
- 訪問調査の時間配分はどのようにすべきか。
- 所見の記載方法は妥当か。
- 課題等の改善状況を確認するための2次調査は必要か。
8 試行事業結果の取りまとめ
- 11月
別紙1
児童福祉施設第三者評価試行事業の流れ(全施設)
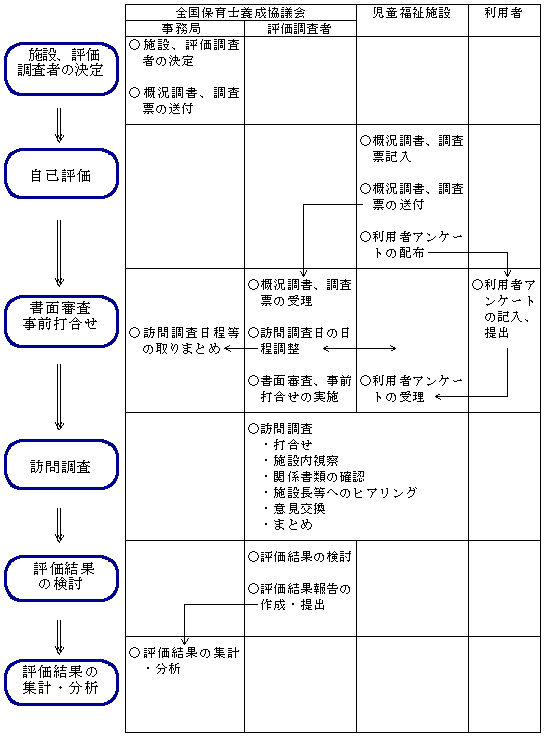
別紙2
児童福祉施設第三者評価試行事業の流れ(児童養護施設等)
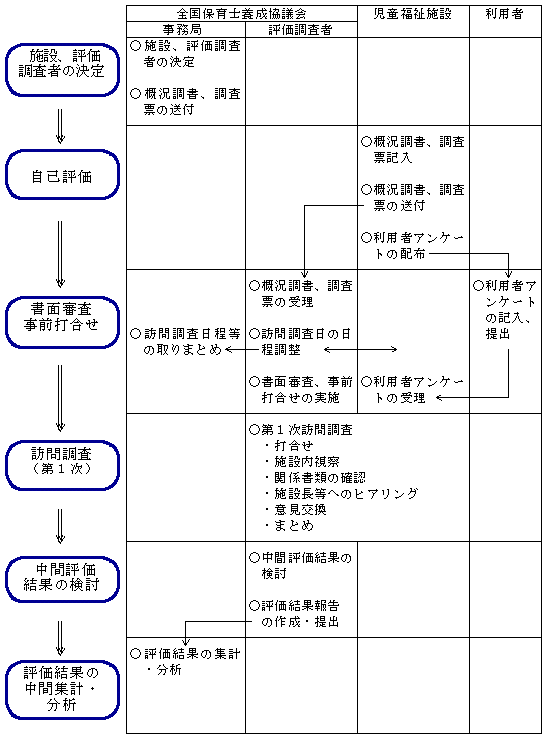
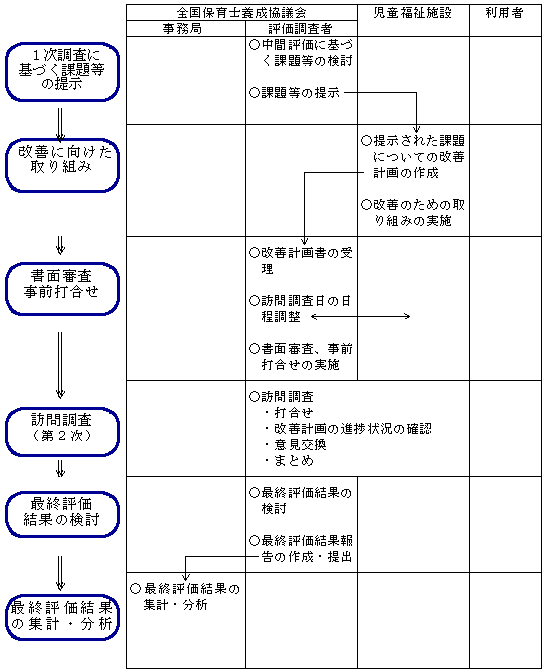
第三者評価試行事業中間集計7「評価基準以外の事項に対する意見」
1 保育所
(1)評価の方法
ア 評価マニュアル
-
○ 開始から終結にいたるプロセスを整理、網羅した手順のマニュアルが必要である。
○ 評価調査者は、自己評価に記載された被調査者の考え方に影響を受けやすいため、客観的な視点で評価を行うためには、マニュアルが有効である。
○ マニュアルには
- 1なぜこの項目が必要か
2その項目を調べるために施設に準備していただくものは何か
3準備されたものをどのように調べるか(着眼点)
4調べた内容から何らかの判断をする際の客観的な基準
5判断しにくい事例についての判断例
を詳細に載せる必要がある。
- 1なぜこの項目が必要か
イ 評価の手順等
- ○ 事前準備資料を決めておく必要があり、
- 1 必ず準備して欲しい資料
2 できれば準備して欲しい資料
3 園の特色がわかる独自の資料
などが考えられる。
○ 実施の前に施設との打合せを行った方がよい。
○ 園長だけではなく、保育士の立場からの自己評価が必要である。
○ 自己評価結果をもとに、評価調査者が事前検討を行う機会を設ける必要がある。
○ ヒアリングの結果、判断基準とは微妙に異なる事例があり、各項目ごとに自由記述欄を設けた方が評価しやすい。
○ 特定の評価調査者の評価に限らず、利用者調査、自己評価、他の団体等の評価など何種類かの評価を受け、その結果により総合的に判断することが望ましい。
○ 総合所見の記述は、「I」と「II・III・IV」の項目数にバラツキがあるため、工夫が必要ではないか。
○ 総合所見は、I〜IVまでの項目にわけずに、全体にわたって記載する方法もあるのでないか。4項目に分けると、重複することが多い。
○ 「キーワード」の趣旨を明らかにされたい。
○ 「特に評価すべき点」の欄には、課題についても記載した方がよいのではないか。
○ 調査後、調査員同士で互いの評価について話し合いをもつ必要がある。
○ 評価結果については、点数のみでなく、報告書と口頭による助言が必要である。
○ どこを改善すべきかなどについて施設へのアドバイスも必要ではないか。
- 1 必ず準備して欲しい資料
ウ 訪問調査の日程
-
○ マニュアルの趣旨を充分に踏まえて評価を行うためには、評価を受ける側も、評価を行う側も1日の評価期間では短すぎる。(複数)
○ 朝の受け入れ場面もみた方がよい。時間配分よりも、みるべき場面をもう少し明確にし、「どこを視るのか」を明らかにする必要がある。
○ 保育内容については、1〜2時間くらいの視察では判断がつかない。また、時間的にも昼食の準備にかかっている時や昼寝から起きた直後では、子どもの様子、遊びの状況把握が難しい。
○ できれば2週間ほど観察した上での評価になればよいと思う。
○ 公立保育園は、書類等の整備はできており、調査にあまり時間も要しないため、評価時間はもっと短くてよい。
○ 食事の時間になってから保育室に行くと、子どもたちの雰囲気をこわしてしまうため、視察の時間を検討する必要を感じた。
(2)評価調査者
-
○ 指定養成施設の教員と保育所長経験者からなるチーム構成とする必要がある。
○ 保育所のことをよくわかっている者が行う必要がある。
○ 少なくても1人は、保育所勤務の経験があり、保育所の実態をよく熟知している者である必要がある。
(3)評価調査者の研修
-
○ マニュアルの内容に基づき、客観的な評価を行うための研修を充実する必要がある。
○ 公平な評価を行うためには、例えば、調査員が何人かのグループで質の高い保育園の調査を行うなどの実習も必要である。
(4)その他
-
○ 第三者評価の趣旨等が現場にあまり知られていないため、実施する際は、趣旨等の理解の徹底が必要である。
○ 評価の料金等を明確にしてもらいたい。
2 乳児院・児童養護施設・母子生活支援施設
(1)利用者の視点
-
○ 保護者に対するアンケートは説明が必要なので時間がかかる。言葉づかいや内容を平易にする必要がある。
(2)評価調査の方法
-
○ 施設自身が行う自己評価を行うためのマニュアルが必要。
○ 資料を送付してもらうなどして事前チェックは必要。
○ 施設として自らサービス点検ができるため自己評価は有意義であり必要。
○ 施設長以外に職員にヒアリングを行うことは啓発ができて有意義。
○ 調査日や時間帯について検討する必要がある。
○ 調査に当たっての施設に対するオリエンテーションが必要。
○ 評価調査者のための評価基準マニュアルが必要。
○ 調査の進め方・尋ね方など手順のマニュアルが必要。
(3)評価調査者
-
○ 少なくとも一人はその施設の運営について精通している評価調査者が必要。
○ 県内の評価調査者の場合評価者と事業者との交流があることが多く、県外の評価調査者が評価を行うべきではないか。
(4)評価調査者の研修
-
○ 評価調査実習が必要ではないか。
○ 客観的な評価を実施するための力量を形成するためには継続的な研修と経験が必要。
検討委員会報告書の柱立て(案)
I 趣旨
II 評価基準について
1 基準作成の考え方
2 基準の構成
(1)保育所
(2)児童養護施設
(3)母子生活支援施設
(4)乳児院
III 利用者の視点について
1 利用者の認識の把握方法
2 利用者アンケート
IV 評価の方法について
1 評価の手順
2 個々の評価基準ごとの評価
3 総合評価
(1)総合所見
(2)段階あるいは点数による総合評価
(3)認定証の交付や格付け
4 評価の決定
(1)評価調査者
(2)評価決定委員会
V 評価結果の公表について
1 公表対象事業者
2 公表する評価結果の範囲
3 評価結果の公表例
4 公表の媒体
VI 評価調査者の研修について
1 研修体系
2 独自研修のプログラム
VII 評価基準、評価の仕組等の見直しについて
今後の検討スケジュール(案)
| 検討委員会 | その他 | |
| 13.6.29 | ○第4回検討委員会
|
|
| 13.7中旬 | ○関係団体からの意見聴取 | |
| 13.7.30 | ○第5回検討委員会
|
|
| 13.8.20 | ○評価基準(試案)の公表 | |
| 13.8.27 〜8.30 |
○評価調査者養成研修試行事業の実施 (全国保育士養成協議会) |
|
| 13.9 〜13.11 |
○第三者評価試行事業の実施 (全国保育士養成協議会) |
|
| 13.12.7 | ○第6回検討委員会
|
|
| 14.1中 | ○第7回検討委員会
|
|
| 14.1下 | ○関係団体からの意見聴取 ○行政関係者からの意見聴取 |
|
| 14.2下 | ○第8回検討委員会
|
|
| 14.3下 | ○第9回検討委員会
|
第三者評価に関する閣議決定事項等
規制改革推進3か年計画
| [ | 平成13年3月30日 閣議決定 |
] |
(4)保育サービスに係る情報提供体制の整備
利用者による保育サービス事業者の的確な選択の促進に資するべく、提供される保育サービスに関する第三者による評価及びこれに係る情報提供の在り方について検討する。
今後の経済財政運営及び経済社会の構造改革に関する基本方針
| [ | 平成13年6月26日 閣議決定 |
] |
医療、介護、保育等のサービス分野での規制改革
医療、介護、保育等サービス給付を内容とする分野においては、そのサービスが効率的、かつ、十分に供給されることが重要である。そのためには、規制改革を進めることが極めて重要である。その際、サービスの質の確保に関するルールを設け、十分なチェックを行っていくことが必要である。
(いわば、「入口の規制ではなく事後の規制」)
仕事と子育ての両立支援策の方針について
| [ | 平成13年7月6日 閣議決定 |
] |
保育に関する情報の提供
保育に関する各自治体の好事例について広く情報提供する。
i−子育てネット等を活用し、提供される保育サービスに関する内容・第三者評価や各種子育て支援情報をユーザーの立場に立った、わかりやすい形で情報提供する
「改革工程表」
| [ | 平成13年9月21日 経済財政諮問会議了承 |
] |
(1)平成14年3月までに措置
(子育て支援)
○保育に関する情報提供強化、保育サービスの第三者評価の推進を行う。
改革先行プログラム
| [ | 平成13年10月26日 経済対策閣僚会議決定 |
] |
ロ 福祉・保育等
介護・保育サービスの量的拡大・質的向上を早急に進めていくために、民間企業を含む多様な経営主体の市場参入の促進、社会福祉法人に関する改革等を図り、消費者の多様な選択肢を拡大する。
- 保育サービスの多様化の促進(分園の設置促進、第三者評価に関するガイドラインの策定等)
オーストラリアのQuality Improvement and Accreditation Systemsについて
(保育向上認定制度について)
1994年1月に発表・開始された制度で、公的な保育助成を受けるためには、保育所はThe National Child Care Accreditation Council(全国保育認定協会)に登録し、認定を受けなくてはならない。
今般、次の通り認定項目が改定され、52項目から35項目にスリム化された。
PartA:交流とコミュニケーション
1:子どもたちとの関係
-
1.1: 職員は、楽しく、人を惹きつけるような雰囲気をつくり、子どもとはあたたかく、親密な態度で接している。 1.2: 職員は、子どもの良い点を伸ばしている。
2:子どもたちの尊重
-
2.1: 職員は、率先して子どもとのコミュニケーションを図るとともに、コミュニケーションにおいては、相手への配慮を欠かすことなく、また、平等意識を高めている。 2.2: 職員は、子どもの異なった能力や社会的・文化的背景を尊重し、個々のニーズに配慮している。 2.3: 職員は、子どもを平等に扱う。 2.4: 食事時間は、楽しく、修養として適切な場であり、社会訓練と積極的な交流のための場としている。
3:家族とのパートナーシップ
-
3.1: 職員と家族は、効果的な会話や文書の交換により、個々の子どもや施設についての情報を交換する。 3.2: 家族が保育所に係る計画策定や運営に参加するよう奨励している。 3.3: 新入の子どもや家族を対象とするオリエンテーション・プログラムがある。
4:職員間の交流
- 4.1: 職員は相互に効果的な意思疎通を図り、チームとして機能している。
PartB:「保育の内容(program)」
5:計画と評価
-
5.1: 「保育の内容」は、施設の基本的考え方や関連する基本的な目標を反映したものとなっている。 5.2: 子どもの学習や健康に係る記録が保管され、個々の子どもに適した「保育の内容」を策定するために使われている。 5.3: 「保育の内容」は、子どもの学習意欲を高めるための手助けとなるよう、子どものニーズや興味、能力に対応している。 5.4: 「保育の内容」は、定期的に評価されている。
6:学習と発育
-
6.1: 「保育の内容」は、子どもが自ら選択をし、新たに挑戦することを奨励したものとなっている。 6.2: 「保育の内容」は、子どもの身体的な発育を促進している。 6.3: 「保育の内容」は、子どもたちの言語や読書き能力の向上を促進している。 6.4: 「保育の内容」は、個人としての発育を促すとともに、対人関係の発育を促している。(foster personal and intrpersnal development) 6.5: 「保育の内容」は、好奇心や論理的な問題意識、数学的な思考を促進している。 6.6: 「保育の内容」は、運動や音楽、視覚的―空間的表現形態を使って、想像力と美的感覚の涵養を促進している。
PartC:子どもの保護、健康と安全
7:保護が必要となる際の対応
-
7.1: 子どもの保護や健康、安全に関する方針や対応を明文化している。かつ、職員は、子どもの健康や安全をモニターし、それを保護するよう行動している。 7.2: 職員は常時、子どもから目を離していない。 7.3: トイレやおむつ交換は、子どもたちが身をもって学ぶようにしてあり、子どもの個々のニーズに対応している。 7.4: 職員は、子どもたちが屋内外の遊びにそれぞれ適した服装を身に付け、また、休憩/昼寝の時間や着替えにあたって、子どもたちが自立的に行うよう働きかけるとともに、子どもの安全や休養、快適さを保つようにしている。
8:健康
-
8.1: 食べ物と飲み物は栄養豊かで、宗教的・文化的にも適切であり、健康的な食習慣を促進している。 8.2: 職員は、効果的で最新の食物管理の基準を満たすとともに、衛生上行うべきことを実行している。 8.3: 職員は、子どもに対し簡単な衛生上の決まりを守るよう教えている。 8.4: 感染症の広まりをコントロールし、予防注射の記録を保管している。
9:安全
-
9.1: 建物と設備は、安全である。 9.2: 危険性のある製品や植物、置物には、子どもを近づかせないようにしている。 9.3: 施設は、職員の健康と安全を促進している。
PartD:管理
10:質を保つための管理
-
10.1: 管理者は、家族と職員から意見を聞いている、また、施設管理に係る文書については、家族も職員も容易に手に入れることができる。 10.2: 人事にあたっての方針と実践は、子どもの保育の継続性を促進するものとなっている。 10.3: 管理者は、新入職員に対し、施設の基本的考え方や目標、方針に焦点をあてた研修プログラムを提供している。 10.4: 管理者は、職員に対し定期的かつ専門的な資質向上の機会を提供し、促進している。
トップへ
報道発表資料 トピックス 厚生労働省ホームページ