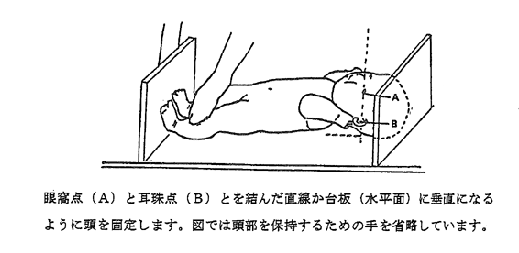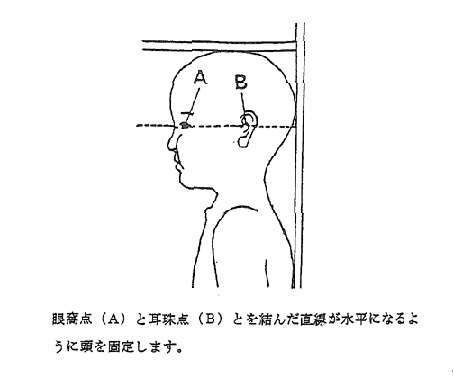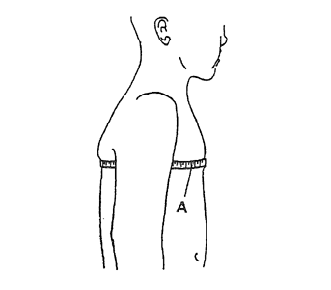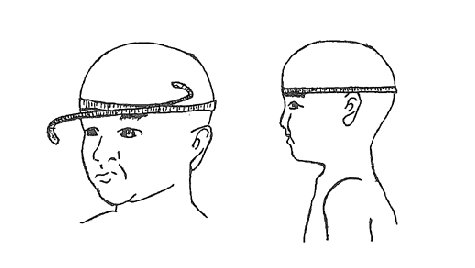ア 2歳未満の乳幼児の場合
-
(ア) 全裸にした児を仰向けにして身長計の台板上にねかせる。
(イ) 補助者は児の頭頂点を固定板につけ、耳眼面(耳珠点と眼窩点とがつくる平面)が台板と垂直になるように頭部を保持する(図1参照)。
(ウ) 計測者は乳児の片側に立ち、乳児の頭に近い方の手で乳児の両膝をかるく台板におさえて下肢を伸展させる(図1参照)。
(エ) もう一方の手で移動板をすべらせて乳児の足のうらにあて、足のうらが台板と垂直な平面をなすようにする。
(オ) 1mm単位まで計測する。
図1 仰臥位身長の計測