| 報道発表資料 | HOME |
1 はじめに
3 基本的な考え方
ア 医療事故と医療過誤
イ インシデントとは
ウ エラーとは
エ 誤認とは
(2) 事故防止策の基本的な考え方
ア エラーと医療事故の関係
イ エラーレジスタントとエラートレラントのアプローチ
ウ リスクマネジメントとは
エ リスクマネジメントの構築
(イ) 職種別の取り組み
[医療施設の管理者の取り組み]
[医師の取り組み]
[看護婦の取り組み]
(ウ) コミュニケーションの重要性
[医療チームにおけるコミュニケーション]
[患者−医療従事者間のコミュニケーション]
(1) 具体的な事故防止方策の検討の前に
(2) 個別的な誤認事故防止方策
ア 術前訪問の際の方策
イ 患者を移送する際の方策
(イ) 患者を移送する際の主治医の対応
(イ) 患者識別バンドの装着
(ウ) 患者の身体への氏名記載
(エ) その他の患者を識別するための方策
(イ) 患者受け渡しの際の患者の氏名確認
(ウ) その他の患者受け渡しの際の方策
(3) 組織としての医療事故防止方策
ア 事故・インシデントの情報収集
イ 事故・インシデントの報告の内容及び分析の実施
ウ 事故防止のための委員会
エ 事故防止のためのマニュアル
オ 事故防止のための職員研修
カ 診療における責任の明確化
(1) 全医療施設で励行すべき基本的な事項
(2) 取り組み方策の例
ア 個別的な取り組み方策の例
イ 組織的な取り組み方策の例
(1) 啓発・普及
(2) 医療従事者の卒前教育及び研修活動の充実
(3) 医療事故防止のための研究の推進
(4) その他の医療事故等への対応
7 参考文献
参考資料1 横浜市立大学病院の事故の概要
参考資料2 海外の医療分野での取り組み(米国の例)
参考資料3 医療分野以外での事故防止の取り組み(航空業界の例)
参考資料4 横浜市立大学病院の事故再発防止策
参考資料5 事故・インシデント分析例
(五十音順)
| (氏 名) | (所 属) | |
| 石 原 哲 | 全日本病院協会常任理事 | |
| 井 部 俊 子 | 日本看護協会副会長 | |
| 大 島 博 幸 | 東京医科歯科大学医学部泌尿器科学教授 | |
| 柿 田 章 | 北里大学病院院長 | |
| 川 村 治 子 | 杏林大学保健学部保健学科教授 | |
| 菊 地 登喜子 | 宮城大学看護部教授 | |
| (座長) | 菊 池 晴 彦 | 国立循環器病センター総長 |
| 花 岡 一 雄 | 東京大学医学部麻酔科学教授 | |
| 北 條 慶 一 | 日本病院会常任理事 | |
| 松 田 暉 | 大阪大学医学部外科学教授 | |
| 宮 坂 雄 平 | 日本医師会常任理事 | |
| 山 本 修 三 | 済生会神奈川県病院院長 | |
平成11年1月11日に、横浜市立大学医学部附属病院(以下「横浜市立大学病院」という。)において、肺を手術する予定の患者と心臓を手術する予定の患者とを取り違え、それぞれ目的以外の手術が行われるという事故(以下「当該事故」という。)が発生した(参考資料1)。
(検討会討議経過)
(1) 第1回検討会
(2) 第2回検討会
(4) 第4回検討会
本報告書は、横浜市立大学病院で発生した患者誤認事故に関連して、他の医療施設での類似事故の防止を目的として、限られた時間の中で、緊急に取りまとめたものであることから、その取り扱いに当たっては以下の点に留意する必要がある。
本検討会は、今般発生した患者誤認に由来する医療事故に関連して、類似事例の防止方策について検討を行った。具体的な防止方策に関する理解を深めるためには、その検討に先立ち、医療事故に関連した基本的な用語について整理をするとともに、事故の防止に当たっての基本的な考え方を概説することが有用であると考える。
(1) 医療事故防止に関する基本的な用語の整理
医療事故防止のための対策を検討するに当たり、関連する用語を以下のとおり整理した。
ア 医療事故と医療過誤
「医療事故」は、医療にかかわる場所で、医療の全過程において発生する人身事故一切を包含する言葉として使われている。医療事故には、患者ばかりでなく医療従事者が被害者である場合も含み、また、廊下で転倒した場合のように医療行為とは直接関係しないものも含んでいる。医療事故のすべてに医療提供者の過失があるというわけではなく、「過失のない医療事故」と「過失のある医療事故」(医療過誤)を分けて考える必要がある。
イ インシデントとは
リスクマネジメント(後述)においては、「事故(アクシデント)」に対応する言葉として「インシデント」という言葉がよく用いられている。
ウ エラーとは
人間の行為が、(1)行為者自身が意図したものでない場合、(2)規則に照らして望ましくない場合、(3)第三者からみて望ましくない場合、(4)客観的期待水準を満足しない場合などに、その行為を「エラー」という。
エ 誤認とは
「誤認」は、エラーの一形態であり、実際に存在しないものを認識したり、存在するものを正しく認識できないことをいう。すなわち、言語の聞き間違い、文字・表示の読み違い、機器のデータの読み違い、手慣れた業務における勘違い、患者に対する認識違いなどが誤認に当たり、ときに、医療事故の原因となる場合がある。
(2) 事故防止策の基本的な考え方
ア エラーと医療事故の関係
エラーのすべてが事故につながるというわけではない。それは、エラーを起こした個人自らがエラーを発見する能力を持ち、また、チームメンバーのチェックが存在していることによる。誤認事故を防止するためには、人間はエラーを犯すものであるということを前提として、個人及びシステムによるエラーのチェック機能を強化していくことが重要である。例えば、エラーの確率が1/100の医療行為に対して、見逃し率1/100のチェックを3回実施するようにした場合、計算上は事故の確率を、10-2×10-2×10-2×10-2=10-8と、極めて低い確率まで下げることが可能となる。
イ エラーレジスタントとエラートレラントのアプローチ
医療が人間により行われる限り、エラーを完全にゼロにすることは極めて困難である。しかしながら、エラーを可能な限り起こしにくくすることや、エラーが起きたとしても、最終的に事故に至らなくすることにより、エラーをコントロールすることは可能である。様々な分野の事故防止の取り組みにおいては、こうした観点に立って、事故防止の方策を2つに大別している。
ウ リスクマネジメントとは
医療事故を防止するためには、医療行為に関わる個々の医療従事者の努力が重要であることはいうまでもないが、高度に細分化・複雑化する医療の環境の中では、医療従事者個人の努力に依存した事故防止のみでは対応に限界があり、組織的な事故防止対策、いわゆる「リスクマネジメント」の考えを導入することが必要となる。 (2) 人間はエラーを犯すということを前提に、個人ではなくシステムの問題ととらえ、予防の視点で事故やインシデントの原因や状況の分析を行うこと (3) 原因分析の結果を踏まえて、事故発生の防止策と事故発生後の対応策を講じ、必要な情報を現場のスタッフにフィードバックすること (4) 対処に当たっては、結果の重大性や頻度に基づいて優先順位を決定し、また、その対処策の有効性について評価を行うこと
エ リスクマネジメントの構築
(ア) 構築のポイント
医療施設にリスクマネジメントを定着させるに当たってのポイントは以下のとおりである。
(イ) 職種別の取り組み
効果的なリスクマネジメントの実施には、医療施設内の様々な部門や職種の積極的な取り組みが必要であることはいうまでもないが、以下に、リスクマネジメントの取り組みにおいて、特に重要な役割を担っている医療施設の管理者、医師、看護職員について解説することとした。
医療事故が発生した際には直接の行為者の責任のみが論じられることが多いが、医療施設の管理者は、医療施設内で発生した医療事故については、自らがすべて責任を負っているという覚悟を持ち、積極的な姿勢で普段から事故防止の取り組みに当たることが必要である。
[医師の取り組み]
医師は、まず自らが診療の過程で事故を引き起こすことのないように心掛ける必要がある。医師のエラーをチェックするためには、医師自身による注意はもとより、スタッフや患者がいつでも医師に気軽に診療の内容について確認できるような雰囲気作りに努め、相互にチェックできるようにしていくことも重要である。
[看護職員の取り組み]
看護職員は処置等の行為を患者に直接実施する機会が多く、医療事故の直接の行為者になることが多いことから、常に自分の行為に誤りがないかどうかを意識しながら責任をもって業務に当たることが必要である。
(ウ) コミュニケーションの重要性
メンバー同士でオープンな発言ができないチームにおいては「誰も何も言わないのだから、これで間違いないのだろう」ということで、メンバーの思い込みを相互に補強し合い、チームとしてのチェック機能が働かない傾向があるといわれている。「おかしい」と思ったことは相互に指摘し合える人間関係を構築していくべきである。
[患者−医療従事者間のコミュニケーション]
医療従事者は、日常から患者に対し個々の人格として関心を持つことが求められるとともに、両者の間の信頼感の醸成に努めることが重要である。
当該事故に関しては、既に横浜市立大学病院が再発防止策を検討しており、その一部が実施に移されている(参考資料4)。
(1) 具体的な事故防止方策の検討の前に
今回の事故は、病棟から手術室への受け渡しの際に、同一の病棟から運ばれてきた2人の患者が取り違えられたことに端を発するが、最も深刻な事態は、それぞれの患者の主治医をはじめとして、事前に患者訪問を実施した医師や看護職員など、多数の医療従事者が関与したにもかかわらず、2人の患者の取り違えの事実に気付かなかった点にある。これは、現在の大規模で、高度に専門分化した医療の現場における、医療従事者と患者の間の希薄な人間関係を象徴するものとして受け止められた。
(2) 個別的な誤認事故防止方策
ア 術前訪問の際の方策
[アンケート調査での実施状況]
「手術室の麻酔科医、看護職員等が、術前に患者の病棟を訪問し、術前評価だけでなく、患者の特徴等の確認を行う。」という方策について実施状況を質問したところ、当該事故以前から実施していた施設が65施設(85.5%)と多数を占めていた。
[アンケート調査での意見]
問題点としては、麻酔科医の術前訪問は術前評価を目的として行っている(2施設)、麻酔科医に患者識別の大任を押し付けるのは問題(1施設)、手術に立ち会う看護職員が必ず術前訪問するということは業務や人員の関係上難しい(15施設)といった回答があった。
[検討会意見]
患者の取り違えを防止するためには、手術に立ち会うスタッフが患者のことを良く知るということが基本となるが、単に面識があるということだけでは十分とはいえない。人間の記憶は不確実であることを十分に認識し、術前訪問の記録を文書として残し、いつでも確認できるようにしておくことが望ましい。
イ 患者を移送する際の方策
(ア) 患者を移送する際の職員の対応
「患者を手術室に移送する際には1人ずつ行う。」という方策について実施状況を質問したところ、72施設(94.7%)とほとんどの施設が当該事故以前から実施していたとの回答であった。当該事故後実施2施設(2.6%)、これから実施予定2施設(2.6%)を含めると、回答のあったすべての施設が実施するという結果であった。
[アンケート調査での意見]
問題点として「看護職員の人員不足」や「看護業務への支障」を挙げる施設が5施設あった。特に、早朝の手術のように深夜勤と日勤の申し送りの時間帯と患者を移送する時間が重なる場合や、同一病棟から多数の患者を同時に移送しなければならない場合に問題になるとのことであった。
[検討会意見]
当然ながら、既にほとんどの医療施設において1人ずつの患者の移送が実施されていることからも、複数の患者を同時に移送することは避けるべきである。そのためにも、業務量に応じて看護職員の配置体制の見直しを図ることや、手術室の運営の工夫等により短時間に業務が集中しないようにすることが重要である。
(イ) 患者を移送する際の主治医の対応
「主治医が病棟から手術室まで同行する。」という方策について実施状況を質問したところ、43施設(56.6%)が当該事故以前から実施していたとのことであり過半数を超えていた。しかしながら、実施予定なしという施設も13施設(17.1%)存在し、有効性を認めつつも現実には実施が困難であることをうかがわせた。
[アンケート調査での意見]
問題点としては、(1)主治医は手術直前まで更衣や臨床的な作業が多く同行が困難(10施設)(2)主治医が1人の場合や連続して手術が行われる場合は困難(4施設)といった回答があった。また、患者の重症度や診療科によって異なる(16施設)という意見もあった。
[検討会意見]
患者の担当医が手術室へ移送する際に付き添うことについては、患者誤認を防止するために有効であるばかりでなく、手術を前に精神的に不安定な状態にある患者に安心感を与える上でも望ましい。しかしながら、術前の準備への対応等を考えると主治医はむしろ早めに手術室に入り、手術の準備を整えた上で、手術室等で患者を出迎える方が現実的な対応であるといえる。
ウ 患者を識別するための方策
(ア) 患者氏名の確認
「名前の呼びかけでなく、名前を患者本人に応答させることにより、患者の確認を行う。」という方策について実施状況を質問したところ、当該事故以前から実施していた施設は23施設(30.3%)と少数にとどまったが、当該事故後に実施29施設(38.2%)、これから実施予定9施設(11.8%)を含めると約8割が実施に前向きな考えであった。
[アンケート調査での意見]
問題点として、(1)麻酔の前投薬の影響で信頼性に劣る(10施設)、(2)小児、難聴、痴呆、意識障害の患者では不確実(9施設)、(3)同姓同名の患者では困難(3施設)、(4)顔見知りの医師や看護職員から名前を聞かれると患者が不快感・不安感を持つ(3施設)といった回答があった。
[検討会意見]
患者本人に名前を名乗ってもらう方法は、患者の名前を単に呼びかける方法よりは、患者誤認の可能性を低くできることから、実施が望ましい。
(イ) 患者識別バンドの装着
「患者を識別するためのバンド等をつける。」という方策について実施状況を質問したところ、当該事故以前から実施していた施設は14施設(18.4%)にとどまったが、当該事故後実施19施設(25.0%)、これから実施予定19施設(25.0%)を含めると約7割が実施に前向きであることが明らかになった。
[アンケート調査での意見]
問題点としては、(1)装着時に患者氏名の誤記や付け間違え等のミスが起こり得る(9施設)、(2)患者の心情やプライバシー保護に配慮する必要がある(7施設)、(3)患者識別バンドが点滴ラインを確保する際に邪魔になる(7施設)、(4)患者識別バンドを装着することにより他の方法による患者確認がおろそかになる可能性がある(2施設)といった回答があった。
[検討会意見]
当該事故においては、手術開始直前に、身体的な特徴が異なっていることや検査所見が術前所見と異なることに複数の医師が気付き、議論を行ったり、確認の電話を病棟に入れる等の対応をしていながら、患者取り違えに気付くに至っていない。これは最終的な患者識別の手段がなかったことが原因であり、患者識別バンドを装着することは患者を識別する手段を増やすという意味で有効であると思われる。また、血液型や禁忌薬等の情報を加えることで他の事故の防止にも有用である。
(ウ) 患者の身体への氏名記載
「患者を識別するために足の裏等にマジック等で氏名を書く。」という方策について実施状況を質問したところ、当該事故以前から実施していた施設は7施設(9.2%)と少数にとどまり、当該事故後実施5施設(6.6%)、これから実施予定2施設(2.6%)を含めても、実施に前向きな回答は2割に満たなかった。また、実施予定なしという回答が45施設(59.2%)と過半数を占めた。
[アンケート調査での意見]
問題点としては、(1)患者の身体にマジックで記載することは、患者を物として扱っているような印象を与えるため患者の理解が得られ難い(9施設)、(2)患者識別バンドと同様に記載時に間違える可能性がある(3施設)といった回答があった。
[検討会意見]
患者の身体に直接マジック等で氏名を記載する方法は、患者識別バンドのように費用がかからず、手術時の邪魔になることもないという利点がある。
(エ) その他の患者を識別するための方策
患者確認の方法は、絶対に誤りがないという方法はないということを前提に、複数の方策を組み合わせることが望ましい。アンケート調査では、バンド、マジック以外の方策として、以下のような回答があった。
エ 患者受け渡しの際の方策
手術室交換ホールでは、病棟から患者を移送してきた病棟スタッフから手術室スタッフへの引き継ぎが行われることから、その際に、患者を誤認する可能性が考えられる。対応策を以下にまとめた。
(ア) 患者とカルテの受け渡し方法
「病棟から手術室への患者受け渡しの際には、患者と同時に、カルテやX線写真等の患者情報の受け渡しを行い、他の患者と入れ替わることのないようにする。」という方策について実施状況を質問したところ、72施設(94.7%)とほとんどの施設が当該事故以前から実施していたという結果であった。
[アンケート調査での意見]
問題点として、手術直前にカンファレンスが行われるような場合には患者とは別に担当医がカルテを手術室に持ち込む場合がある(2施設)との回答があった。
[検討会意見]
当該事故では、手術室に患者を受け渡す場所(ハッチウェイ)とカルテを受け渡す窓口が異なっていたために、手術室への受け渡しの段階で患者とカルテが入れ替わってしまう結果になった。患者とカルテを常に一緒に移送していくことは、このような事態を防ぐ意味で有効であると思われる。
(イ) 患者受け渡しの際の患者の氏名確認
「病棟から手術室への患者受け渡しの際には、渡す側と受け取る側の両者が、共同で患者の名前を復唱する等の方法により患者の確認作業を行う。」という方策について実施状況を質問したところ、当該事故以前から実施していた施設は64施設(84.2%)であり、当該事故後実施5施設(6.6%)、これから実施予定2施設(2.6%)を含めると大多数が実施に前向きな考えであった。また、復唱をしていないという施設でも、例えば、手術室看護職員が病棟看護職員の告げた患者の名前が正しいかどうかをカルテを見て確認するなど、何らかの方法で確認していた。
[アンケート調査での意見]
問題点としては、(1)復唱しても口頭ではミスが発生するため、用紙やネームカードも用いて確認すべき(2施設)、(2)復唱しても本人である確認につながらない(1施設)との指摘があった。
[検討会意見]
当該事故では、手術室看護職員が患者に対して名前を呼びかけ、患者が返答するのを確認しているが、病棟看護職員との間では相互に患者の名前を確認する作業はしていなかった。患者を受け渡す際に「○病棟のAさんです。よろしくお願いします。」「はい、分かりました。○病棟のAさんですね。」というように、患者の名前を復唱するようなことがルール化されていれば、手術室交換ホールで患者誤認に気付いていた可能性がある。
(ウ) その他の患者受け渡しの際の方策
復唱以外の確認方策としては、以下のような回答があった。
オ 手術室の運営に当たっての方策
[アンケート調査での実施状況]
手術スケジュールの組み方について各施設の状況を質問したところ、「同じ時間に一斉に開始されることが多い。」という施設が62施設(81.6%)と大半を占め、「1件ずつ開始時間をずらし、同時に複数の手術が開始されることのないようにしている。」という施設は3施設(3.9%)と少数にとどまった。
[アンケート調査での意見]
手術開始時間をずらすことに伴う問題点としては、(1)手術室の効率的利用のために困難(25施設)、(2)人員、勤務時間帯の制約がある(13施設)、(3)エレベーターの関係で病棟から手術室までの移送にかかる時間をコントロールすることが困難であり開始時間をずらしても計画通りにはいかない(9施設)、(4)事務作業が繁雑になる(4施設)といった回答があった。
[検討会意見]
短時間に業務が集中することは、職員のストレスの原因にもなり、患者・カルテの受け渡し時等に混乱が予想されることから、手術室の運営を工夫することにより、できる限り業務量を分散させることが望ましい。
カ 麻酔開始時の方策
[アンケート調査での実施状況]
「患者が手術室に入室後、麻酔がかけられる前に、執刀医又は主治医が患者に声をかけ確認する。」という方策について実施状況を質問したところ、当該事故以前から実施していたという施設は40施設(52.6%)であり、当該事故後に実施9施設(11.8%)、これから実施予定7施設(9.2%)を含めると、約7割に上った。
[アンケート調査での意見]
問題点としては、(1)麻酔開始時に主治医等が手術室に入っていないことがあり手術開始が遅れてしまう(3施設)、(2)主治医がそばにいれば声かけは不要(3施設)、(3)確認できれば患者を安静にしておく方が望ましい(1施設)といった回答があった。
[検討会意見]
麻酔開始後には、患者の顔の確認が難しくなり、意志疎通もできなくなることから、麻酔医は、原則として主治医又は執刀医の立ち会いのもと麻酔を開始すべきである。
キ 手術部での方策(アンケート調査は実施していない。)
[検討会意見]
多数の手術室を有する病院においては、手術部全体を統括する立場の手術部専任医を配置することが多い。このような手術部専任医を置くことにより、各手術室を巡回し状況を確認することができ、各手術室における異変をいち早く把握することが可能となる。
(3) 組織としての医療事故防止方策
前述のとおり、1件の重大事故の背景には29件の軽症事故、更に300件のインシデントが存在すると言われている(ハインリッヒの法則)。医療分野に限らず、とかく大事故が起きて初めて本格的な対策を講じるという傾向があるが、普段から“ヒヤリ”としたことや“ハッ”としたことに目を向けて、地道にインシデントを減らしていく努力を続けることが、ひいては大きな事故の防止につながるということを、ハインリッヒの法則は教えている。
ア 事故・インシデントの情報収集
[アンケート調査での実施状況]
アンケート調査では、事故・インシデントともに報告を義務付けているという施設は50施設(65.8%)であり、事故のみ報告を義務付けているという施設22施設(28.9%)と合わせると72施設(94.7%)と大多数の施設において何らかの報告を職員に義務付けているということが明らかになった。
[検討会意見]
事故・インシデントの報告については、現状では、実施していても看護職員など一部の職種についてのみという施設が多く、まったく実施していない施設も3割程度存在している。事故・インシデントの報告は、事故防止にとって有用であることから導入に向けて取り組むことが望まれる。その際には、職種別の制度ではなく、全職員が参加する病院全体の制度にすることが重要である。
イ 事故・インシデントの報告の内容及び分析の実施
[アンケート調査での実施状況]
報告の内容については、事故又はインシデントの報告を義務付けている72施設のうち42施設(58.3%)が報告すべき項目を明確にし、専用の報告様式を定めているという回答であった。
[検討会意見]
事故・インシデントの分析をするためには、あらかじめ分析に必要な情報を議論し、その情報を網羅する報告様式を定めておくことが望ましいが、アンケート調査では6割程度の施設でしか報告様式が定められていないという結果であった。
ウ 事故防止のための委員会
[アンケート調査での実施状況]
アンケート調査では、事故防止のための委員会(以下「事故防止委員会」という。)を設置している施設は27施設(35.5%)であり、事故防止委員会に加えて事故防止のための専門部署を持っている施設は5施設(6.6%)であった。
[検討会意見]
医療施設内の問題点の全容を把握し、病院全体として事故防止に取り組むためには、各診療科及び各職種横断的な組織を設けて対応することが望ましい。
エ 事故防止のためのマニュアル
[アンケート調査での実施状況]
アンケート調査では、事故防止のためのマニュアル(以下「事故防止マニュアル」という。)を作成している施設は20施設(26.3%)であり、そのうち定期的な見直しも行っているところは17施設(22.4%)であった。全くマニュアルを作成していないという施設も21施設(27.6%)存在していた。
[検討会意見]
インシデントの報告を受けて事故防止委員会で検討した改善策については、施設職員に周知し徹底する必要があることから、事故防止マニュアルとして明文化することが望ましい。
オ 事故防止のための職員研修
[アンケート調査での実施状況]
アンケート調査では、事故防止に目的を限定した研修を行っている施設は11施設(14.5%)であり、そのうち定期的に実施している施設は9施設(11.8%)とごく少数にとどまった。事故防止のための職員研修を特段行っていないという施設も17施設(22.4%)存在した。
[検討会意見]
事故を防止するための方策を施設職員に周知するもう1つの方法としては職員研修がある。職員研修は、新規に採用された職員に対して体系的な安全教育を実施する機会として活用できるばかりでなく、ベテランの職員についても、新しい情報を提供することにより安全意識の低下を防ぐという意味があり、定期的に事故防止について考える機会を設けることは意義深い。
カ 診療における責任の明確化
[アンケート調査での実施状況]
患者に対する診療体制についての質問に対する回答は、「患者ごとに1人の主治医を定め、責任を明確にしている」という施設は9施設(11.8%)にとどまり、「診療科によって体制は異なっている」50施設(65.8%)、「患者の診療にかかわる複数の医師が、グループとして責任を持つようになっている」11施設(11.8%)という状況であった。
[検討会意見]
主治医グループ制については一長一短があることから、当該事故のみにより主治医グループ制そのものの是非を判断するべきではないと考える。
(1) 全医療施設で励行すべき基本的な事項
本報告書では、医療事故を防止するための方策について整理したが、個々の医療施設の実情は様々であり、現実には実施が難しい場合もある。そこで、以下に全医療施設において励行すべき基本的な事項を示すこととした。
(2) 取り組み方策の例
各施設における具体的な取り組みに資するため、以下に、これまで述べてきた各方策についての検討会意見の要約を示す。
ア 個別的な取り組み方策の例
イ 組織的な取り組み方策の例
本検討会の報告書は、横浜市立大学病院で発生した患者誤認事故を契機に、個々の医療施設で類似事例を防止するためにとり得る方策を中心に取りまとめ、検討を加えたものである。しかしながら、今後の対応として、個々の医療施設を超え、国や医療関係者全体としての対応が必要な課題も下記のとおり残されており、これらの課題について、今後関係者による取り組みが進むことを期待する。
(1) 啓発・普及
我が国においては、リスクマネジメント等の事故防止のための各種の手法について、必ずしも各医療施設に普及・定着している状況ではない。このため、行政機関、医療関係団体、関係学会等の関係者は、各種シンポジウムの開催や関係ガイダンスの作成等により、各医療施設に対して医療事故防止のための各種の方策を普及し、定着を図っていくことが重要である。
(2) 医療従事者の卒前教育及び研修活動の充実
今回の事故が社会的に大きな問題となった理由の1つは、大学病院という将来の我が国の医療を担う人材の養成を行っている場所で発生したことにある。
(3) 医療事故防止のための研究の推進
一般に事故原因の分析及び効果的な対策の立案に当たっては、リスクマネジメント手法やQC(クオリティーコントロール)活動をはじめとした様々な科学的アプローチが有効であり、航空機事故の分野や海外での医療事故分野においては、精力的に研究、開発が進められている。
(4) その他の医療事故等への対応
当該事故の発生以降、誤って消毒液を投与してしまった事故、誤って異なる血液型の血液製剤を投与してしまった事故など、医療事故に関する報道が相次いでいる。
(1) 日本航空技術研究所ヒューマンファクターグループ:ヒューマン・ファクターガイドブック,1995
(2) 全日本空輸株式会社総合安全推進委員会:ヒューマンファクターズへの実践的アプローチ
(3) 日本エアシステム総合安全推進室:ヒューマン・ファクターズのすすめ〜入門から実践まで〜,1997
(4) Charles Vincent, Maeve Ennis, and Robert J. Audley著,安全学研究会訳:MEDICAL ACCIDENTS 医療事故,ナカニシヤ出版,1998
(5) 莇立明,中井美雄:医療過誤法,青林書院,1994
(6) Senders JW, Moray NP:HUMAN ERROR, Lawrence Erlbaum Associates, Inc., New Jersey, 1991
(7) 牛場靖彦:リスクマネジメントの原理・原則,総合法令,1993
(8) 石名坂邦昭:リスクマネジメントの理論,白桃書房,1997
(9) 林喜男:人間信頼性工学−人間エラーの防止術−,海文堂,1988
(10)H.W.Heinrich, Dan Peterson, Nester Roos著,(財)総合安全工学研究所訳:ハインリッヒ産業災害防止論,海文堂,1982
(11)Williams CA, Smith ML, Young PC:Risk management and insurance, McGraw-Hill ,1995
(12)Kavaler F, Spiegel AD:Risk management in health care institutions, Joan and Bartlett, 1997
(13)Youngberg BJ:The risk manager's desk reference, Aspen, 1994
(14)Bogner MS:Human Error in Medicine, Lawrence Erlbaum Associates, 1994
1 被害者
(1) A氏について(年齢74歳、男)
(2) B氏について(年齢84歳、男)
2 事故の事実経過
(1) 病棟から手術室交換ホール
午前8時20分2人の病棟看護婦が、それぞれA氏、B氏を病室から業務用エレベータの中まで移送した。その後、病棟看護婦のうち1人が病棟に戻り、もう一方の病棟看護婦が1人でA氏及びB氏を4階にある手術室交換ホールまで移送した。
(2) 手術室交換ホール
手術室交換ホールにおいて、A氏をB氏の手術担当の看護婦に、B氏をA氏の手術担当の看護婦に引き渡したため、それぞれ異なる手術室に移送された。その際に、手術室看護婦がB氏の名前を呼びかけたのに対しA氏が返事をしたという。
(3) 12番手術室(肺の手術を実施)
麻酔科医は、患者(A氏)の背中に貼られていたフランドルテープ(心疾患患者用の薬剤を塗布してあるテープ)に気付いたものの、患者を取り違えているとは思わずその場ではがした。
(4) 3番手術室(心臓の手術を実施)
手術担当看護婦は、患者(B氏)が十分に剃毛されていないことを麻酔科医から指摘され、剃毛とブラッシングを行った。
(5) 手術終了後ICU入室
手術後、A氏は午後3時50分に、B氏は午後4時20分に、それぞれICUに入室した。
3 事故発生後の経過
1 はじめに
当該事故は、医療事故の中でも、(1)患者を取り違えて手術するという重大なミスであったこと、(2)医療従事者と患者の希薄な関係を象徴する事故であったこと、(3)数多くの医師、看護職員(保健婦・士、助産婦、看護婦・士及び准看護婦・士をいう。以下同じ。)等がかかわっていながら誰1人として手術途中で患者誤認に気付かなかったこと、(4)大学病院という一般に高い機能を持つと認識されている病院において発生したこと、(5)患者の医療に対する信頼なしには成り立たない手術に関連した事故であったこと、などの点において、国民の関心を集めることとなった。
従来、個々の医療事故については、医療施設と患者との間の問題ということで示談や裁判等により処理されることが多かったが、日常多くの手術が実施され、当該事故により国民の間に手術に対する不安が少なからず生じていることを踏まえると、当該事故を単に一医療施設の問題として捉えるのではなく、日本の医療全体の問題として取り組んでいくことが求められた。
このため、平成11年2月に、厚生科学研究の一環として、有識者からなる「患者誤認事故予防のための院内管理体制の確立方策に関する検討会」が設置され、類似事故の再発防止のための具体的な方策についての検討を重ねてきた。本報告書は、その検討の結果を取りまとめたものである。
本報告書では、患者誤認事故の再発防止に焦点を絞った上で取りまとめているが、その他の医療事故防止に共通する方策についても触れている。
今後、本報告書を受けて、全国の医療施設、医療関係団体、行政機関等により、医療事故防止のための積極的な取り組みが進められることを期待する。
(2) 横浜市立大学病院の事故の概要
(3) (社)日本医師会医療安全対策委員会報告書の概要
(3) 第3回検討会
(2) 麻酔科医の立場からの取り組み
(3) 看護職員の立場からの取り組み
(4) アンケート調査案について議論
(5) 報告書骨子案について議論(1)
(2) 認知心理学の専門家からのヒアリング
(3) 航空機事故防止の専門家からのヒアリング
(4) アンケート結果中間報告
(5) 報告書骨子案について議論(2)
(6) その他(医療事故防止に関する海外事例について文献配布)
2 本報告書の位置付け
3 基本的な考え方
「医療過誤」とは、医療の過程において医療従事者が当然払うべき業務上の注意義務を怠り、これによって患者に傷害を及ぼした場合をいう。過失の有無については、事例によっては、必ずしも明確でない場合がある。
また、事実認定が医療事故の発生時点における医療水準に照らして判断されることから、医療過誤の範囲は時代とともに変化することになる。
インシデントの言葉の定義は明確に定められているというわけではないが、本報告書では「患者に傷害を及ぼすことはなかったが、日常診療の現場で“ヒヤリ”としたり、“ハッ”とした経験」と定義し用いることとした。
人間の脳は、コンピュータでも及ばない高度の情報処理能力を有しており、情報が不十分な状況においても、過去の経験や知識により、その情報の不足を補い、柔軟に対応することができる。その反面、環境、心理的状態、身体的状態等の様々な要因により、同じ場面、同じ人間であっても、情報の処理に差が生じることがしばしばある。
F.H.ホーキンスは人間のエラーの確率を単純な作業で1/100、整備された環境での作業で1/1000と述べている。つまり、エラーは特定の不注意な個人に生じる問題ではなく、ある確率で人間一般に起きる、いわば人間の情報処理機能の限界といえる。
脳の情報処理は、感覚器によって知覚した情報を確認し認知し、次に認知した情報を判断し、特定の行動を選択して命令するという、「認知」−「判断」−「行動」という過程で行われている。この「認知」−「判断」−「行動」の一連の過程で間違いが生じた時、誤認というエラーが生じることになる。
医療行為は、医師の指示から複数の医療従事者や場面を経て患者へ提供され、こうした一連のプロセスにおいて、各々が情報処理を行っている。よって、医療従事者から医療従事者への引き継ぎ時や、場面から場面への節目ごとにチェックの機会を設けることが、医療事故を防止する上で重要となる。
1つは「エラーレジスタント」、すなわちエラーの発生自体を抑えることにより事故を防止する手法である。これは、個人の訓練や教育、さらに使いやすい機器・用具の設計や作業手順の改善を通じてエラーの発生頻度を減少させる方策である。
いま1つは「エラートレラント」、すなわちエラーが事故に結びつかないようにすることにより事故を防止する手法である。これは、闇雲にエラーを無くそうとするのではなく、その存在を認め、エラーが発生しても事故に結びつかないようにコントロールする方策である。現在の複雑で、高度に専門分化した医療組織においては、起こり得るすべてのエラーを予測することは困難であることから、「エラートレラント」な手法による防止策がより重要となる。
リスクマネジメントは、もともとは産業界で用いられた経営管理手法であり、事故発生を未然に防止することや、発生した事故を速やかに処理することにより、組織の損害を最小のコストで最小限に食い止めることを目的としている。1970年代半ばに米国で医療分野にも導入され、その後、欧州にも広がった(参考資料2)。我が国では、平成10年に(社)日本医師会の医療安全対策委員会により取りまとめられた「医療におけるリスク・マネジメントについて」の中で、リスクマネジメントの考え方が紹介されている。
医療におけるリスクマネジメントと産業界のそれとの違いは、後者が組織の損害防止に主目的が置かれているのに対し、医療においては、医療の質の確保を図ることに主目的が置かれているという点である。リスクマネジメントは、医事紛争の防止についてもその対象に含める場合があるが、本報告書においては、医療事故の防止の代表的な手法として、この言葉を用いることとした。
ハインリッヒは労災事故の研究で1件の重大事故の背景には29件の同種の軽症事故、更に300件の同種のインシデントが存在すると報告している。重大事故に発展するかインシデントにとどまるかは、単に防御機能が働いたか否かの差であって、その根本的な原因については共通する部分が大きいといわれている。1件の重大事故を防ぐためには、軽微な事故やインシデントの分析からシステム上の問題を発見し予防的な対応を組織的に行うリスクマネジメントの取り組みが求められる。
リスクマネジメントの特徴を整理すると、
であり、具体的な手法としては、
(2) リスクの「把握」−「分析」−「対処」−「評価」のプロセスが継続するようなシステムを構築すること
などが挙げられる。
なお、参考までに航空業界における事故防止の取り組みを参考資料3にまとめた。
(2) リスクマネジメントの目的、対象範囲、活動内容を、職員に理解しやすい形で明文化すること
(3) 事故及びインシデントについて、オープンに議論できる風土を形成すること
(4) リスクマネジメントに関する教育や啓発を実施し、医師をはじめとする職員の理解と積極的な参加を得ること
(5) リスクマネジメントに関する組織(専門部署や委員会)を設け、その組織責任者の権限(調査権等)を明確にすること
(6) 事故防止に有用な情報は職員全員で共有すること
(7) 医療の質を向上させるための院内の他の活動と連携すること
医療施設の管理者に求められる条件としては、
等が挙げられる。
(2) 事故防止に関するリスクマネジメント等の新しい知見を受け入れる柔軟性があること
(3) 事故防止に取り組む強い意志と実行力があること
医療施設の管理者が事故防止の取り組みに理解を示し、積極的に行動することが、事故防止活動を医療施設に根付かせる第一歩であるといえる。
また、医師は、自分の担当する患者に対して看護職員その他のスタッフが実施した行為についても、自分が最終的な責任を負っているのだという心構えで診療に望むことが求められる。
医師が看護職員等のスタッフに指示を出す際には、口頭のみでの指示を避け、指示を分かりやすく正確に伝えることに留意する必要がある。さらに、スタッフが自分の指示通りに作業をしているかどうか、あるいは、自分の指示以外にどのような業務を行っているかといったことに、常に目配りをすることが求められる。
なお、医療事故防止のための医師の役割については(社)日本医師会の医療安全対策委員会が取りまとめた「医療におけるリスク・マネジメントについて」も参考にされたい。
また、看護職員は、患者に接している時間が一番長いことから、患者の観察や患者とのコミュニケーションに努め、異変等に気付いた場合には、速やかに医師等に報告することが重要である。
さらに、医師から指示を受けた場合には、単に機械的に業務をこなすのではなく、その指示の意味や目的について考えながら行動し、疑問があれば、必ず医師に確認するように心掛けることが望ましい。医師の指示にもミスは有り得るということを念頭に置いて、事故防止のためであれば、ちゅうちょせずに発言していくことが期待される。
なお、医療事故防止のための看護職員の役割については、(社)日本看護協会が取りまとめた「看護職の社会経済福祉に関する指針−医療事故編」も参考にされたい。
また、単なる情報伝達ではなく、患者の内面にも配慮した豊かで双方向性のコミュニケーションを日常から積み重ねることが誤認を防止する上で重要である。
さらに、万一事故が起こった場合には、患者や家族に対する十分な説明を行い、専門家としての適切な対処や暖かい精神的支援の実施が望まれる。
4 具体的な事故防止方策
前述のとおり、医療事故の防止に当たっては、実際の事故例の詳細な分析を行い、そこから具体的な防止策を立案することが最も効果的かつ効率的である。
そこで、本報告書においても、横浜市立大学病院の事故対策委員会及び横浜市の事故調査委員会において検討されてきた事項を参考としながら、患者誤認事故防止のための具体的な方策についての検討結果を取りまとめた。ここでは、(1)個別的な誤認事故防止方策と、(2)組織としての医療事故防止方策の2つに分けて整理した。
また、今回の検討に当たっては、特定機能病院を対象に、各種の対策の実施状況や実施上の問題点等についてアンケート調査を実施し、個々の方策の各施設での取り組み状況等についても検証した(配布数82、回収数76、回答率92.7%)。今後の各医療施設が類似事故防止方策を検討していくに当たっての参考のために、アンケート調査の結果についてもあわせて提示することとした。
今後、医学の進歩に伴って医療内容が更に高度化、複雑化していくことや医療提供体制の効率化により平均在院日数が短縮化していくことを踏まえると、患者と医療従事者の間で良好な人間関係を構築し維持していくことは、ますます重要になっていくものと考えられる。
以下、患者の誤認を防止するための個別具体的な手法について述べるが、そのような議論以前の問題として、今日の医療を巡る環境の変化の中で、すべての医療従事者が患者とのより緊密な信頼関係の構築に向けて努力することの重要性をまず強調しておきたい。
術前訪問時の具体的な把握事項としては、顔貌、体格、義歯の有無、頭髪の長さ・色、ほくろ、手術痕、四肢血管の特徴等が挙げられる。
アンケート調査の回答にもあるとおり、麻酔科医については、術前訪問(術前診療を含む)を行うことを原則とするが、手術に立ち会う看護職員が全ての患者について術前訪問することは、実際には難しい場合が多い。
その場合でも、術前訪問の記録により引き継ぎをするなど情報の共有化を図ることが望まれる。
その際には、患者が不快感・不安感を抱かないよう十分な説明をすることが必要である。
しかしながら、アンケート調査でも問題点として指摘があるように、麻酔の前処置の影響や、痴呆、難聴などにより、患者に名前を名乗ってもらうことが困難な場合もあり、必ずしも有効性が高い方策であるとはいえない。あくまでも患者確認のための補助的な手段であることを十分に認識し、この方法のみにより患者確認をすることは避けるべきである。
アンケート調査でも指摘されているとおり、いくつかの実施上の問題点が存在するが、(1)については、装着時に複数の職員が立ち会ったり、患者本人に記入してもらう等の対応をすること、(2)については、患者に患者識別バンドを装着する意義についての十分な説明を行うこと、(3)については、点滴ラインをとる腕を決めておき、その反対の腕に患者識別バンドを装着すること、(4)については、二重三重のチェックを職員に徹底すること、等の対応をあわせて検討することが望ましい。
また一方で、(1)左右誤認を防ぐのにも活用できる(1施設)、(2)患者自ら書いてもらうので確実でありコストもかからないので良い(1施設)との意見もあった。
アンケート調査でも指摘されているように、この方策は患者に不快感・不安感を与える恐れがあり、実施は、患者にその意義を十分に説明して理解を得ることが前提となる。そのため、身体に直接マジックで記載することに理解が得られない場合には、幅広の絆創膏に記載して貼り付ける等の工夫が望まれる。
(2) 患者の氏名を記載した帽子を患者に着用させる。(4施設)
(3) 入院ベッドで手術室まで移送する。(3施設)
(4) 同じ名札を2枚用意し、1枚を搬送用ベッド、もう1枚を手術台に付け照合する。(2施設)
しかしながら、カルテが患者から離れてしまうことや、病棟を出る段階で他の患者のカルテと取り違えてしまうようなことは十分に想定されることから、あらかじめ患者とカルテを容易に照合できるようにしておき、常に確認を怠らないことが重要である。一例としては、カルテに患者の顔写真を入れておく等の工夫が考えられる。
この場合も、患者の確認に当たっては、カルテのみに頼ることなく他の方法と併用することが必要である。
手間のかかる作業とはいえないことから、まだ実施していないような施設についてはこのような確認作業を習慣付けていくべきであろう。
しかしながら、復唱による確認で万全ということではなく、職員1人1人が「思い込み」による誤認の可能性を常に意識し、二重三重の確認を怠らないことが何よりも重要である。
(2) 術前訪問した際の記録との照合を行う。
具体的な方策としてはあらかじめ手術開始時間をずらしてスケジュールを設定する方法が考えられるが、アンケート調査の結果からも明らかなように実情にそぐわない点も多い。次善の策として、少なくとも同じ病棟の手術が同時間に重ならないようにするといった方策の実施が望まれる。
一方で、患者の不安軽減のために大切である(4施設)という前向きな意見もあった。
また、主治医又は執刀医が麻酔開始前に患者に声をかけるということは、患者確認という目的以上に人体にメスを入れる者の礼儀として実施するという意味もある。外科医にとっては手術は日常的な作業であっても、患者にとっては人生で1度経験するかどうかという一大事であることを忘れてはならない。患者の不安を思いやる気持ちを忘れずに、手術に望む際の心構えを新たにするためにも患者への声かけを行うべきである。
また、各手術室においても手術部全体の状況を把握できるように、手術スケジュールや手術の進行状況の一覧表を各手術室に貼り出す方法も検討すべきである。
事故が起きて初めて対策を講じるような「事故処理型」の姿勢から、問題が小さいうちに事故の芽を摘んでしまう「事故防止型」の姿勢へと転換し、組織として事故防止のための取り組みを行うことが望ましい。以下、組織としての取り組み方策について整理した。
しかしながら、事故・インシデントともに報告を義務付けている50施設のうち全職種について報告を義務付けているという施設は14施設(28.0%)にとどまった。職種別では、看護職員が43施設(86.0%)と多く、次いで医師25施設(50.0%)、薬剤師16施設(32.0%)という結果であった。
報告ルートについては、事故又はインシデントの報告を職員に義務付けている72施設のうち47施設(65.3%)が報告ルートを定めており、代表的なルートは、医師であれば「ミスに気付いた医師→病棟医長→診療部長(教授)→病院長」、看護職員であれば「ミスに気付いた看護職員→婦長→看護部長→病院長」であった。
また、事故防止の責任者を定めておくことが報告ルートを明確化する上でも望ましいが、病棟ごとに責任者を置いている施設は32施設(42.1%)、職種ごとが19施設(25.0%)、病院全体が33施設(43.4%)であり、これらすべてに責任者を置いているという施設は13施設(17.1%)という結果であった。
また、単に報告にとどまるのでなく、以下“イ”で述べる分析と有機的な連携を図ることが重要である。
事故・インシデントの報告を施設に定着させるためには、報告ルートをあらかじめ定めておくことが望ましい。その際には、各部門、各職種、そして病院全体の事故防止責任者を定め、それぞれの事故防止責任者が、必要な情報を入手できるように、報告ルートを決めることが望ましい。
また、報告内容の分析状況については、事故又はインシデントの報告を職員に義務付けている72施設のうち57施設(79.2%)が報告内容の分析を行い改善策の検討に用いているという回答であった。
報告された事故・インシデントについては分析を行い、事故防止に役立てていかなければ意味がない。具体的な分析方法は、マクロ的な分析とミクロ的な分析の2つに大別できる。
マクロ的な分析では、事故・インシデントの件数を、診療科別、行為者の経験年数別、診療行為別、内容別、深刻度別等で集計し、事故・インシデントの傾向を把握する。このマクロ的な分析については、ある程度、報告件数が集まる期間(例えば3か月)を設定した上で定期的に行うことにより、経時的な傾向についても把握することが可能となる。マクロ的な分析は、その医療施設における問題点を特定したり、事故防止の取り組みの評価をするのに活用できる。
ミクロ的な分析では、エラーをした本人に対してインタビューを行う等の方法により、更に詳しく事故・インシデント発生の背景要因を精査し、再発を防止するために医療施設全体で取り組むべき方策について検討が行われる。ミクロ的な分析については様々な方法が考えられるが、一例として航空業界で用いられている4M−4Eマトリックス表による分析例とSHELモデルによる分析例を参考資料5に示す。
事故防止委員会の開催頻度については、定期的に開催しているという施設は20施設(26.3%)にとどまった。
事故防止委員会では、各診療科の代表者等で組織し、活動内容としては、(1)インシデント報告に基づく改善策等の検討、(2)重要なインシデントの職員への周知、(3)各種マニュアルの作成、(4)事故を起こした職員に対する助言等が想定される。このような取り組みを行うには、管理部門の一組織としてリスクマネジメント部を設け、専任のリスクマネジャーを配置することも考えられる。
事故を防止するためには平時から医療施設の管理システムの改善に努めることが重要であり、事故発生時の臨時の開催に加えて平時にも定期的に開催することが望ましい。
事故防止マニュアルは各施設において独自に作成することに意義があり、現場の職員の意見を汲み上げて随時改定していくようにしなければ、いずれ形骸化してしまう恐れがある。
また、詳細に解説した冊子形式のものよりは、部門ごとにチェックポイントを1枚に簡潔にまとめ診療現場に掲示できるような体裁にした方が、現場の職員の注意を喚起する上では望ましい。このような体裁にすることは、診療手順の重要な区切りごとにマニュアルに盛り込まれたチェック項目の確認を励行させる上で有効である。
事故防止の職員研修の場では、事故防止委員会等の事故を防止するための医療施設全体としての取り組みや、職員レベルでのマニュアル遵守等の取り組みについて体系的に説明するとともに、身近な事故事例によりケース・スタディを行うことも効果的である。ベテランの職員に持ち回りで職員研修の講師を努めさせることも、病院全体で事故防止を進めていくための雰囲気作りを醸成する上で望ましい。
また、職員研修では、その場限りとなってしまうことが多いことから、日常、事故防止について考える機会をできる限り多く設けることが重要である。例えば、事故防止のための標語やスローガンを募集し職員全員で考える機会を設けたり、採用した標語・スローガンを院内に掲示する等の取り組みが挙げられる。
しかしながら、主治医グループ制を選択する場合には、責任体制が不明確になりやすいという欠点があることを十分に認識した上で、責任者は誰であるのか、あるいは個々の診療の責任は誰が持つのか等を明確にする必要がある。
特に、手術時においては、執刀医、麻酔科医、手術室看護職員等の複数の職種が多人数で、1人の患者の治療に同時に当たることから、責任が分散化してしまう恐れがある。あらかじめ、スタッフ1人1人の役割や責任の範囲を明確にしておくことが必要である。手術の最終責任を負うべき立場の医師(執刀医グループや主治医グループの責任者)は、「手術を開始すべきか否か」といった基本的な判断を、自らの責任で下せるようにしておく必要がある。手術の責任者は誰であるかを明確に定め、手術全体を責任を持って統括する権限を付与することが必要である。
さらに、患者に対しては、少なくとも、主治医が誰であるか、また、主治医グループ制をとっている場合には誰が責任者であるかを、明確に伝えておくことが重要である。その具体的な方法としては、ベッドのネームカードに主治医及び主治医グループの責任者の氏名を記載するといった方法が考えられる。
5 検討会としての提言
6 今後の課題
また、アンケート調査の結果をみると、医学部学生に対する医療事故の防止に関する教育については、必ずしも十分に行われているとは言い難い状況であった。
医療事故の防止に当たっては、リスクマネジメントのような科学的な手法を応用していくことが必要であることから、今後、医師をはじめとする医療従事者の養成課程に、医療事故の防止に関する教育を積極的に導入していくことが望まれる。
さらに、医療従事者の教育課程において、医療は、本来、医療従事者と患者との間の緊密な信頼関係の下で行われるべきであり、安全で患者に安心感を与える医療の提供は、医療従事者に求められる基本的な責務であることを、繰り返し強調することが重要である。
同様の趣旨から、医師をはじめとした医療関係職種の生涯教育のカリキュラムの中に、医療事故の防止を目的とした各種研修を組み込むことについても検討していくべきであろう。
しかしながら、我が国における医療事故の研究は、現在、緒についたばかりであり、研究者の数や研究実績の面からも十分な蓄積があるとは言い難い。また、事故防止のための研究には、医学のみならず、心理学、システム工学と言った様々な学問体系が関わる学際的アプローチが重要となる。
このため、関係分野との連携を深めるとともに、医療事故の防止に資する研究を推進し、同時に、専門家の充実を図っていく必要がある。
医療事故の防止に資する研究については、(1)実際に起きた医療事故・インシデントの情報を収集・分析する手法や、(2)人員の適正な配置、医療用具・施設設備等の医療を取り巻く環境の整備に向けた取り組みが重要である。
現時点では、このような分野における事故防止の観点からの知見が十分に集積しているとは言い難い状況にあることから、今後、調査研究を進めていくことが望まれる。
本報告書は、患者の誤認に基づく事故を中心に事故防止方策を整理したため、すべての医療事故に対応したものではない。医療事故には様々なタイプがあり、また、個々の医療施設によってとるべき対策は異なることから、国主導で医療事故防止を進めるというよりは、各医療施設が主体となって事故防止の取り組みを行っていくことが重要である。国は、このような各医療施設の取り組みを、普及啓発、教育・研修の実施、研究の推進等によりバックアップしていくことが望まれる。
米国医師会は1997年9月に医療事故に関する情報収集と医療事故の防止を目的とした財団National Patient Safety Foundation at AMA(NPSF)を発足させている。我が国における今後の取り組みを考えるに当たっては、諸外国のこのような活動も参考にしながら前向きに検討していくことが望まれる。
7 参考文献
参考資料1 横浜市立大学病院の事故の概要
事故調査委員会報告書に基づいて事故の経過を要約すると以下のとおりである。
実際に行われた手術(肺) :右肺嚢胞切除縫縮術
実際に行われた手術(心臓):僧帽弁形成術
その後、病棟看護婦から手術担当看護婦への申し送りが行われ、カルテは患者とは離れて本来の手術室に運ばれた。
その後、手術は、午前10時5分に、3人の執刀医により開始された。
患者(A氏)には、B氏の腫瘍があると術前に診断した部位と同じところに、嚢胞様病変が認められたため、術前の所見と大きな矛盾はないと判断し、嚢胞の切除を行った。
午後1時50分に患者(A氏)の手術は終了した。
複数の麻酔科医及び執刀医が、患者(B氏)の身体的な特徴がA氏と異なっていることや検査所見が術前所見と異なることに気付き議論が行われた。
念のため、麻酔科医の1人が手術担当看護婦に指示して病棟に確認の電話を入れさせたものの、A氏は確かに手術室に降りているという返事があったため、患者取り違えに気付くに至らなかった。
手術は、午前9時45分に、2人の執刀医によって開始された。
胸骨心膜切開後、執刀医グループの責任者が手術室に入室し、検査結果を再検討したが、患者取り違えに気付くに至らなかった。
左心房を切開し弁逆流試験をすると、予想していたよりも軽度ではあったが病変を認めたため、僧帽弁形成術を施行した。逆流試験にて逆流が消失したのを確認し、午後3時45分に患者(B氏)の手術が終了した。
なお、手術中に、患者(B氏)へA氏の血液が輸血されたが、幸い血液型が同じであったため大事には至らなかった。
A氏の主治医と麻酔科医は、術後に見込んでいた体重と異なるため、A氏ではないのではないかとの疑いを持った。
ICUの医師がB氏を診察し、2人が入れ替わったのかもしれないと思い、A氏の心音を聴いたところ心雑音が聴かれた。そこで、A氏に名前を尋ねたところ、患者が入れ替わっていたことが確認された。
| 平成11年1月11日(月) | 患者取り違え事故発生 直ちに市長に報告 |
|
| 12日(火) | 警察への届出 | |
| 13日(水) | 一部新聞に報道 1回目の記者会見 |
|
| 14日(木) | 2回目の記者会見 (事故調査委員会の設置を発表) |
|
| 21日(木) | 第1回事故調査委員会開催 | |
| 30日(土) | 事故調査委員会委員による病院視察 | |
| 2月7日(土) | 第2回事故調査委員会開催 | |
| 19日(金) | 病院長及び医学部長が辞任 | |
| 27日(土) | 第3回事故調査委員会開催 | |
| 3月8日(月) | 第4回事故調査委員会開催 | |
| 21日(日) | 第5回事故調査委員会開催 (報告書取りまとめ) |
|
| 23日(火) | 報告書を横浜市長に提出 |
1970年代半ば「患者の権利」運動が関連法案の成立によって急速に高まり、原告側の弁護士の活躍もあって医療訴訟が急増した。やがて1980年代になると、医療側敗訴の増加、賠償額の高騰により、民間保険会社は医師賠償責任保険から撤退し、医療施設は無保険状態におかれたり医療過誤保険料が高額化したりするという、いわゆる「医療訴訟危機」「保険危機」を経験することになった。
2 米国の病院の取り組み(ベスイスラエルメディカルセンターの場合)
ニューヨーク州にあるベスイスラエルメディカルセンターでは、本院、分院合わて約2000床の施設に4人の専任のリスクマネージャーを配置している。4人の下には事故調査等の実務を担当するスタッフ、リスクコントロールコーディネーター6人がおり、計10名と事務職員でリスクマネジメント部が運営されている。リスクマネジメント部の部長は副院長級の位置付けがなされている。
航空業界においては、「ヒューマンファクター」という概念と知識が、安全で効率的な航空機の運航の実現のために応用されている。ヒューマンファクターの定義は統一されているわけではないが、「環境の中で生きる人間をあるがままにとらえて、その行動や機能、限界を理解し、その知識をもとに人間と環境の調和を探求し、改善すること」というような意味で用いられている。
2 事故防止のための組織体制
航空業界では、運航部門、整備部門、客室部門、運航管理部門、空港部門等の各部門に安全を管理する組織を設け、ヒューマンエラーに関する報告を分析し対応策を検討する等の業務を行うとともに、総合的な安全推進を担当する組織(総合安全推進委員会等)を設け、全社的な安全意識の向上や安全に関する情報提供等の取り組みを行っている。
3 事故防止のための情報収集
我が国の航空業界では、航空法により、事故や重大なインシデントが発生した際には、運輸大臣への報告が義務付けられているが、それに加えて、航空会社独自の取り組みとしてヒューマンエラーに関する情報の収集及び事故防止の対策への活用が行われている。
4 事故防止のための訓練
航空業界では、ヒューマンファクターの要素を取り入れた様々な訓練が実施されている。その代表的なものがCRM(Crew Resource Management)であり、日本国内のいくつかの定期航空会社により実施されている。
[患者移送]
[患者の引き受けとカルテ等の申し送り]
[術中の基本]
2 今後の対応策
[病院運営システム上の取り組み]
[病院組織管理上の取り組み]
[医療教育上の取り組み]
参考資料2 海外の医療分野での取り組み(米国の例)
1 リスクマネジメントの発展
こうした事態に対応するべく、医療施設自らが財源を確保して設立した自家保険会社や医師賠償責任保険を扱う民間保険会社は医療におけるリスクマネジメントに取り組み始めた。このような保険会社の活動に加えて、州政府による病院の認可、連邦政府からの高齢者病院医療費の支払い、病院機能評価においても、病院におけるリスクマネジメント活動やクオリティアシュアランス(医療の質の確保)活動が重要視されるようになったといわれている。
当初、リスクマネジメントは医療事故や医事紛争により病院の資産を失わないための事務・管理系の業務であり、クオリティアシュアランスは臨床に従事する者による医療の過程や結果を評価、改善していくための活動であった。しかし近年では、医療の質の向上という視点から、情報収集、分析、対応策のフィードバックという一連のプロセスにおいて、これら二つの活動は相互に連携し機能している。
リスクマネジャーには法律、保険、財務、組織管理等に関する知識を習得した看護職がついている。その具体的な職務は事故防止活動のほか、保険購入や訴訟対策に至るまで幅が広い。事故防止活動としては、(1)事故につながる情報の収集と管理、(2)報告された事故の分析、(3)関連法規の遵守のサポート、(4)他の関連委員会との連携、(5)スタッフ教育などを行っている。また、リスクマネジメント活動のみならず、病院機能評価への対応など、クオリティアシュアランスに関する業務も行っている。
こうした内部組織によるリスクマネジメント活動のほかに、外部からのサポートも積極的に活用している。米国の場合、コンサルタント会社や保険会社のサポートを受けている病院は多いが、ベスイスラエルメディカルセンターの場合、他の病院と共同出資して、リスクマネジメントに関してアドバイザー的役割を担う非営利組織を設立している。この組織は、事故報告書の分析、リスクマネジメントに関する教育、リスクマネジャーの育成や業務の支援など、リスクマネジメント全般に関するアドバイスを病院や個々の医療従事者に対して行っている。こうした外部組織の支援も受けてリスクマネジメント活動の充実が図られている。
参考資料3 医療分野以外での事故防止の取り組み(航空業界の例)
1 ヒューマンファクターの応用
ヒューマンファクターが航空機に応用されるようになったのは、第二次世界大戦中の軍用機の操縦席周辺の設計が最初であるといわれており、その後、機器の設計以外にも、ストレス下の人間の行動や訓練方法等にまで研究の範囲が拡大された。
ヒューマンファクターの具体的な取り組みの内容は、(1)企業内にヒューマンファクターの概念と知識を浸透させる、(2)エラーを起こしにくい職場環境を設定する、(3)エラーを管理できるようになるための訓練を行う、の3つが一般的である。
また、欧米では国家としての取り組みも行われており、NASA(National Aeronautics and Space Administration,米国航空宇宙局)によるASRS(Aviation Safety Reporting System,航空安全報告)に代表されるような非公開かつ自主的な報告制度が存在している。ASRSには年間3万件を超える報告が寄せられ、専門家により解析された結果が毎月報告書の形で公開されている。
CRMは1970年代初頭に米国において航空事故が多発したのを受けて、米国の産官学が協力して開発した事故回避のための訓練プログラムであり、個別の人間に対する単独の訓練ではなく、実際の事例に則して主としてチームとしての総合的な対応を訓練するためのものである。
具体的には、(1)状況認識(発生した状況を確実に認識すること)、(2)問題解決(認識した問題を解決する方法を考える)、(3)意志決定(最終的に考えた方法を実行に移す)、(4)コミュニケーション(複数の人間の間の円滑な意志の疎通)、(5)ストレスマネジメント(緊急事態のストレスや長時間飛行による疲労下での行動の自己管理)など多岐にわたる項目により構成されている。CRMでは、知識に偏重するのではなく、LOFT(Line Oriented Flight Training)というシミュレーターを用いた実践的な訓練との併用により効果を上げている。
当初、CRMはCockpit Resource Managementと呼ばれ、操縦室内の乗員だけを対象とするものであったが、その後、管制官や整備員、客室業務員、運航管理者等にまで対象範囲を広げCrew Resource Managementとして広く実施されるようになっている。
参考資料4 横浜市立大学病院の事故再発防止策
1 事故後の緊急対策
[患者移送]
以下のとおりとする。
[術前訪問]
[行動基準(マニュアル)]
参考資料5-1
4M−4Eマトリックス表による分析例
(手術室交換ホールにおいて患者を誤認したことについての分析例)
| MAN (人間) |
MACHINE (物、機械) |
MEDIA (環境) |
MANAGEMENT (管理) |
||
| 具体的要因 | ○ 患者受け渡し時に患者の確認が不十分であった。 | ○ 患者を引き渡すハッチウェイとカルテの窓口が別々であった。 | (1) 患者を識別できるものがなかった。 (2) 患者の名前を呼びかけたところ他人の名前であるのにもかかわらず患者がうなずいた。 |
○ 看護婦が同時に2人の患者を移送した。 | |
| 対 応 策 |
EDUCATION (教育・訓練) |
○ 患者受け渡し時の手順を定め、職員への研修を行う。 | (2) 患者によっては、他人の名前に応答することもあり得ることを研修等により、職員に周知する。 | ○ 患者の移送は1人ずつ行うこととし、職員に周知する。 | |
| ENGINEERING (技術・工学) |
○ カルテの受け渡しは、カルテの窓口を使用せず、ハッチウェイを介して患者と同時行う。 | ||||
| ENFORCEMENT (強化・徹底) |
○ 患者受け渡し時の手順をマニュアルに盛り込む。 | ○ 交換ホールでの患者及びカルテの受け渡しの手順をマニュアルに盛り込む。 | (1) 各患者にバンドを装着する。 (1) 足の裏にマジックで名前を書く。 (2) 患者の名前を呼びかけるのではなく、患者に名前を応答してもらう。 (2) 病棟スタッフと手術室スタッフが、患者の名前を復唱するようにする。 |
○ 患者の移送は1人ずつ行うことをマニュアルに盛り込む。 | |
| EXAMPLE (模範・事例) |
○ 改訂したマニュアルを配布し周知・徹底する。 | ○ 改訂したマニュアルを配布し周知・徹底する。 | (1)(2) 改訂したマニュアルを配布し周知・徹底する。 | ○ 改訂したマニュアルを配布し周知・徹底する。 | |
○ 4Mとは、事故原因の分類に用いられる区分であり、(1)MAN(人間)、(2)MACHINE(物・機械)、(3)MEDIA(環境)、(4)ANAGEMENT(管理)の4つを指す。
○ 4Eとは、事故対策の分類に用いられる区分であり、(1)EDUCATION(教育・訓練)、(2)ENGINEERING(技術・工学)、(3)ENFORCEMENT(強化・徹底)、(4)EXAMPLE(模範)の4つを指す。
○ 4M−4E方式は、上記のようなマトリックス表を用いて事故の原因ごとの対策案を網羅的に整理するのに便利である。
参考資料5-2
| Event | SHEL | 要因 | 対策例 |
| ○ 手術室交換ホールにおいて、患者及びカルテの受け渡しをする際に患者を誤認し別の手術室に移送した。 | L-S | ○ 患者(A氏)にB氏の名前を呼びかけたところ返事をしたことから、患者がB氏であると思い込んだ。 | ○ 患者本人に名前を応答させることにする。 |
| L-H | ○ 患者を受け渡すハッチウェイとカルテの受け渡し台が別々になっていたことが、患者からカルテが離れる原因になった。 | ○ カルテの受け渡し台は使用せず、ハッチウェイに おいて、患者及びカルテを受け渡すことにする。 | |
| L-E | ○ 朝の看護業務が多忙であったため、1名ずつ移送すべきところを、看護婦1名が2名の患者を移送した。 | ○ 業務量に応じて手術日朝の看護体制を見直し、1名ずつ移送できる体制にする。 | |
| L-L | ○ 病棟看護婦と手術室看護婦の間で、確認作業を行わなかった。 | ○ 病棟看護婦と手術室看護婦が患者の名前の復唱等により共同で患者確認を行うことにする。 |
○ このモデルを用いて、上図のとおり事故・インシデントの分析を行うことが、航空業界において推奨されている。その分析に当たっては、中心のL自体の問題と併せて、L-S、L-H、L-E及びL-Lのそれぞれのインターフェースに問題がなかったかを分析し、その結果に基づいて改善方策を検討することになる。
参考資料5-3
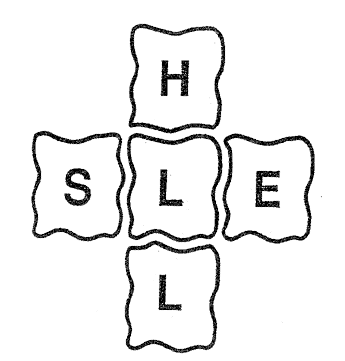
| S= | Software(ソフトウェア) |
| H= | Hardware(ハードウェア) |
| E= | Environment(環境) |
| L= | Liveware(人間) |
照会先:厚生省健康政策局総務課 課長補佐 青木 龍哉(内2513) 課長補佐 神ノ田昌博(内2516) 代表 [現在ご利用いただけません] 直通 3595-2189
| 報道発表資料 | HOME |