| 第1―1図 女性の年齢階級別労働力率 |
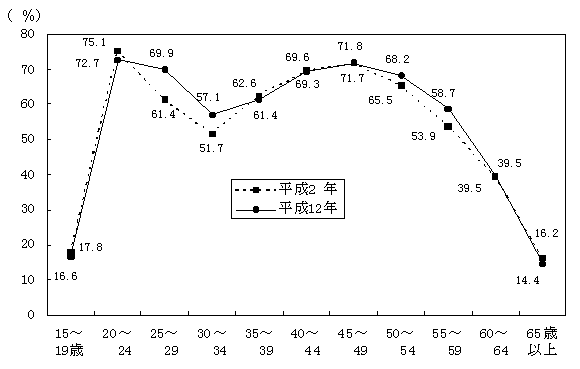 |
| 資料出所:総務省統計局「労働力調査」 |
1 労働力人口、就業者、雇用者の状況
(1) 労働力人口
平成12年の女性の労働力人口(就業者+完全失業者)は2,753万人で、前年に比べ 2万人、0.1%の減(11年12万人減、0.4%減)となり、2年連続の減少となった。
また、労働力率(15歳以上人口に占める労働力人口の割合)は、前年より0.3%ポイント低下し49.3%となり、平成9年以降低下傾向が続いている(第1―1表)。
年齢階級別に女性の労働力率をみると、M字型カーブのボトムを形成している30〜34歳層で57.1%となり10年前(平成2年)と比較すると5.4%ポイント上昇した(第1―1図)。
配偶関係別に女性の労働力率をみると、未婚者では62.2%、有配偶者では49.7%となっている。未婚者と有配偶者の年齢階級別にみた労働力率を10年前と比較すると、未婚者では30〜34歳層、35〜39歳層で労働力率が上昇し、未婚者全体の女性労働力率を押し上げている一方、有配偶者では同じ年齢層で低下している(第1―2図)。
平成12年の女性の非労働力人口は2,824万人で、前年と比べ34万人増加した。
| 第1―1表 労働力人口、労働力率の推移 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資料出所:総務省統計局「労働力調査」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第1―1図 女性の年齢階級別労働力率 |
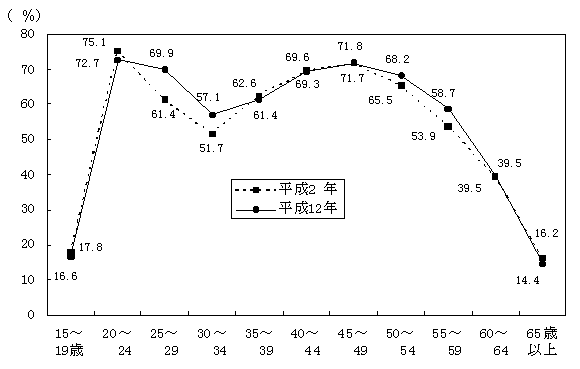 |
| 資料出所:総務省統計局「労働力調査」 |
| 第1―2図 配偶関係、年齢階級別労働力率の推移 |
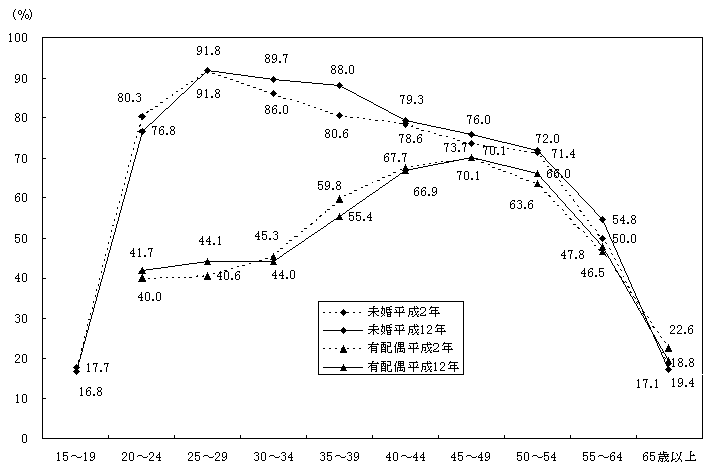 |
| 資料出所:総務省統計局「労働力調査」 |
(2) 就業者と完全失業者
平成12年の女性の就業者数は2,629万人で前年より3万人減少した。平成10年以降2年連続で低下した雇用者は、平成12年には増加に転じ、家族従業者、自営業者は減少した。就業者に占める雇用者数の割合は81.4%で引き続き上昇している(第1―2表)。
| 第1―2表 従業上の地位別就業者数及び構成比の推移 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平成12年の女性完全失業者は123万人、完全失業率は4.5%となり、平成11年と同様に過去最高水準が続いている(第1―3図)。
| 第1―3図 完全失業率の推移 |
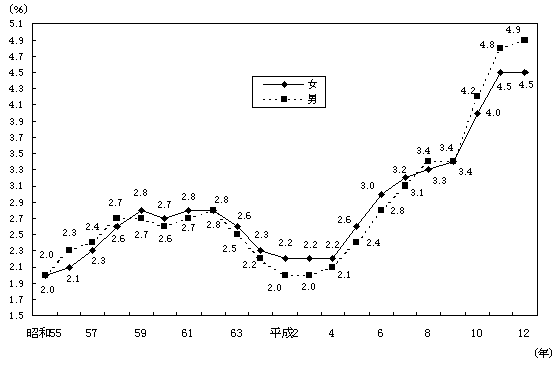 |
| 資料出所:総務省統計局「労働力調査」 |
(3) 雇用者
平成12年の女性雇用者数は2,140万人で、前年より24万人増加(前年比1.1%増)し、3年ぶりの増加となった。雇用者総数に占める女性の割合は前年に比べ0.3%ポイント上昇し、初めて40.0%になった。
産業別には、サービス業が783万人と最も多く、次いで卸売・小売業,飲食店(611万人)、製造業(402万人)となっており、これら3業種で女性雇用者の83.9%を占めている。サービス業、卸売・小売業,飲食店では前年より増加しているが、製造業では減少傾向が続いている(第1―4図)。
職業別にみると、事務従事者が730万人と最も多く、次いで、専門的・技術的職業従事者が342万人となった。専門的・技術的職業従事者は前年より10万人増加(前年比3.0%増)した。
雇用形態別にみると、常雇(常用雇用)が3年ぶりに5万人の増加となった一方で、臨時雇は21万人と引き続き大幅な増加となった。
平成11年の女性労働者の平均勤続年数は、8.5年と前年より0.3年長くなった。
| 第1―4図 雇用者数の推移(全産業) |
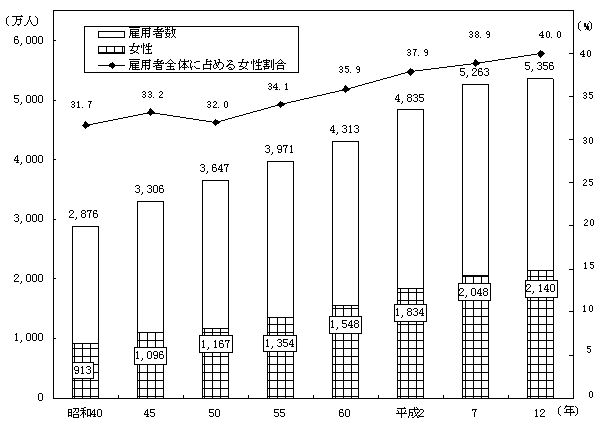 |
| 資料出所:総務省統計局「労働力調査」 |
(4) 労働市場の状況
平成11年の女性の入職者数(一般及びパートタイム労働者計)、離職者数はともに増加したが、就業形態別にみると、パートタイム労働者への入職者数(145万3,200人)が初めて一般労働者への入職者数(141万6,800人)を上回った。
平成12年3月の女性の新規学卒就職者総数に占める大卒の割合は36.1%と初めて高卒を上回って最大となった。
また、新規学卒労働市場の悪化により女性の大学卒業者の就職率は57.1%と前年より2.7%ポイントと低下した。なお、男性の大学卒業者の就職率は55.0%(11年60.3%、前年差5.3%ポイント減)と大幅に低下し女性の就職率をやや下回ったが、卒業者数から進学者数を除いた就職率では引き続き男性が女性を上回っている(女性61.9%、男性64.2%)。
2 景気停滞期の雇用動向
バブル崩壊以降今日まで景気は停滞基調が続いているが、この間については、さらに2つの景気後退期(平成3年2月〜平成5年10月、平成9年3月〜平成11年4月)が内閣府の景気循環判断から示されている。
こうした状況を踏まえ、以下では、平成3年から平成5年を「第1期」とし、また平成13年3月現在でも引き続き停滞状況であることから、平成9年から直近の平成12年を「第2期」として、男女の雇用動向の変化をみた。
(1) 女性で「非正規」化が進展した第2期
第1期の3年間では雇用者数は4.0%の増加となっているが、第2期の4年間では雇用者数は0.6%の減少となった。
男女別にみると、女性は第1期中に4.7%増、第2期中に0.6%増と、第2期には増加幅は縮小しているものの引き続き増加したが、男性は第1期中では増加(3.5%)し、第2期中では減少(-1.5%)している(第1―5図)。
| 第1―5図 雇用者数の各期間中の増減率 |
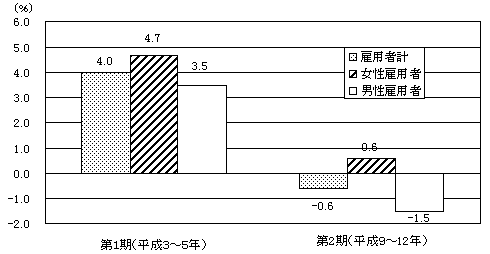 |
| 資料出所:総務省統計局「労働力調査」 |
ロ 第2期での「非正規化」は、特に女性雇用者で顕著
雇用形態別に、「正規の職員・従業員」(以下、「正規」という)とその他の雇用者(以下、「非正規」という)に分けて、「正規」、「非正規」別の各雇用者群が全体の増減率にどの程度の寄与をしたのか(寄与度)についてみると、雇用者全体では、第1期中の増加に対しては「正規」、「非正規」ともに増加に寄与していたが、第2期中の減少に対しては「正規」は減少に寄与し、「非正規」は増加に寄与するという相反する動きがみられた。
男女別にみると、第1期中では、「正規」の増加(寄与度2.6%)については男性の寄与度(2.0%)の方が女性(0.6%)よりかなり大きいのに対して、「非正規」の増加(同2.0%)については女性の寄与度(1.2%)の方が男性(0.8%)より若干大きい。
一方、第2期の「正規」の減少(寄与度-3.7%)については、男女ともその寄与は同程度である(女性-1.9%、男性-1.7%)のに対して、「非正規」の増加(同2.5%)については女性の寄与度(1.9%)の方が男性(0.6%)よりかなり大きい(第1―6図・7図)。
雇用者中の「正規」比率を男女別にみると、第1期中、第2期中ともに女性での低下幅が男性に比べて大きく、特に第2期中の女性雇用者の正規雇用者比率の低下幅(-4.6%ポイント)が大きい(第1―3表)。
| 第1―3表 第1期、第2期中の正規雇用者比率の変化 | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| 資料出所:総務省統計局「労働力調査特別調査」 | |||||||||||||||||||||||||||
ハ 第1期中の増加は「常雇」の増加、第2期中の減少は「常雇」の減少と「臨時雇」の増加が寄与
非農林業雇用者の従業上の地位別に「常雇」、「臨時雇」、「日雇」に分けて、各雇用者群の寄与度をみると、雇用者全体では、第1期中の増加には「常雇」の増加が大きく寄与するとともに「臨時雇」の増加も寄与していたのに対して、第2期中の減少には「常雇」の減少と「臨時雇」の増加という相反する寄与がみられた。
男女別にみると、第1期中の雇用者の増加率(4.0%)に対する女性雇用者の寄与度は1.8%、男性雇用者の寄与度は2.2%であるが、男女のどちらについても「常雇」の増加が大きく寄与(寄与度は、女性1.5%、男性2.1%)している。
| 第1―6図 第1期中の雇用者計に対する男女、雇用形態別寄与度 |
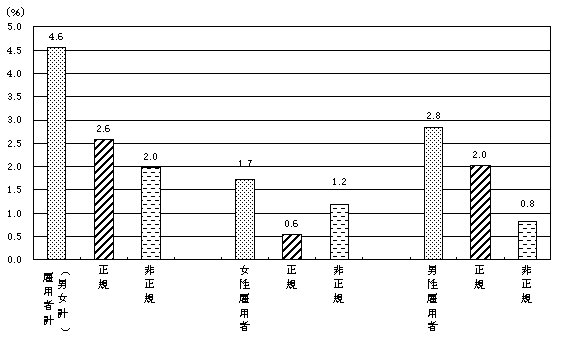 |
| 資料出所:総務省統計局「労働力調査特別調査」 |
| 第1―7図 第2期中の雇用者計に対する男女、雇用形態別寄与度 |
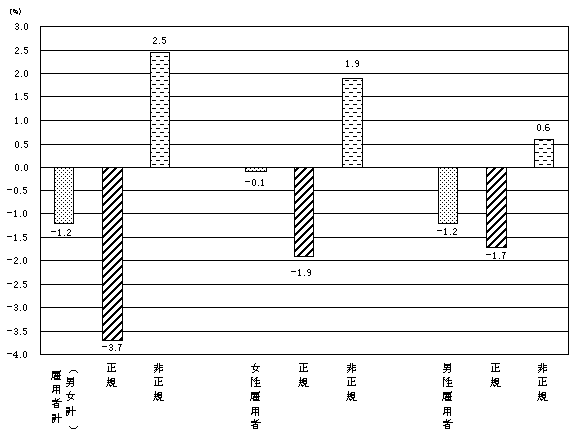 |
| 資料出所:総務省統計局「労働力調査特別調査」 |
第2期中の雇用者の減少率(-0.7%)に対しては、女性雇用者の増加(寄与度0.2%)と男性雇用者の減少(同-0.9%)が相まった結果となっているが、女性雇用者の増加には「臨時雇」の増加(寄与度0.9%)が、男性雇用者の減少には「常雇」の減少(同-1.4%)が大きく寄与している(第1―8図・9図)。
| 第1―8図 第1期中の雇用者計に対する男女、従業上の地位別寄与度 |
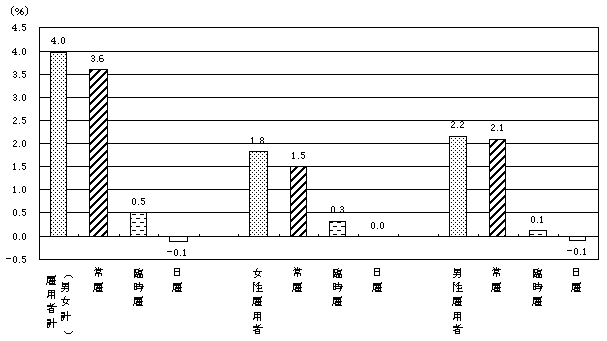 |
| 資料出所:総務省統計局「労働力調査特別調査」 |
| 第1―9図 第2期中の雇用者計に対する男女、従業上の地位別寄与度 |
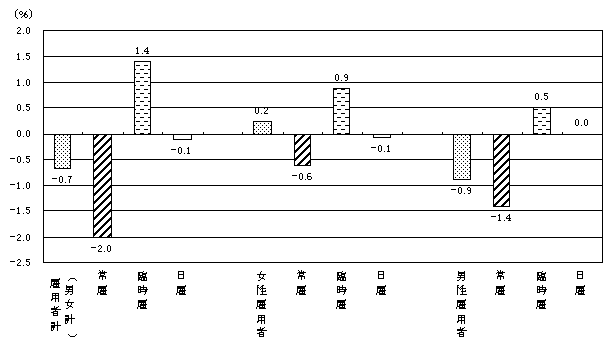 |
| 資料出所:総務省統計局「労働力調査特別調査」 |
(2) 男女別離入職状況
第1期、第2期(平成12年は集計中のため平成9〜11年)の各期間の期間平均離職率(各期間中の常用労働者に占める離職者の割合)をみると、第1期(14.6%)に比べ第2期(15.1%)は0.5%ポイント上昇している。
男女別に離職率をみると、第1期に比べ第2期では、女性労働者では0.2%ポイント (19.4%から19.2%へ)低下し、逆に男性労働者では1.0%ポイント(11.6%から12.6%へ)上昇し、この結果、男女間格差は縮小した。
特に、「出向等を除く経営上の都合」による離職は、第1期では女性労働者の方がやや高いものの、第2期では男女間格差はみられなくなっており、さらに、結婚、出産・育児、介護を除いた個人的な理由による離職(「純粋な個人的な理由」)についても、女性の方が離職率が高いが、第1期に比べ第2期では男女とも離職率は低下し、男女間格差も縮小(第1期:5.5%ポイント、第2期:5.0%ポイント)している(第1―10図)。
| 第1―10図 男女、離職理由別の期間平均離職率 | ||||
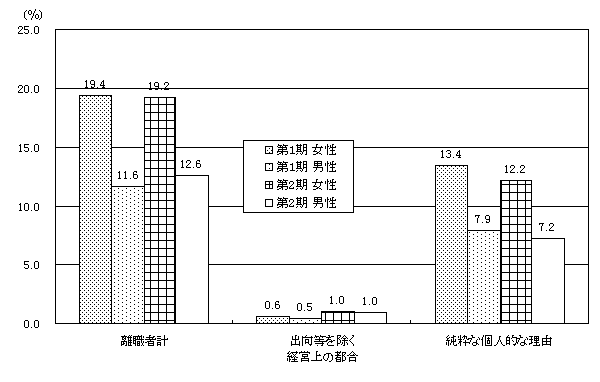 | ||||
| 資料出所:厚生労働省「雇用動向調査」 | ||||
|
ロ 入職率の低下と「入職のパート化」
期間平均入職率(各期間中の常用労働者に占める入職者の割合)をみると、労働者全体では第1期(15.6%)に比べ第2期(14.1%)では1.5%ポイント低下している。
さらに、一般労働者への入職者とパートタイム労働者への入職者に分けてみてみると、第1期に比べ第2期では、一般労働者の入職率は12.1%から9.9%へと大幅な低下(2.2%ポイント)をしているが、他方、パートタイム労働者の入職率は3.5%から4.2%とやや上昇(0.7%ポイント)している。この結果、入職者全体に占めるパートタイム労働者の比率は22.4%から29.9%へ上昇(7.5%ポイント)し、「入職のパート化」が進んだ(第1―11図)。
| 1―11図 男女別一般、パートタイム労働者への期間平均入職率 | ||||
| ||||
| 資料出所:厚生労働省「雇用動向調査」 | ||||
| ||||
ハ 学卒でもみられる「入職のパート化」
学卒者は男女のいずれでも、第1期、第2期ともにパートタイム労働者より一般労働者への入職率が高いが、一般労働者への入職率は第2期では低下し、その低下幅は女性で0.5%ポイント(1.5%から1.0%へ)、男性で0.2%ポイント(1.4%から1.2%へ)であり、男性に比べて女性でより大きくなっている。
一方、パートタイム労働者への入職率は、学卒女性では第1期(0.1%)に比べ第2期(0.2%)では0.1%ポイントの上昇がみられるが、学卒男性では第1期、第2期とも同水準(0.1%)である。
こうした結果、学卒男女の入職行動では一般労働者への入職率が低下したことから相対的に「入職のパート化」が進んでいるが、学卒女性ではパートタイム労働者への入職率の上昇もみられ、この傾向がより著しい(第1―12図)。
| 第1―12図 男女、学卒・非学卒別一般、パートタイム労働者への期間平均入職率 | |
| |
| 資料出所:厚生労働省「雇用動向調査」 |
(3) 勤労者家計の状況
勤労者家計の状況をみると、世帯主の勤め先収入の期間平均額(実質)は、第1期に比べ第2期にはやや減少(-0.6%)し、妻の勤め先収入は大きく増加(4.9%)した。
この結果、世帯主の勤め先収入に対する妻の勤め先収入の割合は、第1期(11.0%)に比べ第2期(11.7%)では0.7%ポイント上昇し、家計への貢献度が高まっている。
しかし、妻の勤め先収入が増えたとはいえ、世帯主及び妻の勤め先収入の合計額(実質)は、第1期の520,764円から第2期の520,459円に減少(-0.1%)しており、厳しい家計状況を反映して、平均消費性向(可処分所得に対する消費支出の割合)は第1期の74.4%に比べ第2期には71.7%へと2.7%ポイント低下しており、消費の切りつめがみてとれる(第1―4表)。
| 第1―4表 勤労者家計の状況 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 資料出所:総務省統計局「家計調査」 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
3 労働条件等の状況
平成11年の女性一般労働者(パートタイム労働者を除く。)のきまって支給する現金給与額は、23万700円(前年比1.7%増)で、そのうち所定内給与額は21万7,500円(同1.2%増)と、ともに前年より増加し、伸び率も前年を上回った。
4 パートタイム労働者の状況
平成12年における女性の短時間雇用者(非農林業で週間就業時間が35時間未満の雇用者)は754万人で、短時間雇用者総数に占める女性の割合は71.6%と7割を超えている。また、女性の非農林業雇用者2,089万人(休業者を除く)に占める短時間雇用者の割合は36.1%となっている。
また、平成11年における女性パートタイム労働者の平均勤続年数は4.9年で、前年に比べ0.1年伸長し、1時間当たりの所定内給与額は887円で、前年に比べ1円増加(対前年比0.1%増)した(第1―13図)。
| 第1―13図 短時間雇用者(週間就業時間35時間未満の者)数及び構成比の推移 ―非農林業― |
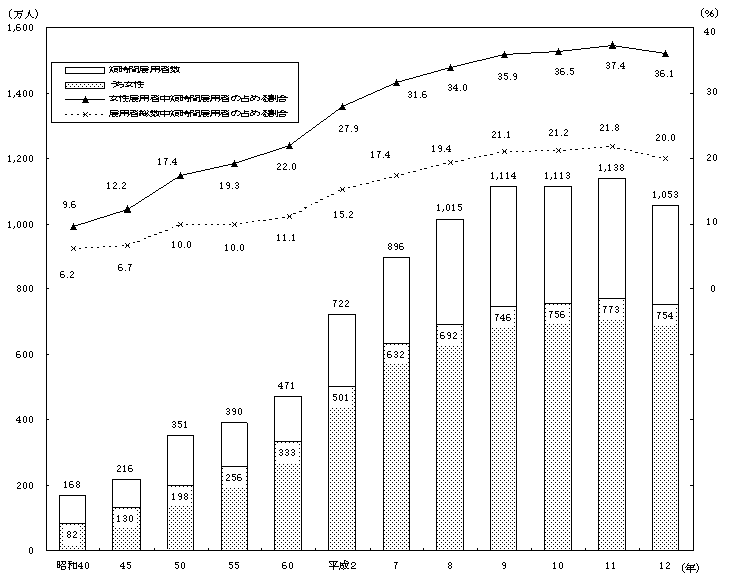 |
| 資料出所:総務省統計局「労働力調査」 注)雇用者数は休業者を除く。 |