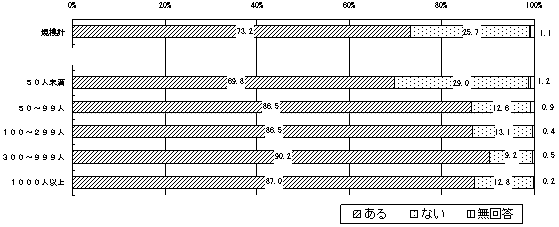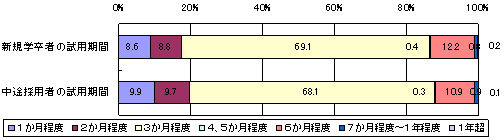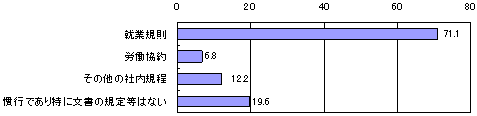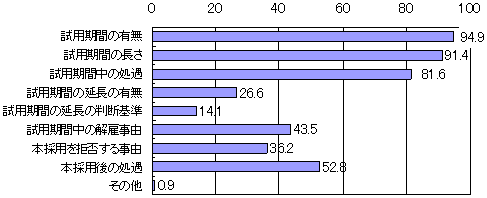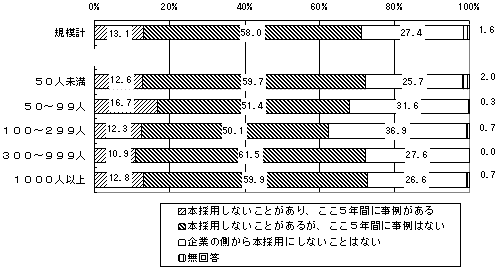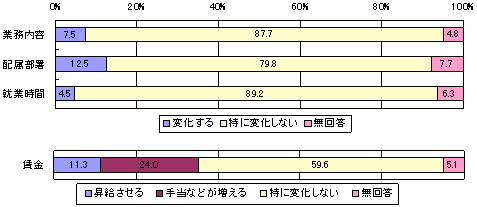| 【 | 試用期間であることを労働者が知らなかった例】 |
| 【 | 試用期間の長さ、延長が問題となった例】
期間の定めのない契約で雇い入れられた労働者が、入社して3か月が経過した時点で、「1か月試用期間を延長し、この間の勤務状況が不良であれば解雇を受け入れる」旨の誓約書への署名を求められた。就業規則には3か月間を試用期間とする旨の規定があるが、それまで労働者は、試用期間が設定されていることを知らなかった。
労働者は、上記の誓約書には署名をしたが、さらに1か月後、再度同様の書類に署名を求められた。労働者が納得いかずにこれを拒否したところ、合意退職扱いとされ、これにより経済的な損害を受けたとして補償金を求めたもの。
会社側は、労働者本人が就業規則に記載されている試用期間の定めをおそらく知らなかったということを認めた上で、改善の兆しはあるものの能力不足であるので試用期間の延長を申し入れたところ、労働者がこれを拒否したのであるから解雇ではないと主張した。
|
| 【 | 試用期間中に経費削減を理由として解雇された例】
労働者は、期間の定めのないパート社員として採用された。採用時に交付された労働条件通知書には、試用期間が3か月であることが明記されていた。
ところが、採用1か月半後に経費削減を理由として解雇されたため、労働者は納得がいかないとして慰謝料を請求したもの。
会社側は、解雇理由が労働者の勤務状況等ではなく会社全体の経費削減であることを認めた上で、試用期間中であり、解雇についての裁量権は会社にあると考えていると主張した。
|
| 【 | 裁判例:試用期間中は本採用後に比べて広い範囲の解雇の自由が認められるとされた例】(3頁と同一の事件)
労働者は、大学在学中に社員採用試験に合格し、大学卒業と同時に会社側に3ヶ月の試用期間を設けて採用された。
会社側は、労働者が、採用試験の際に提出を求めた身上書の所定の記載欄に虚偽の記載をし、または記載すべき事項を記載せず、面接試験における質問に対しても虚偽の回答をした(具体的には、学生時代に学生運動に関与した等の事実を秘匿した)ことを理由として、試用期間の満了直前に、本採用を拒否する旨の告知をしたもの。
判決では、「(試用期間中に労働者を不適格と認めたときは解約できる旨の)解約権の留保は、大学卒業者の新規採用にあたり、採否決定の当初においては、その者の資質、性格、能力その他上告人(会社側)のいわゆる管理職要員としての適格性の有無に関連する事項について必要な調査を行ない、適切な判定資料を十分に蒐集することができないため、後日における調査や観察に基づく最終的決定を留保する趣旨でされるものと解されるのであって、今日における雇傭の実情にかんがみるときは、一定の合理的期間の限定の下にこのような留保約款を設けることも、合理性をもつものとしてその効力を肯定することができるというべきである。それゆえ、右の留保解約権に基づく解雇は、これを通常の解雇と全く同一に論ずることはできず、前者については、後者の場合よりも広い範囲における解雇の自由が認められてしかるべきもの」とされた(三菱樹脂事件 昭和48年最高裁判決)。 |