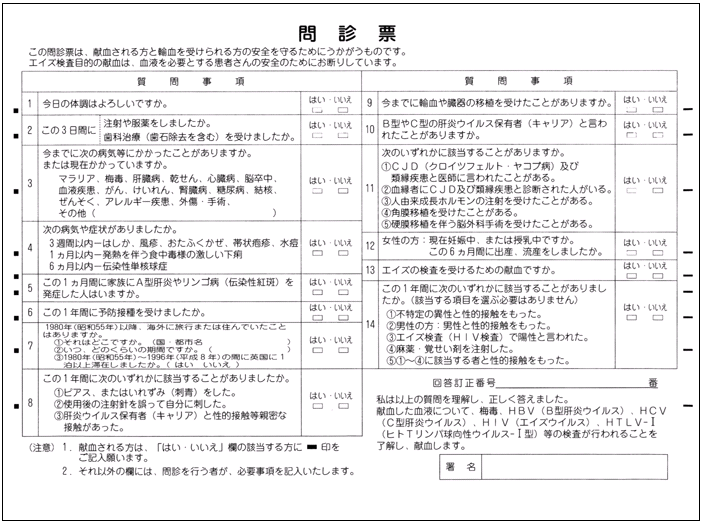�u�A���Ö@�̎��{�Ɋւ���w�j�v�i����āj
����17�N����
�����J���Ȉ��H�i�nj��t���
�ڎ�
| �� |
�u�A���Ö@�̎��{�Ɋւ���w�j�v�i����āj
|
�i�Q�l�j
�͂��߂�
�@�A���Ö@�́C�K���ɍs��ꂽ�ꍇ�ɂ͋ɂ߂ėL�������������Ƃ���C�L���s���Ă���B
�ߔN�C�i�i�̈��S��̐��i�ɂ��C�Ɖu���y�ъ������A������p�E�����ǂ͌������C�A���p���t�̈��S���͔��ɍ����Ȃ��Ă����B�������C�����̗A������p�E�����ǂ����₷�邱�Ƃ͂Ȃ�����ł���B���Ȃ킿�C�A���ɂ��ڐA�БΏh��a�iGVHD�j�C�A���֘A�}���x��Q�iTRALI�j�C�}���x����C�G���V�j�A�ہiYersinia enterocolitica�j�ɂ��s���ǂȂǂ̏d�Ăȏ�Q�C����Ɋ̉��E�C���X��q�g�Ɖu�s�S�E�C���X�iHIV�j�Ɋ���
���E�C���h�E��
���ɂ��鋟���҂���̊����C
�q�g�p���{�E�C���XB19��v���I���̊����Ȃǂ��V���ɖ�莋�����悤�ɂȂ��Ă����B�܂��C�s�K���A���ɂ��v���I�ȗn�������́C�܂�ł͂��邪�C�������Ă���Ƃ���ł���B
�@���̂悤�Ȃ��Ƃ���A���Ö@�̓K���ƈ��S��ɂ��ẮC��ɍŐV�̒m���Ɋ�Â����Ή������߂��
�C�A���ɂ��ď\���Ȓm���E�o����L�����t�̂��ƂŎg�p����ƂƂ��ɁC����p�������ɋً}���u���Ƃ�鏀�������Ă������Ƃ��d�v�ł����B
�@�����ŁC�@���̌��ɂ���ē���ꂽ���t�i�@�����j���܂߂āC�A���Ö@�S�ʂ̈��S������݂̋Z�p�����ɉ��������̂Ƃ���w�j�Ƃ��āu�A���Ö@�̓K�����Ɋւ���K�C�h���C���v�i�����Ȍ��N����ǒ��ʒm�C��������502���C�������N9��19���j�����肳�ꕽ��11�N�ɂ͉��肳��āu�A���Ö@�̎��{�Ɋւ���w�j�v�Ƃ��Đ��肳�ꂽ�B
�@�{�w�j�̍���̉���ł́C����11�N�̐����̗A���Ö@�̐i�����W�܂��C�����
�u���S�Ȍ��t���܂̈��苟���̊m�ۓ��Ɋւ���@���v�i���a31�N�@����160���G����15�N7���ꕔ�����{�s�j
��8���Ɋ�Â��C�u��ÊW�ҁv�͌��t���܂̓K���g�p�ɓw�߂�ƂƂ��ɁC���t���܂̈��S���Ɋւ�����̎��W�y�ђɓw�߂Ȃ���Ȃ�Ȃ���
���A���Ö@��K���ɍs����ł̏��K��Ɋ�Â��čČ������s���C�����������̂ł���B
| �� |
���������ŁC�R���E�R�̌����C�j�_���������iNAT�j���ʂ̉A���� |
�@�u��ÊW�ҁv�́C
| �� |
�@���萶���R�����i���g�p����ۂɂ́C���ޗ��ɗR�����銴���̃��X�N���ɂ��āC���i�̒��ӂ��K�v�����邱�Ƃ��\���F������K�v�����������i�u���S�Ȍ��t���܂̈��苟���̊m�ۓ��Ɋւ���@���v��9���Ɋ�Â��u���t���܂̈��S���̌���y�ш��苟���̊m�ۂ�}�邽�߂̊�{�I�ȕ��j�v��Z�y�ё掵�j�C
������C |
| �� |
�@���t���܂̗L�����y�ш��S�����̑����Y���i�̓K���Ȏg�p�̂��߂ɕK�v�Ȏ����ɂ��āC���Җ��͂��̉Ƒ��ɑ��C�K���\���Ȑ������s���C���̗������i���Ȃ킿�C���t�H�[���h�E�R���Z���g�j����悤�ɓw�߂Ȃ���Ȃ�Ȃ������i�@��68����7�j�C
�܂��C |
| �� |
�@���萶���R�����i�̎g�p�̑Ώێ҂̎����C�Z�����̑��K�v�Ȏ����ɂ��ċL�^���쐬���C�ۑ��i20�N�j���邱�Ɓi�@��68����9��3���y�ё�4���j
���K�v�ł���B |
�@�A���Ö@�̎�ȖړI�́C���t���̐Ԍ����Ȃǂ̍זE������Ìň��q�Ȃǂ̒`�����������ʓI�Ɍ������͋@�\�I�ɒቺ�����Ƃ��ɁC���̐������[���邱�Ƃɂ��Տ��Ǐ�̉��P��}�邱�Ƃɂ���B
���̖�܂̓��^�ɂ���Ď��Â��\�ȏꍇ�ɂ�����A���͋ɗ͔�����ׂ��ł���A���^����ꍇ�ɂ��K�v�ŏ��ʂɂƂǂ߂�ׂ��ł���B
| 2�j |
�A���ɂ��댯���Ǝ��Ì��ʂƂ̔�r�l�� |
�@�A���Ö@�ɂ͈��̃��X�N�����Ƃ���C���X�N��������ʂ����҂���邩�ǂ������\���ɍl�����C
�K���ƗA���ʂ����߂�ׂ��ł���B�K�������߂�B�A���ʂ͌��ʂ�������K�v�ŏ����ɂƂǂ߁C�ߏ�ȓ��^�͔�����B�܂��C���̖�܂̓��^�ɂ���Ď��Â��\�ȏꍇ�ɂ́C�A���͋ɗ͔����ėՏ��Ǐ�̉��P��}��B
| 3�j |
�����Ɠ��Ӂi�C���t�H�[���h�E�R���Z���g�j |
�@���Җ��͂��̉Ƒ��������ł��錾�t�ŁC
�A���Ö@�̕K�v���C�g�p���錌�t���܂Ǝg�p�ʁC�A���ɔ������X�N�₻�̑��̗A����̒��ӓ_�y�ю��Ȍ��A���̑I�����ɂ����A���Ö@�ɂ������ȉ��̍��ڂ��\���ɐ������C���ӂ���œ��ӏ����쐬���C�ꕔ�͊��҂ɓn���C�ꕔ�͐f�Ø^�ɓY�t���Ă����i�d�q�J���e�ɂ����Ă͓K�ɋL�^��ۊǂ���j�B
| �i1�j |
�A���Ö@�̕K�v�� |
| �i2�j |
�g�p���錌�t���܂̎�ނƎg�p�� |
| �i3�j |
�A���ɔ������X�N |
| �i4�j |
����p�E�����Nj~�ϐ��x�Ƌ��t�̏��� |
| �i5�j |
���Ȍ��A���̑I���� |
| �i6�j |
�����nj����ƌ��̕ۊ� |
| �i7�j |
���^�L�^�̕ۊǂƑk�y�������̎g�p |
| �i8�j |
���̑��C�A���Ö@�̒��ӓ_ |
| 1�j |
���t���܂̑I���C�p�@�C�p�� |
�@���t���̊e�����́C�K�v�ʁC���̓������C�Y�����Ȃǂ����ꂼ��قȂ�C�܂��C�̊O�Ɏ��o����ۑ����ꂽ�ꍇ�C���̋@�\�͐��̓��ɂ���ꍇ�Ƃ͈قȂ�B�A���Ö@�����{����Ƃ��ɂ́C���҂̕a�ԂƂƂ��Ɋe���t�����̎��@�\���\���l�����āC�A����̖ڕW�l�Ɋ�Â��C�g�p���錌�t���܂̎�ށC���^�ʁC�A���̉y�ъԊu�����߂�K�v������B
�@�ړI�ȊO�̐����ɂ�镛��p�⍇���ǂ�h���C�z�n�ւ̕��S���ŏ����ɂ��C����ꂽ�����ł��錌�t��L���ɗp���邽�߁C�S���A��������Č��t����
��p�����̕K�v�ʂ݂̂�₤�����A�����s���B
�@
�@���ł̎��{�Ǘ��̐����K���Ɋm�����Ă���ꍇ�́C�ł����S���̍����A���Ö@�ł��邱�Ƃ���C�A����v����O�Ȏ�p�i��ɑҋ@�I�O�Ȏ�p�j�ɂ����ĐϋɓI�ɓ������邱�Ƃ����������B�u���S�Ȍ��t���܂̈��苟���̊m�ۓ��Ɋւ���@���v�̎�|�ł���C�u���S���K���ȗA���v�̐��i�̂��߂ɂ��C���Ȍ��A���̕��y�͏d�v�ł���C
�A����v�����p�����I�Ɏ��{���Ă����Ë@�ւ͎��Ȍ��A�����X�^���_�[�h�ȗA����ÂƂ��Ē蒅�����邱�Ƃ����߂���B
�@�A���ɔ��������ǂ̃��X�N�����炷���߂ɁC���P�ʂ̗A���p���t�̎g�p�Ȃǂɂ��C�ł��邾�������҂̐������Ȃ�����B�Ԍ��������iMAP���Ԍ����Z���t�Ȃǁj�ƋÌň��q�̕�[��ړI�Ƃ��Ȃ��V�N���������Ƃ̕��p�͋ɗ͔�����ׂ��ł���B�i���t���܂̎g�p�w�j�Q�Ɓj
�@�V�N���������C�Ԍ����Z���t�C�A���u�~�����܋y�ь����Z���t�̓K���Ȏg�p���@�ɂ��ẮC���t���܂̎g�p�w�j�ɉ����čs���邱�Ƃ����������B
�@�A�����K���ɍs��ꂽ���Ƃ��������߁C�A���̕K�v��
�y���C�A���ʐݒ�̍���
��f�Ø^�ɋL�ڂ��C�y���A���O��̗Տ������ƌ����l�̐���
�����L�q���Ă�������A�����ʂ�]�����C�f�Ø^�ɋL�ڂ����B
�@�A���Ö@���s���ꍇ�́C�e��Ë@�ւ݂̍���ɉ������Ǘ��̐����\�z����K�v�����邪�C��Ë@�֓��̕����̕������ւ��̂ŁC���̂悤�Ȉ�т����Ɩ��̐����Ƃ邱�Ƃ����������B
�@�a�@�Ǘ��ҋy�їA���Ö@�Ɍg���e�E�킩��\�������C�A���Ö@�ɂ��Ă̈ψ������Ë@�֓��ɐ݂���B���̈ψ�������I�ɊJ�Â��C�A���Ö@�̓K���C���t���܁i�������搻�܂��܂ށj�̑I���C�A���p���t�̌������ځE�����p���̑I���Ɛ��x�Ǘ��C�A�����{���̎葱���C���t�̎g�p�����C�Ǘጟ�����܂ޓK���g�p���i�̕��@�C�A���Ö@�ɔ������́E����p�E�����ǂ̔c�����@�Ƒ�C�A���֘A���̓`�B���@��@���̌��̊�⎩�Ȍ��A���̎��{���@�ɂ��Ă���������
�ƂƂ��ɁA���P�ɂ��Ē���I�Ɍ�����B�܂��C��L�Ɋւ���c���^���쐬�E�ۊǂ��C�@���Ɏ��m����B
�@�a�@���ɂ�����A���Ɩ��̑S�ʂɂ��āC������̊ēy�ѐӔC������t��C������B
�@�A���Ö@�����I�ɍs���Ă����Ë@�ւł́C�A�������ݒu���C�ӔC��t�̊ē̉��ɗA���Ö@�ψ���̌������������{����ƂƂ��ɁC
�A���Ɋ֘A���錟���̂ق��C���t���܂̐����E�ۊǁE
���o�����̎����I�Ɩ����܂߂Ĉꊇ�Ǘ����s���C�W���I�ɗA���Ɋւ��邷�ׂĂ̋Ɩ����s���B
�@�A��
�����Ɩ��S�ʁi�A�������Ɛ��܊Ǘ����܂ށj�ɂ�����
�\���Ȓm�����o�����L�x�ȗՏ��i���͉q���j�����Z�t���A�������Ɩ��̎w�����s���C����ɗA�������͌����Z�t��24���ԑ̐��Ŏ��{���邱�Ƃ��]�܂����B
�@�A���p���t�̍̌����s���ꍇ�ɂ́C�����Ҏ��g�̈��S�m�ۂƎ҂ł��銳�҂ւ̊����Ȃǂ̃��X�N��\�h���邽�߁C�����҂̖�f���\���ɍs���C�E�C���X�ȂǂɊ������Ă���댯���̍��������҂������K�v������B���Ƀq�g�Ɖu�s�S�E�B���X�iHIV�j�����ɂ��ẮC�����҂̗��������߂Ȃ��犴���̊댯��������s�ׂ����s�����҂����O����B
�@�̌����ꂽ���t�ɂ��ẮCABO���t�^�CRho�iD�j�R���C�ԐڍR�O���u�����������܂ޕs�K���R�̃X�N���[�j���O�̊e�������s���B����ɁCHBs�R���C
�RHBs�R�́C
�RHBc�R�́C
�RHCV�R�́C
�RHIV-1�C-2�R�́C
�RHTLV-I�R�́C
HBV�CHCV�CHIV-1
�ɑ����j�_���������iNAT�j�����C�~�Ō��������y��ALT�iGPT�j�̌������s���B
| �@��: |
�A���p���t�̈��S�����m�ۂ��邽�߁C�����Ƃ��ē��{�ԏ\���Ђ̌��t�Z���^�[�ōs���Ă�����̂Ɠ��l�̌���������B�Ȃ��C��L�ɉ����āC�q�g�p���{�E�C���XB19�����CHBV�CHCV�CHIV-1�j�_������������{�ԏ\���Ђ̌��t�Z���^�[�ł͎��{���Ă��邪�C�q�g�p���{�E�C���XB19�����͐����R��������ɂ͋L�ڂ���Ă��Ȃ��B |
�@���������Ă���҂ɂ��ẮC�����L2�D�̑S���ڂ̌������s���B���t�^���O��̌������ʂƕs��v�ł���ꍇ�ɂ́C�K��
�V���ɍ̌����ꂽ���̂�p�����Č������s���C���̌������������C���̂��Ƃ��L�^����B
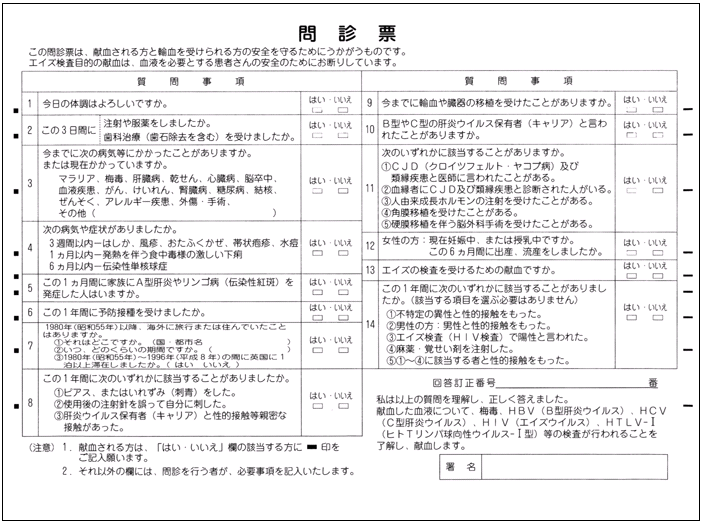
�@�R������Ɗ����̋@������������邽�߁C�\�Ȍ��荂�P�ʂ̗A���p���t�����C���Ȃ킿2�P�ʂ̐Ԍ����Z���t�C�����̌��R���̐V�N����������
�����Z���t���g�p����B
�@�A����ڐA�БΏh��a�̗\�h�ɂ́C�����p�����܂ޗA���p���t�ɕ��ː��Ǝ˂����ėp���邱�Ƃ�
�L���ł���B�S�Ǝ˖�ɍŒ��15Gy�i50Gy���z���Ȃ��j�̕��ː��Ǝ˂��s���Ďg�p����B�Ǝˌ�̐Ԍ���
�����i�S�����܂ށj�ł͏㐴���̃J���E���C�I�����㏸���邱�Ƃ���C�V�����E���n���E�����C�t�s�S���ҋy�ы}����ʗA�����҂ɂ��ẮC�Ǝˌ㑬�₩�Ɏg�p���邱�Ƃ��]�܂����B
|
IV |
�@���҂̌��t�^�����ƕs�K���R�̃X�N���[�j���O���� |
�@���ҁi�ҁj�ɂ��ẮC�s�K���A����h�����߁C
�A�������{�����Ë@�ւŐӔC���������ȉ��̌������s���B
�@ABO���t�^�̌����ɂ́C�RA�y�эRB�����p���Ċ��Ҍ�����A�y��B�R���̗L���ׂ�C������I���e�������s���ƂƂ��ɁC���m��A�y��B������p���Ċ��Ҍ������̍RA�y�эRB�R�̗̂L���ׂ�C������E���������s��Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�I���e�����ƃE�������̈�v���Ă���ꍇ�Ɍ��t�^���m�肷�邱�Ƃ��ł��邪�C��v���Ȃ��ꍇ�ɂ͂��̌���������K�v������B
�@
���ꊳ�҂���̈قȂ鎞�_�ł�2���̂ŁC��d�`�F�b�N���s�����Ƃ��]�܂����K�v�������B
�@���ꌟ�̂ɂ��ĈقȂ�2�l�̌����҂����ꂼ��Ɨ��Ɍ������C��d�`�F�b�N���s���C�ƍ��m�F����
���Ƃ��]�܂����悤�ɓw�߂��B
�@�RD�����p����Rho�iD�j�R���̗L������������B���̌������A���̊��҂̏ꍇ�ɂ́C�R���A���Ƃ��Ď�舵���C
�ԐڍR�O���u���������ɂ��㔽������D�^�iD weak�܂���DU�^�j�̌���D�R���m�F�����͍s��Ȃ��Ă��悢�B
| 3�D |
�s�K���R�̃X�N���[�j���O���� |
�@�ԐڍR�O���u�����������܂ޕs�K���R�̂̃X�N���[�j���O�������s���B�s�K���R�̂����o���ꂽ�ꍇ�ɂ́C���莎�����s���B
�Ȃ��C37���Ŕ�������Տ��I�ɈӋ`�i����p���������\���j�̂���s�K���R�̂����o���ꂽ�ꍇ�ɂ́C���҂ɂ��̎|���L�ڂ����J�[�h���펞�g�т����邱�Ƃ��]�܂����B
�@����4�����ȓ��̓����ł́C��e�R���̈ڍs�R�̂����邱�Ƃ⌌�����̍RA�y�эRB�R�̂̎Y�����s�\���ł��邱�Ƃ���CABO���t�^�̓I���e�����݂̂̔���ł悢�BRho�iD�j�R���ƕs�K���R�̃X�N���[�j���O�̌����͏�L2�C3�Ɠ��l�ɍs�����C�s�K���R�̂̌����ɂ͊��҂̕�e�R���̌�����p���Ă��ǂ��B
|
V |
�@�s�K���A����h�����߂̌����i�K�������j����т��̑��̗��ӓ_ |
�@�K�������ɂ́CABO���t�^�CRho�iD�j�R���y�ѕs�K���R�̃X�N���[�j���O�̊e�����ƗA���O�ɍs��������K�������i�N���X�}�b�`�j�Ƃ�����B
| 1�j |
���t�^�ƕs�K���R�̃X�N���[�j���O�̌��� |
�@ABO���t�^��Rho�iD�j�R���̌�����IV-1�C2�C�s�K���R�̃X�N���[�j���O������IV-3�Ɠ��l�ɍs���B
| 2�j |
�����K�������i�N���X�}�b�`�j |
�@
�����Ƃ��āCABO���t�^�������̂Ƃ͕ʂ̎��_�ō̌��������̂�p���Č������s���B
�@�����K������
�i�N���X�}�b�`�j�ɂ́C���҂�ABO���t�^�����^�̌��t�i�ȉ��CABO���^���Ƃ����j��p����B����ɁC���҂�Rho�iD�j�A���̏ꍇ�ɂ́CABO���t�^�����^�ŁC����Rho�iD�j�A���̌��t��p����B
�@�Ȃ��C���҂�37���Ŕ�������Տ��I�ɈӋ`�̂���s�K���R�̂������Ă��邱�Ƃ����炩�ȏꍇ�ɂ́C�Ή�����R���������Ȃ����t��p����B
�܂��C���҂̌��t�^�ƗA�����錌�t���܂̌��t�^���R���s���[�^��ŏƍ��m�F����R���s���[�^�N���X�}�b�`�p���邱�Ƃ��L�p�ł���B���̏ꍇ�C���t�Z���^�[���狟������錌�t���܂Ƀ��x������Ă��錌�t�^���Ċm�F���Ă������Ƃ��]�܂��B
�@�����K������
�i�N���X�}�b�`�j�ɂ́C���Ҍ����Ƌ����Ҍ����̑g�ݍ��킹�̔����ŋÏW��n���̗L���肷��厎���Ɗ��Ҍ����Ƌ����Ҍ����̑g�ݍ��킹�̔����肷�镛�����Ƃ�����B�厎���͕K���C���{���Ȃ���Ȃ�Ȃ��B
�@�p���Ƃ��ẮCABO���t�^�̕s�K�������o�ł��C����37���Ŕ�������Տ��I�ɈӋ`�̂���s�K���R�̂����o�ł���ԐڍR�O���u�����������܂ޓK���ȕ��@��p����B�Ȃ��C
�Տ��I�Ӌ`�̂���s�K���R�̂ɂ���厎����
�z���i�s�K���j�ł��錌�t��A���ɗp���Ă͂Ȃ�Ȃ��B
| �i4�j |
�R���s���[�^�N���X�}�b�` |
�@
���炩����ABO���t�^�CRho�iD�j�R���^�����ƍR�̃X�N���[�j���O�����ɂ��C�Տ��I�ɖ��ƂȂ�R�̂����o����Ȃ��ꍇ�ɂ́C�����K���������ȗ����CABO���t�^�̓K�������m�F���邱�ƂŗA���͉\�ƂȂ�B
�@
�R���s���[�^�N���X�}�b�`�Ƃ́C�ȉ��̊e���������S�ɖ��������ꍇ�ɃR���s���[�^��p���ď�q�����K�������m�F������@�ł���C�l�דI�Ȍ��̔r���ƁC�菇�̍������C�ȗ͉����\�ł���B�K�v�ȏ����́C�ȉ��̂Ƃ���B
| �@(1) |
�@���ʂ̕s��v��܂̑I��������Ă���ۂɂ͌x�����邱�� |
| �@(2) |
�@���҂̌��t�^��2��ȏ�قȂ錟�̂ɂ��m�F����Ă��邱�� |
| �@(3) |
�@���܂̌��t�^���Ċm�F����Ă��邱�� |
�i4�@5�j |
�����ł̓K�����̑I�� |
�@4�����ȓ��̓����ɂ��Ă��C�����Ƃ���ABO���^����p���邪�CO�^�ȊO�̐Ԍ���
������p����ꍇ�ɂ́C�RA���͍RB�R�̗̂L�����ԐڍR�O���u�����������܂ތ����K�������i�厎���j�Ŋm�F���C�K������Ԍ���
������A������B�܂��C�s�K���R�̗z���̏ꍇ�ɂ́i1�j�C�i2�j�Ɠ��l�ɑΏ�����B
�@�����K������
�i�N���X�}�b�`�j�̎��{�ꏊ�́C���ʂȎ���̂Ȃ�����C���҂̑������Ë@�֓��ōs���B
�@�ً}�ɐԌ����̗A�����K�v�ȏo�����V���b�N��Ԃɂ���~�}���҂ɂ��āC�����Ɋ��҂̌����p���t���̎悷�邱�Ƃɓw�߂邪�C�̌��s�\�ȏꍇ�ɂ͏o���������t�������ɗ��p���Ă��ǂ��B�A���p���t���܂̑I���͏ɉ����Ĉȉ��̂悤�ɑΏ����邪�C
���t�^�̊m��O�ɂ�O�^�̐Ԍ��������̎g�p�i�S���͕s�j
�C���t�^�m���ɂ�ABO���^���̎g�p�������Ƃ���B
| 1�j |
ABO���t�^�m�莞�����^�̌��t�̎g�p |
�@���҂̍ŐV�̌��t�����̂Ƃ��āCABO���t�^�y��Rho�iD�j�R���̔�����s���C������ABO���^���ł���Ԍ���
�����i�܂��͑S��
�j��A������B�A���ƕ��s���āC�������������K�����������{����B
| 2�j |
���t�^���m��ł��Ȃ��ꍇ��O�^�Ԍ��������̎g�p |
�@�o�����V���b�N�̂��߁C���҂�ABO���t�^�肷�鎞�ԓI�]�T���Ȃ��ꍇ�C���^�����s�������ꍇ�C�ً}���Ɍ��t�^����p���Ȃ��ꍇ�C���邢�͌��t�^���肪����ȏꍇ��
�C��O�I��O�^�Ԍ���
�������g�p����i�S���͕s�j�B
| �@���F |
O�^�̐Ԍ��������𑊓��ʗA��������ɁC���҂�ABO���^���̗A���ɕύX����ꍇ�́C�V���ɍ̎悵���ŐV�̊��Ҍ��t�ƌ����K�������i�N���X�}�b�`�j�̎厎�����H���t�@�i�v���@�C�����j�ōs���C�K�����錌�t��p����B |
| 3�j |
Rho�iD�j�R�����A���̏ꍇ |
�@Rho�iD�j�R�����A���Ɣ��������Ƃ��́CRho�iD�j�A���̌��t�̓���ɓw�߂�B
Rho�iD�j�A����D�悵��ABO���t�^�ٌ͈^�ł��邪�K���̌��t�i�ٌ^�K�����j���g�p���Ă��悢�B���Ɋ��҂��������͔D�P�\�ȏ�����Rho�iD�j�z���̌��t��A�������ꍇ�́C�ł��邾������Rho�iD�j�A���̌��t�ɐ�ւ���B
�@
�Ȃ��C48���Ԉȓ��ɕs�K���R�̌��������{���RD�R�̂����o����Ȃ��ꍇ�́C�RD�Ɖu�O���u�����̓��^���l������B
| �@���F |
���{�l�ł�Rho�iD�j�A���̕p�x�͖�0.5%�ł���B |
�@�}�ɗA�����K�v�ƂȂ����Ƃ��ɁC�����K������
�i�N���X�}�b�`�j�����{�̌��t
�C���t�^�����{����O�^�Ԍ������g�p�����ꍇ���邢��Rho�iD�j�A�����҂�Rho�iD�j�z���̌��t��A�������ꍇ�ɂ́C�S����t�͋~����ɂ��̎��R�y�ї\�z����鍇���ǂɂ��āC���҂܂��͂��̉Ƒ��ɗ������₷�����t�Ő������C���ӏ��̍쐬�ɓw�߁C���̌o�܂�f�Ø^�ɋL�ڂ��Ă����B
�@��ʗA���Ƃ́C24���Ԉȓ��Ɋ��҂̏z���t�ʂƓ��ʖ��͂���ȏ�̗A�����s���邱�Ƃ������B�o��
�ʋy�����x
�Ȃ��̏ɉ����Ď��̂悤�ɑΏ�����B
| 1�j |
�lj��A�����̌����K�������i�N���X�}�b�`�j |
�@��p���̒lj��A���Ȃǂő�ʗA�����K�v�ƂȂ������҂ɂ��ẮC�����ΊԐڍR�O���u���������ɂ������K������
�i�N���X�}�b�`�j���s�����ԓI�]�T���Ȃ��ꍇ������B���̂悤�ȏꍇ�ɂ͏��Ȃ��Ƃ������H���t�@�ɂ��厎���i�v���@�C�����j���s���CABO���t�^�̊ԈႢ�����͋N�����Ȃ��悤�ɔz������B����CABO���^�������ł��Ȃ��ꍇ�ɂ�2-2�j
�C4�j�܂��C���҂�Rho�iD�j�A���̏ꍇ�ɂ�2-3�j�ɏ����đΏ����Ă��悢���C2-
5 4�j�̋L�ڎ����ɗ��ӂ���B�����K�������p�̌��t���̂́C�ł��邾���V�����̌��������̂�p����B
�@�ً}�ɑ�ʗA����K�v�Ƃ��銳�҂ŁC���O�ɗՏ��I�ɈӋ`�̂���s�K���R�̂����o���ꂽ�ꍇ�ł����Ă��C�Ή�����R���A���̌��t���Ԃɍ���Ȃ��ꍇ�ɂ́C��L1�j�Ɠ��l��ABO���^����A�����C�~����ɗn��������p�ɒ��ӂ��Ȃ��犳�҂̊ώ@�𑱂���B
�@
��L�̂悤�ȏo�����V���b�N���܂ޑ�ʏo�����ł́C���ɓ��^�Ԍ��������A�������ł͑Ή��ł��Ȃ����Ƃ�����B���̂悤�ȏꍇ�ɂ͋~������Ƃ��čl���CO�^�Ԍ������܂ތ��t�^�͈قȂ邪�C�K���ł���Ԍ��������i�ٌ^�K�����j���g�p����B
�@
�������C�g�p�ɂ������ẮC3�|1�j�������炷��B
�q���Ҍ��t�^���m�肵�Ă���ꍇ�r
| ���҂`�a�n���t�^ |
�ٌ^�ł��邪�K���ł���Ԍ��� |
| �n |
�Ȃ� |
| �` |
�n |
| �a |
�n |
| �`�a |
�n�C�`�C�a |
�q���Ҍ��t�^�����m��̏ꍇ�r
�@
O�^
| 4�D |
�����K�������i�N���X�}�b�`�j�̏ȗ� |
| 1�j |
�Ԍ��������ƑS���̎g�p�� |
�@�����҂̌��t�^�������s���C�ԐڍR�O���u�����������܂ޕs�K���R�̃X�N���[�j���O�������A���ł���C�����҂̌��t�^�������K���ɍs���Ă���C
ABO���^���g�p�����������͏ȗ����Ă��悢
���CABO���^�����g�p�����B
�@��L1�j�Ɠ��l�ȏ����̂��ƂŁC����4�����ȓ��̓����ōRA���邢�͍RB�R�̂����o���ꂸ�C�s�K���R�̂��A���̏ꍇ�ɂ́C
ABO���^���g�p���������K�������͏ȗ�����
���悢
���C�B
�@
�Ȃ��CABO���^
�����g�p����Rho�iD�j�R���A���̊����ɂ�Rho�iD�j�R���A�����^����A������B
�@
�܂��C���̕s�K���R�̂̌����ɂ��ẮC��e�R���̌�����p���Ă��悢�B
| 3�j |
�����Z���t�ƐV�N���������̎g�p�� |
�@�Ԍ������قƂ�NJ܂܂Ȃ������Z���t�y�ѐV�N���������̗A���ɓ������ẮC�����K�������͏ȗ����Ă悢�B�������C�����Ƃ���ABO���^�����g�p����B
�@�Ȃ��C���҂�Rho�iD�j�A���ŏ����D�P�̉\���̂��銳�҂Ɍ����A�����s���ꍇ�ɂ́C�ł��邾��Rho�iD�j�A���R���̂��̂�p����BRho�iD�j�z���̌����Z���t��p�����ꍇ�ɂ́C�RD�Ɖu�O���u�����̓��^�ɂ��RD�R�̂̎Y����\�h�ł��邱�Ƃ�����B
�@
�V���ȗA���C�D�P�͕s�K���R�̂̎Y���𑣂����Ƃ����邽�߁C�ߋ�3�����ȓ��ɗA�����܂��͔D�P��������ꍇ�C���邢�͂���炪�s���Ȋ��҂ɂ��āC�����K�������ɗp���錌�t���̂͗A���\����O3���ȓ��ɍ̌�����
�����̂ł��邱�Ƃ��]�܂����B
| 2�j |
�ʌ��̂ɂ��_�u���`�F�b�N |
�@
���̂̎��Ⴂ�ɂ��ߌ�A����\�h���邽�߁C�����K������
�̍���������
�����̂����t�^�̌���
�Ɏg�p�����������̂Ƃ͕ʂɁC�V�����̌�����
����������p��
�āC���������t�^�������ēx�����{����B
| 6�D |
�s�K���A����h�����߂̌����ȊO�̗��ӓ_ |
|
1�j |
���t�^�����p�����̍̌����̎��������ɒ��ӂ��邱�ƁB |
�@
���t�^�����p���̂��̌����~�X���Ⴂ�����t�^���������~�X�ɂȂ��邱�Ƃ������邱�Ƃ����C���t�^�̔���͈قȂ鎞���̐V�������̂�2����{���C����̌��ʂ�����ꂽ�Ƃ��Ɋm�肷�ׂ��ł���B���̂̎��Ⴂ�ɂ́C�̌����҂̌��i������ׂ̃x�b�h�̊��҂���������Ȃǁj�ƁC���̊��Җ����X�s�b�c�̌����ɊԈ���č̌��������̂ł������̎��Ⴂ�������B�O�҂ɂ��ẮC���t�^�����p�̍̌��̍ۂ̊��Ҋm�F���d�v�ł���B��҂ɂ��ẮC�菑���ɂ�郉�x�����Җ��̏����ԈႢ�̑��C���̍̌��ȂǂŁC�������҂̍̌��X�s�b�c�������������Ȃ��珇���̌����āC�X�s�b�c�̌��������Ⴆ�邱�Ƃ�����B�����������X�s�b�c�̌����������Ǘ��ĂȂǂɕ��ׂč̌�������@�́C�̌��X�s�b�c�������Ⴆ��댯������̂��C������ׂ��ł���B1���ҕ������݂̂��̌��X�s�b�c�����܂Ƃ��Ă����Ȃ���Ȃ�Ȃ��p�ӂ��̌������B
| 2�j |
�������ʂ̓`�[�ւ����L�ڃ~�X���������~�X�ɒ��ӂ��邱�ƁB |
�@
���t�^����͐������Ă��C���茋�ʂ�`�[�ɋL�ڂ���ۂ���͂���ۂɊԈႦ��댯�������邱�Ƃ���C�ʐl��l�̌������ɂ���`�F�b�N�m�F���s�����Ƃ��]�܂����B
�@
�܂��C�R���s���[�^�V�X�e����p�������ʓ��͂̊m�F���L���ł���B
| 3�j |
�������ʂ̋L�^�Ɗ��҂ւ̒ʒm |
�@
���t�^���茋�ʂ͓]�L�����ɁC�f�Ø^�ɓ\�t����ƂƂ����l���ɗ��ӂ����҂ɒʒm����B
| 4�j |
�ȑO�̌������ʂ̓]�L�~�X������`�B�̌��ɂ��댯���ɒ��ӂ��邱�ƁB |
�@
�ȑO�Ɏ��{���ꂽ���t�^�������ʂ𗘗p����ꍇ�ɂ́C�O����@���̐f�Ø^����̌��t�^�������ʂ�]�L����ۂ��~�X����C�d�b�ɂ�錌�t�^�̖₢���킹�̍ۂ̓`�B�~�X�̌��������B�]�L������ł̌��t�^�̓`�B���~�X�ԈႢ���N���₷�����Ƃ���C�\�t�������茋�ʗp�����m�F����K�v������B
|
VI |
�@��p�����͒����ɗA������\���̏��Ȃ��ꍇ�̌��t���� |
�@���t�ʂɂ����C�܂��A���Ɩ��������I�ɍs�����߂ɁC�ҋ@�I��p����܂߂Ē����ɗA������\���̏��Ȃ��ꍇ
�ɂ��̌��t�������@�Ƃ����C���t�^�s�K���R�̃X�N���[�j���O�@�i�^�C�v�A���h�X�N���[���FT&S�j�ƍő��p���t�����ʁiMSBOS�j���̗p���邱�Ƃ��]�܂����B
| 1�D |
���t�^�s�K���R�̃X�N���[�j���O�@(Type & Screen �@;T & S�@) |
�@
�ҋ@�I��p����܂߂āA�����ɗA������\�������Ȃ��Ɨ\�������ꍇ�C�҂�ABO���t�^�CRho�iD�j�R���y�сC�Տ��I�ɈӋ`�̂���s�K���R�̗̂L�������炩���ߌ������CRho�iD�j�z���ŕs�K���R�̂��A���̏ꍇ�͎��O�Ɍ����K������
�i�N���X�}�b�`�j���s��Ȃ��B�ً}�ɗA���p���t���K�v�ɂȂ����ꍇ�ɂ́C
�A���p���t���I���e�����ɂ��ABO���^���ł��邱�Ƃ��m�F���ėA�����邩�C���邢�͐����H���t�@�i�v���@�C�����j�ɂ��厎�����K���̌��t��A������B���́C�\�߃I���e�����ɂ��m�F����Ă��錌�t���܂̌��t�^�Ɗ��҂̌��t�^�Ƃ��R���s���[�^��p���ďƍ��E�m�F���ėA�����s���i�R���s���[�^�N���X�}�b�`�j�B
| 2�D |
�ő��p���t�����ʁiMaximal Surgical Blood Order Schedule ; MSBOS�j |
�@�m���ɗA�����s����Ɨ\�������ҋ@�I��p��ł́C�e��Ë@�ւ��ƂɁC�ߋ��ɍs������p�Ⴉ��
��p�p���ʂ̗A���ʁiT�j�Ə������t�ʁiC�j�ׁC���҂̔�iC/T�j��1.5�{�ȉ��ɂȂ�悤��
�ʂ����t�������K������
�i�N���X�}�b�`�j���s����
���O����������B
| 3�D |
��p���t�����ʌv�Z�@�iSurgical Blood Order Equation ; SBOE�j |
�@
�ߔN�C���ҌŗL�̏����������C��薳�ʂ̏��Ȃ��v�Z�@������Ă���B���̕��@�́C���҂̏p�O�w���O���r���iHb�j�l�C���҂̋��e�ł���A���J�nHb�l�i�g���K�[�GHb7�`8g/dL�j�C�y�яp���ʂ̕��ϓI�ȏo���ʂ�3�̐��l����C���ҌŗL�̌��t�����ʂ����߂���̂ł���B�͂��߂ɏp�OHb�l���狖�e�A���J�nHb�l�������C���҂̑S�g��Ԃ����e�ł��錌�t�r���ʁi�o���\���ʁj�����߂�B�p���ʂ̕��ϓI�ȏo���ʂ���o���\���ʂ������C�P�ʐ��Ɋ��Z����B���̌��ʁC�}�C�i�X���邢��0.5�ȉ��ł���CT&S�̑ΏۂƂ��C0.5���傫����Ύl�̌ܓ����Đ����P�ʂ�������������ł���B
�@���S�����ʓI�ȗA���Ö@���ߌ�Ȃ����{���邽�߂ɁC���̊e���ڂɒ��ӂ���K�v������B
�@
�܂��A�A�����{�̎菇�ɂ��āA�m�F���ׂ��������܂Ƃ߂��A�����{�菇�������m���A���炷�邱�Ƃ��L�p�ł���i�A�����{�菇���Q�Ɓj�B
�@�e��̗A���p���t�́C���ꂼ��ł��K�����������ŕۑ����Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�Ԍ���
�����C�S����2�`6���C�V�N����������-20���ȉ��ŁC���L���x�L�^�v�ƌx�u���t�����A���p���t��p�ۗ̕�ɒ��ł��ꂼ��ۑ�����B
�@�����Z���t�͂ł��邾�����₩�ɗA������B�ۑ�����ꍇ�́C�����i20�`24���j��
�����U�
���Ȃ����ۑ�����B
�@���x�Ǘ����s�\���ȏ�Ԃł́C�A���p���t�̊e�����͋@�\�ቺ�𗈂��₷���C���̊��҂ւ̓]�p���ł��Ȃ��Ȃ�B
���t�����A���p���t�̕ۊǁE�Ǘ��́C�@���̗A������ňꊇ���ďW���I�ɊǗ�����ׂ��ł���B�a�����p���Ȃǂɂ͎��ۂɎg�p����܂Ŏ����o���Ȃ����Ƃ������Ƃ���B�����o������͂ł��邾�������g�p���邪�C��p���Ȃǂ�30���ȏ㌌�t���茳�ɒu���ꍇ�ɂ��C��L1�j�Ɠ��l�̏������ŕۑ�����B
| �@���F |
���t�����A���p���t�̕ۊǁE�Ǘ��ɂ��Ắu���t���ܕۊNJǗ��}�j���A���i�����ȖǁC����5�N9��16���j�v���Q�ƁB�������C�����������邱�Ƃ�����̂ōŐV�̃}�j���A�����Q�Ƃ���K�v������B |
�@���҂ɗA���������t���͊Ō�t�́C�A���̎��{�O�ɊO�ό����Ƃ��ăo�b�O���̌��t�ɂ��ĐF���̕ω�
�i�o�b�O���ƃZ�O�����g���̌��t�F���̍��ɗ��Ӂj�C�n����Ì���̗L���C���邢�̓o�b�O�̔j���̗L���Ȃǂُ̈킪�Ȃ��������Ŋm�F����B
�@�A���̏����y�ю��{�́C�����Ƃ��Ĉ��Ɉꊳ�҂��Ƃɍs���B�����̊��҂ւ̗A���p���t����x�ɂ܂Ƃ߂ď������C���̂܂܊��҂��犳�҂ւƑ����ėA�����邱�Ƃ́C���Ⴂ�ɂ�鎖�̂̌����ƂȂ�₷���̂ōs���ׂ��ł͂Ȃ��B
�@�����I�ȉߌ�ɂ�錌�t�^�s�K���A����h�����߁C�A���p���t�̎n�����C�A���������y�їA�����{���ɁC���ꂼ��C����
����
�i���������ɒ��Ӂj�C���t�^�C���t�����ԍ��C�L�������C�����K�������̌�������
�C���ː��Ǝ˂̗L���Ȃǂɂ��āC���������K���[�̋L�ڎ����ƗA���p���t�o�b�O�̖{�̋y�ѓY�t�`�[�Ƃ��ƍ����C�Y�����҂ɓK�����Ă�����̂ł��邱�Ƃ��m�F����B�������ȂNJ��Җ{�l�ɂ��m�F���ł��Ȃ��ꍇ�C���Y���҂ɑ���Ȃ�����
���K��
�����̎҂ɂ���m�F���邱�Ƃ��d�v�ł���B
�@�m�F����ꍇ�́C��L�`�F�b�N���ڂ̊e���ڂ�2�l�Ō��݂ɐ����o�������ēǂݍ��킹�����C���̎|���L�^����B
�@�܂�ł͂��邪�C�����������邢�͔��ɂ悭���������̊��҂��C�������ɗA����K�v�Ƃ��邱�Ƃ�����B���҂̔F���iID�j�ԍ��C���N�����C�N��Ȃǂɂ��l�̎��ʂ����I�ɐS�����Ă����K�v������B
�@
�m�F�C�ƍ����m���ɂ��邽�߂ɁC���҂̃��X�g�o���h�Ɛ��܂��g�ђ[���i
PDA�j
�Ȃǂ̓d�q�@���p�����@�B�I�ƍ��p���邱�Ƃ��]�܂����B
�@���������A����lj�����ꍇ�ɂ��C�lj�����邻�ꂼ��̗A���p���t�ɂ��āC��L3�j�`8�j�Ɠ��l�Ȏ菇�𐳂������܂Ȃ���Ȃ�Ȃ��B
�@
�A���O�ɑ̉��C�����C�����C����ɉ\�ł���Όo��I�������_�f�O�a�x�iSpO2�j�𑪒��ɁC�A�����J�n���C����p�������ɂ́C�ēx���肷�邱�Ƃ��]�܂����B
�@�ӎ��̂��銳�҂ւ̐Ԍ����A���̗A�����x�́C�A���J�n���ɂ͊ɂ₩�ɍs���BABO�^�s�K���A���ł́C�A���J�n���ォ�猌�ǒɁC�s�����C���ɁC���ɂȂǂ̏Ǐ�����̂ŁC�A���J�n��5���Ԃ̓x�b�h�T�C�h�Ŋ��҂̏�Ԃ��ώ@����K�v������B
�~���I�ȋً}�A����v���銳�҂ł͋}���A����K�v�Ƃ��C�ӎ��������łȂ����Ƃ������C���o�I�����ɂ��s�K���A�����^�����Ƃ͍���͕s�\�ł���̂ŁC�ċz�E�z���Ԃ̊ώ@�̑��ɓ��A���s���ĔA�̐F�������邱�Ƃ�p�삩��̏o���̏�Ԃ��ώ@���邱�ƂȂǂɂ��C�����I�ȑ��o�I�����ɂ���āC�s�K���A���̑��������ɓw�߂�B
�@�A���J�n��15�����x�o�߂������_�ōēx���҂̏�Ԃ��ώ@����B�����^�n�������̖������Ƃ��m�F������ɂ��C���M�E�@���]�Ȃǂ̃A�����M�[�Ǐ����Ό�����̂ŁC���̌���K�X�ώ@�𑱂��đ��������ɓw�߂�B
�@�A���I����ɍēx���Җ��C���t�^�y�ь��t�����ԍ����m�F���C�f�Ø^�ɂ��̐����ԍ����L�^����B
�@
���ɁC��q�����A���֘A�}���x��Q�i
TRALI�j
�C�ۊ����ǂł͗A���I����ɏd�Ăȕ���p��悷�邱�Ƃ�����C�A���I������������p���I��
�ώ@���邱��
���\�ȑ̐�������B
�@
���ɁA�A���O��̌������s���Ă���ꍇ�́A�u���t���ܓ��Ɋւ���k�y�����K�C�h���C���v�����炵�Č��̂�ۑ�����B
�@
���Ҍ��̂̕ۑ��ɂ������ẮA�u���t���ܓ��Ɋւ���k�y�����K�C�h���C���v�������炷�邱�ƁB�ȉ��A�ꕔ�v������B
�@
��Ë@�ւ����Y�w�j�iVIII�̂P�̂Q�j�́i�Q�j�y�сi�R�j�j�ɏ]���ėA���O��̌��������{���Ă��Ȃ��ꍇ�́A�A���O��̊��Ҍ��t�i�����������͌����K���������Ŏg�p�����������邢�͌����i�����ƕ����j�Ŗ�Pml�j���̊ԁA-20���ȉ��ʼn\�Ȍ���ۑ����邱�ƂƂ��A���{�ԏ\���Ђ��猟���˗����������ꍇ�ɂ͓��Y�w�j�ɏ]���Č������s�����ƁB
�@
���̍ہA�R���^�~�l�[�V�����̂Ȃ��悤�Ƀf�B�X�|�[�U�u���̃s�y�b�g���g�p����Ȃǂ̑Ή����]�܂��B
�@
�Ȃ��A���Y�w�j�ɏ]���ėA���O��̌������s���Ă���ꍇ�ł����Ă��A�����̋^�z�����ʁA���݃E�C���X�̊��������̗L�����m�F���邽�߁A�A���O��̊��Ҍ����i���j�̍Č������s�����Ƃ�����̂ŁA
| �@(1) |
�A���O�P�T�Ԓ��x�̊Ԃ̊��Ҍ����i���j |
�y��
| �@(2) |
�A����R�������x�̌����i���j |
�ɂ��Ă��ۊǂ��Ă�����̂�����A���{�ԏ\���Ђɒ��A�����ɋ��͂��邱�Ɓi�@���̌��̏ꍇ�͏����j�B
�@
���̍ۂ̕ۊǏ����́A�����������͌����K���������Ŏg�p�����������邢�͌����i�����ƕ����j���Pml���x�A-20���ȉ��łR�����ȏ�\�Ȍ���i2�N�Ԃ�ڈ��Ɂj�ۊǂ��邱�Ƃ��]�܂����B
| �� |
�@�����J���Ȉ��H�i�nj��t��ہ@����17�N3�� |
|
VIII |
�@�A���i�A���p���t�j�ɔ�������p�E�����ǂƑ� |
�@�A������p�E�����ǂɂ͖Ɖu�w�I�@���ɂ����́C�������̂��́C�y�т��̑��̋@���ɂ����̂Ƃ�����C����ɂ��ꂼ�ꔭ�ǂ̎����ɂ�葦���^�i���邢�͋}���^�j�ƒx���^�Ƃɕ�������B�A���J�n���y�їA��������łȂ��A���I����ɂ��C�����̕���p�E�����ǂ̔����̗L���ɂ��ĕK�v�Ȍ������s�����C�o�߂��ώ@���邱�Ƃ��K�v�ł���B
�@�����̕���p�E�����ǂ�F�߂��ꍇ�ɂ́C�x�Ȃ��A�����傠�邢�͗A���Ö@�ψ���ɕ��C
�L�^��ۑ�����ƂƂ��ɁC���̌����𖾂炩�ɂ���悤�ɓw�߁C�ގ��̎��Ԃ̍Ĕ���\�h�������u����B���ɐl�דI�ߌ�i���҂̎��Ⴂ�C�]�L�~�X�C�����~�X�C���̍̎�~�X�Ȃǁj�ɂ��ꍇ�́C���̔��������y�эu����ꂽ�\�h����L�^�Ɏc���Ă����B
| �@�i1�j |
�����^�i���邢�͋}���^�j����p |
�@�A���J�n�㐔�����琔���Ԉȓ��ɔ��ǂ��Ă���
�����^�i���邢��
�}���^�j�̏d�Ăȕ���p�Ƃ��ẮC�^�s�K���ɂ�錌�Ǔ��n���C
�A�i�t�B���L�V�[�V���b�N�C�ۉ������A���ɂ���ی��ǂ�G���h�g�L�V���V���b�N�C�d�퐫���Ǔ��ÌŁC�z�s�S�C�A���֘A�}���x��Q�iTRALI�j�Ȃǂ�����B
�@���̂悤�ȏǏ��F�߂��ꍇ�ɂ́C�����ɗA���𒆎~���C�A���Z�b�g���������Đ����H���t���͍זE�O�t�ގ��A�t�܂̓_�H�ɐ�ւ���B
�@
�`�a�n���t�^�s�K�����܂ޗn����F�߂��ꍇ�i����p��̌������͌����̗n�������C�w���O���r���A�j�ɂ́C���t�^�̍Č����C�s�K���R�̌����C���ڃN�[���X�����������{����B
�@�x���^�̕���p�Ƃ��ẮC�A����24���Ԉȍ~�C�����o�߂��Ă��猩����
�x���^�n�����A������p�iDHFR;Delayed�@Hemplytic�@Transfusion�@Reaction�j������B���NJO�n����A���㎇���a�Ȃ�
�̏Ǐ�������B
| �@�i1�j |
�����^�i���邢�͋}���^�j����p |
�@
�A�i�t�B���L�V�[�V���b�N�C�ۉ������A���ɂ��ی��ǂ�G���h�g�L�V���V���b�N�C�d�퐫���Ǔ��ÌŁC�z�s�S�C�A���֘A�}���x��Q�iTRALI�j�Ȃǂ���������B
�@
���̂悤�ȏǏ��F�߂��ꍇ�ɂ́C�����ɗA���𒆎~���C�A���Z�b�g���������Đ����H���t���͍זE�O�t�ގ��A�t�܂̓_�H�ɐ�ւ���B
�@
�����Z���t�͂��̋@�\��ۂ��߂Ɏ����i20�`24���j�Ő����UṂ��Ȃ���ۑ�����Ă��邽�߂ɁC�܂�ɍۂ̉������݂邱�Ƃ�����C���̌��ʂƂ��ėA���ɂ��ۊ����ǂ��N���邱�Ƃ�����B�܂��C�Ԍ����Z���t�ɂ��Ă͒����ۑ��ɂ��G���V�j�A�ۊ��������ƂȂ�B
�@
�����ƂȂ�A���p���t�̕ۑ��⊳�Ҍ��̂̌����ɂ��ẮC�u���t���ܓ��ɌW��k�y�����K�C�h���C���i�����P7�N3�������J���Ȉ��H�i�nj��t��ہj�v�����炷��i�Q�l�P�Q�Ɓj�ƂƂ��ɁC�����ƂȂ�A���p���t�����̉�����ɓ������Ă͎Q�l2�ɏ]���悤�w�߂�B
| �@�A |
�@�A���֘A�}���x��Q�iTRALI�j |
�@
TRALI�͗A�����������͗A����6���Ԉȓ��i������1�`2���Ԉȓ��j�ɋN�����S�����̔x������ċz�����悷��C�d�ĂȔ�n�����A������p�ł���B�Տ��Ǐ�ь��������ł͒�_�f���ǁC���������g�Q���ʐ^��̗����x����̂ق��C���M�C�����ቺ�����Ƃ�����B�{����p�̔��Ǘv���Ɋւ��Ă͖����s���ȓ_���������C�A�����t���������͊��Ҍ��t���ɑ��݂���R�������R�̂��a�ԂɊ֗^���Ă���\��������C���̑����ܒ��̎����̊֗^����������Ă���B�Տ��̌����TRALI�̔F�m�x���Ⴂ���Ƃ┭�ǂ����}���ł��邱�Ƃ���C��������Ă���Ǘ�������Ɛ��������B���Âɍۂ��ẮC�A���̉ߕ��ׂɂ��S�s�S�ivolume
overload�j�Ƃ̊ӕʂ͓��ɏd�v�ł���BTRALI�̏ꍇ�ɂ͗��A�܂͂������ď�Ԃ����������邱�Ƃ�����C�ӕʂɂ͐T�d�������ׂ��ł���BTRALI�Ɛf�f�����ꍇ�ɂ́C���ٓI�ȖÖ@�͂Ȃ����C�_�f�Ö@�C�}�ǁC�l�H�ċz�Ǘ����܂߂��������K�ȑS�g�Ǘ����s���K�v������B�唼�̏Ǘ�͌��ǂ��c�����ɉ���Ƃ���Ă��邪�C���S�����͏\���������Ƃ����B�Ȃ��C���Y�������^��ꂽ�ꍇ�͌������̍R�������R�̂�RHLA�R�̗̂L���ɂ��Č�������B
�@�{�ǂ͗A����7�`14�����ɔ��M�C�g���C�����C�̋@�\��Q�y�єČ��������ǂ��Ĕ��ǂ���B�{�ǂ̗\�h��Ƃ��ĕ��ː��Ǝˌ��t�̎g�p���L���ł���iIII-4-2�j���Q�Ɓj�B���\�h��̓O��ɂ��2000�N�ȍ~�C�m��Ǘ�͂̕Ȃ��B
�@�{�ǂ́C������ΗA����2�`3�J���ȓ��ɔ��ǂ��邪�C�̉��̗Տ��Ǐ邢�͊̋@�\�ُ̈폊����c���ł��Ȃ��Ă��C�̉��E�C���X�Ɋ������Ă��邱�Ƃ��f�f�����ꍇ������B���ɋ����҂��E�C���h�E���ɂ��邱�Ƃɂ�銴�������ƂȂ�B���̂悤�Ȋ����̗L��������ƂƂ��ɁC�������Â�}�邽�߁C��t���������X�N���l�����C�������^����ꍇ�Ȃǂɂ́C�ʕ\�̂Ƃ���C�̉��E�C���X�֘A�}�[�J�[�̌��������s���K�v������B
�ʕ\
| �@ |
�A���O���� |
�A���㌟�� |
| �a�^�̉� |
HBs�R��
HBs�R��
HBc�R�� |
�j�_���������iNAT�j
�i�A���O�����̌��ʂ���������A��
�̏ꍇ�A�A����3������Ɏ��{�j |
| �b�^�̉� |
HCV�R��
HCV�R�A�R�� |
HCV�R�A�R������
�i�A���O�����̌��ʂ���������A��
�̏ꍇ���͊��������Ɣ��f���ꂽ
�ꍇ�A�A����1�`3������Ɏ��{�j |
| �@�B |
�@�q�g�Ɖu�s�S�E�C���X���� |
�@��V���Ɖu�s�S�nj�Q�i�G�C�Y�j�̋N���E�C���X�iHIV�j�����ł́C������2�`8�T�ŁC�ꕔ�̊����҂ł͍R�̂̏o���ɐ�Ĉ�ߐ��̊��`�l�Ǐ����邱�Ƃ����邪�C�����͖��Ǐ�Ɍo�߂��āC�Ȍ�N�]�ɂ킽�薳�njɌo�߂���B���ɋ����҂��E�C���h�E���ɂ���ꍇ�̊��������ƂȂ�B�ҁi���ҁj�̊����̗L�����m�F���邽�߂ɁC��t���������X�N���l�����C�������^����ꍇ�Ȃǂɂ́C�A���O��HIV�R�̌������s���C���̌��ʂ��A���ł���C�A����2�`3�����ȍ~�ɍR�̌��������s���K�v������B
| �@�C |
�@�q�g�s�����p�������E�C���X |
�@�A���ɂ��q�gT�����p�������E�C���XI�^�iHTLV-I�j�Ȃǂ̊����̗L����Ɖu�R�̎Y���̗L���Ȃǂɂ��Ă��C��f��K�v�ɉ����������ɂ��ǐՂ��邱�Ƃ��]�܂����B
�@
���M�E�ċz����E�����ቺ�Ȃǂ̍ۊ����ǂ��^���ǏF�߂�ꂽ�ꍇ�́C�۔|�{�̂ق��K�X�G���h�g�L�V�����̌��������{����B�n����F�߂��ꍇ�́C���t�^�̍Ċm�F�Ȃǂ��s���B
�@
�o�b�O�Ǝg�p���Ă����A���Z�b�g�܂��͔����������t�B���^�[�Z�b�g���������B
�@
�������܂̍۔|�{�����s�����߂ɁC2���I�ȉ������N���Ȃ��悤�ɒ��ӂ���B
�@
�A���Z�b�g�̃N�����v���d���߂āC���ːj�������������ȃL���b�v�ŃJ�o�[����B
�@���̏�ԂŁC���₩�ɐ����ȃr�j�[���܂ɓ���ėA������֕ԋp����B�A������ł͗A���Z�b�g�̃`���[�u�������`���[�u�V�[���ŃV�[�����邱�Ƃ��]�܂����B�����ȃr�j�[���܂ɓ��ꂽ�܂܂ŕۊǂ���B
�@
�n����F�߂��ꍇ�́C�A���j�̌��a�C�Ԍ����Z���t�̉����̗L���C�y����܂̓��ꃋ�[�g�����������^�̗L���ɂ��Ċm�F����B
3�j |
�������܉���̂��߂̐E������ |
�@
���܊m�ۂƉ���́C�f�ÉȊŌ�t�E��t�̋��͂��s���ł���B�܂��C�A������C�Z�t�����łȂ��C�A��������S�����Ă��钆�����������̌����Z�t�̊֗^���K�v�ł���̂ŁC��L�̒��ӎ��������m����B
3�D |
����p���������̂��߂̊��Ҍ��̍̎�ƌ��� |
�@
���M�E�ċz����E�����ቺ�Ȃǂ̍ۊ����ǂ��^���ǏF�߂�ꂽ�ꍇ�́C�۔|�{�̂ق��K�X�G���h�g�L�V�����̌�����K�����{����B�n����F�߂��ꍇ�ɂ��C���t�^�̍Č����C�s�K���R�������C���ڃN�[���X���̌����Ȃ������{����B
4�D |
�ԏ\�����t�Z���^�[�ւ̌��������̈˗� |
�@
�ȉ��̊�ɑ������钆���ǂ���d�ǂ̗A������p��ɂ��Ă͐ԏ\�����t�Z���^�[�Ɍ��������̈˗����s�����Ƃ��]�܂����B
�@
�q�A������p�d�Ǘ�̊�ār
�@
�A���J�n��24���Ԉȓ��Ɉȉ���1���ڈȏ�̕ω����F�߂�ꂽ���́B
a�j |
�����F30mmHg�ȏ�̒ቺ |
b�j |
���M�F2���ȏ�̏㏸�܂���39���ȏ�̔��M |
c�j |
�ċz����C�_�f�O�a�x�iSaO2�j�F90���ȉ��ɒቺ |
d�j |
����X���ʐ^�F�x���� |
e�j |
���̑���L���ڂɑ�������Տ����� |
2�j |
���Ԍ��t�Z���^�[���t���� |
�������ځF |
�g���v�^�[�[�E�R�����`���R�́E�R�������R�̂Ȃ� |
�̌��ǁF |
EDTA�̌���2�`5mL�C�v���[���̌���2�`5mL |
�@
��������ɍ̌����C�A�����i�A�������j��茌�t�Z���^�[�֑��t
�@
�����ɒ�o�ł��Ȃ��ꍇ�͗①�ۑ��B
5�@2�D |
�A������i�A��������C��t�j�ɂ��R���T���e�[�V���� |
�@
�P�Ȃ邶�]�ȊO�ł͗A�����������p�������̗Տ������C���ÁC�A������p�̌�������ƕ���p����������t�����A���p���t�̑I���ɂ��āC���������߂邱�Ƃ��]�܂����B
6�@3�D |
�A���Ö@�ψ���ɂ��@���̐��̐��� |
�@
�A���Ö@�ψ���ɂ����āC�����ƂȂ�A���p���t�����̉���E���������̂��߂̊��Ҍ��̍̎�Ɋւ��āC�f�ÉȂ̋��͑̐����\�z����ƂƂ��ɁC�����̋Ɩ����\�Ȍ����Z�t�̔z�u���܂ޗA�����Ɩ��i�����Ɩ��j�̐��̐������s�����Ƃ��]�܂����B
7�D |
�A���ɔ��������^�i���邢�͋}���^�j����p�E�����ǂƔ��ǎ��̑Ή� |
�@
�A���J�n�㐔�����琔���Ԉȓ��ɔ��ǂ��Ă���}���^�i���邢�͑����^�j�̏d�Ăȕ���p�̏Ǐ��F�߂��ꍇ�ɂ́C�����ɗA���𒆎~���C�A���Z�b�g���������Đ����H���t���͍זE�O�t�ގ��A�t�܂̓_�H�ɐ�ւ���B
�@
�����E�����E�ċz���E�̉����肵�C�ċz����C�����ቺ������Β��f�E����X���ʐ^�E���t�K�X�𑪒肷��B
|
IX |
�@���t���܂̗L�����C���S���ƕi���̕]�� |
�@�A���Ö@���s�����ꍇ�ɂ́C�A���p���t�̕i�����܂߁C���^�ʂɑ�����ʂƈ��S�����q�ϓI�ɕ]���ł���悤�C�A���O��ɕK�v�Ȍ������s���C����ɗՏ��I�ȕ]�����s������ŁC�f�Ø^�ɋL�ڂ���B
|
X |
�@���t���g�p�Ɋւ���L�^�̕ۊǁE�Ǘ� |
�@���t���܁i�A���p���t���܋y�ь������搻�܁j�ł����ē��萶���R�����i�Ɏw�肳�ꂽ����
���ɂ��ẮC�����C���Y���t���܂̎g�p�ɂ�芳�҂ւ̃E�C���X�����Ȃǂ̂����ꂪ�������ꍇ�ɑΏ����邽�߁C�f�Ø^�Ƃ͕ʂɁC���Y���t���܂Ɋւ���L�^���쐬���C���Ȃ��Ƃ��g�p������20�N�������Ȃ����ԁC�ۑ����邱�ƁB�L�^���ׂ������́C���Y���t���܂̎g�p�̑Ώێ҂̎����y�яZ���C���Y���t���܂̖��̋y�ѐ����ԍ����͐����L���C�g�p�N�������ł��邱�Ɓi�@��68����9�y�і@�{�s�K���i���a36�N�����ȗߑ�1���j��62����11�y��14�j�B
| �@�� |
�@�i���a35�N�@����145���B�ȉ��u�@�v�Ƃ����B�j��2���6���ɋK�� |
| �@���F |
����15�N5��15���t�����0515011���u���萶���R�����i�ɌW��g�p�̑Ώێ҂ւ̐������тɓ��萶���R�����i�Ɋւ���L�^�y�ѕۑ��ɂ��āv�i�i�Ёj���{��t�������Č����J���Ȉ��ǒ��ʒm�j |
�@���Ȍ��A����
�@���ł̎��{�Ǘ��̐����K���Ɋm�����Ă���ꍇ�́C���파�A���̕���p�����������ł����S�ȗA���Ö@�ł����C�ҋ@�I��p���҂ɂ�����A���Ö@�Ƃ��ĐϋɓI�ɐ��i���邱�Ƃ�
���߂��Ă���B
| �@��: |
�t�������Ȍ��A���̎��{�ɓ������ẮC�u���Ȍ��A���F�̌��y�ѕۊNJǗ��}�j���A���v�i�����ȖǁC����6�N12��2���j���Q�ƁB�������C�����������邱�Ƃ�����̂ōŐV�̃}�j���A�����Q�Ƃ���K�v������B�Ȃ��C���Ȍ��A���w��E���{�A���w������ψ���ɂ�鎩�Ȍ��A���K�C�h���C�������Ăɂ��āi���Ȍ��A����14����1��1�`19�ŁC2001�N�j���Q�l�Ƃ���B |
|
1�j |
���������Ȍ��A���F��p�O�Ɏ��Ȃ̌��t��\�ߍ̌��C�ۑ����Ă������@ |
|
2�j |
��ߎ����Ȍ��A���F��p�J�n���O�ɍ̌����C�l�H�P���t��A��������@ |
|
3�j |
��������Ȍ��A���F�p���E�p��ɏo���������t�����������@ |
�@
���ɁC��ߎ��������ɔ�ׂāC���ėp���̂��钙�������Ȍ��A���̕��y�C�K���̊g�傪���҂���Ă���B
| 2�D |
�C���t�H�[���h�E�R���Z���g |
�@
�A���S�ʂɊւ��鎖���ɉ����C���Ȍ��A���̑ΏۂƂȂ蓾�銳�҂ɑ��āC���Ȍ��A���̈Ӌ`�C���Ȍ��̌��E�ۊǂɗv������ԁC�̌��O�̕K�v�����C���Ȍ��A�����̃g���u���̉\���ƑΏ����@�ȂǁC���Ȍ��A���̎��ۓI�Ȏ����ɂ��ď\���Ȑ����Ɠ��ӂ��K�v�ł���B
�@
���Ȍ������ɑς�����S�g��Ԃ̊��҂̑ҋ@�I��p�ɂ����āC�z���t�ʂ�15���ȏ�̏p���o���ʂ��\������C�A�����K�v�ɂȂ�ƍl������ꍇ�ŁC���Ȍ��A���̈Ӌ`�𗝉����C�K�v�ȋ��͂�������Ǘ�ł���B���ɁC�H�Ȍ��t�^����ɖƉu�i�s�K���j�R�̂����ꍇ�ɂ͐ϋɓI�ȓK���ƂȂ�B
�@
�̏d40kg�ȉ��̏ꍇ�́C�̏d����z���t�ʂ��v�Z���Ĉ��̌��ʂ�ݒ�i���ʁj����ȂǐT�d�ɑΏ�����B6�Ζ����̏����ɂ��ẮC���̌��ʂ�̏dkg�������5�`10mL�Ƃ���B50�Έȏ�̊��҂Ɋւ��ẮC���Ȍ��̌��ɂ��S���njn�ւ̈��e���C���ɋ��S�ǔ���Ȃǂ̊댯�������O�ɕ]�����C���{����ꍇ�́C�厡��i�z��Ȃ̈�t�j�Ƌٖ��ɘA�������C�\�z�����ω��ɑΏ��ł���̐��𐮂��āC�T�d�Ɋώ@���Ȃ���̌�����B���̑��C�̉��C�����C�������Ȃǂ��̌��v��Ɏx����y�ڂ��Ȃ����Ƃ��m�F����B
�@
�ی��ǂ̉\��������S�g�I�ȍۊ������҂́C���Ȍ��̕ۑ����ɍۑ��B�̊댯��������C�����I�Ɏ��Ȍ��A���̓K�����珜�O����B�G���V�j�A�ہiYersinia Enterocolitica�j�Ȃǂ̒����ۂ��ÐH�����������̍����̊댯�����l�����C4�T�ȓ��ɐ��n�l�������Ȃǂ̒��������ǂ��^����Ǐ��������҂���͍̌����s�Ȃ�Ȃ��B�s���苷�S�ǁC���x�̑哮���ً���ǂȂǁC�̌��ɂ��z���Ԃւ̏d��Ȉ��e���̉\����ے�ł��Ȃ��z�펾�����҂̓K�����T�d�ɔ��f���ׂ��ł���B
�@
���파�A���Ɠ��l�C���ҁE���t�̎��Ⴆ�ɋN������A���ߌ�̊댯���ɒ��ӂ���K�v������B���Ȍ��̌��ɂ������ẮC���h���ʂ���̍ۍ�������ђ����ۂ��ÐH�������������܂ތ��t�̍̎�ɂ��ۉ����̊댯���ɒ��ӂ���K�v������B�̌��j���h�����镔�ʂ̐��@�Ə��ł́C
���{�ԏ\���Ќ��t�Z���^�[�̍̌���Z�ɏ����������O�ɍs���B
����ɁC�̌����̕���p��C���ɁC�̌����C�̌�����ѓ_�H�I���E���j��C�����č̌���x�b�h����̈ړ����Ȃǂɏo�����C��ʑ����C�⊾�Ȃǂ̏Ǐ����I�Ȍ��ǖ����_�o���ˁiVVR�j�ɏ\�����ӂ���K�v������B
�@�ɂ߂Ă܂�ł͂��邪�C�����_�o�������N�������Ƃ����蓾��̂ŁC�j�̎h�����ʋy�ѐ[���ɒ��ӂ���B
| 2�j |
���ǖ����_�o�����iVaso-Vagal Reaction ; VVR�j |
�@���ǖ����_�o���˂Ȃǂ̔������F�߂���ꍇ������̂ŁC�̌����y�э̌����
�����Ҋ����̗l�q���悭�ώ@����B�̌���ɂ�15�����x�̋x�e���Ƃ点��B
| �@���F |
���ǖ����_�o���˂͋����҂�1���ȉ��ɔF�߂��C�����Ⴂ�����ł͔�r�I�����F�߂���B |
�@�̌���̈����ɂ��~�����s�\���ł���ƌ���ł��₷���̂ŁC�K���Ȉ��͂ŏ��Ȃ��Ƃ�15���Ԉ������C�~�����m�F����B
| 6�D |
���Ȍ��A���e�@�̑I���Ƒg�ݍ��킹 |
�@���҂̕a��C�p���Ȃǂ��l�����āC�p�O���������Ȍ��A���C�p���O��ߎ����Ȍ��A���C�p���E�p��̉�������Ȍ��A���Ȃǂ̊e���@��K�ɑI�����C���͑g���킹�čs�����Ƃ���������ׂ��ł���B
|
XII |
�@�@���ŗA���p���t���̎悷��ꍇ�i���Ȍ��̌��������j |
�@�@���ō̌����ꂽ���t�i�ȉ��u�@�����v�Ƃ����B�j�̗A���ɂ��ẮC�����҂̖�f��̌��������t�̌������s�\���ɂȂ�₷���C�܂������҂��W�߂邽�߂Ɋ��҂�Ƒ��Ȃǂɐ��_�I�E�o�ϓI���S�������邱�Ƃ���C���{�ԏ\���Ђ̌��t�Z���^�[�����
�K�Ȍ��t�������̐����m������Ă���
�����n���ɂ����ẮC���ʂȎ���̂Ȃ�����s���ׂ��ł͂Ȃ��B
�@�@�����ɂ��A���Ö@���s���ꍇ�ɂ́CIII�`X�ŏq�ׂ��e�����ɉ����C���̓K���̑I������{�̐��݂̍���ɂ��Ĉȉ��̓_�ɗ��ӂ���B
�@
I���̐����Ɠ��ӂ̍����Q�ƁiI�|2�|3�j�j���C�A���Ɋւ�������Ɠ��ӂ���C�@�����A�����K�v�ȏꍇ�ɂ��āC���Җ��͂��̉Ƒ��ɗ������₷�����t�ł悭�������C���ӂ�B
�܂��C�����ǃE�C���X�̃X�N���[�j���O�����̐��x�y�їA���ɂ��
�����Ǔ`�d�̊댯����
�������C���ӂ�B
�@�ȏ�̓��e�̐����ɂ�铯�ӂ�����ꂽ�|��f�Ø^�ɋL�^���Ă����B
�@
���{�ԏ\���Ќ��t�Z���^�[���狟������Ȃ�����������p��
�Ȃǂ̗A����K�v�Ƃ��邪�C
���{�ԏ\���Ђ̌��t�Z���^�[����͋�������Ă��Ȃ����߁C�@����
�����̌����s���p�����ꍇ�B
�@������ƒn�Ȃǂœ��{�ԏ\���Ђ̌��t�Z���^�[����
���C���t�̔������Ԃɍ���Ȃ��ً}���Ԃ̏ꍇ�B
|
3�j |
�H�Ȍ��t�^�ŕ�̌��t���g�p������Ȃ��ꍇ |
| 4�j |
�V��������Ɖu���������ǁiNAITP�j�ŕ�e�̌����̗A�����K�v�ȏꍇ |
�@�̌����������Ɏg�p���錌�t�i�ȉ��u�����V�N���v�Ƃ����B�j�̗A�����]�܂����ƍl�����Ă����ꍇ���C���̐�ΓI�K���͂Ȃ��B
�@���ɁC�ȉ��̏ꍇ�͉@�����Ƃ��Ă̓����V�N����K�v�Ƃ�����ʂȎ���̂���ꍇ�Ƃ͍l�����Ȃ��B
�@������x�ȏ�̗ʂ̓������邢�͐Ö����ǂ̑����ɂ��o���́C�A���ɂ���Ď~�����邱�Ƃ͂ł��Ȃ��B
�@�o���������̕s���ɂ����̂ł���Ό����A�����C�܂��Ìŏ�Q�ɂ����̂ł���Ìň��q���܂�V�N��������
�i���邢�͐V�N�����j�̗A�����K���ƂȂ�B
�@�ʏ�̐Ԍ���
������S�����̐Ԍ����̗A���ŏ\���ړI��B�����邱�Ƃ��ł���B
�@�̌���1�T�Ԉȓ��̐Ԍ���
������S���̗A���ɂ�蔭�ǂ��邱�Ƃ͂܂�ł���B
�@�����V�N���t���ɑz�肳��関�m�̈��q�ɂ��Տ����ʂ����҂��邱�Ƃ́C���ؓI�f�[�^�̂Ȃ��ȏ�C����ł͕s�K�ƍl����ׂ��ł���B
�@�@���̌��ł��C�u���S�Ȍ��t���܂̈��苟���̊m�ۓ��Ɋւ���@���{�s�K���v�ɏ]���č̌����邱�Ƃ������Ƃ���B��f�ɍۂ��ẮC����
�����҂̖�f�̎����iIII�|1�Q�Ɓj�ɗ��ӂ��C�����R�炵�̂Ȃ��悤�ɁC�\�ߖ�f�[��p�ӂ��Ă����ׂ��ł���B
�@�̌��ɔ��������҂ւ̎��̂╛��p���ł��邾�������邽�߁C
���Ȍ��A�����{��̗��ӓ_�iXI��5
�j�Ɏ����ق��C�ȉ��̓_�ɒ��ӂ���K�v������B
�@�̌����ꂽ���t�ɂ��čs���������e���C���炩���ߋ����҂ɐ������Ă����B
�@�Ȃ��C�����҂��������ʂ̒ʒm����]����ꍇ�ɂ́C�l���̔閧�ێ��ɗ��ӂ���B
�@�̌��j���h�����镔�ʂ̐��@�Ə��ł́C���{�ԏ\���Ќ��t�Z���^�[�̍̌���Z�ɏ������ē��O�ɍs���B
�@�̌��Ɍg���҂́C�w�����o������t�Ƌً}�x�⌟���̗D�揇�ʂȂǂɂ��ď\���A�g���Ƃ�B
�@�@���̌����s���ꏊ�́C�������C�̌����s�����߂ɏ\���ȍL���C���邳�C�Â����ƓK�ȉ��x���m�ۂ���K�v������B
| 7�D |
�̌����ꂽ�A���p���t�̈��S���y�ѓK�����̊m�F |
�@�@�����̌�����III�`V�̗A���p���t�̈��S���y�ѓK�����̊m�F�̍��Ɠ��l�ɍs���B
�@�ً}���ȂǂŗA���O�Ɍ������s�����Ƃ��ł��Ȃ������ꍇ�ł��C�A����̊��҂̌o�ߊώ@�Ǝ��Â��K�v�ɂȂ�ꍇ�ɔ����āC
������A���ɗp����
�@����
�t�ɂ���
�������q�̌������s���B
�@�@������A�����ꂽ���҂ɂ��Ă�X�Ɠ��l�̋L�^���쐬���ĕۊǂ���B
������
�@�A���Ö@�́C�����w�ɂ����čł��m���Ȍ��ʂ̊��҂ł���K�{�Ȏ��Ö@�̈�ł��邪�C���̎��{�ɂ͂��܂��܂Ȋ댯�������Ƃ���C���̂悤�Ȋ댯�����ŏ����ɂ��Ă����S�����ʓI�ɍs�����߂ɁC�A���Ö@�Ɍg��邷�ׂĂ�
�E���͂��̎w�j�ɑ����Ă��̓K���Ȑ��i��}��ꂽ���B
�@����C�A���Ö@�̈�w�I�i���ɑΉ��������ł͂Ȃ��C�u���S�Ȍ��t�̈��苟���̊m�ۓ��Ɋւ���@���v�̐���Ȃǂɏے������悤�ȎЉ�I���̕ω��ɂ������āC�{�w�j�͎����������邱�ƂȂ�������
�����Ă����\��ł���B
�Q�l1�@��Ë@�ւɂ�����ۂւ̑Ή��i���t���ܓ��ɌW��k�y�����K�C�h���C���i�����j�j
�@��Ë@�ւɂ����ẮC�A���Ɏg�p�����S�Ắu�g�p�ς݃o�b�O�v�Ɏc�����Ă��鐻�܂��o�b�O���ƁC�����ɗⓀ�ۑ����Ă������Ƃ��]�܂��i�Ⓚ�͕s�j�B
�@�Ȃ��C�g�p�㐔���o�߂��Ă��ҁi���ҁj�Ɋ����ǔ��ǂ̂Ȃ��ꍇ�͔p�����Ă������x���Ȃ����ƂƂ���B
| 2�j |
�ҁi���ҁj���t�ɌW�錌�t�|�{�̎��{ |
�@�ҁi���ҁj�̊����ǔ��nj�C�A����̎ҁi���ҁj���t�ɂ�錌�t�|�{���s���C���{�ԏ\���Ђɑ��āC���Y���҂ɌW�錟�����ʋy�ь��N�������ƂƂ��ɁC�����Ǝғ��̏����W�ɋ��͂���悤�w�߂邱�Ƃ����߂���B���̍ہC�①�ۑ�����Ă����S�Ắu�g�p�ς݃o�b�O�v����邱�Ƃ��K�v�ł���B
�@�܂��C���Y�����Ǔ��Ɋւ����ی��q����̊�Q�������͊g��̖h�~�̂��߂ɕK�v�ƔF�߂�Ƃ��́C�����J���ȁi�Ɨ��s���@�l�@���i��Ë@�푍���@�\�j�ɕ���p�����Ǖ��s�����Ƃ��K�v�ł���B
�@���̌�C���Y�ҁi���ҁj�ɕa��̕ω��������������Ƃ�m�����ꍇ�́C�����Ǝғ��ɏ�����悤�w�߂�K�v������B
�Q�l2�@�����ƂȂ�A���p���t�����Ɋւ�������y������
|
1�j |
�����ƂȂ�A���p���t�����Ɋւ��錟������ |
�@
���M�E�ċz����E�����ቺ�Ȃǂ̍ۊ����ǂ��^���ǏF�߂�ꂽ�ꍇ�́C�۔|�{�̂ق��K�X�G���h�g�L�V�����̌��������{����B�n����F�߂��ꍇ�́C���t�^�̍Ċm�F�Ȃǂ��s���B
| 2�j |
�����ƂȂ�A���p���t���������̒��� |
�@
�o�b�O�Ǝg�p���Ă����A���Z�b�g�܂��͔����������t�B���^�[�Z�b�g���������B
�@
�����ƂȂ�A���p���t�����̍۔|�{�����s�����߂ɁC2���I�ȉ������N���Ȃ��悤�ɒ��ӂ���B
�@
�A���Z�b�g�̃N�����v���d���߂āC���ːj�������������ȃL���b�v�ŃJ�o�[����B
�@
���̏�ԂŁC���₩�ɐ����ȃr�j�[���܂ɓ���ėA������֕ԋp����B�A������ł͗A���Z�b�g�̃`���[�u�������`���[�u�V�[���ŃV�[�����邱�Ƃ��]�܂����B�����ȃr�j�[���܂ɓ��ꂽ�܂܂ŕۊǂ���B
�@
�n����F�߂��ꍇ�́C�A���j�̌��a�C�Ԍ����Z���t�̉����̗L���C�y����܂����ꃋ�[�g�����������^�̗L���ɂ��Ċm�F����B
| 3�j |
�����ƂȂ�A���p���t��������̂��߂̐E������ |
�@
�����ƂȂ�A���p���t�������m�ۂƉ���́C�f�ÉȊŌ�t�E��t�̋��͂��s���ł���B�܂��C�A������C�Z�t�����łȂ��C�A��������S�����Ă��钆�����������̌����Z�t�̊֗^���K�v�ł���̂ŁC��L�̒��ӎ��������m����
�B