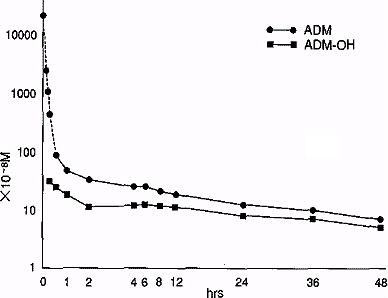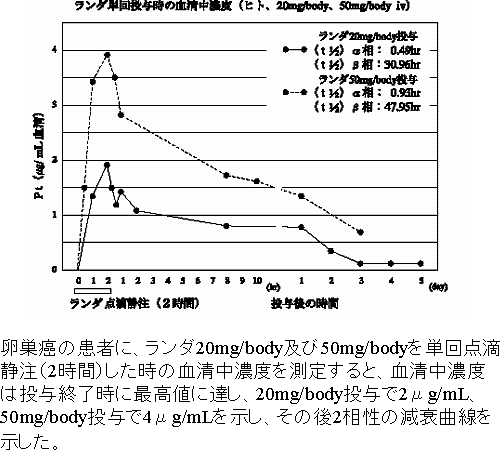| 1. |
|
Thigpen JT, Blessing JA, DiSaia PJ, et al. A randomized comparison of doxorubicin alone versus doxorubicin plus cyclophosphamide in the management of advanced or recurrent endometrial carcinoma:A Gynecologic Oncology Group Study. J Clin Oncol 12:1408-1414,1994 |
進行・再発子宮体癌356例を対象にドキソルビシン単剤(ADM:60 mg/m2)とADM:60 mg/m2+シクロフォスファミド(CPA:500mg/m2)のランダム化比較試験が行われた。3週ごとに投与が反復された。登録全356例中、測定可能病変を有さない症例が56例で測定可能病変を有する症例は300例であった。実際、300例中24例は評価不能であり、抗腫瘍効果は276例で判定された。ADM単剤投与の132例中、完全寛解 (CR)7例、部分寛解(PR) 22例で奏効率は22%であり、ADM+CPA投与の144例中、CR 18例、PR 25例で奏効率は30%であった。無増悪生存期間(PFS)と全生存期間(OS)はADM単剤とADM+CPAでそれぞれ、3.2ヶ月、6.7ヶ月と3.9ヶ月、7.3ヶ月であった。予後に関係するPS、組織学的分化度、肝転移や腹腔内病変に関して多変量解析すると奏効率は差がなかった(relative odds of response,1.58;p=0.06,one-tailed test)。生存期間はADM+CPAがやや長い傾向にあった(17% reduction in death rate; p=0.048)。毒性として白血球減少(284例で評価)はADM+CPAに高頻度、血小板減少(284例で評価)は同程度であった。消化器毒性は318例中151例に出現しADM+CPAに高頻度であったが、両群間で差はなかった。その他、貧血、悪心、心毒性、倦怠感、発熱も320例中10例未満であり両群間で差はなかった。この試験で7例が死亡したが、治療に関連する可能性がある死亡は2%であった。この試験の結論は、ADMに CPAを併用することでADM単剤に比べてわずかに有効性が高まるがより頻繁な、重度な骨髄抑制や消化器毒性が増加する。この時点でADMにCPAを併用することは標準的でないと考えられた。
| 2. |
|
Thigpen JT, Blessing JA, Homesley H, et al: Phase III study of doxorubicin with/without cisplatin in advanced or recurrent endometrial carcinoma: a Gynecologic Oncology Group (GOG) study. Proc Am Soc Clin Oncol:261, 1993 (GOG 107) |
米国の臨床試験グループであるGOG (Gynecologic Oncology Group)により行われた第三相比較試験(GOG107)で、進行期III/IVまたは、再発子宮体癌、化学療法の前治療歴のない、測定可能病変を有する患者を対象にADM単独(60mg/m2 3週間隔)とAP療法(ADM 60mg/m2+ CDDP 50mg/m2 3週間隔)とにランダム化割り付けされた。本試験の主要評価項目は奏効率、無増悪生存期間、全生存期間であった。1988年12月1日から1992年12月1日までに281名の患者が登録され(ADM群150例、AP群131例)、そのうち、18例が不適格症例であった。患者背景について、それぞれ、年齢は、49歳以下4.7%、7.6%、50-59歳 22.0%、22.1%、60-69歳 38.7%、37.4%、70-79歳 32.0%、29.0%、80歳以上 2.7%、3.8%、PSはPS 0 35.3%、38.2%、PS 1 48.0%、39.7%、PS 2 16.7%、22.1%、前放射線治療歴有りは、29.3%、35.1%、組織型は、endometrioid 49.3%、47.3%、serous 15.3%、15.3%、adenosquamous 16.0%、13.0%、adenocarcinoma, unspecified 9.3%、13.0%、clear cell 6.0%、4.6%、mucinous 0%、0.8%、villoglandular 0.7%、1.5%、other 3.3%、4.6%であった。奏効率はADM群で25%(CR 8%、PR 17.4%)、AP群で42%(CR 19.1%、PR 22.9%)とAP療法が優れていた。無増悪生存期間の中央値はADM群で3.8ヶ月、AP群で5.7ヶ月とAP群が優れていた。全生存期間の中央値は、ADM群で9.2ヶ月、AP群で9.0ヶ月であり、有意差は認められなかった。毒性 (GOG criteria) については、ADM群、AP群それぞれ、白血球減少は、1,000〜1,999 /mm3 32.9%、および34.1%、1,000/mm3未満7.4%、および27.9%、血小板減少は、25,000〜49,999 /mm3 1.3%、および8.5%、25,000 /mm3未満0.7%、および5.4%、悪心・嘔吐は、悪心のみ、14.0%、および10.9%、24時間中1-5回の嘔吐13.4%、および27.1%、24時間中6回以上の嘔吐2.7%、および9.3%であった。(文中のデータはGOG statistical report 1998による)
| 3. |
|
Aapro MS, van Wijk FH, Bolis G, et al. Doxorubicin versus doxorubicin and cisplatin in endometrial carcinoma: definitive results of a randomized study (55872) by the EORTC Gynaecological Cancer Group. Ann Oncol 14:441-448,2003 (EORTC 55872) |
ヨーロッパの多施設共同試験グループEORTCによって行われた第二/三相比較試験で、進行・再発子宮体癌にADM単剤(ADM:60 mg/m2)とAP療法(ADM 60 mg/m2+CDDP 50 mg/m2)とを比較した。本試験の主要評価項目は抗腫瘍効果(奏効率、生存期間)であり、副次的評価項目は毒性であった。患者の適格規準は、組織学的に証明された進行・再発子宮体癌、(1)評価可能病変を有する、(2)75歳以下、(3)生命予後3ヶ月以上が期待できる、(4)PS 2以下、(5)十分な臓器機能を有する、(6)説明と同意が得られる、であった。除外規準は、(1)前化学療法がある、(2)放射線治療やホルモン療法から4週間以上の間隔がある、(3)同時・異時重複癌を有する、(4)脳・髄膜・胸水・腹水を有する、(5)骨転移のみ、(6)活動性の感染症、心不全、コントロールされない高血圧などの疾患を有する、であった。治療方法はADM単剤(ADM:60 mg/m2)、AP療法(ADM 60 mg/m2+CDDP 50 mg/m2)それぞれ、4週間隔に投与が反復された。骨転移などに対する放射線照射の併用は許容された。次コースの開始基準は白血球数3,000/mm3、かつ血小板数50,000-99,000/mm3であり、次コース開始基準を満たさない場合は投与が延期された。投与延期後、白血球数2,000-2,900/mm3、または血小板数50,000-99,000/mm3となった場合は、ADMの投与量を次コースより50%減量した。投与を2週間延期しても、白血球数2,000/mm3未満、または血小板数50,000/mm3未満であった場合は、プロトコール中止とした。Day15の白血球数1,000-1,900/mm3または血小板数50,000-74,000/mm3、またはビリルビン値2.5-5.0mg/dlであった場合は、ADMを50%減量、Day15の白血球数1,000/mm3未満、または血小板数50,000/mm3未満、またはビリルビン値 > 5.0mg/dlであった場合はADMを25%に減量した。口内炎が起こった場合ADMを50%減量した。血清クレアチニン値が正常値の1.25倍以上となった場合、または、クレアチニンクリアランスが半分以下に減少した場合は、CDDPの投与量を50%減量した。中等度以上の知覚異常、または筋力低下、または、聴力障害が出現した場合はCDDPの投与を中止した。最低2コース投与するものとし、増悪が認められるまで投与を継続した。ADMの投与は7コースまで(計420mg/m2)とした。本試験のデザインはランダム化第二/三相試験であり、第二相試験の段階でそれぞれの群で20例の登録があった時点で、5例以上奏効率があることが確認された後、第三相試験に移行した。1988年9月から1994年6月まで177名ADM群87例、AP群90例の患者が登録された。登録症例のうち、12例が不適格症例であった。うちわけは、ステージの違い(ADM群2例、AP群2例)、測定可能病変の欠如(ADM群3例、AP群1例)、評価病変に放射線治療歴あり(ADM群1例、AP群1例)、全身状態不良(AP群1例)、前治療あり(ADM群1例)であった。患者背景について、ADM群、AP群それぞれ、年齢の中央値は、63歳(41-76歳)、63歳(40-76歳)、PSはPS 0 39例、29例、PS 1 29例、42例、PS 2 17例、15例、不明2例、4例、進行例は、36例、36例、再発例は、51例、54例、腫瘍の分化度は、Well 16例、18例、Moderate/Poorly 71例、72例、前手術歴有りは、73例、79例、前放射線治療歴有りは、48例、40例、前化学療法歴有りは、1例、0例、前ホルモン療法歴有りは、15例、25例であった。
奏効率はADM群で17.2%(CR 9.2%、PR 8.0%)、AP群で43.3%(CR 14.4%、PR 28.9%)とAP療法が優れていた(p<0.001)。無増悪生存期間の中央値はADM群で7ヶ月(95%信頼区間6-10)、AP群で8ヶ月(95%信頼区間7-11)とAP群がやや優れていた。全生存期間の中央値は、ADM群で7ヶ月(95%信頼区間4-9)、AP群で9ヶ月(95%信頼区間7-14)であり、AP群がやや良好であった(long-rank p=0.107, Wilcoxon p=0.064)。
毒性(WHO grading)は、165例(ADM 82例、AP 83例)で評価され、ADM群、AP群それぞれ、白血球減少は、1,000〜1,999 /mm3 17.1%、および44.6%、1,000/mm3未満13.4%、および10.8%、血小板減少は、25,000〜49,999 /mm3 4.9%、および10.8%、25,000 /mm3未満0.0%、および2.4%であった。悪心・嘔吐は、Grade3が10例、29例、Grade4が0例、1例、感染は、Grade3が1例、0例、Grade4が0例、2例、心毒性は、Grade3が1例、1例、Grade4はなし、口内炎は、Grade3が0例、5例、Grade4は認められなかった。他に重篤な有害事象は認められなかった。AP群の90例中1例(1%)が1コース目開始2週後に治療と関連が否定できない死亡が観察された。
| 4. |
|
Randoll ME, Brunetto G, Muss H, et al. Whole abdominal radiotherapy versus combination chemotherapy in advanced endometrial carcinoma: A randomized phase III trial of the Gynecologic Oncology Group. Proc Am Soc Clin Oncol 21:2 (#3),2003 (GOG 122) |
米国GOGでは子宮体癌III/IV期の術後治療として、米国でそれまでの標準的治療であった全腹部照射 (WAI)とAP療法 (ADM60 mg/m2 + CDDP50 mg/m2、3週ごと、8コース、ADMの最大投与量は420mg/m2)とを比較するランダム化第三相試験を行った(GOG 122)。適格基準は、(1)子宮全摘術+両側付属器摘出術+骨盤及び傍大動脈リンパ節サンプリングによるステージングが行われ、III/IV期の症例、(2)術後残存腫瘍が2cm以下になった症例、(3)骨髄・腎・肝機能が保たれている症例、(4)傍大動脈リンパ節転移例では鎖骨上リンパ節生検が陰性・胸部CT陰性であること、であった。主要評価項目は無再発生存期間で副次評価項目は生存期間、毒性、QOLであった。不適格症例は26例(WAI群11例、AP群15例)であった。CDDPの減量は行わず、ADMの最大投与量は420mg/m2、血液毒性、消化器毒性、心毒性によりADMは15 mg/m2減量された。WAI群は治療完遂例84%、副作用で中止例3%、治療期間の中央値は 1.3ヶ月であり、AP群ではそれぞれ 63%、17%、5.1ヶ月であった。患者背景について、WAI群、AP群それぞれ、年齢の中央値は、63歳(26-84歳)、63歳(27-85歳)、PSはPS 0 51%、52%、PS 1 43%、43%、進行期III期は、75%、72%、進行期IV期は、25%、28%、腫瘍のGradeは、Grade115%、13%、Grade2 29%、30%、Grade3 52%、53%、組織型は、endometrioid 52.5%、47.4%、serous 21.3%、20.6%、mixed 9.4%、16.0%、adenosquamous 5.9%、6.2%、clear cell 3.5%、5.2%、であった。Grade 3-4の毒性としてWAIでは白血球数 4%、消化器症状 13%、治療死 4例であり、AP療法ではそれぞれ62%、20%、8例であった。無再発生存としてはWAI群202例中126例が再発し、AP群194例中111例が再発しており、両群間のHR 0.81 (95%CI 0.63-1.05)とAPが良好であった。生存としてはWAI群202例中120例が死亡、AP群194例中90例が死亡しており、両群間のHR 0.71 (95%CI 0.54-0.94)でAPが良好であった。 |