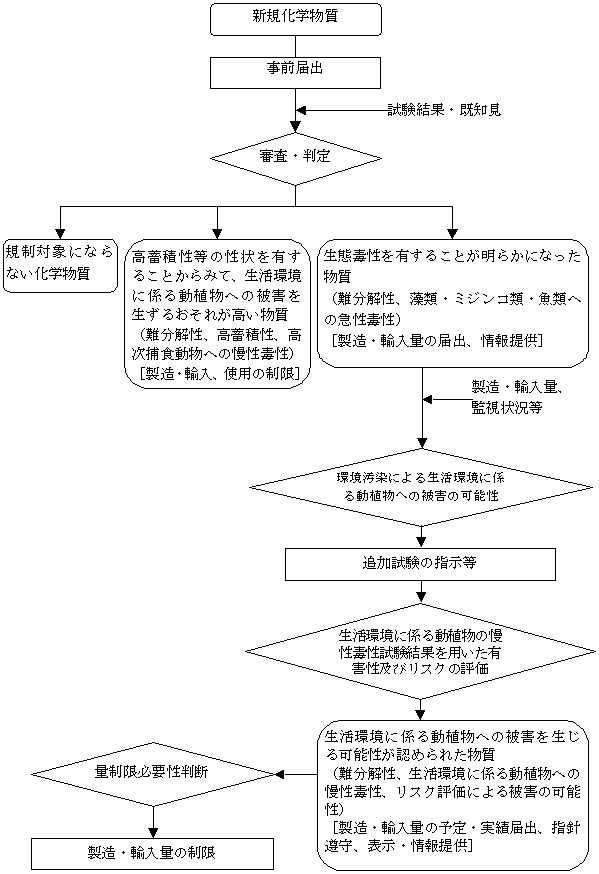環境中の生物への影響に着目した化学物質の審査・規則の考え方の案
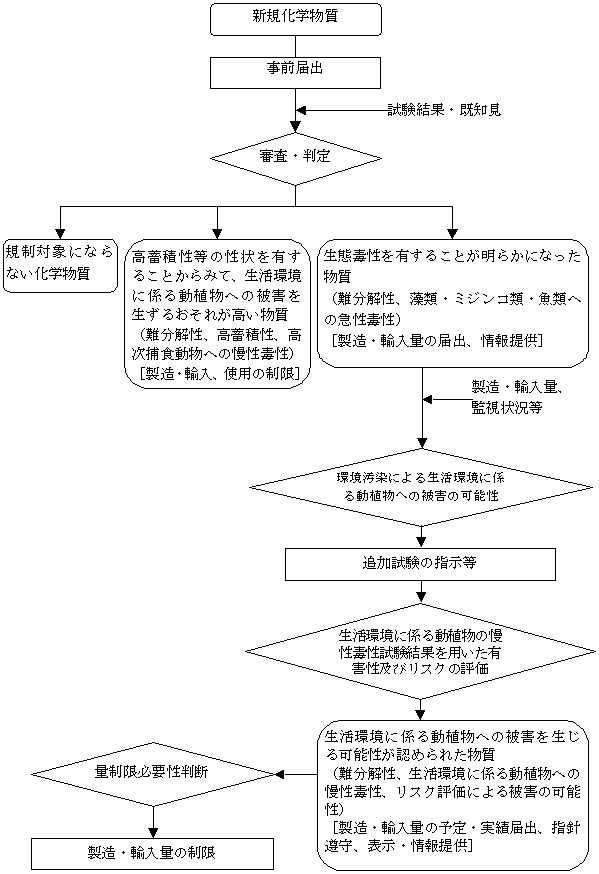
| 資料2 |
環境中の生物への影響に着目した化学物質の審査・規制について
(前回の議論の整理)
1.基本認識
化学物質の中には、人の健康への影響のみならず、環境中の生物への影響を示すものがあり、その程度は不明であるが、これらの化学物質が生態系に何らかの影響を及ぼす可能性は否定し得ない。一方、環境中の生物や生態系の本質的な多様性に起因して、保全すべき生態系、保全対象とすべき生物の範囲や保護の程度についてはさまざまな議論があり、化学物質による生態系全体への影響そのものを評価する手法が確立していない中で、現状では、個別の試験生物への有害性の評価を活用して生態系への影響の可能性を可能な限り考慮しようとされているところである。
国際的には、人の健康と環境(生物及びその生息環境を含む。)の保護を目的とすることを基本として化学物質管理に係る各種の政策協調や協力が進展しつつあり、近年採択された国際条約や諸外国における化学物質の審査及び規制の制度においても、人の健康の保護だけでなく環境の保全の観点が含まれているのが一般的となっている。
我が国においては、環境基本法及び環境基本計画において、生態系の保全は環境保全施策の重要な目標の一つであると位置づけられ、化学物質対策を推進していく上でも、生態系に対する化学物質の影響の適切な評価と管理を視野に入れることが必要であるとしている。これらを踏まえ、国は化学物質による環境中の生物への影響に関する試験の実施等を推進するととともに、環境基本法の生活環境* の保全の観点から、水産動植物の保全のための農薬の評価手法の見直し、有用動植物及び餌生物等を対象とした水生生物保全に係る水質目標の設定など、環境中の生物への影響に着目した様々な取組が進められているところである。
化学物質管理に係る法令においては、平成11年に新たに制定された化学物質排出把握管理促進法のPRTR制度やMSDS制度の対象化学物質には、人の健康を損なうおそれがある化学物質に加え、動植物の生息若しくは生育に支障を及ぼすおそれのある化学物質も選定されている。しかしながら、化学物質の審査及び規制に関して、昭和48年に制定された化学物質審査規制法は「人の健康を損なうおそれがある化学物質」による環境の汚染防止を目的としており、新規化学物質の事前審査をはじめ、生態系への影響に関する法的措置は講じられていない。本年1月のOECDによる我が国の環境保全成果レビューにおいても、化学物質管理において生態系保全を含むように規制の範囲をさらに拡大することが勧告されたところである。
| * | 人の生活に密接な関係のある財産並びに人の生活に密接な関係のある動植物及びその生育環境を含む。 |
| ○ | こうした状況等を踏まえると、政府部内における他の環境保全のための化学物質対策に係る取組も考慮に入れ、生態系への影響との因果関係に関する科学的不確実性に留意しつつ、各種の制度において整合性のとれた考え方のもとで、化学物質の審査及び製造等の規制においても、化学物質の環境中の生物への影響に着目した何らかの対応が必要である。 |
なお、ここでいう「規制」とは、化学物質の管理や取扱いに関する法的措置を広く指すものであり、化学物質の製造・使用等について、定量的な管理目標値等に基づいた制限(禁止を含む)による直接規制だけではなく、製造量等の届出、指針の策定・遵守、表示の義務付けなどの措置も含まれうるものとして用いている。
2.審査及び規制の基本的考え方及び枠組について
(1)生態毒性の審査の基本的考え方
生態系は、多様な生物と、それらの生息と生育の基盤となる大気、水、土などの自然的構成要素の総体として成り立っているものであり、それらの間の物質循環やエネルギーのやり取りといった複雑な過程を通じて相互に作用し、動的に複合したものとされている。
生態系への影響とは、こうした生態系の機能と構造を損なうことと考えることができるが、生態系を構成する要素は複雑で、地域によっても多種多様であり、また、時間的にも推移するものであるため、ある個別の要因による生態系に対する影響については、科学的因果関係を含めその程度を具体的に把握することが困難である。また、この意味で、特定の化学物質による生態系全体への影響を客観的に評価・把握するような手法は確立したものとはなっていない。
一方、生態系を構成する生物に注目すると、ある生物種を用いた試験結果において強い毒性を示す化学物質もあり、特定の生物個体群への重大な影響が生じる場合には、生態系の機能と構造に何らかの影響を及ぼす可能性を否定し得ない場合があると考えられる。このような点に着目して、化学物質による特定の生物に対する個体群レベルでの致死、成長、繁殖等への影響(生態毒性)を評価することにより生態系に何らかの影響を及ぼす可能性が示唆される化学物質を特定することは可能と考えられ、この考え方を基本とする生態毒性試験が国際的にも活用されているところである。
| ○ | 上記の認識を踏まえれば、個別の化学物質が生態系に及ぼす影響については、これを客観的・定量的に評価することは困難であるものの、生態毒性試験を活用することにより、生態系への何らかの影響の可能性が示唆される化学物質を特定できると考えられる。このため、現行の化学物質審査規制法における審査の枠組の中で、新規化学物質等につき、生態毒性試験結果を用いて、環境中の生物への影響について一定の評価を行うことが適当である。 |
| ○ | 生態毒性の評価の方法としては、欧米等における審査の初期段階での生態毒性の評価方法や化学物質排出把握管理促進法の対象物質選定時の考え方を参考にしつつ、試験の実施可能性・容易性や国際整合性を踏まえて設定すべきである。 |
| ○ | 具体的な評価の方法としては、生態系の機能において重要な食物連鎖等の関係に着目し、生産者、一次消費者、二次消費者等の生態学的な機能で区別して、それぞれに対応する生物種をモデルとして用いるとの考え方に基づき、試験実施が容易な藻類、ミジンコ類、魚類の急性毒性試験の結果を用いて評価することが適当と考えられる。なお、評価に用いる試験の項目や対象生物種に関しては、今後の科学的知見の充実や国際的な動向を十分踏まえ、将来において、必要に応じその内容について見直すことを可能とするような柔軟な仕組みとすることが適当である。 |
(2)生態毒性がある化学物質に対する規制の基本的考え方及びその枠組
生態毒性試験において一定の毒性を示す化学物質のうち、特に難分解性の性状を有するものについては、環境中へ放出された場合、長期間環境中に残留する性格を有することから、製造や使用等の状況によっては、回復困難な環境汚染を引き起こし、実際に環境中の生物の生息・生育等に影響を及ぼす可能性を否定し得ない。このような難分解性で生態毒性を有する化学物質による回復困難な環境汚染を未然に防止する観点からは、これらの性状が明らかとなった化学物質に対しては、人の健康の保護に係る措置と同様に、科学的知見に基づいて、その性状や環境中における残留状況に応じて必要な措置を講ずることが適当と考えられる。
また、具体的な措置の内容については、生態系あるいは環境中の生物への影響について現状において如何なる評価が可能かを十分に考慮しつつ、検討することが必要である。例えば、製造・輸入量の制限や使用の制限等、環境中の濃度を管理するために環境への放出量を制限する措置(直接規制)を講ずる場合には、定量的評価に基づきリスク管理に必要な目標値等が合理的に設定されることが必要である。また、直接規制以外の手法により化学物質の環境への放出を抑制するための適正管理を促す措置を講ずる場合には、必ずしも定量的な目標値等に基づかずに実施することも可能であると考えられる。
| ○ | このような点も考慮すると、生態系への化学物質の影響の適切な評価と管理を視野に入れた化学物質対策を推進する中で、生態毒性を有する難分解性の化学物質に対する規制としては、以下の枠組とすることが適当である。 |
|
(1) 適正管理を促す措置 生態毒性を有する化学物質であっても、生態系への影響との因果関係における不確実性は否定できず、また、これを定量的に評価することは困難である。このため、生態毒性を有する化学物質であっても直ちに生態系を保護の対象として数量制限を行うなどの直接規制を講ずることは合理的ではない。しかしながら、生態系への影響の可能性を考慮すれば、環境放出を抑制することが望ましいことから、難分解性で生態毒性を有する化学物質については、これを取り扱う事業者が環境汚染の防止のための適正管理を行えるよう、生態毒性等に関する情報を提供するための措置を導入する。 (2) 定量的な管理のための直接規制 難分解性で生態毒性を有する化学物質については、保護の対象を一定の範囲に限定することによって、それらの動植物に対し被害を生ずるおそれについて定量的に評価することが可能となる場合もある。このような場合には、リスク管理に必要な目標値等が合理的に設定できるため、被害の未然防止の観点から、直接規制の導入を検討することも可能であると考えられる。 |
| ○ | 直接規制が必要な場合としては、現在の化学物質審査規制法における管理対象化学物質の要件の考え方を考慮して整理すれば、以下の二つが考えられる。 |
| (1) | 難分解性で生態毒性を有する化学物質については、生活環境に係る動植物に対しても有害性を有し、相当広範な地域の環境に相当程度存在しているか、又は近くその状況に至ることが見込まれる場合には、それらの動植物に被害を生ずる可能性があるものもある。このため、環境中の濃度をそうした被害が生じないレベルに管理するため、こうした性状が明らかになった段階で、監視を行うとともに、必要な場合には放出を直接抑制することが必要となる。 |
| ○ | このため、難分解性で生態毒性を有する化学物質については、製造・輸入実績数量及びその用途の把握等を通じて環境汚染の状況を推定し監視することが必要である。 |
| ○ | 難分解性で生態毒性を有する化学物質について、生活環境に係る動植物に対しても有害性を有し、それらに被害を生ずるおそれが認められる状況に至った段階では、現在の第二種特定化学物質と同様に、さらに製造・輸入予定数量を併せて把握し、被害の発生を防止するため必要な場合には製造・輸入予定数量の制限を行うことが必要である。 |
| ○ | また、数量制限が必要となるような環境汚染の状況を生ずることのないよう、事業者において環境放出量を抑制することが重要であり、個別の化学物質ごとに、その取扱いにあたってとるべき管理のための措置を指針として示し事業者に遵守させるとともに、表示を義務づけるといった措置を講じることが必要である。 |
| ○ | 生活環境に係る動植物に被害を生ずるおそれの判定においては、環境中での残留に伴う低レベルでの長期的な暴露による影響を判断するために、人の生活に密接な関係のある動植物のうち、暴露を受けやすく、実際に被害を受ける可能性があるものに係る慢性毒性試験により有害性を確定した上で、その結果と、モニタリング調査またはモデル予測に基づき予測される環境濃度を用いて判断することが適当である。 |
| (2) | 難分解性に加え高蓄積性を有する化学物質については、食物連鎖を考慮すると、特に高次捕食動物が、環境中の化学物質による直接的な暴露よりも食物となる生物の摂取を通してより高い暴露を受け、さらにそのようにして体内に取り込んだ化学物質を体内に蓄積してしまうこととなる。高次捕食動物には鳥類や哺乳類といった人の生活に密接な関係のあるものが含まれることから、難分解性・高蓄積性を有する化学物質が高次捕食動物に対して有害性を持つものである場合には、これが一般的に製造、使用等された場合、生活環境に係る動植物への深刻又は不可逆な被害を生ずるおそれが高いと認められ、環境への放出をできるだけ防ぐことが必要となる。 |
| ○ | このため、難分解性・高蓄積性であって高次捕食動物に対する有害性を有する化学物質については、現在の第一種特定化学物質と同様に可能な限り環境中へ放出されることがないよう厳しく管理されるような制限措置を講じることが必要である。 |
| ○ | 判定の指標としては、被害を受ける高次捕食動物に関して、技術的対応可能性も踏まえつつ生物種や試験法を選定する必要があり、具体的には、例えば、哺乳類、鳥類の繁殖や発生等に係る慢性毒性試験の結果を用いることが適当である。 |
(3)既存化学物質について
| ○ | 既存化学物質についても、以上の枠組にしたがって、既存の知見や点検結果を活用して判定を行い、必要な場合には規制対象とすべきである。 |
3.関連事項
| ○ | 環境中の生物への影響に着目した化学物質の審査・規制に関連して以下の事項についても対応を図ることが必要である。 |
(1)試験実施体制の整備
現在、国内において生態毒性試験を実施可能な機関が少ないなど、今後、生態毒性の審査制度を導入するに当たって必要となる体制の整備は必ずしも十分でないと考えられる。
| ○ | このため、今後、生態毒性試験の実施が円滑に進むよう、試験機関の能力向上に向けた支援、試験生物の供給体制の整備等により、生態毒性試験を実施可能な試験機関を拡充し、円滑な審査・規制の実施に必要な体制の構築に取り組むことが必要である。 |
(2)調査研究の推進
化学物質による生物への影響に関する知見としては、藻類、ミジンコ類、魚類の急性毒性以外のものについては必ずしも十分であるとは言えない状況にある。
| ○ | このため、生態系や環境中の様々な生物の生息又は生育への化学物質の影響に関し、調査研究が進展するよう、各種生態毒性試験の実施、調査研究体制の整備、生態毒性に係るデータベースの整備、分子生物学的手法を用いて毒性機序の解明を目指す毒性ゲノム科学(Toxicogenomics)に係る調査研究等を推進していくとともに、化学物質のモニタリングや生物学的なモニタリング等に総合的に取り組むことにより実環境における化学物質と生物の生息又は生育状況との因果関係の把握にも努める必要がある。 |
| ○ | なお、内分泌かく乱作用が疑われる化学物質については、国際的な動向も踏まえながら、引き続き作用機序の解明、試験法の開発、有害性やリスクの評価など科学的知見の集積等に努めていく必要がある。 |
(3)良分解性物質への対応
現行の化学物質審査規制法においては、新規化学物質について事前審査制度を設け、環境中に長期的に残留するおそれのある難分解性の化学物質については蓄積性、長期毒性に関する審査・判定を行うまでは製造・輸入を認めないこととする一方、良分解性と判定された化学物質については、その段階で製造・輸入を認めている。また、難分解性の化学物質のうち環境汚染を生じ人の健康を損なうおそれがある化学物質を対象として、製造・輸入等の規制措置を講じている。
良分解性の化学物質の中にも、生態毒性を有するものがあり、生産量や使用形態、環境への放出状況等によっては環境中に継続的に存在し、環境中の生物へ何らかの影響を及ぼす可能性があると考えられる。このため、このような化学物質による環境汚染の未然防止に取り組むことが必要となるが、良分解性の化学物質は、本質的に環境中で分解・消失しやすいものであるため、その環境汚染を防止するための取組は、難分解性物質とは異なるものとなる。
また、分解性の如何を問わず、化学物質による環境汚染の防止のため、これまでにもさまざまな自主的取組や法的規制により排出抑制対策が講じられ、一定の成果を上げてきていることにも留意する必要がある。
| ○ | こうしたことを踏まえると、良分解性の物質については、必要に応じ、リスク評価を行っていくとともに、PRTR制度の対象とする等の自主的な管理の改善措置、他法律や条例に基づく排出規制等の排出段階での措置により対処することを基本とすることが適当である。 |
| ○ | なお、良分解性物質の有害性に関するデータの取得については、高生産量の物質を中心に、国際的にも協調しつつ官民が共同でこれを把握し評価を行う取組が進められていることから、このような取組を一層推進していくことが適当である。 |
環境中の生物への影響に着目した化学物質の審査・規則の考え方の案