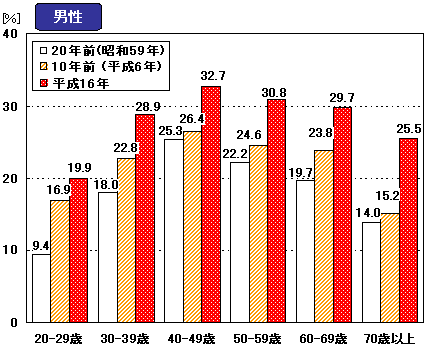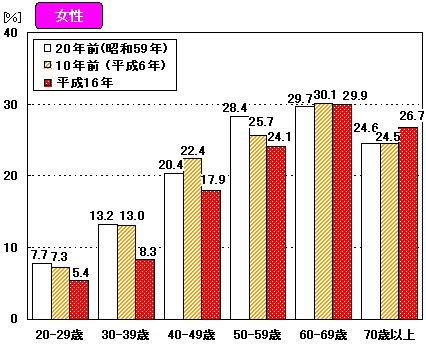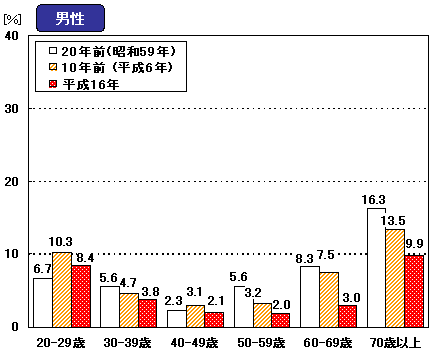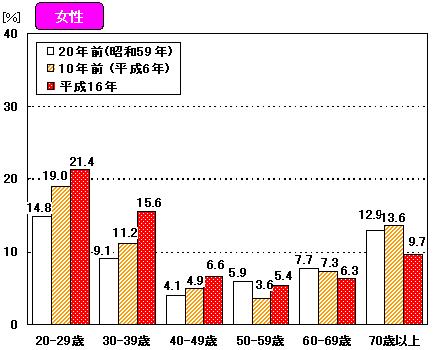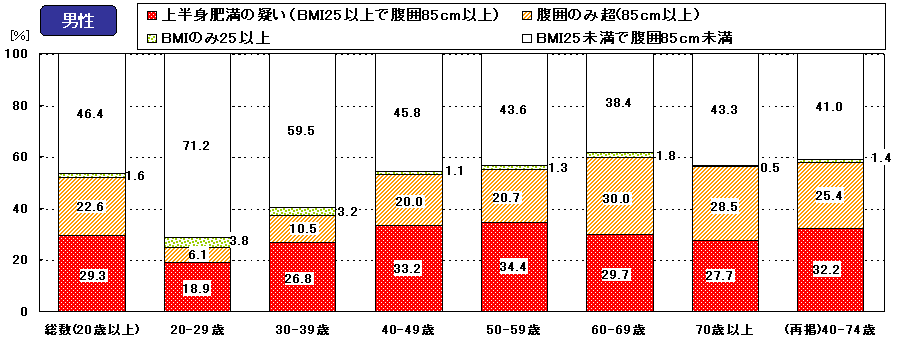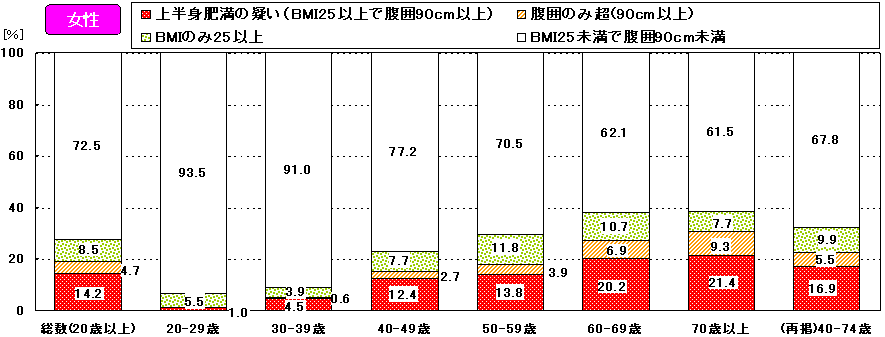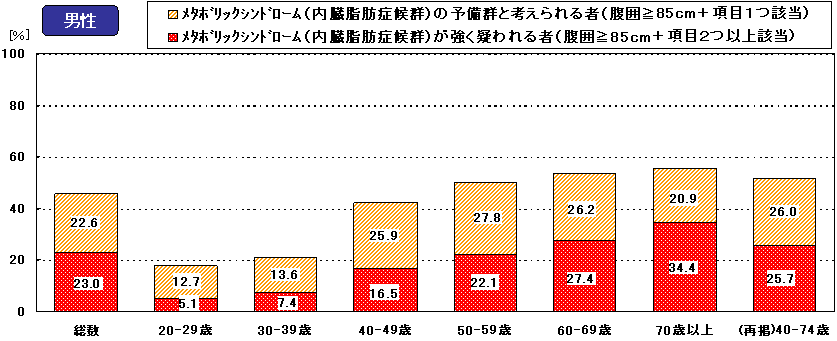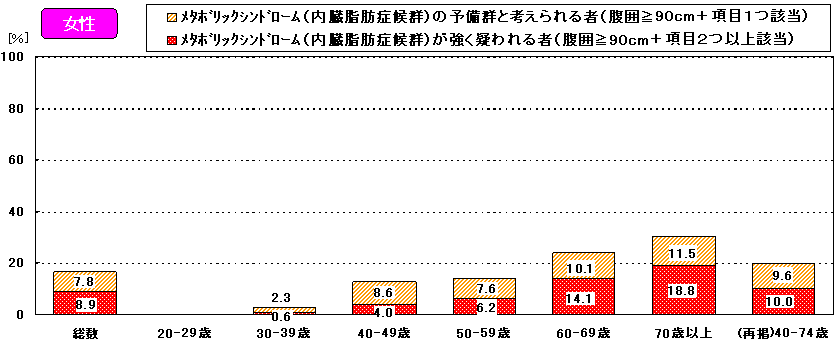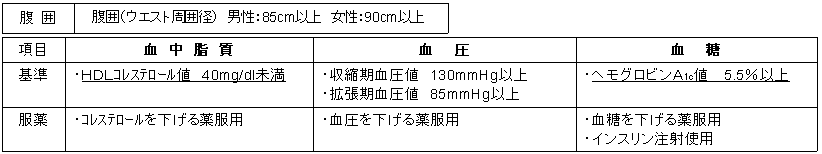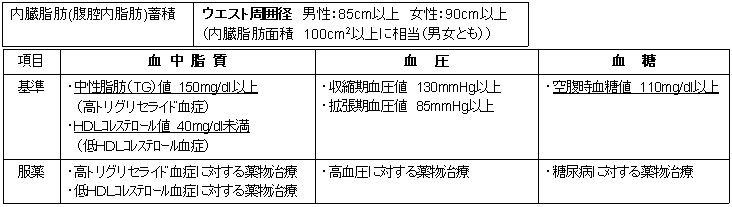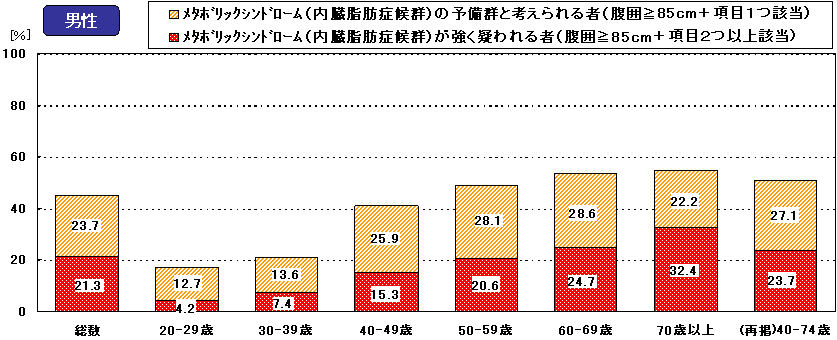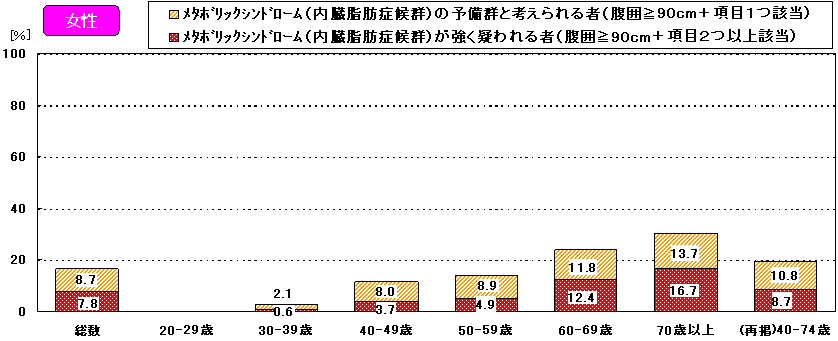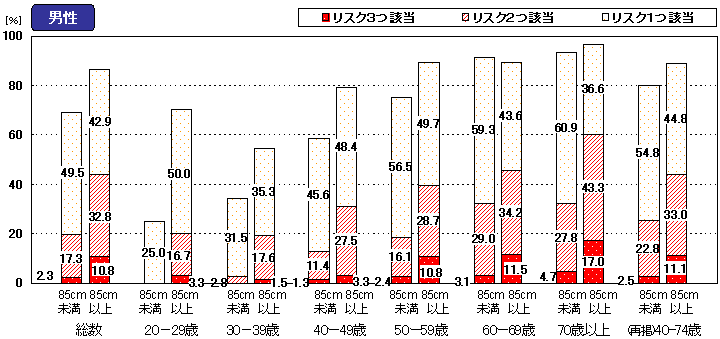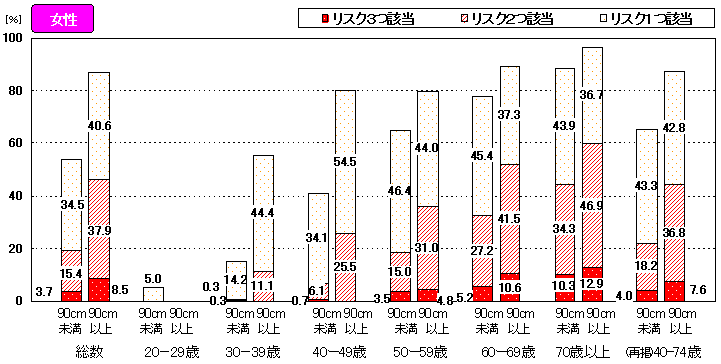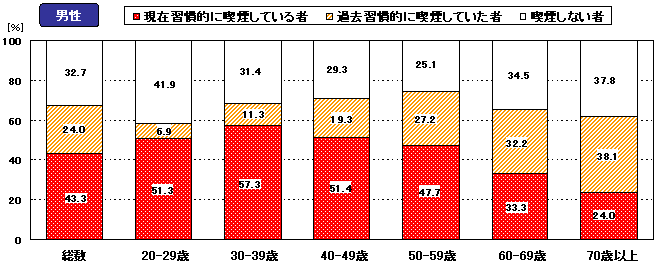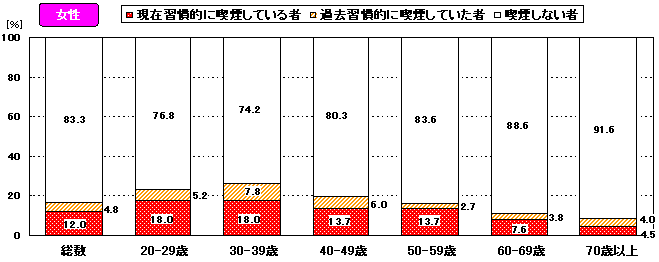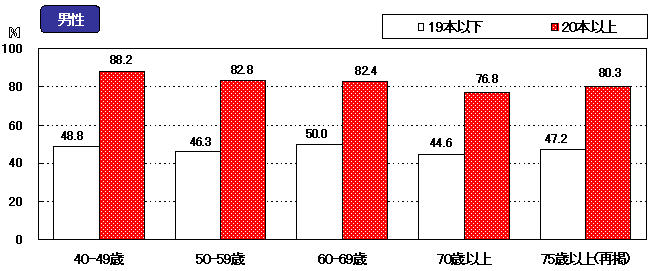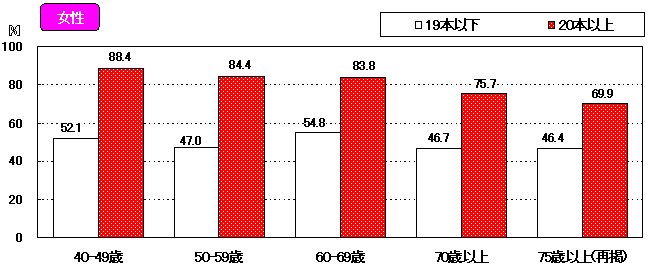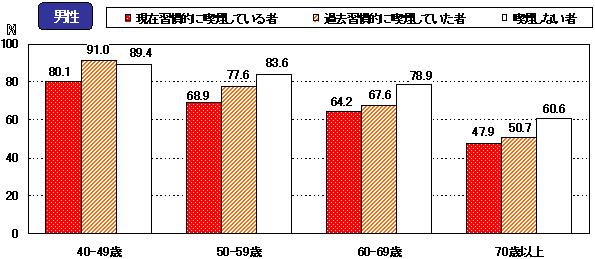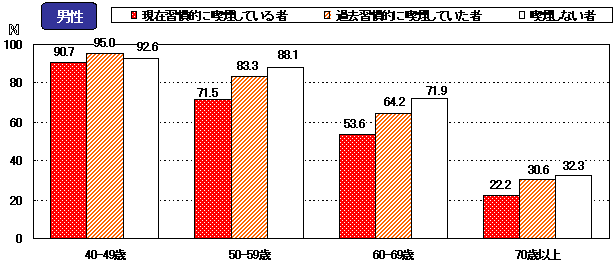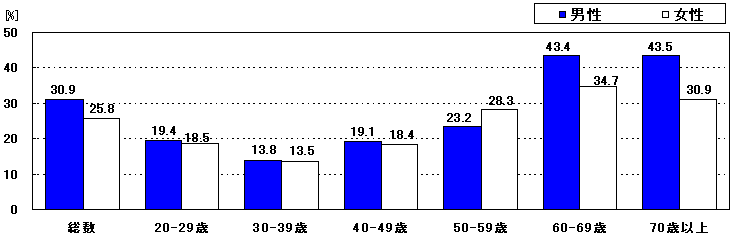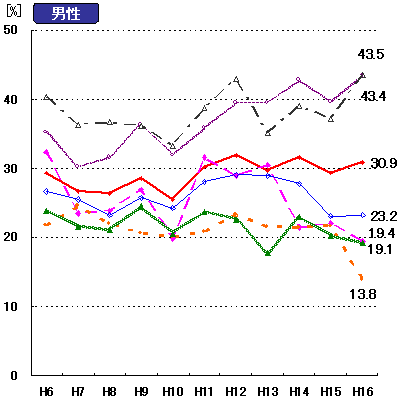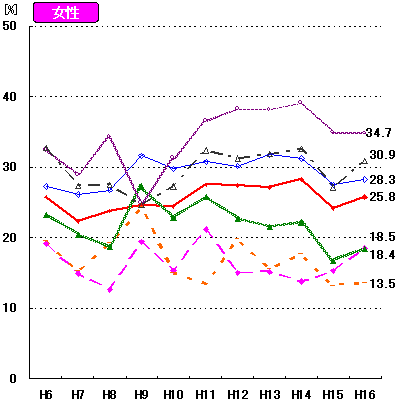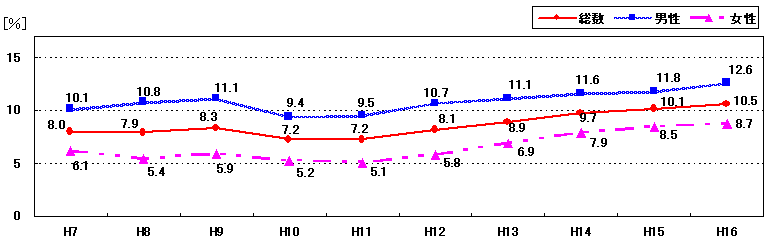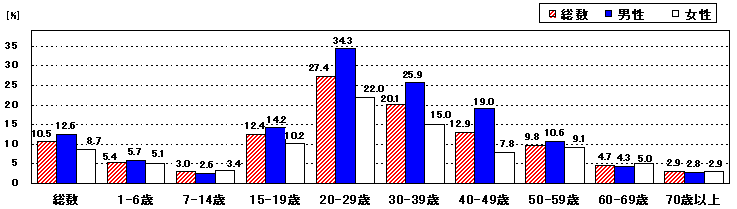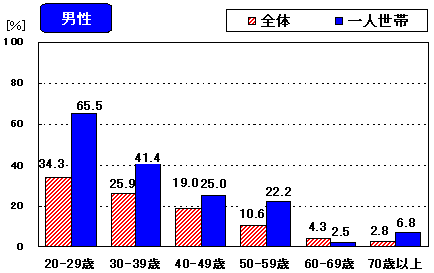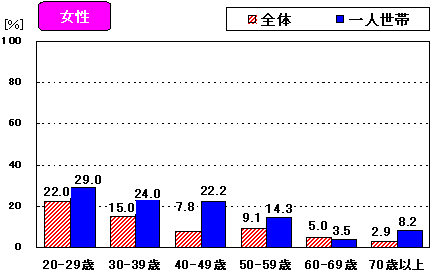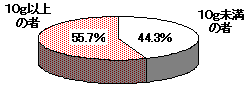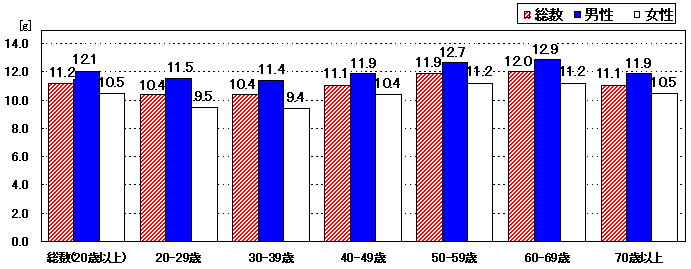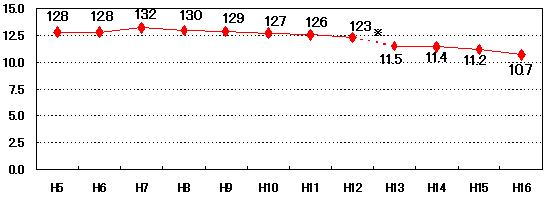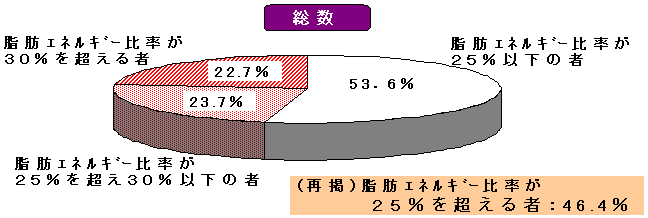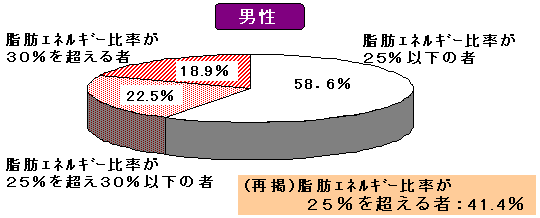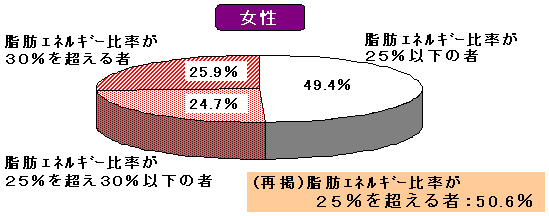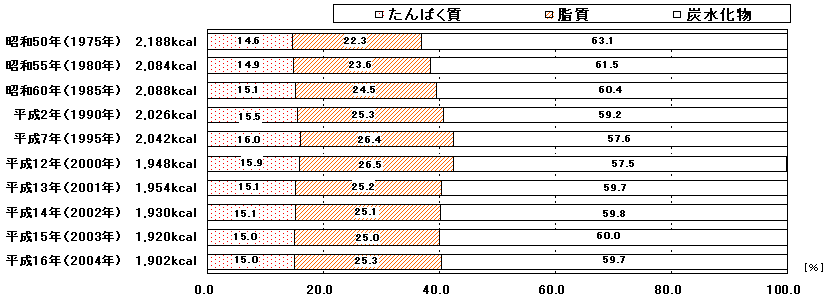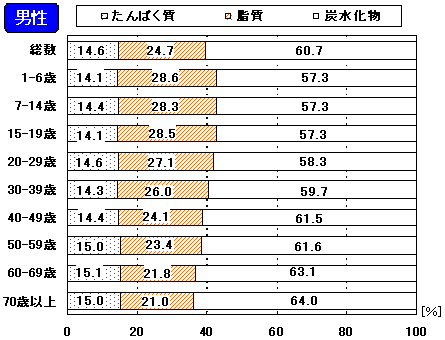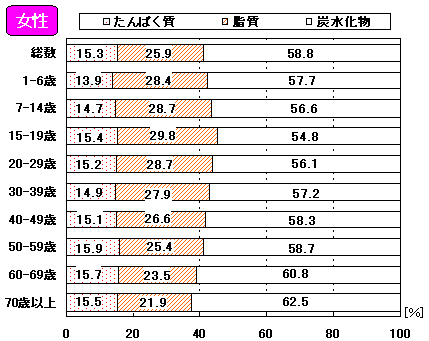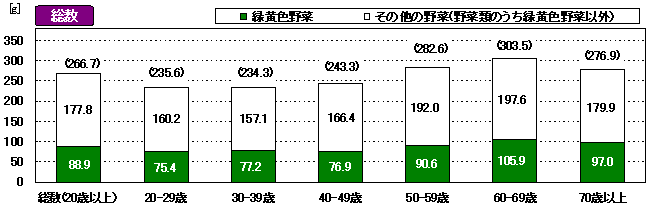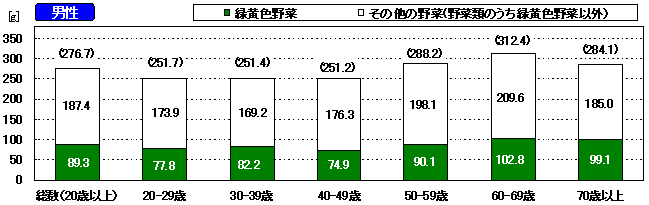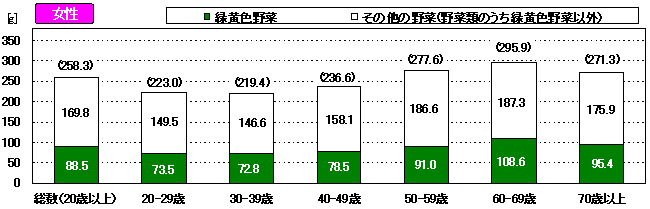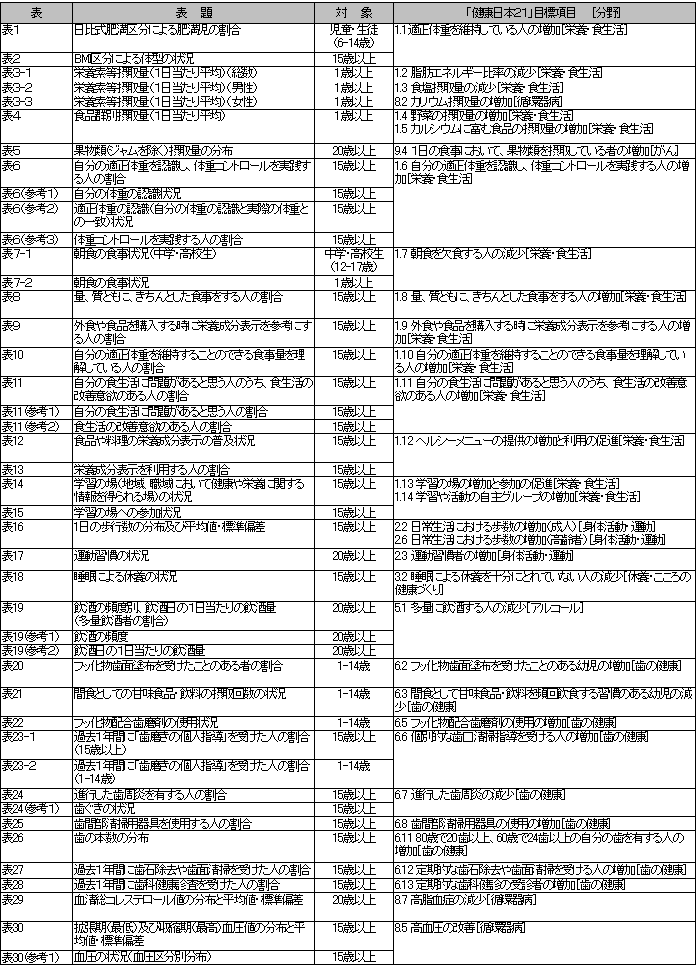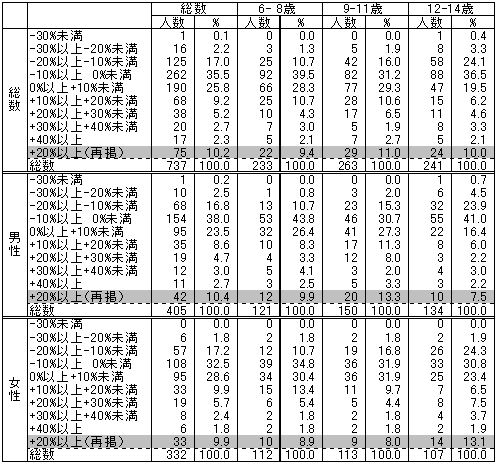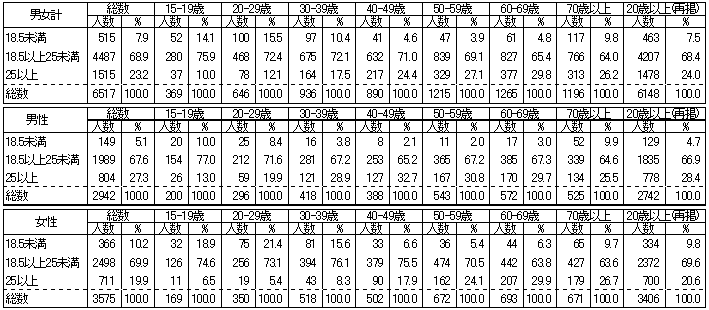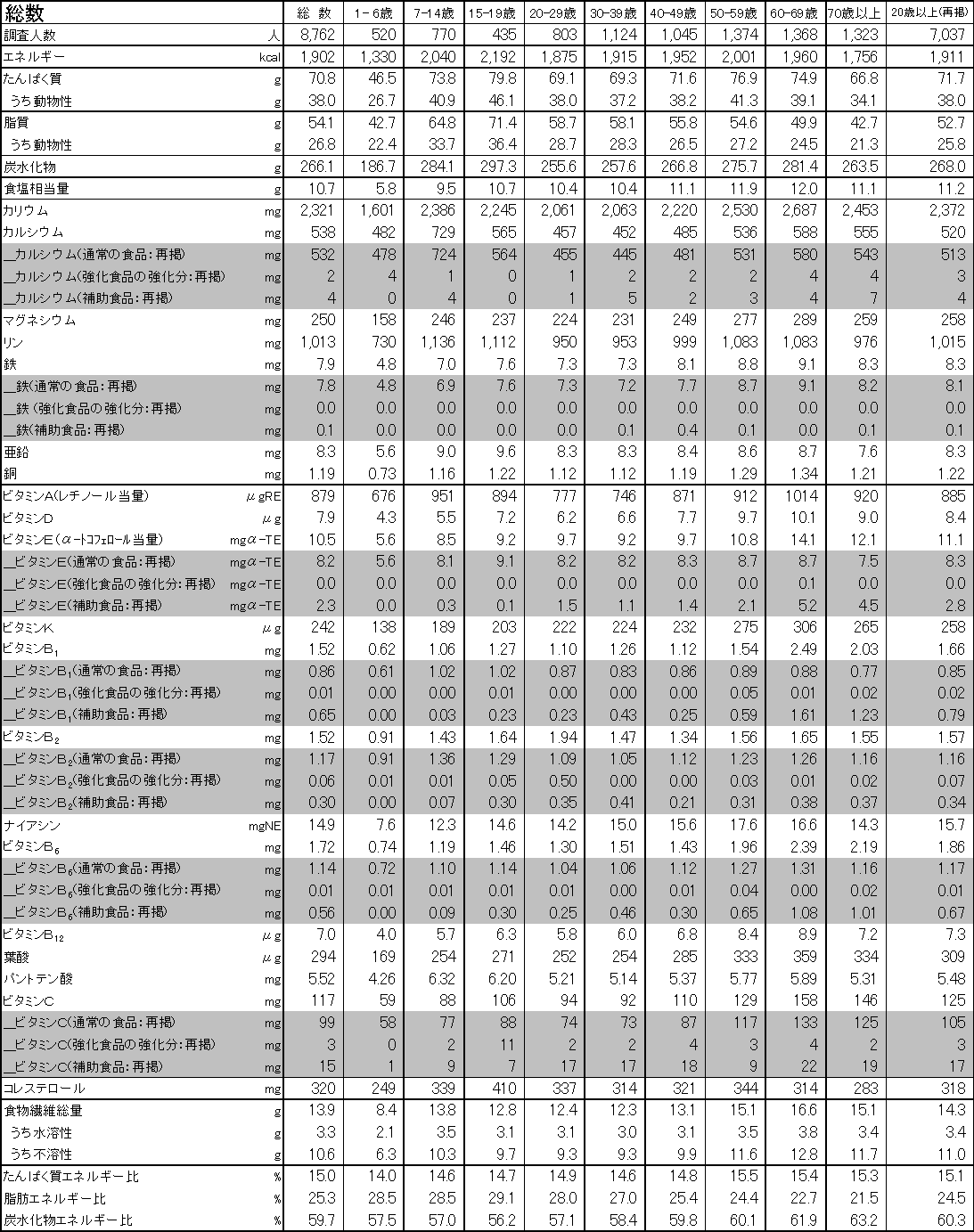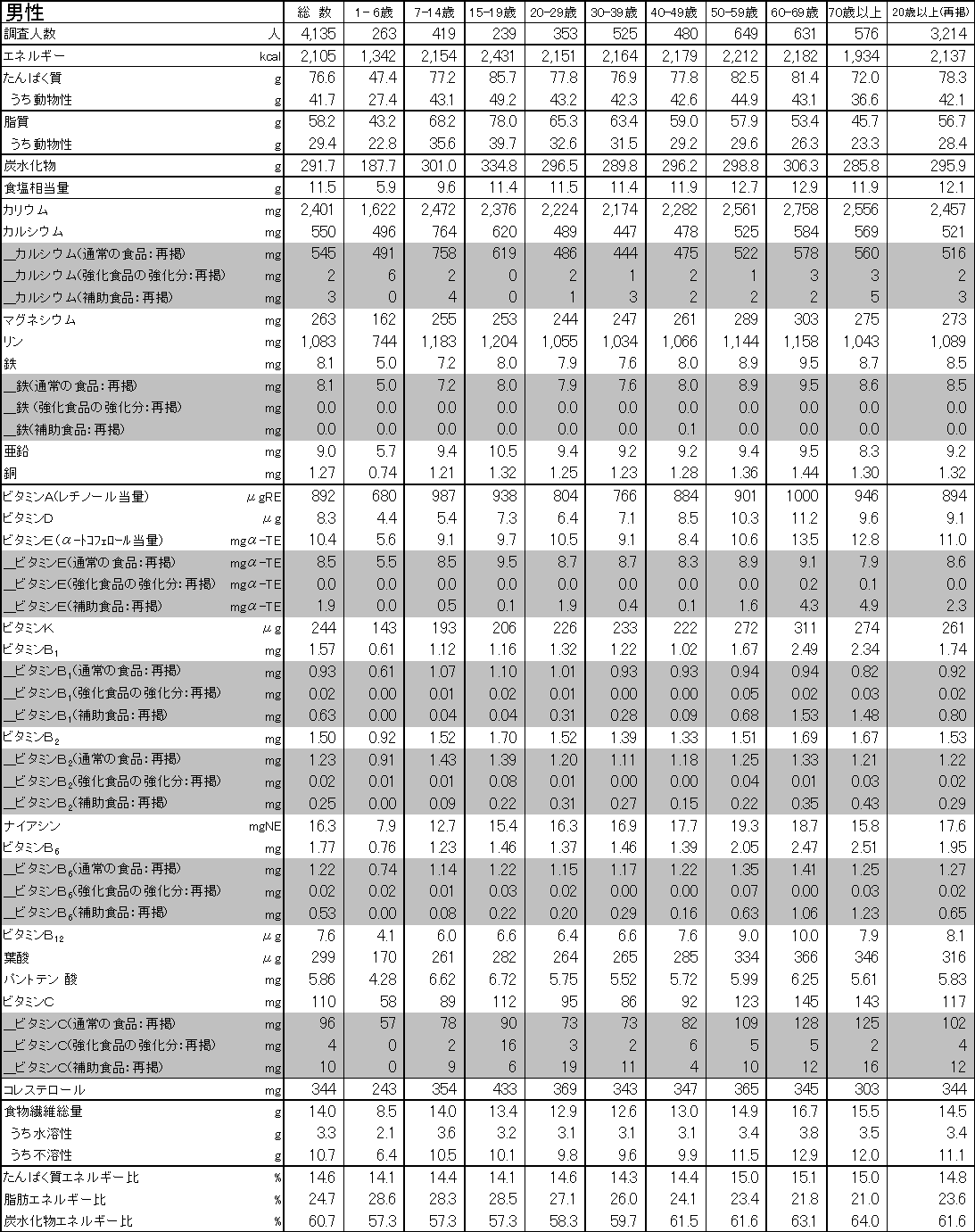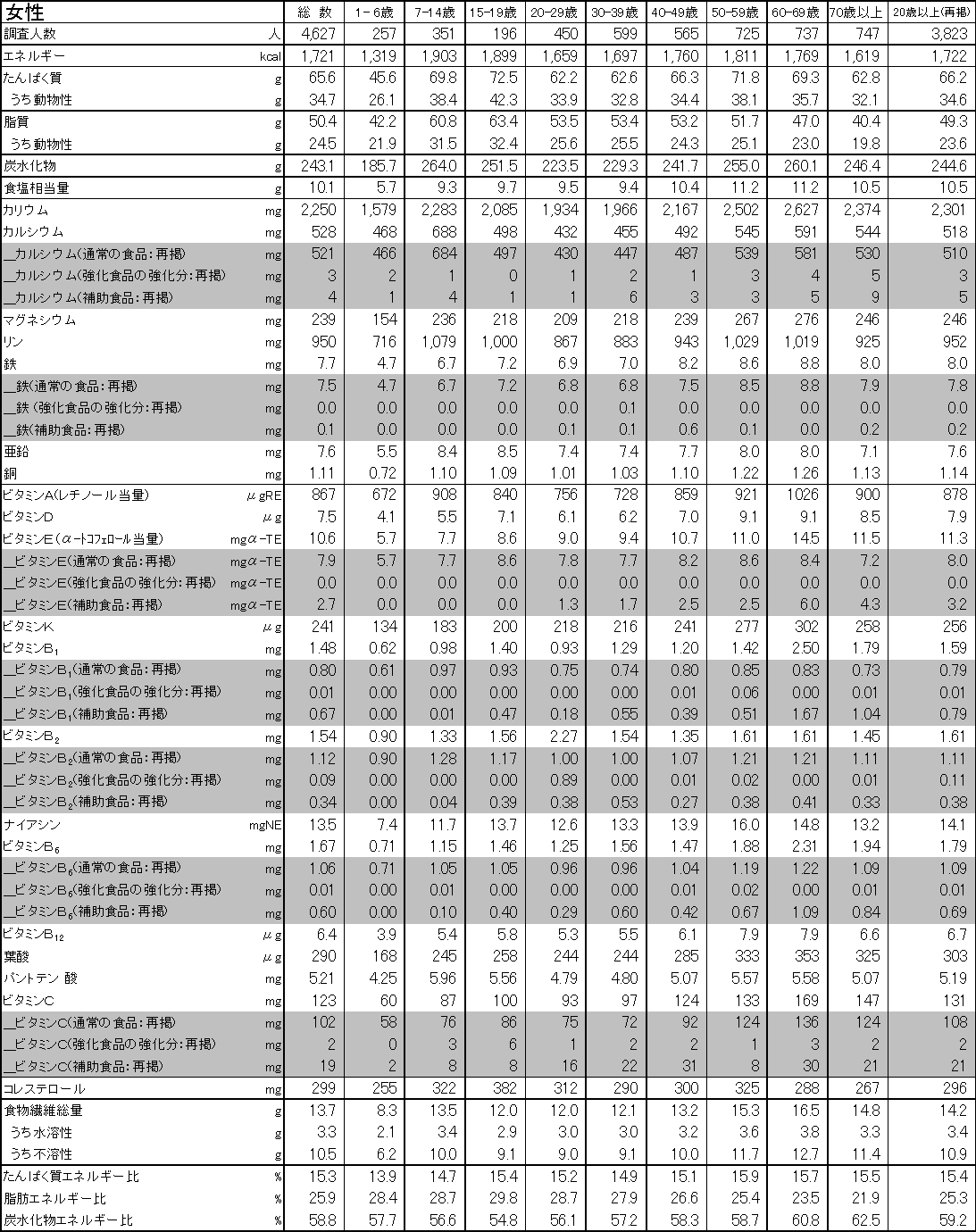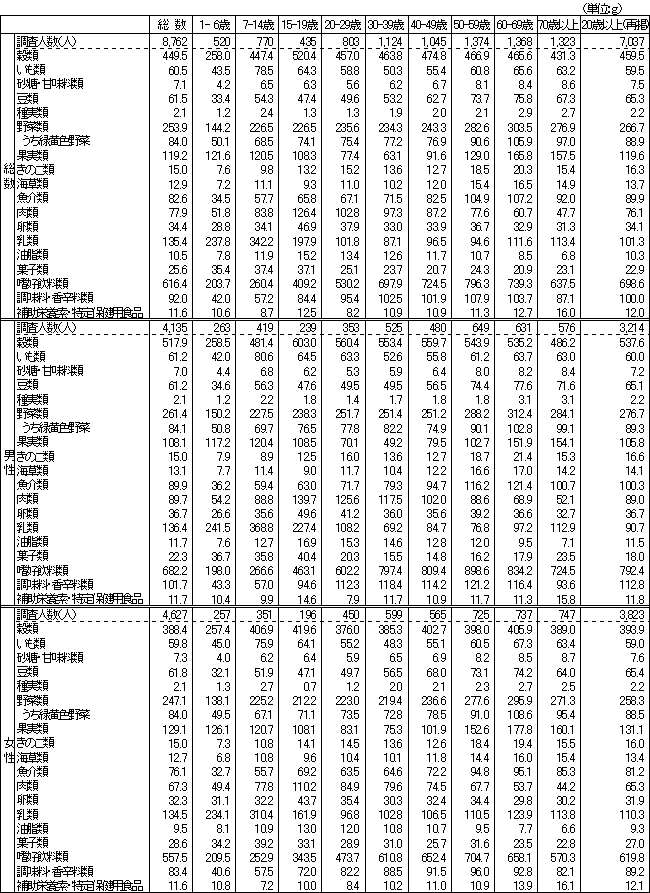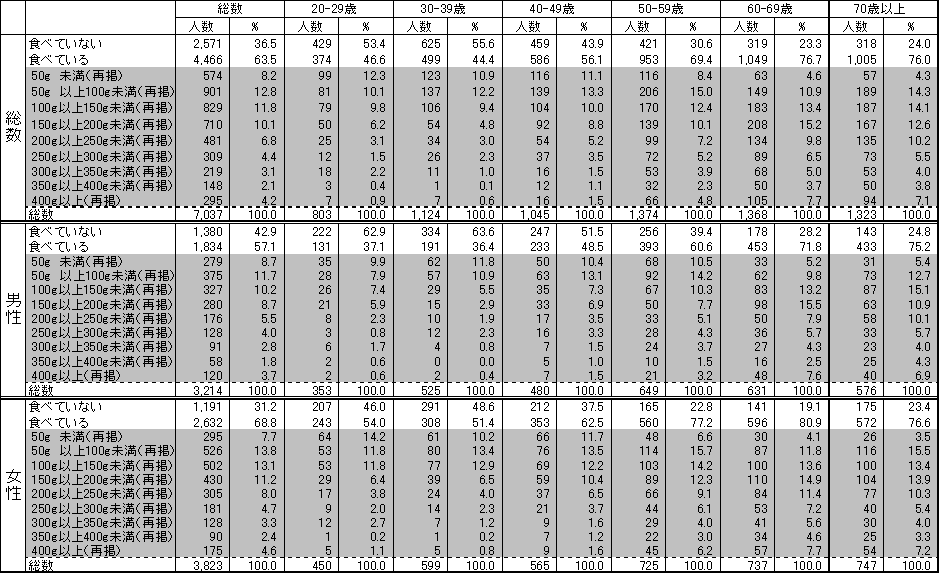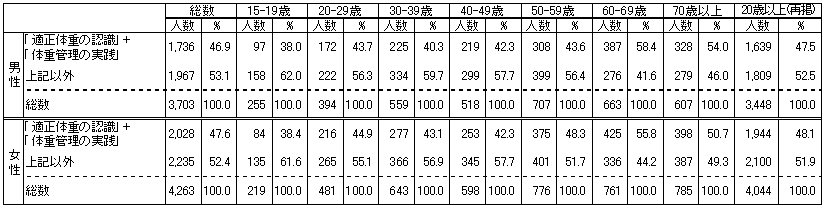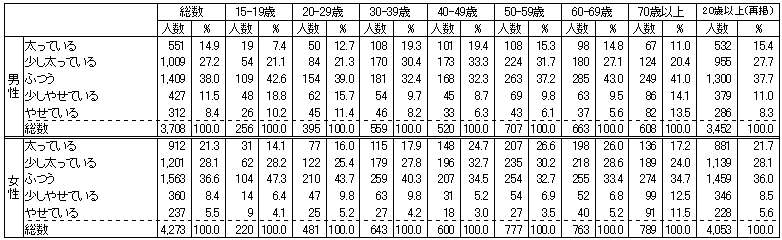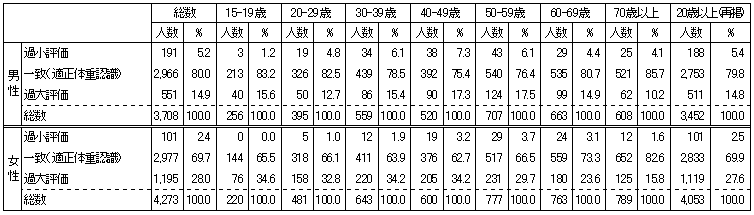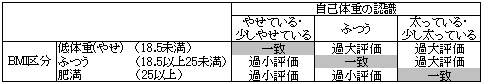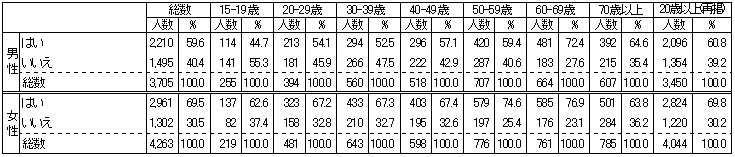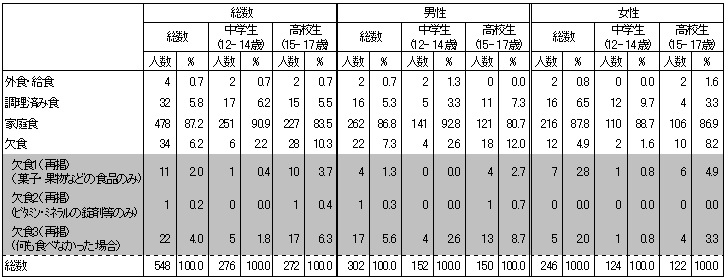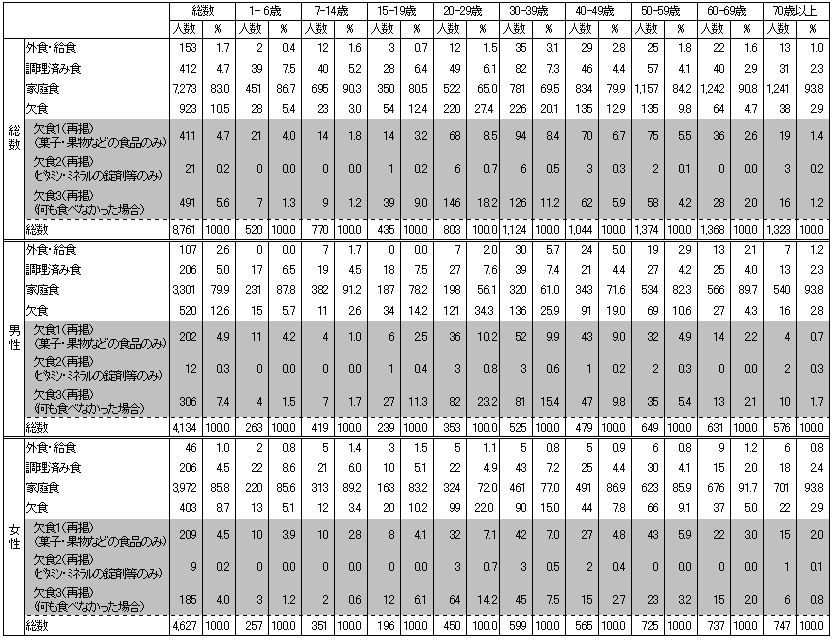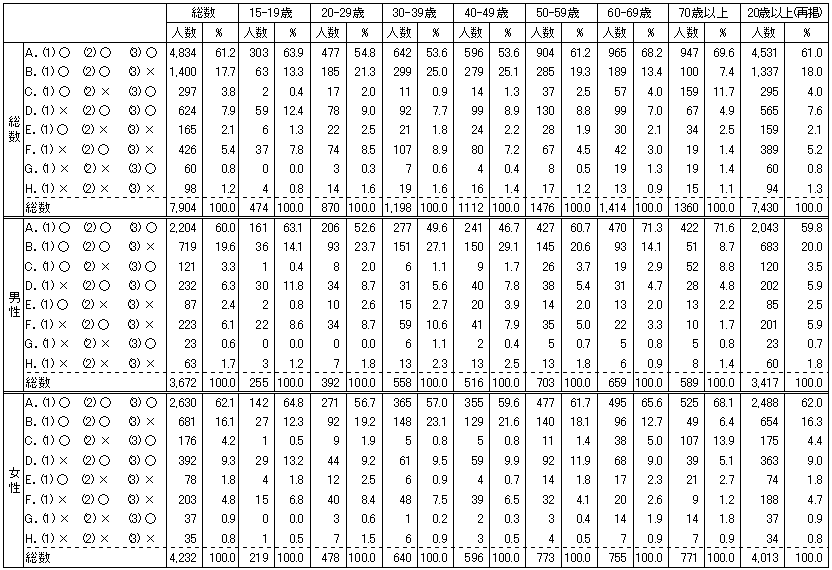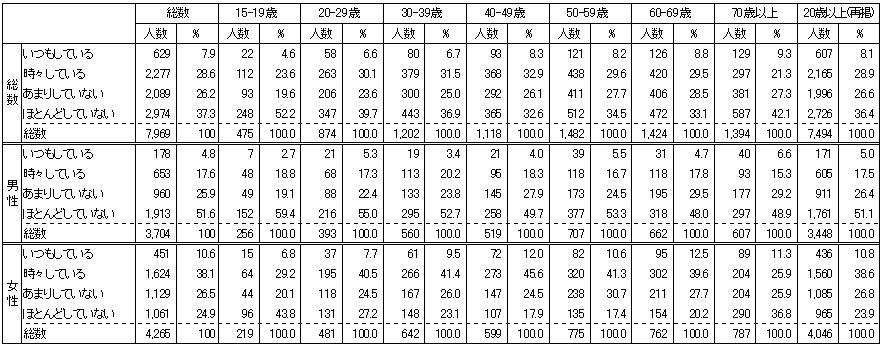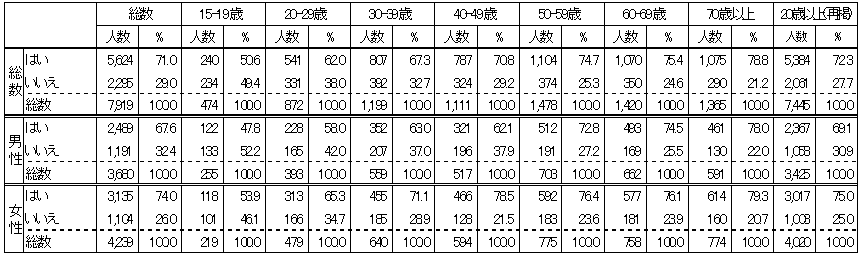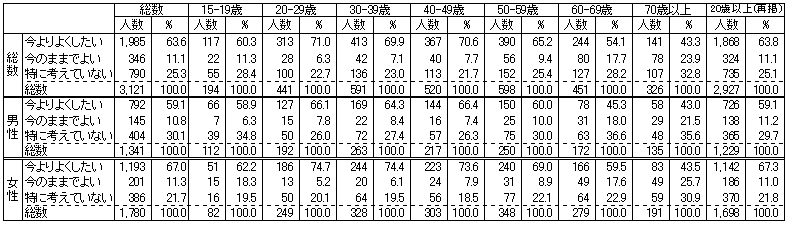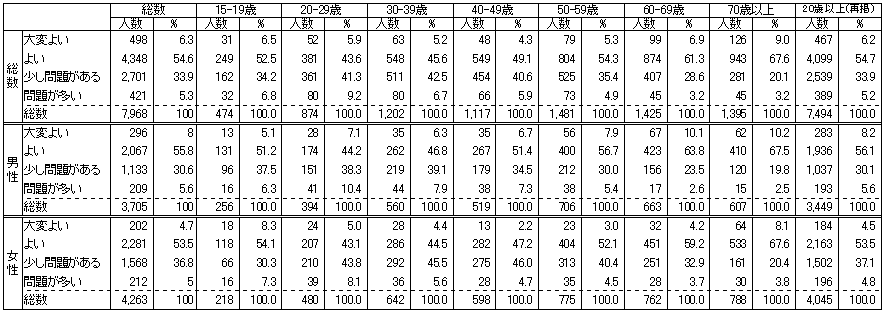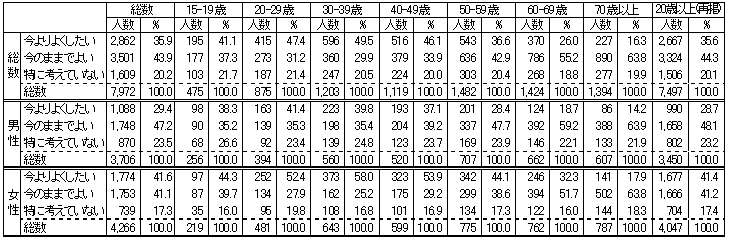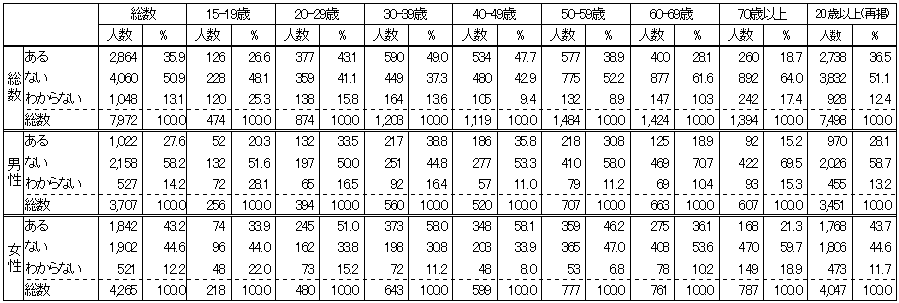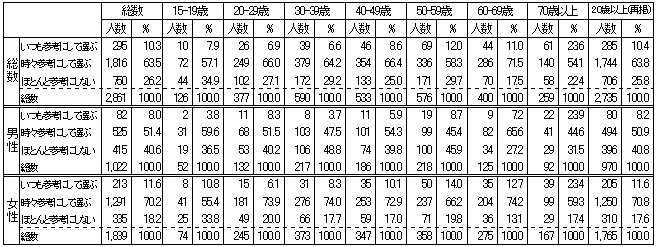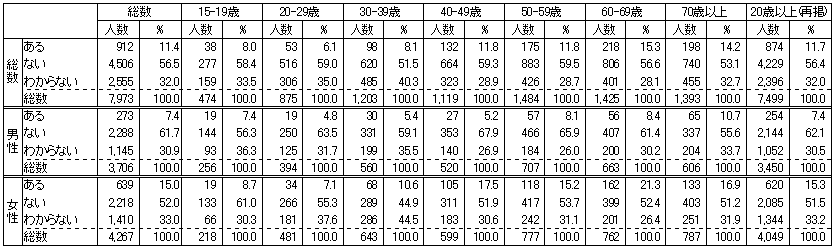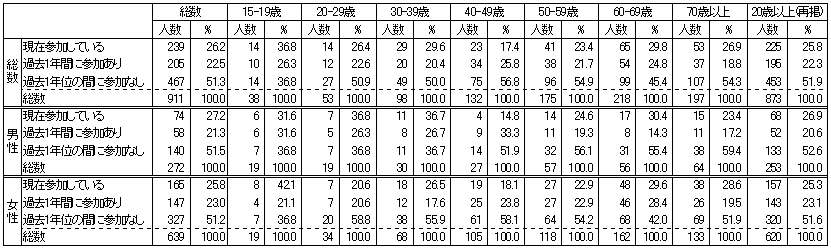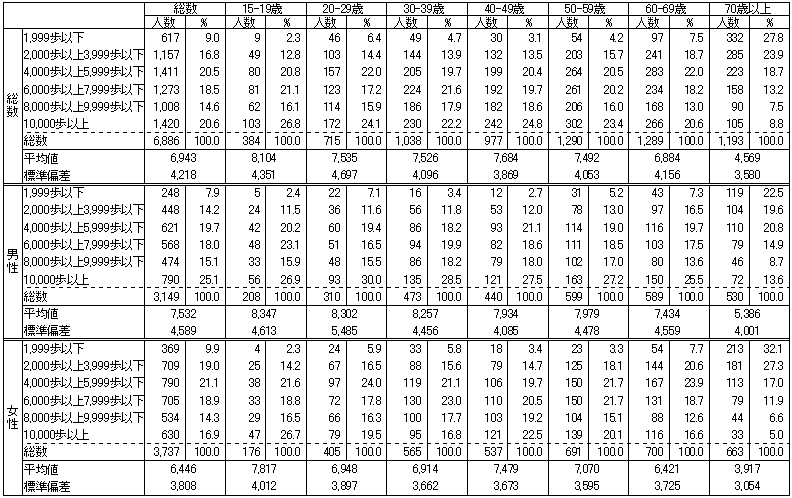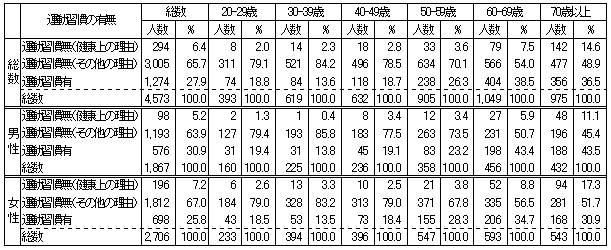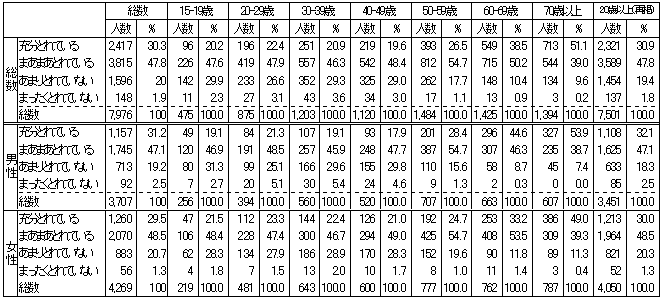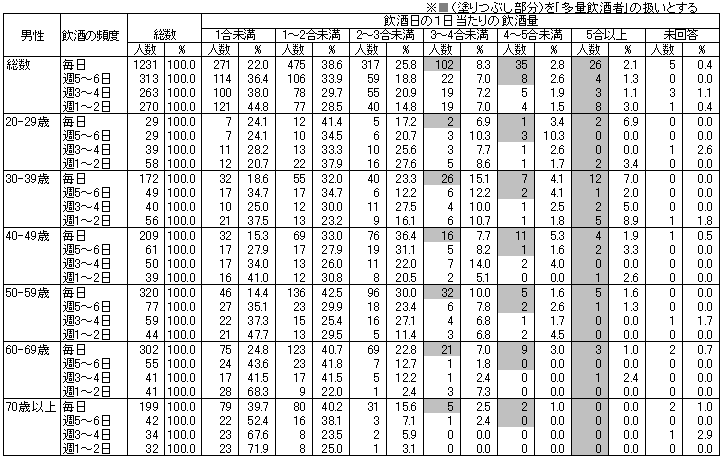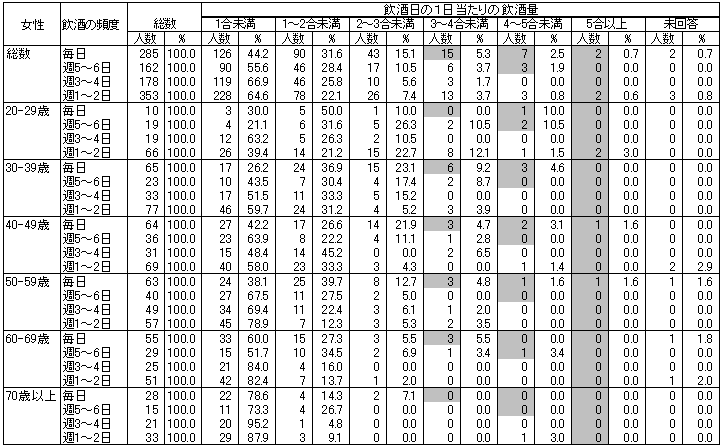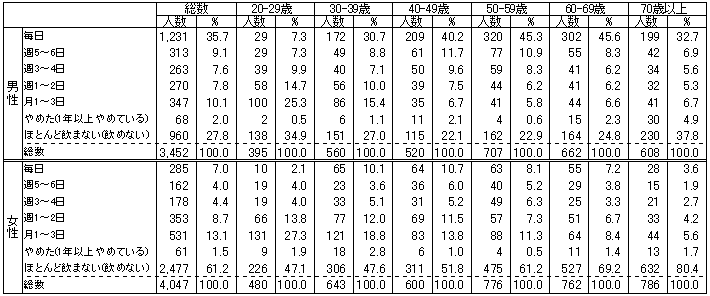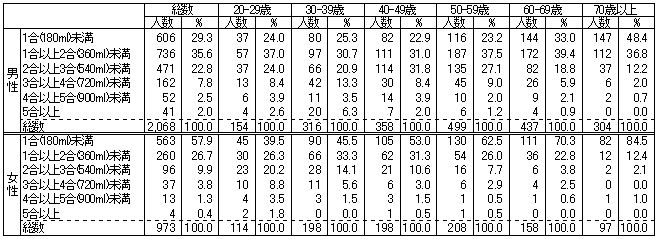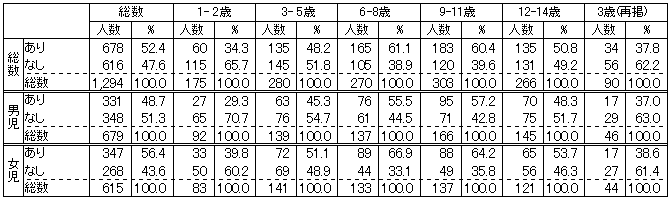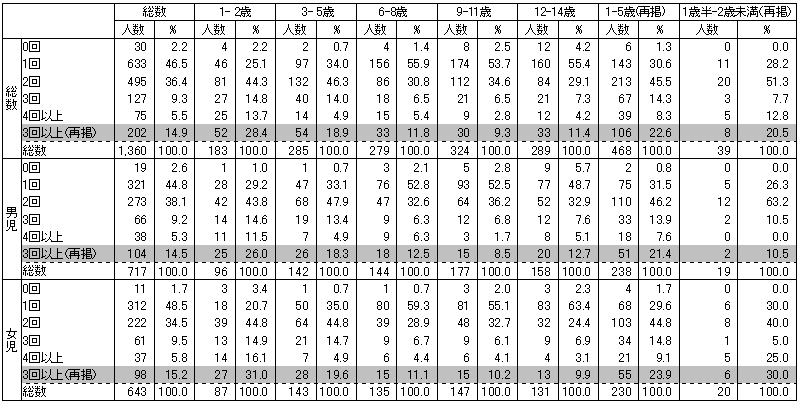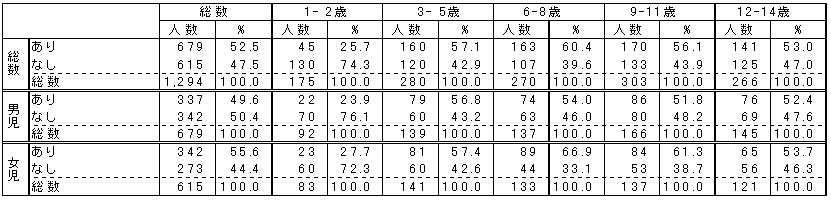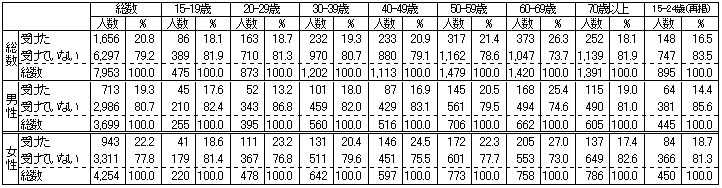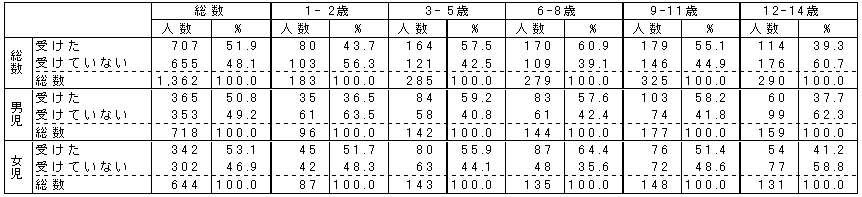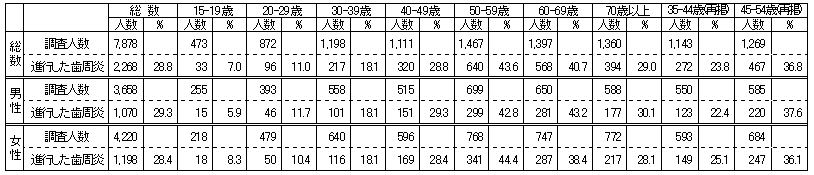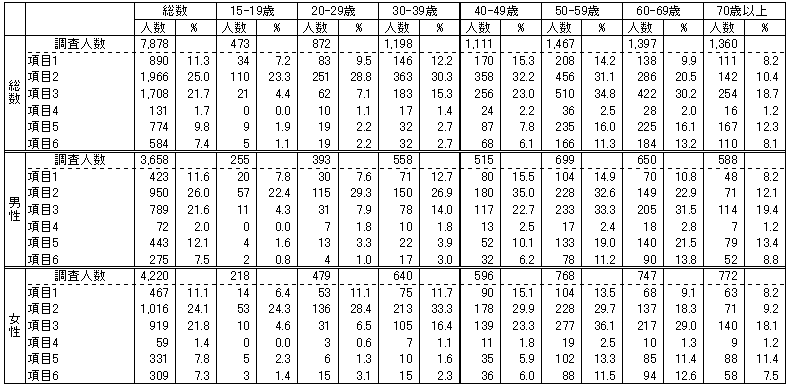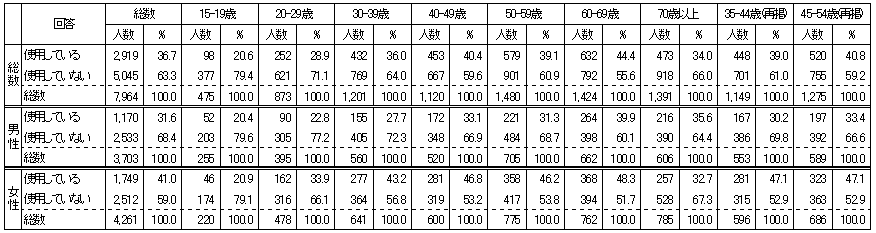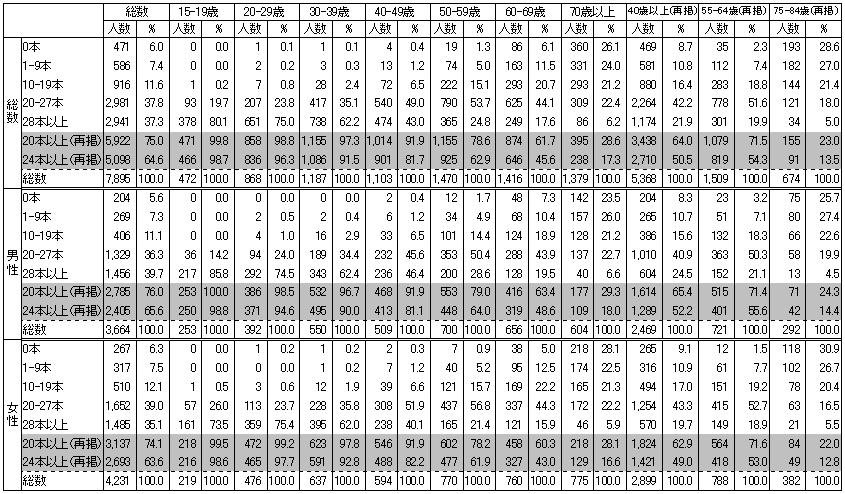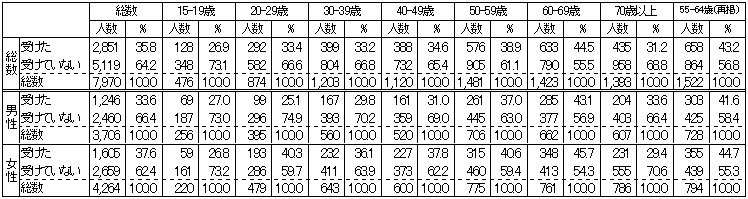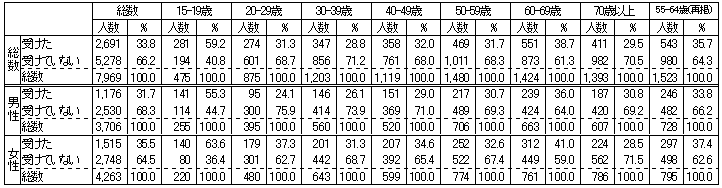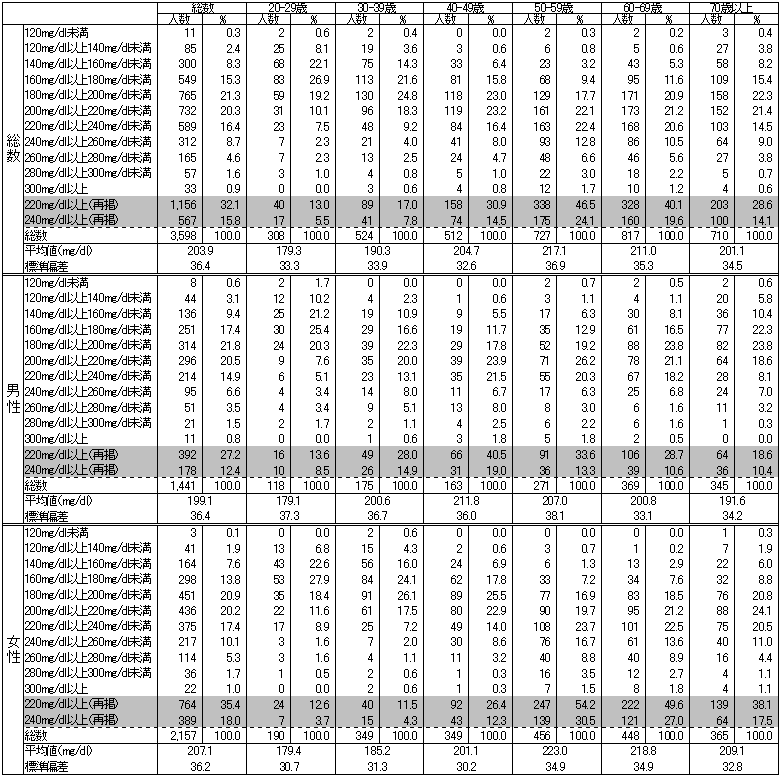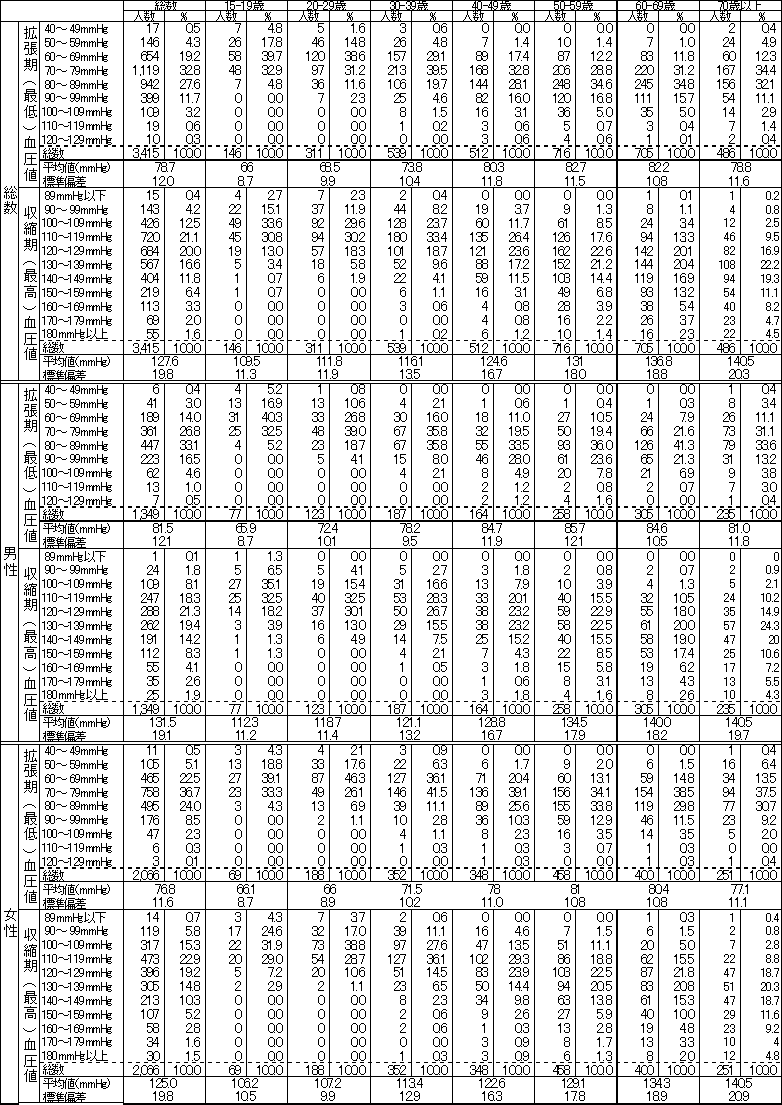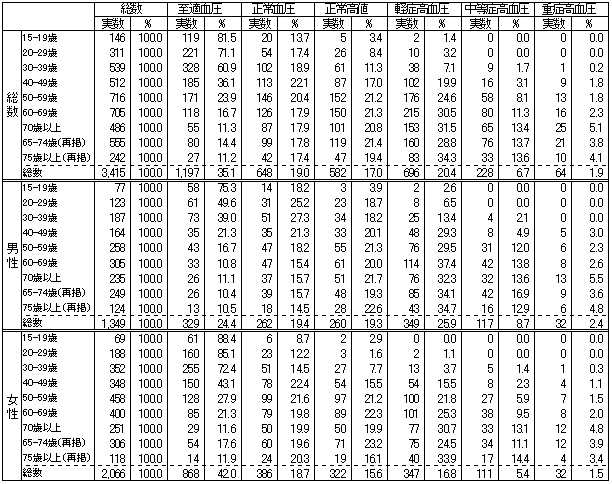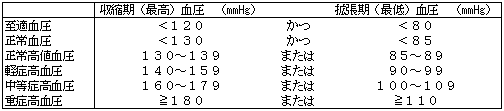平成16年
国民健康・栄養調査結果の概要
健康局総務課生活習慣病対策室
電話03−5253−1111
内線2345
| 1. |
調査の目的
この調査は、健康増進法(平成14年法律第103号)に基づき、国民の身体の状況、栄養素等摂取量及び生活習慣の状況を明らかにし、国民の健康の増進の総合的な推進を図るための基礎資料を得ることを目的とする。 |
| 2. |
調査対象及び客体
調査の対象は、平成16年国民生活基礎調査において設定された調査地区内の世帯の世帯員で、平成16年11月1日現在で満1歳以上の者とした。
調査の客体は、平成16年国民生活基礎調査において設定された調査地区から、層化無作為抽出した300単位区内の世帯及び世帯員とした。ただし、うち2単位区は、平成16年10月に発生した新潟県中越地震の影響により、調査が不能であった。
調査実施世帯数は、3,421世帯であり、集計客体数は下記のとおりである。 |
| 総数 |
総数 |
1-6歳 |
7-14歳 |
15-19歳 |
20-29歳 |
30-39歳 |
40-49歳 |
50-59歳 |
60-69歳 |
70歳以上 |
| 身体状況調査 |
7,689 |
467 |
664 |
370 |
663 |
950 |
894 |
1,217 |
1,267 |
1,197 |
| 血液検査 |
3,932 |
- |
- |
- |
308 |
527 |
519 |
773 |
940 |
865 |
| 栄養摂取状況調査 |
8,762 |
520 |
770 |
435 |
803 |
1,124 |
1,045 |
1,374 |
1,368 |
1,323 |
| 生活習慣調査 |
9,345 |
555 |
807 |
476 |
876 |
1,203 |
1,120 |
1,484 |
1,427 |
1,397 |
| 男性 |
総数 |
1-6歳 |
7-14歳 |
15-19歳 |
20-29歳 |
30-39歳 |
40-49歳 |
50-59歳 |
60-69歳 |
70歳以上 |
| 身体状況調査 |
3,556 |
242 |
365 |
200 |
298 |
420 |
390 |
544 |
572 |
525 |
| 血液検査 |
1,549 |
- |
- |
- |
118 |
176 |
170 |
284 |
406 |
395 |
| 栄養摂取状況調査 |
4,135 |
263 |
419 |
239 |
353 |
525 |
480 |
649 |
631 |
576 |
| 生活習慣調査 |
4,428 |
286 |
432 |
256 |
395 |
560 |
520 |
707 |
664 |
608 |
| 女性 |
総数 |
1-6歳 |
7-14歳 |
15-19歳 |
20-29歳 |
30-39歳 |
40-49歳 |
50-59歳 |
60-69歳 |
70歳以上 |
| 身体状況調査 |
4,133 |
225 |
299 |
170 |
365 |
530 |
504 |
673 |
695 |
672 |
| 血液検査 |
2,383 |
- |
- |
- |
190 |
351 |
349 |
489 |
534 |
470 |
| 栄養摂取状況調査 |
4,627 |
257 |
351 |
196 |
450 |
599 |
565 |
725 |
737 |
747 |
| 生活習慣調査 |
4,917 |
269 |
375 |
220 |
481 |
643 |
600 |
777 |
763 |
789 |
| 3. |
調査項目
| 1) |
身体状況調査票
| ア. |
身長、体重 |
(満1歳以上) |
| イ. |
腹囲 |
(満15歳以上) |
| ウ. |
血圧 |
(満15歳以上) |
| エ. |
血液検査 |
(満20歳以上) |
| オ. |
1日の運動量〈歩行数〉 |
(満15歳以上) |
| カ. |
問診〈服薬状況、運動〉 |
(満20歳以上) |
|
| 2) |
栄養摂取状況調査票(満1歳以上)
世帯員各々の食品摂取量、栄養素等摂取量、食事状況〈欠食・外食等〉 |
| 3) |
生活習慣調査票(満1歳以上)
食生活、身体活動・運動、休養(睡眠)、飲酒、喫煙、歯の健康等に関する生活習慣全般を把握した。特に平成16年調査では、「歯の健康」及び「健康日本21中間評価事項」を重点項目とした。なお、1〜14歳は「歯の健康」に関する項目のみとした。 |
|
| 4. |
調査時期
| 1) |
身体状況調査 |
: |
平成16年11月 |
| 2) |
栄養摂取状況調査 |
: |
平成16年11月の特定の1日(日曜日及び祝日は除く) |
| 3) |
生活習慣調査 |
: |
栄養摂取状況調査日と同日 |
|
| 5. |
調査方法
| 1) |
身体状況調査 |
: |
調査対象者を会場に集めて、調査員である医師、管理栄養士、保健師等が調査項目の計測及び問診を実施した。 |
| 2) |
栄養摂取状況調査 |
: |
世帯毎に調査対象者が摂取した食品を秤量記録することにより実施し、調査員である管理栄養士等が調査票の説明、回収及び確認を行った。 |
| 3) |
生活習慣調査 |
: |
留め置き法による自記式質問紙調査を実施した。 |
|
| 6. |
調査系統
調査系統は次のとおりである。
厚生労働省−都道府県・政令市・特別区−保健所−国民健康・栄養調査員 |
| この調査結果に掲載している数値は、四捨五入のため、内訳合計が総数に合わないことがある。 |
| 第1部 |
体型及びメタボリックシンドローム(内臓脂肪症候群)の状況 |
男性では、いずれの年齢階級においても、肥満者の割合が20年前(昭和59年)、10年前(平成6年)に比べて増加しており、30〜60歳代男性の約3割が肥満。
女性では、20〜40歳代で低体重(やせ)が増加しており、20歳代の約2割が低体重(やせ)。 |
平成16年の結果においては、30〜60歳代男性、60歳代女性の約3割に肥満がみられた。男性では30〜60歳代まで肥満者の割合がほぼ横ばいであるのに対し、女性では60歳代まで年齢とともに肥満者の割合が高くなっていた。一方、低体重(やせ)の者の割合は、20歳代女性で約2割であった。
また、20年前(昭和59年)及び10年前(平成6年)に比べ、肥満者の割合は、男性ではいずれの年齢階級においても増加していたが、女性では20〜50歳代で減少していた。一方、低体重(やせ)の者の割合は、女性の20〜40歳代で増加していた。
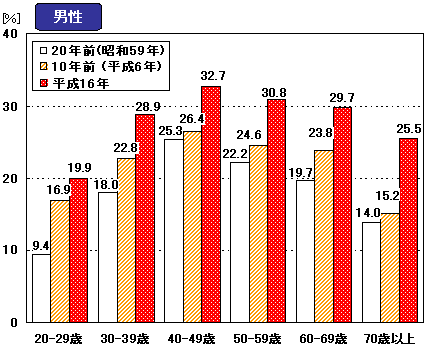
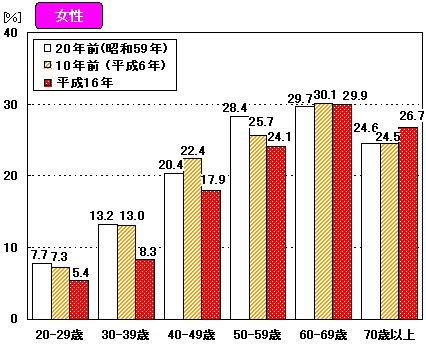
| 図2 |
低体重(やせ)の者(BMI<18.5)の割合(20歳以上) |
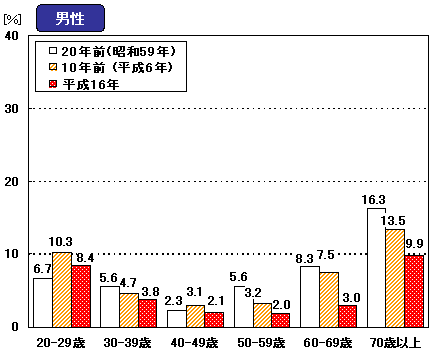
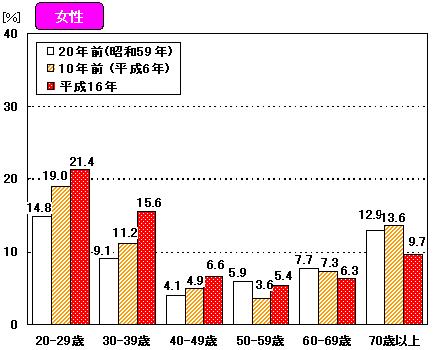
肥満度:BMI(Body Mass Index)を用いて判定
BMI=体重[kg]/(身長[m])2により算出
|
BMI |
<18.5 |
低体重 |
(やせ) |
| 18.5≦ |
BMI |
<25 |
普通体重 |
(正常) |
|
BMI |
≧25 |
肥満 |
|
(日本肥満学会肥満症診断基準検討委員会,2000年) |
(参考)「健康日本21」の目標値(2010年)
| 20歳代女性のやせの者 |
15%以下 |
| 20〜60歳代男性の肥満者 |
15%以下 |
| 40〜60歳代女性の肥満者 |
20%以下 |
|
内臓脂肪型肥満の診断基準の一つである上半身肥満が疑われる者の割合は、20歳以上の総数で男性の29.3%、女性の14.2%であった。
また、男性では30歳代以上の約3割に、女性では60歳代以上の約2割に上半身肥満が疑われた。
| 図3 |
BMIと腹囲計測による肥満の状況(20歳以上) |
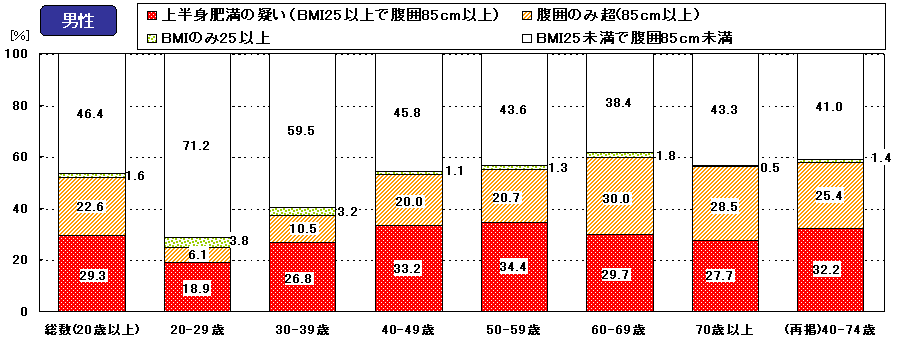
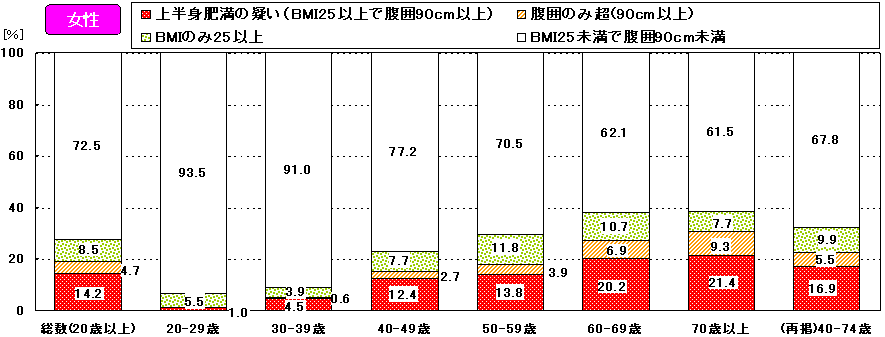
(参考)内臓脂肪型肥満の診断基準:
| ・ |
| BMI25以上で、 |
男性のウエスト周囲径85cm以上、 |
|
女性のウエスト周囲径90cm以上を上半身肥満の疑いとする。 |
|
| ・ |
上半身肥満の疑いと判定され、腹部CT法による内臓脂肪面積100cm2以上(男女とも)を内臓脂肪型肥満と診断する。(日本肥満学会肥満症診断基準検討委員会、2000年)
|
| ※ |
国民健康・栄養調査の「腹囲」は、「立位のへその高さ」で計測したが、ウエスト周囲径と計測位置は同じである。 |
|
| 3. |
メタボリックシンドローム(内臓脂肪症候群)の状況 |
メタボリックシンドローム(内臓脂肪症候群)が強く疑われる者と予備群と考えられる者を併せた割合は、男女とも40歳以上で特に高い。
40〜74歳でみると、男性の2人に1人、女性の5人に1人が、メタボリックシンドローム(内臓脂肪症候群)が強く疑われる者又は予備群と考えられる者。 |
20歳以上において、メタボリックシンドローム(内臓脂肪症候群)が強く疑われる者の割合は、男性23.0%、女性8.9%、予備群と考えられる者の割合は、男性22.6%、女性7.8%と、いずれも男性で高くなっていた。
また、強く疑われる者の割合は、男性では40〜50歳代で約2割、60歳以上で約3割であり、強く疑われる者に予備群と考えられる者を併せた割合は、男性では30歳代の約20%から40歳代で40%以上、女性では30歳代の約3%から40歳代で10%以上と、男女とも40歳以上で特に高くなっていた。
40〜74歳でみると、強く疑われる者の割合は、男性25.7%、女性10.0%、予備群と考えられる者の割合は、男性26.0%、女性9.6%であり、40〜74歳男性の2人に1人、女性の5人に1人が、メタボリックシンドローム(内臓脂肪症候群)が強く疑われる者又は予備群と考えられる者であった。
| 4. |
腹囲区分別、血中脂質、血圧、血糖のいずれかのリスクを有する状況 |
| メタボリックシンドローム(内臓脂肪症候群)の診断基準の1つである腹囲が男性85cm、女性90cm以上の者は、未満の者に比べ、血中脂質、血圧、血糖のいずれかのリスクを2つ以上有する割合が高い。 |
メタボリックシンドローム(内臓脂肪症候群)の診断基準の1つである腹囲が男性85cm、女性90cm以上の者は、未満の者に比べ、いずれの年齢階級においても、メタボリックシンドローム(内臓脂肪症候群)の疑いの判定項目である、血中脂質、血圧、血糖のいずれかのリスクを2つ以上有する割合が高かった。
また、血中脂質、血圧、血糖のいずれかのリスクを2つ以上有する割合は、男女とも年齢とともに増加していた。
| 図6 |
腹囲区分別、血中脂質、血圧、血糖のいずれかのリスクを有する割合(20歳以上) |
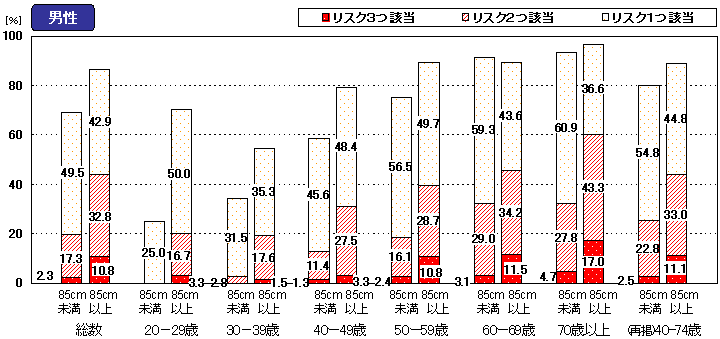
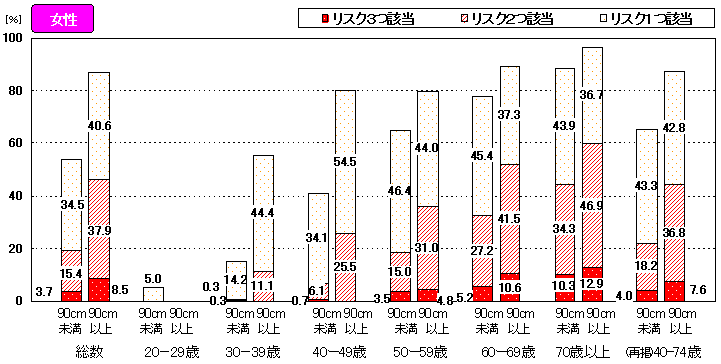
| 現在習慣的に喫煙している者の割合は、男性では30歳代が最も高く約6割、20、40、50歳代で約5割、女性では20〜30歳代で最も高く約2割。 |
現在習慣的に喫煙している者の割合は、男性で約4割、女性で約1割であり、男性では30歳代が最も高く約6割、20、40、50歳代で約5割、女性では20〜30歳代で最も高く約2割であった。
また、男性において過去習慣的に喫煙していた者の割合は、年齢とともに高くなっていた。
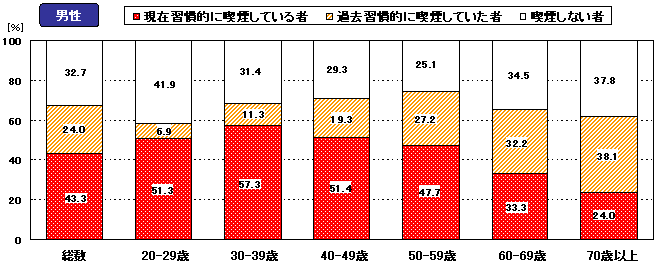
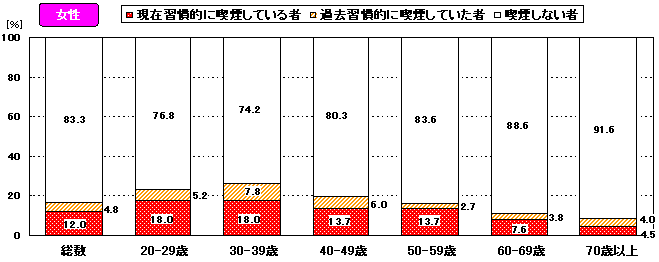
現在習慣的に喫煙している者:
| |
これまで合計100本以上又は6ヶ月以上たばこを吸っている(吸っていた)者のうち、「この1ヶ月間に毎日又は時々たばこを吸っている」と回答した者 |
過去習慣的に喫煙していた者:
| |
これまで合計100本以上又は6ヶ月以上たばこを吸っている(吸っていた)者のうち、「この1ヶ月間にたばこを吸っていない」と回答した者 |
喫煙しない者:
| |
「まったく吸ったことがない」又は「吸ったことはあるが、合計100本未満で6ヶ月未満である」と回答した者 |
|
| 40歳以上において、歯の本数が20本以上の者は19本以下の者に比べ、「何でもかんで食べることができる」と回答した者の割合が高い。 |
40歳以上において、「何でもかんで食べることができる」と回答した者の割合は、歯の本数が20本以上の者では約8割である一方、歯の本数が19本以下の者では約5割であり、歯の本数が20本以上の者は19本以下の者に比べ、いずれの年齢階級においても、「何でもかんで食べることができる」と回答した者の割合が高かった。
| 図8 |
歯の本数区分別、「何でもかんで食べることができる」と回答した者の割合(40歳以上) |
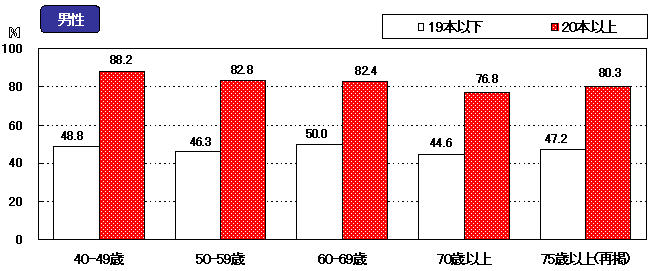
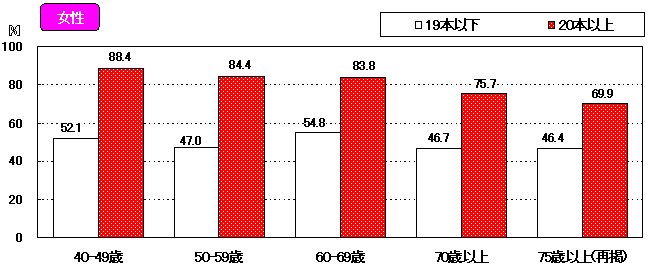
| 30歳代以下においては、歯の本数が19本以下の者が少ないことから、歯の本数に関する比較は困難である。 |
| 40歳以上の男性においては、現在習慣的に喫煙している者は喫煙しない者に比べ、「何でもかんで食べることができる」と回答した者の割合及び歯の本数が20本以上の者の割合が低い。 |
「何でもかんで食べることができる」と回答した者の割合は、年齢とともに低くなっており、現在習慣的に喫煙している者は喫煙しない者に比べ、40歳以上のいずれの年齢階級においても低かった。
また、歯の本数が20本以上の者の割合も年齢とともに低くなっており、現在習慣的に喫煙している者は喫煙しない者に比べ、40歳以上のいずれの年齢階級においても低かった。
| 図9 |
喫煙習慣別、「何でもかんで食べることができる」と回答した者の割合(40歳以上) |
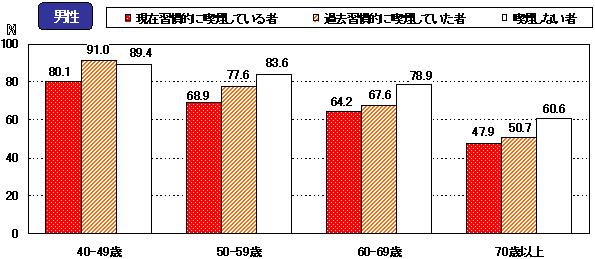
| 図10 |
喫煙習慣別、歯の本数が20本以上の者の割合(40歳以上) |
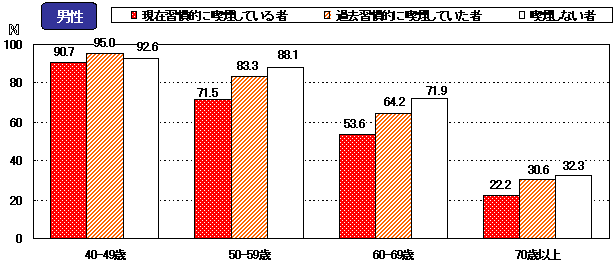
| 女性においては、現在習慣的に喫煙している者の割合が少ないことから、喫煙習慣別の比較は困難である。 |
運動習慣のある者の割合は、成人の男性で約3割、女性で約2.5割。
運動習慣のある者の割合が高いのは、男性では60歳以上、女性では50歳以上、一方、その割合が低いのは、男性の20〜50歳代、女性の20〜40歳代。 |
平成16年の結果では、運動習慣のある者(1回30分以上の運動を週2日以上実施し、1年以上継続している者)の割合は、男性の60歳代以上で高く、男性の20〜50歳代、女性の20〜40歳代で低かった。
また、運動習慣のある者の割合の年次推移をみると、単年では、ばらつきがあるものの、経年的な傾向としては男女とも総数ではほぼ横ばいである。年齢階級別にみると、男性の60歳以上、女性の50歳以上で高く、その他の比較的若い年齢層で低い傾向が続いている。
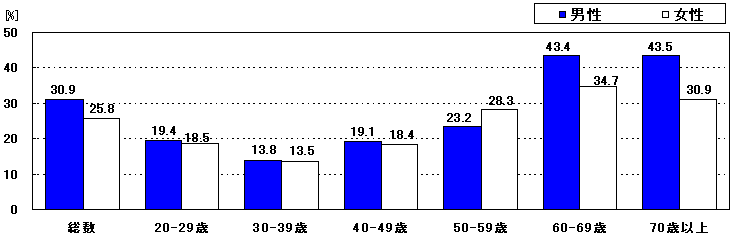
| 図12 |
運動習慣のある者の割合の年次推移(20歳以上) |
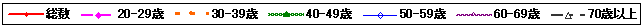
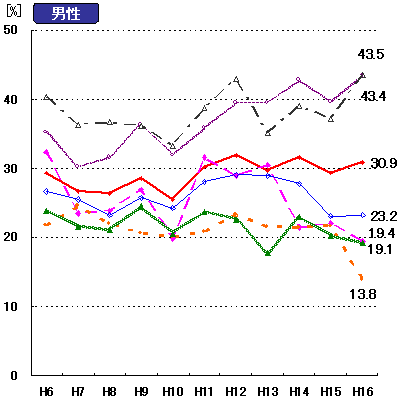
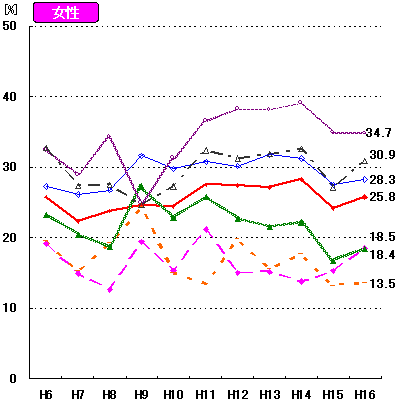
運動習慣のある者:
| |
1回30分以上の運動を週2日以上実施し、1年以上継続している者 |
|
(参考)
「健康日本21」の目標値(2010年)
| 運動習慣者の割合 |
男性 39%以上
女性 35%以上 |
|
朝食の欠食率は、平成11年以降、全体的に男女とも増加しており、特に男女とも20歳代で最も高く、男性で約3割、女性で約2割。
20歳代の一人世帯に限った朝食の欠食率は、男性で約7割、女性で約3割。 |
朝食の欠食率は、特に男女とも20歳代で最も高く、男性で34.3%、女性で22.0%であり、その後、年齢とともに低くなっていた。
一人世帯に限った朝食の欠食率は、男性の20歳代で65.5%、30歳代で41.4%であり、女性の20歳代で29.0%であった。
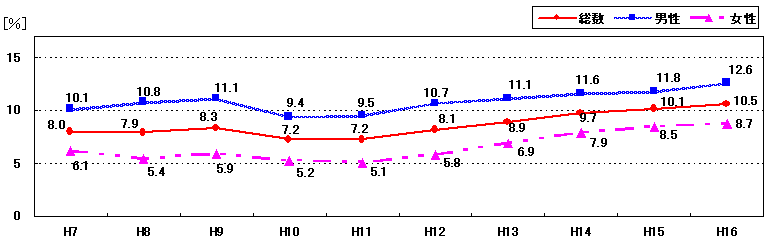
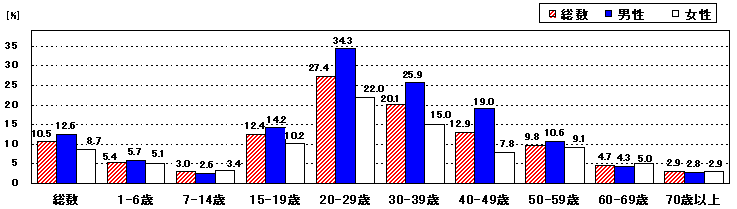
| 図15 |
朝食の欠食率−全体と一人世帯−(20歳以上) |
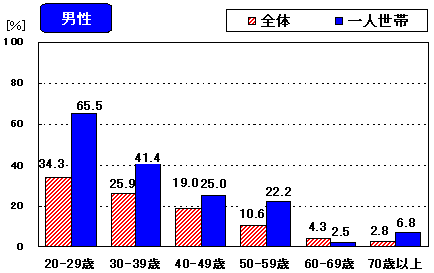
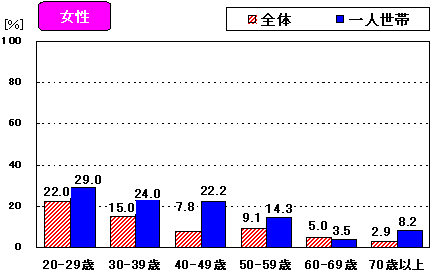
本調査での「欠食」は以下3つの場合の合計である。
| (1) |
何も食べない(食事をしなかった場合) |
| (2) |
菓子、果物、乳製品、し好飲料などの食品のみ食べた場合 |
| (3) |
錠剤・カプセル・顆粒状のビタミン・ミネラル、栄養ドリンク剤のみの場合 |
|
(参考)「健康日本21」の目標値(2010年)
朝食の欠食率 20、30歳代男性 15%以下 |
| 食塩を1日当たり10g以上摂取している者の割合は、成人の5割以上。 |
成人の5割以上の者が、食塩を1日10g以上摂取していた。
また、成人の1日当たりの食塩摂取量の平均値は、11.2g(男性12.1g,女性10.5g)であった。
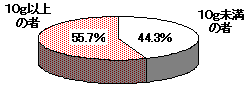
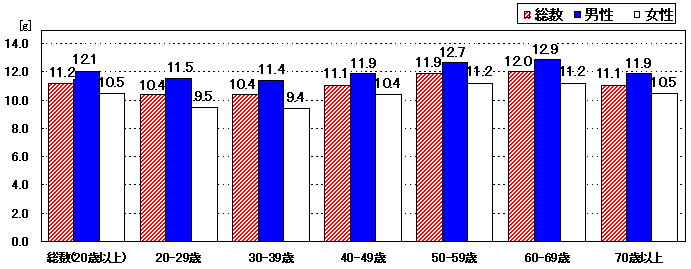
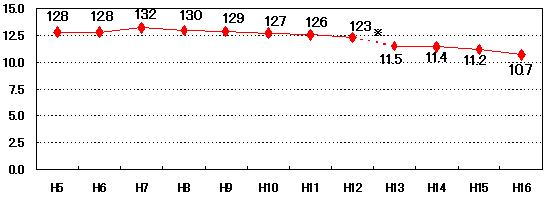
| 食塩摂取量(g)=ナトリウム(mg)×2.54/1,000 |
| ※ |
平成12年までは四訂日本食品標準成分表、平成13年からは五訂日本食品標準成分表を用いて算出している。 |
|
| (参考) |
「健康日本21」の目標値(2010年)
食塩摂取量 成人10g未満 |
|
| 脂肪からのエネルギー摂取が25%を超えている者の割合は、成人で男性約4割、女性約5割。 |
脂肪からのエネルギー摂取が25%を超えている者の割合は、成人で男性の約4割、女性の約5割であり、うち男性の約2割、女性の約2.5割が30%を超えていた。
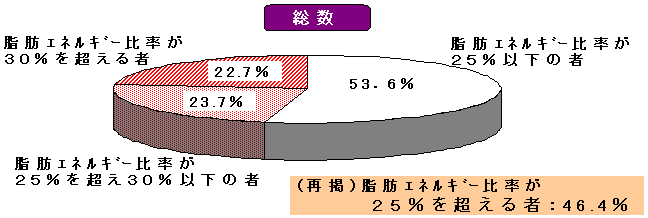
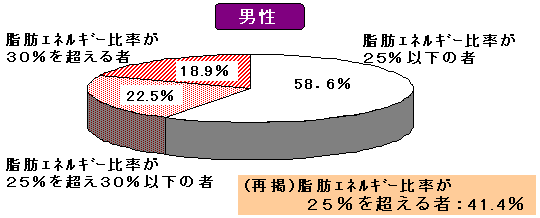
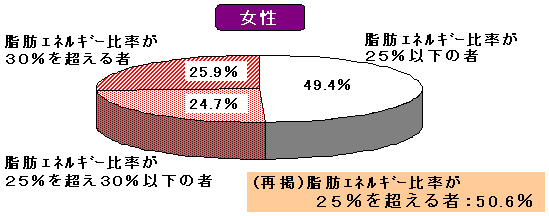
| 図20 |
エネルギーの栄養素別摂取構成比の年次推移(1歳以上総数) |
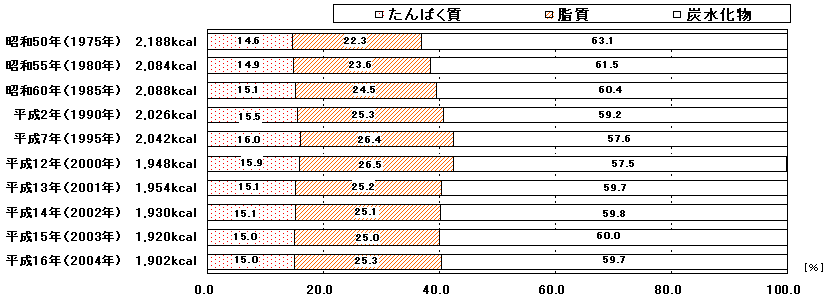
| 図21 |
エネルギーの栄養素別摂取構成比(1歳以上) |
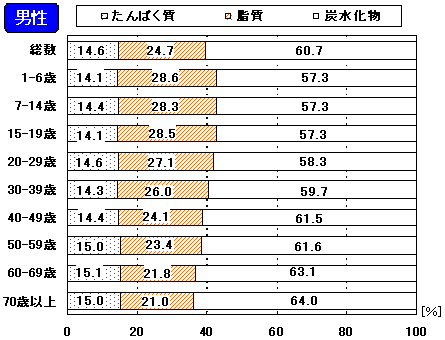
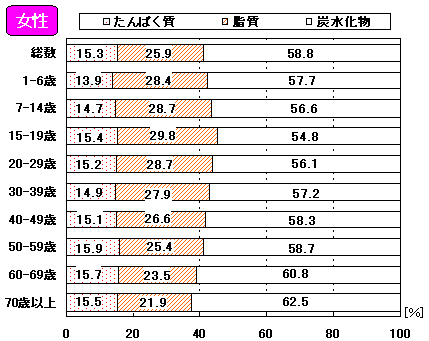
脂肪エネルギー比率:
脂肪からのエネルギーの摂取割合 |
(参考)第6次改定日本人の栄養所要量−食事摂取基準−
脂肪エネルギー比率 1〜17歳 25〜30% 18歳以上 20〜25% |
| (参考) |
「健康日本21」の目標値(2010年)
脂肪エネルギー比率 20〜40歳代 25%以下 |
|
| 野菜摂取量は、年齢とともに増加していたが、最も摂取量の多い60歳代においても、平均で303.5g。 |
野菜類の摂取量の成人全体における平均では266.7g、最も多い60歳代の平均で303.5gであり、また、男女とも20〜40歳代で少なかった。
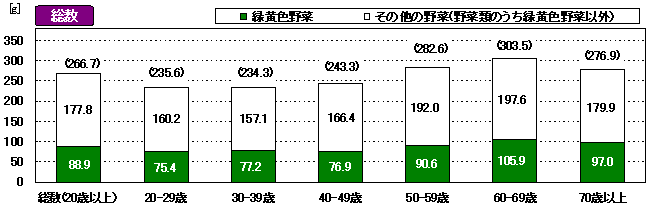
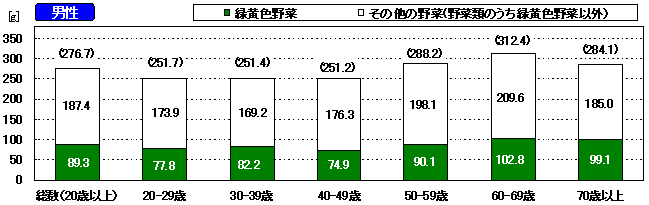
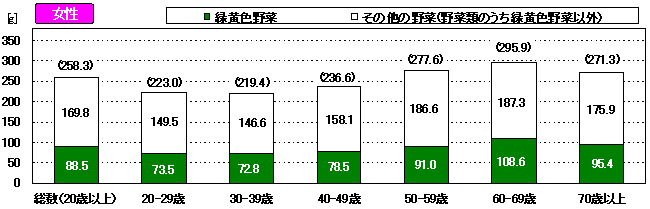
| ( )内は、「緑黄色野菜」及び「その他の野菜(野菜類のうち緑黄色野菜以外)」摂取量の合計。 |
(参考) 野菜類摂取量に対する気象条件の影響
調査時期である平成16年11月は台風などの気象の影響により、生鮮野菜の価格は例年よりもかなり上回った(指定野菜の価格は前年比190%(東京都中央卸売市場における指定野菜の卸売価格動向)。
また、調査時期の生鮮野菜全体の購入量は、例年よりも落ち込みがみられた(過去5年間の1ヶ月あたり平均購入量に対する11月購入量は平成12〜15年においては100%以上、平成16年は94%(総務省「家計調査」結果より算出)。 |
(参考)
「健康日本21」の目標値(2010年)
| 野菜摂取量 |
成人350g以上 |
| うち緑黄色野菜 |
成人120g以上 |
|