|
|
||||||||||||||
石綿による健康被害への対応について
過去に石綿を製造し、又は取扱う業務に従事していた方々に、肺がん、中皮腫等の健康被害が多発していることが企業から公表されています。石綿による被害は今後も増加することが懸念されています。(石綿については別紙1、労災認定状況については別紙2参照)
厚生労働省としては、石綿作業従事労働者の健康障害の防止について、これまで以下のような対策を講じてきました。
|
石綿を製造し、又は取扱う作業については、昭和46年に「特定化学物質等障害予防規則」を制定し、換気装置の設置、作業主任者の選任等のばく露防止対策を義務づけるとともに、健康診断の実施、作業環境測定等の対策を講じてきました。また、平成7年に、有害性の高いアモサイト(茶石綿)及びクロシドライト(青石綿)を含有する製品については、その製造・使用等を禁止し、さらに平成16年には、その他の石綿も禁止の対象とすることとし、一部を除いて全面的な石綿製品の製造・使用等の禁止を行いました。 また、退職者の健康管理についても、万全を期するために、一定の要件を満たす退職者に対する健康管理手帳の交付及び健康診断の実施などの対策を講じるとともに、石綿による労働者の健康被害への補償については、平成15年9月に、石綿に係る認定基準を改正し、労災認定の迅速化、適正化に努めてきました。 また、今後、石綿製品が使用された建築物の解体等が増加すること等から、建築物の解体作業等における石綿粉じんの飛散防止対策等を内容とする「石綿障害予防規則」を新たに制定し、本年7月より施行したところです(飛散防止対策については別紙3参照)。 なお、有害性の高いアモサイト・クロシドライトは、EUでは平成5年に使用を禁止し、我が国では、平成7年に製造等を禁止しました。 また、我が国においては、平成16年より、石綿製品の原則製造等禁止しました。一方、EUにおいては、平成17年より、石綿使用を禁止しています。米国においては、多くの石綿製品が禁止されていません。 |
さらに、今般の状況を受け、厚生労働省では以下のような対応を図っています。
| (1) | 石綿による新たな健康被害の発生を防止するため、現に石綿を製造し、又は取り扱っている事業場に対して、監督指導等を実施し、石綿障害予防規則等の遵守を徹底することとしました。また、健康管理手帳制度及び労災補償制度についての周知を行うこととしました。 |
| (2) | 現に石綿を製造しておらず、また取り扱っていない事業場であっても、石綿による健康被害が発生しているものに対しては、石綿の製造等の作業に従事していた者の範囲や健康管理の状況等について確認するために、立ち入り等による調査を行うこととしました。 |
| (3) | 石綿による健康被害を予防するため、過去に石綿を製造、又は取扱う業務に従事して退職した者に対しても健康診断を実施するよう事業者に対して要請を行い、また、過去に石綿を製造し、又は取扱う業務に従事していたと思われる方に対して、健康診断受診を呼びかけることとしました。また、健康管理手帳制度及び労災補償制度について、改めて周知を行うこととしました。 |
| (4) | このような措置の適切な実施のため、業界団体及び日本医師会に対して協力依頼を行うこととしました(別添の(ご案内)を厚生労働省HPに掲載)。 |
| (5) | 石綿の全面使用禁止に向けて、経済産業省に対し代替化の促進について協力を要請しました。また、経済産業省、国土交通省等の関係省庁に対しても、所管する業界において労働安全衛生法及び石綿障害予防規則に基づく対策が徹底されるよう、協力を要請するとともに、健康管理手帳制度及び労災補償制度の周知についても協力を要請しました。 |
| (6) | 中央労働災害防止協会及び建設業労働災害防止協会において、事業者の方々からの石綿のばく露防止対策に関する相談に対応することとしました。 |
| (7) | 各都道府県に設置されている独立行政法人労働者健康福祉機構産業保健推進センターにおいて、産業保健関係者、労働者等からの健康に関する相談に対応することとしました。 |
| (8) | 独立行政法人労働者健康福祉機構労災病院において、労働者等からの診療等に関する相談に対応することとしました。 |
| 事業者に対する関係法令の遵守徹底のための指導等 |
我が国は、1970年頃から90年頃にかけて年間約30万トンという大量の石綿を輸入していましたが、これらの石綿の大部分は建材に使用されたと言われており、この時期に建築されたマンション、ビル等の建築物には石綿が多く使用されています(別紙4参照)。今後、これらのマンション、ビル等の建築物の建て替えなどによる解体が増加することが予想されていますが、本年7月より施行された石綿障害予防規則に基づく作業場所の隔離、湿潤化等の措置を徹底することにより石綿粉じんの飛散の防止等に努めることとしています。
石綿による新たな健康被害の発生を防止するため、現に石綿を製造し、又は取り扱っている事業場に対して、監督指導等を実施し、石綿障害予防規則により義務づけられているばく露防止対策、健康診断の実施等の措置を確実に実施するよう、指導を行うこととし、また、健康管理手帳制度及び労災補償制度について周知を行うこととしました。
また、石綿を製造しておらず、又は取り扱っていない事業場であっても、石綿による健康被害が発生している事業場に対しては、各都道府県労働局及び労働基準監督署が立ち入り等により調査を行い、石綿の製造等の作業に従事していた者を確実に把握しているか、健康診断の実施等の健康管理が適正に実施されてきているかを確認することとしました。
これらの事業場において、石綿を製造し、又は取扱う業務に従事して退職した者についても、事業場の責任で健康診断を実施するよう要請を行うこととしました。
さらに、業界団体に対して、傘下の事業場が法令に基づく措置を確実に実施するよう周知徹底を行うよう指導を行うこととしました。
| 個人に対する健康診断の受診勧奨及び健康管理手帳制度・労災補償制度の周知 |
| ■ | 過去に在籍していた事業場で石綿を取扱う作業等に従事していた方への呼びかけ 過去に在籍していた事業場で、以下のリスト(★)に該当する作業を行っていた方は、石綿にばく露している可能性がありますので、胸部レントゲン検査等による健康診断を受けるようにしてください(その際、医師に自分が過去に石綿に係る作業を行っていた旨お伝え下さい)。なお、厚生労働省から各事業場に対し、退職者に対しても健康診断を行うよう要請を行っておりますので、過去に在籍していた事業場から健康診断の連絡等があった場合は、積極的に利用してください。また、リストにある作業に従事していた方は、発がんリスクを高めることになるので、喫煙をしないようにしてください。 また、受診された結果、一定の所見が見られる場合(※1)は、最寄りの都道府県労働局に申請していただければ、健康管理手帳の発行を受け、無料で定期的に健康診断を受けることができます。また、石綿肺、肺がん、中皮腫等を発症した場合には、それが石綿にばく露したことが原因であると認められれば、労災補償を受けることができます。詳しくは最寄りの労働基準監督署へお問い合わせ下さい。
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■ | 現在在籍している事業場で石綿を取扱う作業等に従事していた、又はしている方への呼びかけ 労働安全衛生法及び石綿障害予防規則においては、事業者は、石綿を取扱う作業等に従事させていた又は従事させている労働者に対して、6ヶ月に1度、健康診断を実施しなければならないこととされています。厚生労働省より事業場に対し、健康診断の実施を徹底するよう指導を行っておりますので、現に在籍している事業場で、上記リストに該当する作業を行っていた、又は行っている方は、事業場で行われる健康診断を確実に受診するようにしてください。また、発がんリスクを高めることになるので、喫煙をしないようにしてください。 |
| 各種相談窓口の設置 |
| ■ | 都道府県労働局・労働基準監督署における相談の受付 石綿に関する健康管理手帳、健康診断、労災補償についてのお問い合わせ、ご相談は最寄りの労働局、労働基準監督署までお願いします。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■ | 中央労働災害防止協会 労働衛生調査分析センター・大阪労働衛生総合センターにおける相談の受付 中央労働災害防止協会において、従来から石綿含有製品の代替化に関する相談窓口を開設しておりますが、これに加え、事業者の方々からの石綿ばく露防止対策に関する相談を受け付けることとしましたので、労働衛生調査分析センター(03-3452-3068)又は大阪労働衛生総合センター(06-6448-3784)までご相談下さい。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■ | 建設業労働災害防止協会における相談の受付 建設業労働災害防止協会において、事業者の方々からの建築物の解体作業等における石綿ばく露防止対策に関する相談を受け付けることとしましたので、電話03-3453-8201までご相談下さい。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■ | 独立行政法人労働者健康福祉機構 産業保健推進センターにおける相談の受付 産業保健推進センターにおいて、産業保健関係者、石綿による健康被害を受けられた労働者及びその家族の方々からの健康に関するご相談を受け付けることとしましたので、最寄りの産業保健推進センター(http://www.rofuku.go.jp/sanpo/index.html)までご相談下さい。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■ | 独立行政法人労働者健康福祉機構 労災病院における相談の受付 労災病院において、石綿ばく露歴のある方、その家族の方々、開業医等からの診断・治療、健康診断に関するご相談を受け付けることとしましたので、最寄りの労災病院までお問い合わせ下さい。(対応可能な労災病院は以下のとおりです)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(ご案内)
健康管理手帳制度とは
|
がんその他の重度の健康障害を発生させるおそれのある業務のうち、石綿を製造し、又は取扱う業務など一定の業務に従事して、一定の要件に該当する方は、離職の際又は離職の後に住居地の都道府県労働局長に申請することにより、健康管理手帳が交付されます。 健康管理手帳の交付を受けると、指定された医療機関又は健康診断機関で、定められた項目による健康診断を決まった時期に年2回(じん肺の健康管理手帳については年1回)無料で受けることができます。 |
★詳しくは別紙5をご覧下さい。
労災補償制度とは
|
労働者の業務災害、または通勤災害について、必要な保険給付を行う制度です。 現在雇用されている方や過去に雇用されていた方が、石綿肺、肺がん、中皮腫など、石綿との関連が認められる疾病にかかり、そのために療養したり、休業したり、あるいは不幸にして亡くなられた場合には、労災補償の対象となることが考えられます。具体的には労働基準監督署に請求書を提出する等の手続が必要となります。 |
★詳しくは別紙6をご覧下さい。
|
<本件に関する厚生労働省のお問い合わせ先>
|
これまでに掲載した石綿情報は、こちらをご覧下さい。
| 別紙1 |
石綿について
| 1. | 石綿の種類
| |||||||||||||||
| 2. | 石綿の有害性 石綿粉じんを吸入することにより、主に次のような健康障害を生じるおそれがある。
|
| 別紙2 |
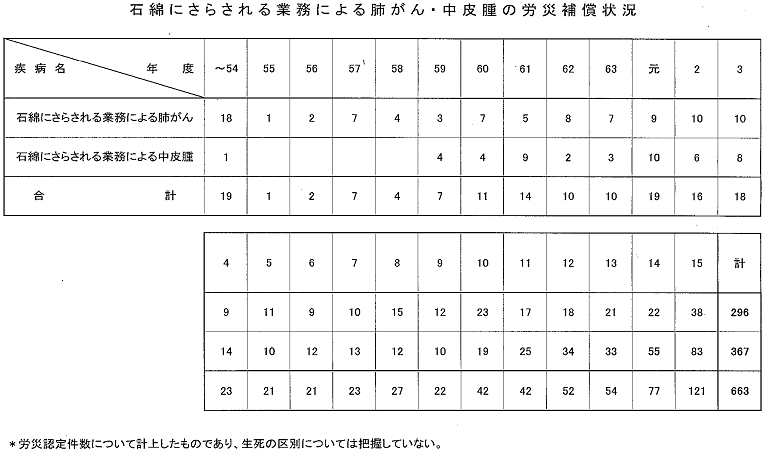
| 別紙3 |
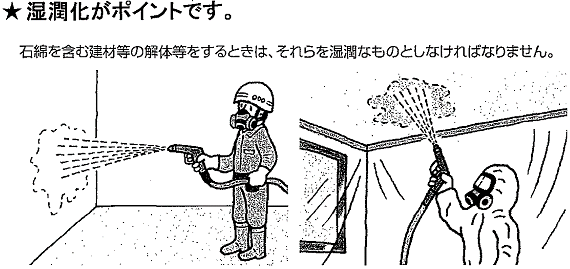
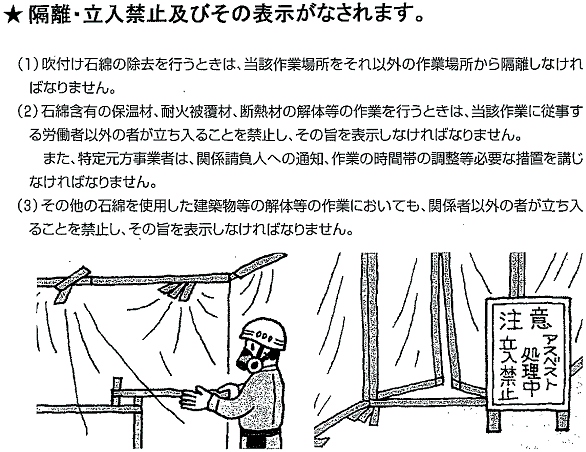
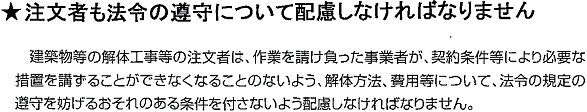
| 別紙4 |
石綿の使用状況
| (1) | 輸入量 日本の石綿輸入量は1960年代より増加し、1974年の35万トンを最高に年間約30万トン前後で推移してきたが、1990年代から年々減少傾向にあり、2002年は4万3千トンとなっている。2004年の輸入量は8千トンであり、前年比67%減となっている。 日本への主な輸入元は、カナダ(65.7%)、ブラジル(19.5%)、ジンバブエ(10.8%)である(2004年) 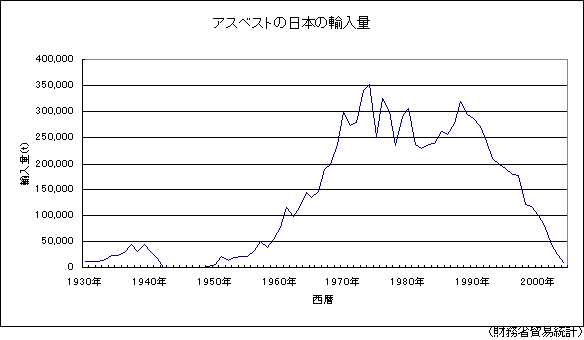
| |||||||||||||||||||||||||||
| (2) | 石綿品の用途 石綿の使用量のうち9割以上が建材に使用されており、その他、化学プラント設備用のシール材、摩擦材等の工業製品等に使用されている。 (なお、平成16年10月1日より建材、摩擦材、接着剤の製造等は禁止されている。)
| |||||||||||||||||||||||||||
| 別紙5 |
労働安全衛生法に基づく健康管理手帳について
がんその他の重度の健康障害を発生させるおそれがある業務のうち、次の表の左欄の業務に従事して、表の右欄の要件に該当する方は、離職の際又は離職の後に住所地の都道府県労働局長に申請することにより、健康管理手帳が交付されます。
健康管理手帳の交付を受けると、指定された医療機関又は健康診断機関で、定められた項目による健康診断を決まった時期に年に2回(じん肺の健康管理手帳については年に1回)無料で受けることができます。
| 業務 | 要件 | ||||||
|
当該業務に3月以上従事した経験を有すること(注1)。 | ||||||
|
じん肺法の規定により決定されたじん肺管理区分が管理2又は管理3であること。 | ||||||
|
当該業務に4年以上従事した経験を有すること。 | ||||||
|
当該業務に5年以上従事した経験を有すること。 | ||||||
|
当該業務に5年以上従事した経験を有すること。 | ||||||
|
当該業務に3年以上従事した経験を有すること。 | ||||||
|
両肺野にベリリウムによるび慢性の結節性陰影があること。 | ||||||
|
当該業務に3年以上従事した経験を有すること。 | ||||||
|
当該業務に4年以上従事した経験を有すること。 | ||||||
|
両肺野に石綿による不整形陰影があり、又は石綿による胸膜肥厚があること。 |
| 注1) | ベンジジン、ベーターナフチルアミン又はジアニシジンに関する業務の従事期間を合計すれば3月以上となる方は交付要件を満たします。 |
| 注2) | 粉じん作業には、石綿を取り扱う作業も含まれているため、石綿を取り扱う作業に従事した方については、交付要件を満たす場合、「11」だけでなく「3」の健康管理手帳の交付を受けることができます。 |
| 別紙6 |
石綿による疾病の認定基準
(平成15年9月19日付け基発第0919001号)の概要
(平成15年9月19日付け基発第0919001号)の概要
| 第1 | 石綿による疾病と石綿ばく露作業 | ||||||
| 1 | 石綿による疾病 石綿との関連が明らかな疾病としては、次のものがある。
| ||||||
| 2 | 石綿ばく露作業 石綿ばく露作業の主なものには、次の作業がある。
| ||||||
| 第2 | 石綿による疾病の取扱い | ||||||
| 1 | 石綿肺(石綿肺合併症を含む。) 石綿ばく露労働者に発生した疾病であって、じん肺法第4条第2項に規定するじん肺管理区分が管理4に該当する石綿肺又は石綿肺に合併したじん肺法施行規則第1条第1号から第5号までに掲げる疾病(じん肺管理区分が管理4の者に合併した場合を含む。)は、労基則別表第1の2第5号に該当する業務上の疾病として取り扱うこと。 | ||||||
| 2 | 肺がん 石綿ばく露労働者に発症した原発性肺がんであって、次の(1)又は(2)に該当する場合には、別表第1の2第7号7に該当する業務上の疾病として取り扱うこと。
| ||||||
| 3 | 中皮腫 石綿ばく露労働者に発症した胸膜、腹膜、心膜又は精巣鞘膜の中皮腫であって、次の(1)又は(2)に該当する場合には、別表第1の2第7号7に該当する業務上の疾病として取り扱うこと。
| ||||||
| 4 | 良性石綿胸水及びびまん性胸膜肥厚 石綿ばく露労働者に発症した良性石綿胸水又はびまん性胸膜肥厚については、石綿ばく露作業の内容及び従事歴、医学的所見、必要な療養の内容等を調査の上、本省に協議すること。 なお、当該疾病が業務上と認められる場合には、別表第1の2第4号8に該当する業務上の疾病として取り扱うこととなる。
|
| 別紙6-1 |
<石綿ばく露作業の例>
| (1) | 石綿鉱山又はその附属施設において行う石綿を含有する鉱石又は岩石の採掘、搬出又は粉砕その他石綿の精製に関連する作業 | ||||||||||
| (2) | 倉庫内等における石綿原料等の袋詰め又は運搬作業 | ||||||||||
| (3) | 以下の石綿製品の製造工程における作業
| ||||||||||
| (4) | 石綿の吹付け作業 | ||||||||||
| (5) | 耐熱性の石綿製品を用いて行う断熱若しくは保温のための被覆又はその補修作業 | ||||||||||
| (6) | 石綿製品の切断等の加工作業 | ||||||||||
| (7) | 石綿製品が被覆材又は建材として用いられている建物、その附属施設等の補修又は解体作業 | ||||||||||
| (8) | 石綿製品が用いられている船舶又は車両の補修又は解体作業 | ||||||||||
| (9) | 石綿を不純物として含有する鉱物(タルク(滑石)、バーミキュライト(蛭石)、繊維状ブルサイト(水滑石))等の取扱い作業 | ||||||||||
| (10) | 上記(1)〜(9)の石綿又は石綿製品を直接取扱う作業の周辺等において、間接的なばく露を受ける可能性のある作業 |