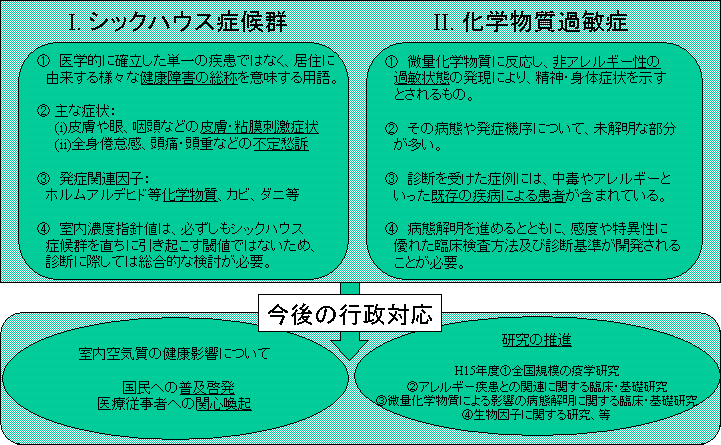|
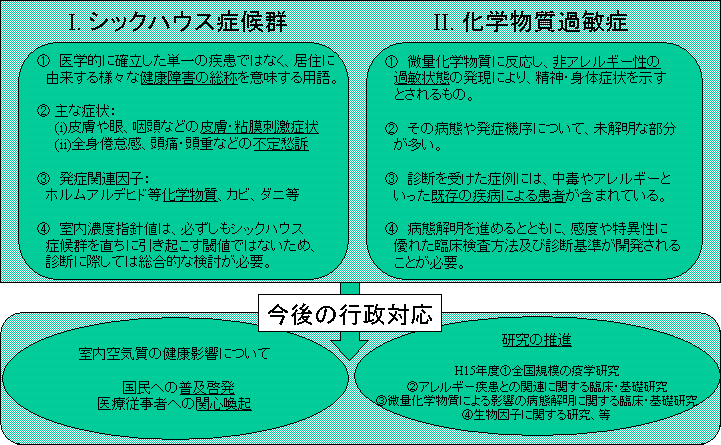
|
(照会先) 厚生労働省健康局生活衛生課 担当 難波江・伊藤(内2432) |
近年のシックハウス症候群を始めとする室内空気質による健康影響への関心の高まりを受け、厚生労働省健康局生活衛生課では、有識者からなる「室内空気質健康影響研究会」を平成15年5月から3回にわたり開催し、室内空気質の健康影響について、厚生労働科学研究等を通じてこれまでに得られた医学的知見の整理をお願いしてきた。今般、その報告書が取りまとめられたので公表することとする(概要:別紙参照)。
| ○ | 研究会のメンバー
|
| ○ | 開催経過
|
室内空気質健康影響研究会は、室内空気質の健康影響について、これまでに実施されてきた調査研究で得られた医学的知見を整理することを目的として開催されたものであり、主として「シックハウス症候群」及び「MCS(Multiple Chemical Sensitivity:多種化学物質過敏状態)/化学物質過敏症」の2つの論点について議論を行ってきた。本研究会報告書の概要は、以下の通りである。
1.シックハウス症候群について
(1)健康障害の総称としてのシックハウス症候群
これまでの用語の使用実態に鑑みると、シックハウス症候群は医学的に確立した単一の疾病というよりも、「居住者の健康を維持するという観点から問題のある住宅において見られる健康障害の総称」を意味する用語であると見なすことが妥当である。
これまでに得られた知見によれば、(1)皮膚や眼、咽頭、気道などの皮膚・粘膜刺激症状及び(2)全身倦怠感、めまい、頭痛・頭重などの不定愁訴、が訴えの多い症状であることが示されている。その原因については、化学物質等居住環境における様々な環境因子への暴露が指摘されているが、全てが解明されるに至っていない。
(2)発症関連因子としての化学物質
シックハウス症候群の主な発症関連因子として、建材や内装材などから放散されるホルムアルデヒドや、トルエンをはじめとする揮発性有機化合物がこれまで指摘されている。室内環境中には、ホルムアルデヒドをはじめとして、高濃度での暴露を受けた場合に、粘膜刺激症状などの健康障害を引き起こすことがある化学物質や、トルエンなどの有機溶剤のように、高濃度での暴露を受けた場合に、頭痛やめまい、さらには意識障害といった中枢神経障害を来すことがある化学物質が存在する。
中でも、ホルムアルデヒドについては、0.08ppmという建築物衛生関係法令上の基準値が定められている。これは、環境衛生上良好な状態を維持するという観点から定められた基準であり、皮膚や粘膜に障害のない者については当該基準値をわずかに上回った濃度の暴露を受けたとしても直ちに影響が生じることはないと考えられるが、アトピー性皮膚炎や気管支喘息をはじめとするアレルギー関連疾患の既往等があり、皮膚・粘膜の防御機能に障害がある者では、当該基準値を上回る濃度での暴露が持続した場合、皮膚や粘膜の症状が増悪するおそれがある値でもある。
また、防蟻剤として使用されてきたクロルピリホスについては、これを使用するしろあり駆除従事者への健康影響を示唆する報告がなされており、気密性の高い住宅でこれを使用し比較的高濃度での暴露が持続した場合、特に感受性の高い居住者に健康影響が生じる可能性は否定できない。
従って、建築基準法関連法令の改正により、建材としてのホルムアルデヒドの使用が規制されるとともに、クロルピリホスの使用が禁止されたことは、これらの物質による健康障害の発生を防止する上で適切かつ重要な規制的措置であると考えられる。
(3)化学物質以外の環境因子の関与
皮膚・粘膜刺激症状や不定愁訴を誘発する要因は必ずしも化学物質だけではない。皮膚・粘膜刺激症状はアレルギー疾患や感染症などの患者でも高頻度に認められる症状であり、また、温度、湿度及び気流等の温熱環境因子が増悪因子となりうる。
また、全身倦怠、めまい、頭痛・頭重などの不定愁訴は、各種疾患により生じるほか、温熱環境因子、生物因子(感染症)、照度、騒音及び振動等の様々な物理的環境因子、精神的ストレスなどが発症・増悪に関連することから、化学物質が係る症状の関連因子であると判断するためには、十分な除外診断が必要である。
(4)室内濃度指針値とシックハウス症候群との関連
「シックハウス(室内空気汚染)問題に関する検討会」における指針値の策定は、指針値を満足するような建材等の使用、住宅や建物の提供が考慮されるようになったという点で大きな役割を果たしている。
しかしながら、指針値をわずかに上回る濃度での化学物質の暴露を受けた者が、粘膜刺激症状などの症状を訴えた場合に、「シックハウス症候群」と判断される場合があるなど、当該指針値を巡って「シックハウス症候群」についての誤解も見受けられる。そもそも指針値は、化学物質により「シックハウス症候群」を引き起こす閾値を意味する値ではない。そのため、室内環境での濃度が指針値を超過していることだけをもって、直ちに、当該化学物質が症状誘発の原因であると判断することは必ずしも適当ではなく、症状誘発の関連因子を特定するためには、慎重かつ適切な臨床診断に基づく総合的な検討が必要である。
2.MCS/化学物質過敏症について
(1)非アレルギー性の過敏状態としてのMCS/化学物質過敏症
化学物質が生体に及ぼす影響には、これまで、中毒とアレルギー(免疫毒性)の2つの機序があると考えられてきた。これに対し、近年、微量化学物質暴露により、従来の毒性学の概念では説明不可能な機序によって生じる健康障害の病態が存在する可能性が指摘されてきた。当該病態については、様々な概念及び名称が提唱されているものの、国際的にはCullenが提唱した「MCS(Multiple Chemical Sensitivity:多種化学物質過敏状態)」の名称が、また、わが国では石川らが提唱した「化学物質過敏症」の名称が一般に使用されている。
(2)MCS/化学物質過敏症に関する臨床研究報告
MCS/化学物質過敏症として報告されている症候は多彩であり、粘膜刺激症状(結膜炎、鼻炎、咽頭炎)、皮膚炎、気管支炎、喘息、循環器症状(動悸、不整脈)、消化器症状(胃腸症状)、自律神経障害(異常発汗)、精神症状(不眠、不安、うつ状態、記憶困難、集中困難、価値観や認識の変化)、中枢神経障害(痙攣)、頭痛、発熱、疲労感等が同時にもしくは交互に出現するとされている。
(3)MCSに関する学会等の見解
MCSについては、これまでにいくつかの学会等で見解が取りまとめられている。
1996年2月にベルリンにて、IPCS(国際化学物質安全性計画:UNEP、ILO、WHOの合同機関)、ドイツ連邦厚生省等の主催でMCSに関する国際ワークショップが開催され、MCSについて(1)既存の疾病概念では説明不可能な環境不耐性の患者の存在が確認される、(2)しかし、MCSという用語は因果関係の根拠なくして用いるべきではない、として新たにIEI(Idiopathic Environmental Intolerances:本態性環境非寛容症)という概念が提唱された。
その後、米国アレルギー喘息免疫学会(American Academy of Allergy, Asthma and Immunology)、米国産業環境医学協会(American College of Occupational and Environmental Medicine)の委員会においても、MCSに関して、ベルリンワークショップの結論と同様な見解が示されている。
一方、「コンセンサス1999」と題する見解が、米国の研究者34名の署名入り合意文書として1999年に公表され、MCSを次のように定義している:(1)再現性を持って現れる症状を有する、(2)慢性疾患である、(3)微量な物質への暴露に反応を示す、(4)原因物質の除去で改善又は治癒する、(5)関連性のない多種類の化学物質に反応を示す、(6)症状が多くの器官・臓器にわたっている。
このように、MCSの病態の存在を巡って否定的見解と肯定的見解の両方が示されてきた。なお、ベルリンワークショップは、国際機関やドイツ連邦政府機関の主催により開催されたものであるが、そこで示された見解は必ずしも主催機関の公的見解ではない。また、コンセンサス1999についても、研究者間の合意事項であり、米国政府機関の公的見解ではないことに留意する必要がある。
(4)化学物質過敏症の呼称について
非アレルギー性の過敏状態としてのMCSの発症メカニズムについては多方面から研究が行われており、最近では、中枢神経系の機能的・器質的研究と、心因学説に立脚した研究報告が多数なされているものの、決定的な病態解明には至っていない。しかしながら、その発症機序の如何に関わらず、環境中の種々の低濃度化学物質に反応し、非アレルギー性の過敏状態の発現により、精神・身体症状を示す患者が存在する可能性は否定できないと考える。
一方、MCSに相当する病態を表す用語としてわが国では「化学物質過敏症」が用いられてきたが、「化学物質過敏症」と診断された症例の中には、中毒やアレルギーといった既存の疾病概念で把握可能な患者が少なからず含まれており、MCSと化学物質過敏症は異なる概念であると考えられる。そのため、既存の疾病概念で病態の把握が可能な患者に対して、「化学物質過敏症」という診断名を付与する積極的な理由を見いだすことは困難であり、また、化学物質の関与が明確ではないにも関わらず、臨床症状と検査所見の組み合わせのみから「化学物質過敏症」と診断される傾向があることも、本病態について科学的議論を行う際の混乱の一因となっていると考える。
本研究会としては、微量化学物質暴露による非アレルギー性の過敏状態としてのMCSに相当する病態の存在自体を否定するものではないが、「化学物質過敏症」という名称のこれまでの使用実態に鑑みると、非アレルギー性の過敏状態としてのMCSに相当する病態を示す医学用語として、「化学物質過敏症」が必ずしも適当であるとは考えられず、今後、既存の疾病概念で説明可能な病態を除外できるような感度や特異性に優れた臨床検査法及び診断基準が開発され、微量化学物質による非アレルギー性の過敏状態についての研究が進展することを期待したい。
3.今後の課題
(1)国民への正しい知識の普及啓発
住宅環境における健康問題について国民が正しい知識を得て、健康的な居住環境の確保に取り組めるように、普及啓発の取組を積極的に行うことが重要である。
また、「シックハウス症候群」及び「化学物質過敏症」については、名称の使用等を巡って混乱が見られる状況にあるが、本研究会での議論を踏まえ、室内濃度指針値との関連を含め、国民の正しい理解の向上を図ることが必要である。
(2)医療従事者への関心の喚起
室内環境中の環境因子により健康に影響を受けたと思われる患者の診療に当たっては、当該関連環境因子と症状との因果関係を検討した上で、環境因子が原因となっている可能性がある場合には、環境改善等により症状の軽快を図ることが重要である。本報告書の公表により、室内空気質の健康影響問題に対する医療従事者の関心及び理解が一層高まることを期待する。
(3)基礎及び臨床的研究の推進
「シックハウス症候群」については、様々な環境因子の暴露により多彩な症状が発現することが確認されているが、その原因の詳細な把握や、治療法及び予防法の確立のための更なる研究の推進が必要である。
微量化学物質暴露による非アレルギー性の過敏状態としてのMCSに関しては、発症メカニズムをはじめ、科学的には未解明な点が多いのが現状であり、様々な研究領域からの多角的なアプローチによるMCSの病態解明や治療法及び予防法の確立のための研究の更なる推進が必要である。
なお、わが国ではMCSに関する診断基準については、過去に研究班の活動等を通じて策定が試みられたものの、未だ専門家の間での合意を得られていない状況にある。今後研究を推進するにあたっては、現時点で一定の合意を得た診断基準を暫定的にでも策定する必要がある。
|